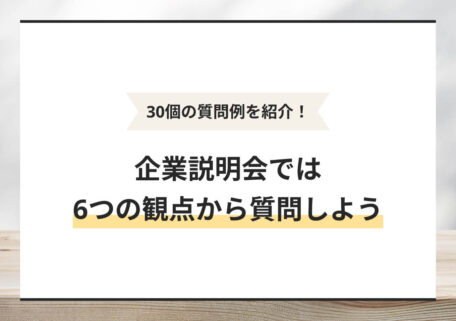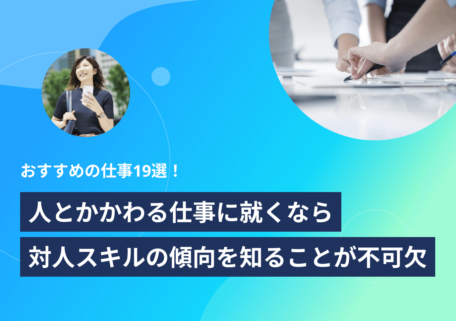Q
その他
回答しない
研究職に向いている人の特徴って何ですか?
将来、研究職に就きたいと考えている大学院生です。研究室での研究生活はそれなりに楽しめていますが、自分が本当に研究職に向いているのかどうか、自信が持てない部分もあります。
周りの研究者の人たちを見ていると、熱心に研究に取り組んでいるのはもちろんのこと、私にはない特別な能力を持っているように感じることがあります。
研究職として活躍されている方は、具体的にどのような考え方やスキル、性格の持ち主なのでしょうか? 研究職に向いている人の特徴や共通点があれば教えてください。自分が研究者としてやっていけるのかどうか、見極める参考にしたいです。
※質問は、エントリーフォームからの内容、または弊社が就活相談を実施する過程の中で寄せられた内容を公開しています
研究職に向いているのは知的好奇心が止まらない人!
研究職での働き方が向いている人の特徴としては、5つ挙げられます。
①好奇心や探求心が尽きない人
研究はわからないことをコツコツと明らかにしていく作業が多いです。「なぜ?」「どうしてそうなる?」と疑問を持ち、それを突き詰めることが研究において大事になります。
「わからないことが知りたい」という気持ちが継続するかどうかが、向き不向きを見極めることができる大きなポイントなのです。
②試行錯誤ができる人
研究は失敗することがつきものである職種といえます。それでも何度も仮説を立てて、考えることができるかが重要です。
③忍耐強さと継続力
研究職は具体的な成果が出るまでに時間がかかることは少なくありません。努力がすぐに報われることのほうが稀です。地道な積み重ねを「無駄じゃない」と信じられる気持ちが、あなたのキャリアの支えになります。
最初からうまくいく人は少ない! 不安でも続けたい気持ちを強く持とう
大切なのは向き・不向きよりも研究を続けたいという気持ちだと私は思います。失敗や数々のプレッシャーから迷うこともあるかもしれません。
本当に自分に向いているのかなど自信がないまま継続することはよくあることです。誰も最初から一人前ではありません。一歩ずつ続けていく歩んでいくという気持ちを持ち、焦らずに進んでいきましょう。
自分が「続けたい」と思うなら研究職の資質は十分にある!
質問者さんの研究分野は、理系の自然科学・科学技術か、文系の人文科学・社会科学のどちらになるのでしょうか。
分野が違えば、キャリアパスや収入は大きく異なり、研究対象によっても進む道が変わります。当然、求められるスキルや資質も違ってくるのです。
まず理系の研究職は実験や数値データに基づき、技術や理論の発展を目指します。これには根気や粘り強さが必要です。
一方、文系の研究は概念や理論の探究、歴史・文化的背景の分析が中心で、独自の枠組みを構築しながら社会の意味を探求します。
理系は実証可能な現象を扱い、文系は抽象的な概念に向き合う点が特徴的です。
理系・文系問わず研究職には常に試行錯誤していく意識が大切
アプローチは異なりますが、どちらも新しい知見を通じて社会の発展に貢献します。研究者には、知的好奇心の強さ、忍耐力、柔軟性が求められ、成果を実社会に活かす視点も重要です。
研究職に向いているかどうかは、キャリアや収入の懸念ではなく、「研究を続けたい」という気持ちにかかっています。1つのテーマを追求するのが好きなら、研究者としての資質は十分にあるといえます。
大学院に進んだのなら、質問者さんにはすでに知的好奇心があるはずです。自信をなくしているようですが、どの点に不安を感じているのでしょうか。
人はうまくいかないと自分には向いていないと考えがちです。しかし、多くの研究者は試行錯誤しながら研究を続けています。
研究を続けたいと思えるなら、その道に進む価値があると私は思います。
以下の記事では研究職の具体的な仕事内容や就職に向けた対策方法などを解説しています。研究職への就職・転職を検討している人は、一度目を通しておきましょう。
関連記事
研究職ってどんな仕事? 狭き門を勝ち抜くための志望動機例も紹介!
研究職を志望する場合は、仕事内容や適性の理解が必須です。また研究職のメリットデメリットも押さえておきましょう。この記事では研究職に向いている人の特徴や研究職に就くコツをキャリアコンサルタントが解説します。志望動機例文も紹介するので参考にしてください。
記事を読む

あなたが受けないほうがいい業界・職種を診断しよう
就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。
そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。
自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。