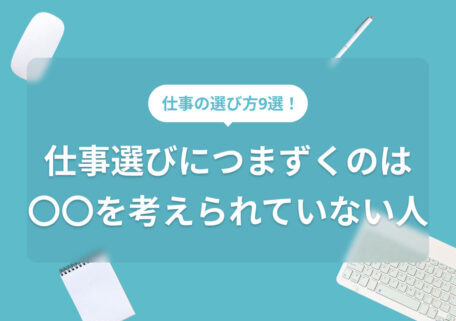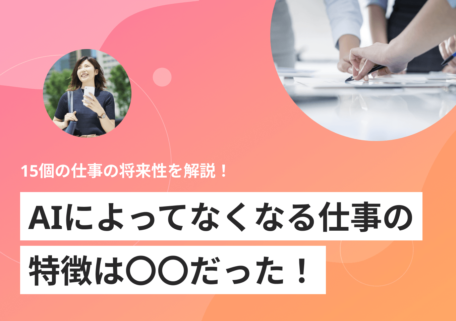Q
大学3年生
男性
趣味を仕事にしないほうがいいのは本当ですか?
就職活動で自己PRを考えるにあたり、自分の好きなことや趣味を仕事にしたいと考えています。
しかし、親や先輩から「趣味は仕事にしないほうがいい」とアドバイスされました。なぜそう言われるのか理由がわからず、本当にそうなのか気になっています。
好きなことを仕事にすれば、やりがいを感じられると思っていました。また、つらいことや大変なことがあったときに、乗り越えられそうな気もします。
趣味を仕事にすることのメリットやデメリット、好きなことを仕事にしようと考えている人が、今から考えておくべきことなど、アドバイスをお願いします。
※質問は、エントリーフォームからの内容、または弊社が就活相談を実施する過程の中で寄せられた内容を公開しています
趣味だと続かない可能性がある! 3つの要素で選ぼう
自身の好きなことや趣味を仕事にしたいと考えているのですね。
「好きを仕事にする」ことは、仕事をするうえでのモチベーションにもつながるためメリットもたくさんありますが、一方でデメリットも抱えています。
それは、好きなものを好きでい続けられる保証がないことです。
現状で好きなものは、これまでの環境のなかで好きになったものであり、環境やマーケットがガラッと変わると興味関心が薄れてしまう可能性があります。
また、好きな領域だったとしても、あなたの強みが活かせない環境だと、長く働くという観点で苦労するかもしれません。
そのため、「自分の価値観と合うか」「自分の強みを活かせるか」「好きな領域であるか」という要素を掛け合わせて、重なる部分を持つ仕事選びをするのがおすすめです。
何が好きなのかを定義! 選択肢を広げてみよう
さて、あなたの「好きなこと」は、どのようなところが好きだと思えるでしょうか。
仮にスポーツが好きだったとした場合、以下のように、「好き」にもいろいろな種類があることがわかります。
・プレイヤーとして試合に出るのが好き
・試合に向けて努力するのが好き
・チームで目標達成のために切磋琢磨するのが好き
・スポーツチームを応援するときの熱狂感が好き
自分自身の中で「好き」の定義を定めていただくと、もっと選択肢が広がるかもしれませんよ。少しでも参考になれば幸いです。
好きの対象次第! 何をすることが好きなのか考えよう
あなたの愛する「趣味」が、具体的にどのような「動き」をしているか考えてみてください。「名詞」ではなく「動詞」で考えるのがコツです。
たとえば、小説を「読む」のが好きな人が、必ずしも小説を「書く」小説家として成功するとは限りません。
ありがちな失敗例として、「子ども(名詞)」が好きで、「勉強(名詞)」が得意だから「学校の教師」を目指すパターンがあります。
しかし、教師の仕事は「勉強を教える」だけにとどまりません。「生き方を教える」「クレームに対応する」「事務仕事をする」などの動詞が苦痛なら、長続きはできないでしょう。
趣味が消費者側だと仕事にならない可能性がある
より本質的な視点から言うと、あなたの趣味が「消費者的」であるときは、稼ぎを生み出す「仕事」にはつながりにくいです。
たとえば「推し活」は代表的な消費者の趣味です。推し活でお金を稼げるのは「推される側」であり、「推す側」ではないですよね。
あなたの趣味を「動詞」で考えたとき、また「消費者的か、生産者的か」で考えたとき、「生産者的な動きが好きでおこなっている趣味」であれば、ぜひ仕事にしてみてください。
それ以外の場合は、少し考え直したほうが良いでしょう。
こちらの記事では、仕事の選び方について解説しています。経験に基づく客観的な観点で仕事選びのコツが紹介されているので、チェックしておきましょう。
趣味を仕事にすると、プライベートとの線引きが難しくなることがあります。仕事とプライベートのバランスの取り方が気になる人は、こちらの記事もおすすめです。
あなたが受けないほうがいい職業をチェックしよう
就活では、自分が適性のある職業を選ぶことが大切です。向いていない職業に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまいます。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析して、ぴったりの職業を診断できます。
適職診断で強み・弱みを理解し、自分がどんな職業に適性があるのか知りましょう。
簡単な質問に答えて、あなたの強み弱みを分析しよう。
今すぐ診断スタート(無料)
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人