この記事のまとめ
- 約4割の人は正規雇用ではなく非正規雇用を選んでいる
- 正規雇用と非正規雇用の違いは4つ
- 正規雇用と非正規雇用で悩んだときの判断基準を解説
正規雇用の仕事を探しているもののなかなか見つからず、非正規雇用の仕事でも良いのではないかと悩む人もいるのではないでしょうか。正規雇用と非正規雇用の違いを良くわかっていなければ、自分に合った雇用形態に悩む人も多いです。
正規雇用と非正規雇用で悩んだときは、それぞれの特徴を理解したうえで、自分のキャリアプランやワークライフバランスを考えた働き方に合わせて選ぶと後悔することが少なくなります。
この記事では、正規雇用と非正規雇用の違いやそれぞれが向いている人をキャリアコンサルタントの古田さん、隈本さん、吉野さんと一緒に解説します。自分に合った働き方を見つけて、後悔のない就職活動をしましょう。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
3位:自己分析ツール
選考で使えるあなたの強み・弱みがわかります
4位:WEBテスト対策問題集
SPI、玉手箱、TG-WEBなどの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
5位:内定者ES100選
大手内定者のESが見放題!100種類の事例から受かるESの作り方がわかります
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
正規雇用と非正規雇用の違いは働き方の自由度や安定感
自分に合った雇用形態を見つけるためには、正規雇用と非正規雇用の特徴やメリット・デメリットに着目する必要があります。どちらも違った良い点があるため、一概にどちらが良いとは言い切れないのです。
しかし、比較使用としてもそれぞれの特徴がわからなければ、判断できないと悩む人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、前半で正規雇用と非正規雇用の4つの違いと、雇用形態の種類を解説します。自分が働くうえで重視したい項目を考え、判断基準にしましょう。
そしてその後で、正規雇用・非正規雇用が向いている人をそれぞれ解説します。記事を最後まで読めば、自分に向いている雇用形態が正規雇用か非正規雇用か判断できます。
面接が上手くいかないときは、面接回答集を活用してください
面接で聞かれる質問に答えられるか不安ですよね。ただ、何を質問されるか分からず対策しようにも出来ない人は多いはず。
そこで、活用したいのが無料の「面接回答例60選」です。この資料があれば、伊藤忠商事や森永製菓、トヨタ自動車などの人気企業の面接でもよく聞かれるような質問とその答え方60通りが一目でわかります。
どんな質問が来ても確実に回答できるようになれば、面接はもう怖くありません。今すぐ活用し、面接を突破するのに役立てましょう!
・あなたの強み・長所を教えてください。
・あなたの夢を教えてください。
【花王株式会社】
・この職種を希望する理由を教えてください。
・あなたにとって仕事とは何ですか。
【森永製菓】
・あなたの強みを当社でどう生かせますか。
・当社の業界を志望する理由を教えてください。
非正規雇用を選ぶ人の割合は約4割と少なくない
非正規雇用の働き方に興味があっても、選ぶ人が少なければメリットが多くないのではと思う人もいるのではないでしょうか。自分の周囲に非正規雇用で働く人がいなければ、働き方のイメージがわかないものです。
厚生労働省が発表する正規雇用労働者と非正規雇用労働者の推移によると、2023年に非正規雇用として働いている人は約37%と少なくありません。そのため、非正規雇用の働き方を選んだとしても、めずらしいとは言えないのです。
家庭や育児、趣味、副業、キャリアアップのための転職が前提などさまざまな理由から、柔軟な働き方ができるために非正規雇用を選択している人が多いです。正規雇用になれなかったわけではないことも共通しています。
まずは比較しよう! 正規雇用と非正規雇用の4つの違い
正規雇用と非正規雇用、どちらの雇用形態が良いか悩んだときは、それぞれにどのような違いがあるのか理解しましょう。人によって働き方に求めるものは違うため、重視する部分にメリットが多い雇用形態を選ぶと後悔が少なくなります。
ここからは、正規雇用と非正規雇用の違いを4つ解説します。自分に合っている雇用形態を見極め、仕事を探しましょう。
①雇用期間
正規雇用で働く場合、基本的には定年までの就業を前提として採用されます。そのため、雇用期間は無期雇用となり、入社すれば本人の意思による退職や、会社に不利益を発生させたといった懲戒解雇がなければ、定年退職まで辞めることはありません。
一方で、非正規雇用は雇用形態によって、有期雇用となっており、一定期間で退職となる可能性があります。たとえば、契約社員であれば一年といった決められた期間ごとに契約が更新され、更新されなければ退職となるのです。
そのため、同じ企業で長く働き続けたいという考えがある場合は、正規雇用のほうが安定して働くことができます。ただし、非正規雇用であっても、パートやアルバイトとして働けば無期雇用で働ける職場もあるため、契約時に雇用期間を確認しておくと安心です。
②勤務時間・勤務地
正規雇用で入社した場合、契約時に決められた勤務時間を働くことになります。また、勤務地も契約段階でおおむね決まりますが、全国に支社がある企業の場合、転勤や異動となる可能性も想定が必要です。
非正規雇用として入社すると、雇用形態によっては勤務時間は自分の都合で決められる可能性があります。さらに、転勤・異動の可能性が少ないため、同じ地域で長く働きたいという人にも向いています。
プライベートを優先して自由に働きたい場合には、非正規雇用のほうが勤務時間に融通が効くことが多いため、望む働き方をかなえやすくなるのです。
③給与形態
毎月安定して同じ金額を給与としてもらいたい場合は、正規雇用で勤めるほうがおすすめです。正規雇用は欠勤や早退などをしていなければ、契約時に決められた給与が支払われます。
非正規雇用で入社する場合、給与は働いた時間に合わせて計算されることが多く、プライベートの都合で出勤の回数が少なければそれだけ収入が減ってしまいます。収入面は生活にも直結するため、少ないと不安を覚える人もいるのではないでしょうか。
また、企業によってはボーナスが支給される場合もありますが、法律上の義務ではないため、非正規雇用には支給されない可能性も否定できません。
④福利厚生
2020年4月に厚生労働省より同一労働同一賃金が実施されたことから、近年は正規雇用と非正規雇用の大きな福利厚生の差は少なくなっています。そのため、雇用保険や健康保険など基本的な福利厚生は非正規雇用であっても問題なく使用できる企業がほとんどです。
しかし、企業によっては退職金制度の用意や住宅手当など、法律では義務とされていない福利厚生もあります。企業のなかには、法律上義務とされていない制度は非正規雇用を対象外としている場合もあるのです。
そのため、なるべく福利厚生が整った状況で働きたいと考える人は、正規雇用で働くことがおすすめです。
正規雇用は雇用期間の安定性や福利厚生が魅力で、将来の生活設計を重視する人に適しています。一方、非正規雇用は勤務時間や勤務地が柔軟で、短期的な働きやすさを求める人向けです。
選ぶ際は、自分のキャリア目標や生活環境、優先したい要素から判断することが大切です。
退職金制度について詳しく知りたい人は以下の記事も参考にしてみてください。退職金の有無にかかわらず、後悔しないキャリアを選択するためのポイントを解説しています。
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
雇用形態を理解! 正規雇用と非正規雇用の種類
そもそも、正規雇用と非正規雇用にどのような雇用形態があり、それぞれの特徴を理解していなければ、選びようがないという人もいるのではないでしょうか。特に非正規雇用は雇用形態が豊富なため、何も考えずに選んでしまうと後悔する可能性があります。
この章では、正規雇用と非正規雇用の雇用形態の種類をそれぞれ解説します。メリットやデメリットも踏まえて、自分に合った雇用形態を見つけましょう。
正規雇用
正規雇用の種類
- 正社員
- 短時間正社員
正規雇用は、就業する企業に直接雇用される形になります。そのため、二つの雇用形態で共通している点は福利厚生は入社した企業に準じるものとなる、給与は契約時の金額となる点です。
しかし、短時間正社員には正社員にないメリット・デメリットがあるため、安易に選んで良いとは言えません。給与や求人の多さにも違いがあるため、その点への理解を深めましょう。
ここでは、正規雇用の種類を二つ解説します。それぞれの特徴を理解して、正社員のなかでも選択肢があることを理解しましょう
正社員
一般的にいわれる正社員とは、企業によって決められた8時間前後の就業時間を週に5日程度勤務するフルタイムと呼ばれる働き方をする人です。企業によっては勤務時間の前後があったり、週の労働時間が違う場合もあります。
正社員として働くメリットは、給与が安定していることから社会的信用の高さです。家や車など高額のローンを組む場合でも、安定した収入があるという点で審査が通る可能性が高まります。
また、企業としても週5日8時間安定して働いてくれるため、人材を確保しやすい観点から求人も多い雇用形態です。多くの選択肢から、自分に合った企業を選べます。
短時間正社員
短時間正社員とは、企業に正社員として入社しているものの、フルタイム正社員に比べると1週間の所定労働時間が短い働き方です。
厚生労働省の短時間正社員のページによると、以下を基準としています。
短時間正社員の基準
- ①期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している
- ②時間当たりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同種のフルタイム正社員と同等
短時間正社員はプライベートと仕事を両立したい人が選ぶことが多く、育児や介護をしている世代や定年後に働いている人が多いです。
短時間正社員にはプライベートな時間が確保しやすいというメリットがある反面、給与は働く時間が短い分フルタイム正社員より少なくなります。さらに、フルタイム正社員に比べると求人数が少ないため、自分の希望条件に合った仕事を見つけるまでに時間がかかる可能性があります。
- 短時間正社員は魅力が多い分枠が少なく、ライバルも多い印象です。選考を勝ち抜くコツはありますか?
短時間正社員は3つのポイントで採用を勝ち取ろう
選考の際、企業の担当者は次のようなことを知りたいと考えています。
①自己PRを明確に
短時間正社員の場合は、短時間でも高いパフォーマンスを発揮できるところをアピールしましょう。自分の強みやスキルを具体的に示し、どのような形で貢献できるかを明確にすることが大切です。
②柔軟性を強調する
短時間正社員はとくに、柔軟な働き方を求められます。柔軟性や適応力を強調し、あらゆる状況に対応できることをアピールしましょう。
③コミュニケーション能力をアピール
短時間でも効果的に仕事を進めるためにはコミュニケーション能力は必須です。しっかりアピールしましょう。
そのほか、企業文化や価値観に合致することなどをアピールすると良いでしょう。
39点以下は要注意!就活の弱点を克服するために今すぐ診断しよう
就活では気をつけるべきことが多いです。いざという時に「その対策はしていなかった…」と後悔したくないですよね。
後悔せずに就活を終えたい人は、今すぐ「就活力診断」で診断しましょう。たった30秒であなたの弱点を判定し、これからするべき就活対策がわかるようになります。
無料で使えるので今すぐ診断し、就活で後悔しないようになりましょう!
非正規雇用
非正規雇用
- 契約社員
- 派遣社員
- パート・アルバイト
- 業務委託
非正規雇用には就業する企業に雇用される場合や別の企業の社員として働く場合、企業には雇用されない働き方などがあり、それぞれメリットやデメリットが変わってきます。後悔のない選択をするためには、違いをきちんと理解し、自分に合った働き方を選ぶ必要があるのです。
しかし、周囲に非正規雇用で働いている人がいないと、働き方や魅力が理解できない人もいるのではないでしょうか。
ここからは、非正規雇用に含まれる雇用形態を4つ解説します。メリット・デメリットどちらも理解して、自分に合った働き方を見つけましょう。
契約社員
契約社員は、就業する企業に直接雇用されるものの、半年や一年など決められた期間ごとに契約を更新して働く雇用形態です。給与や福利厚生は正社員とほぼ同等の内容になるものの、契約期間の短さから長期にわたる責任の重い仕事は任されにくいというメリットがあります。
一方で、契約社員は契約期間が終了すると仕事をなくす可能性があります。契約の更新が必ずされるとは限らないため、同じ企業に長く勤めたい人には向かない雇用形態です。また、責任ある仕事を任せられることが少ないため、キャリアを積みにくいというデメリットもあります。
やりたい仕事内容で選んだところ、契約社員の募集しかなかった、というケースは何度かありました。図書館や美術館のスタッフ、芸術やスポーツの講師などの人気職は、契約社員でも非常に倍率が高いです。
派遣社員
派遣会社に登録して紹介された企業で仕事をするのが、派遣社員の働き方です。派遣社員は働く時間の融通が効きやすく、ライフスタイルに合わせた仕事を探しやすくなっています。さらに、派遣会社のサポートがあるため、未経験でも仕事に就ける可能性が多いです。
しかし、派遣会社は有期雇用のため、契約社員と同じように契約が更新されなければ仕事を失うため安定感が少なくなります。同じ派遣先に勤めて良い期間は3年までと決まっているため、その期間を過ぎたら派遣先企業に直接雇用されるか、派遣会社で無期雇用派遣に切り替えるかなどの選択が必要です。
さらに、就業先に雇用されるわけではないため、使用できる福利厚生も多くありません。
パート・アルバイト
パート・アルバイトとして働く場合、自分が就業可能な時間帯をシフトとして提出できることが多いため、働く時間を縛られたくないという人に向いている雇用形態です。働く時間を自由に選びたい理由は、プライベートを充実させたい、育児に専念したいなど人それぞれですが、比較的採用されやすいため仕事も見つけやすくなっています。
ただ、パートやアルバイトで働く場合、自分が働いた時間分しか給与が発生しないため、収入が安定しにくい傾向があります。さらに、雇用保険や健康保険に加入したいと思っても、一定の条件を満たす必要があるため、働き方の自由度は減ってしまうのです。
また、働き方の自由度が高いといっても、同じ時間帯の出勤を希望するスタッフが多ければ希望通りに働けるとは限りません。
業務委託
業務委託とは、企業に雇用されず決められた仕事に対して報酬が発生する働き方です。雇用契約がない分、働く時間や業務の進め方の自由度が高く、場所の制限も少なくなります。
業務委託を企業から受ける場合は特定のスキルを求められることが多く、企業での育成や研修はない場合が多いです。そのため、企業に入社してから成長するのではなく、業務に対してある程度の知識や技術が求められます。
また、雇用契約がない分社会保険や雇用保険は使用できず、福利厚生は基本的にありません。仕事がなければ収入も発生しないため、常に顧客を探し続ける必要があります。
安定感を重視! 正規雇用が向いている人
正規雇用が向いている人
- 安定した働き方がしたい人
- ボーナスや福利厚生を魅力に感じる人
- 昇給や昇進を目指す人
正規雇用は就業時間や日数の拘束が多い分、非正規雇用に比べると安定した給与や社会的な信頼を得られます。働いているときに収入の不安や仕事をなくす心配をしたくない人は、正規雇用が向いているといえます。
しかし、いざ自分が正規雇用に向いているのかといわれると、判断できず悩む人もいるのではないでしょうか。
この章では、正規雇用が向いている人の特徴を3つ解説します。自分が当てはまるかを考え、正規雇用への理解をさらに深めましょう。
安定した働き方がしたい人
正規雇用として働く魅力の一つとして、無期雇用のためトラブルがなければ定年まで働ける点にあります。給与も毎月決まった金額が支払われるため、必要な生活費や自由に使えるお金の想定がしやすく、安定した生活が送れるのです。
非正規雇用として働く場合、有期雇用で採用されることが多く、一定期間で職を失う可能性が付き纏います。契約社員や派遣社員の場合、契約が更新されなければ新たに仕事を探す必要が出てきて、就職活動に手間や不安を感じてしまう場合もあるのです。
なるべく同じ仕事を続けていきたい、仕事で不安を感じたくない、という人であれば正規雇用が向いています。
ボーナスや福利厚生を魅力に感じる人
正規雇用では企業の実績によって、年に数回決められたタイミングでボーナスが支給されることがあります。給与と別で支給されるため、お得に感じる人もいるのではないでしょうか。ボーナスは法律で決められた義務ではないため、非正規雇用だと支給していない企業も多くあります。
ほかにも、住宅手当や退職金など法律で義務化されていない福利厚生は数多くあり、企業によっては非正規雇用だとそれらを使用できない場合もあります。福利厚生のなかには日々の生活に密接したものもあるため、正規雇用と比べたときに待遇の差を感じる可能性があるのです。
企業が用意しているボーナスや福利厚生に魅力を感じるのであれば、正規雇用での入社を選択肢に入れましょう。
昇給や昇進を目指す人
同じ企業に正規雇用として長く務めれば、できる仕事が増えていき昇給や昇進のチャンスが出てきます。始めは一般社員として入社したものの、責任ある仕事を任せられ、役職が着く場合もあるのです。
人によっては、責任ある仕事を任せられることにやりがいを感じるケースもあります。同じ部署内のスタッフをマネジメントする立場になったり、新人教育を任せられるようになったりすれば、企業によっては役職手当も期待できるのです。
一つの企業に長く務めれば、年数の経過とともに昇給も期待でき、毎月の給与が増える可能性もあります。より安定した働き方ができ、企業でも活躍が可能です。
- 給与が増える以外に昇進するメリットが思い浮かびません。責任が増える印象がありますが、ほかに良い点はあるのでしょうか。
仕事のやりがいや達成感、人脈の拡大がメリット
まず、権限拡大により、業務の進め方や意思決定において自分の裁量が増え、仕事を主導的に進められます。自分のアイデアを形にする機会が増え、やりがいや達成感を得やすくなるでしょう。
また、昇進によって新たな責任や役割を任されるため、マネジメント力や問題解決能力などのスキルが磨かれ、キャリアの幅が広がるきっかけになります。
さらに、昇進したポジションでは他部署や上層部との接点が増えるため、視野が広がり、人脈の拡大にもつながります。これらは、次のキャリアステップに役立つ要素です。
もちろん、責任が増えることで負担が大きくなる一面もありますが、その分成長の機会が得られる点は昇進の給与面以外のメリットでしょう。
自由度を重視! 非正規雇用が向いている人
非正規雇用が向いている人
- 自由な時間に働きたい人
- さまざまな仕事を経験したい人
- 扶養内で働きたい人
非正規雇用として働く場合、正規雇用に比べると働く時間を短くできたり、合わないと思ったら辞めやすかったりといったメリットがあります。一方で、収入や雇用が安定せず、不安を感じる場面も覚悟しておかなければいけません。
ここでは、非正規雇用が向いている人の特徴を3つ解説します。自分が魅力的に感じるのかを考え、非正規雇用が向いているのか判断しましょう。
自由な時間に働きたい人
非正規雇用で働くメリットの一つとして、働く時間の自由さが当てはまります。正規雇用は一般的にフルタイムの勤務が求められますが、非正規雇用の場合は短い時間での就業や好きな時間にシフトを出すことが叶います。
介護や育児でプライベートが忙しい人や、趣味に多くの時間を当てたい人にとって、就業時間の自由さは魅力を感じる人も多いのではないでしょうか。
正規雇用で働く場合、決められた就業時間に休む場合は給与が差し引かれ、休みが多ければ勤務態度の評価にも影響が出ます。非正規雇用として働く場合、もともとの就業時間を短くする選択肢も取れ、フルタイムで働くには体力がないという人でも向いています。
さまざまな仕事を経験したい人
パートやアルバイト、派遣社員など非正規雇用で働く場合、正規雇用として一つの企業に勤めるよりもさまざまな仕事を経験することも可能です。
たとえば、アルバイトで飲食店に勤めたとして、別の仕事がしたくなったら退職して事務職のアルバイトに就くこともできます。さまざまな業務の実務経験をつけられ、自分に合った仕事を見つけやすい点が魅力です。
さらに、人によっては複数の仕事を掛け持ちする選択肢もとれます。昼間は事務職、夜は居酒屋のスタッフとして働けば、飽き性の人でも続けやすくなります。一つの仕事では飽きてしまうという場合にも、非正規雇用はおすすめの雇用形態です。
飽き性の人が仕事を探す場合は、続けやすい仕事の傾向を理解するのもおすすめです。下記の記事では飽き性の人に向けた仕事を解説しているため、ぜひ参考にしてください。
扶養内で働きたい人
家族が正規雇用で働いている人の場合、非正規雇用で採用され、扶養の範囲内でのみ収入を得たいという人もいます。このタイプの人は正規雇用として採用されると扶養の範囲を出てしまうため、非正規雇用しか選択肢にないのです。
扶養内で働けば、税金や社会保険料の負担を減らすことが可能です。さらに、配偶者や家族の社会保険に加入できるため、基本的な社会保障も得られます。育児や介護などプライベートな理由で長時間働くことが難しい人であれば、パートやアルバイトなど時間の融通が効きやすい非正規雇用が向いています。
- 非正規雇用として働きたいと考えていますが、デメリットが気になります。吉野さんが非正規雇用を選ぶなら、どのような部分に魅力を感じて選びますか?
仕事内容がやりたいことなら選ぶ価値がある
正社員のデメリットには、職種を限定できない点が挙げられます。
ジョブ型/メンバーシップ型という働き方の区別もありますが、特定の会社の社員になるより、職種の専門性を深めることに価値を見い出す人もいます。ジョブ型職業としては、美容師、料理人、看護師などが例として挙げられます。
働く場所やスタイルが変わっても、その職業のプロであることに変わりはありません。非正規であっても、オファーされる年俸、待遇や自由度はさまざまのため、メリットがあれば、選ぶ価値はあると思います。
企業にとっても必要な存在! 正規雇用ではなく非正規雇用を採用する理由
正規雇用ではなく非正規雇用を採用する理由
- 人手不足を解消できる
- 人件費を抑えられる
- 育成コストを抑えやすい
正規雇用は定年退職まで勤めるのが基本のため、一度育成すればその後にかかるコストは少なくできます。さらに、正規雇用は固定で勤務する時間が決まってるため、採用すると人材が確保しやすくなるのもメリットです。
しかし、企業のなかには正規雇用ではなく非正規雇用を求めているところもあり、なぜなのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
ここでは、企業が正規雇用ではなく非正規雇用を採用する理由を3つ解説します。企業側の視点を理解しておくと、企業で求められる自分の立ち位置がわかりやすくなります。
人手不足を解消できる
非正規雇用を雇う企業のなかには、純粋に正規雇用だと人材が集まらず、慢性的な人手不足に陥っているところがあります。人手不足が続けば現在働いている正規雇用の負担が大きくなり、退職や体調不良につながる可能性があるのです。
しかし、人によっては正規雇用ではなく非正規雇用の条件であれば就業しても良いという人も多くいます。企業は非正規雇用の雇用枠を用意することでそういった人材を採用し、人手不足の解消を狙っている可能性があるのです。
現在は人手不足でも、非正規雇用が増えてくれば正規雇用の負担が少なくなり、時間をかけて新たな人材を採用する余裕が出てきます。その結果、うまくいけば万銭的な人手不足な状況を解決できる可能性があるのです。
人手不足によって非正規雇用を採用する業界で多く見られるのは、サービス業、製造業、建設業、農業です。
共通するのは繁忙期と閑散期に差があり、繁忙期のみ人手を増員したい際に非正規雇用を採用しています。ほかにも、IT業界や医療分野でも増加傾向にあります。
人件費を抑えられる
飲食業界やアパレル業界などは、人が必要な時間に偏りがある場合も多いです。非正規雇用は正規雇用と違い勤務時間が短い場合も多いため、人が必要な時間にシフトを集中させることができます。
正規雇用のみを採用していると、飲食業界であればランチとディナーの間のアイドルタイム、アパレル業界であれば平日の日中など人が少ない時間帯も人件費がかかります。利益が発生しない時間も人件費がかかってしまえば、企業の全体的な収益が減ってしまうのです。
そのため、業界や企業によってはあえて非正規雇用を採用し、人件費の削減を目指す企業もあります。
育成コストを抑えやすい
業務委託をはじめとした、技術やスキルを持った非正規雇用を人材として採用すると、一から自社で人材を育てるよりも育成にかかるコストを抑えられます。たとえば、他社で実績を積んだプログラマーを非正規雇用で採用すれば、持っている技術を活かして働いてもらえるのです。
企業で活躍できる人材を一から育てるのは、時間も手間もかかり、利益につながるまで時間がかかります。企業は社員が成長するまでの間一時的に高い人件費をかけて非正規雇用を採用しても、契約期間の取り決めが事前にあれば、長期間の損失にはなりません。非正規雇用が利益を出している間に一から自社の社員を育てれば、非正規雇用の契約期間が終わった後も、継続した成果が期待できます。
このように、即戦力となる優秀な人材を採用できることも、企業が非正規雇用を頼る理由です。
正規雇用だけではない! 非正規雇用向けの制度
非正規雇用向けの制度
- 同一労働同一賃金制度
- 雇止め法理
- 5年ルール
給与や福利厚生だけを見ていると、正規雇用ばかりが安定しており、非正規雇用のメリットが少ないと感じる人もいるのではないでしょうか。非正規雇用として長く働いていても、正規雇用に比べればメリットがないと思う可能性もあります。しかし近年では、非正規雇用が働きやすいように制度が整えられているのです。
この章では、非正規雇用向けの制度について解説します。どのような制度があるのか理解しておけば、非正規雇用として長く働いてから役立つ可能性があります。
同一労働同一賃金制度
同一労働同一賃金制度は、厚生労働省が2020年に実施した施策で、同一企業内での正規雇用と非正規雇用の待遇差を減らすための制度です。この施策では給与だけでなく福利厚生や研修制度に関しても、正規雇用と非正規雇用の差をなくすことを目的としています。
この制度は企業にとってマイナスに見える場合もありますが、一方で労働者のモチベーションを高め、入社後の定着率を高める目的もあります。非正規雇用の待遇が悪いことで採用した人材がすぐに退職してしまえば、その期間に育てた手間やコストが無駄になってしまうからです。
そのため、現在は正規雇用と非正規雇用の間に給与や基本的な福利厚生で大きな差は少なくなり、非正規雇用でも働きやすい企業が多くなっています。
雇止め法理
契約社員や派遣社員が急に職を失う可能性がある契約の更新に対して、制限を設ける制度が雇止め法理です。雇止め法理は以下2つの条件に当てはまると適用されます。
雇止め法理の条件
- 更新手続きがルーズで正社員の雇用契約と大きな差がないとき
- 契約社員が更新を期待しても無理がないという事情があるとき
一つ目は、企業が契約社員を更新するときの書類を作っていなかったり、書類を作っていても更新後の作成だったりするときに当てはまります。二つ目は、契約社員に長期雇用を考えていると口頭で伝えているケースなどです。ただし、仕事がなくなったら契約の更新はされないと伝えてあれば、当てはまらないため注意しましょう。
5年ルール
5年ルールとは、雇用期間の定めがある社員が同一企業で5年以上就業する場合、本人の希望があれば無期雇用に転換できる制度です。有期雇用のときと同じ条件で無期雇用に転換できるため、自分にとって働きやすい条件で仕事を続けられます。
5年ルールの特徴は、雇用期間が無期限に変わるだけのため、正社員になるわけではないという点です。雇止めの不安がなくなり、同じ企業で継続して勤務を続けられます。企業としても、同じ人材に長く勤めてもらうため、採用コストや育成コストを下げられるメリットがあります。
ただし、5年ルールは本人からの希望がなければ適用されません。使用したい場合は5年経過してからの更新のタイミングで、担当者に申し出る必要があります。
- 非正規雇用が担当者に5年ルールの適用を申し出るときに注意するポイントがあれば解説お願いします。
5年ルールの適用条件と働き方の希望を確認しておこう
まず、自分が無期転換申込権を行使できる条件を満たしているか確認しましょう。同一の使用者との間で通算契約期間が5年を超える場合、申込権が発生しますが、申し出るタイミングは現在の契約期間中である必要があります。
また、5年ルールの適用の申し出は口頭でできますが、後々のトラブルを防ぐために書面でおこないましょう。
次に、無期契約後の働き方をイメージしておきましょう。無期転換によって雇用は安定しますが、一般的に契約内容や労働条件は現在の契約を引き継ぎます。本当に今の条件のまま、職務に従事したいかを明確にしておきましょう。
さらに、申込権が発生する前に契約を打ち切られる可能性もゼロではないため、雇止めリスクにも備えておくと安心です。
状況を変えたいなら! 非正規雇用から正規雇用を目指す方法
非正規雇用から正規雇用を目指す方法
- 資格取得や勉強でスキルアップを目指す
- 正社員登用制度を利用する
- 転職エージェントを活用する
現在は非正規雇用として働いている場合でも、今後は正規雇用に雇用形態を変更したい人もいるのではないでしょうか。その場合は、非正規雇用から正規雇用に変わるコツを理解しておくと、自分のやるべきことが明確になります。
この章では、非正規雇用から正規雇用を目指す方法を3つ解説します。転職の必要があるのかも踏まえて解説するため、ぜひ参考にしてください。
資格取得や勉強でスキルアップを目指す
現在非正規雇用として働いており、やりたいことが明確な場合は、目指す職業に必要な資格を取得したり、スキルアップを目指したりすることがおすすめです。正規雇用として働く場合、企業はなるべく戦力になりそうな人材を優先して選ぶ傾向があります。
そのため、未経験可の求人であっても、なるべく事前に必要なスキルや知識を身に付けておくと、採用される確率が高まります。たとえば、事務職を目指すのであれば最低限のパソコンスキルを身に付けたり、プログラマーを目指すのであれば、プログラミング技術を磨いておきましょう。
仕事に就くために知識や技術を学んだことをアピールすれば、業務へのやる気や熱意も伝えられます。
まだどの仕事を目指せば良いかわからないときは、これからの時代に役立つ資格を取得しておくと、就職活動が進めやすくなります。こちらの記事ではこれからの時代に役立つ資格を解説しているため、併せてチェックしておきましょう。
また、未経験からプログラマーを目指すなら自分に適性があるかも確認しておきましょう。下記の記事ではプログラマーの仕事内容や適性を解説しているため、目を通しておきましょう。
正社員登用制度を利用する
現在働いている企業に正社員登用制度があれば、利用することで人間関係や仕事内容を大きく変えずに正規雇用に雇用形態を変えられます。ただし、正社員登用制度は企業への導入が推進されていますが、必須ではありません。企業によっては制度自体がない可能性もあるため、気になったら社員に確認することがおすすめです。
また、正社員登用制度を使用するにあたり、企業によっては面接や筆記試験を実施するケースもあります。自分の勤めている企業の正社員登用制度では何をおこなうのか併せて確認しておくと、対策が立てやすくなります。
正社員登用制度を利用して正規雇用になった人の共通点は、契約先の職場の環境や業務内容に満足しており、長期的な勤務意欲を持っていることです。
長期的な勤務先でのキャリア目標がある人は、自分の経験スキルを職場で発揮できており、上司や同僚と良好な関係を築いて信頼関係を構築しています。
転職エージェントを活用する
現在の仕事を辞めて新しい企業の正規雇用を目指す場合は、一人で就職活動をするのではなく、転職エージェントへの相談もおすすめです。転職エージェントはさまざまな企業の求人情報を有しており、候補者の希望する条件や今までの経験から適切な企業を紹介してくれます。
また、転職エージェントでは履歴書の添削や面接練習をおこなうこともでき、一人で就職活動をするよりも直すべきポイントが明確になります。企業が求める人材も把握しているため、どのような回答が適切かアドバイスをくれるのです。
転職エージェントの利用には費用が発生しないため、気になったらまずは相談だけでもしてみましょう。
- 今までアルバイトでしか働いたことがなく、キャリアに自信がありません。良い求人を紹介してもらえないのではと不安がありますが、転職エージェントで仕事を紹介されないケースもありえるのでしょうか?
経験と志望職種によっては紹介されない可能性もある
転職エージェントが大いに役立つのは、以下のケースです。
①経験があり即戦力性が高い仕事に転職する場合
②人手不足の未経験分野に転職する場合
転職エージェントは、就職先企業から紹介料をもらうビジネスモデルのため、企業の求める人材に合致しない場合は紹介されない可能性もあります。
特に、事務職をはじめとした人気職種では、即戦力になる人の応募が優先されるでしょう。それでも希望する職種に応募したい場合は、エージェントを使わず、自分で求人を探して応募することをおすすめします。
就活のプロが解説! 正規雇用か非正規雇用か悩んだときの判断基準とは
正規雇用と非正規雇用への知識を身に付けても、実際に自分がどちらを選べば後悔しないのか、悩む人も多いのではないでしょうか。転職するとなると大きな決断になり、簡単には選べない人も多くいます。
そこでこの章では、キャリアコンサルタントの古田さんに正規雇用か非正規雇用で悩んだときの判断基準を解説してもらいます。自分が何を優先したいのかを明確にして、後悔のない判断をしましょう。
アドバイザーコメント
総合的に判断して働き方を決めよう
①収入、安定性
正規雇用は安定した収入と雇用の継続性が期待でき、福利厚生や退職金なども充実しています。非正規雇用では、収入が不安定になる場合もありますが、短期間で高収入を得られる仕事もあります。
②時間の自由度
正規雇用は基本的にフルタイム勤務のため、時間の自由度は低いです。非正規雇用は時間や期間を選べ、自由度は高く柔軟な働き方ができます。
③キャリアアップ
正規雇用は長期的なキャリアアップを見込める環境であることが多く、専門性を高めることができます。非正規雇用は短期間に多様で広範な経験を積むことができますが、キャリアアップは難しい場合があります。
④個人的な状況
結婚や育児などの、ライフイベントに対するサポートは正規雇用の方が充実しています。また、自身の病気や家族の介護へのサポートも同様です。
非正規雇用は一定の条件を満たしていないと産休や育児休暇を取得できないなど、正規雇用と比べてライフイベントに対するサポートを受けにくい部分があります。
これらのポイントを総合的に考慮し、自分にとって最適な働き方を選ぶと良いでしょう。
正規雇用と非正規雇用で悩んでいる人におすすめのQ&Aも併せてチェック!
正規雇用と非正規雇用の特徴が理解できても、自分に合っている選択肢がわからず悩む人もいるのではないでしょうか。現在非正規雇用として働いていると、そのままで良いのではと考える人もいるはずです。
そこでこの章では、PORTキャリアに寄せられたQ&Aから、正規雇用と非正規雇用のどちらを選べば良いか悩む人におすすめの内容を4つ紹介します。キャリアコンサルタントのアドバイスを参考にして、自分に合った選択をしましょう。
正規雇用と非正規雇用の違いを知って自分に合った働き方を選ぼう
正規雇用と非正規雇用では、給与や福利厚生など4つの違いがあり、何を重視するかで選ぶべき選択肢が変わってきます。自分が重視する部分を明確にしたうえで、それぞれの違いを理解すると、後悔のない選択ができます。
また、非正規雇用から正規雇用を目指す場合は、必要な資格取得や勉強をしてスキルアップを目指すのもおすすめです。
将来的に自分がどうなりたいのかを考え、目指す未来をかなえられる選択肢を選びましょう。
アドバイザーコメント
正社員経験がない場合は一度目指してみることがおすすめ
厚生労働省の調査によると、正社員として働く機会がなく非正規雇用で働いている『不本意非正規雇用』の割合は、非正規雇用労働者全体で2013年の19.2%から2023年の9.6%へと減少傾向にあります。
戦略的に非正規を選ぶのも一つの方法ですが、不安や臆病心から「大変そう」「自信がない」と思ってとどまっているのはもったいないです。特に、一度も正規職を経験せずに年齢を重ねると、不安感が高まると思います。
仕事を選ぶ際は何年続けるつもりかという中長期計画を立てよう
重要なのは、能力開発の視点です。たとえば、5年後にはどのようなスキルを持ち、どれだけ稼げる自分になっていたいかを考え、計画を立てる必要があります。
自分で能力開発について考えるのが難しい場合は、正社員として働き、任された仕事に全力で取り組むことが役立ちます。
若いうちから仕事のえり好み・食わず嫌いをするのはもったいないです。自分の才能や適性はやってみなければわかりません。試行錯誤して、納得いく選択をしましょう。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi







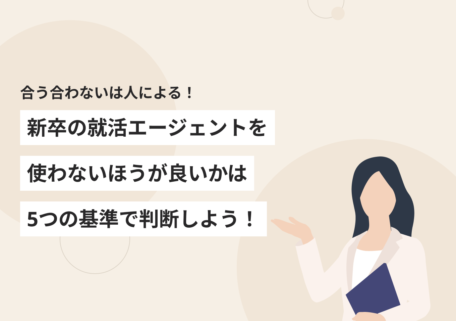









3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー
Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/性格応用心理士1級
Minoru Kumamoto〇就職・転職サイト「職りんく」運営者。これまで500名以上のキャリア相談を受けた実績。応募書類や採用面接の対策支援をする他、自己分析の考え方セミナーを実施
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/公認心理師
Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当
プロフィール詳細