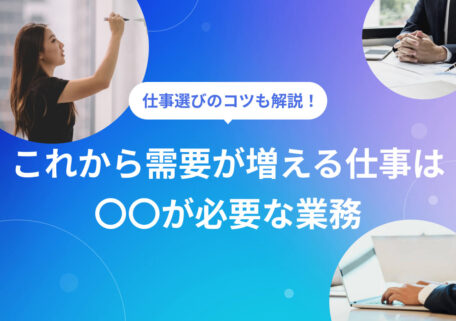Q
大学3年生
男性
公務員と民間企業の違いについて、ずばり模範解答を教えてください!
公務員を目指して勉強中の学生です。公務員試験では、公務員と民間企業の違いについて質問されることがあると聞いたのですが、どのように答えるのが正解なのでしょうか?
それぞれの特徴についてはある程度理解しているつもりですが、「公的機関が運営しているかどうか」くらいしか解答が思いつきません。
ずばり模範解答を教えていただけないでしょうか? 答え方のポイントを知りたいです。
※質問は、エントリーフォームからの内容、または弊社が就活相談を実施する過程の中で寄せられた内容を公開しています
目的と成果の評価軸が大きな違い
公務員試験の面接では、公務員と民間企業の違いを正確に理解し、自分なりの考えを持っているかが見られます。
模範解答としては、仕組みの違いだけでなく、その違いが働き方や価値観にどう影響するかまで言及できると説得力が増します。
たとえば、民間企業と公務員の違いは、大きく目的と成果の評価軸にあります。
目的の違い
公務員は法律や条例に基づいて公共の利益を守ることが目的なので、すべての国民に公平なサービスを提供することが求められます。
これに対し、民間企業は利益の創出が目的なので、顧客に選ばれることで事業が成り立ちます。この違いを明確に認識しているのがポイントです。
成果の評価軸の違い
また、成果に対する評価にも違いがあります。
民間企業では売上や利益といった数値が重要視されるのに対し、公務員は長期的視点や社会的な影響など、短期的には目に見えにくい成果が重視される傾向にあります。
こうした違いを理解したうえで、「民間のスピード感や成果主義にも魅力を感じてはいるものの、地域に根差して長期的に住民に貢献できる公務員の仕事により強く惹かれています」といった形で回答すると良いでしょう。
営利目的かどうかが大きな違い
公務員と民間企業の最も大きな違いは、営利目的であるか否かです。
公務員は税金で運営されており、国民や市民への奉仕が基本であるため、商売はおこないません。意思決定においても、国民や市民のためになるか、税金の適切な使途かが重視されます。
利益と奉仕の視点を意識しよう
一方、民間企業は営利を目的とし、自力でお金を稼ぎます。
そのため、三方よし(会社よし、顧客よし、社会よし)を基本とし、事業によってどれだけの利益を生み出し、顧客や社会につなげられるかという視点で物事を考えます。
同じ事象に対しても、利益のとらえ方が両者で根本的に異なります。身近な例を挙げて、お金の流れを中心に考えると、この違いが明確に理解できるでしょう。
以下の記事では公務員と民間企業の違いを解説しています。「そもそもどう違うのかわからない」と疑問を持つ人は、前提となる情報であるため、必ず押さえておきましょう。
関連記事
公務員と民間企業はここが違う! どちらが向いているかも徹底解説
公務員と民家企業は働き方や業務内容が違うというイメージはなんとなくあるかもしれません。しかし具体的に何が違うかと聞かれると、答えられないかもしれません。就職先を選ぶうえで民間企業と公務員の違いを十分理解しておくことは重要なので、この記事で詳しく解説します。
記事を読む
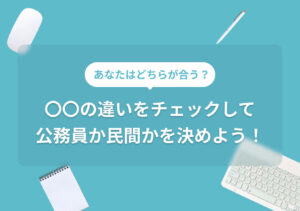
あなたが受けないほうがいい業界・職種を診断しよう
就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。
そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。
自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。