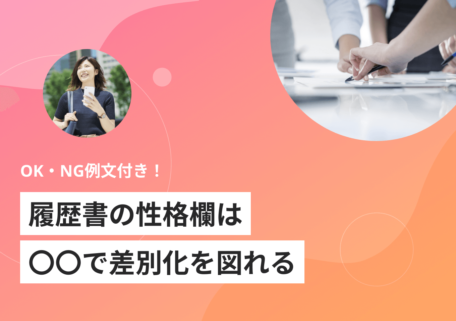Q
大学3年生
女性
就活の小論文は「です・ます」調で書くべきですか?
選考で小論文の提出を求められており、書き方について悩んでいます。
一般的に小論文は「である」調で書くものだと思っていたのですが、採用担当者にそれを提出するのは失礼に当たりそうで抵抗があります。
「です・ます」調で書いたほうが、より敬意が伝わるのではないかと考えていました。
就活の小論文において、「です・ます」調と「である」調のどちらを使用したほうが良いのでしょうか?
もし「である」調で書くのが一般的だとして、あえて「です・ます」調で書いた場合、評価が下がるなどのデメリットはあるのでしょうか?
企業側が就活の小論文で重視している点を踏まえたうえで、適切な文末表現についてプロのキャリアコンサルタントの方からご意見を伺いたいです。
※質問は、エントリーフォームからの内容、または弊社が就活相談を実施する過程の中で寄せられた内容を公開しています
小論文の文体は統一が重要! 評価してもらいたい印象で選ぼう
結論から言うと、どちらでも問題ありません。
ただし、重要なのは文章内で文体を統一することです。「ですます調」で始めたなら最後まで「ですます調」、「である調」で始めたなら最後まで「である調」で書き切るようにしましょう。
である調は客観性を持ち、力強く言い切る印象を与えます。一方、ですます調は就活の場において、面接官に丁寧な印象を抱いてもらいやすいです。
そのため、ご自身がどのように評価してもらいたいかに合わせて、文体を選ぶと良いでしょう。
「ですます調」なら丁寧な印象、「である調」だとスマートな印象に
個人的には「ですます調」のほうが丁寧な印象を受け、読みやすく、内容が入ってきやすいと感じますね。
「である調」で書かれていると、強い思いやスマートな印象を受けるため、最近は「である調」も多く見かけます。
ただ、これは私の推測も入りますが、面接官の年代によっては「ですます調」を好む人が多いかもしれません。
文字数も考慮を! 規定内に収まるかも判断基準に
どちらでなければいけないというルールはありませんが、「印象」のほかに「文字数」も選択の理由になります。
「ですます調」は文字数が多くなりがちです。
そのため、規定文字数内に内容をまとめきるには、簡潔に書ける「である調」を選ぶ学生も結構いるように感じます。
文体は「です・ます」でも「である」でもOK!
結論から言うとどちらでも構いません。小論文で企業が見ているのは文体そのものではなく、「思考の深さ」や「論理的な構成力」、「自分の考えを丁寧に伝える姿勢」だからです。
この悩みは、毎年案外たくさんの学生さんから聞かれますが、人によって文体を変えていました。
たとえば、教育業界を志望していて、「です・ます」調で書ききった学生さんの例があります。読みやすく、温かみのある文体がその人柄とマッチしており、結果的に高評価を得ていました。
一方、コンサル志望の学生さんは「である」調で一貫し、論理的な主張が際立ちました。どちらも成功例です。
テーマに沿ってトーンを調整しよう
大切なのは、「提出対象や目的に合わせたトーン設計」です。企業に提出する正式な文書という意識を持ちつつ、自分の言葉で考えを伝えることがポイント。
もし悩む場合は、募集要項や過去の設問傾向を確認し、学術的テーマなら「である」調、自己意見中心なら「です・ます」調、という形にすると良いでしょう。
結局どちらを選んでも、文体よりも内容の誠実さが何よりも評価されます。文末表現に迷う自分の姿勢こそ、言葉を大切にする誠実さの表れです。自信を持って、あなたらしい論文を仕上げてくださいね。
効果的なES対策をしたいなら
「内定者ES100選」を使いましょう!
「ESに何を書けばいいか分からない…」と悩んでいませんか?就活は限られた時間で効率的に進める必要があります。ESだけに時間をかけすぎるのはNGです。
そんな時に役立つのが、「ES回答例100選」。大手企業に内定した先輩たちの実際のESが無料で見られます。
業界や職種ごとのES例を参考に、効率よく志望企業のESを完成させましょう!