この記事のまとめ
- まずは自身に出ている仕事の限界サイン10項目を確認しよう
- 限界サインが出た状況でやってはいけないNG行動がある
- 仕事の限界サインが出たら検討すべき5つの選択肢
仕事に限界を感じて、「このまま続けるのはきつい」「もう少し頑張ったほうが良いのではないか」と悩む人も多いのではないでしょうか。仕事が原因で心身に限界サインが出ていても、実際に仕事を休むことへの不安は大きいものです。
大切なのは、まず自身の状況を客観的に見つめ直し、適切な対処をすることです。場合によっては、転職や休職を検討することも必要かもしれません。
この記事では、キャリアアドバイザーの木原さん、小西さん、野村さんのアドバイスを交えながら、仕事の限界サインや対処法について詳しく解説します。限界を感じたままの状況で仕事を続けることに悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
【完全無料】
社会人におすすめ!
就職・転職前に使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:年収診断
志望職種×あなたの経験で今後の想定年収を確かめよう!
4位:WEBテスト対策模試
模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
5位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
仕事の限界サインは自分らしいキャリアを見つける機会と前向きにとらえてみよう
仕事に限界を感じることは、多くの社会人が経験する共通の悩みです。一方で、この「限界」と感じたときは、自分らしいキャリアを見つける重要な機会ともいえるかもしれません。
この記事では、仕事の限界サインといわれる10項目や、その対処法について詳しく解説していきます。まずは自身の心身の状態を最優先に、客観的にいまの状況を理解することから始めましょう。そうすることで、今後のキャリアについて適切な行動をしやすくなります。
また、仕事の限界サインが出たときのNG行動も解説します。今後の生活やキャリアを守るためにも、さまざまなリスクを理解しておきましょう。記事の後半では、仕事の限界を感じたときの選択肢を解説します。転職を考える際の判断基準なども含め、今後の働き方とどう向き合っていくか長期的な目線でキャリアを考える際の参考にしてみてください。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。
これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。
また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。
既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。
まずはチェック! 仕事の限界サインといわれる10項目
仕事の限界サインは、身体とメンタルの両面に表れ、それぞれ特徴的な症状があります。まずはこれらの限界サインを認識することで、適切な対処がしやすくなります。
ここでは、仕事の限界サイン10項目を解説します。身体とメンタルの両方に表れる限界サインを自身の状態と照らし合わせながら、チェックしていきましょう。
仕事がつらいと感じる人は、以下の記事をチェックしておきましょう。仕事がつらいと感じるときの対処法や、転職や退職を選択したほうが良いケースも解説しています。
身体に表れる仕事の限界サイン4選
身体に表れる仕事の限界サイン4選
- 体調不良が治りづらい
- 体重の増減が激しい
- 理由もなく突然涙が出ることがある
- 睡眠の質が下がる
身体に表れる仕事の限界サインは、長期的なストレスや過度な労働などが原因で生じやすくなります。特にこれらの体調不良が長引いている場合、注意が必要です。
たとえば、通常なら数日で回復するはずの風邪や疲労感がなかなか治らない状態が続いているのであれば、早い段階で療養する必要があるかもしれません。
また、睡眠の質の低下も重要なサインです。寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりすることが続くと、日中の仕事のパフォーマンスにも大きく影響します。これらの症状が複数表れている場合は、身体が発するSOSとしてとらえて、早めの対策を考えることが大切です。
身体に表れる仕事の限界サインとして特に注意すべきは、慢性的な疲労感と睡眠障害です。休んでも疲れが取れず、不眠や過眠が続く場合、身体が回復できていない可能性が高いです。
これらのサインを軽視すると、心身の健康が損なわれ、最終的にはバーンアウトと呼ばれる燃え尽き症候群やうつ病などの深刻な問題に発展する恐れもあるため、放置せず早めの対策が肝心です。
入社後のミスマッチに苦しみたくない人は、まずは自分に合う仕事を把握しよう
既卒の就活は新卒時と異なり、選択肢が限定されます。焦って適性のない企業に入社すると、現場とのギャップに悩み、早期離職を繰り返す負のスパイラルに陥りかねません。
既卒の人は、「適職診断」を活用しましょう。質問に答えていくだけで、あなたの価値観や特性を数値化し、相性の良い職種を特定します。
「自分に合う仕事」という明確な根拠を持って企業を選べるため、入社後のミスマッチで苦しみたくない人は今すぐ活用しましょう。
メンタルに表れる仕事の限界サイン6選
メンタルに表れる仕事の限界サイン6選
- 悲しみを感じることが増える
- 常に孤独感がある
- 些細なことにイライラするようになる
- 身だしなみに気を使えなくなる
- 仕事でミスが増える
- 何もしたくない無気力な状態が続く
メンタルに表れる仕事の限界サインが出た場合、業務を続けていることで心理的な負荷が蓄積されている可能性が高いといえます。怒りや悲しみを頻繁に感じたり、些細なことにイライラしやすくなったりする傾向が強まっていると、業務に集中できず仕事のミスが増えやすくなります。
特に、何もしたくない無気力な状態が続いている場合、仕事だけではなく日常生活に影響するほど深刻である可能性が高いため、心身の状態が悪化する前に早めに対処することが必要です。
また仕事の限界サインがメンタルに表れる場合、身体に表れる限界サインよりも自覚しづらいため、日々の感情を見逃さないようによく振り返りましょう。
メンタルに表れる仕事の限界サインのなかでも特に、身だしなみに気が配れなくなる状態には注意が必要です。具体的には、髭が伸び放題、髪がボサボサ、服がヨレヨレといった状態です。
接客など対人の仕事が多い人は、相手に不快な印象を与えかねません。日常生活でも、同じことがいえます。メンタルの乱れは外見に表れるので、周囲の人が異変に気付いてくれることもあります。
仕事でミスが続いて悩んでいる人はこちらの記事をチェックしてください。原因やミス後の対応を詳しくまとめています。
以下のQ&Aでは、仕事をしたくない状況を打破する方法についてキャリアコンサルタントが解説しています。併せてチェックして理解を深めましょう。
自分で改善するのが難しい! 仕事の限界サインが出る外的要因4つ
自分で改善するのが難しい! 仕事の限界サインが出る外的要因4つ
- 職場の人間関係が悪い
- 任される仕事量が多すぎる
- 業務に対する評価や給与が不公平
- 苦手な業務を任されている
仕事の限界サインには、自身の行動だけでは改善が難しい外的要因が関係していることがあります。外的要因は、職場環境や業務内容に深く根ざしているため、個人の力だけでは根本的な解決ができない可能性があるのです。
ここでは、仕事の限界サインを引き起こす外的要因を4つ解説します。これらの外的要因を理解することで、自分の状況をより客観的に分析しましょう。
仕事のストレスを常に感じている人は、こちらの記事もおすすめです。仕事で溜め込んだストレスを解消するおすすめの方法や、ストレスを溜め込まないようにする対策まで解説しています。
仕事選びでミスしたくないなら、自分と相性のいい仕事を特定しよう
既卒採用において、企業は「長く活躍してくれるか」を厳しくチェックしています。自分の適性を把握しないまま進める就活は、不採用のリスクを高めるだけでなく、入社後のキャリアを台無しにする危険があります。
仕事選びでミスしたくない人は、「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの価値観や特性を数値化し、相性のいい仕事を特定します。
あなたの資質が最大限に活かせて、長く活躍でき仕事に就くためにも、今すぐ診断を活用しましょう。
①職場の人間関係が悪い
職場の人間関係が悪化すると、日々のストレスが増大し、仕事への意欲が低下する原因となります。特に問題となるのは、パワーハラスメントやモラルハラスメントです。自身を侮辱する発言や暴言などの精神的な攻撃は個人の尊厳を傷つけ、メンタルに悪い影響を与えます。
また、職場の人間関係が悪いとチームで協力しづらくなったり、過度な競争意識が生まれたりして仕事を進めづらくなる要因となります。自身が直接被害を受けていなくても、周りの同僚が問題を抱えている状況では、仕事に集中できなくなる要因になります。
職場の人間関係が悪い状況を個人の力だけで改善することは難しいことを覚えておきましょう。
- 職場の人間関係が悪くてもう限界です……。
職場の人間関係のほとんどは組織の責任
職場でのパワハラやモラハラ、チーム内の人間関係の悪化は、非常につらいでしょう。これらの問題は多くの場合、あなた自身のせいではなく、外的要因によって引き起こされています。
あなたがどれだけ努力しても他者の行動を変えることは難しいため、自分を責める必要はありません。自分の健康と幸福を最優先に考え、信頼できる同僚や上司に相談したり、必要に応じて人事部門や専門機関に相談したりすることも検討してください。
職場の人間関係が悪いことから、人とかかわりたくないと感じた人には以下の記事もおすすめです。人とかかわるストレスを軽減する方法や、できるだけ人とかかわらずに働ける仕事10選を解説しています。
②任される仕事量が多すぎる
日々の業務量が個人の処理能力を超えると、残業や休日出勤が増えて心身ともに疲弊しやすくなります。特に仕事量の増加が一時的ではなく、日常的である場合は人員不足や非効率な業務プロセスなど、組織的な問題が背景にあることが多いため、個人の努力だけでは解決が難しくなります。
また、仕事量の多さは単に時間の問題だけではなく、生産性の低下にもつながります。たとえば、締め切りに追われるあまり、丁寧な仕事ができなくなったり、ミスが増えたりすることで、さらなるストレスを生み出す悪循環に陥り限界サインを感じやすくなるのです。
今の仕事量が多く悩みがある人はことらの記事を参考にしてみてください。多くなってしまう原因や対処法を詳しくまとめています。
仕事量が多すぎて仕事に限界を感じている人には、こちらの記事もおすすめです。仕事が終わらないときに考えられる原因や、仕事が多いときの対処法を解説しています。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
③業務に対する評価や給与が不公平
業務に対する評価や給与に対して不公平さを感じることは、モチベーションの低下や仕事への不満を引き起こす要因となります。自身の努力や成果が正当に評価されない環境では、仕事への意欲が低くなり限界サインと感じるのも無理はありません。
この問題は、評価基準の不透明さや、上司との認識のズレから生じることがあります。また、同じ業務量や責任を負っているにもかかわらず、給与に大きな差がある場合も不公平さを感じやすくなります。
さらに、昇進や昇給の機会が限られていると感じることも、将来のキャリアに対する不安を生み出します。このような状況は、組織の評価システムや報酬体系を見直す必要があるため、個人の努力で変えられないケースがほとんどです。
- 上司や会社の評価に納得できません……。
部下の評価をする上司側の問題という可能性もある
上司や会社からの評価に納得できないと感じたときは、まず評価基準や評価コメントが定量的か、具体的で明確かを確認しましょう。
もし曖昧で属人的な基準による評価であれば、個人の努力だけでは解決が難しい可能性があります。このような場合、上司に定期的なフィードバックを求め、評価基準の具体化や確認の機会を設けることをおすすめします。
また、信頼できるメンターやほかの同僚にも意見を聞き、自分の立ち位置を客観的に確認することも重要です。
それでも改善が見られない場合、長期的なキャリアを考慮し、環境を見直す選択肢もありうるかもしれませんが、くれぐれも慎重に考えて行動してください。
④苦手な業務を任されている
自身の適性や興味と合わない業務を任されることは、ストレスの原因になります。特にその業務が自身の強みを活かせない分野であったり、入社当時に想定していた業務とかけ離れている場合、限界を感じることで仕事の効率や質が低下しやすくなります。
苦手な業務を任されていることを新しい分野に挑戦する機会ととらえることもできますが、長期間にわたってこの状況が続くと、モチベーションの維持が難しくなることも少なくありません。
さらに、苦手な業務によるストレスは、本来得意な業務にも悪影響を及ぼす可能性があります。自身の能力を十分に発揮できない状況が続くと、キャリア全体に対する不安や焦りも生じやすくなります。
意識で変えられるかも? 仕事の限界サインが出る内的要因4つ
意識で変えられるかも? 仕事の限界サインが出る内的要因4つ
- 周りに気を遣いすぎている
- 何事も周りと比べてしまう
- 業務で人に頼れない
- プライベートと仕事の切り替えができていない
仕事の限界サインには、外的要因だけではなく、自身の内面にかかわる要因も影響しています。これらの内的要因は、自身の意識や行動パターンに根ざしているため、気付きと努力次第で改善できるかもしれません。
ここでは、仕事の限界サインを引き起こす内的要因4つを解説します。仕事の限界を感じている状況に対して、効果的な対処法を見つけるためにも、事前にこれらの要因を理解しておきましょう。
仕事の限界サインが出る内的要因を改善したい人には、こちらの記事もおすすめです。結果を残している人の特徴や考え方のコツを理解しておくことで、仕事のストレスを和らげられるかもしれません。
まずは自己分析ツールで自分の強み・弱みを確認しよう!
「自己分析って時間がかかるし、正直面倒だな」と思っていませんか。
「自己分析ツール」を使えば、たった3分であなたの強みに合った適職を見つけられます。
自己分析を億劫に感じるときは、ツールを使って効率化しましょう。
- 自分の強みや弱みが分からない人
- 自己PRや志望動機に使える長所を知りたい人
- 自分にあった仕事を知りたい人
①周りに気を遣いすぎている
周囲への過度な気遣いは、自身のストレスを増大させる要因となります。常に周りの人の反応を気にしたり、自分の意見を抑えたりすることで、本来の自分らしさを失ってしまい限界サインとして表れる危険性があるのです。
特に自分の業務を後回しにして周りの期待に応えようとしてしまうと、自己犠牲の積み重ねとなり、長期的には心身の疲労につながります。
また、過度な気遣いは業務効率の低下も招きます。たとえば、断るべき仕事を引き受けてしまったり、必要以上に同僚の仕事をフォローしたりすることで、自分の業務に支障をきたす場合があります。
②何事も周りと比べてしまう
常に自分を周りの同僚と比較することは、自尊心の低下を引き起こす要因となります。たとえば、同僚の昇進のみに注目してしまい、昇進できていない自分を責めたり、自身の成長や努力を過小評価したりしてしまうことなどが挙げられます。
日頃から他人と比較してしまう習慣がある場合、周囲の華やかな面のみを目にすることで、自分の現状に不満を感じやすくなっている可能性があります。しかし、そこで見えているのは、その人の一面に過ぎません。
また、比較の対象が適切でない場合も考えられます。たとえば、経験や立場が大きく異なる人と自分を比べてしまい、必要以上のプレッシャーを感じてしまうことがあります。
周りの人々に刺激されて仕事の成果を上げていくことは重要ですが、過度な比較をすると精神的な負担となる可能性もあるのです。
仕事の成果に関してあなたと他人の優劣を判断するのは上司の仕事であって、あなたの仕事ではありません。
ついつい周りが気になってしまう気持ちはわかりますが、自分でコントロールできないことを気にしてもメンタルが削られるだけです。「なるようにしかならない」ぐらいの気の持ちようが大切です。
③業務で人に頼れない
仕事で人に頼ることができないと、自分の負担が増えて限界サインを感じやすくなります。その心理は、過剰な責任感や「他人に迷惑をかけたくない」という思いから生じていることが考えられます。しかし、すべての業務を一人で抱え込むことは、過度な負担やストレスにつながりかねません。
また、チームワークの観点からも問題があり、周囲と信頼関係を構築する機会を逃してしまう可能性があるのです。さらに、自分の能力以上の仕事を抱え込むことで、業務の質の低下やミスの増加を招くリスクもあります。
これは結果的に、自己評価の低下や仕事への自信喪失につながってしまうため、キャリアにも悪い影響を与えるかもしれません。
- 上司や先輩に声をかけづらいため、頼ることに抵抗があり一人で抱え込んでしまいます……。
周囲に頼ることはむしろ良いことだととらえよう
責任感が強いことは素晴らしい長所ですが、一人ですべてを抱え込むことは逆にリスクを高めることがあります。業務はチームで進めるものであり、周りに頼ることも大切なスキルです。
上司や先輩はあなたをサポートするためにいるので、遠慮せず声をかけてみましょう。頼ることは決して迷惑をかけることではなく、周囲との信頼関係を築き、チームの業務の質を向上させる有効な手段です。
まずは小さな相談から始め、少しずつサポートを受け入れることで、仕事がよりスムーズに進み、結果としてより大きな成果を出せるはずです。
あなたの努力を無駄にしないためにも、周囲を信頼して協力を求めてみてください。
自己分析で悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!
ChatGPTなどの生成AIは、就活準備にも非常に役立ちます。
「就活準備プロンプト集」では、就活のプロが考えた、生成AI用の命令文を豊富に用意していますよ。
このプロンプト集を活用すると、性格と経験を入れるだけで、AIが5つの強みを判断してくれます。プロンプト集で就活準備を効率化しましょう。
- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト
- チャットを使用した、模擬面接プロンプト
- 自己PRで使える強み診断プロンプト
④プライベートと仕事の切り替えができていない
仕事とプライベートの境界線が曖昧になることは、心身の疲労を蓄積させる要因となります。たとえば、常に仕事のことを考えている状態では、十分な休息が取れません。
休日や就業後も仕事関連のメールをチェックしたり、業務の心配をしたりすることで、リフレッシュの機会を逃してしまいます。
またこの状態が続くと、家族や友人との時間が犠牲になり、プライベートの人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、趣味や自己啓発の時間が取れなくなることで、長期的には仕事の質に悪い影響が出るかもしれません。
特にリモートワークをしている場合、時間や場所を問わず仕事ができてしまうため、仕事とプライベートの区別が付きにくくなり、限界サインが生じやすくなります。
キャリアのプロからのアドバイス! 仕事の限界サインが出たときの対処法
仕事の限界サインについて理解を深めたものの、「具体的にどのように対処すれば良いかわからない」と悩んでいる人もいるでしょう。仕事に限界を感じながらも、解決するためにすぐ行動に移せないことで、もどかしさを抱えている人もいるかもしれません。
そこで、多くの就業者を支援してきたキャリアアドバイザーの木原さんに、仕事の限界サインが出たときの効果的な対処法について聞きました。プロの視点から見た実践的なアドバイスを参考に状況改善に役立てましょう。
アドバイザーコメント
物事のとらえ方を見直す練習をしてみよう
仕事の限界のサインが出たとき、内的要因なのか外的要因なのかを考えて対処することが重要です。内的要因は、個人の思考や感情が影響するものです。
たとえば、自分以外の人達がひそひそ話をしている場面において、まったく気にならない人もいれば、「自分の悪口を言われているのではないか」と気が気ではなくなる人もいます。
一方で、「何か自分へのサプライズかな」とポジティブにとらえ、ワクワクする人もいるのです。
必要以上に気にしすぎたりネガティブにとらえたりしていないかなど、自分のものの見方や考え方に意識を向けることで、楽しく働くことはもちろん、豊かな人生を送ることにもつながります。
外的要因から心身を守るためにできる行動
一方で外的要因には、仕事の環境や業務量、職場の人間関係が関係するため、個人の努力だけではすぐに解決が難しいことも多いです。
自分一人で解決しようとせず、周囲のサポートを求める姿勢も大切です。どうしても解決が難しい場合には、思いきって外部環境を変えることも選択肢の一つでしょう。
限界サインに気付いたらまずは無理をせず、自分の心身を守ることを最優先に考えてください。心身ともに健康的な働き方を目指すことが、長期的なキャリア形成においても重要です。
リスクを知っておこう! 仕事で限界サインが出たときのNG行動
リスクを知っておこう! 仕事で限界サインが出たときのNG行動
- 今の職場で無理をしすぎる
- 無断欠勤する
- 仕事が限界と感じるのは甘えだと思い込む
仕事の限界を感じたとき、思わず取ってしまいがちな行動のなかには、状況をさらに悪化させてしまうものがあります。これらの行動は一時的な解決策に見えても、長期的には自身のキャリアや心身の健康に悪い影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
ここでは、仕事で限界サインが出たときに避けるべきNG行動を解説します。これらのNG行動のリスクを理解して、より適切な対処をできるようにしましょう。
今の職場で無理をしすぎる
すでに限界を感じている状況で残業や休日出勤をし続けることは、一時的に業務をこなせたとしても長期的には心身の健康を損なってしまう危険があります。また無理を重ねることで仕事の質が低下し、ミスが増えるなど、本来の目的とは逆効果になる可能性もあるのです。
さらに、周囲の人々から過度に期待されたり、負担をかけたりしてしまうリスクもあります。「この人なら大丈夫」という認識が広まり、さらなる無理を強いられる悪循環に陥る可能性も考えられます。
自身の限界を認識し、適切に休息を取ることが、長期的には生産性の向上につながります。無理をせず、自身に合った働き方を模索していきましょう。
責任感が強い人や、完璧主義がたたってすべての仕事を自己完結したいような人は、一人で抱え込み背負いがちです。
仕事がうまく回っているときは問題ないのですが、不調に陥り仕事に支障をきたすようになると、組織に多大な負の影響を与える恐れがあります。
無断欠勤する
仕事の限界サインが出て無断欠勤してしまうことは、一時的な逃避に過ぎず、問題の根本的な解決にはつながりません。むしろ、さまざまな面で状況を悪化させる可能性があります。
まず、無断欠勤は職場の信頼関係を著しく損ないます。同僚や上司との関係が悪化し、復帰後の職場環境がさらに厳しくなる可能性もあるのです。また、社内評価としてマイナスポイントとなり、将来の昇進に悪い影響を与えることもあります。
さらに、無断欠勤に関する記述が就業規則に定められていて、それに該当する場合、懲戒処分の対象となることがあります。また目安として2週間以上の無断欠勤が続くと、無断欠勤による解雇が裁判所で正当と判断される可能性があるのです。
無断欠勤を考えてしまうほど仕事に限界を感じる前に、状況の改善に取り組むことが大切です。
無断欠勤はNGと感じていても、今の状態で無理をして出勤すると自分をさらに追い詰めることになるかもしれません。疲れや気力の低下は、これまで頑張ってきた証拠です。
自分を責めず、心の声に耳を傾けて、休むことを選んでみてください。もし会社への連絡が難しいと感じるなら、短いメッセージでも構いません。
自分で連絡することが難しい場合は、友人や家族に頼っても良いです。心の健康が最優先なので、焦らずに自分を大切にしてくださいね。
仕事が限界と感じるのは甘えだと思い込む
「仕事が限界と感じるのは甘えだ」と思い込むことは、自身の心身のSOSサインを無視することになるため、問題をさらに悪化させる原因となります。
限界を感じたことには決してネガティブな要素だけではなく、仕事を真面目にやっているというポジティブな要素もあります。また、限界を感じたということは、自身の状況を把握できているという証ともいえるのです。
仕事に限界を感じることは決して甘えではなく、自己管理能力の表れだととらえましょう。自身の状態を正確に認識し、必要に応じて周囲に相談するなどして適切な対処をおこなうことで無理なく仕事を続けやすくなります。
無理は禁物! 仕事の限界サインが出たときの5つの選択肢
無理は禁物! 仕事の限界サインが出たときの5つの選択肢
仕事の限界サインに気付いたときは、それぞれ適切な対処をすることが重要です。しかし、具体的にどのような選択肢があるのか、わからない人も多いのではないでしょうか。限界を感じているからこそ、冷静な判断が難しくなっているのかもしれません。
ここでは、仕事の限界サインが出たときの5つの選択肢について解説します。無理をせず、自分のペースで最善の選択をするための指針として、これらの選択肢を参考にしてください。
仕事の限界サインが出て、仕事に行きたくないと感じている人は、こちらの記事もチェックしておきましょう。自分や仕事を客観的にとらえ、不安を解消する方法を解説しています。
①思い切って仕事を休む
仕事の限界サインが出たら、思い切って休暇を取ることで、問題に冷静に向き合いやすくなります。仕事が中心となる日々からできるだけ離れて、十分な睡眠や趣味の時間を確保すると、心身がリセットできます。
また、この期間を利用して自分の状況を客観的に見つめ直し、本当に今の働き方を続けていって良いのかを熟考することも可能です。可能であれば、有給休暇を取得したり、短期間の休職を検討したりして、心身をリフレッシュさせましょう。
なお休職制度を利用する場合、企業によって休職の条件や期間が定められているため、事前に確認しておくのがおすすめです。自身の心身の状態を最優先に考え、必要に応じて中長期で休むことを視野に入れて、検討してみてください。
仕事を休む決断をなかなかできない人は、以下の記事がおすすめです。キャリアの専門家とともに「仕事を休むことは甘えなのか」について解説しているので、仕事の向き合い方をもう一度考える際の参考にしてみましょう。
②信頼できる人に相談する
仕事の限界を感じたとき、信頼できる人に相談することで問題を解決したり、自分では気付かなかった問題の視点や解決策が見つかったりすることがあります。また、悩みを共有することで、精神的な負担が軽減されるかもしれません。
特に職場の上司や人事部門に相談する場合は、具体的な改善案を一緒に考えやすくなります。たとえば、業務量の調整や役割の見直しなど、実践的な解決策を見出せる可能性があります。
なお、相談相手には、すでに信頼関係があり、自身の状況を理解してくれる人を選ぶことが大切です。また、相談する際は感情的になりすぎず、できるだけ冷静に状況を説明することを心掛けましょう。
- 相談相手をどのように選ぶのが良いのでしょうか?
悩みの種類によって相談先を変えることが大切
極めて慎重かつ冷静に相談相手を選ぶことが肝要です。相談相手を間違えると、かえって心の傷口が広がってしまいます。
これまでの付き合いを通じて、人として信頼できるうえ、しっかりと秘密を守れる口が硬い人を見極める必要があります。また、人生経験が豊富な人であれば、アドバイスの引き出しをたくさん持っていることが多いです。
仕事や仕事に関係する人間関係がメインの悩みの場合は、上司や人事部門、あるいは入社時から面倒を見てもらっている先輩などが良いでしょう。あなたが考えもしなかった道に導いてくれるかもしれません。
メンタル面の悩みなら、仲の良い同期なども適切です。お互いに似たような悩みを抱えていて「話しているうちにスッキリした」ということもあるかもしれません。
あるいは、外部リソースを活用することも選択肢の一つです。たとえば我々のようなキャリアコンサルタントや産業カウンセラーは、その道のプロです。
③プライベートを充実させる
仕事以外の時間を意識的に楽しむことで、ストレス解消やモチベーション回復につながる可能性があります。具体的には、趣味の時間を増やしたり、家族や友人との交流を深めたりすることが考えられます。
さらに、適度な運動や健康的な食生活を心掛けることも重要です。体調管理は心の健康にも直結するため、日々の生活習慣を見直すことが仕事のストレスを和らげることもあります。
プライベートを充実させることは、仕事の問題から逃げることではありません。むしろ、リフレッシュした状態で仕事に向き合うための準備ととらえましょう。仕事とプライベートのバランスを取ることで、長期的には仕事のパフォーマンス向上にもつながる可能性もあるのです。
④部署異動を打診する
仕事の限界を感じて、いまの部署で状況を改善することが難しいと感じた場合、部署異動を検討するのも選択肢の一つです。新しい環境や業務内容の変更が、モチベーションの回復や自身に適した仕事環境を見つけることにつながる可能性があります。
部署異動を打診する際は、まず上司や人事部門と話し合うことが重要です。自分の状況や希望を明確に伝え、会社の方針を踏まえたうえで取れる選択肢を把握しましょう。
部署異動をする際は、一時的な逃避にならないように注意が必要です。なお異動先でも同じ問題に直面する可能性はあるため、根本的な原因と向き合うことが大切です。
たとえば、数字を扱う分析業務に苦手意識があり、毎日必ず残業をしなければならないほどその業務と向き合っているとします。その現状に強いストレスを感じているなら、仕事の適性について上司に一度相談し、そのうえで改善の見込みが感じられなければ部署異動を検討しても良いといえます。
その場合、可能であれば異動にともなうキャリアへの影響も考慮したうえで、長期的な視点を持って決断しましょう。
上司に相談しづらい場合、上司のさらに上の立場の人や、人事部の人に直接相談するのも有効です。ただしその際は、状況を冷静かつ客観的に伝えるようにしましょう。
また、信頼できるメンターやほかの上司への相談をサポートしてもらうために人事部門に相談するのも、一つの方法です。
⑤転職を検討する
会社の事情で部署異動ができず、職場で生じた問題が解決できる見込みがないなら、転職を検討することも選択肢の一つです。転職をすることで、キャリアの再構築やモチベーションの回復につながる可能性があります。
転職を検討するうえで重要なのは、仕事で限界を感じた原因の解消につながる適切な選択肢を選ぶことです。たとえば、インフラエンジニアをしていて夜勤や休日出勤があることによって、仕事の限界を感じたなら、日勤以外のシフトが生じやすいインフラエンジニアという職種自体が自身に合っていない可能性があります。
そのため、限界を感じた問題によって幅広い視野を持って、転職先を検討しましょう。また転職において不安な要素やその後のキャリアで悩むことがあるなら、転職エージェントに相談するのもおすすめです。
転職エージェントは採用担当ではないため、現状の不満を正直に話しやすいところがメリットといえます。転職のプロの意見を参考に、自身が納得できる転職先を探しましょう。
- 仕事が限界なのですが、転職するか部署異動を打診するか迷っています。どういった基準で決めたら良いのでしょうか?
現職で解決可能かどうかが判断のポイント
転職するか部署異動を打診するかを判断する際は、まずストレスの原因を特定しましょう。業務内容や人間関係、仕事環境など、具体的な要素の観点から原因を洗い出します。
次に、キャリアの目標を振り返り、自分が目指す方向性に合う選択肢を考えてみてください。現職で解決可能な問題であれば、まずは部署異動を打診するのが有効な手段です。
ただし、会社全体の方針や風土に不満がある場合は、転職を視野に入れても良いかもしれません。最終的には、自分がどちらの選択でより健やかに、前向きに働けるかを自分基準で判断することが大切です。
転職に伴って退職の相談をする前に、以下の記事もチェックしておきましょう。退職を上司に相談する際の適切なタイミングや、伝え方について解説しています。
慎重に行動しよう! 仕事の限界サインを感じて転職する際のコツ
転職は新たなキャリアへの扉を開く可能性がある一方で、適切な準備や判断がなければ、同じ問題に直面するリスクもあります。仕事の限界サインを感じて転職を決めるなら、あらゆる可能性を考慮して慎重に行動することが重要です。
ここでは、仕事の限界サインを感じて転職する際のコツを解説します。これらのコツを理解し、実践することで、より良い転職先の選択と新たな環境でのキャリアを歩みやすくなります。
心身の健康を整えてから転職先を考える
仕事の限界を感じて転職を考える際、心身の健康を整えて冷静な判断ができる状態かを確認しましょう。心身が疲弊した状態で転職活動を始めると、長期的な視点での判断が難しくなり、自身のキャリアにとって適切な選択ができない可能性があります。
自身の心身の状態が万全でないなら、まずは十分な休息を取り、ストレスを軽減することが重要です。また、必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
キャリアカウンセラーや心理カウンセラーなどの助言は、自己理解を深め、より良い転職の方向性を見いだすのに役立ちます。
このように、心身の健康が整ってから転職先を考えることで、自分に本当に合った職場を冷静に選択できる可能性が高まります。焦らず、自分のペースで準備を進めることが、転職を成功させるカギです。
仕事の限界サインが出た原因を排除できる職場を見極める
転職先が仕事の限界サインが出た原因を排除できる職場でないと、同じ問題に直面する可能性があります。転職先を検討する前に、まず現在の仕事の何が限界と感じる原因なのか、問題の本質を見極めることが重要です。そして、転職によってその問題を解決できる可能性が高いかを冷静に判断しましょう。
たとえば、限界サインが出た原因が残業の多さであった場合、転職先候補となる企業の平均残業時間や有給休暇取得率、労働時間の管理方法などを確認することで、同じ失敗を繰り返すリスクを減らせます。
なお、自身が理想とする転職先の求人が現時点で出回っていない場合、納得のいく求人が見つかるまで中長期で転職活動を続けていくことになります。転職エージェントに相談したり、興味のある企業の採用情報を定期的にチェックしたりして、積極的に情報を収集するように心掛けましょう。
転職に不安を感じた場合は、まず限界を感じた原因を明確にし、それが新しい職場で解決できるかを慎重に見極めましょう。
また、焦らず冷静に自己分析を行い、自分に合った環境を見つけるための準備を進めることで、不安を軽減しながら前向きな転職を実現できるはずです。
仕事の限界サインが出たら心身の健康を優先してキャリアを見直そう
仕事の限界サインを感じたときは、まず自分の心身の健康を最優先に考えることが重要です。記事では仕事の限界サインの具体的な症状や、限界サインが出る外的・内的要因について詳しく説明しました。これらの情報をもとに、自分の状況を正確に把握することが、適切な対処への第一歩となります。
特に限界サインが長期的に出ているなら、無理をせずに休暇を取ったり、信頼できる人に相談したりするなど、状況に応じて対処しましょう。必要であれば、部署異動や転職も視野に入れて、今後のキャリアを長期的な視点で検討することが大切です。
心身の状態が回復してきたら、より充実したキャリアを築くために少しずつ行動してみるのがおすすめです。より自分らしい働き方を見つける機会として仕事の限界サインを活かし、充実したキャリアを実現させましょう。
アドバイザーコメント
限界サインが出るのは仕事を頑張っている証拠
人間は誰しも、そんなに強いものではありません。例えが適切かどうかわかりませんが、大谷翔平選手のように鋼のようなメンタルを持っている人はほとんどいないのが実情です。
したがって、仕事で限界サインが出るのは当たり前のことです。何ら恥ずかしいことではなく、弱くてダメな人間というわけでもありません。
日々の仕事は本当につらいものです。楽しみながら仕事をしている人なんて、ほんの一握りではないでしょうか。大半の人は、仕事をしていれば悩みやトラブルなど当たり前のように出てくるものです。
そうしたなかで頑張り続けている人達には、本当に「お疲れ様です」の言葉しか見当たりません。
今の環境に耐え続けなければならない理由はない
ただ、限界サインを出し続けっぱなしで、一向に回復の兆しが見られないようなときは、環境を変えることも必要です。転職やキャリアチェンジがこれに当たります。
組織にとって、あなたの代わりはいくらでもいるのです。総理大臣や米国大統領ですら、何かあったときの代理を定めていて、交代要員はすぐ出てきます。
「我慢を続ければいつか好転するはず」というのは希望的観測にほかならない場合もあります。今後どう働き生きていきたいかを考え、その理想に合った行動を選んでみてください。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi














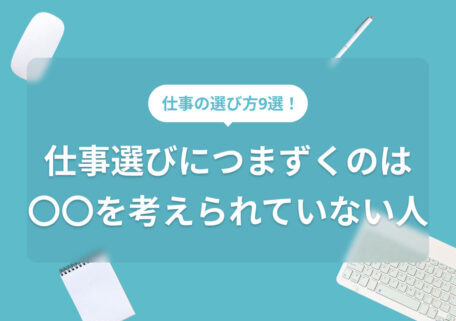








3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/Koyoriキャリアワールド代表取締役
Chieko Kimura〇2度のアメリカ留学、20年以上の外資系IT企業勤務を経て、現在は留学生向け就職支援をおこなう。また、企業のキャリア支援や新入社員のクラウドコーチングなどにも幅広くたずさわる
プロフィール詳細大学教員/キャリアコンサルタント
Kazuyoshi Konishi〇大手メディア政治記者から駐在員の夫としてキャリアを一時中断。帰国後は大学院でキャリア形成を研究する一方、ジャーナリストとして活動、現在は大学教員として活躍中
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表
Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う
プロフィール詳細