この記事のまとめ
- 就職で役立つ簿記は何級かキャリアコンサルタントが解説
- 簿記が役に立たないと言われる理由を理解して取得するか決めよう
- 就活のプロが説明! 簿記を就職活動で武器にする方法とは
簿記の資格を取得していると、就職活動で活かせるのか気になる人もいるのではないでしょうか。簿記の資格は企業の経理部や会計事務所などの仕事に直接関係するだけでなく、アピールの仕方によってさまざまな仕事に活かせるのです。
しかし、自分の目指す職種に対する適切な簿記のアピール方法が理解できていないと、採用担当者の印象には残りにくくなります。
この記事では、簿記を就職活動で活かす方法をキャリアコンサルタントの野村さん、板谷さん、渡部さんと一緒に解説します。簿記の資格から採用担当者がどのような印象を持つのか理解して、アピールの仕方を考えましょう。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
1位:自己PR作成ツール
自己PRが思いつかない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
2位:志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
3位:WEBテスト対策模試
模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
4位:面接回答集60選
見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました
5位:逆質問例100選
面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています
【併せて活用したい!】
スキマ時間3分でできる就活診断ツール
①適職診断
たった30秒であなたが受けない方がいい仕事がわかります
②面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
簿記の活かし方の理解は就職活動での差別化につながる
一言で簿記を取得していると言っても、業務で直接的にスキルを活かせるのは企業の経理職や会計事務所で勤務する場合が多いです。そのため、簿記の資格は就職活動で役立たないと思う人もいるのではないでしょうか。
しかし、簿記の資格をアピールする際はほかの学生との差別化を意識することで、企業の経理部や会計事務所以外の企業でも活躍できることを伝えやすくなります。さらに、簿記で得た知識や能力が企業の情報収集にも役立つのです。
そこでこの記事では、最初に就職活動で役立つ簿記の基礎知識や、各級の難易度や可能な業務レベルを解説します。簿記の資格といっても、就職活動では何級が必要なのか理解して、取得を目指しましょう。
そしてその後で、簿記の資格が役立つ就職先や、就職活動で簿記をアピールする方法を解説します。記事を最後まで読めば、就職活動で簿記を活かす方法が理解でき、納得いく就職先を見つけやすくなります。
「簿記」をアピールするなら、自己PR作成ツールを活用しよう
自己PRは就活において必ずといっていいほど必要になります。自己PRが曖昧なまま就活がうまくいかなかったという就活生は多くいます。
そこで活用したいのが「自己PR作成ツール」です。これを使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
基本情報を確認! 就職活動で役立つ簿記とは
簿記の資格をまだ取得していない人だと、どのような能力や知識を得られるのか何となく理解していても、就職活動で活かせる理由がわからない人もいるのではないでしょうか。
簿記の能力を身に付けておくと、就職活動だけでなく、職種によっては入社後も活躍できるのです。
ここでは、簿記の資格の基本情報を解説します。日商簿記・全経簿記・全商簿記の3つから、取得しておくべき簿記の種類も解説するため、ぜひ参考にしてください。
また、就職活動で役立つ資格を知りたい人は、下記の記事でも資格の種類を解説しているため、志望企業に合わせて必要な資格を考えましょう。
企業の決算書を作成するスキルが身に付く
簿記は、事業で使用するお金のやりとりを記録し、経営状況を表す決算書を作成するスキルが身に付く資格です。
決算書
企業が毎年決められた月に収入や支出をまとめた書類のこと
企業は、確定申告のタイミングで作成した決算書を税務署に提出しています。
簿記の資格を取得すると、企業のお金の流れを記録したり読み取ったりできるようになるため、経理や会計業務に役立つのです。
上場企業が作成した決算書は誰でも見ることができるため、簿記の資格を取得しておくと、企業の経営状況が理解できるようになります。
このように、簿記の資格は就職活動で活躍できるというアピールだけでなく、企業研究や業界分析の一環としても使用できます。
就職活動を有利に進めるなら日商簿記の取得がおすすめ
一言で簿記といっても、運営団体が3つあり、受験する試験によって知名度や難易度が変わってきます。
簿記の種類
- 日商簿記
- 全経簿記
- 全商簿記
全商簿記はおもに商業高校に在学している学生向けの試験です。また、全経簿記は経理の専門学校に通う生徒が受けることが多くなっています。就職活動で簿記の取得を考えている場合は、日本商工会議所が主催している日商簿記が知名度や人気の高さからおすすめです。
日商簿記はほかの簿記の資格と比較しても難易度は高めですが、独学でも十分に取得が可能です。
就職活動で言われる「簿記」の資格は一般的に日商簿記を指しているケースが多いため、採用担当者からの印象にも学生が取得している能力のレベルが理解しやすくなります。
就職支援でかかわった簿記取得者のうち、10人中9人以上は日商簿記の取得者でした。
全商簿記や全経簿記については、取得者はいたのかもしれませんが、学生向けの印象があるため履歴書に書かない場合もあるかもしれません。
就職活動のために今後取得するなら日商簿記が良いでしょう。
コピペで使える自己PR文がかんたんに作れます
自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?ツールで実際に文章を作成してみてからブラッシュアップする方が効率的に受かりやすい自己PRを作成することができます。
「自己PR作成ツール」 を使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
日商簿記は就職後に役立つ! 各級の難易度と可能な業務レベル

各級の難易度と可能な業務レベル
- 日商簿記3級
- 日商簿記2級
- 日商簿記1級
日商簿記は3つの級に分かれており、それぞれ身に付く知識や難易度が変わってきます。
目指す業務や活用の仕方によって必要な級が変わってくるため、就職活動で簿記を活かしたい場合は自分の志望職種と合わせて取得する資格を選びましょう。
この章では、日商簿記の各級の難易度や、可能な業務レベルを解説します。
日商簿記3級:会計業務の基礎知識が身に付く
簿記の試験は商業簿記と工業簿記という試験科目に分かれていますが、簿記3級での出題範囲は商業簿記のみとなります。そのため、勉強量がほかの級よりも少なく、はじめて勉強をした人でも100時間程度で取得が可能といわれています。
日商簿記3級の基礎知識
- 試験形式:統一試験・CBT方式
- 試験日(統一試験):2月・6月・11月
- 試験日(CBT方式):各試験会場が設定する任意の日
- 受験費用:3,300円(税込)
- 目安勉強時:約80時間〜100時間
- 合格率:30〜40%
統一試験
鉛筆や電卓を使って解答する試験方式
CBT方式
パソコンを使って解答するネット試験方式
日商簿記3級を取得していても、企業では会計業務の基礎知識を有していると見られる程度です。しかし、基礎知識があれば企業の決算書の内容を理解できるため、就職活動には役立つ可能性があります。
日商簿記2級:一般企業で経理業務が可能
日商簿記2級を取得していれば、商業簿記と工業簿記のどちらの知識も身に付くため、企業で経理業務が可能になります。経理や会計事務所に勤めることを考えている場合は、2級の取得を目指しましょう。
日商簿記2級の基礎知識
- 試験形式:統一試験・CBT方式
- 試験日(統一試験):2月・6月・11月
- 試験日(CBT方式):各試験会場が設定する任意の日
- 受験費用:5,500円(税込)
- 目安勉強時(3級取得者)約200~250時間
- 目安勉強時(初心者)約300~350時間
- 合格率(統一試験):約10〜20%
- 合格率(CBT方式):40%弱
日商簿記2級の内容は初心者からでは350時間程度必要といわれていますが、その内容は3級とも重複しています。そのため、3級を取得した後すぐに2級の勉強を始めれば、内容は理解しやすくなります。始めから2級の取得を目指す人も少なくありません。
簿記2級を取得している学生は、努力を積み上げる力や経理・会計の基礎知識を有する点が評価できます。
また、数字に対する理解力や業務の正確性も期待できます。特に経理職を目指す場合、即戦力の可能性を感じますが、他者との差別化も重要と考えます。
テンプレを活用すれば受かる自己PR文が作れます
自己PRのネタを決めても、それを裏付けるエピソードに悩む学生は多いです。しかし、特別なエピソードがなくても受かる自己PRを作ることはできます。
そこで紹介したいのが「自己PR作成ツール」です。自己PR作成ツールなら、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、分かりやすいテンプレであなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
日商簿記1級:経営管理や経営分析の知識が身に付く
1級は日商簿記のなかでもっとも難易度が高く、経営管理や経営分析の知識を身に付けることが可能です。一方で、1級を独学で取得するのは難易度が高く、500〜1,000時間程度の勉強時間が必要といわれています。
日商簿記1級の基礎知識
- 試験形式:統一試験
- 試験日:6月・11月
- 受験費用:8,800円(税込)
- 目安勉強時:2級取得者:約400~600時間
- 合格率:10%前後
今まで簿記の資格を取得したことがない人が簿記の1級を目指すなら、講座を利用することがおすすめです。さらに、就職活動と簿記の1級の取得を並行しておこなうなら、試験日を確認したうえで就職活動と被らない時期に勉強を進める必要があります。
採用経験者が解説! 就活で簿記を活かすには現実的に何級が必要?
就職活動に役立つからという理由で簿記の資格取得を目指すなら、何級を選ぶべきなのか悩む人もいるのではないでしょうか。目指す職種によっては簿記の資格の級数自体を評価されるとは限りません。
そこでこの章では、キャリアコンサルタントの板谷さんに就職活動で簿記を活かすためには現実的に何級の取得が必要なのか解説してもらいます。自分の目指す方向性と照らし合わせて、必要な能力を理解しましょう。
アドバイザーコメント
簿記を取得する目的によって目指すべき級は異なる
就職活動で簿記の資格を活かしたい場合、現実的に何級が必要なのかについて3つのパターンを見ていきましょう。
①経理・会計業務に活かしたい場合
簿記2級以上が求められることが多いでしょう。簿記1級まで取得することができていれば、経営管理や経営分析の観点があるということをアピールすることができます。
②就職活動の選考に活かしたい場合
簿記3級であっても、社会人としての基礎的な会計知識を持っている証となり、数字に強いという印象を与えることができます。
商業高校では、全商簿記と合わせて日商簿記を取得する人も一定数いて、簿記3級を取得している人は多いです。簿記2級以上を持っているとさらなる強みにつながります。
簿記は理想の企業を見極める際にも役立つ
③就職活動の企業研究で活かしたい場合
簿記3級の知識を活用し、業績や収益性を分析することができます。簿記2級を持っている場合には、決算書からコスト管理などより詳細について認識できることから、企業研究に役立てることができます。
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
目指せる仕事はさまざま! 簿記の知識が役立つおもな就職先3選
簿記の知識が役立つおもな就職先3選
- 企業の経理部
- 会計事務所
- 金融業界
簿記の資格を取得していると、企業の経理部や会計事務所などの仕事に勤めるときに役立ちます。簿記の資格を直接的に活かせる仕事を目指す場合は、より高い級を取得することで即戦力をアピールでき、採用担当者の印象に残りやすくなるのです。
ここからは、簿記の知識が役立つおもな就職先を3つ解説します。簿記が評価される就職先を理解して、就職先選びの参考にしましょう。
①企業の経理部
簿記を取得していると企業のお金のやり取りを記録でき、決算書が作成できるようになります。そのため、企業の収入や支出の管理をおこなう経理部に勤めることが可能です。
経理部はほとんどの企業に存在するため、一度勤めれば将来的にライフステージの変化で引越しや転職があっても働き続けることができます。しかし、多くの企業は経理部に新しい人材を採用する際、未経験の人よりも経験者を選ぶ傾向が高いです。
そのため、新卒で経理部への就職を目指す場合、経験者と比べて実力で大きく負けない点を伝えるために簿記の資格が役立ちます。ただし、企業の経理部を目指す場合は一般的に簿記2級程度の能力が求められます。
- 企業の経理部に入りたいと思い簿記2級を取得しましたが、ほかの学生との差別化や効果的なアピールにつながりますか?
簿記2級の取得したうえで差別化の工夫を意識しよう
簿記2級を取得していることは、経理職を目指すうえで基礎知識や努力の資質をアピールできるため有利に働きます。
ただし、簿記2級を持っている学生はほかにも多いため、差別化の工夫が重要です。
具体的には、資格取得の過程で得た課題解決能力やスケジュール管理能力を、自己PRや志望動機で具体的に伝えるのがおすすめです。
また、取得した知識を活用して企業研究や業界分析を深め、その成果を選考時に示すことで、採用担当者により強い印象を与えられます。
さらに、関連資格の取得やインターンシップでの実績を加えることで、より魅力的な候補者としてアピールできます。
②会計事務所
会計事務所
個人や法人に対して会計業務をサービスとして提供している企業
企業によっては日々の記帳や確定申告時の書類作成を自社でおこなわず、会計事務所に経理業務を委託している可能性があります。
会計事務所と企業の経理部の違いは、自社の会計業務をおこなっているかという点です。企業の経理部は自社の会計業務をおこない、会計事務所は自社だけでなく他社の会計業務も委託されています。
そのため、会計事務所に勤める場合は規模や業界の異なる企業の経理に触れることができるのです。
会計事務所に勤める場合は、一般的に簿記2級から1級の能力が求められます。経理と同じく3級しか取得していない場合は採用担当者の印象に残りにくくなります。
③金融業界
金融業界には銀行や証券会社などが所属していて、自社だけでなく他社の財務状況を確認するために決算書に目を通すことがあります。そのため、金融業界を目指す場合は簿記の資格を取得していると、業務内容が理解しやすく、活躍できる可能性が高まるのです。
金融業界で働く場合、直接的な業務で2級以上の能力が求められるわけではありません。簿記の資格自体を持たずに働いている人もいるため、営業職や窓口業務などを志す場合、では3級でも金融関係の知識をアピールすることは可能です。
しかし、金融業界で働く場合はキャリアアップの条件に簿記2級の取得を求めるケースもあるため、学生のうちに取得しておくと、就職に役立つだけでなく将来的な昇進につながる可能性があります。
金融業界を目指す場合は、資格取得以外にもトレンドの理解に力を入れましょう。下記の記事では金融業界のトレンドや選考対策を解説しているため、ぜひ参考にしてください。
簿記の資格は幅広い業界で活用できます。製造業では、原価計算や生産コスト、利益の管理に活かすことができます。
小売業や流通業では、売上や在庫の管理、店舗ごとの収益分析に役立てることができます。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
職業選択においてやりたいことはもちろんですが、その中でも適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうため適職への理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業と低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみよう!
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
能力のアピール以外にも! 簿記を活かして就職するメリット5選
簿記を活かして就職するメリット5選
就職活動で簿記を取得しておくと、企業研究に役立ったり、未経験で経理の業務を目指せるなどのメリットがあります。就職の選択肢が広がるため、自分の希望する業界への就職も近付くのです。
ここでは、簿記を活かして就職するメリットを5つ解説します。自分が魅力を感じるメリットがあるか確認して、取得を目指すか考えましょう。
①企業の経営状況がわかり業界・企業分析に役立つ
簿記の資格を取得すると、企業が公開している決算書を見て経営状況が理解できるようになり、業界分析や企業分析に役立ちます。
なるべく安定して働ける企業に就職したいと思う場合、赤字を出している会社に応募することは避けたい人も多いです。そのとき、企業が公開している決算書を読み解いてから応募するか検討すれば、安定していない会社に入社する可能性は減らせます。
志望企業だけでなく取引先企業の情報まで確認し、業界全体の動向を理解したり、どのような企業と取引しているのかまで理解することもできます。
また、企業が所属している業界を分析したい場合は、売上率や原価率、利益率などに着目することで、事業の課題や将来性も理解できるようになるのです。
簿記の資格を取得することで税務会計の知識が身に付きますが、企業分析に活かす場合はそれに加えて管理会計という視点で収益性や成長性、安全性などを見ていくのがおすすめです。
簿記の学習を通して経費や利益について理解できている人は、そういった数字を見ることで企業分析に活かしやすくなります。
企業研究は正しい手順でやらないと効果がでないため、こちらの記事を参考に比較するべき項目や手順を明確にしましょう。
②未経験から経理関連の仕事を目指せる
簿記の資格を取得しておけば、経験者が有利になりやすい経理関係の仕事も、未経験から目指せます。もともと企業の経理部の人数は採用人数が多くないこともあり、新卒では狭き門になりがちです。
そのため、新卒で企業の経理部を希望して就職活動をしても、ほかの部署を勧められた経験がある人もいるのではないでしょうか。
しかし、簿記の資格を取得していれば、会計業務の基本を理解できていると理解してもらえ、採用担当者の目に留まる可能性が高まります。ただし、未経験から経理関係の仕事を目指す場合は、2級以上を取得しておかないと難しくなるため注意しましょう。
新卒で経理の仕事を目指す場合は、戦略的に就職活動を進めましょう。こちらの記事では新卒で経理を目指す方法を解説しているため、併せてチェックしてください。
③経理部門はほとんどの企業にあるため就職先の幅が広がる
企業はかならず収入や支出の記録や管理が必要になるため、多くの企業では自社で経理部門を持っています。そのため、簿記の資格を取得しておくと就職先の幅が広がり、就職活動が有利に進む可能性が高まるのです。
たとえば、今後の成長性を期待してIT業界に身を置きたいと思っていても、IT関係のスキルがないと難しいと思う人もいるかもしれません。しかし、簿記の資格をアピールできればIT業界の経理部も視野に入り、安定したキャリアの構築につながる可能性があるのです。
ただし、中小企業やベンチャー企業など小規模だと、予算の都合で自社に経理部を設置せず、会計事務所に業務を委託している可能性もあります。
自分が目指す企業が中小企業やベンチャー企業の場合は、経理部門を設置しているのかを確認しておきましょう。
大企業や中小企業、ベンチャー企業の定義がそもそもわからない場合は、特徴を理解しておくことで自分に合った企業を選びやすくなります。こちらの記事解説しているため、ぜひ参考にしてください。
大企業と中小企業の違い
大企業と中小企業の違いを5つの観点で比較! 特化した対策も解説
④転職活動でも評価されやすくなる
新卒の段階で簿記の資格を取得しておくことで、将来的に経理の仕事に転職したいと思った場合に役立ちます。経理の仕事は経験者が優遇される場合も多いため、新卒で目指しても、必ず採用されるとは限りません。
簿記の資格は一度取得すれば有効期限がないため、一度ほかの仕事に就いてから経理の仕事に転職する場合でも志望先で評価される可能性が高まります。
特に、簿記2級の資格は勉強時間が3級よりも増え、企業に勤めてからだと時間の捻出が難しい場合もあります。
そのため、学生のうちに取得しておけると、一度企業に入社した後に企業の経理部や会計事務所で働きたいと思ったとき、別の職種からでも転職しやすくなるのです。
また、簿記2級は企業の経理部や会計事務所以外でもコンサルティングや営業職を目指す場合にも役立ちます。幅広い選択肢から自分に合った仕事を見つけやすくなり、理想のキャリアプランを考えられるようになります。
学生時代に簿記の資格を取得しておくと、転職時には経理や会計、財務関連の仕事を目指しやすくなります。
また、金融業界やコンサルティング業務にも活かせるため、キャリアの選択肢が広がり、安定した職種への転職がしやすくなります。
⑤キャリアアップにつながる上位資格取得の土台になる
将来的にキャリアアップを考えるなら、簿記の資格を取得しておくことで、税理士や公認会計士を目指せる確率が高まります。どちらの仕事も基礎は簿記の資格と似通っているため、税理士試験や公認会計士試験の勉強に活かしやすいのです。
税理士や公認会計士の資格を取得した場合、必ずしもその仕事をしなければいけないわけではありません。しかし、資格を取得しておくことで自分の能力を採用担当者にアピールしやすくなります。
企業に勤めて一から税理士や公認会計士を目指すとなると、勉強時間の確保が難しく、負担も多くなる可能性があります。だからこそ、在学中に簿記の資格を取得しておいて基礎の知識を固めると、上位資格を目指したいと思ったとき、行動に移しやすくなるのです。
不安を解消しよう! 簿記が就職で「役に立たない」と言われる理由
簿記が就職で「役に立たない」と言われる理由
簿記の資格について調べていると、「役に立たない」という情報を目にして、不安に思う人もいるのではないでしょうか。
しかし、簿記の資格が役に立たないという意見は根拠が乏しいケースが多いため、真に受けてしまうとせっかくのスキルアップのチャンスを逃してしまう恐れがあります。
そこで以下では、簿記が就職で「役に立たない」と言われる理由を解説します。資格を取得する前に疑問を解決して、勉強に集中できる環境を作りましょう。
直接活きる仕事が経理や会計事務所など限定的なため
簿記の資格が直接活かせるのは、企業の経理部や会計事務所などがメインです。金融業界でも活かせる面はありますが、企業の決算書の内容が理解できるといった部分であり、簿記で学んだ作業を実際におこなうわけではありません。
そのため、簿記の資格を直接的に評価する業界は少ないと考えられ、就職で役に立たないと言われてしまうのです。
しかし、簿記の資格は取得しているだけで数字への強さや資格取得に向けて努力できる人材であるとアピールでき、採用担当者の印象に残る可能性があります。
そのため、希望する業界や職種が簿記が直接活かせる分野でなくてもアピール方法を工夫することで、十分に就活に役立ちます。
- 何となく簿記を取得しましたが、アピール方法がわかりません。どの業界でもアピールしやすい簿記の魅力や強みを教えてください。
簿記を通して論理的思考力や経営視点が培われる
簿記は非常に汎用性の高い資格です。簿記を取得することで、基本的な会計知識が必要な場面でもスムーズに対応することができます。
また、仕訳や帳簿の整合性を踏まえた論理的思考力を高めることもできます。
決算書の財務諸表を読み解く力は、企業の強みや課題を把握することにつながり、経営視点を持てるという点をアピールできるようになるのです。
さらに、コスト計算や利益率を加味した企画を立案することや、顧客の財務分析を踏まえて最適な提案を営業することができるなど、さまざまな分野で簿記の知識をアピールすることができます。
資格保有者が多く差別化が難しいため
簿記の資格は合格点を超えれば全員が合格できる絶対評価のため、勉強すれば取得できる確率の高い仕事です。また、簿記の資格の活かし方がわからないものの、取得のしやすさや学校の指示でとりあえず受験している人もいて、資格の取得者が多くいます。
そのため、ただ履歴書に簿記の資格を持っているという点を記載するだけでは、ほかの学生と印象が変わらず、採用担当者の心に残りにくくなるのです。
簿記の資格を直接役立つ仕事以外の就職活動で活かすには、志望動機や自己PRのエピソードを利用して資格勉強によって得たものや強みをアピールすることがおすすめです。
自分ならではのエピソードが考えられれば、採用担当者の目に留まり選考に役立つ可能性があります。
簿記を活かした志望動機を作成するためには、まずは書き方を理解しましょう。こちらの記事では志望動機を作成する方法を解説しているため、ぜひ参考にしてください。
資格よりも実務経験が重視されやすいため
経理の仕事を目指す場合、「ただ簿記の資格を持っている」という人材よりも実務経験がある人が採用されやすい傾向があります。それは、簿記の資格を有しているだけでは実務に役立つ能力やスキルを持っていることを十分に示せるとは限らないからです。
そのため、経理の業務を目指して簿記の資格を取得したとしても、必ずしも希望の職種に就けるとは限りません。新卒で経理の仕事に就くためには、経験者を採用するのとは違ったメリットや自身の魅力を採用担当者へ伝える必要があるのです。
ただ、簿記の資格は経理にならなければ無駄になるというわけではありません。新卒で希望する仕事に就けなくても、将来的に税理士や公認会計士を目指したとき、基礎となる可能性があります。
企業によっては経理を外注しているため
ほとんどの企業に経理部門があるとはいっても、自社に経理の人員を採用するコストがない中小企業やベンチャー企業の場合、会計事務所へ業務を委託している可能性があります。
そうなると、希望する企業があっても、経理部門がなければ別の職種を選ぶ必要が出てくるのです。
そのため「就職活動を目的に簿記を取得しても、就職に役立てられず勉強する時間がもったいない」という意見もあります。
しかし、中小企業やベンチャー企業であっても、すべての業務を委託しているとは限りません。さらに、簿記の資格は直接的に活かす以外にも取得までの努力やスケジュール管理などアピールできるポイントが多く、就職活動に役立つ可能性が高いです。
経理の仕事は将来なくなる可能性があるため
AI(人工知能)の普及によって、経理の仕事は将来的になくなることが危惧されています。苦労して簿記の資格を取得しても、仕事がなければ活かす場所がなく、無駄になってしまうと考えている人もいるのです。
そのきっかけは、オックスフォード大学が2013年に報告した情報通信白書によると、「10~20年内に労働人口の47%が機械に代替可能である」という予測を発表したことです。
さらに、野村総合研究所が「2030年頃までに日本の労働人口の49%がAIやロボットなどに代替可能」という試算を発表し、そのなかに経理が含まれています。
しかし、万が一AIによって経理の仕事がなくなっても、あらかじめ簿記の知識をもとに上位資格を取得して公認会計士や税理士などを目指すことで、将来的にキャリアを高めやすくなります。
- 実際経理の仕事はすぐなくなる可能性はあるのでしょうか? 簿記の資格を取得することが無駄にならないか不安です。
簿記の知識は長期的なキャリアに活かせる
将来的に経理の仕事がAI(人工知能)や自動化で代替される可能性はありますが、すべての業務がすぐに消えるわけではありません。
現在、自動化が進むのは、データ入力や仕訳作業など反復的な業務が中心です。
一方で、財務分析や予算計画、経営戦略に関わるような付加価値の高い業務は、まだ人間の判断や経験が必要とされます。
簿記の資格は、これらの基礎となる知識を提供するため、直接的な経理業務以外でも役立ちます。
たとえば、企業研究や財務分析に活用したり、税理士や公認会計士といった関連する上位資格を目指す基盤とすることも可能です。
経理業務の変化に対応し、自身のスキルを磨き続けることで、資格を無駄にせず将来性を高めるキャリアを築くことができます。
近年はAIの普及によって、さまざまな職業がなくなる可能性が示唆されています。こちらの記事ではAIでなくなる可能性がある仕事を解説しているため、不安な場合は併せて目を通しておきましょう。
持っているだけではダメ! 就職活動で簿記をアピールする方法
簿記の資格はただ履歴書に記載するのではなく、アピール方法に工夫することで採用担当者の印象に残る確率が高まります。アピール方法を工夫すれば、簿記の仕事が直接役立つ仕事でなくても、採用担当者に評価される場合があるのです。
この章では、就職活動で簿記をアピールする方法を解説します。簿記の資格を就職活動で十分に活かす方法を理解して、選考突破に役立てましょう。
取得した理由を明確に伝える
簿記の資格を取得する理由は、「経理の仕事をしたい」「金融業界で役立つと思った」など抽象的であることが多いです。
そのため、採用担当者に漠然と取得したと思われないよう、「金融の仕事に就きたいと思い簿記を取得した」「将来的に税理士の資格を取得したいと思っている」といった形で、取得した理由を明確に伝えましょう。
もちろん、履歴書の資格欄だけでは資格の取得理由まで伝えることはできません。しかし、志望動機や自己PRに資格取得のエピソードを記載することで、併せて簿記の資格を取得した理由を添えられるのです。
仮に簿記の知識が直接役立つ仕事でなくても、資格を取得したこと自体が、努力できる人材であることをアピールするための材料となります。資格取得までの努力を無駄にしないためにも、簿記を活かせる強みやエピソードを考えましょう。
- 特に理由もなく、「お金関係の資格が欲しい」という理由だけで簿記を取得してしまいました。そんな理由でも、採用担当者に伝えて良いのでしょうか。
簿記の資格取得によるプラスの変化を考えよう
もちろん事実を伝えることはまったく問題ありませんし、特に強い動機がなくても資格取得ができているので、ネガティブな印象にはならないでしょう。
大切なのは、資格取得した後のことです。たとえば現在、簿記の学習をしたことで何か前向きな変化があったのかどうかという視点は採用担当者が気になるところです。
「数字に敏感になった」「家計管理が改善できた」など良い影響があるのであれば、きっかけは「お金関係の資格が欲しい」という表面的なものであっても、今の自分に役立っていて知識を活用しているというアピールにつなげることができます。
一方で、「軽い気持ちで資格は取ったけれど何も変わっていない」という状況であれば、簿記の資格を取得したことには触れないほうが無難です。
資格はあれば良いというものではなく、活用できていなければ意味がないからです。
簿記だけでなく関連する資格も取得しておく
簿記の資格を取得する際は、関連する資格も取得しておくことで、企業への志望度の高さや業界への理解度を伝えやすくなります。
たとえば、金融業界を目指す場合は顧客へ資産運用の提案をおこなうにあたり、ファイナンシャル・プランナーの資格が役立ちます。
ほかにも、経理の仕事を目指す人であれば、財務諸表の理解力を養う目的としてビジネス会計検定や、電子会計データの取り扱い方法への理解が深まる電子会計実務検定などの資格もおすすめです。
このように志望職種によって必要な資格は異なるため、希望する業界や職種に必要な資格を調べて簿記と併せて取得しておきましょう。
そうすることで、採用担当者が履歴書に目を通したとき学生が将来的にどのような業務に就きたいのかわかりやすくなり、自社とのマッチ度を見極めやすくなります。
就活のプロが解説! 簿記の資格を武器に差別化するコツ
簿記の資格は就職活動に役立ちますが、ただ履歴書に記載するだけでは、採用担当者の記憶に残らない可能性があります。簿記の資格を武器にするためにも、ほかの学生と差別化するコツを理解しておきましょう。
この章ではキャリアコンサルタントの野村さんに、簿記の資格を武器に就職活動でほかの学生と自分を差別化するコツを解説してもらいます。簿記の資格の活かし方を理解して、就職活動を有利に進めましょう。
アドバイザーコメント
簿記の資格取得に関連するエピソードが差別化のコツ
簿記の資格を持つ学生が多いなかで差別化を図るには、資格取得の過程や活用法について具体的な内容や苦労したことをエピソードを交えて伝えることが重要です。
たとえば、試験勉強を通じて培った自己管理能力や目標達成の努力を、具体的な体験を交えて示すことで、採用担当者にポジティブな印象を残せます。
また、資格を活かして企業研究や財務分析をおこない、その成果を自己PRや志望動機で入社後に取り組みたい内容も含めて説明するのも効果的です。
簿記の資格取得の先にあるステップアップの視点も重要
さらに、関連資格の取得やインターンでのエピソードや実績を加えると、スキルの幅や広さをアピールすることもできます。
特に、ファイナンシャル・プランナーやビジネス会計検定を取得すれば、金融分野やコンサルティング分野への応用力も示せます。
加えて、自分ならではの視点を資格と結びつけることで、ほかの候補者との差別化が可能です。
文系的な視点や異なるバックグラウンドを活かした提案力を具体的に伝えると、企業にとっての魅力を高められます。資格を起点に自分の価値を示すことが、就活を成功させる鍵です。
就職活動に間に合わせよう! 今から簿記を取得する3ステップ
今から簿記を取得する3ステップ
- 取得したい簿記の級数を決める
- 勉強のスケジュールを考える
- ネット試験を利用し資格を取得する
まだ簿記の資格を取得していない人は、選考までに合格するためにも、スケジュールを立てて進めていく必要があります。簿記の資格は2級と3級の合格率が30%前後と、決して低いわけではないものの、計画的に進めなければ合格できない可能性があるのです。
この章では、就職活動に役立てるために、簿記を今から取得したい人向けの方法を3つのステップに分けて解説します。どのような手順で資格取得を進めるのかを理解して、行動に移しましょう。
ステップ①取得したい簿記の級数を決める
簿記の資格の取得を目指す場合は、まず勉強のスケジュールを立てるために取得したい級を選びましょう。簿記の資格で一番取得しやすいのは3級ですが、持っている人も多いため、採用担当者の印象には残りにくくなります。
そのため、就職活動で活かしたいという気持ちがあれば2級からの受験も方法の一つです。ただ、簿記の3級を取得すれば会計業務の基礎知識は身に付くため、まずは3級を取得して、その後に2級を目指す形でも問題ありません。
なお、簿記の1級は未経験が取得を目指すにはかなりの時間がかかるうえ、独学での取得は難易度が高めです。取得したい理由が明確でない限りは、3級や2級を目指すことをおすすめします。
ステップ②勉強のスケジュールを考える
勉強のスケジュールを考えるときは、資格したい級の試験がいつあるのかをもとに考えましょう。また、簿記の試験にはインターネットを利用して受験するCBT方式と実際に筆記で回答する統一試験があり、どちらを選ぶかによって試験日が異なります。
今まで簿記の勉強をしたことがない人が、3級を目指す場合に必要な勉強時間は100時間弱です。また、2級を目指す場合は350時間ほどといわれています。一日に勉強できる時間が2時間であればおよそ6カ月程度の勉強時間を確保しましょう。
なお、勉強のスケジュールを考えるときは少し余裕を持って組んでおくと、進捗に遅れがでても試験に間に合います。試験の日程をずらすのはモチベーションに影響が出る可能性があるため、始めから余裕を持っておきましょう。
- 統一試験かCBT方式の受験で悩んでいます。それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
統一試験とCBT方式は人によって向き不向きがある
ネット上で受験できるCBT方式は受験の頻度が高いので予定を合わせやすいです。
また、体調不良やその他のトラブルなどで受験できなくなった場合でも容易に受け直せることや、結果がわかるのも早いという利便性があることなどが大きなメリットです。
統一試験のCBT方式の難易度は同じといわれていますが、導入当初の2020年と2021年は、CBT方式の方が合格率が高かったということがありました。
原因は諸説ありますが、回答方式が記述式ではないことが影響しているともいわれており、記述式の問題に苦手意識がある人にはCBT方式が良いかもしれません。
一方で、CBT方式のデメリットはPC操作やID管理などの手間がやや増えることと、問題用紙にメモできないことなどです。
統一試験では、これらのメリット、デメリットがCBT方式の逆になると考えてください。
ステップ③ネット試験を利用し資格を取得する
なるべく早めに簿記の資格を取得したい場合は、実施している回数が多いネット試験がおすすめです。ネット試験であれば基本的にほぼ毎月試験を実施しているため、自分のスケジュールに合わせて予定が立てられます。
また、ネット試験を利用するときは全国約140カ所の会場から行きやすい場所を選べます。商工会議所の公式ホームページから、行きやすい会場を選びましょう。
なお、ネット試験は実施している日数が多いものの、筆記で受ける統一試験の前後は施行休止期間が設けられています。そのタイミングに受験したい場合は受けやすい日程を選べない可能性があるため、スケジュールを立てるときは注意しましょう。
向いている方法を見つけよう! 簿記を取得するための勉強方法
簿記は独学で取得できるといっても、目指す級数やスケジュールによっては、通信講座を利用するほうが適している可能性があります。自分の状況や勉強方法によって向き不向きは異なるため、それぞれのメリットやデメリットを理解して選びましょう。
ここからは、簿記を取得するための勉強法を解説します。自分に合った方法を見つけて、資格取得を目指しましょう。
独学:費用が少なく済む
簿記は2級や3級であれば、独学での取得も十分に可能です。それぞれ1,700円程度のテキストや問題集を買うだけで済むため、なるべく少ない費用で資格を取得したい人に向いています。
独学で簿記の取得を目指す場合、自分で一からスケジュールを考えたり、モチベーションを保ったりする必要があります。教えてくれる人がいない分、疑問点があれば質問ができず、自分で調べる必要が出てくるのです。
また、取得したい簿記の級が1級の場合は独学では時間がかかりすぎる可能性があります。就職活動が本格化するまでに勉強時間が確保できるかを考え、計画的に進めなければいけません。
一方で、3級や2級であれば初心者が独学で勉強する場合でも100〜350時間ほどで取得を目指せます
通信講座:疑問点の解消が可能
通信講座を利用すれば、サービスによって試験までの期間に合わせてスケジュールを立ててくれたり、疑問点を質問できる機能があったりして、手厚いサポートを受けられます。ほかにも、スマホを使用して隙間時間に動画を視聴して勉強できるサービスもあります。
しかし、通信講座を利用する場合、多くのサービスでサポート期間が1年程度と決まっているため勉強の期間には注意しましょう。その期間を過ぎると、仮に簿記の資格を取得できていなかったとしてもサポートを受けることはできなくなります。
たとえば、スタディングの簿記講座では、2級と3級をセットで受講すると21,800(税込)で翌年の3月末日までサポートを受けられます。期間を過ぎた場合はそれ以上サービスを受けられません。
ただ、簿記の1級の取得を考えている場合は独学でかかる1,000時間ほどの勉強時間が、通信講座であれば600時間程度に減らせる可能性があります。そのため、なるべく早く1級を取得したい人は、通信講座の利用がおすすめです。
一方で、3級では通信講座を利用しても勉強時間は100時間ほどかかるため、時間の短縮はあまり見込めません。また、2級であれば独学で350時間ほどの勉強時間が250時間程度になることが期待できるため、なるべく早く取得したい場合には向いています。
自分でスケジュールを立て、疑問点に関しても自力で調べながら取り組むことができる人であれば、独学が向いているといえます。
一方で、学習習慣が身に付いておらずモチベーションを保ち続けることが難しい人や、体系的かつ効率的に学びたい人は、通信講座が向いているといえます。
簿記などの資格を就職活動に役立てる際に知っておきたいQ&A
簿記の資格が就職活動に役立つと理解できても、役に立たないという意見が気になって取得を悩む人もいるのではないでしょうか。今から簿記の資格を取得するか悩むなら、自分がどのように活かしたいかを明確にしておきましょう。
そこでこの章では、PORTキャリアに寄せられたQ&Aから、簿記の資格が就職活動で役立つのか悩む人におすすめの内容を4つ紹介します。キャリアコンサルタントのアドバイスを参考にして、取得するべきか判断しましょう。
簿記を就職活動で活かすならまずは2級の取得を目指そう
簿記の資格を就職活動で活かすなら、最終的に2級が取得できるように勉強をしましょう。簿記の2級を取得しておけば、3級を持っている人より差別化でき、企業の経理部や会計関係の仕事に就ける可能性が高まります。
勉強自体は3級からでも問題はないものの、2級まで取得しておくことで採用担当者の目に留まりやすくなる可能性があります。
仮に経理・会計関係の仕事に就かないとしても、簿記の資格を取得するまでにした努力やスケジュール管理能力は、就職活動でも役立つ場面はあります。「役に立たない」と決めつけず、簿記がどのように役立つかを理解して、資格取得を目指しましょう。
アドバイザーコメント
簿記の資格を就職に活かすにはスキルアップの視点が重要
簿記に限った話ではありませんが、よほど専門的な資格でないと、保有しているだけで評価されることはまずありません。
企業が重視しているのは資格の価値ではなく、あなたの価値なのです。資格は、あなたが保有する能力のほんの一部を証明するだけのものであることを、まず再認識してください。
「資格が役に立たない」と主張する人は、大きく2つに分けられます。一つは、資格に関係なく能力が発揮できている人です。そしてもう一つは、資格の価値に期待をかけすぎている人のように感じます。
後者は、資格を持っているだけで評価が高まると勘違いしている傾向があるのですが、資格取得はあなたのスキルを高めるための一つの手段にすぎません。スキルアップという目的と、資格取得という手段とを混同しないようにしましょう。
簿記の資格は汎用性の高いビジネススキルを示す手段の一つ
簿記の資格は、経費や係数の感覚を養うためにとても有効なものです。資格自体が直接目先の仕事に関係していなくても、ビジネスマンとして持っておいて損はない知識です。
自分自身の熟達や成長という観点で簿記の資格をとらえ、幅広い場面で活かしてもらえればと思います。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

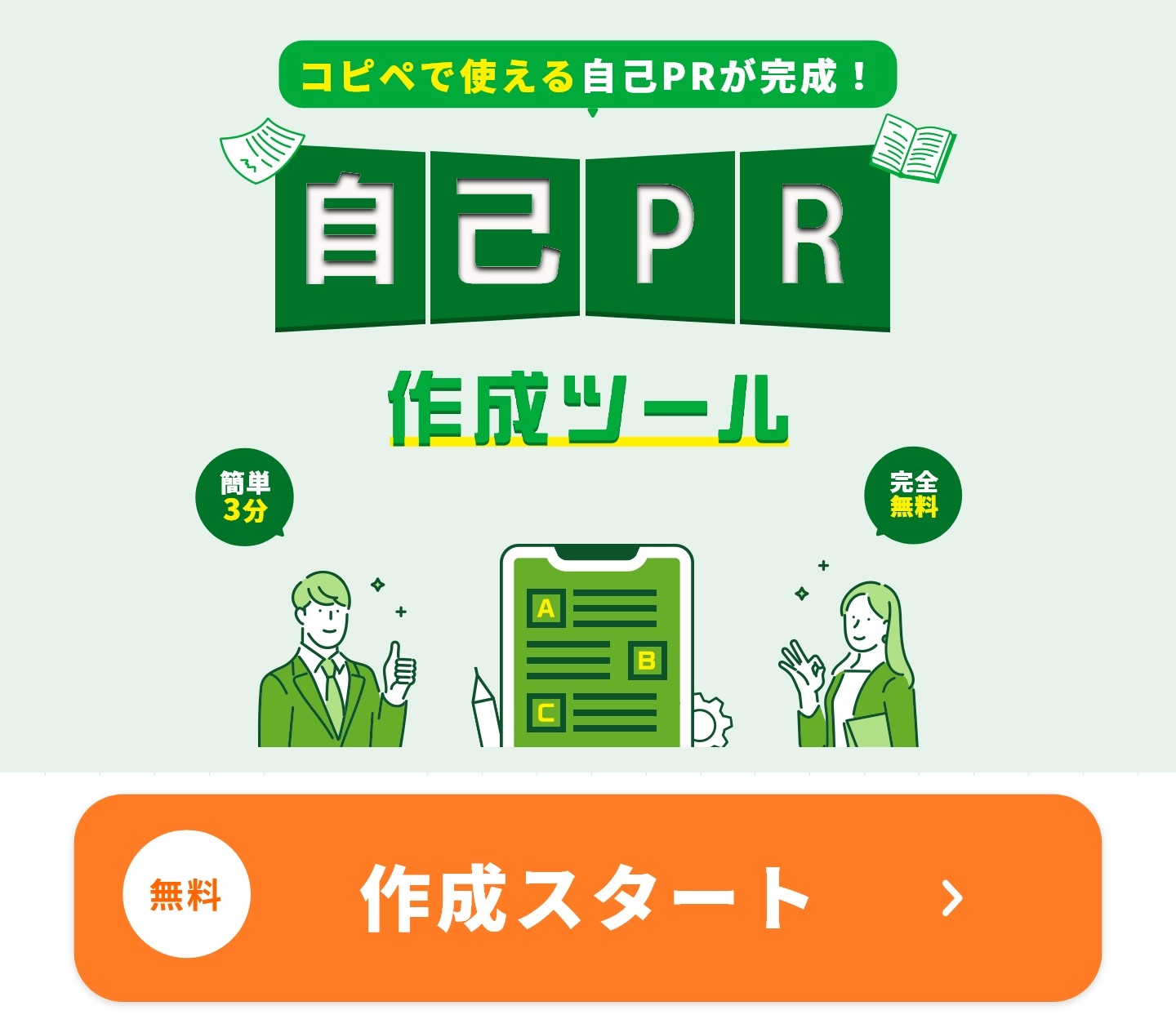
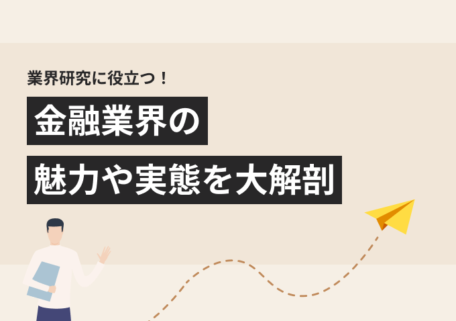




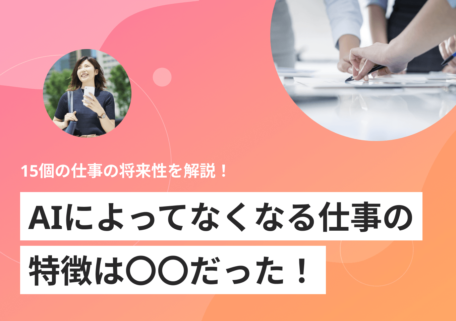















3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表
Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/コラボレーター代表
Yukari Itaya〇未就学児から大学生、キャリア層まで多様な世代のキャリアを支援。大企業からベンチャー、起業・副業など、幅広いキャリアに対応。ユニークな生き方も提案するパーソナルコーチとして活躍
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/合同会社渡部俊和事務所代表
Toshikazu Watanabe〇会社員時代は人事部。独立後は大学で就職支援を実施する他、企業アドバイザーも経験。採用・媒体・応募者の全ての立場で就職に携わり、3万人以上のコンサルティングの実績
プロフィール詳細