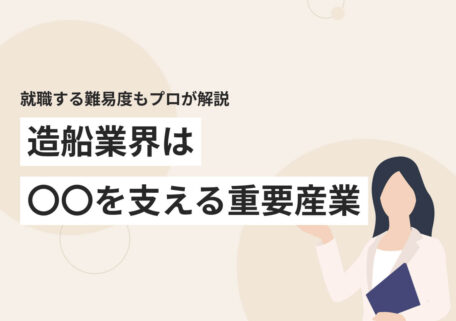Q
その他
回答しない
就活の企業研究はどこまでやるべきですか?
就職活動で企業研究が大事だとよく聞くのですが、具体的にどこまで調べれば良いのかわからず困っています。
企業のホームページ(HP)や就職サイトを見ても、事業内容や企業理念、福利厚生など、見るべき項目がたくさんありすぎて、一つの企業にどれくらいの時間をかければ良いのか、また、どの情報を深く掘り下げるべきなのかがわかりません。
周りの友人は「〇〇社のIR情報まで見た」とか「競合他社と比較して強みを分析した」とか言っていて、自分だけ出遅れている感じがします。
就活対策の企業研究は具体的にどこまでやっておけば良いのでしょうか? 最低限これだけは押さえておくべきというポイントや、効率的な企業研究の進め方についてもアドバイスをお願いします。
※質問は、エントリーフォームからの内容、または弊社が就活相談を実施する過程の中で寄せられた内容を公開しています
どこまでやるかは自分次第! 興味を持った点を深掘りしていこう
企業研究に限らず、物事の準備において言えるのは、「ここまでやれば大丈夫」というラインは自分で決めるのが大切です。
企業のHPや就職サイトには、多くの人たちに知ってほしい情報がたくさん掲載されています。そのため、事業内容や経営理念、IR情報、福利厚生などの豊富な情報を、すべて頭に入れるのは難しいでしょう。
HPなどを見ていると、途中で「特にこの情報はもっと知りたい」というものが出てくる可能性があります。たとえば、「事業内容で新規事業とあるがどのようなものか?」あるいは、「経営理念に”すべての人を笑顔にする”とあるが、誰の笑顔を特に求めているのか」などです。
情報に接したときに深く読み込んでいくのも大事で、逆質問のネタにもなります。HPや就職サイトであれば、まずは全体の情報に目を通してから、特に興味深いところを深く読み込んでいく進め方がおすすめです。
周りと合わせる必要はない! どこに時間をかけるかは自分で決めよう
また、周りの友人がやっていることを真似しても良いと思います。とはいえ、あまり周りの友人に左右されないように自分軸を持って就活を進めていくことも大切です。
すべての企業の研究に時間をかける必要はありません。特に気になった企業や志望度の高い業界などは、メリハリをつけて調べていくのも効率的に進める手段だと思ってください。
企業研究は5つのポイントを押さえよう! +αの研究も大切
企業研究をどこまで深めるべきか、悩ましいですよね。最低限押さえておくべきラインとしては、事業ポートフォリオや主要な財務三指標、競合比較、自社ならではの提供価値、そして最新のニュースなどが挙げられます。
さらに一歩踏み込むなら、IRで確認できる中期経営計画のKPIや新規投資分野、直近で取得した特許、活躍している社員のキャリア事例まで調べておくと、より深い理解につなげられるでしょう。
ツールをうまく活用して企業研究を効率的に進めていこう!
時間の配分は、一次面接までであれば1社につき約2時間、本選考前であれば1社につき約4時間が目安です。
効率化のためには、「Googleアラート」で企業名を登録したり、金融庁の「EDINET」で決算短信をチェックしたりするなどのツール活用をしていきましょう。
面接でほかの学生と差がつくのは、「その企業の弱みを踏まえたうえでの改善提案」です。「現状、御社の利益率は同業他社と比較してマイナス2ptですが、私は〇〇の経験を活かして、この点を改善できると考えます」というように、具体的な提案ができるレベルを目指しましょう。
「具体的な企業分析の方法がわからない」と疑問を持つ人は以下の記事を参考にしてください。企業分析の具体的な方法や実施する際の注意点などを解説しています。
企業研究を就活で活かすためのポイントはこちらのQ&Aで解説しているので、あわせて確認してみてください。
あなたが受けないほうがいい職業をチェックしよう
就活では、自分が適性のある職業を選ぶことが大切です。向いていない職業に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまいます。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析して、ぴったりの職業を診断できます。
適職診断で強み・弱みを理解し、自分がどんな職業に適性があるのか知りましょう。
簡単な質問に答えて、あなたの強み弱みを分析しよう。
今すぐ診断スタート(無料)
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人