この記事のまとめ
- 心理カウンセラーに向いている人の特徴6つを把握しよう
- 活躍する人の特徴を現役のプロが解説
- 心理カウンセラーとして求められる4つのスキルを紹介
既卒や第二新卒者が転職するにあたって、「心理カウンセラーはどんな人が向いているのだろう」と疑問に思う人は多いのではないでしょうか。
心理カウンセラーに向いている人を一言で表すと「客観的な視点を持って仕事ができる人」です。医療福祉分野に関してよく知らないまま飛び込んでしまうと、「想像していた仕事と違った」と後悔する可能性があります。
そうならないためにも、心理カウンセラーに向いている人の特徴や仕事内容を詳しく理解しておきましょう。
この記事では、キャリアアドバイザーの吉野さん、古田さん、永田さんとともに、心理カウンセラーに向いている人の特徴を解説したうえで、向いていない人の特徴まで解説します。さらに、仕事の内容や心理カウンセラーの特徴まで解説しているため、最後まで読んで業界について理解を深めて、自分に合った仕事か判断しましょう。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
心理カウンセラーに向いているのは「客観的な視点」を保てる人
心理カウンセラーに向いている人は、客観的な視点を持って顧客と適切な距離感を持って接する力がある人が求められます。相手の心に寄り添う仕事ですが、一定の距離感を保ちながら、顧客が心地良い時間を過ごせるように配慮する必要があります。
この記事では、心理カウンセラーに向いている人の特徴を6つ紹介します。次に、向いていない人の特徴まで紹介するため、自分に当てはまる点がないか確認してください。
また、心理カウンセラーならではの魅力や仕事内容に関しても解説しているため、自分がどのような働き方をしたいのか考えながら読み進めてください。
最後に、おすすめの資格を紹介するため、自分の目指したい心理カウンセラーに必要な資格を見つけて、就活に向けて準備を進めて行ってください。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認してみよう
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
いくつ当てはまる? 心理カウンセラーに向いている人の6つの特徴
いくつ当てはまる? 心理カウンセラーに向いている人の6つの特徴
まずは心理カウンセラーに向いている人の特徴を把握していきましょう。向いている人にとっては、顧客の身近な存在として支えられるため、やりがいを感じられます。
ここで解説する向いている人の特徴から、自分がいくつ当てはまるのかチェックをしながら読み進めて行ってください。
特徴①一定の距離を守れる対話力がある人
プロのカウンセラーとして、顧客と一定の距離感を保ちながら接することが大切です。顧客のなかには、怒りや憎しみ、悲しみといったさまざまな感情を抱えた人もいます。
そのような顧客の相談を受けた場合でも、感情移入せずに、専門家としての客観的な視点を維持しながら寄り添うことが重要です。
顧客にとって心地の良い空間づくりがおこなえるように、一定の距離感を保ちながら接する能力が求められます。
カウンセラーが自分の感情に振り回されないためには「自分と相手は違う人間なんだ」と、自他の境界をしっかり持つことが必要です。この点が家族や友人が親身に相談に乗るのと、専門職として対応することの違いです。
特徴②相手の話を根気強く聞く傾聴力がある人
カウンセリングをおこなうなかで、相手のありのままの存在を受け入れながら、話を聞くことで解決の方法を導き出していきます。
顧客の中には、うまく言葉で言い表せられなかったり、話が脱線したりすることがあります。また、話したい内容が多すぎて、伝えるのに多くの時間を要する場合もあるでしょう。そのようななかで、相手の言葉を遮ることなく、根気強く耳を傾けることが大切です。
相手の話を聴きながらでも、声のトーンやあいづちのタイミング、顔の表情まで気を配ることで、顧客とカウンセラーとしての信頼関係が構築できるでしょう。
私は初回が一番根気が必要だと感じています。クライエントは頭の整理ができていないまま話し始めることが多く、多くの情報を伝えようと一生懸命に話そうとしてくれます。そのため、こちらも話を整理しながら聞く根気が必要になります。
面接で傾聴力をアピールしたい人は以下の記事がおすすめです。傾聴力をアピールするコツや注意点を解説しています。
特徴③論理的思考で課題解決ができる人
心理カウンセラーは、顧客の感情に寄り添いながらも、専門家として客観的な視点で問題解決の糸口を見つけていく必要があります。
多くの顧客は、複雑な感情を抱えており、自分の気持ちが整理できていないまま感情的な言葉で悩みを相談します。そのため、カウンセラーには、顧客の言葉の背景にある本質をとらえ、それを明確な言葉で整理して伝える能力が必要です。
心理カウンセラー自身が、自分の感情や感覚で話を進めてしまうと、具体的な解決策が見つからずにカウンセリングの効果を発揮できなくなります。
顧客の悩みを解決するためにも、論理的な思考で物事を判断し、悩みや解決策を言語化しながら伝えていく能力が求められるでしょう。
特徴④顧客の守秘義務を守れる人
心理カウンセラーとして、顧客のプライバシーを守るためにも、個人情報などを外部に漏らすことは禁止されています。
それは、顧客が安心してカウンセラーに悩みを打ち明けられるようにするためであり、心理的な支援として必ず必要です。
もし、カウンセラーが個人情報などを漏らして規則違反した場合は、法律上において守秘義務違反となり、損害賠償などの責任を負わなければなりません。
顧客が安心して相談できる環境を作るためにも、個人情報は必ず外部へ漏洩しないことが重要です。
特徴⑤新しい知識を学び続ける意欲的な人
顧客の悩みを解決するためには、心理カウンセラーとして正しい知識を身に付けながら、新しい情報を常にアップデートしていかなければなりません。
また、顧客の年齢や性別、性格もさまざまであるため悩みも多種多様に存在します。多くの顧客の問題を解決していくためには、幅広い知識をインプットしながら、臨床で役立てていく必要があるでしょう。
顧客の抱える問題の解決方法の答えは一つではないため、常に新しい情報を取り入れながら、相手の状況に合わせて最適な解決策を導くことが大切です。
特徴⑥感情に左右されずに寄り添える人
心理カウンセラーとして、顧客の悩みに共感することは大切ですが、感情移入しすぎない判断力が求められます。
特に、人の感情に敏感になりやすく感受性が高いカウンセラーが、感情移入しやすい傾向にあります。感情移入をしてしまうと、顧客と同じ悲しみに浸ってしまい、ストレスを抱えてしまいます。
感情移入しすぎないためにも、相手の話に共感しながら自分の感情をコントロールできるように、物事を客観視できる能力を鍛えることが大切です。
まず「感情移入してはいけないんだ」と意識することが大切です。感情移入しすぎることは時に自分自身を苦しませることにつながります。
カウンセリング中に感情的になっていることに”気づく”ということが大切で、それを繰り返して内省していくことだと思います。
あなたが受けないほうがいい職業を診断しましょう
就活を進めていると、自分に合う職業がわからず悩んでしまうことも多いでしょう。
そんな時は「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格、価値観を分析して適職や適さない職業を特定してくれます。
自分の適職や適さない職業を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
厳しい一面もある! 心理カウンセラーに向いていない人の4つの特徴
厳しい一面もある! 心理カウンセラーに向いていない人の4つの特徴
心理カウンセラーに向いている人の特徴を知って、自分は当てはまっていそうだと感じる人もいるのではないでしょうか。しかし、その特徴に当てはまっていても、これから解説する4つの厳しい一面を読んで、慎重に進路を考慮した方が良い人もいるかも知れません。
実際に働いてみて、自分の思い描いていた働き方ができなければ、徐々につらくなっていく可能性も考えられます。これから説明する、向いていない人の特徴も必ず確認しておいてくださいね。
特徴①「こうすべき」という固定観念が強い人
人に対して自分の価値観や考えを押し付ける傾向がある人は心理カウンセラーに向いていない可能性があります。
カウンセリングを通して悩みに対する問題解決の方法は一つとは限らず、それぞれの生き方や考え方によって最適な選択は異なります。
そのため、「こうすべきだ」と自分の固定概念を押し付けるのではなく、顧客の価値観を尊重しながら、一緒に問題解決方法を探していくことが大切です。
自分の価値観を正解として考えるのではなく、顧客の価値観に寄り添いながら、問題解決していくことが大切です。
- 顧客が社会的に問題のある価値観であっても共感しなくてはいけないのでしょうか?
共感を示しながら相手を尊重することが大切
「共感」と「同感」は異なります。自分と違う価値観を持つ顧客の人生や生活の話を聴き、気持ちや考えの背景を知ることで、「そういった経緯からこの価値観になったのだな」と理解や共感を示すことができます。
これにより、相手を尊重することができます。考えや行動の変化を促すことや、違う考え方を提案することも、まずは尊重や信頼関係の構築があってこそ成り立ちます。
心理カウンセラーの面接で、「大切にしている価値観」について聞かれる可能性もあります。以下の記事を参考に回答方法を参考にしてくださいね。
特徴②感情の起伏が激しい人
感情の起伏が激しく、情緒が安定していない人はカウンセラーに向いていない可能性があります。心理カウンセラーには、顧客の感情に寄り添いながらも、専門家として冷静に受け止めて正しく対応する能力が求められます。
そのため、感情の起伏が激しいと、顧客からの相談を受けても自分の感情が不安定になることで、適切な支援ができなくなります。
たとえば、顧客に対して怒りの感情を抱いた場合、自分では制御できなければ、相手にもイラついた雰囲気が伝わり、心を閉ざしてしまいます。
感情のコントロールができずに、相手にそのままの感情をぶつけてしまう人はカウンセラーをするのは難しかもしれません。
- 感情をコントロールするのが苦手です。トレーニングすることで克服できますか?
論理的な思考で解決していくことが大切
できます。どんな感情でも自分で認識して論理的に解決していこうという気持ちがあれば可能だと思っています。心理カウンセラーであるならば、なおさら自分の気持ちがしっかりコントロールできなければクライエントとのかかわりは困難です。
具体的には、認知行動療法のなかにコラム法というものがあります。これは自分の気持ちのなかに湧き起こった感情やその時の出来事などを書き出して点数化してみて、気持ちを整理していくやり方です。
特徴③ストレス耐性が弱い人
日頃からストレス耐性が弱い人は心理カウンセラーに不向きの傾向があります。人のストレス耐性は生まれ持った要素も大きいですが、環境によっても変化します。
顧客の苦しみや悲しみに共感しすぎるあまりに、気持ちの切り替えができないまま、抱え込み心を病んでしまうことも考えられます。
ストレスを抱えても、周りのスタッフに相談したり、日頃からストレス解消をしたりして仕事とプライベートを分けることが大切です。
さまざまな価値観や悩みを抱えた人とかかわる仕事であるため、ストレス耐性が弱いと、心理カウンセラーに向いていない傾向です。
カウンセラーに必要なストレス耐性は「あいまいさに耐える力」といわれます。心理的課題は、短期間ではなかなか解決しないものです。焦らず、楽天的に構える力があると、顧客にも希望をもって対応することができます。
ストレス耐性を求められる職業であるからこそ、面接で「どんなときにストレスを感じますか」という質問を受ける可能性があります。面接官からの信頼を勝ち取るためにも、以下の記事を参考に回答を準備しておいてくださいね。
特徴④人と話すことに苦手意識がある人
人とコミュニケーションをとることに苦手意識がある人は、心理カウンセラーに向いていない可能性があります。
カウンセラーとしての仕事は、顧客との対話を通して解決方法を導き出していく仕事であるため、コミュニケーション能力は必須になっていきます。
さらに、顧客のなかにはコミュニケーションに苦手意識を持った人もいるため、本質的な悩みを探るにはカウンセラーの対話力にかかっています。
そのため、聞く力や話す力どちらが欠けていても顧客を適切に支援するのは難しいでしょう。
- 私自身社交的な性格ではありませんが、それでも心理カウンセラーは務まりますか?
社交的ではない方が向いていることがある
はい、務まると思います。むしろ、心理カウンセラーに社交性は必須事項ではないと個人的には考えているので、引っ込み思案な性格のカウンセラーさんはたくさんいらっしゃいます。
むしろ、自分からペラペラと話したり、あれこれ口を挟むことはクライエントにとって良い要素ではありません。そのため社交的な性格ではない人の方が向いている側面もあります。
心理カウンセラーとしてコミュニケーション能力は重要なスキルです。面接でしっかりアピールできるように以下の記事を確認してくださいね。
コミュニケーション能力の言い換え
コミュニケーション能力は12個の言い換えで勝負しよう! 例文つき
コミュニケーション能力の自己PR方法
例文12選|コミュニケーション能力の自己PRを3ステップで解説
あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
現場のプロに聞いた! 心理カウンセラーはどんな人が活躍できる?
ここまで、心理カウンセラーに向いている人の特徴と併せて、向いていない人の特徴を解説してきました。具体的にどのような人材が求められるか理解できたところで、心理カウンセラーとして働くイメージがしやすくなった人もいるでしょう。
しかし、なかには「結局どんな人が活躍してるの?」と思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで就職支援のプロであるキャリアアドバイザーの古田さんから、実際に心理カウンセラーはどんな人が活躍できるのかを解説してもらいます。ぜひ参考にしてくださいね。
アドバイザーコメント
7つのスキルを持ち合わせている人は活躍できる
専門知識があることが前提ですが、「共感力」「コミュニケーション能力」「忍耐力・辛抱強さ」「柔軟性」「論理的思考」「洞察力」「自己管理能力」といったスキルを持ち合わせている人は活躍できるでしょう。
まず、共感力がないとクライエントの感情や視点を理解することができません。クライエントが感じる苦しみや感情を共有できることが、信頼関係を築く第一歩になるからです。
そして、コミュニケーション能力がないと、言葉の定義や意味をクライエントとすり合わせることができません。明確かつ適切なコミュニケーションができるかどうかや、非言語的なサインを読み取る洞察力も必要です。
また、頭の中が整理できていないクライエントの話を辛抱強く聞いて、どこに課題があって、何に気付けていないかなどを論理的に考え、忍耐強くサポートをしなければなりません。
自分自身のメンタルケアも重要
それだけでなく、クライエントと共倒れしないよう自分のメンタルケアも必要です。これらの能力に自信がない人には不向きかもしれません。どれか1つでも欠けるとつらい仕事だと思います。
特別な動機がなくても大丈夫!
ツールを使えば魅力的な志望動機が作れます
「第一志望以外の志望動機が思い浮かばない……」と感じたことはありませんか?そんな時にぜひ活用してほしいのが「志望動機作成ツール」です。
簡単な質問に答えるだけで、特別な動機がなくても採用したいと思われる志望動機が簡単に作成できます。
志望動機で困ったら、まずはツールを活用してみましょう。
(人材業界の場合)
やりがいを感じるかも重要! 心理カウンセラーならではの魅力
心理カウンセラーを目指すためには、適性を見極めることは重要です。 しかし、それと同じくらい大切なのが「やりがい」を感じられるかどうかです。
転職するからには、できるだけ長く心理カウンセラーとして活躍していきたいですよね。ここでは、心理カウンセラーならではの魅力や仕事で得られる充実感について紹介します。
悩んでいる人の役に立ち充足感を感じられること
心理カウンセラーの仕事のやりがいは、心の悩みを抱えた顧客に対して、一緒に問題を解決していく過程にあります。
最初は、ネガティブな感情が強い顧客でも、かかわりのなかで少しずつ心のモヤモヤが晴れて明るい気持ちになっていく姿を間近で見られます。
顧客に寄り添い、カウンセリングを通して、人生をサポートできることは、大きな充足感をもたらしてくれるでしょう。
徐々に自分の気持ちと向き合い、前向きな姿勢になっていく様子に立ち会えることは、心理カウンセラー職業ならではの喜びです。
新しい価値観に触れて視野が広がること
心理カウンセラーとしてさまざまな顧客と向き合うなかで、多様な生き方や価値観に触れられることも、この職業の大きな魅力の一つです。
顧客との対話を通して、今まで考えられなかった視点や価値観に触れることで、自分を見直すきっかけにもつながり、柔軟な思考が身に付きます。
年齢や職業など背景の異なる顧客との対話は、カウンセラーとしての成長だけでなく、人生をより豊かなものにしてくれるでしょう。
確実に成長ができることだと思います。それはうれしいことばかりではなく時にハッとさせられるような、とてつもない後悔の念のような場合もあります。
でも、それを経験することでまた一つステージが上がったなと喜ぶことができるのも事実です。
スキルアップをすぐに感じられること
心理カウンセラーの仕事は、すぐにスキルアップを感じられる点も大きな魅力です。心理カウンセラーが使う傾聴術や質問の技法などは、カウンセリングですぐに活用できるため、効果を実感できます。
傾聴
相手の話を深くまで理解しようと誠心誠意向き合いながら耳を傾けること
そうすることで、これまで解決できなかった問題が徐々に前進したり、顧客が心を開いてくれたりとプラスに働きます。
専門知識や研修会などの参加で学んだ実践的な知識まで、顧客とのカウンセリングですぐに活かせることで、自身の成長も加速しやすいでしょう。
カウンセラーになりたての頃、ミラーリングや反射的傾聴を違和感なく自然に使えるようになった時、クライエントがいろいろなことを話し始めるようになったことがあり、効果を実感したことは今でも記憶に残っています。
適性を感じたら理解を深めよう! 心理カウンセラーとは?
ここまで読み進めてきて、「自分に向いていそうだな」と感じたら、実際に心理カウンセラーの仕事内容やどのような場所で活躍できるのかを詳しくみていきましょう。
実際に働く場所によって心理カウンセラーとしての役割も大きく変わってくるため、どのような場所で活躍していきたいのか、イメージを膨らませながら読み進めていってくださいね。
また、働くうえで大切なのが給料の部分です。心理カウンセラーの年収に関しても解説しているので、参考にしてください。
心理カウンセラーの基本情報
心理カウンセラーとは、顧客の心の問題や悩みに専門的な立場から寄り添い、解決に向けてサポートする専門家です。
専門的な知識や技法を活用し、顧客とのカウンセリングを通して、一緒に問題を解決していきます。
現代社会では、仕事や人間関係のストレス、将来への不安など数多くの人が心に悩みを抱えており、心理カウンセラーの重要性は高まっています。
また、働く場所も多様にあるため、医療機関だけにとどまらず、一般企業や学校などさまざまな場所で活躍できます。
心理カウンセラーの活躍場所ごとの仕事内容
心理カウンセラーの活躍場所ごとの仕事内容
心理カウンセラーの職場は多様にあり、職場ごとに仕事内容や役割は大きく異なります。ここからは、活動場所ごとの仕事内容を解説していきます。
実際に自分はどんな場所で働きたいのかイメージを膨らませながら読み進めてくださいね。
教育現場:生徒や児童・教職員のケア
教育現場では、心理カウンセラーとして生徒や児童、ときには教職員などをカウンセリングして悩みをサポートしていきます。不登校やいじめ、学業不振、進路の悩みなど、教育現場特有の問題に対してカウンセラーとして専門的なサポートを提供します。
活動場所は、小中高校をはじめ、フリースクールや教育支援センターなどにも心理カウンセラーが在籍しています。教職員や行政機関と連携しながら、生徒一人ひとりの状況や環境に応じた支援をおこない、学校生活を安心して送れるサポートをしています。
スクールカウンセラーは、児童生徒の悩み相談に直接乗るだけではありません。支援体制の調整やコーディネイト、他機関への連携づくりなど、相談室の外に出て活動する場面も多々あります。
医療機関:精神科医と連携しながら患者のカウンセリング
医療機関では、うつ病やパニック障害、社会不安障害など心に病気を抱えた患者に対して、カウンセリングを通して一緒に問題を解決していきます。
活躍場所は、病院や精神科クリニック、児童福祉施設など医療機関といっても多岐にわたります。各医療機関の特性に応じて、外来患者への定期的なカウンセリングから、入院患者の治療プログラムまで、さまざまな場面で専門性を発揮します。
また、医療現場の心理カウンセラーは、箱庭療法や認知行動療法などの心理検査をおこないながら、精神科特有のアプローチで回復をサポートします。
箱庭療法
砂が敷き詰められた箱の中に、動物や植物などのミニチュアの人形を自由に配置することで、無意識の心の状態を表現する心理療法。
認知行動療法
物事の受け取り方(認知)に働きかけて、柔軟な考え方や行動のパターンを身に付けていく技法
- 医療機関の心理カウンセラーはハードなイメージがありますが、どうでしょうか?
ハードな一面もあるがやりがいも感じられる
私は医療機関での経験がないので知識レベルにはなりますが、基本的には心理検査(知能検査や発達検査など)が大半を占めているようです。
大半は大きな施設で働くことが多いですし、地域のクリニックでも同様に検査はおこなうので1日の仕事の大半は心理面接と心理検査で時間を過ごすことになるでしょう。
それ以外にも多職種による会議は患者さんのご家族のケアなども場合によってはおこなうことがあるのでやはりハードですが、それだけやりがいがある仕事でもあります。
福祉施設:高齢者やその家族へのケア
福祉施設とは、子どもやお年寄り、障害者などに対して福祉サービスを提供する施設です。児童福祉施設や障害者福祉施設、高齢者福祉施設などが該当します。
福祉施設の現場では、家庭内暴力や虐待、セクシュアルマイノリティ(同性愛者)などの悩みを抱えている方が多い傾向です。
そのため、福祉施設の心理カウンセラーは、利用者の状況に応じた心理的なサポートをして、生活の質の向上と自立を支援します。
ときには、利用者の家族に対しても相談やサポートすることがあるため、福祉施設の心理カウンセラーは、重要な役割といえます。
施設の利用者のカウンセリングはもちろん、利用者の家族やほかの機関とも連携する必要があるため、仕事は多岐にわたります。障害者の場合は意思疎通が難しいこともあるため、信頼関係を築くことが何より大変です。
一般企業:従業員へのメンタルヘルス対策
企業に従事する社会人のメンタル不調も問題となっており、一般企業の心理カウンセラーとして従事する人も多いです。
一般の企業で働く場合は、産業カウンセラーやキャリアカウンセラーとして従事し、従業員の人間関係やハラスメント、長時間労働に関する悩みをサポートします。
特に、一般の企業では上司に相談しにくい環境もあるため、専門家として従業員と面談を通して、働きやすい環境づくりを整えます。
仕事の内容としては、ストレスチェックや健康診断の実施、職場内を循環して問題点を発見、解決していく必要があります。
- 一般企業の心理カウンセラーは、どのような悩みを聞くことが多いですか?
産業分野の心理職は他職種連携が大切
産業分野の心理職は、職場適応やストレスマネジメントについての相談に対応します。休職・復職についての相談助言も大事な役割です。
企業と契約している外部の専門会社(EAP:Employee Assistance Program:従業員援助プログラム)スタッフとして相談にあたることもあります。
会社の人事部や産業医、本人やその上司との連携をとることもあり、「多職種連携」の姿勢が求められます。
司法分野:非行少年の更生などをサポート
心理カウンセラーとして、家庭裁判所や刑務所、少年院で非行少年などの立ち直りをサポートすることも可能です。非行や犯罪を犯した背景には、複雑な心理的問題や環境問題が関与していることが多く、心理カウンセラーとしての専門的なサポートが必要です。
おもに、対象者との面談をおこない、家族関係やこれまでの成長の過程を深掘りしながら、対象者を理解していきます。ときには、対象者の家族とも面談をおこない、より良い関係作りや環境づくりを提供していくのも重要な仕事の役割です。
非行少年の犯罪を犯した背景、家族などの周囲の関係を考慮しながら、再非行防止のためにサポートしていくことが求められます。
司法分野で仕事をするにはおもに臨床心理士、公認心理師などであり、おもに受刑者に対してカウンセリングをしたり集団療法をおこなうこともあります。
犯罪を犯した人が社会復帰できるためのあらゆる支援をおこなうことになるので熟練した経験が必要となります。
心理カウンセラーの年収
心理カウンセラーの年収は、Indeed Japanの情報によると、約353万円(月収約25万円)です。心理カウンセラーのなかでも、公認心理師の資格を持っている場合であると、年収は約380万円(月収約27万円)と、少し差があります。
病院や企業で働く場合は、公認心理師や臨床心理士などの資格が必須となるのが一般的です。そのほかは、勤務形態や給与水準によって変動するでしょう。
- 収入を上げたい場合は、心理カウンセラーとして病院などで働いた方が良いのでしょうか?
経験を積んで独立を目指す方が収入アップが見込める
臨床心理士や公認心理師の場合は、病院や教育機関、国の機関や企業内などでもニーズがあるため、ある程度安定した収入を得られますし、それ以上の収入アップを目指す場合は、独立するなどして自分で料金を設定することで収入を上げやすくなります。
そのほか、書籍の執筆や講演などでも追加の収入を得ることができます。最近ではオンラインや専用アプリでカウンセリングを請け負う先生も増えてきています。
民間のカウンセラー資格でも独立はできますが、資格の認知度が低く、実績がないとクライエントは来てくれないため、公認心理師と同額の収入かそれ以上を得たい場合は、関連資格を追加で取得するなどすれば可能かもしれません。
企業に刺さる志望動機は、AI作成ツールを試してください
「企業に伝わる志望動機ってどうやって書くの…?」そんな悩みはありませんか?
「志望動機作成ツール」では、AIがあなたの思いや強みを文章に落とし込み、選考に強い志望動機を作成します。
面接官の心に響く内容を準備し、次のステップに進む準備を整えましょう!
現役のプロに聞いた! 心理カウンセラーのキャリアを想像してみよう
ここまで、心理カウンセラーならではの魅力や仕事内容を詳しく解説してきました。ここまで読んで、心理カウンセラーとして、「自分ならこんな働き方がしたい」というイメージが湧いた人もいるでしょう。
しかし、なかには「心理カウンセラーはどんなキャリアパスを描けるの?」と思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで就職支援のプロであるキャリアアドバイザーの永田さんから、心理カウンセラーとしてどのようなキャリアを築いていけるのかを解説してもらいます。ぜひ参考にしてくださいね。
アドバイザーコメント
下積みの経験を経て開業するのが最も最良
私が考えるなかで最も最良だと思うキャリアの歩み方があるので紹介したいと思います。大前提として心理カウンセラーは名乗るだけでできる仕事ですから特に資格も必要なくその日からすぐになれます。しかしそれだけでは長くキャリアを築くことは難しいでしょう。
ですからやることとして
①臨床心理士と公認心理師を取得する
②5領域の分野のどこかで3〜5年(できれば10年)は臨床経験を積む
③学会や勉強会を通して開業しているカウンセラーなどとパイプを作る
④準備をして開業する
が現実的かと思います。
ここまでしっかり下積みができていると開業してうまくいけばそれなりに続けていけますし、また勤めようと思えば実績もあるので採用してもらうこともできます。
選択肢の幅を広げるためにも資格は取得しておいた方が良い
また長くキャリアを重ねることで災害支援の現場や海外の被災地支援の現場などへも行ける可能性もあるので、そのとき自分がどうしたいかによって自由に選択できます。これもやはり実績のある資格が成せる技なので取得することをおすすめします。
心理カウンセラーに必要な4つのスキル
心理カウンセラーに必要な4つのスキル
心理カウンセラーとして働くためには、専門的な知識に加えて、いくつかスキルが求められます。ここからは心理カウンセラーに必要な4つのスキルを紹介します。
顧客の心に寄り添い、効果的な支援を提供するために必要なスキルなので、最後まで読んで確認してくださいね。
①相談者の動きや言動から読み取る洞察力
顧客の言葉以外の非言語的な表現を見逃さず読み取る洞察力のスキルが必要です。顧客は、心の中の気持ちをうまく表現できないことが多いため、実際の表情や言動から読み解く必要があります。
たとえば、顧客が話をしている際に目が泳いでいる場合は、緊張や不安を感じている可能性が高いです。
このように読み解くことができれば、カウンセラーは顧客の緊張がほぐれるように、話しやすくなるような聞き方や質問の仕方を工夫しなくてはなりません。
顧客の非言語的な表現には、心の中の気持ちが表れていることが多いため、カウンセラーにとって洞察力は重要になります。
- 人に寄り添う気持ちはありますが、気持ちを読み取ることは苦手です。向いていないのでしょうか?
トレーニング次第でスキルは向上させられる
寄り添う気持ちがあることはカウンセラーとして大切な資質の1つです。最初から何でも上手にできる人はいません。
自分に何が足りていないのか、何を勉強・トレーニングすれば足りないスキルを身に付けられるかを考えて取り組むことで、スキルを向上させることは可能だと思います。
現役のカウンセラーも、資格を取得したら終わりではありません。日々、新しい情報を得るために勉強やトレーニングを欠かさない先生もたくさんいらっしゃいます。
まずはできることがないか探して挑戦してみてはいかがでしょうか。寄り添う気持ちは持っているのですから、諦めるのはまだ早いと思います。
②心理学に関する専門的な知識
顧客に効果的なカウンセリングを受けてもらうためには、カウンセラーの専門的な知識が必須になります。
また、年齢や生活背景の異なる顧客が多いため、豊富に知識を持っているとさまざまな人に対応できます。
専門的な知識は、大学や専門学校で学んだり、資格を取得して身に付けたりすることが可能です。
心理カウンセラーには、「一生勉強し続ける姿勢」が求められます。勉強量について一概には言えません。しかし、最低限の勉強で済ませたい、学ぶことが苦痛だと感じる人には、この職業はあまり向いていないかもしれません。
③悩みを受け入れ続ける辛抱強い心
どのような内容の相談を受けた場合でも、顧客を否定せずにありのままを肯定することが大切です。
カウンセラーは、顧客に対し傾聴の姿勢で共感しながら話を聞く能力が求められます。ときには、デリケートな悩みやつらい経験を打ち明けられることもありますが、そのようなときこそ、顧客が安心して相談できるような環境づくりが大切です。
カウンセラーは、顧客の気持ちに寄り添いながら、一緒に解決策を見つけていくことが重要です。
④相談者に安心感を与えられる包容力
心理カウンセラーにとって最も重要な役割の一つは、顧客が安心して自分の思いを話せる環境を作ることです。特に初対面の場合だと、緊張して思うように言葉が出てこない顧客もいます。
そのため、まずは顧客のありのままの存在を受け入れて、共感して寄り添う姿勢が重要です。温かな表情、穏やかな声のトーン、適度なアイコンタクトなど、非言語的なコミュニケーションに気を配ると、信頼関係を築いていけるでしょう。
「このカウンセラーは理解してくれる」と思ってもらえるように、安心感を与えられるような表情や言動に注意を向けることが大切です。
心理カウンセラーに向いているなら! 目指すための3つの方法
心理カウンセラーを目指すことを決意している人もいるのではないでしょうか。心理カウンセラーになるためには、いくつかの方法があります。
カウンセラーを目指す方法は、自分の現状や目標に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。ここからは、心理カウンセラーになるための具体的な方法を紹介していきます。
①大学や専門学校で専門的に学ぶ
心理カウンセラーを目指すなら、大学や専門学校で学ぶのが一般的です。心理カウンセラーの資格のなかで、臨床心理士や認定心理士の資格は、大学や専門学校の指定された科目を履修することで、受験資格が与えられます。
そのため、国家資格の取得を考えている人や社会人の人はすべて、大学や専門学校で学ぶことが必須のため注意が必要です。
社会人の人は、すぐに大学や専門学校へ通うのは難しい人も多いため、自分のキャリアの計画をしっかり立てたうえで、十分に検討することが大切です。
心理学は幅広い分野で役立つ知識です。福祉や学校、医療分野で就職したい人におすすめです。社会貢献や人にかかわることが多いビジネスにも活かせるところはメリットなので、その分野で活躍したい人にもおすすめです。
②資格取得のために民間スクールや通信講座で学ぶ
特に社会人などは、民間のスクールや通信講座を活用して資格を取得するのがおすすめです。
臨床心理士や公認心理師などの国家資格は、大学や専門学校で学ぶことが必須ですが、民間の資格であれば働きながらの社会人でも比較的取得しやすい資格です。
民間スクールでは、 心理学の基礎知識と実際の演習を交えながら学べるため、就職後もスキルを活かしやすいです。また、就職のサポートが手厚いところもあるため、就職先も安心して見つけられます。
一方、通信講座では1日数時間の勉強で知識を身に付けることができるため、働きながらでも勉強ができます。
また、オンラインや対面での授業を選べる通信講座もあるため、生活スタイルに合わせて選択できるところもメリットです。
自分の周りの人との接し方について学びたい、趣味として心理学を学びたいという人にとっては良いかもしれません。そこで学んだことがきっかけで本格的に心理学の世界に進んでいくかもしれませんね。
③現場で経験を積みながら働く
働く場所によっては、心理カウンセラーの資格は必須ではないため、実績を積みながら仕事ができます。
未経験で実績を積む場合は、ボランティアや助手として働くことがおすすめです。現場で経験を積みながら知識を取得できます。
しかし、心理カウンセラーとしての資格は必須ではなくても、資格を保有している人と比較して信頼性にも欠けて、働く場所も制限されるでしょう。現場で経験を積みながら、民間資格の取得を目指すのも一つの方法です。
- 心理カウンセラーになるのに、資格は持っておいた方が良いのでしょうか?
資格の取得は心理学を体系的に学べる手段の一つ
「自分の傷ついた体験を活かして人を支援したい」と考える人もいますが、それだけでは技術として十分ではありません。資格の有無にかかわらず、心理支援の技術を習得し、継続的に研鑽を積むことは不可欠です。
心理学や心理療法を体系的に学ぶには、資格取得の学習枠組みを活用するのが役立ちます。
資格取得団体で得られる人とのつながりは、将来的に研鑽をともにする仲間となり、学習会や研究会の情報も得やすくなります。資格講座を利用することは、効果的な勉強方法を知るだけでなく、人脈を広げるうえでもメリットがあります。
心理カウンセラーにこれから挑戦する人におすすめの資格9選!
心理カウンセラーにこれから挑戦する人におすすめの資格9選!
ここまでで、心理カウンセラーの目指す方法などを解説してきましたが「実際にどんな資格があるの?」と疑問に思った人も多いのではないでしょうか。
心理カウンセラーと一口に言っても、働く場所によって必要な資格は異なります。資格がなくても働ける場所はありますが、顧客からの信頼性を担保するためにも、資格は取得しておいた方が良いでしょう。
ここからは、おすすめの資格を9選紹介します。自分の目指す進路に合わせて資格取得を目指してくださいね。
①公認心理師
| URL | 公認心理師 |厚生労働省 |
| 受検費用 | 28,700円 |
| 受検資格 | ・指定された4年制の大学で必要な科目を履修し、その後、大学院でさらに2年間学んだ者・4年制大学で必要な科目を履修後、認定施設で2年以上の実務経験を積んだ者 |
| 受検方法 | 筆記試験 |
公認心理師は厚生労働省が認める国家資格です。この資格は、資格を取得した人だけが名乗れる資格(名称独占資格)です。
資格を取得するためには、大学へ通い指定された科目を履修することが必須条件になります。さらにそこから、大学院または現場で実務経験を積んだ人に受検資格が与えられます。
心理カウンセラーのなかでは、唯一の国家資格であり、そのほかの資格はすべて民間資格に該当します。国家資格は法律に従って一定の社会的地位が保証されているため、資格を保有しているだけで信頼性が高まるでしょう。
- 民間資格と比較して国家資格を保有していることのメリットを教えていただきたいです。
国家資格は民間資格よりも圧倒的な信頼感がある
公認心理師は国家資格であるため、法律に基づいて認められている信頼性が非常に高い資格です。そのため、就職の際だけでなくクライエントからの信頼を得やすいところはメリットでしょう。
また、公認心理師試験に合格するためには、高度な専門知識や技術が必要です。専門性が高いという点でも民間資格と比較すると圧倒的な説得力があります。
そのため、医療、教育、福祉、司法など幅広い分野で活躍できるだけでなく、就業先での昇進の際にも有利に働き、より高い職位や待遇を得やすいこともメリットといえるのではないでしょうか。
心理学を活かせる仕事について知りたい人は以下の記事を参考にしてください。資格に関して詳しく解説していますよ。
②臨床心理士
| URL | 臨床心理士とは |
| 受検費用 | 受験申請:1,500円 |
| 受検資格 | ・指定大学院を修了した者・臨床心理士養成に関する専門職大学院を修了した者・諸外国で指定大学院と同等以上の教育歴があり、修了後の日本国内における心理臨床経験2年以上ある者・医師免許取得者で、取得後に心理臨床経験2年以上ある者 |
| 受検方法 | ・一次試験(筆記)・二次試験(面接) |
臨床心理士は、日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間の資格です。臨床心理士の資格を得るためには、指定の大学や専門学校で、専門的な知識を学び卒業した人しか受検ができません。
さらに、臨床心理士は資格を取得して終わりではなく、5年ごとの再認定が必要となります。そのため、臨床心理士になってからでも、継続的に勉強をしながらスキルを身に付ける必要があるでしょう。
- 心理カウンセラーの資格が多すぎて選べません……。
資格団体に直接問い合わせて調べてみよう
資格取得者の活躍状況を調べてみましょう。「資格名+カウンセリング」と検索すると、その資格を持つ人がどこでカウンセリングをおこなっているか、具体的な情報が得られます。
もし資格取得者の活動情報が見つからないなら、その資格は生涯学習や自己啓発の役割にとどまるのかもしれません。
正直なところ、心理カウンセラー資格は玉石混淆です。資格を活かして就職、転職、独立を目指しているのであれば、「卒業生は具体的にどのように活躍していますか?」と資格団体に直接質問して確認することをおすすめします。
③日本心理学会認定心理士
| URL | 認定心理士資格申請 |
| 受検費用 | 申請書類 審査料:11,000円 認定料:33,000 円 |
| 受検資格 | 4年制の大学(一般心理学や医学などの科目を含む)を卒業し,その在学期間に取得した単位を認定単位とする |
| 受検方法 | 試験なし |
日本心理学会認定心理士は、公益社団法人が運営している日本心理学会が認定する民間資格です。心理カウンセラーとして働くために、専門的な知識を保有し、技能を大学で習得していることを証明する資格です。
職能の資格ではないため、認定心理士という職業ではなく、将来心理カウンセラーとして活躍したい人が取得する資格となっています。
- 日本心理学会認定心理士はどのような人が保有するべき資格なのか詳しく教えていただきたいです。
人と関わる仕事に就くためのアピールとして効果的
日本心理学会認定心理士は、大学で取得した単位を証明するものなので、大学を卒業した後、大学院や研究職に進む際に単位を取得した証明書として申請する人がいます。
そのため、どのような人が保有すべきかというよりは、進路や仕事に活かせる(活かしたい)と感じた人が必要に応じて申請するものです。
活かせる職種も、心理カウンセラーだけでなく医療方面の職種や学校などで教育に携わる職種、接客業や顧客と対面するような職種、企業の人材開発や人材育成に携わる職種など、「人とかかわる仕事」に就く際にアピール材料にはなるので、必要に応じて申請すると良いでしょう。
④JADP認定メンタル心理カウンセラー
| URL | メンタル心理カウンセラー資格|日本能力開発推進協会 (JADP) |
| 受検費用 | 5,600円(税込) |
| 受検資格 | 当協会指定の認定教育機関などがおこなう教育訓練において、その全カリキュラムを修了した者 |
| 受検方法 | 講座の受講筆記試験 |
JADP認定メンタル心理カウンセラーとは、一般財団法人の日本能力開発推進協会が認める民間資格です。
教育や医療の現場で求められるカウンセリングのスキルや、知識を持っていることを証明できます。受検するためには、協会が提供している講座カリキュラムを履修し検定試験に合格する必要があります。
- JADP認定メンタル心理カウンセラーは、どのような人が保有するべき資格なのか詳しく教えていただきたいです。
心理学の基礎の教養を身に付けたい人におすすめ
「心理学って興味があるな」「カウンセリングに興味があるな」と感じる人が心理学の基礎的な教養として身に付けたいと思う場合に取得する資格だと思います。保有していることで特段何かの職業に就くことができるわけではありません。
ですが、カリキュラムを修了し認定してもらうことで自分に自信がつくこともありますし、それがきっかけとなり心理カウンセラーへの道を本格的に歩んで行こうという動機にもつながることがあります。
⑤チャイルド心理カウンセラー
| URL | チャイルド心理カウンセラー®資格認定試験 |
| 受検費用 | 10,000円(税込) |
| 受検資格 | なし |
| 受検方法 | 講座受講在宅受検 |
チャイルド心理カウンセラーは、日本メディカル心理セラピー協会が認定する民間の資格です。資格を取得することで、教育現場などで、DVや暴力、学校でのいじめなどの問題に対応できる心理学の知識を保有していることの証明になります。
受検するためには、協会より指定された講座の受講と資格試験への合格が必須になります。
今後、福祉や教育の現場などで積極的に子どもとかかわる心理カウンセラーを目指したい人におすすめの資格です。
⑥福祉心理カウンセラー
| URL | 福祉心理カウンセラー資格認定試験 |
| 受検費用 | 10,000円(消費税込み) |
| 受検資格 | なし |
| 受検方法 | 在宅受検 |
福祉心理カウンセラーとは、日本メディカル心理セラピー協会が認定する民間の資格です。この資格は、福祉の現場で、心理学の理論や基礎知識を活かして支援できることを証明する資格です。
資格の取得後は、介護老人保健施設や児童福祉施設、訪問介護などの現場で活躍できます。子どもから大人まで幅広い人々の支援をしたい人におすすめの資格です。
⑦JADP夫婦心理カウンセラー
| URL | 夫婦カウンセラー資格|日本能力開発推進協会 (JADP) |
| 受検費用 | 5,600円(税込) |
| 受検資格 | 認定教育機関での課題修了した者 |
| 受検方法 | 在宅受検 |
JADP夫婦心理カウンセラーとは、一般財団法人の日本能力開発推進協会が認める民間資格です。カウンセリングを通して、夫婦間での離婚や育児に関して心理的な問題を解決できます。
おもな活動場所としては、結婚相談所などの結婚関連施設やヘルスケア施設、福祉施設の家族支援部門など、働く場所は多岐にわたります。
今後、心理カウンセラーとして夫婦や家族間での問題の解決に携わっていきたい人におすすめの資格です。
⑧TA心理カウンセラー
| URL | NPO法人 日本交流分析協会|TA心理カウンセラーとは |
| 受検費用 | ・受講料:132,000円(税込)(含テキスト代 8,800円)・認定試験受験料: 22,000円 (税込)・合格後の認定登録料:33,000円(税込) |
| 受検資格 | ・TAインストラクター資格取得後1年以上経過し、資格取得後もTAおよび周辺理論などの学習を精力的に続け、レベル向上を図っている者・現にカウンセラーを業としている者、または経験者、若しくは目指して研修中の者・養成委員会が別に定める支部推薦基準を満たし、協会の社会貢献活動に熱心な者 |
| 受検方法 | 講座の受検認定試験 |
TA心理カウンセラーとは、日本交流分析協会が認定する民間資格です。TAとは、(Transactional Analysis:交流分析)のことを指し、資格を取得することで、人間関係における心理的な交流を分析、改善できるようになります。
資格を取得するためには、TA心理カウンセラーの10日間の養成講座を受講した後に、認定試験を受けることができます。学校や職場での人間関係の問題をサポートしていきたい人におすすめの資格です。
⑨産業カウンセラー
| URL | 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 |
| 受検費用 | 352,000円(教材費を含む、税込)学科試験:10,500円(税込み)実技試験:21,000円(税込み) |
| 受検資格 | ・協会が指定する講座を受講した者・4年制大学学部の卒業者で、指定された科目を修了した者・社会人で週3回以上の職業経験があり、大学院の研究科で指定された専攻の修了者であること |
| 受検方法 | 講座の受講(対面またはオンラインでの受講可能)学科試験、実技試験 |
産業カウンセラーは、一般社団法人の日本産業カウンセラー協会が認定する民間の資格です。一般企業などの職場におけるメンタルヘルスケアの専門家として知られています。
一般的には、社員からのメンタルヘルスやキャリアに関する相談を受けて、一緒に問題を解決していきます。
また、必要に応じてストレスチェックの実施や結果に対する対応、従業員支援プログラム(EAP)の運営などをおこないます。心理カウンセラーとして企業での活躍に興味がある人におすすめの資格です。
心理カウンセラーの適性を見極めて自分に向いている仕事を目指そう!
自分に合った仕事を見つけるためにも、心理カウンセラーに向いている人の特徴を把握しておくことが大切です。しかし、働き始めてギャップを感じる可能性も考えられるため、向いていない人の特徴や仕事の内容をしっかり確認したうえで目指すことを判断してください。
最後に心理カウンセラーにおすすめの資格を9つ紹介しているため、自分の目指すべき姿が決まったら、ぜひ資格の取得にチャレンジしてくださいね。
あなたが心理カウンセラーとして働き始める前に、この記事を読んでキャリアの選択に活かしてください。
アドバイザーコメント
心理カウンセラーとして生計を立てるのは容易ではない
心理援助職は、「カウンセラーになりたい人の方が、カウンセリングを受けたい人より多い」といわれる状況にあります。
そのため、カウンセラー資格の認定講座や養成講座がビジネスとして盛んに展開されています。
学ぶ過程では、面白さや新たな発見があります。また、学んだことを自分の生活や現在の仕事に役立てられる要素もたくさん見つかるでしょう。
しかし、「心理カウンセラーとして生計を立てる」という視点で考えると、また別の現実が見えてきます。生計を立てるのは簡単ではないし、甘くもないのです。
自分でカウンセリングを受けて決断する方法もある
まずは、ご自身で心理カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。ドラマや漫画で描かれるイメージとはギャップがあるかもしれません。
調べてみれば、自治体が運営する無料相談所から、オンラインで個人事業として開業しているものまで、さまざまな相談機関が見つかるでしょう。
相談内容は、「心理カウンセラーになりたいという目標について話したい」で構いません。この記事を参考にするだけでなく、実際に複数のカウンセラーに会い、いくつかのカウンセリングを体験してから決断しても遅くはないでしょう。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi
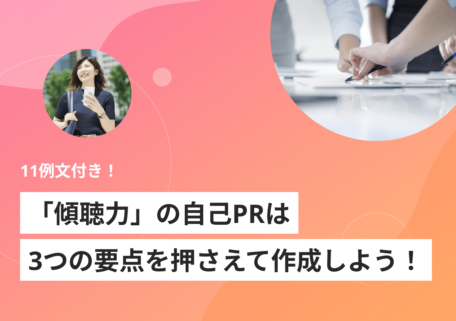


















3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/公認心理師
Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー
Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/メンタル心理カウンセラー
Syuya Nagata〇自動車部品、アパレル、福祉企業勤務を経て、キャリアコンサルタントとして開業。YouTubeやブログでのカウンセリングや、自殺防止パトロール、元受刑者の就労支援活動をおこなう
プロフィール詳細