この記事のまとめ
- 自己分析シートは自身の経験や価値観を効率よく整理するためのツール
- 目的ごとに適切な自己分析シートのテンプレを選ぼう
- 自己分析シートを作ったら企業選びや面接対策に活かそう
「自己分析をどうやって進めたら良いかわからない」「自分の強みや価値観が整理できない」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
そんな人は、自分の経験や感情を体系的に整理できる、目的別の自己分析シートを使うのがおすすめです。自己分析シートを活用することで、就活の軸となる価値観や強みを明確にできるため、自己分析をスムーズに進められます。
この記事では、キャリアコンサルタントの富岡さん、田邉さん、永田さん、 渡部さん、板谷さんとともに自己分析シートの基本的な役割から目的別の6つのテンプレート、具体的な作成手順まで詳しく解説します。
また、3万人以上の就職支援実績がある渡部さん、学生から社会人まで幅広い世代の就活相談を受けている板谷さんからは、実際のキャリア支援から見えた「自己分析シートを活用すべき人の特徴」や「就活の進み具合に応じたおすすめの自己分析シート」について教えてもらいました。
自己分析シートで自己理解を深めることで、理想の企業に出会える可能性も高くなります。就活を成功させたいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
1位:自己PR作成ツール
自己PRが思いつかない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
2位:志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
3位:WEBテスト対策模試
模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
4位:面接回答集60選
見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました
5位:逆質問例100選
面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています
【併せて活用したい!】
スキマ時間3分でできる就活診断ツール
①適職診断
たった30秒であなたが受けない方がいい仕事がわかります
②面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
自己分析シートとは? 2つの役割を説明
自己分析シートとは、自分の経験や価値観を整理するためのツールです。自己分析シートの役割を正しく理解することで、就活に向けた自己理解を深めやすくなるため、まずはその基本的な役割や効果を把握しておくことが重要です。
ここでは、自己分析シートの2つの役割について解説します。後に解説する6つの自己分析シートから自身に合ったものを選ぶためにも、まずは自己分析シートを使って何ができるのかを明確にしましょう。
プロのアドバイザーならこうアドバイス!自己分析シートを作成することで自分を客観視できる
就活生のなかには、自己分析にはシートを使わずに整理をしても同じと考えている人がいるかもしれません。たしかに、自己分析シートを使わなくても過去の経験を整理できる人もいます。
しかし、基本的に自己分析にはシートを使うのがおすすめです。すでに多くの就活生が使っていて、就活に必要な情報を無駄なく整理ができます。自分を客観視することも可能です。
シートなしで自己分析を進めると、常に自分と向き合うため客観的な視点が欠けてしまうことがあります。
客観的な視点が欠けると、自己分析の内容に一貫性がないことや具体性がないことに気づけません。すると、アピールしたいことが伝わらずにESや面接で選考落ちになってしまうケースがあります。
自己分析シートは就活の相談にも活用することが可能
また、OB・OG訪問や面接練習をするときにも自分の経験をシートで簡単に伝えることができ、つまりシートを作成するだけで就活の相談に活用することもできるのです。
自分の経験やアピールしたいことを客観視するためにも、自己分析シートを活用しましょう。
そもそも自己分析を初めておこなう場合は、こちらの記事も参考にしましょう。自己分析の正しいやり方やメリット、業界や企業選びに活かす方法を解説しています。
自分のことを簡単に整理できるもの
自己分析シートを使うことで、漠然とした自身の特徴やこれまでの経験をわかりやすく整理できます。普段の生活では、自分の価値観や強み、これまでの経験について深く考える機会は少ないため、いざ面接で「あなたの強みは何ですか」と聞かれても答えに困ってしまう人が多いものです。
そこで、自己分析シートを活用すると、過去の経験や感情の変化を項目ごとに書き出すことができ、自分の情報が視覚的に整理されます。
たとえば、自分史シートでは時系列に沿って経験を振り返ったり、モチベーショングラフでは感情の起伏を線グラフで表現したりと、頭のなかで混在していた情報を明確に分類することが可能です。
このように自己分析シートは、頭のなかで混在していた自身に関する情報を効率よく整理して、客観的に把握しやすくするツールなのです。
自分を多角的に知れるもの
自己分析シートには、さまざまな視点から自身を分析し、新たな一面を発見する役割があります。一人で自己分析をおこなう場合、どうしても同じような視点や思考パターンに偏り、自身の本当の特徴や可能性を見落としてしまうことがあるものです。
一方、自己分析シートには、それぞれ異なる分析の切り口が用意されているため、普段は気づかない自身の側面を発見できます。
たとえば、SWOT分析では強み・弱み・機会・脅威の4つの観点から、will・can・mustシートでは「やりたいこと」「できること」「求められること」の3つの視点から、多角的な視点で自分を見つめ直すことが可能です。
このように複数の角度から自分を分析することで、就活で活かせる新しい強みや価値観を見つけられ、より魅力的な自己PRや志望動機を作成できるようになります。
プロのアドバイザーはこう分析!就活は企業から見極められる場! 深い自己理解で選考通過につなげよう
学生時代の人間関係は、気の合う人間同士で付き合っていれば良く、互いの利害関係もそれほど大きくない関係であると思います。そのような環境では自分の強みや弱みを明確にしたりする必要もほとんどなく、ことさら自分をアピールする機会も少ないのではないでしょうか。
ところが就活では、自分がどのような人間で、過去の経験をもとに何を身に付けているかを具体的に聞かれることになります。企業は、ともに仕事をするにふさわしい人材を探しており、報酬に見合うだけの強みや適性を持つ人物かどうかあらゆる角度からあなたを分析しようとするのです。
自己分析シートがあれば深い自己理解で就活に臨める!
自己分析シートは、獏然と理解している自分自身のことについて、より明確に可視化してくれるツールであり、書類の自己PRや面接の質問など、あらゆる場面に有効な、自分についての情報を整理してくれます。
頭ではわかっているのになかなか説明できない、というような言語化能力に自信のない人、自分の強みといわれても特に思いつかない、というような人ほど、時間を取って考える機会を作り、しっかりシートに書き出してみてください。
4つの質問に答えるだけで自己PRが作成できます
自己PRは就活において必ずといっていいほど必要になります。自己PRが曖昧なまま就活がうまくいかなかったという就活生は多くいます。
そこで活用したいのが「自己PR作成ツール」です。これを使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
目的別で整理できる! 自己分析シート6選
目的別で整理できる! 自己分析シート6選
自己分析シートにはさまざまな種類があるため、自分の目的や知りたいことに合わせて適切なものを選ぶことが重要です。
ここでは、自己分析をおこなう目的別に、自己分析シートの例6選と作成手順を紹介します。それぞれの自己分析シートがどのような人に向いているかを理解して、自分に合った方法で自己分析を進めましょう。
①自分史:自分の経験を時系列で振り返りたい人向け

自分史
これまでの人生で起きたことを歴史の年表のようにまとめる手法
自分史は、自分の価値観や行動パターンを見つけたい人におすすめの自己分析シートです。
幼少期から現在までの経験を時系列で整理することで、自分がどのような場面で喜びを感じ、どんなときにストレスを抱えるのかといった傾向を客観的に把握できます。これにより、就活の軸を見つけやすくなるのです。
また、自分史の最大の特徴は、長期的な視点で自分を分析できることです。過去に起こった一つひとつの出来事は小さく見えても、時系列で並べることで自身でも気づいていなかった強みや一貫した価値観・性格が浮かび上がってきます。
ここからは、実際の作成手順を紹介していくので、一緒に作成を進めていきましょう。
自分史の作成手順
- 時系列に沿ってエピソードを書く
- エピソードの共通点を見つける
- 共通点から根底にある価値観や強み・弱みを見つける
作成手順1:時系列に沿ってエピソードを書く
自分史という名の通り、自分の歴史を表すもの、つまり年表を作るイメージです。まずは時系列に沿って起きた出来事を書きます。
書き出す際は、大変だったこと、頑張ったこと、うれしかったこと、悔しかったことなど、感情が大きく動いた経験を中心に選ぶのがポイントです。なぜなら、感情が動いた出来事ほど記憶に残りやすく、あなたの価値観や性格を反映している可能性が高いためです。
なお、完璧に思い出そうとする必要はありません。たとえば、「中学生のとき部活をがんばった」「高校で大学受験に挑戦した」といったように、まずは思いつくままに書き出してみてください。
作成手順2:エピソードの共通点を見つける
エピソードを洗い出したら、共通点を見つけます。たとえば、以下のように見つけ出しましょう。
ポジティブな出来事から共通点を見つける例
・クラスの文化祭リーダーとして準備をとりまとめ、その結果自分のクラスが表彰されたことがうれしかった
・大学で成績優秀者として表彰されたことがうれしかった
→共通点:自分の努力が評価されることがうれしい
ネガティブな出来事から共通点を見つける例
・高校時代親友と喧嘩し、1年くらい口を聞かない時期があり、ストレスだった
・大学のサークルで人間関係に悩まされ、4年間続けたもののストレスの種だった
→共通点:人間関係がうまくいかないとストレスになりやすい
このように複数のエピソードを比較して共通点を見つけることで、あなたが何を大切にして生きているのか、どんな状況で力を発揮するかが見えてきます。
また、共通点を見出そうとする過程のなかで、作成手順1で挙げたエピソードへの理解も深まっていくものです。だからこそ、ためらわずに印象的な出来事を書き出していきましょう。
作成手順3:共通点から根底にある価値観や強み・弱みを見つける
共通点を見つけ出したら、あなたの根底にある価値観や強み、弱みを分析し、キャリア選択に活かしましょう。
たとえば「努力が認められるとうれしい」という共通点があった場合、あなたは他者からの評価を重視する価値観を持っていると考えられます。この場合、個人の成果が明確に評価される職場環境や、頑張りが結果に直結する仕事が向いている可能性が高いです。
一方で、年功序列で努力が評価に反映されにくい環境では、モチベーションを維持しにくいと感じる場合もあります。このように価値観を明確にすることで、企業選びの軸を見つけられ、面接での自己PRにも活用できるようになります。
共通点から、根底にある価値観や強み、弱みを見つけ出し、そこからどのような仕事が合っているのか、どんなキャリアを描くべきかなどを考えましょう。
項目に沿って自分史を作っていくと、思考が巡り今まで忘れていた経験を思い出すことができます。
今までの出来事は、いろいろなことを学び、気づいた貴重な学習経験です。急いで完成させることを目指さず、じっくりとその時の様子、感情を思い出し、抽象化していきましょう。
ここまで自分史の作成方法と自分史を作成してわかることを解説しました。以下の記事では自分史を就活で最大限活かせる方法をまとめているので参考にしてみてください。
②モチベーショングラフ:自分の感情の動き方を知りたい人向け

モチベーショングラフ
人生の出来事に対する感情の変化をグラフで表す手法
モチベーショングラフは、自分がどんなときにやる気が出るかを知りたい人におすすめの自己分析シートです。
横軸に年齢、縦軸にモチベーションの上下を設定し、これまでの経験を点で表してつなげることで、感情の波を視覚的にとらえられます。これにより、自分の行動パターンや価値観を客観的に分析することが可能です。

また、モチベーショングラフの特徴は、感情の起伏に注目して自分を分析できることにあります。たとえば、同じような経験をした人がいても、人によってモチベーションの上がり方は異なるものです。
ここからはモチベーショングラフの作成方法を解説していきます。自己分析に活用したい人は、ぜひ参考にしてください。
作成手順1:モチベーションが上がる際の共通点を見出す
まずは横軸に年齢、縦軸にモチベーションの高低を表すグラフを作成し、これまでの人生で印象に残っている出来事を書き込んでいきましょう。
モチベーションが高かった出来事はグラフ上部、低かった出来事は下部に点を置き、それらを線でつなげることで感情の波が見えてきます。グラフが完成したら、モチベーションが高い出来事と低い出来事それぞれの共通点を探してみましょう。
モチベーションが高い出来事の共通点を見出す例
・中学時代に家族に海外旅行に行き、初めて触れる文化に刺激を受けた
・マーケティングゼミで現場に実地調査に行き、多くのことを学び刺激的だった
→共通点:新しいこと・刺激あること
モチベーションが低い出来事の共通点を見出す例
・中学時代の野球クラブチームで、厳しいながらも意味を見出せない練習が嫌になり辞めた
・高校時代、非効率な教師の指導に納得がいかず、学校に行かなくなる時期があった
→共通点:非合理で納得感がないことを強制されること
作成手順2:共通点から仕事に求めることを見つける
モチベーションが高い出来事と低い出来事の共通点を見いだせたら、それを踏まえた「仕事に求める条件」や「避けたい環境」を明確にしましょう。
たとえば、モチベーションが高い出来事の共通点が「海外に携わり、多くの刺激を受けられること」ならば、海外に挑戦する機会があったり、成長度合いが高く刺激を受けられる環境が合っているといえます。具体的には、新規事業に携わる機会がある企業や、海外展開している会社などが候補として挙げられます。
一方で、モチベーションが低い出来事の共通点が「非合理で納得感がないことを強制されること」であれば、古い慣習にとらわれた企業や、説明なく業務を押し付ける職場環境は避けるべきです。
このように分析結果を企業選びや職種選択に活かすことで、長期的にモチベーション高く働ける環境を見つけられます。
モチベーショングラフは、「落ち込んでいて何とかモチベーションを保ちたい時」にも活用すると良さそうです。
頭の中だけで考えていると、自分の人生のどんな出来事の時に気持ちの浮き沈みがあるのかということはわかりにくく、視覚化して分析することで合理的にモチベーションを保つことができるようになります。
以下の記事ではモチベーショングラフのさらに詳しい書き方をまとめています。就活への活かし方も解説しているので併せて参考にしてみてください。
③ライフラインチャート:やりがいを感じた瞬間を整理したい人向け

ライフラインチャート
人生で起こった出来事を可視化して、その時点での幸福度の変化をグラフで表す手法
ライフラインチャートは、自分がどんなときに充実感ややりがいを感じるかを知りたい人におすすめの自己分析シートです。
横軸に年齢、縦軸に幸福度を設定し、これまでの経験を振り返って感情の変化を線グラフで表現することで、自分にとって本当に大切な価値観や働く目的を明確にできます。

ライフラインチャートの特徴は、幸福度に焦点を当てて自分を分析することです。モチベーショングラフと似ていますが、ライフラインチャートはより深い満足感や充実感に注目します。
たとえば、人の役に立ったときや困難を乗り越えて成長を実感したときなど、心から「やって良かった」と思えた瞬間を整理できるため、仕事選びで重視すべき価値観を発見することが可能です。
作成手順1:幸福度が高い経験の共通点を見出す
ライフラインチャートを作るには、まず横軸に年齢、縦軸に幸福度を示したグラフを作成します。そして、これまでの人生で幸福感や充実感を感じた出来事を振り返って線グラフで表現しましょう。そのうえで、幸福度が高かった経験の共通点を探します。
幸福度が高い経験の共通点を見出す例
・吹奏楽部でコンクール金賞という1つの目標に向かって皆で頑張っていた時に充実感を感じ、実際に金賞を獲れた時はとても幸せだった
・大学時代、短期留学に行き、海外に多くの友達ができ、幸福感を感じた
→友人と切磋琢磨したり、楽しい時間を過ごせることが幸せ
また、幸福度が下がる環境を避けるために、幸福度が低い経験も分析しておくことが重要です。
幸福度が低い経験の共通点を見出す例
・中学時代、周囲と価値観が相容れず、信頼できる友人がいなかった
・大学時代のアルバイトで、社員の接し方がきつく、精神的な負担だった
→周囲の人と良い関係を築けない時に不幸を感じる
このように「幸福度」を軸に出来事を振り返ることで、自分のモチベーションの源が見てきます。単にエピソードを思い出すだけでなく、そこに共通するパターンや特徴を探すように意識してみましょう。
作成手順2:共通点から仕事に求めることを見つける
幸福感を感じるときとそうでないときの共通点を見出したら、社会人になってから充実感を感じられるように、仕事に求める条件を明確にしましょう。
たとえば「友人と切磋琢磨したり、楽しい時間を過ごせることが幸せ」と感じるのであれば、チームワークを大切にする企業文化や、社員同士の関係が良好な職場環境がある企業を探します。具体的な方法としては、会社説明会やOB・OG訪問で企業の雰囲気を確かめましょう。
一方で、「周囲の人と良い関係を築けない環境」で幸福度が下がる傾向があるなら、人間関係の風通しが良い会社かどうかを事前にしっかりと調べる必要があります。
このようにライフラインチャートの分析結果を活用することで、長期的に幸福感を持って働ける職場を選べるようになります。
ライフラインチャートを作成することで、入社後のミスマッチを防ぐことにつながります。過去に経験した幸福度が下がるエピソードと同じような経験をしそうな企業は、就職先として選ぶと幸福度が下がるため避けるべきです。
④SWOT分析:頻出質問の回答を考えたい人向け

SWOT分析
強み(Strength)・弱み(Weakness)・機会(Opportunity)・脅威(Threat)の4つの視点から物事を分析する方法。自己分析だけではなく、事業やビジネス戦略の立案にも使われる。
SWOT分析は、面接でよく聞かれる質問への回答を準備したい人におすすめです。ビジネスの世界でよく使われる分析手法を自己分析に応用することで、客観的かつ論理的に自分の特徴を整理できるため、説得力のある自己PRや志望動機を作成しやすくなります。
また、SWOT分析の特徴は、強み・弱みからなる内的要因と機会・脅威からなる外的要因の両方から自分を見つめ直すことができる点にもあります。ここからは、具体的な作成方法を解説していくので、手順に倣って作成を進めていきましょう。
作成手順1:「SWOT」の4つの視点から自分を分析する
SWOT分析では、4つの視点から自分を客観的に分析していきます。企業が経営戦略を立てるためにおこなうSWOT分析を、自己分析用に活用すると、以下の通りになります。
自己分析でおこなうSWOT分析
- 「S=strength」→自分の長所
- 「W=weakness」→自分の短所
- 「O=opportunity」→自分にとってプラスの機会
- 「T=threat」→自分にとってマイナスの機会
Opportunity(機会)やThreat(脅威)とは、それぞれ自分にプラス、マイナスに働く環境のことであり、自分だけの力ではコントロールできない社会情勢や業界動向などを指します。就活関連のニュースをチェックしたり業界研究をしたりしてから考えるとより見つけやすくなります。
これを踏まえたうえで、4つの視点をそれぞれ思いつく限り書き出してみましょう。
Strength(自身の強み)の例
・気配りができる
・チャレンジ精神がある
・明るい
・真面目
・コミュニケーション能力が高い
・英会話が得意
・プログラミングが得意
・体力がある
こちらの記事では、長所一覧表60選を紹介しています。効果的なアピール方法も解説しているので参考にしてみてください。
Weakness(自身の弱み)の例
・融通が利かない
・楽観的すぎる
・単純作業が苦手
・計算が苦手
・優柔不断
・集中力が続かない
短所はこちらの記事で見つけ方を解説しているので、併せて参考にしてください。こちらの記事を読めば、短所から長所を見つけることもできます。
Opportunity(自分にプラスとなる外的要因)の例
・売り手市場で内定が出やすくなっている
・副業が解禁されはじめている
・海外進出する企業が増えている
・リモートワークが幅広い業界で普及した
・志望する企業の新卒採用は学歴不問
Threat(自分にマイナスの外的要因)の例
・志望職種がAI(人工知能)の発達により採用人数が減った
・志望業界の市場が縮小している
・景気が不安定になった
作成手順2:4つの視点から合っている仕事を考える
SWOT分析で整理した4つの内容を組み合わせることで、自身に合った仕事や避けるべき環境を具体的に見つけられます。たとえば、強みと機会を掛け合わせれば自分が活躍できる分野、弱みと脅威を組み合わせれば避けるべき環境が明確になるため、より戦略的な企業選びがしやすくなるのです。
SWOT分析から合っている仕事を考える例
- 長所:チャレンジ精神がある×プラスの機会:海外進出が増えている
→海外でチャレンジできる環境にある仕事が合っている - 長所:行動力がある×短所:単純作業が苦手
→事務職などのルーティンワークを強いられる環境は避ける - 長所:創造力がある×マイナスの機会:変化が激しい時代
→変化が激しい時代にも活躍できるクリエイティブな仕事を選ぶ
このように多角的な視点から自己分析することで、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的に活躍できる環境を見つけやすくなります。
SWOT分析はマーケティング戦略として使われることが多くあります。まず、最終的な目的や目標があったうえで分析していくことが大事になってきます。
自己分析として使う際にも「自分が望む姿」を念頭においたうえで各項目を洗い出すことでより明確になるでしょう。
⑤will・can・must:好きを仕事にしたい人向け

will・can・must
やりたいこと(will)・できること(can)・求められること(must)」の3つの視点から自己分析する方法
will・can・mustは、好きなことを仕事にしたい人におすすめの自己分析方法です。この3つの要素が重なる部分を見つけることで、自身の興味関心と能力、社会のニーズが一致する理想的な仕事を発見しやすくなります。
また、will・can・mustの特徴は、主観的な「好き」だけではなく、客観的な「能力」と現実的な「需要」も同時に考えられることです。好きなことだけを追求すると現実離れした選択になってしまうケースがありますが、3つの視点を組み合わせることで実現可能性の高いキャリアプランを描けます。
ただし「好き」という感情を客観的に深掘りするのは簡単なことではありません。だからこそ、ここから紹介する作成手順に従って、正しいやりかたを身に付けていきましょう。
- 「will」のやりたいことがそもそもない場合はどうしたら良いのでしょうか。
canから考えてみよう
人には生まれつき自らの意志がありますが、成長するに連れて他人の意図を読むようになり、自分の意志に気づかなくなってしまうことが多々あります。
そんな時は、やりたいことを無理に探すのではなく、自分ができること、身につけてきたこと、強みを思い浮かべてください。
人にとっての天職はwill、can、mustの重なった部分と言われています。まず、canを考え自分の仕事の条件として何があるかを把握した後、その中で「できるけどやりたくないこと」は除外するようにしてください。消去法でやってもいいこと≒willが見えてきます。
天職については以下の記事で詳しく解説しています。天職に就きたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
こちらのQ&Aでは自己分析で「やりたいこと」を見つける方法を回答しているので参考にしてみてください。
作成手順1:「will・can・must」の3つの視点から自分を分析する
まずはwill・can・mustをそれぞれ思いつく限り書き出しましょう。ここでは制限を設けずに、自由に考えてアイデアをたくさん出すことが重要です。
will・can・mustの例
- Wil(やりたいこと)l:人を笑顔にする仕事がしたい、好きなデザインの小物に携わりたい、音楽に携わりたい、チームで協力して成果を出したい
- can(できること):料理、裁縫、幅広いジャンルの音楽の見識がある
- must(社会から求められること):グローバル化への対応、デジタル技術の活用、高齢化社会への対応
mustは社会のトレンドや課題を指し、SWOT分析の機会(Opportunity)や脅威(Threat)に相当します。現在社会が抱える問題や今後重要になりそうな分野を幅広く考えて書き出しましょう。
作成手順2:共通点から仕事に活かせることを見つける
will・can・mustを書き出したら、それぞれ重要だと思う項目を選んで組み合わせ、自分に合った仕事を見つけてみましょう。すべての要素を満たす仕事が理想ですが、まずは2つの要素が重なる分野から検討するのも効果的です。
will・can・mustの共通点から合っている仕事を見つける例
- 「will(人を笑顔にしたい)」×「can(料理が得意)」×「must(高齢化社会への対応)」
→介護施設での栄養士、シニア向け料理教室の講師 - 「will(音楽業界で働きたい)」×「can(コミュニケーションが上手)」×「must(デジタル技術の活用)」
→音楽配信サービスの企画職、アーティストのSNSマーケティング担当、音楽イベントのプロモーター
canだけでなくcannotも考えることがポイントです。cannotを把握すると「自分の課題・足りないことを自覚している学生」と高評価が得られます。
未経験で就職できる新卒だからこそcan以上にcannotを重視しましょう。
⑥ikigaiチャート:仕事を中心とした人生を送りたい人向け

ikigaiチャート
日本語の「生き甲斐」から名付けられた自己分析シート。「好きなこと」「得意なこと」「社会貢献になること」「お金になること」の4つの要素から人生の目的を見つけられる。
ikigaiチャートを使って4つの要素を具体的に考えることで、あなたの生きがいを見つけて、仕事と人生の充実感を両立できる理想的なキャリアを発見できます。
ikigaiチャートの特徴は、個人の幸福と社会貢献、経済的な安定とのバランス、すべてを考えられることです。will・can・mustと似ていますが、より「お金になること」を明確に分離している点が異なります。
好きで得意なことでも収入につながらなければ生活が困難になり、逆に収入は良くても好きでなければ長続きしません。持続可能で充実したキャリアを築きたいと考えている人は、ここから紹介する作成手順に倣ってシートを完成させましょう。
作成手順1:「生き甲斐」を見つける4つの視点から自分を分析する
分析の手順はwill・can・mustとほぼ同じです。まずは以下項目について、思いつく限り洗い出します。
ikigaiを考える例
- 好きなこと:体を動かすこと、映画鑑賞、読書、友人や知人と話すこと、分析や研究
- 得意なこと:人との会話、提案、戦略を立てる、人を笑顔にする
- 得たい報酬:都心で一人暮らしをしたいため、30代で最低でも年収500万円
- 社会貢献になること:人を笑顔にすること、人々の資産形成
仕事に関連しそうなものでも、そうでなくても、思いつく限り書き出していきましょう。
作成手順2:共通点から仕事に活かせることを見つける
4つの視点から分析できたら、そこからそれぞれの要素を組み合わせて、可能な限り条件を満たせる仕事を探しましょう。完全に一致する職業が見つからない場合は、3つの要素が重なる分野から検討するのも効果的です。
4つの視点から仕事に活かせることを見つける例
- 好きなこと「データ分析・人と話すこと」
- 得意なこと「問題解決・交渉」
- お金を稼げること「年収500万円以上」
- 社会貢献になること「持続可能な社会づくり」
→環境コンサルタント、再生可能エネルギー関連企業の営業職
このように4つの要素を掛け合わせることで、個人の充実感と社会貢献、経済的な安定をバランス良く実現できる理想的な職業を見つけられます。
さらに、自己理解を深めたい人は、以下の記事も参考にしましょう。自己分析に役立つ105の質問に回答して、書類選考や面接対策に備える方法を解説しています。
自己分析と併せて他己分析もおこなうことで、より正しく自己理解を深めることができます。こちらの記事を参考にしてくださいね。
プロのアドバイザーならこうアドバイス!自己分析シートを選ぶときは「自分の状況や考え」に合わせるのがコツ
上記で紹介している6つの自己分析シートが、それぞれどのような状況の学生におすすめできるのかについてお伝えします。
①自分史は、面接で自分のエピソードを語るのに思い浮かばない学生におすすめです。
②モチベーショングラフは、感情の動きを通して、強みや弱みを探ることができるので、自分の強みや弱みについてのエピソードを考えている学生におすすめします。
③ライフラインチャートは、職業選択の際に大切にする軸を探す学生におすすめです。
④SWOT分析は、自分自身を客観的にとらえて、就職活動全体の戦略を立てたい学生におすすめします。
⑤will・can・mustは自分自身について棚卸しをすることで、理想と現実について可視化することができるので、職種選択で悩んでいる学生におすすめです。
⑥ikigaiチャートは、自分自身の人生を大きくとらえて長期的なキャリアについて考えたい学生におすすめします。
自己理解を深めたいときには客観的視点も取り入れるようにしよう
自己PRなどで自分のことを記載する際に自己理解が必要な状況の学生には、「エレメンツコード」がおすすめです。
無料で自分自身の現在の性質や自分軸か他人軸かなどについて、全体から見た自分の位置についての詳細なレポートを受け取ることができるので、客観的に自分自身のことを把握することができるようになります。
コピペで使える自己PR文がかんたんに作れます
自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?ツールで実際に文章を作成してみてからブラッシュアップする方が効率的に受かりやすい自己PRを作成することができます。
「自己PR作成ツール」 を使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
自分を客観的に知るなら他己分析シートも使ってみよう

自己分析シートは、あくまで自分の視点から自身を分析するものであり、客観性に欠けるところがあります。そこで、他己分析も併せておこなえば、自分を多角的、客観的に知ることができます。
他己分析は、上の他己分析シートを使っておこないましょう。ジョハリの窓といい、以下4つの視点から分析します。
ジョハリの窓
- 開放の窓ー自分も他人も知っている自分の特徴
- 盲点の窓ー自分は気づいていないものの他人は知っている自分の特徴
- 秘密の窓ー自分は知っているものの他人が気づいていない自分の特徴
- 未知の窓ー誰からもまだ知られていない自分の特徴
友達や家族に、自分はどういう人だと思うか聞いてみましょう。できるだけたくさん伝えてもらいます。そのうえで、他者から言われた特徴と、自分が思っている自分の特徴をジョハリの窓の4つに分類してみてください。
ジョハリの窓で重要なのは、「開放の窓」にある項目を増やすことです。「盲点の窓」や「秘密の窓」が多い人は、上手く自己開示できておらず、日々葛藤を抱いている可能性があります。
仕事探しにおいても、開放の窓をたくさん開けるような環境に身をおける場所を探すことで、居心地の良い職場環境を手に入れられるのではないでしょうか。
アドバイザーのリアル・アドバイス!自己分析結果を他人に聞いてもらうことも有効な他己分析になる
あなたのことを知っている人に他己分析をお願いするときは上記のように、「私の強み、弱みはどこだと思う?それはなぜ?」と具体的なエピソードとセットで聞くようにしてください。自己PRでは必ず面接官を納得させる具体的な経験が必要になるので、ここで聞いた第三者の発言を含めることができると説得力が増します。
今まであまり一緒に何かをしたことがないという人にも他己分析をしてもらうことは可能です。
自分史や、モチベーショングラフ、ライフラインチャートを作成した後に第三者に自分の人生の物語を話し、聞いてもらいます。その後聞いてもらった人から再度あなたの人生を語り直してもらい、強みや弱みについて感想をもらいます。
第三者の視点から自分の人生に新たな気付きを得ることができる
こうすることで、自分では気づかなかったけれど、第三者の視点で感じた自分についてフィードバックをもらうことができます。
どうして語り直しをしてもらうかというと、人生を語る際にはたくさんある小さな出来事をつなぎ合わせて大きなストーリーを作るため、出来事の間に筋書きを加えています。
自分で語ることであなたが感じている自分の人生の意味に気づくことができ、語り直されることで相手が感じたあなたの人生のストーリーに気づきをもらうことができるからです。
テンプレを活用すれば受かる自己PR文が作れます
自己PRのネタを決めても、それを裏付けるエピソードに悩む学生は多いです。しかし、特別なエピソードがなくても受かる自己PRを作ることはできます。
そこで紹介したいのが「自己PR作成ツール」です。自己PR作成ツールなら、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、分かりやすいテンプレであなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
作った後が重要! 自己分析シートの就活での活かし方
自己分析シートは作成すると満足してしまうかもしれませんが、作成後にしっかりと就活に活かすことが肝心です。ここからは、自己分析シートの就活での活かし方を解説します。
ここで解説する内容を参考に、分析して終了にはせず、自己分析シートを就活の心強い友と言えるような存在にしましょう。
就活の軸を見つけ出してマッチする企業を選ぶ
自己分析シートを作成すると、いくつかのゆずれない条件が浮かび上がってくるのではないでしょうか。それは「就活の軸」といえ、それをもとに企業選びをおこなうと納得感のあるキャリアを見つけることができます。
「自己分析シートは使ったものの結局軸がわからない」「譲れない条件が何個もあって選べない」などと、自分で就活の軸を見つけるのが難しい人は、キャリアアドバイザーに相談してみましょう。完成した自己分析シートを見せることで、あなたの企業選びの軸を一緒に考えてくれたり、それに合う企業を紹介してくれます。
就職エージェントに登録したり、大学のキャリアセンターに行き、キャリアアドバイザーに相談してみてくださいね。
おすすめの就職エージェント
- キャリアパーク! 就職エージェント
年間1,000名以上に面談をおこなうアドバイザーが、豊富な経験をもとに、キャリアサポートをおこなう
もしくは、インターネットで、自己分析シートの結果に基づき条件を絞って検索するのも一つの手です。以下の就職サイトなどで条件を絞って検索してみましょう。
おすすめの就職サイト
自分に合う企業を相談したいなど、就活の相談先についてはこちらの記事で解説しているので、併せて参考にしてくださいね。
分析結果をもとに選考対策をする
自己分析シートの結果から、選考対策につなげることも可能です。たとえばSWOT分析では、以下の質問対策に活用できます。
SWOT分析を活かせる質問例
- 自己PR
- 志望動機
- 長所・短所
- 学生時代力を入れたこと
自己分析シートで自分の特徴やそれに付随するエピソードを洗い出しますが、それを踏まえれば選考では以下のようにアピールできます。
SWOT分析を自己PRに活かす例
SWOT分析
長所:チャレンジ精神がある×プラスの機会:海外進出が増えている
→海外でチャレンジできる環境にある仕事で貢献できる
→自己PRにすると……
私の強みはチャレンジ精神があることです。
私は大学時代、英語が苦手だったのですが、克服してさまざまなバックグラウンドを持つ人と話したいと考え、英語力を克服することを決意しました。
ただ、部活動が忙しく留学ができなかったため、留学生が参加している大学の授業に積極的に参加することにしました。
留学生の授業に参加する日本人は初めてということで、最初は教授から拒否されましたが、何度も依頼し参加させてもらうことができました。
そして留学生と積極的に交流することで、授業外の時間も一緒に過ごすことになり、最終的にTOEICの点数を400点から730点に伸ばすことができました。
御社に入社後も、チャレンジ精神と培った語学力を活かして、御社が積極展開されている海外進出などに貢献し、成長をけん引する存在となりたいです。
SWOT分析の結果から見つけた強みと機会をうまくストーリーとしてつなぎ、組み立てられていますね。
「留学生が参加している大学の授業」という表現が抽象的すぎるためもう少し授業の内容を補足できるとさらに良いです。
プロのアドバイザーならこうアドバイス!自己分析シートを活用して就活の軸を考えミスマッチを防ごう
就活の軸は、就職活動の成功を左右すると言っても過言ではないほど重要です。就活の軸が明確であれば、エントリーすべき企業だけでなく内定を承諾する企業の判断もできます。
しかし、就活の軸の考え方を教わる機会はないため、自信を持って考えることができない就活生も多いですよね。そのときに活用するものが自己分析シートです。シートを活用して自己分析ができていると、自分が重視したい環境や風土、ビジョンなどを簡単に把握することができます。
エントリー企業・入社する企業を選ぶ際に活用しよう
また、自己分析シートは重視したいことの優先度を考えやすい特徴もあります。
たとえば、自己分析シートから「1人で取り組んだ受験よりも、チームで取り組んだ部活の方が幸福度が高い」などとわかった場合、チームで働く体制があることを就活の軸に設定した方が良いですよね。
エントリー企業だけでなく入社先を決めるときにも自己分析シートを活用しましょう。
こちらのQ&Aでは、自己PR動画の効果的な締め方についてキャリアコンサルタントが解説しています。自己分析シートで自己理解を深めた内容を効果的にアピールするためにチェックしておきましょう。
自己PRが思いつかない人は、ChatGPTを活用して自己PRを完成させよう
ChatGPTを使った自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?
簡単な質問に答えていくだけでChatGPTが自動で魅力的な自己PRを作成します。
作った自己PRは選考で活用できるものになっているので、ぜひ活用して採用される自己PRを完成させましょう。
自己分析シートを作るときの5つの注意点
自己分析シートは簡易的に自分のことを分析できるシートですが、あることに注意しなければ役立ちにくいどころか、あなたの足を引っ張る存在にもなりえます。
ここからは、自己分析シートを作る際の注意点を5つ解説するので、参考にして気を付けつつ、効果的な自己分析シートを作成しましょう。
①一度作成して終わりにしない
よくあるのが、自己分析シートを作ったことに満足して、その後一切見ないというものです。自己分析シートの作成は就活を成功させる手段であり、活用しなければ意味がありません。
一度作成して終わりにはせず、選考対策や長期的なキャリアを考えることに活かしてくださいね。
自己分析シートは面接本番で活用することを意識しましょう。自己分析が甘いと、面接で質問された時にしどろもどろになってしまう可能性があります。
作成後は何度も読み返したり、友人に見せてフィードバックをもらったりなどして自己理解を深めると良いでしょう。
②企業が求める人物像を意識しすぎない
選考対策に活かすことを意識するあまり、企業の求める人物像に沿った内容にしてしまう人も多くいます。
たとえば、企業がチャレンジ精神がある人を求める人物像に設定している場合、自分の長所もチャレンジ精神があるとして書いてしまうケースです。
自己分析シートは自分のことを理解し、それをキャリア選択に活かすためのものであり、企業が求める人物像から逆算して作っているのでは本末転倒です。
納得感を持って企業を選び、入社するためにも、まずは企業のことを意識せず、素直な気持ちで自分を見つめましょう。
企業に気に入られたいがために相手の求める人物像を演じてしまうと、仮に内定をもらえたとしても入社後にミスマッチが起こり、お互いが苦しくなってしまいます。
内定をもらうことがゴールではありません。長い目で見て、幸せに働くためにも自分軸を見つけてください。
③短所もしっかりと見つけ出す
自己分析シートでよくあるのが、長所や強みなど選考でアピールになることに集中して分析してしまうことです。
もちろん長所なども重要ですが、短所も把握したうえでキャリア選択をしなければ、苦手なことを強いられる職場でつらい思いをするかもしれません。
また、選考でも「短所は何ですか」と聞かれることがあります。自分のことを客観視できる人材なのかを確かめるため、長所以上に重視する企業もあり、短所もしっかりと見つけ出しておくことが重要なのです。
短所を分析していないと、リスクを管理できない人材と判断されてしまい選考結果に影響する可能性もあります。
反対に短所を把握していることで、仕事上でのリスクも事前に把握できそうな人材というイメージになり、好印象です。
④業界・企業研究も同時におこなう
企業が求める人材像を意識しすぎないことが重要と解説しましたが、一定自己分析を進めたら、どんな業界や企業が合うのかを同時に調べていくことも重要です。
人はさまざまな面を持っているので、自己分析には終わりがありません。企業研究を進めるうえで、違和感を感じたり、わくわくしたりとさまざまな感情を持つのではないでしょうか。そこで、新たな自分を発見し、さらなる自己理解につながるのです。
さらに、業界、企業理解を進めたうえであれば、自己分析シートも効率的に作成できます。たとえばSWOT分析やikgaiチャート、will・can・mustでは、それぞれ社会から求められていることを分析すると解説しましたが、これを「志望業界・企業が社会から求められていること」とすると、考えやすくなりますよね。
- 業界・企業研究と自己分析はそれぞれどんなタイミングでやっていけばよいのでしょうか。
ある程度企業調査してから自己分析をすると精度が高まる
業界・企業研究と自己分析、どちらが先でなければいけないということはないと思います。
ですが個人的には、興味がある企業をある程度先に調査しておくと良いのかなという印象です。
会社説明会やOB・OG訪問などで、会社の人から直に聞いた情報が頭に入った状態で自己分析にとりかかった方が、自分に本当にあっている企業がどこなのかということがイメージしやすくなるのではないかと思っています(自己分析するなかで「自分の長所はこうだからあの会社が良いかもな」といった具合に)。
すぐに誰でも知ることができる企業理念や給与などのデータよりも、生の声や意見を聞いてからの会社選びでは自己分析および職業選択の質も変わってくることでしょう。
⑤分析結果を具体的な言葉で語れるようにする
自己分析シートで見つけた自身の強みを選考で効果的にアピールするためには、具体的なエピソードとセットで語れるようにすることが重要です。採用担当者は多くの学生と接するため、「責任感がある」「コミュニケーション能力が高い」といったありふれた表現だけでは印象に残りにくく、あなたの魅力を十分に伝えられません。
たとえば、自己分析で「人を支えることにやりがいを感じる」という自身の価値観を見つけた場合、「同じ部活の後輩からの相談に乗り続けた結果、退部を考えていたメンバーが最後まで活動を続けられた」のように、具体的なエピソードを用意しましょう。
このように、分析結果と実体験を結びつけることで、説得力のある自己PRを作成できるため、採用担当者にあなたの人柄や能力をアピールしやすくなります。
面接でキャリアビジョンを聞かれてうまく回答できない人は多いと思います。以下の記事ではキャリアビジョンについて詳しく解説しているので参考にしてみてください。
自己PRで悩んだらまずは作成ツールを使ってみよう!
「自己PRがうまく書けない」「どんな強みをアピールすればいいかわからない」…そんな悩みを抱えている方には「AI自己PR作成ツール」がおすすめです。
AIがあなたの経験やスキルに基づいて魅力的な自己PRを自動で生成し、短時間で書き上げるサポートをします。
短時間で、分かりやすく自分をアピールできる自己PRを完成させましょう。
そもそも自己分析って何のためにする? 自己分析の3つの目的
自己分析の3つの目的
- 自分の適性や強みを知るため
- 今後のキャリアを明確にするため
- 選考の通過率を上げるため
ここまで自己分析シートの作り方や活用方法を解説しましたが、「そもそも就活に自己分析ってどれくらい重要なのだろう?」と考える人もいるかもしれません。自己分析をやらずに就活を進める人もいますが、いつか必ず行き詰まってしまいます。
ここからは、自己分析の目的を3つ解説します。ここから解説する内容を参考に、そもそもなぜ自己分析をするべきなのかを明確化して、自己分析シートを作成する目的意識を持ちましょう。
自己分析はノートを使ってやることもできます。以下の記事では自己分析ノートのやり方と就活での活用法をまとめているので参考にしてみてください。
転職活動においての、自己分析ノートの作成方法については、以下のQ&Aで紹介しています。あわせて読んでみてください。
①自分の適性や強みを知るため
就職活動とは、自分に合う会社を見つけ、入社するための活動ですよね。自分に合う会社を見つけるには、まずは自分のことを理解する必要があります。
自分の適性や強みを理解していなければ、本当に自分にマッチしているのかわからないまま入社することになり、後悔するかもしれません。
就職活動をはじめ、人生は選択の連続です。たくさんある選択肢の中から自分が納得し、幸せになる選択をするためには自分自身の適性や強みを知っていることが重要となります。
人に決めてもらうのではなく自信を持って自己決定するために自己分析を進めていきましょう。
②今後のキャリアを明確にするため
自己分析とは、過去や現在の自分から将来の自分を描くものです。つまり、どんな社会人になりたいのか、今後のキャリアを明確にすることができるといえます。
なりたい社会人像がわかれば、どんな会社に入社すべきなのか、入社後は何を目的に業務をするべきなのかが見えます。
現在は終身雇用制度を見直したり、導入しない企業も増えており、会社の判断に任せるのではなく、自身でキャリアを考え、主体的に構築する必要があります。
今後のキャリアを明確にするなら、まずは自分自身を理解したうえで、方向性を定める必要があるのです。つまり、今後のキャリア構築のためには自己分析が最重要であるわけです。
自己分析を通してキャリアを明確にすることで、自分のキャリア選択への納得感が生まれます。
実現したいことが明確になると、壁を乗り越える原動力になり、大きく成長するきっかけにもなりますよ。
キャリア形成の重要性はやり方は、こちらの記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてくださいね。
③選考の通過率を上げるため
選考では、自己分析ができていなければ説得力のある回答ができません。たとえば以下の質問です。
自己分析ができていなければ回答できない質問の例
- 自己PRをしてください
- 志望動機を教えてください
- 学生時代力を入れたことは何ですか
- 長所・短所は何ですか
そしてこれらの質問は、面接で必ずと言って良いほど聞かれます。たとえこの質問自体にはうまく答えられたとしても、その後の深掘り質問に対応できずに、納得感を残すアピールができなくなってしまうでしょう。
選考通過率を上げ、希望の企業に就職するためにも、自己分析は重要なのです。
ただ、自己分析がうまくできていなくとも、真摯に向き合おうと努力した姿が見られれば、大きく印象が変わらない時もあります。
2つの視点から分析してみよう! 自己分析のパターン
自己分析=自分を分析するということですが、分析の着眼点がわからなければ効果的な結果は得られません。自己分析に重要なのは2つの視点であり、これを意識することで、偏りなく自身を分析することができます。
ここからは、その2つの視点を解説するので、これを念頭に自己分析シートを作成していきましょう。
他者との比較
客観的な視野で分析するために、他者との比較が有効になります。周囲から褒められること、周囲よりも得意だと思うことなど、他者と比較し、自分がどのような人間か考えてみましょう。
自分を多角的に分析できるよう、あらゆる人を思い浮かべることがポイントです。距離感が近い・遠い人、異性・同性、昔・今の親友などバラエティを持たせ、10人程度と比較すると自分のさまざまな面が見えてきます。
そしてあらゆる他者と比べるなかで、共通する自分の特徴が見つかるのではないでしょうか。たとえば、行動力が誰よりもあると思えば、それがあなたの強い個性です。
- 他人と比較して優れていると思うところが一個もありません……。
周囲から影響を受けていることを洗い出してみよう
日本の子どもの自己肯定感は先進国最下位と言われているので、自分には優れているところがないと感じる人も多いかもしれません。しかし、それはあなただけではなく日本人の特徴とも言えます。
優れている点が思い浮かばないのであれば、周りの人から影響を受けて実践していることを考えてみましょう。
どんなところが素敵だと思ったか、どうして自分も真似してみようと思ったかを深掘りしていくと自分という人間が大切にしたいもの、ありたい姿が見えてきます。
自分のなかでの比較
他人との比較のみでは、見つけられない自分の特徴は多々あります。そこで、自分のなかで特徴を比較することも重要です。
たとえば、「人と何かをするよりも1人でコツコツと取り組むことが得意だ」「1つのことに集中するよりもマルチタスクの方が合っている」など、これまでの経験から、自分のなかで比較しましょう。ここでは、他人よりも優れているかなどは考える必要はないのです。
そして、自分のなかでの比較と、他人との比較を組み合わせることで、多面的に自分を理解することができます。
- 器用なタイプで、何でもできるので逆に自分の中で比較して強み弱みを見つけるのが難しいです。
過去の成功体験から強みを考えよう
自分の中での比較が難しいと感じる就活生は、過去の成功体験から自己分析することがおすすめです。成功をするためには強みを発揮しているため、あなたがアピールできる強みを見つけるきっかけになります。
たとえば、TOEICで高得点を取った成功体験があるのであれば、「コツコツと継続すること」や「学習の計画を立てること」などが見つかりますよね。
このように過去の経験を比較することで自己分析することも良い方法です。
自己分析シートで新たな自分が見つかる! 納得のいく企業選びに役立てよう
自己分析が大切だとはわかっていても、ES作成や面接対策に追われて、なかなか時間をかけられないというのが実際のところでしょう。
そこで、自己分析シートを使うと、自身の特徴や価値観が明確になり、効率的に自己理解を深められます。この記事で解説した6つのシートは、それぞれ異なる視点から自分を分析できるため、目的に合わせて使い分け、これまで気づかなかった強みや価値観を発見しましょう。
ただし、自己分析シートを作成するだけでは、就活で十分に活用することはできません。分析結果をもとに企業研究をおこない、自身に合った職場環境や仕事内容を見極めることが就活を成功させるために重要だといえます。
また、自己分析シートで見つけた自身の強みや価値観を具体的なエピソードとともに語れるよう準備することで、説得力のある自己PRや志望動機を作成することも可能です。
自己分析シートをしたうえで自身が納得のいく企業を選び、やりがいのある仕事に就ける環境を探しにいきましょう。
アドバイザーからあなたにエールシンプルに「自分のことを深く知る」視点で工夫して自己分析しよう
自己分析シートには難しいフォーマットもあり、特に初めて取り組む人は混乱してしまうかもしれませんが、自己分析とは言わば「自分のことをもっと深く知りましょう」ということです。それほど難しく考える必要など全然ありません。
自分でできそうであればオリジナルな方法で自己分析しても良く、上記で紹介している方法を取り入れて全部試してみるのもありだと思います。
分析結果はあくまで参考であり前向きに就活を進めよう
よく自己分析の結果を通して落ち込んでしまう人もいます。ですが、注意すべき事は「今の自分の姿」であり、分析結果があなたの全てではありません。
その結果を踏まえてこれから成長し、全く違う価値観や心のあり方に出会う事だってあります。また、自身のこれからのキャリアに変化をもたらすことだってできます。
学生の皆さんにはまだまだどんな可能性だって広がっています。
自己分析結果に一喜一憂せずに、まずは今の自分と向き合って就職活動に取り組んでほしいと思います。
忙しい日々の生活の中での自己分析は大変かと思いますが、満足のいく自己分析ができることを祈っております。頑張ってください!
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

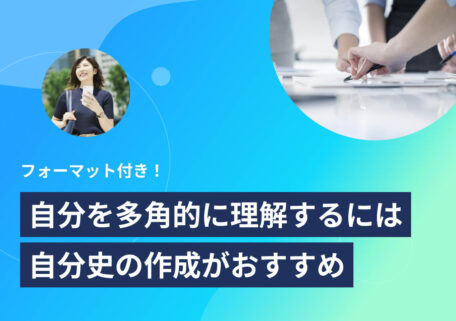





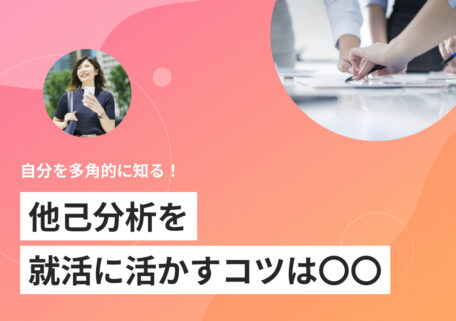
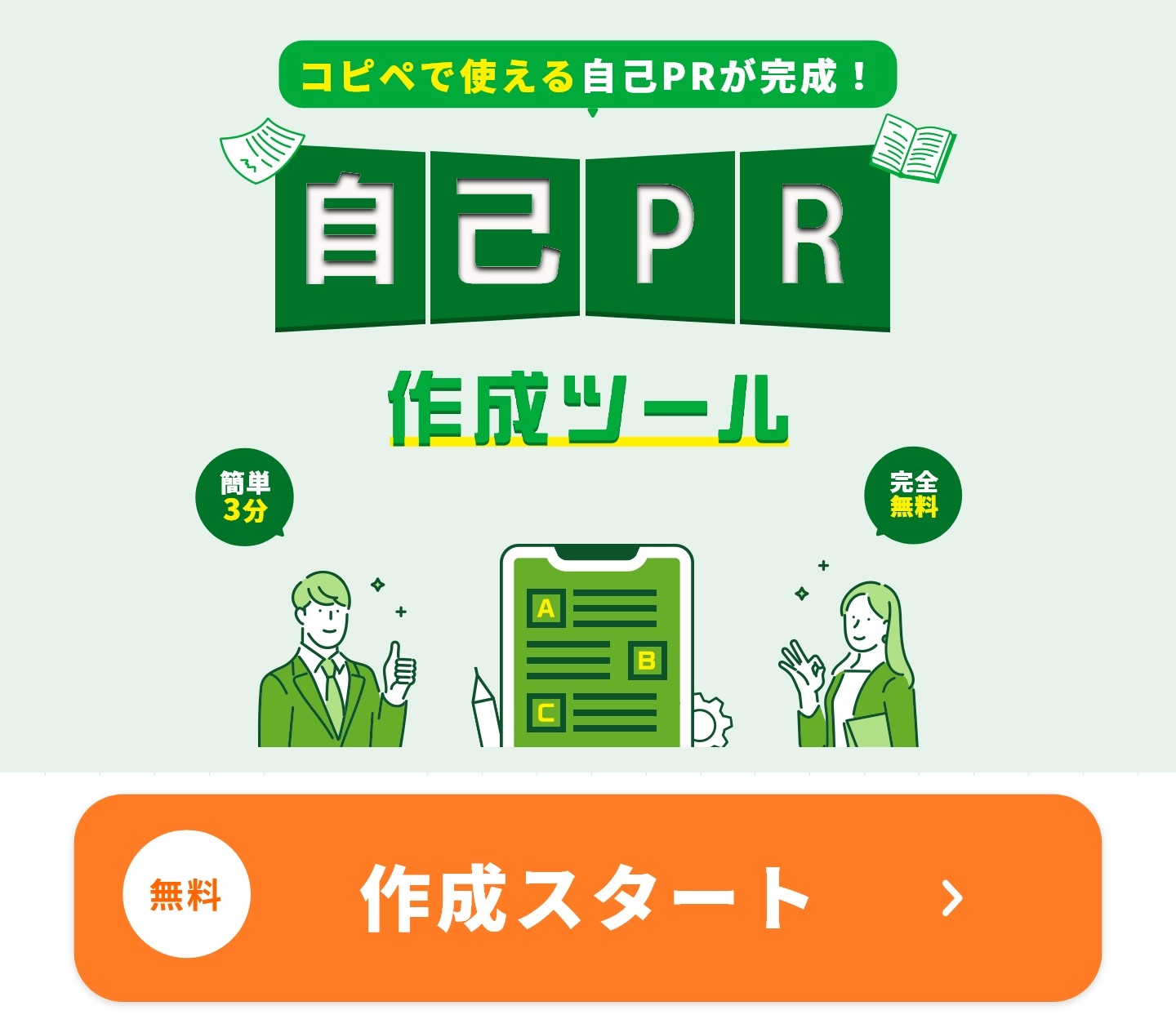


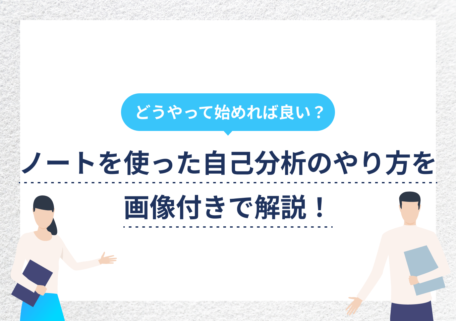


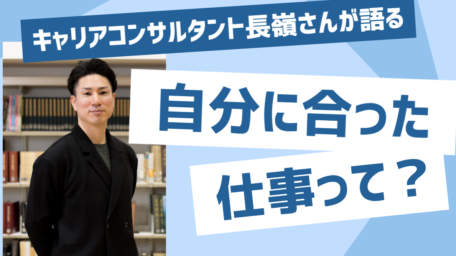

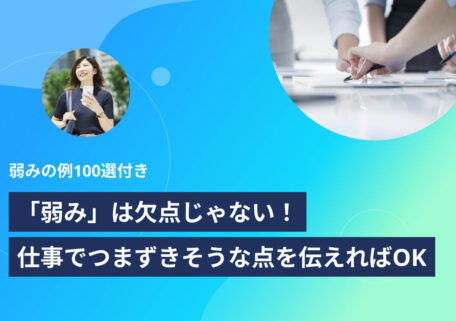







5名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/産業カウンセラー
Junko Tomioka〇南箕輪村のキャリア教育推進コーディネーターに就任後、独立。現在は地方中高生やベトナム人留学生の就活支援、企業内キャリアコンサル、地方就職のサポートをおこなう
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/なべけんブログ運営者
Ken Tanabe〇新卒で大手人材会社へ入社し、人材コーディネーターや採用、育成などを担当。その後独立し、現在はカウンセリングや個人メディアによる情報発信など幅広くキャリア支援に携わる
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/メンタル心理カウンセラー
Syuya Nagata〇自動車部品、アパレル、福祉企業勤務を経て、キャリアコンサルタントとして開業。YouTubeやブログでのカウンセリングや、自殺防止パトロール、元受刑者の就労支援活動をおこなう
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/合同会社渡部俊和事務所代表
Toshikazu Watanabe〇会社員時代は人事部。独立後は大学で就職支援を実施する他、企業アドバイザーも経験。採用・媒体・応募者の全ての立場で就職に携わり、3万人以上のコンサルティングの実績
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/コラボレーター代表
Yukari Itaya〇未就学児から大学生、キャリア層まで多様な世代のキャリアを支援。大企業からベンチャー、起業・副業など、幅広いキャリアに対応。ユニークな生き方も提案するパーソナルコーチとして活躍
プロフィール詳細