この記事のまとめ
- ノートを使った自己分析のやり方4選を紹介
- 自己分析ノートを作るなら、目的に合わせて作成を進めよう
- 自己分析ノートの結果はキャリア形成にも役立つ
自己分析は、就活の方向性を確認する重要な作業です。しかし、重要さは理解していても、「ノートで自己分析をする方法がわからない」「自己分析でノートを使うなら何を書けば良いの?」と悩んでいる人もいるでしょう。
自己分析ノートは目的に沿ったやり方と手順を押さえれば簡単に作成できます。作成した自己分析は志望業界や企業の選定だけでなく、自己PRなどのアピールにも有効になるため、目的を決めてノートを作り、選考を突破して内定につなげましょう。
記事では、学生の自己分析を日々サポートしているキャリアコンサルタントの富岡さん、井上さん、楳内さん、高尾さんのアドバイスを交えつつ、ノートを使った自己分析のやり方について解説します。
また、新卒から管理職クラスまで幅広い層のキャリア相談に対応している高尾さんに、自己分析でノートを使うメリットや、ノート作成のポイントについて聞いてみました。ノートを使った自己分析を始めてみたいという人は、ぜひ参考にしてくださいね。
この記事を読んでいる人の中で、転職活動での自己分析ノートのやり方について知りたい人は以下のQ&Aも読んでみてください。キャリアコンサルタントがアドバイスしているので参考にしてみてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:自己分析ツール
選考で使えるあなたの強み・弱みがわかります
3位:面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
4位:内定者ES100選
大手内定者のESが見放題!100種類の事例から受かるESの作り方がわかります
5位:WEBテスト対策問題集
SPI、玉手箱、TG-WEBなどの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
特徴も解説! ノートを使った自己分析のやり方4選
特徴も解説! ノートを使った自己分析のやり方4選
- 自分史:自身の興味・関心の方向性がわかる
- モチベーショングラフ:価値観や考え方に気付ける
- マインドマップ:思考を整理してアイデアを広げられる
- Will・Can・Must:自分に合ったキャリアを見つける参考にできる
自己分析は「興味や価値観を把握したい」「キャリアプランを明確にしたい」などさまざまな目的で作成します。特にノートを使うことで、自分の特徴を整理しやすくなり、考えをまとめながら客観的に見直すことができます。
ここでは、自己分析で知りたい内容にあわせて、ノートで自己分析を進めるやり方を4つ紹介します。それぞれの自己分析で特徴が異なるため、自分に合った方法で取り組んでみてくださいね。
①自分史:自身の興味・関心の方向性がわかる

自分史とは、自身の半生を振り返り、自己理解を深めるのに効果的な手法です。過去から現在までの印象的な出来事や経験を時系列に沿って記載することにより、自分という人物を客観的に見ることができ、興味や価値観の方向性が理解できます。
自分史を作成するときには、過去の具体的なエピソードを把握しておくことが重要です。ノートで、自分史を作るページとは別に、過去の経験や思いを書き出すだけのページを作ってみると、エピソードの整理がしやすくなります。
まずは必要な要素を洗い出し、自分史を完成させるための準備をしましょう。
作成した自分史から見えてくる自分の価値観や強みは、選考でのアピール材料にもなります。さらに、どのような出来事から強みが形成されたのかを具体的なエピソードを交えて伝えることで、より説得力のある自己アピールができますよ。
- 年代ごとに分ける際、どの程度細かく分けるのが良いでしょうか?
近い過去ほど細かく分けて具体的に振り返るのがおすすめ
年代ごとに分ける場合、小学生・中学生・高校生・大学生の4つで分けるのが一般的です。
1年ずつ分けても問題ありませんが、かなりの時間と労力が必要となるので、まずはこの4つをベースに考えていくと良いでしょう。
4つの年代の中でも、大学時代のエピソードは就活において最も質問される回数が多く、記憶にもはっきりと残っていると思います。そのため、あえて大学時代のみ1年ずつに分けて、具体的に振り返ってみるのも有効ですね。
自分史の書き方をさらに詳しく知りたい人は、こちらの記事がおすすめです。記入例付きでポイントを解説しています。
②モチベーショングラフ:価値観や考え方に気付ける

モチベーショングラフは、過去の経験や出来事を振り返り、それらが自分のモチベーションにどのように影響を与えたかを可視化する手法です。このグラフを作成すれば、自分の価値観や考え方について新たな気付きを得られるでしょう。
モチベーショングラフを書くときは、ノートを横向きに使うことがおすすめです。横長に使うことで、年齢の軸を長く取れるため、多くの出来事を書き込めます。
また、2色のペンを使って、モチベーションの高い・低いを目立たせる、テーマ別に経験を書くなど、視覚上の工夫を凝らすことも良いでしょう。
前述の自分史と組み合わせれば、書いた出来事に対してどのような環境や条件下でモチベーションの上下が起きていたかを判断できます。
また、面接では長所や短所、自己PRなどが質問されますが、モチベーショングラフでその根拠となるエピソードを整理できていれば、より具体性のある回答ができるでしょう。
過去を振り返るという点では自分史と似ていますが、感情の起伏によって自身の向いている環境が判断できるのはモチベーショングラフの強みといえます。
- モチベーションの上下を振り返ることのメリットがいまいちわかりません……。
自分の気持ちがプラスにはたらくポイントが仕事選びの基準の一つになる
モチベーションの上下を振り返ると、自分がどんなときにやる気を感じるか、幸せを感じるかなどに気付くことができます。そこから自分が仕事で大切にしたい価値観を考えていくこともできるのです。
「なにか一つのものを極めるときにモチベーションが高くなる」
「人と一緒に頑張るときにモチベーションが高くなる」
「目標をクリアすることにモチベーションが高くなる」
などが見えてくるとどのような仕事に就けばやりがいを持って働くことができるかわかり、それを仕事選びの基準の一つとすることができます。
モチベーショングラフの書き方にはコツがあります。こちらの記事でテンプレとともに具体的な手順を解説しているので、併せて参考にしてください。
モチベーショングラフは「人生曲線」と呼ばれることもあります。こちらのQ&Aでもキャリアコンサルタントが書き方のコツを解説しているので、併せてチェックしてみましょう。
③マインドマップ:思考を整理してアイデアを広げられる

マインドマップとは、1つのテーマを決めて自分の考えやアイデアを書き出して視覚化し、思考を整理する自己分析手法です。最初に決めたテーマから考えをどんどん深掘りしていくため、アイデアを広げられます。
たとえば、「自分」がテーマならノートの中心に「自分」と書き、得意なこと、頑張ったこと、苦手なことなど、自分について思いつくことをその周辺に書いていきましょう。そこからさらに派生させていけば、具体的な特徴が明確になります。
さらに、思いついたことがあれば追加で情報を足していけるため、アイデアを幅広く集められるでしょう。
言語化が難しいときは絵やイメージ図で書き出しておくと、後で見たときに考えを再現しやすくなります。就活でやりたいことを見つけたいときや苦手なことを知りたいときなど、自身の考え方を深掘りする際にマインドマップを試してみましょう。
考えやアイデアがなかなか思いつかない人は、以下の記事がおすすめです。自己分析に必要なあらゆる質問が分野別に紹介されています。
④Will・Can・Must:自分に合ったキャリアを見つける参考にできる

Will・Can・Mustでは、以下のポイントに考えを当てはめることで、自身の将来に向けた目標の手がかりを見つけられます。
Will・Can・Mustの意味
- Will:やりたいこと
- Can:できること
- Must:しなければならないこと
Willでは自身が実現したいことや興味があることを書き出します。Canで現在持っている能力やスキルを基にできることを書き、Mustでは目標に向けて必要な行動や取り組みを書きましょう。
3つそれぞれの関係性を探り、一致する部分があれば自分にとって最適なキャリアの可能性が高いです。また足りない部分があれば、克服することで新たな可能性にもつながりますよ。
ノートでWill・Can・Mustを整理するときは、画像のようにベン図を使う方法、もしくは表形式で作成する方法がおすすめです。ベン図であれば、見開き2ページを使って円を作成することで、3つの要素が重なる部分が認識しやすくなります。
一方、表形式で作成する方法であれば、1ページを3分割してWill・Can・Mustを縦軸に置き、横軸でそれぞれの要素を書き込んでいきましょう。
ベン図よりは視認性が下がるものの、手早く書き出すことができます。要素別に色分けをしてみると、要素の重なりも見出しやすいでしょう。
将来の目標(Will)が明確な人でも、CanとMustを言語化することで、自己実現に向けてどんなスキルや経験が必要かを明確にすることができるため、長い目でみた自分のキャリアに合った業界・企業選びに役立ちます。
ほかにも自己分析に使える手法がいくつかあります。こちらの記事でフォーマット付きで紹介しているので、併せてチェックしてみてください。
アドバイザーのリアル・アドバイス!自己分析はノート1冊で「行動」につなげることがカギ
私のおすすめは、1つのプロジェクトごとにノート1冊を使い、1つの手法やアイデアは見開き1ページでまとめて完結させるやり方です。具体的には、左ページに図を描き、右ページに要約を書くという構成にします。
左ページには、自分史・モチベーショングラフ・マインドマップ・Will/Can/Mustなど、テーマに応じた図を使って思考を可視化します。そして右ページには、「事実/解釈/強み/弱み/次の行動」の5行で要約を書き、気づきを整理します。
このセットを繰り返していくことで、自分の気づきを具体的な行動につなげることができ、結果として面接で語れるエピソードの材料にもなるのです。
実際、紙のノートで行うメリットも多く、たとえば以下のような点が挙げられます。
①手で書くことで、記憶に残りやすく、感情も乗りやすい
②ノートを見開いたときに全体像が一目でわかり、俯瞰や関連付けがしやすい
③思考の流れが時系列で残るため、後から具体例として見返しやすく、面接準備にも役立つ
このように、ノートを使って「見える化」しながら整理していくことで、自分の強みや成長のプロセスが言語化され、アウトプットにつながりやすくなります。
定期的な更新が効果的! 複数の手法で自分を見つめ直そう
そのなかで、どの自己分析をおこなうかは、効用を理解したうえで決めることがおすすめです。たとえば、自分史では「何に興味を持ち続けてきたか」や「どんな転機があったか」といったパターンを見つけることができます。
モチベーショングラフは、自分のエネルギー源や逆に消耗してしまう要因を視覚的に捉えるのに効果的です。マインドマップを使えば、自由な連想から思考を広げたり、これまで気づかなかった盲点を発見できます。
また、Will/Can/Mustでは、「自分がやりたいこと(Will)」「できること(Can)」「求められること(Must)」の重なりを見つけることで、意思と市場性のバランスを客観的に確認できるのです。
これらの手法を定期的におこなったうえで、月に1回程度を目安に「統合ページ」を作成することをおすすめします。このページでは、4つの手法から共通して見えてきたキーワードの中から上位3つを抽出し、それをもとに翌月の行動目標を立てるようにします。
たとえば、「新しい観点で自己分析してみる」「自己分析で見つけた課題を行動に移す」といった目標です。
こうしたサイクルを取り入れることで、自己分析が単なる振り返りではなく、動きのある計画として機能し、より実践的な自己理解につながっていきます。
自己分析ツールを使って、自分の長所と適職を確認しましょう
「なんとなく」で進める就活は、後からミスマッチに気づくことも。大事なのは、自分の強みや適職をきちんと理解しておくことです。
「自己分析ツール」を使えば、あなたの長所・短所、そして向いている働き方まで一目で整理できます。
後悔のない就職活動のために、今すぐ診断を始めましょう。
・自分に合った適職がわからない
・時間をかけずに自己分析をしたい人
自己分析ノートで整理したい3つのこと
自己分析ノートで整理したい3つのこと
- 現在: 自身の基本的な性格や考え方
- 過去: これまでに印象的だった出来事
- 将来: これからの人生で実現したいこと
ここまで、自己分析の目的別におすすめの手法を紹介しました。しかし、いざ書き出そうと思っても、何から手を付ければ良いかわからない人もいますよね。
自己分析をスムーズに進めるためにも、まずは自己分析で整理したいポイントを認識することから始めましょう。ここからは、自己分析ノートでまず整理したい3つのことを解説します。
この3つを意識して取り組むことで、必要な情報を取りこぼすことなく、自己分析を進めることができます。
現在: 自身の基本的な性格や考え方
自己分析では、現在の自身の基本的な性格や考え方を理解しましょう。性格や考え方など、特徴を知ることは、将来的に自分に合った業界や企業を選ぶときの基準になります。
たとえばチームワークを大事にする性格を理解できれば、企業へのアピールにつながるうえに、自己PRに深みを持たせられます。
現在について知るには「自分史」や「モチベーショングラフ」がおすすめです。過去の経験を含めて分析することで、現状の自分がどのように構築されたのかがわかります。
もし特徴の把握が足りなければ、自分に合った業界や働き方が不明確なまま就活を進めることになり、途中で迷いが出るかもしれません。未来の目標の土台が固まるので、まずは基本的な性格や考え方を把握しておきましょう。
働くうえで、人とのかかわりが不可欠です。周囲と良好な関係を築いていくために、まずは自分のことを理解し、相手に対してどう行動していくのかを考えることが重要になります。
企業は、応募者が自己理解している性格や考え方によって、入社後に活躍してくれる人材かどうかを見ているのです。
自己PRの考え方がよくわからない人は、こちらの記事で確認しておきましょう。例文7選付きで書き方を解説しています。
過去: これまでに経験した挫折や印象的な出来事
前述した現在の性格や考え方は、過去の経験があってこそです。過去に挫折したことや印象的な出来事を分析すれば、自己成長したきっかけを発見できます。
挫折から立ち直った経験や考え方を洗い出せば、困難な状況をどのように乗り越えるのか、自分が持っている強みをアピールできます。
さらに、印象的な出来事から何を感じ取ったかを明確にすれば、自身がどのような環境下で感情が左右されるのかを把握できるでしょう。
ほかにも、幼い頃はどんな子どもだったか、これまでの人生でどんなことを頑張ってきたのかなど、さまざまな経験から自身の特徴を分析するのに役立ちます。
過去の経験を整理するには「自分史」と「モチベーショングラフ」を2つ同時に作成するのが効果的です。出来事を洗い出しながら感情を分析して、現在の自分がどのように構築されたかにつなげましょう。
過去の分析では、生まれたときから順を追って振り返るのがおすすめです。小さい頃は内気な性格だったが、小学生で始めたスポーツの経験によって外交的な性格になったなど、ターニングポイントに気付くことができます。
昔のことがなかなか思い出せないという人は、直近の記憶をたどって書いていってもOKです。
過去の挫折経験を振り返るコツは、こちらの記事で解説しています。併せて参考にしてみてください。
将来: 仕事と人生で実現したいことや大事にしたいこと
自己分析は過去を振り返るものと思われがちですが、実は将来について考えることも重要です。仕事だけでなくプライベート面も含めて、理想の将来像や実現したいことを考えてみましょう。
それをかなえるため、これからどんな経験やキャリアが必要なのかを逆算すれば、就活の方向性を見い出せます。
また選考では、人生の目標だけでなく、5年後や10年後の具体的なビジョンをどのように考えているかを尋ねられます。そういった質問にも、慌てずに明確に伝えられるように将来像を理解しておくことが重要です。
方向性を決めるには「Will・Can・Must」がおすすめです。キャリアプランへの具体的な行動を決める部分になるため、自分にとって何が重要かをしっかり考えてみましょう。
もし将来の目標が思い浮かばないときは「マインドマップ」を活用しましょう。思考の整理はアイデアを生み、キャリアプランを決める手がかりになりますよ。
キャリアビジョンまで考えることで、自己分析が一気に深まります。こちらの記事で効果的な描き方をチェックしてみましょう。
プロのアドバイザーはこう分析!「使える自己分析」で就活の軸が明確になる
自己分析ノートで必ず整理すべきなのは、以下の6点です。
①再現性のある強み/弱み
②価値観TOP3(優先順位付き)
③エネルギーの源と消耗要因
④避けたい環境
⑤成功の傾向と失敗の要因
⑥意思×市場性の重なり(狙う職務・業界の仮説)
根拠となるエピソード付きで整理されていると、より良いです。その際の書き方は、「証拠となる事象→解釈→次の行動」の順番で整理するようにしましょう。
また、事実からネクストアクションを洗い出す際は、各項目を以下の1セットにするのがおすすめです。
・【具体的事実(数字・固有名詞・他者の証言)】
・【そこからの解釈(自分らしさ/条件/特徴)】
・【ネクストアクション(面談・OB・OG訪問・短期インターンなど)】
また、現在・過去・将来の3章立てで整理するときも、「境界条件(この条件なら力が出る/出にくい)」を整理すると、再現性の高い振り返りになります。
分析の精度を高めながら常にアップデートさせよう!
整って見えるのに中身が薄いと感じられる自己分析では、反証が欠けていることが多いです。過度な一般化をするのではなく、あえて「うまくいかなかった事例→学び→再発防止」を作っておくと、根拠に厚みが出ます。
最後に、月に1回内容を見返して仮説の更新日を設け、進路の仮説と検証結果をアップデートすることで、「使える自己分析」に育ちます。
自己分析ツールで今月中に自己分析を終わらせてください
自分の弱みはわかっていても、強みは思いつかないものですよね。「これ、本当に強みって言えるのかな?」と悩んでいる多いはず。
そんな時は「My Analytics」を活用しましょう。このツールを使えば簡単な質問に答えていくだけで、あなたの強み・弱みが簡単にわかります。
無料で使えるので、自分の強みを確かめたい人は今すぐ診断しましょう。
・自己PRや志望動機に使える長所を知りたい人
・自分にあった仕事を知りたい人
自己分析ノートの作成手順
自己分析ノートの作成手順
- 手順①自己分析のテーマを決める
- 手順②テーマに基づいて考え方や出来事を書き出す
- 手順③書き出した内容に「なぜ」と深掘りしていく
- 手順④気付いたことや大事だと思うことを整理する
- 手順⑤テーマや手法を変えて②~④を繰り返す
自己分析ノートで必ず整理したいポイントが理解できたら、そのポイントを踏まえて自己分析ノートの作成を進めていきましょう。いざノートを用意しても、作成手順がわからないと「どこから手をつければいいのか」と手が止まってしまうことがあります。
そこで、ここからは自己分析ノートの作成手順を解説します。記事で紹介する5つの手順を参考にして自己分析ノートを作成し、自己分析を深めましょう。
手順①自己分析のテーマを決める
自己分析を始めるときに複数のテーマを設定してしまったり、逆にテーマを決めずに進めてしまったりすると、分析の方向性が定まらず、自己分析の成果が見えにくくなってしまいます。
そのため、まずは自己分析のテーマを1つに決めることが大切です。
たとえば過去に焦点を当て、夢中になって取り組んだことや頑張った経験、挫折した出来事を書き出してみましょう。未来から逆算したい場合は、希望の働き方や人生で大事にしたい価値観などをテーマにすると効果的です。
このようにテーマを定めて書き出すことで、自分の特徴や行動の傾向が整理され、次の深掘りがスムーズになります。就活で自己PRや志望動機を考える際にも活用しやすくなりますよ。
手順②テーマに基づいて考え方や出来事を書き出す
テーマを決めた後は、自身の考えや印象的な出来事を思い返してみましょう。
日々の小さな成功や友人との思い出深い会話など、些細なことでもノートにメモをすることがポイントです。
もし思い出せないという場合は、時系列順に記憶を辿っていくととスムーズです。学生時代から現在までの出来事を順に書いていくと、忘れていた経験や自分の価値観につながるヒントが見つかることもあります。
また、ポジティブな経験だけでなく、失敗や悔しかったことも書き出しておくと、あなたの強みや課題、大切にしている考え方がより立体的に浮かび上がってきます。
- 何から手を付ければ良いかわからないので、まず分析すべきおすすめのテーマを教えてほしいです。
やりがいや選考での頻出質問に沿ったテーマを分析してみよう
まだ志望業界や就活の軸が決まっていないという人は、「やりがいや達成感を感じたこと」というテーマから考えてみることがおすすめです。
自分の心が動いた瞬間がどんなときだったかを思い出すことで、自分のやってみたいことや働きたい環境が見えてきやすくなります。
選考対策としておすすめのテーマは、「頑張ったこと」「失敗経験とそれをどう乗り越えたか」です。
どの企業でも必ず聞かれると言っても良いほど頻出の質問のテーマであるため、具体的なエピソードとともに話せるよう、ノートに書き起こしておきましょう。
手順③書き出した内容に「なぜ」と深掘りしていく
②で書き出した考えや経験は洗い出すだけでなく、「なぜ」と問いかけてさらに深掘りしましょう。このステップは、自分の行動や感情に「なぜ」と問いかけていき、さらに深い部分の考えを知るのが目的です。
「なぜ」と深掘りする例
テーマ「頑張ったこと」
高校3年生のときサッカー部の大会で優勝した
↓
なぜ優勝できたのか:練習を頑張ったから
↓
なぜ頑張ったのか:サッカーが好きだから
↓
なぜ好きなのか:チームメイトとのコミュニケーションやチームの一体感があるから
↓
なぜ一体感があると良いのか:みんなで目標に向かって努力するのが好きだから
このように深掘りしたことで、自分はチームでの取り組みや目標に向かって努力することが好きだと理解できます。また努力してきたエピソードが明確になり、アピールポイントも見つかりましたね。
「なぜ」と深掘りすれば、過去のエピソードをより具体化できます。過去の行動からなぜそうしたのか?」「なぜ頑張れたのか?」など、自身の性格や価値観を見つけて自己理解を深めるために、必ずおこないましょう。
- どこまで「なぜ」を繰り返すべきですか? 終わりが見えないように感じてしまいます。
5回を目安に繰り返し深掘りしてみよう
「なぜ」を繰り返し深掘りしていく分析のことを、「5whys」と呼んだりします。5回の「なぜ」を繰り返すことで、根本原因を探っていくという手法だからです。
選んだエピソードによっては、深掘りしやすいものと、そうでないものがあるでしょう。
5回ほどスムーズに繰り返すことができたなら、それは自分にとって印象的な出来事であり、面接で話す際により自分の言葉で伝えやすく、熱意や思いが届けられる要素といえます。
手順④気付いたことや大事だと思うことを整理する
③の手順を終えたら、これまでに書き出した考えや出来事に対して、「なぜ」の深掘りから得られた気付きや大切にしたいことを整理します。
たとえば手順③の深掘りで見えたのは下記の内容です。
気付いたことや大事だと思うことの例
・チームで協力することが好き
・コミュニケーションを大事にしている
・目標に向かって努力できる
自身の性格や考え方が理解できるだけでなく、アピールポイントもわかり、将来像のイメージも考えやすくなります。
このように洗い出した情報を見てみると、これまでの経験から強みやスキルが形成されているはずです。見つけた特徴の中から、自己PRや企業選びなどに役立てられそうなエピソードを見極めましょう。
手順⑤テーマや手法を変えて②~④を繰り返す
1つのテーマが終わったら、テーマを変えてさまざまな方向から自己分析を進めましょう。その際、頑張ったことや成果などポジティブなテーマを考えるべきと思いがちですが、実は失敗などのネガティブな出来事からも気付くものがたくさんあります。
たとえば「挫折したこと」を振り返れば、何が原因だったのか、どうすべきだったのかなどを分析でき、自分の弱みや今後の課題を見つけられるかもしれません。
さらに、テーマだけでなく自己分析の手法も変えて書くのが効果的です。手法を変えれば書く内容にも変化が出て、別の手法では気付けなかった強みや価値観が見えてくるでしょう。
たとえば最初に自分史を作ったのであれば、次にマインドマップを書くことで、自分史の中で表現しきれなかった感情や考えなどが明確になり、性格や価値観をより正確につかむことができますよ。
自己分析についてさらに詳しく知りたい人は、下記の記事を参考にしましょう。自己分析の重要性や内定につなげるコツを解説しています。
自己分析をするなら自己分析ツールが一番おすすめ!
自分の弱みはわかっていても、強みは思いつかないものですよね。「それ、強みって言えないよ」と思われたくない人も多いはず。
そんな時は「自己分析ツール」を活用しましょう。このツールを使えば簡単な質問に答えていくだけで、あなたの強み・弱みが簡単にわかります。
無料で使えるので、自分の強みを確かめたい人は今すぐ診断しましょう。
自分の長所を分析するなら「自己分析ツール」がオススメ
今すぐ診断を見てみる【無料】
・自己PRや志望動機に使える長所を知りたい人
・自分にあった仕事を知りたい人
自己分析ノートの疑問をプロが解決! 「始める時期」と「ノート選びのコツ」って?
自己分析をノートでやる目的は理解できても、実際に作るとなると「いつから取り組むべき?」「どんなノートが良いのだろう」などと疑問に思う人もいますよね。
疑問を解決するためにも、就活のプロであるキャリアコンサルタントの楳内さんに、自己分析を始める時期やおすすめのツールを聞きました。自己分析ノートを作る準備段階として重要なポイントとなるため、参考にしましょう。
アドバイザーからワンポイントアドバイスノートは感じたことをすぐに書き留められるものを選ぼう
自己分析ノートは、結果はもちろん、そのプロセスや感じたこと、気付いたことなどの細かな情報を、日頃から記録しておくことが大切です。
そのため、いつでもどこでもさっと取り出して書き留めておけるように、持ち歩きやすいノートを使いましょう。スマートフォンのメモ機能で記録し、後でノートに書き写しておくのも良いですね。
また自己分析は、表やグラフを使っておこなうこともあるので、ノートやルーズリーフに手書きをするのと同時に、応募や面接時など後から振り返って活用するために、PCでデータや結果をまとめても良いかもしれません。
余裕を持って作成しておくことで自己PRや志望動機に活かせる
自己分析は1回やって終わりというものではなく、就活を進めながら、また仕事に就いた後も、その都度アップデートさせていきましょう。
自己分析ノートの作成時期は明確に決まっているわけではありませんが、就活では自己PRや志望動機を作成する際にこの自己分析ノートが活用できるので、その前には完成させておきたいところですね。
短期間で進めるよりも、3カ月や半年など時間をかけて進めることで、より効果的な自己分析につながっていくでしょう。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
作成後も重要! 自己分析ノートの活用方法
作成後も重要! 自己分析ノートの活用方法
- 見つけた強みや弱みは今後の方向性に合っているか比べる
- ネガティブな経験からも学びや反省を振り返る
- 第三者に見てもらって意見やアドバイスをもらう
- 定期的に見直して就職の方向性を確認する
自己分析ノートは一度作成するだけでも発見がありますが、そこで終わらせず、さらなる活用法も試すことで就活に存分に活かせます。
ここでは特に効果的な4つの活用法を解説するので、ぜひ併せて実践し、納得のいく就職につなげましょう。
見つけた強みや弱みは今後の方向性に合っているか比べる
自己分析ノートを書いて自身の強みや弱み、価値観などに気付けたら、それらが今後のキャリアプランと合っているかどうかを比べましょう。
分析してわかった自分の特徴を就活に役立てようとしても、希望業界の求めるスキルや人物像に合っていないケースが考えられるためです。
具体的には、強みがその業界や職種で活かせるのか、弱みは入社後に克服するべき課題となりそうかを考えます。目指す方向性の精度を確かめることができ、今後のアクションがクリアになります。
たとえ自分の強みや弱みが今後の方向性に合っていなかったとしても、別の道があることに早く気付けたと前向きに捉えましょう。
自分で強みが見つけられなかった場合は、家族や友人など、自分をよく知る人に質問してみるのが効果的です。
また自身の強みが希望業界とマッチしていない場合は、「なぜその業界が良いと思ったのか」をテーマに、改めて考え直してみましょう。
面接ではキャリアプランを聞かれることがあります。こちらの記事では例文付きでキャリアプランの考え方を解説しているので、参考にしてみてください。
ネガティブな経験からも学びや反省を振り返る
面接では、ネガティブな経験について質問されるケースがあります。企業は、入社後も困難に打ち勝てる人、臨機応変に対応できる人を求めているため、あなたがネガティブな経験からも学びを得ているのかを知りたいのです。
そのため、過去の挫折や失敗についても自己分析ノートで詳しく振り返り、その経験から自分はどのように立ち直ったのか、どのように成長したのかなどを考え、具体的に話せるようにしておきましょう。
- ネガティブに感じた経験が特に思い浮かばないときは、どうしたら良いですか?
目標を達成できなかった経験・人間関係に苦労した経験などを振り返ろう
自分史を作成するときにはさまざまな出来事を振り返りますよね。部活や習い事、勉強やアルバイトでどんな目標を立てたか、それに対しての結果はどうだったか振り返ってみてください。
その中でも目標達成できなかったものに対しては、反省を次にどう活かしたか言語化してみましょう。挫折体験とまでいかなくても、十分にエピソードとして通用します。
またネガティブな経験としてよくあるのが、人間関係です。うまくいかない人間関係からどんなことを学んだか、今どんなことに気を付けているかなどを振り返ってみてください。
企業がネガティブな経験から何を知りたいかを理解できれば、自己分析で何を深掘りすべきか整理できます。こちらの記事でポイントを押さえましょう。
第三者に見てもらって意見やアドバイスをもらう
自分自身のことを客観的に見るのは難しいため、ノートで自己分析を深めても、まだ自分では気付けていない一面もあるかもしれません。
そのため、自己分析ノートを完成させたらぜひ第三者に確認してもらいましょう。友人や家族、キャリアアドバイザーなどに見てもらい、アドバイスをもらうことで新たな視点や気付きを得られます。
たとえば自分の強みと弱みを書いたページを見せて、共感する部分や疑問を感じる部分を聞いたり、その人から見た自分の特徴を教えてもらったりしましょう。第三者の意見から、新しい自分の性格や価値観を発見できるかもしれません。
周囲に自分を分析してもらう方法は「他己分析」といいます。こちらの記事でおすすめの質問20選を紹介しているので、ぜひ友人や家族とやってみてください。
定期的に見直して就職の方向性を確認する
就活中は、いろいろな企業や業界を調べるため、希望業種が変わったり不安を感じて迷いが出たりします。そのため自己分析ノートは定期的に見直して、自分が大事にしたいことが何なのか忘れないように確認しましょう。
実際に選考を受けていく中で自分の本当の興味や価値観に気付いたり、目指すキャリアの方向性が変わったりするのは珍しくないため、自己分析ノートも現状に合わせて柔軟に更新するようにしてくださいね。
何か変化した点があると感じたら、マーキングしたり書き換えたりして、最新の情報にしておきましょう。
企業ごとのエントリーや面接時、また迷いや不安が生じたときなどのタイミングで、自己分析ノートを見返してみる習慣をつけましょう。
また就活は、やるべきステップを行ったり来たりするものです。月末などのタイミングで、1カ月ごとに振り返りも含めて見返すことをおすすめします。
まずは自己分析ツールで自分の強み・弱みを確認しよう!
「自己分析って時間がかかるし、正直面倒だな」と思っていませんか。
「自己分析ツール」を使えば、たった3分であなたの強みに合った適職を見つけられます。
自己分析を億劫に感じるときは、ツールを使って効率化しましょう。
- 自分の強みや弱みが分からない人
- 自己PRや志望動機に使える長所を知りたい人
- 自分にあった仕事を知りたい人
自己分析でノートを使う3つのメリット
自己分析でノートを使う3つのメリット
- 自身の能力や価値観を客観的に見つめ直せる
- 後から見返して選考対策に役立てられる
- 自己分析の種類に合わせて使い分けられる
就活における自己分析の重要性は理解していても、なぜ自己分析にノートを使うのか理由がわからない人もいますよね。
しかし理解不足のまま自己分析ノートを作成しても、ただ漠然とした内容になり、何も得られない可能性があります。事前にノートを使う目的やメリットを押さえることが大切です。
ここではまず、自己分析をノートでやる3つのメリットを紹介します。自己分析ノートを作る前の基礎の部分のため、必ず理解しておきましょう。
①自身の能力や価値観を客観的に見つめ直せる
経験や感情から自身と向き合える自己分析ですが、ノートに書くことで思考が整理され、自身の能力や価値観を客観的な視点で見つめ直すことができます。
頭で考えるだけでは、実際に分析しようとしても思考がバラバラになり、まとまらないことがありますよね。自己分析ノートはそういった思考の整理に役立つのです。
客観的に見ることで、もしかしたら思いがけないことが強みだと気付いたり、逆に得意と思っていたことが弱みだとわかったりと、新たな発見にもつながりますよ。
さらに、新しく見つけた能力は選考で企業にアピールできる要素になり、気付いた価値観から違った業種への道も開けるかもしれません。
能力が強みだとわかってはいても、実際に自分の優れた面を発見するのは難しいものです。
強みを抜きん出た特別な能力として捉えるのではなく、まずは自分があまり苦労しなくてもできてしまう「当たり前なこと」に目を向けてみましょう。
②後から見返して選考対策に役立てられる
自己分析ノートには印象的な出来事だけでなく、些細なことやそのとき芽生えた感情、分析中に自分について感じたことなど、小さな気付きも書き込みます。
大きな出来事であればいつでも思い出せるかもしれませんが、小さな気付きは忘れてしまいますよね。そういった忘れてしまいそうな気付きもノートに記載しておくことで、いつでも見返して選考対策に役立てられます。
また、就活の途中で希望業界を変更したり、別の企業に興味を持ったりした際も、自己分析ノートをいつでも見返して、本当に自分の性格と合っているのか、価値観からブレていないかなどを確認できますよ。
③自己分析の種類に合わせて使い分けられる
自己分析ノートは、考え方や価値観を分析したいとき、将来のキャリアプランを考えたいときなど、目的に合わせて使い分けるのも効果的です。
たとえば、就活を進める中で新たな業界に興味を持ったとしましょう。今後のキャリアプランを新しく考える必要が出た場合、過去の分析とは別にキャリアプランの分析用のノートを作ることで、より思考の整理ができて選考対策に活かせます。
ただし、ノートをいくつも作ると管理が大変で、1冊にまとめたいという人もいますよね。決まりがあるわけではないので、シンプルにまとめたい人は1冊にするなど、自分の好みに合わせて作ってみましょう。
ノートごとにテーマを分けて書いていくと、そのテーマについて深く内省することができます。
また、その後にエントリーシート(ES)や履歴書を書く時、自分の強みや志望動機、キャリアプランを探しやすくなるのです。大雑把な人はノートを使い分けた方が整理されて良いと思いますよ。
自己分析で悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!
ChatGPTなどの生成AIは、就活準備にも非常に役立ちます。
「就活準備プロンプト集」では、就活のプロが考えた、生成AI用の命令文を豊富に用意していますよ。
このプロンプト集を活用すると、性格と経験を入れるだけで、AIが5つの強みを判断してくれます。プロンプト集で就活準備を効率化しましょう。
- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト
- チャットを使用した、模擬面接プロンプト
- 自己PRで使える強み診断プロンプト
自己分析の基本を就活QAでおさらいしよう!よくある疑問にも回答
ここまで、ノートを使って自己分析を進める方法を解説してきましたが、そもそも自己分析自体に疑問があると、ノートを作成する際につまずいてしまうこともあります。
だからこそ、自己分析についての疑問や、ノートを作る際に気になったことなどは早めに解決しておきましょう。
ここからは、自己分析ノートを作るうえで知っておきたい点や、疑問としてよく目にする点について、就活QAで回答していきます。あらためておさらいして、しっかりと整理された自己分析ノートを作っていきましょう。
①方法・形式について(ノートで活用できるもの)
②対象別のやり方について
③ノートに書く内容について
自己分析ノートは目的別にやり方を使い分け! 企業選びや面接対策にも活かそう
自己分析ノートは、自己流でなんとなく書くのではなく、目的に合わせてやり方を使い分けることが大切です。企業選びに活かしたいのか、面接で自己PRや志望動機を整理したいのか、まずは自分が何を知りたいのかを明確にして取り組みましょう。
そのうえで、過去の経験を振り返るのか、将来のキャリア像を描くのかといったテーマに応じて、適したフォーマットや手法を選ぶのがおすすめです。目的に沿って分析を進めることで、選考対策やキャリアプランに役立つ多くの気づきを得られます。
また、作成したノートはそのままにせず、書いた後に希望業界と照らし合わせたり定期的に更新することでさらに効果が高まります。書いて終わりにせず、活用法を実践して最大限に役立ててくださいね。
アドバイザーからあなたにエール選考でうまく答えられない原因は自己分析での言語化不足にある
自己分析は、就活において最も重要なポイントです。あなたがどれだけ素晴らしい能力や経験を持っていても、それが面接官に伝わらなければあなたの魅力は半減してしまいます。
面接で聞かれた質問に対して、なんとなく回答は思い浮かんでいるものの、うまく答えられなかった経験がある人も多いのではないでしょうか。そのような状況に陥る要因の大半は、「言語化不足」にあります。
自己分析ノートでどんどんアウトプットして満足のいく就活にしよう
自己分析ノートを作るメリットは、新しい自分の価値観に気付けたり、思考を整理できたりすることだけではありません。
頭の中で思い浮かべたことを言葉で一度アウトプットしておくことで、自分の経験や考えをいつでも相手に伝えられる状態にすることができるという効果もあります。そのためESや履歴書を書くときだけでなく、面接対策としても非常に役立つのです。
これから就活を始める人も、すでに始めている人も、自己分析ノートを活用して自分の新たな魅力を発掘してみてください。自己分析ノートを味方にして、満足のいく就活になるよう応援しています。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

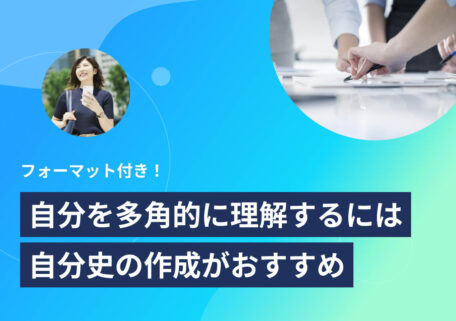


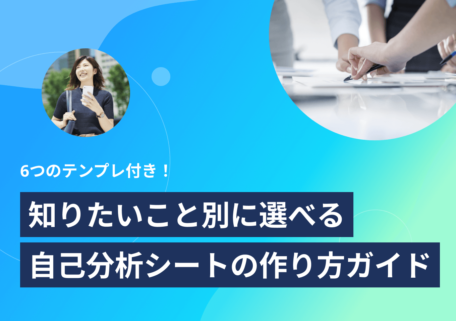






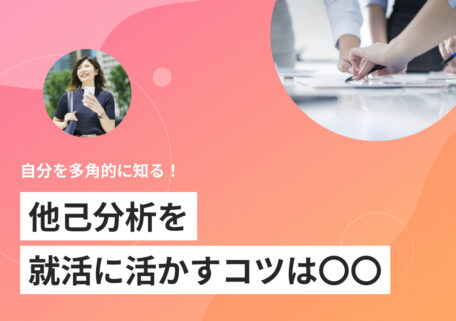






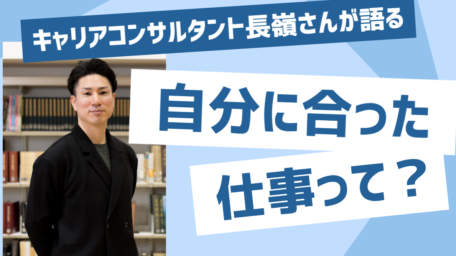
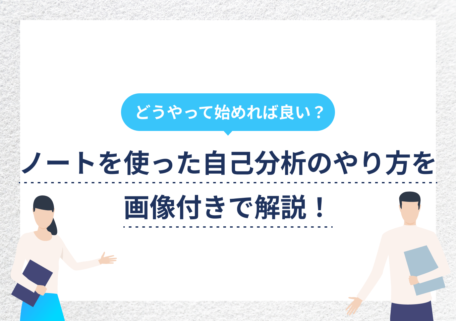








3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/産業カウンセラー
Junko Tomioka〇南箕輪村のキャリア教育推進コーディネーターに就任後、独立。現在は地方中高生やベトナム人留学生の就活支援、企業内キャリアコンサル、地方就職のサポートをおこなう
プロフィール詳細キャリアコンサルタント
Natsuki Inoue〇新卒で携帯電話販売代理店業界のベンチャー企業に入社。現場にてBtoC営業を経験した後、人事部では新卒採用を中心に、社内研修講師や社員面談などの人事業務に幅広く従事
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/ワーズアンドキャリア代表
Yukiko Umenai〇アナウンサーとしてのノウハウを活かし、総合人材会社で研修や社員教育を担当。人材の活躍やキャリア形成支援にも注力し、大学ではキャリア講義やカウンセリング、就職支援を担っている
プロフィール詳細