この記事のまとめ
- 深い自己分析と業界・企業分析で自分に合う職業が見つかる
- 適職を見つけるためには4ステップで進めるのがおすすめ
- 自分に合う職業を見つけるには労力がかかるがそれに見合う価値がある
企業に入社して数年以内に「この仕事は本当に自分に合っているのかな」と疑問を抱くのはよくあることです。転職未経験の人はほかの企業で働いたことがないため、このような疑問を抱きがちです。
実際、その疑問が大きくなり、転職を決断する人もいます。今回は自分に合う職業について今一度考え、適職を見つけるための具体的な方法をチェックしていきましょう。
自分に合う職業に就ければ、ストレスなく意欲的に仕事に取り組めます。転職したいと感じ始めた人に向けた情報も記事後半で解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
徹底した自己分析と業界・企業分析で自分に合う職業を見つけられる
自分に合う職業を見つけるためには、徹底した自己分析と業界・企業分析の擦り合わせが欠かせません。自分の価値観を明確にしたうえで、それを実現できる企業に入社してこそ理想のキャリアを実現できます。
ただし、仕事をしながらやみくもに自分に合う職業を探すと適職を見つけられず、結果的に転職を繰り返す可能性が高いです。適職探しに挫折するのを防ぐためにも、記事前半では効率よく自分に合う職業を見つけるためのステップを具体的に解説しています。
記事後半の内容は、実際に転職したいと考え始めた人向けのチェックリストや、自分に合う仕事が見つからない人に向けた具体的なアドバイスです。実例を出しながら詳しく解説しているので、最後まで読めばキャリア選びで失敗するリスクを低く抑えられます。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認してみよう
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
自分に合う職業とは? まずは定義を確認
組織心理学の世界的権威であるエドガー H. シャイン博士によると、自分に合う職業の定義は、以下のとおりです。
自分に合う職業の3つの定義
1.自分の才能を十分に発揮できること
2.自然に情熱を注ぎ、熱中できること
3.それをおこなうことで意味や価値を感じられること
この3つが自分に合う職業の定義です。
3つの条件を頭に入れて、この先の自己分析や企業分析で自分に合う職業を見つける際の参考にしましょう。
シャイン博士の「自分に合う職業の3つの定義」を頭に入れて、自分に合う職業を探していきましょう。
一方で、仕事から選ばれるという側面もあるので、自分では3つの定義に当てはまっていると思っても、企業や顧客から同様の評価を受けない場合もあります。
他者の意見にも耳を傾ける柔軟な姿勢も大事です。
自分に合う職業を見つけるのが難しい3つの理由
自分に合う職業を見つけるのが難しい3つの理由
- ①自分の価値観を正確に言語化できていないから
- ②企業分析で十分情報を集められていないから
- ③入社後に気付くストレスポイントがあるから
自分に合う職業の定義がはっきりしても、実は適職を見つけることは想像以上に難しいのです。自分に合う職業を見つけたと思っても、正しく自己分析や企業分析ができていてなければ、それは本当の適職ではない可能性があるためです。
職業選択には単なるスキルや経験、価値観だけでなく、収入や働き方なども関わってきます。
ここから解説する自分に合う職業を見つけるのが難しい理由を細かくチェックして、自分がなぜ適職をすぐ見つけられないのかを明確にしましょう。
①自分の価値観を正確に言語化できていないから
自分に合う職業が見つからない最も大きな原因が、自身の価値観を明確に言語化できていないことです。自分の価値観が正確に言語化できていなければ、自分に合う職業が見つかってもそれが適職だと確信できません。
多くの人は「やりがいのある仕事がしたい」「自分の能力を活かせる仕事に就きたい」といった漠然とした希望は持つことは多いです。しかし、それが具体的にどんな状態なのか説明できる人は多くありません。
たとえば、やりがいと言っても、以下のように複数の解釈があります。
やりがいの解釈例
- 誰かの役に立てる実感新しい
- 社会に価値を生み出せる喜び
- 自身の成長の実感
このように人によって捉え方はさまざまです。自分にとって本当に重要な価値観を言語化できなければ、職業に求める条件が曖昧になります。結果、自分に合う職業を見つけられないのです。
②企業分析で十分情報を集められていないから
事前に企業の情報を十分に収集できていないことも、理想のキャリアの実現が難しい理由の一つです。不十分な情報をもとに就職先を選んだ場合、チェックしていなかった部分が自分と合わず、自分に合う職業ではないと感じてしまう可能性があります。
また、表面上のリサーチが十分でも、職業を決める情報としては不十分な場合もあります。たとえば、パンフレットや企業のウェブサイトには業務内容や待遇などが詳しく書かれている一方、実際の社風や社員のキャリアパスなどの具体的な情報は得づらいです。
これらの根本的な情報不足が発生している状況が新入社員と企業のミスマッチを引き起こし、自分に合う職業を見つけるのを一層難しくしています。
適職かどうかは最終的にマッチングが決め手となります。いくら自己分析を頑張っても企業選びを間違えば適職にはなり得ません。
そのため、転職には企業情報を正確に知ることが重要です。ネット上の情報に加え社内事情に詳しい人物から情報を得るのがおすすめです。
③入社後に気付くストレスポイントがあるから
実際に働き始めるまで気付かないストレス要因が企業や職場に存在することも、自分に合う職業を見つけるのが難しい大きな理由です。入社前と入社後のネガティブなギャップが許容できない水準だと、ほかの条件が理想的でも自分に合っていないと感じてしまいます。
ネガティブなギャップが発生するおもな要因は以下のとおりです。
| 要因 | 詳細 |
|---|---|
| 業務上の予期せぬ課題 | ・想定していなかった責任範囲 ・想像以上の業務量 ・実務に入って初めて気づく難しさ |
| 企業文化や職場の雰囲気とのミスマッチ | ・予想と異なる企業文化 ・職場内の雰囲気の不和 ・人間関係の不和 |
| キャリアパスに関する問題 | ・理想のキャリア実現の困難さ ・昇進・昇格の難しさ ・スキルアップ機会の欠如 |
これらのストレスポイントは、入社前の情報収集だけで完全に把握するのは困難です。実際に業務を開始してから問題が徐々に表面化してくるケースが多いため、ネガティブなギャップをゼロにするのは難しいと捉えておきましょう。
ネガティブなギャップを防ぐためには、入社前の企業研究の深さが重要です。ホームページや採用情報だけでなく、社員のインタビュー記事やレビューサイト、SNSの情報も参考にすると良いでしょう。
可能ならばOB・OG訪問を活用して、職場の雰囲気などサイトからは得られない情報も収集できると安心です。
さらに、インターンシップや職場見学に参加すると、実際の業務や職場環境を体験できます。
しっかりと企業研究をおこない、自分の価値観や希望と合致するかを確認しておくことでネガティブなギャップの防止につながります。
具体的に把握しておこう! 自分に合う職業に就く3つのメリット
具体的に把握しておこう! 自分に合う職業に就く3つのメリット
- ①業務でのストレスを感じづらくなる
- ②意欲的に取り組めるため成果が出やすい
- ③自己肯定感が高まりやすい
自分の才能を存分に発揮して、やりがいを感じながら熱中できる職業を見つけることは難しいことです実際、自分に合う職業を見つけられないままキャリアを終える人がいるのも事実です。
しかし、自分に合う職業に就くことには、この難しさに向き合う価値があるほどの大きなメリットがあります。
ここからは、自分に合う職業に就くメリットを3つに分けて詳しく解説します。充実したキャリアを築きたい人は、以下で詳細をチェックしてみてください。
①業務でのストレスを感じづらくなる
自分に合う職業に就けば業務上のストレスが少なくなり、より快適に働けます。仕事内容自体が自分の価値観や適性に合っているため、普通ならストレスのかかる業務でも前向きに捉えられるためです。
業務自体が自分にとってつらいと、成果がでない段階で大きなストレスを抱える可能性が高いです。結果的につらいと感じる可能性が高まり、仕事が長続きしなくなることがあるのです。
一方、業務上のストレスが少なければ、思うように結果が出なくても努力を継続しやすくなります。さまざまな方法を試しながら成果を追求できるため、成果にもつながりやすくなるのです。
また、業務でのストレスが少ないと精神の健康を維持しやすいのも大きなメリットといえます。
②意欲的に取り組めるため成果が出やすい
自分に合う職業では仕事への興味や関心が自然に高まり、意欲的に業務に取り組めます。その結果、業務効率が向上してより大きな成果を上げやすくなるのです。
具体的には、以下のような好循環が生まれます。
自分に合う職業が作り出す好循環の例
- 自分に合う職業が作り出す好循環の例
- モチベーションの維持・向上
- スキル向上への意欲アップ
- スキル・能力の獲得
- 業務効率の向上
自分に合う職業に就くと、モチベーションが高まり、結果的に業務効率が向上するといった好循環が生まれて、スキルや能力が右肩上がりに伸びていく可能性が高まります。
また、自分に合った職業に就ければ、仕事を続けるなかで困難な状況に直面しても、自然に努力できることも考えられるのです。自分から意欲的に試行錯誤できる分、逆境に陥っても早急に脱却しやすくなります。
あなたが受けないほうがいい職業を診断しましょう
就活を進めていると、自分に合う職業がわからず悩んでしまうことも多いでしょう。
そんな時は「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格、価値観を分析して適職や適さない職業を特定してくれます。
自分の適職や適さない職業を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
③自己肯定感が高まりやすい
自分に合う職業に就くと、仕事を通じて自己肯定感が高まる傾向があります。自分の強みやスキル、経験を活かせる環境で働くことで、より本来の自分らしさを発揮できるためです。
自己肯定感が高まることには自信を持てる以外にも以下のメリットがあります。
自己肯定感が高まることのメリット
- 自分のキャリアビジョンが明確になる
- 自分の新しい可能性を見出せる
- ポジティブな理由でキャリアを選択できる
また職場での前向きなコミュニケーションが増えたり、新しいことに主体的に挑戦したりして、同僚や企業にも良い影響を与えられます。
このように、適切な職業選択によって、仕事の満足度を高められるだけでなく人生をより充実したものにできるのです。
自分に合う職業に就くと成果が出やすいため、一緒に働くチームの仲間や上司が仕事をしやすくなり、チームで成果を上げることへの貢献につながります。
結果的に会社に貢献することになり、会社からの評価も上がります。これもメリットの一つです。
自分に合う職業を見つける方法を4ステップで解説

自分に合う職業を見つけるのは難しい一方、より充実した、豊かな人生を実現することが可能になります。しかし、自分に合う職業を見つける具体的な方法がわからず、悩みを抱える人もいるかもしれません。
ここからは、自分に合う職業を見つける具体的な方法を解説していきます。まずは適職探しの全体像を把握し、その後に詳細を解説するので、方法がわからず悩みを抱えている人は参考にしてください。
以下の手順を踏めば、自分に合う職業を見つけられる確率が一気に高まります。
①自己分析をおこなう
まずは自己分析を通じて自分の価値観や性格を明確にしましょう。自己理解は自分に合う仕事を見つける際の核となる部分であるため、特に入念に取り組んでください。
自己分析ではまず過去の経験や行動に目を向け、そこから自分の価値観や考え方を明確にします。それぞれの経験の共通点、相違点を整理・比較することで、自分の特徴が明確になるのです。
経験の整理によって価値観・考え方が明確になったら、それらをもとに将来像やビジョンを明確にします。ビジョンを明確にすることで、過去・現在・未来の自分をつなぎ、自分の理想を言語化しやすくなります。
自分に合う職業を見つけたい人は、何よりも先に土台となる自己分析から取り組んでください。
すぐにできて深く自己を分析できる方法を知りたい人は、以下もチェックしてみてください。内定につながる自己分析法がわかります。
②自分にとっての「合う」の条件を言語化する
自己分析で自分の価値観や理想の将来像が明確になったら、分析内容をもとに自分にとっての「合う」を定義しましょう。
自分にとっての「合う」の例
- 早いうちから活躍したい→若手の裁量権が大きい企業
- チーム一丸となって働きたい→協力的な企業風土が根付く企業
- 社会にインパクトを与えたい→社会への影響力が大きい企業
自分にとっての「合う」が定まらないまま次のステップに移ってしまうと、自分に合う企業を見つけても確信が持てなくなります。結果、「なんとなく合っているかもしれない」という感覚で企業を選んでしまい、ミスマッチが起こる可能性が高まるのです。
企業選定・分析に移る前に必ず自分にとっての「合う」を定義して、判断基準を明確にしておきましょう。
判断基準を作る際は、基準をリストアップして優先順位をつけて整理する方法がおすすめです。その後、絶対に譲れない条件と他の要素次第で妥協できる条件の線引きをしておきましょう。
譲れない条件を明確にしておけば、企業とミスマッチする確率を下げられます。
- 絶対に譲れない条件が多すぎて、職業選びがなかなか進みません。どうすれば譲れない条件と妥協できる条件を正しく線引きできるのでしょうか。
Must・Want・Nice to haveの3つに分類して重要度を明確にしよう
譲れない条件が多すぎると感じる場合は、まず条件をリストアップし、それぞれの優先度を明確にしてみましょう。
「絶対に譲れないもの(Must)」「できれば満たしたいもの(Want)」「あれば満たしたいもの(Nice to have)」の3つに分類し、それぞれの重要性をじっくり考えてみてください。
優先度を決める際に、「長期的な満足感が得られるか」「キャリア形成にプラスになるか」という2つのポイントを考えるようにすると良いでしょう。
また、すべての条件を満たす企業は少なく、価値観が変わることもありえるため、柔軟な視点を持つことも大切です。
インターンシップや説明会、OB・OG訪問など職場や業界のリアルな一面を知ると、譲れない条件の再定義ができるかもしれません。
③企業分析をおこなう
自己分析で自分の価値観や譲れない条件などを明確にできたら、業界・企業分析に移ります。まずは自己分析をもとに、自分の価値観やキャリアビジョンにマッチする業界を絞り込みましょう。
その後、業界内の企業から自分に合いそうな企業をピックアップします。このとき、各企業に関する以下の情報を整理して、より深く分析すべき企業を絞り込みましょう。
企業分析前にチェックすべき企業情報
- 仕事内容
- 社風
- 企業理念
なお、ほかの条件が理想的でも上記が自分に合わなければ再び現職と同じ理由で悩む羽目になる可能性があります。自分に合う企業を見つけるためにも、上記条件が自分に合う企業のみに絞り込み、より深く企業分析をしてください。
企業分析については以下で詳しく解説しています。より詳しく企業分析のやり方を知りたい人は、以下の記事もチェックしてみてください。
④自分に合う企業を選別する
企業分析によって自分の価値観に合いそうな企業を絞り込めたら、さらに分析を深めて自分に合う企業だけを選別します。
具体的には以下の企業情報をチェックして、整理・比較しましょう。
自分に合う企業を選別する際に整理すべき情報
- 給料・福利厚生
- 労働時間・労働条件
- 将来性
- 転勤頻度
- 離職率
- 選考時期
仕事内容・社風・企業理念に加えて上記をチェックすれば、事前に働くことのイメージができ、企業とのミスマッチのリスクをより低く抑えられます。
情報を整理できたら、各企業の情報を比較してより自分の理想に近い企業を探しましょう。譲れない条件・妥協できる条件と照らし合わせることで、本当に自分に合う企業を見つけられます。
最初は気になる会社をいくつもリストアップすると思いますが、最終的には一つの業界につき7社以下、できれば5社程度に絞ることをおすすめします。
人が一度に把握できる数は7前後だと言われています。それ以上になると対応が雑になったり連絡が疎かになる恐れがあり、結局通過率が下がることがあります。
自分に合う職業がわからない人は、以下の記事もチェックしてみましょう。図表や簡単な4ステップを使って適職を見つける方法を詳しく解説しています。
向いてる仕事がわからない
向いてる仕事がわからない……図解で読み解く適職の見つけ方
自分にあっている仕事
自分に合った仕事を簡単4ステップで発見! 後悔しない方法を解説
あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
自分に合う職業を見つけるための自己分析のやり方6ステップ
自分に合う職業を見つけるための自己分析のやり方6ステップ
自分に合う職業を見つける方法を4ステップが理解できたら、ここからはそのステップに沿って実際に自分に合う職業を探し始めましょう。
適職探しの土台になるのが、ここから解説する自己分析です。正確な自己理解ができていなければ、これまで同様に仕事に疑問を抱えながら続けてることになる可能性が高まってしまいます。
この先のキャリアを理想に近づけるためにも、すべての基礎となる自己分析は徹底的におこなってください。事前に紹介した自分に合う職業の定義を念頭に置いたうえで、自分の価値観を明確にしていきましょう。
①過去の経験のなかから掘り下げるテーマを複数決める
自己分析でまずやることは、掘り下げるテーマのピックアップです。掘り下げるテーマを複数決めて分析の方向性を定めることで、自分の価値観やそれにもとづく行動を網羅的にチェックできます。
具体的なテーマの例は以下のとおりです。
掘り下げるテーマの例
- 頑張ったこと
- 楽しかったこと
- 困難を乗り越えたこと
- 熱中していたこと
- 周囲に貢献したこと
- 失敗から学んだこと
- やり遂げたこと
テーマを決める際は自分の価値観のうち、どの側面を掘り下げたいかを基準に選びましょう。
仕事に求める条件を掘り下げたい場合は熱中したことや頑張ったことを、自分の強み・弱みを明確にしたい場合は苦しかった経験や困難を乗り越えた経験を選ぶと、的確に自分の価値観を浮き彫りにできます。
事前にテーマを決めて自己分析を始めれば、分析の方向性がブレづらくなります。
ネガティブな経験を振り返ることには大きな価値があります。なぜならば、失敗や困難を乗り越えた経験が成長や学びをもたらしてくれるからです。
また、ネガティブな経験から得た気づきは、自分が大切にしている価値観や本当に避けたいものを明確にします。もちろん面接で説得力のあるエピソードとしても使えますよ。
②それぞれのテーマに関するシーンを洗い出す
テーマを定めたら、それぞれのテーマに関する経験を洗い出してみましょう。それぞれのテーマに合わせて複数のシーンをピックアップすることで、より多角的な分析ができます。
たとえば「熱中したこと」というテーマに関してシーンをピックアップする際は、以下のようにおこないましょう。
| シーン | 詳細 |
|---|---|
| 小学生 | クラブチームに所属して野球だけに熱中した。勉強にはあまり熱中せず。 |
| 中学生 | 部活で野球を頑張りつつも、徐々に勉強にも興味を持ち始めた。野球ではレギュラーに選ばれ、さらに熱意が高まった。 |
| 高校生 | 部活を引退してから勉強に没頭。野球に関連する勉強にも興味を持ち始め、野球をプレーするだけでなく理論的な部分を追求し始めた。 |
| 大学生 | プレーヤーとして野球部に入ったが、スコア分析や栄養学から野球にかかわるほうが楽しいと自覚する。マネージャーに転身してチームをサポートしながら、県優勝に尽力した。 |
シーンを洗い出す際は、小学生から現在までの経験を洗い出すのがおすすめです。自分の価値観や考え方が確立してからの経験に絞ることで、自己分析がより正確になります。
③それぞれのシーンに関するエピソードを深掘りする
テーマ別でいくつかのシーンをピックアップできたら、それぞれのエピソードを深掘りしましょう。それぞれのエピソードを深く分析すれば、その時々の自分の考えや価値観をより明確にできます。
エピソードを深掘りする際は、「なぜ?」と自分の行動に対して理由を問い続けることで、自分の根本的な価値観が明確になります。
エピソードの深掘りの例
- プレーヤーとして野球部に入ったが、スコア分析や栄養学から野球にかかわるほうが楽しいと自覚する
↓なぜ? - 物事をいくつかの要素に分割して、それぞれを分析して効果的な方法を探るのが興味深いと感じた
↓なぜ? - 物事を多面的に見て、その本質を解き明かすことに価値を感じるから
↓なぜ? - それにより、効果的な手法を見つけられて結果が出るから
このように「なぜ?」を繰り返すことで、自分が何に対して価値を感じるのか明確にできます。
「なぜ?」と深掘りする目安は3回ほど。自分の根本的な価値観が明確になればOKです。
根本的な価値観が出てくると、自分の中で腑に落ちる・腹落ちする感覚が生まれると思いますので、そこまで深掘りできれば十分です。
④自己分析の内容を整理して自分の価値観や考え方を明確にする
それぞれのテーマ・シーンに沿ったエピソードを深掘りできたら、次はそれらを整理して本当の自分らしさや価値観を探ります。
たとえば前述のエピソードの深掘り例では、自分が物事を多面的に分析するだけでなく、それによって「現状をより良くする」ことに価値を感じているとわかりました。
小学生時代や中学生時代のエピソードも同様に深掘りすれば、「現状をより良くする」以外に自分が価値を感じる条件が見つかるかもしれません。
見つかった条件を整理・比較することで、自分の本当の価値観が明確にできます。
転職の軸を明確にする方法は、以下の記事でも解説しています。自分だけの転職軸を見つけたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
⑤友人や家族に自分の印象や強み・弱みを聞く
より正確な自分の特徴をとらえるために、最後は友人や家族などの視点から自分を分析してみましょう。面接で自分を評価するのは面接官である以上、周りから見た自分への理解は欠かせません。
友人や家族が自分に対して抱く印象と自己分析を照らし合わせることで、より正確で客観的な分析がおこなえます。具体的には、他人から見た自分の特徴を聞くと自己分析の内容を事実と解釈に分けられるのです。
事実と解釈の違いは、以下のとおりです。
| 定義 | 例 | |
|---|---|---|
| 事実 | 実際に起こったこと、現実に存在する事柄 | ・自分はサッカーで県選抜に選ばれた ・コミュニケーションが上手だとよく言われる |
| 解釈 | 事実に対する自分の考えや意見 | ・自分はサッカーが得意だ ・人と話している時が一番楽しい |
他人からの印象を聞いたら、自己分析と突合して事実と解釈を整理しましょう。
- 他己分析をしている学生としていない学生の間には、面接の時にどのような差が生まれるのでしょうか。
他者からの意見も加わりより自信に溢れたアピールが可能になる
他己分析には自己分析にはなかった気づきを得られる可能性があり、それを強みとして面接でアピールできます。
また、他己分析と自己分析が合致すれば、確実に自身の特徴として認識できるため、さらに深掘りし、価値観の軸として自己PRを組み立てることができます。
軸がしっかりしたストーリーを熱意を持って語ることで、意欲や真剣さを伝えることが可能です。
そして自分の価値観に確信を持つことで自信に満ちた態度で面接に臨むことができるようになります。
自己PRが思いつかない人は、ChatGPTを活用して自己PRを完成させよう
ChatGPTを使った自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?
簡単な質問に答えていくだけでChatGPTが自動で魅力的な自己PRを作成します。
作った自己PRは選考で活用できるものになっているので、ぜひ活用して採用される自己PRを完成させましょう。
⑥自己分析・他己分析をもとに自分にとっての「合う」を定義する
自己分析・他己分析ができたら、それらをもとに自分にとっての「合う」を定義しましょう。
自己分析・他己分析の両方を十分おこなってから「合う」を定義することで、本当に自分に合った職業を見つけやすくなります。自分の思い込みに左右されることなく、事実をもとに適職を見つけられるためです。
逆に、解釈を排除せずに自分に合った企業を探そうとすると、ミスマッチが起こる可能性が高くなります。解釈はその時々の心理状態に影響を受ける一時的なものの場合が多いです。
たとえば「サッカーで県選抜に選ばれた」という事実は変わることがありません。一方、解釈は「自分はサッカーが得意だ」となる場合もあれば、「一握りの才能がある人には敵わない」に時には変化することも考えられるでしょう。
一時的な感情で「合う」を定義しないように、必ず事実と解釈を切り分けたうえで判断しましょう。解釈ではなく事実に即して自分の「合う」を定義できれば、同じ失敗を繰り返すリスクを最小限に抑えられます。
これまでの自分を振り返るには「自分史」の活用も有効です。自己分析への活かし方は以下で詳しく解説しています。
適職を見つけるための企業分析の5ステップ
適職を見つけるための企業分析の5ステップ
徹底的な自己分析ができたら、次は企業分析に取り掛かります。業界、企業の順に対象を絞り込み、それぞれの企業が自分に合いそうかチェックしていきましょう。
企業分析は情報収集・整理・比較が基本です。注目すべきポイントや具体的な分析方法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
なお企業分析の際も、事前におこなった自己分析がもとになります。なぜなら自己分析で明確になった自分の価値観をもとに、企業を絞っていくためです。だからこそ、自己分析が不十分だと企業分析もうまくいきづらくなるのです。
企業分析をうまく進められないと感じたら、一度自己分析が十分かチェックすることも検討してみてください。
①自己分析をもとに業界をいくつかに絞る
企業を絞る前に、まずは自己分析をもとに自分に合う業界を選定しましょう。業界分析で各業界の特徴を明確にし、自己分析と擦り合わせることで自分に合う業界を絞り込めます。
楽しかったことや熱中したことなどのテーマを深掘りする際に見つけた自分の価値観をもとに業界を絞るのが効果的です。
業界を絞り込む際のおすすめの方法
- 業界地図をもとに分析する
- 書籍やニュースで情報を集める
- 業界団体のホームページ(HP)をチェックする
- 合同説明会に参加する
業界を絞る際は業務内容だけでなく、各業界のキャリアビジョンや労働条件などにも目を向けましょう。自己分析で得た自分が快適に働ける条件や実現したい将来像なども考慮して業界を選ぶことが重要です。
業界を絞り込む際の有効な方法の一つに合同説明会があります。合同説明会に参加する前にチェックしておいてほしい内容は、以下にまとめています。
営業や、人事、エンジニア、デザイナーなどの具体的な職務内容で選択することも可能です。
また、バックオフィスや、接客・サービス、企画職などの役割ごとに選ぶこともできるでしょう。
この場合のポイントは、自分のスキル・強み・興味が活かせるかどうかです。しっかりと自己分析し、情報を幅広く収集することで、業務内容の違いを理解しましょう。
②企業分析で集めるべき情報を把握する
業界を絞り込めたら企業分析に移ります。まずは企業分析でどのような情報を集めるべきか知るところから始めましょう。
企業分析で集めるべき情報は、以下のとおりです。
企業分析で集めるべき情報
- 仕事内容
- 社風
- 企業理念
- 労働時間・労働環境
- 給料
- 福利厚生
- 転勤・異動の有無
- 離職率
- 将来性
- 選考時期
企業分析では仕事内容や給料ばかりに注目してしまいがちですが、自分に合う職業を見つけるためには社風や企業理念、労働環境なども重要です。
自己分析でわかった自分の考え方・価値観をもとに上記の情報を収集すれば、自分に合う企業を見つけやすくなります。
なお、そのほかに自分にとって重要な要素が自己分析で見つかった場合は、あわせてリストアップしておきましょう。
③それぞれの企業の情報を実際に収集する
集めるべき情報が明確になったら、インターネットやイベントを通じて実際に情報を収集します。以下の方法でそれぞれの企業の情報を集め、自分に合った企業を探す準備をおこないましょう。
企業の情報を集める方法の例
- 就活四季報をチェックする
- 各企業のHPをチェックする
- 会社説明会に参加する
- OB・OG訪問をおこなう
- インターンに参加する
就活四季報やHPなどを活用することで手軽に情報を集められる一方、集められる情報は一般的なものになります。
ただし、すべての企業を入念にチェックしていると、膨大な時間がかかります。そのため、まずは四季報や各企業のHPで情報を集めた後、自分に合いそうと感じた企業をリストアップしましょう。
その後説明会への参加やOB・OG訪問をおこなうと、効率よく企業分析を進められます。
企業分析に取り掛かる際は、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。就活生が不安に感じがちなポイントを重点的に解説しています。
就職四季報
就職四季報の活用方法! 就活を有利にするポイントや読み方を伝授
インターンの探し方
インターンの効果的な探し方8選を学年別で解説! ありがちな失敗も
④企業ごとの情報を整理して比較する
会社のHPチェックやOB・OG訪問、インターンで各企業の情報が集まったら、各社の情報を比較しましょう。
企業の情報を収集するだけでは企業分析にはなりません。集めた情報を整理してそれぞれの企業を深く理解し、比較して各企業の特徴を明確にすることが企業分析の本質です。
企業分析で各社の情報を整理・比較する際は、以下のように自分に問いかけて、自分に合う企業を絞り込んでいきましょう。
企業分析の例
- どの企業が理想のキャリアを最も実現しやすいか?
- 自分がストレスなく働けそうな企業はどこか?
- どの企業なら自分のスキル・経験を活かせるか?
リストアップした企業の比較を通じて、それぞれの企業の働きやすさやキャリア観とのマッチ度、その企業ならではの強みなどを明確にしましょう。
その企業を率いている社長や会長の考え方・テーマは何か、現在の財政状況と今後の事業計画、これらは将来性の判断につながります。
これらは会社がどういう方向に向かおうとしているか知るポイントであり、自分が各企業の考えとどの程度一致しているか知り、安定して長く働ける企業を選びましょう。
⑤自分に合いそうな企業を絞り込む
企業分析でそれぞれの企業の特徴を明確にできたら、自分に合いそうな企業を絞り込みましょう。自己分析と企業分析が十分できていれば、それらを擦り合わせることで自分に合う理想的な企業を見つけられます。
企業を絞り込む際は、自己分析で明確にした「譲れない条件」と「妥協できる条件」をもとに各企業を再度チェックしましょう。
次に、譲れない条件をすべて満たす企業のうち、そのほかの条件が理想に近い企業をリストアップします。その後、再度条件をもとにそれらの企業を比較して、理想的な順番に並べるという工程を踏むのがおすすめです。
ポイントは「このなかの企業ならどこに就職しても不満は少ない」と思える企業のみをリストアップすることです。「譲れない条件」と「妥協できる条件」を厳格に定めておけば、再びミスマッチが起きる可能性を低く抑えられます。
実際に自分に合いそうな企業が見つかった人は、就活を進めましょう。就活の流れや志望動機作成の具体的なステップは、以下で詳しく解説しています。
就活の流れ5ステップ
就活の流れを5ステップで解説! 時期別の選考対策も紹介
志望動機
志望動機例文35選|基本とプラスアルファで差別化するコツ
志望動機の作り方
志望動機の作り方大全|就職支援のプロが好印象を残すコツを解説
志望動機の構成
志望動機はこの構成で決まり! 盛り込む6要素と伝える順番を解説
自己PRで悩んだらまずは作成ツールを使ってみよう!
「自己PRがうまく書けない」「どんな強みをアピールすればいいかわからない」…そんな悩みを抱えている方には「AI自己PR作成ツール」がおすすめです。
AIがあなたの経験やスキルに基づいて魅力的な自己PRを自動で生成し、短時間で書き上げるサポートをします。
短時間で、分かりやすく自分をアピールできる自己PRを完成させましょう。
就活のプロが解説! 自分に合う職業を見つけることの重要性
ここまで、自分に合う職業・企業の探し方を4ステップで具体的に解説しました。ここまでの内容が理解して実践すれば、自分に合う企業がいくつか見つかる可能性が高まります。
ただ、自分に合う職業を見つけるのは大変で労力が必要です。「本当にそこまでする価値があるの」と考えている人もいるかもしれません。
そこでここでは、就活のプロに自分に合う職業を見つけることの重要性を聞きました。なぜ適職を見つけることが重要なのか、〇〇さんの考えを参考にしてください。
アドバイザーコメント
小関 珠緒
プロフィールを見る今自分に合う職業を見つけなければずっと悩み続けることになる
ここまで読んで、自分に合う職業を見つけることに労力がかかりすぎると二の足を踏んでいる人もいるかもしれません。ですが、自分に合う職業を見つけることは、非常に大切ですので、ぜひがんばって取り組んでいきましょう。
なぜなら、ここで自分に合う職業を見つけずに、新しい仕事に就いたとしても、将来改めて「自分に合う職業は何か?」と考える可能性が高いからです。
早いうちに、合う仕事を見つければ、迷いも少なく、回り道する可能性も低くなります。
自分に合う職業を見つけられれば人生の満足度も高まる
仕事は、人生のなかで時間、労力ともに大きな割合を占めます。その時間や労力を自分に合わないことに使っているのは苦痛でしょう。
一方で、自分に合う仕事ができれば、パフォーマンスが発揮でき、人生の満足度も高まります。
ただ、自分に合う職業はすぐには見つからないかもしれません。また見つかったとしても、年齢や経験を重ねることで合う仕事が変わる可能性もあります。
時間をかけて、行動しながら確認し、検証していくという長いスパンで考えても構いません。慌てずどっしりと構えて、ひとつひとつ丁寧に向き合っていきましょう。
転職前に確認! 入社後のミスマッチを防ぐためにすべき4つの対策
転職前に確認! 入社後のミスマッチを防ぐためにすべき4つの対策
- ①今の企業の不満に感じる点を明確にしておく
- ②以前の就活でミスマッチが起きた理由を分析しておく
- ③過去の失敗をもとに転職後にミスマッチが起きないかチェックする
- ④複数社の適職診断を活用して客観的な視点も参考にする
ここまで、自分に合う職業を見つける重要性とその具体的な方法を解説してきました。自分に合う職業を見つけるには手間がかかる一方、理想的なキャリアの実現には大きなメリットがあることを理解できたと思います。
ここでは、企業とのミスマッチを防いで自分にあった職業に就くために、転職前に必ずチェックすべき4つの項目を解説します。
同じ失敗を繰り返さないよう、ミスマッチを防ぐための対策を確認して、志望企業が本当に自分に合っているかを見極めましょう。
①今の企業の不満に感じる点を明確にしておく
入社後のミスマッチを防ぐためにも、まずは今の企業で不満に感じる点をリストアップしておきましょう。今感じている不満やストレスに感じるポイントを明確にしておけば、同じ内容のミスマッチを繰り返さずに済みます。
不満に感じる点は自己分析同様に「なぜ?」を繰り返すことで、より本質的なミスマッチの原因を明確にできます。たとえば以下のように「なぜ?」を繰り返して不満の理由を明確にしていきましょう。
不満の理由を明確にする方法
- 職場の人間関係が良くない
↓なぜ? - 互いに競争し合う雰囲気があり、いがみ合いになっている
↓なぜ? - インセンティブ制度で過度な競争が生まれている
↓なぜ? - インセンティブ制度のメリットばかりに注目していた
上記の分析例から、制度一つひとつのメリットだけでなくデメリットまで考慮したうえで企業を選ぶべきという気づきを得られます。
なお、この分析で判明した条件は、自己分析の際に作成した譲れない条件に追加しておくとよりスムーズに自分に合う企業を見つけられます。
②以前の就活でミスマッチが起きた理由を分析しておく
今の企業で発生したミスマッチとその原因などを明確にしておくと、同じ失敗を繰り返すリスクをより低く抑えられます。複数企業で就業経験がある人は、過去のミスマッチをすべて分析しておけば、リスクをさらに低く抑えられます。
転職前に分析しておくべき項目は、以下のとおりです。
明確にしておくべき項目
- ミスマッチの詳細
- ミスマッチが発生した原因
- 入社前後の良いギャップ・悪いギャップ
- ギャップが生じた原因
分析の結果、「意外によかった」と感じた点やその理由も明確にしておけば、より自分に合う職業を見つけられる可能性を高められます。
③過去の失敗をもとに転職後にミスマッチが起きないかチェックする
転職先企業を決める際は、過去の失敗を繰り返さないようにすることが肝心です。自己分析だけでなく実体験にもとづいた対策を講じることで、効率良くミスマッチの原因を排除できます。
前述のとおり、過去のミスマッチの詳細・原因分析に加え、以下のような過去に経験したギャップの詳細・原因分析も有効です。
ミスマッチにつながるギャップの例
- ノルマはないと聞いていたが、実際はノルマに近い制度があった
- 若いうちから活躍できると思っていたら、実際は若手の裁量が小さかった
- 部署の希望が通りやすいと言われていたが、実際は年次が高まらないと異動制度を利用できなかった
自分がこれまでに感じたギャップやその原因を事前に分析しておけば、同じタイプのミスマッチを防げます。
- 過去に発生したミスマッチの原因やギャップは明確にできましたが、再発防止の具体的な方法がわかりません。どうしたら同じ失敗を繰り返さずにすみますか?
志望先で同じ問題が発生しないか入念に確認しよう
基本は転職先候補について、以前のミスマッチ原因と同様の問題が起こらないか確認することです。
たとえば、若いうちから裁量を任されることについて確認するなら、インターンシップや面接の際に、それに該当する実例やどのような実績によってそれが実現したのかを尋ねてみましょう。
そして、尋ねる対象はできるだけ現場の人を選ぶことがおすすめです。
また、ノルマの考え方について「ノルマがない」と言われた場合、通常は目標管理をするものだと思いますが、それはどのようにおこなわれているのか尋ねるなどしてください。
できるだけ具体的に教えてもらうことが大事です。
そのような確認をおこなうことは面接等で不利になるものではなく、信念に基づいて真摯に尋ねることで評価につながる場合もあります。
就職はゴールではなく、その先の長い職業人生の始まりです。悔いの無いよう、懸念は残さないでください。
④複数の適職診断を活用して客観的な視点も参考にする
自分に合う職業を探す過程で、複数の適職診断を活用するのも効果的です。適職診断は自分が入力した情報をもとに客観的に適職を判断してくれます。適職診断は他己分析の一環として取り入れるのがおすすめです。
最近は詳細な情報をもとに、自分の経験やスキル、志向に合った適職を教えてくれる診断ツールもあります。自己分析だけでは気づけなかった条件や、適職の選択肢が見つかることもあります。
適職診断ツールは、以下の観点で選ぶのがおすすめです。
適職診断ツールの選び方
- 無料で利用できるか
- 口コミの数が多く、評価が高いか
- 具体的な職業と適職の条件の両方を提示してくれるか
- 向いていない職業もあわせて教えてくれるか
このように、自己分析・他己分析に加えて適職診断ツールの結果も参考にすれば、自分に向いている職業がさらに見つかりやすくなります。
自分に合う職業を探す参考に、適職診断ツールを使うのも悪くありません。
どれが良いかは人によって違うため、試しにどれかを一回使ってみるのがおすすめです。
その結果をもとに、キャリアカウンセラーなど専門家に相談すると、より自分に合う仕事が見つかりやす口なります。
自分に合う職業が見つからない場合にとるべき3つの対処法
自分に合う職業が見つからない場合にとるべき3つの対処法
- ①仕事の幅を広げて適職がないか検討してみる
- ②やりたくないことから消去法で再度考えてみる
- ③転職エージェントに相談する
ここまで読んで、上記の4ステップで自分に合う職業を見つけられなかった人もいるかもしれません。ここからは、そんな人に向けて適職を見つけるための3つの対処法を紹介します。
ここまでの4ステップをもとに以下の方法を実行すれば、自力で適職を見つけられなかった人でも理想的なキャリアを実現できる職業が見つけられる可能性が高まります。
また、下記3つは組み合わせて使うことも可能です。それぞれの方法を活用して、自分に合う職業を見つけてください。
ESで悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!
『就活準備をもっと効率よく進めたい...!』と思っていませんか?「就活準備プロンプト集」は、生成AIを活用して自己PRや志望動機をスムーズに作成できるサポートツールです。
簡単な入力でプロが使うような回答例が出せるため、悩まずに就活準備を進められます。生成AIを活用して効率良く就活準備を進めたい人におすすめです。
- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト
- チャットを使用した、模擬面接プロンプト
- 自己PRで使える強み診断プロンプト
①仕事の幅を広げて適職がないか検討してみる
そもそも自分に合う職業が見つからない人は、業界・企業の選定時に仕事の幅を絞りすぎている可能性が高いです。自分に合う職業が見つからなかったら、一度以下のポイントを見直してみましょう。
見直すべきポイント
- 自己分析で自分の価値観を正しく理解できているか
- 自己分析と他己分析をもとに的確に「合う」を定義できているか
- 企業分析で適切な情報を集められているか
- 自分に合いそうな企業をもれなく選定できているか
自分に合う職業が見つからなかった場合、「合う」の定義を厳しくしすぎていないか、譲れない条件と妥協できる条件の境界が適切か見直してみてください。
その後、自己分析と企業分析の擦り合わせまでの要所をそれぞれチェックすることで、自分に合う企業を見落としていないか網羅的にチェックできます。
②やりたくないことから消去法で再度考えてみる
自己分析や企業分析を再考しても自分に合う職業が見つからない人は、一度やりたくないことから考えてみるのもおすすめです。
自分に合う職業を絞っていくのではなく、合わない職業を消していくことで自然に合う職業が浮き彫りになることもあります。
やりたくないことをもとに消去法で考える場合も、同様のステップで自己分析や企業分析に取り組みましょう。
消去法で考える際の具体的なステップ
- 自己分析で過去〜現在までの自己を深掘りする
- 自分にとっての「合わない」の条件を言語化する
- 企業分析後、それぞれの企業情報を整理して条件を比較する
- 自分の「合わない」に当てはまる企業・職業を消していく
消去法にて残った企業を再度自分の価値観・考え方と比較してみましょう。やりたくないことを明確にするだけで、一気に視野が広がり自分に合う職業・企業が見つかることもあります。
- 消去法で自分に合わない職業・企業の条件を明確にできたら、その後はどのようなステップで進めれば良いのでしょうか。
自分に合わない職業以外を網羅的に見て合う仕事を見つけよう
消去法で自分に合わない職業・企業の条件を明確にできたら、それ以外の職業をえり好みせず、視野に入れていきましょう。以前より、選択の範囲が広がっているはずです。
また、その条件を転職エージェントの担当者やキャリアカウンセラーに伝えると、これまでの自分では選ばなかった職業を提案されることもあります。
好き嫌いは別にして、その職業についてリサーチしてみる、一度応募してみるなど行動に移してみましょう。
動いていくなかで、「予想とは違って、自分に合う仕事だった」という気付きが得られるかもしれません。
③転職エージェントに相談する
試行錯誤しても自分に合う職業が見つからない人は、キャリアのプロである転職エージェントに相談してみましょう。
転職エージェント
採用を検討する企業の募集条件と転職希望者の情報をもとに、両者にとって理想的なマッチングを支援するキャリアのプロ。転職支援のノウハウが豊富なため、転職希望者が自分で転職先を探すよりも効率的、かつ理想的な転職を叶えられる可能性が高い。
専任のアドバイザーとの面談を重ね、自分の適正やスキル、経験をもとに企業とのマッチメイクをおこなってもらえます。転職の全工程をサポートしてもらえるため、安心して任せられるのも転職エージェントの魅力です。
自力で理想的な転職先を探すのが難しいと感じた人は、転職支援のプロに一度相談してみてください。
SNSや他人の評価で選ぶのではなく、話してみて自分と相性が良い人物を選びましょう。
きちんとあなたの話を聞いて、あなたの意向を尊重しつつプロとしての助言も適切にできる人。
とにかくたくさん受けろと言わない人。そして合わないと感じたら担当を変えることです。
自分に合う職業への転職を成功させて満足いくキャリアを実現しよう
この記事では自分に合う職業を見つけるための具体的な方法や、適職に就く重要性を解説しました。自己分析から始まる4ステップを実行すれば、理想的なキャリアを歩める可能性が一気に高まります。
自分に合う職業を見つけるのは労力がかかる作業ですが、適職にはそれだけの価値があります。今まったく自分に合う職業がまったく見当がつかない人でも、着実に分析すればきっと適職が見つかるはずです。
記事で紹介した方法を丁寧に実践し、ミスマッチを防ぎながら理想の就職に向けて進み始めましょう。
アドバイザーコメント
木原 渚
プロフィールを見る自分に合う職業を探すには最初に自分を知ることが重要
「自分に合った職業や企業がわからない」と感じるのは、多くの人が経験する自然なことです。社会的に「良い」と言われる企業が必ずしも自分にとって良い企業とは限りません。焦らずにまずは、自分を知ることから始めましょう。
自分自身の価値観、興味、得意なこと、これまでの経験などを振り返ることが大切です。また、世の中にはまだ知らない仕事や企業がたくさんあります。
企業のホームページや採用情報だけでなく、社員のインタビュー記事、SNS、口コミサイトの情報に加え、インターンシップや説明会に参加することで、職場の雰囲気や実際の業務を体感することができるでしょう。
自分に合う職業を見つけられれば人生の満足度が高まる
適切な職業選択ができれば、人生全体の満足度が高まります。しっかりと4つのステップを踏み、できるだけミスマッチを防ぐことが必要です。
ただし、最初から完璧な企業や職業を探さないことも大切です。すべての条件を満たす仕事や企業はほとんど存在しません。
どんな選択肢を選んだとしても、それが新たな学びや成長につながり、自分らしいキャリアを築く土台となるはずです。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi





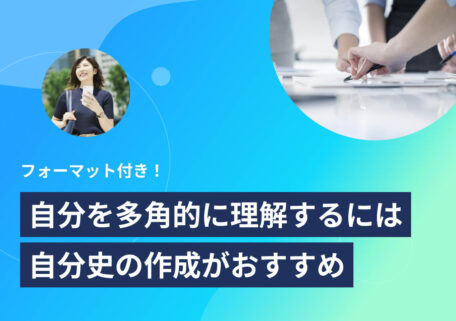














3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/1級キャリアコンサルティング技能士
Nagisa Kihara◯放送・行政・人財開発など多様な職種を経験する中でキャリア支援に興味を持つ。一人ひとりが楽しく働き、豊かに生きられる社会を目指し、現在はカウンセラーや研修講師として活動中
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/ヒトノビ代表
Tamao Koseki〇就職時は準備不足で苦労するも大手企業に入社。転職して実用書の編集者を10年経験し、独立。キャリアコンサルタント資格を取得し、現在は強みを引き出して活かす人材育成をおこなう
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリア・デベロップメント・アドバイザー
Rie Kuwata〇2018年にキャリアコンサルタントとして独立。企業対象の研修講師や各学校でのキャリアカウンセラーを経てハローワーク就職支援ナビゲーターを務め、年間約3,000名の相談を受けている
プロフィール詳細