この記事のまとめ
- 造船業界は日本の貿易量の99.6%を支える重要な産業
- 日本の造船業界は最新技術を駆使して海外の競合に対抗している
- 造船業界には文系・理系それぞれが活躍しやすい職種がある
造船業界に興味がある人のなかで「造船業界の具体的な仕事内容がイメージできない」「将来性に不安がある」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
造船業界は日本の貿易を支える重要な産業です。近年では、韓国や中国との競争激化や環境規制の強化など、さまざまな変化に直面しています。そのため、業界の現状や将来性を正しく理解したうえで、自身のキャリアプランを考えることが重要です。
また、造船業界には設計・開発から生産管理、営業までさまざまな職種があるため、自身の強みを活かせる分野を見つけることが就活を成功させる鍵となります。
この記事では、キャリアコンサルタントの隈本さん、野村さん、楳内さんのアドバイスを交えつつ、造船業界の基礎知識や職種別の仕事内容について詳しく解説します。造船業界への理解を深め、自身のキャリアの選択肢として検討したいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
造船業界は日本の貿易を支える重要な産業の一つ
造船業界は日本の製造業の中核を担い、高度な技術力と品質で世界から評価されている重要な産業です。日本の造船技術は世界トップクラスの競争力を持ち、特に環境性能や燃費効率に優れた船舶の開発において強みを発揮しています。
また、造船業は関連産業への波及効果も大きく、舶用機器メーカーや素材産業など多くの企業と連携して日本のものづくりを支えているのです。
この記事では、造船業界の現状や課題、将来性まで幅広く解説します。まずは造船業界の全体像を把握し、業界特有の魅力や仕事内容について理解を深めていきましょう。
また、造船業界で活躍している人に共通する特徴や求められるスキルも解説します。自身の強みを活かせる職種を見つけるための判断材料として参考にしてください。
そして記事の後半では、造船業界の就職難易度や選考対策について解説します。実際に造船業界へのキャリアを検討するなら、造船業界での就活の実態を押さえておきましょう。
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
まずはここから! 造船業界の基礎知識
まずはここから! 造船業界の基礎知識
- 造船業界とは
- 造船の流れ
- ビジネスモデル
- 平均年収
造船業界に興味がある人は、まず業界の仕組みや特徴を理解することがキャリアの第一歩です。造船業界は高度な専門技術と長い歴史を持つ産業であるため、基礎知識を身に付けることで業界特有の魅力や課題を把握しやすくなります。
ここでは、造船業界の基礎知識である造船の流れやビジネスモデルなどを解説します。これらを理解してこれから進める企業研究や職種選びの土台を作り、より具体的に自身のキャリアを検討できるようにしましょう。
造船業界とは
造船業界は、船舶の設計・製造をおこなう産業で、日本においては江戸時代から続く長い歴史を持っています。特に戦後の高度経済成長期には、日本の造船業は1956年から8年間世界一の建造量を誇り、国の基幹産業として経済発展を支えてきました。
日本は資源や食料の多くを海外に依存していて、四方を海に囲まれた島国という地理的特性から、海上輸送が物流の中心となっています。
経済産業省の参考資料によると、日本の貿易量の99.6%は海上輸送によるもので、造船業はこの海上輸送をおこなうための船舶を提供する重要な役割をはたしているのです。
エネルギー資源や原材料の輸入、自動車や電子機器などの工業製品の輸出において、海上輸送は欠かせない存在であり、造船業界は日本の経済活動を根底から支える基盤産業として安定した需要を持ち続けています。
造船業界への理解を深めたい人は、関連業界である以下の海運業界についての記事もチェックしておきましょう。海運業界の特徴やビジネスモデル、大手企業について解説しています。
あなたが受けないほうがいい業界・職種を診断しよう
就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。
そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。
自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
造船の流れ
造船は複雑な工程を経て完成します。近年の大型船舶は生産効率が高いブロック建造方式によって作られています。
ブロック建造方式
船体を複数のブロックに分けてそれぞれ作り、各ブロックを溶接して完成させる方法
おもな造船の流れは以下のとおりです。
ブロック建造方式による造船の流れ
- 受注:船主の希望に合わせた内容で契約
- 設計:船の仕様を満たす設計図面の作成
- 水槽試験:模型を使い、性能や必要な出力を確認
- 資材発注:鋼板や機器類を製鉄所や舶用機器メーカーから調達
- 加工・組立:鋼板の切断・曲げ加工などでブロックを製作
- ブロック搭載:大型クレーンで船台やドックに運び船の形に組立
- 進水: 完成した船体を初めて水に浮かべる
- 艤装:エンジンや航海計器、船室の取り付け
- 試運転・引渡し:性能確認後、船主に完成品を引き渡す
ブロック建造方式による造船は、数年かけて完成となるのが一般的です。大型船の場合、数百人から数千人の技術者や作業員がかかわる大規模プロジェクトとなり、造船所の広大な敷地内で幅広い専門技術が結集し、一隻の船が誕生します。
ビジネスモデル
造船業界のビジネスモデルは、おもに受注生産を基本としています。船主や海運会社からの発注を受けて、船舶の設計・建造をおこない、完成した船舶を引き渡すことで収益を得る仕組みです。
造船所は船種ごとに特化した技術や設備を持ち、さまざまな種類の船舶を建造します。大型の商船では1隻あたり数十億円から数百億円の価格となり、受注から引き渡しまでには1〜3年程度の期間がかかるのが一般的です。
造船業界の特徴として、為替変動の影響を大きく受けることが挙げられます。円高になると海外の造船所と比較して価格競争力が低下するため、収益に影響が出やすい構造となっています。
また、鋼材価格の変動も利益に直結するため、資材調達のタイミングや交渉も重要な要素です。
ただし、受注後に為替変動による船価の変更は基本的におこなわれないため、大きな為替変動があり、新たな受注数が減ったとしても、すでに受注している生産分で数年程度は事業が続けられるのが特徴です。
- 造船企業は、船を受注できないと収益がゼロになってしまうのでしょうか?
受注がなくてもほかの収入源を確保できる
造船企業は、船の受注が減ると収益に大きな影響を受けますが、既存の船舶修理やメンテナンス、橋梁事業などをおこなうことで安定した収益を確保しているところもあります。
大手造船企業においては、環境に配慮した新しい船の開発や造船技術を活かした洋上風力発電の基礎構造製造など、単に船を造るビジネスにとどまらず、幅広い事業を展開しています。
また中小企業においては、独自技術による高付加価値船に力を入れ、国際的競争力を高めるために奮闘しているのです。
あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
平均年収
求人ボックスによると、造船業界の正社員の平均年収は約447万円です。月給に換算すると約37万円となります。また、国税庁の令和5年民間給与実態調査によると、日本の給与所得者の平均年収は460万円なので、造船業界の平均年収はそれをやや下回る水準です。
造船業界の給与分布を見ると、最も多いのは年収305〜376万円の人で、業界内での給与幅は全体で305〜875万円と幅広くなっています。つまり、勤務先の規模や職種、経験年数によって待遇が大きく異なる傾向があるのです。
特に設計職や管理職など専門性の高いポジションでは、平均を大きく上回る年収が期待できます。造船業は技術の蓄積が重視される業界のため、長期勤続によるスキルアップに応じて給与も上昇する傾向があります。
また、船舶の建造現場では、造船工程の遅れによる残業や夜勤などの手当が加算されることで、収入が増加するケースもあるのです。
激しい競争! 日本の造船業界の現状・課題
激しい競争! 日本の造船業界の現状・課題
- 世界シェア3位の技術力を誇る
- 韓国・中国との価格競争に直面している
- カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが求められる
日本の造船業界は世界有数の技術力を誇る一方で、韓国や中国との厳しい国際競争に直面しています。近年は価格競争力の低下や環境規制の強化など、さまざまな課題へ取り組む必要があるのです。
ここでは、日本の造船業界の現状や課題について解説します。業界が持つ高い技術力という強みと、国際競争や環境規制などの課題を理解して、自身が造船業界に貢献する方法を考える手がかりにしましょう。
世界シェア3位の技術力を誇る
経済産業省の参考資料によると、船舶建造量で比べた世界シェア上位は、以下のとおりです。
2022年時点の造船業界の世界シェア
- 中国:45%
- 韓国:29%
- 日本:17%
日本の造船業界は長年培ってきた高度な技術力により、世界シェア3位の地位を維持しています。船舶の設計から建造、メンテナンスに至るまでの一貫した技術力は海外からも高く評価されていて、日本の造船所で建造された船は高い信頼性と品質で知られているのです。
また、日本の造船技術は大型客船のような、高い専門性と精密な技術を要する高付加価値船において優位性を保っています。これらの船舶は単なる輸送手段ではなく、最先端技術の集合体として非常に複雑なシステムを要するため、日本の緻密な製造技術が活きる分野です。
また、日本の造船所で建造された船舶は長期間安定して運航できるため、船舶の安全性や耐久性においても世界トップレベルの評価を受けています。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
韓国・中国との価格競争に直面している
日本の造船業界は韓国や中国の急速な台頭により、厳しい価格競争に直面しています。特に韓国は政府の手厚い支援によって大型タンカーやコンテナ船分野で強みを持ち、中国は豊富な労働力と低コストを武器に建造量を急増させています。
日本の造船業界は人件費や製造コストが高く、純粋な価格競争では不利な状況に置かれているため、高い技術力を活かした高付加価値船への特化や生産効率の向上に努めているのです。
しかし、日本の造船業界は若年層の人材不足も深刻な問題となっているので、世界市場でのシェア拡大は簡単ではありません。高齢化による技術者の減少と新規人材の確保難により、技術継承が課題となっているため、若手エンジニアの採用・育成は日本の造船業界全体の課題といえます。
日本の造船業界は、省エネ技術や環境規制に対応した高付加価値の船で競争力を保っています。
国際的な環境規制が厳しくなるなかで、省エネや低炭素技術を求める需要が増え、日本の高い技術力で安定した収益が見込めます。
カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが求められる
カーボンニュートラル
温室効果ガスの排出量をゼロにすること。2020年10月に日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言した
国土交通省の国際海運2050年カーボンニュートラルに向けた取組によると、造船業界では、2050年までにカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが急務となっています。
国際海事機関(IMO)による温室効果ガス排出規制の強化を受け、環境負荷の低減が競争力を左右する重要な要素となりつつあるのです。
国際海事機関(IMO)
船舶の安全や船舶からの海洋汚染の防止など、海事問題に関する国際協力を促進する国連の専門機関。International Maritime Organizationの略
具体的には、水素やアンモニアなどのクリーンエネルギーを燃料とするゼロエミッション船の開発・普及が進められています。日本の造船企業はそれぞれの技術を活かし、低炭素・脱炭素技術の開発に注力していて、次世代環境対応船の実用化を目指しています。
ゼロエミッション
人間の活動による排出をできる限りゼロにする取り組み
また、船舶建造過程においても環境負荷低減の取り組みが始まっていて、グリーンスチールの活用や、造船所における省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入なども課題です。
グリーンスチール
生産時の二酸化炭素などの排出量を削減した鉄鋼材料のこと
これらの環境対応は追加コストをともないますが、将来的な国際競争力維持のためには避けて通れない課題であり、技術開発と人材育成が急務となっています。
- 船舶に環境負荷の低さが求められると、造船の受注にどれだけ影響するのでしょうか?
世の中の低環境負荷の動きによる影響は大きい
環境負荷の少ない船舶へのニーズは確実に高まっていて、環境性能は造船業界の「競争力の源泉」であり、造船の受注にも大きな影響を与えています。
国際的にはIMO(国際海事機関)が、CO2排出削減や燃費効率の改善など規制を強化しています。
そのため、船主や運航会社は環境基準をクリアした船舶を求める傾向が強くなり、造船企業も新規受注には環境対応力が必要とされているのです。
また、企業が環境負荷の少ない船舶を保有することで、「脱炭素に積極的な企業」というブランド価値が高まり、企業の安定的な成長がかかわるESG投資の対象にもなりやすくなります。
運航コストの削減や、港湾での環境規制への適応もしやすくなるなど、実利面でのメリットもあります。
所要時間はたったの3分!
受けない方がいい職業を診断しよう
就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。
就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。
- 自分に合う職業がわからない人
- 入社後のミスマッチを避けたい人
- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人
最新動向から紐解く! プロが語る造船業界の今後の将来性
国際競争が激化していることを知り、造船業界の将来性について不安を感じている人も多いのではないでしょうか。確かに韓国や中国との競争激化などの課題はありますが、環境規制強化や技術革新を背景に、実は新たな成長機会も生まれています。
ここでは、造船業界の将来性について、次世代船舶の開発による新市場創出と、世界の海上物流量増加による安定需要という2つの観点から解説します。造船業界の将来性を見極めて、キャリア選択の判断材料にしましょう。
以下のQ&Aでは、海運業界の今後についてキャリアコンサルタントが解説しています。造船業界にも関連する内容なので、併せて目を通して理解を深めましょう。
次世代船舶の開発で新たな市場を創出している
日本の造船業界は、環境規制が強化されたことを技術革新のチャンスに変えるべく、次世代船舶の開発に積極的に取り組んでいます。
特に水素やアンモニアを燃料とし、利用時に二酸化炭素を排出しないゼロエミッション船の開発は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた重要な施策です。
国内では、ジャパンエンジンコーポレーションやIHI原動機が世界初となるアンモニア燃料と重油の混焼運転試験を開始し、すでに技術開発で先行しています。
政府もグリーンイノベーション基金を活用し、長期的な支援をおこなうことで、新燃料対応エンジンや燃料タンク・供給システムの開発を後押ししています。
グリーンイノベーション基金事業
カーボンニュートラルの実現に向けた企業の研究開発を支援する国の基金事業。総額2兆円の基金により、最長10年間の継続的な支援を受けられる
この取り組みにより、2020年代後半から始まる環境対応船への代替需要を取り込み、建造量の増加が見込まれています。さらに鉄鋼業界との連携によるグリーンスチールの活用など、ほかの産業への波及効果も生まれつつあるのです。
グリーンイノベーション基金による支援が終わった場合、一時的に新規採用は減少する可能性があります。
ただ、長期的に見れば環境技術の重要性自体は変わらず、環境規制は強化され続けるため、特に大手造船企業では環境技術系採用が続くと考えられます。
世界の海上稼働量が増加することで需要が安定的に拡大している
経済産業省の参考資料によると、世界の海上貨物輸送量は、1990年から30年間で毎年平均約3.5%の成長を続けていて、今後も拡大することが見込まれています。
輸入依存度の高い日本にとって、海上輸送は貿易量のほとんどを担う重要な輸送手段であり、海運業界の基盤となっているのです。
国際的には、2022年時点で世界第3位の船腹量を誇る日本の商船隊は、国際海運市場で高い競争力を持っています。さらに、IMOが2050年頃までのゼロエミッション達成を国際目標として掲げた影響で、環境対応船への需要は今後急増すると予測されています。
同時に、G7などの国際枠組みで推進されているグリーン海運回廊構想により、特定航路でのゼロエミッション船の運航に向けた動きも加速しているため、環境性能の高い船舶への需要はさらに高まることが期待されているのです。
グリーン海運回廊
海運に必要な燃料の製造・輸送時の排出から船上排出を含めたサイクル全体で、低・脱炭素化された燃料や技術が導入された航路のこと
G7
自由民主主義国かつ先進国で形成された国際会議。カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・日本・イギリス・アメリカの7か国を指す
- 将来的に環境性能が高い船への需要が低下して、日本の造船業界が国際競争でさらに不利になる可能性はあるのでしょうか?
環境関連のニーズが今後なくなるとは考えにくい
環境性能が高い船への需要が完全になくなる可能性は低いと考えられます。国際的な環境規制は年々強化されていて、CO₂排出削減やエネルギー効率向上は長期的な課題となっています。
特に、欧州を中心にカーボンニュートラルの目標が厳格化され、海運業界でも環境配慮型の船舶が求められ続けるでしょう。
一方で、燃料技術の進化や新たな規制の変化により、現在の環境技術が時代遅れになるリスクはあります。
そのため、日本の造船業界は水素・アンモニア燃料船など次世代技術の開発を進め、柔軟に対応することが重要です。
競争力維持には、環境技術だけでなく、コスト削減や効率的な生産体制の構築も欠かせません。
就職する業界を選ぶうえで将来性を重視したい人には、以下の記事がおすすめです。成長の可能性が高い13業界や、これから伸びる業界に就職するための準備について解説しています。
職種別! 造船業界の仕事内容
職種別! 造船業界の仕事内容
- 設計・開発
- 生産管理・製造管理
- 営業
- 資材調達
造船業界では多様な職種が連携して一隻の船を完成させるため、それぞれの専門性が重要です。設計・開発から始まり、生産管理や製造管理・営業・資材調達など、各工程で異なる専門知識やスキルが求められます。
ここでは、造船業界のおもな4つの職種について解説します。造船業界のキャリアを検討する前に、どのような職種があるのか理解しておきましょう。
設計・開発
造船業界の設計・開発職は、船の図面を作る仕事です。依頼主の希望に合わせて、船の大きさや速さ、性能などを決め、パソコンで詳しい設計図を描きます。
3DCADなどの設計ソフトを使って詳細な設計図を作成したあと、設計した船が実際に性能を発揮するかを確かめるために、水槽試験用の模型を製作して実際の航行状態をシミュレーションします。
試験結果に基づいて設計の修正や改善をおこない、他部門と連携して設計の実現可能性を検討することも業務の一部です。
3DCAD
立体データを設計するためのソフトウェア。3次元CADとも呼ばれる
設計・開発には、造船工学や機械工学の専門知識、数学や物理の基礎力を活かした構造計算や性能予測能力が求められます。近年は環境規制が厳しくなり、燃費性能や環境技術に関する最新知識も必須です。
さらに、他部門の設計・開発職や生産現場と連携して設計を進めるため、技術的なスキルや知見だけではなく、チームでの協働力とコミュニケーション能力も求められるのが特徴です。
設計開発職について理解を深めたい人は、こちらの記事をチェックしておきましょう。設計開発と混同しやすい職種や、設計開発に必要なスキルを解説しています。
生産管理・製造管理
生産管理・製造管理職は、設計図をもとに実際に船を効率良く造る工程を管理する仕事です。船は完成まで数年かかる大規模なプロジェクトなので、工程表作りや品質チェック、予算管理などを適切におこない、納期どおりに製造を進めることが重要です。
また、建造現場でのトラブル対応や納期遅延を防ぐための先読み判断、予算内での建造完了のための調整も業務の一部です。造船所では天候の影響で工期が遅れることもあるため、そのような状況でも納期を守るための代替案を素早く提案し、実行する必要があります。
このように生産管理・製造管理は、プロジェクト全体を俯瞰するマネジメント能力や、多くの作業員や部署と連携するためのコミュニケーション能力が求められます。
営業
造船業界の営業職は、新規顧客の開拓や既存顧客との関係維持を通じて船舶の受注を獲得する仕事です。
具体的には、船舶市場の動向調査、見込み顧客への提案資料作成、商談、契約交渉、納船後のアフターフォローまでを担当します。数十億から数百億円という高額な商談を進めるため、船価や納期・性能などの条件交渉も重要な業務です。
さらに、海外の顧客との取引が多いため、英語での商談や提案書作成もおこないます。また、顧客と長期的な信頼関係を構築するために、契約後も建造状況の報告や、引き渡し後のサポート体制の整備なども業務の一部です。
このように、造船業界の営業職は、顧客に自社の船舶をアピールするための船舶に関する知識や高度な営業力・語学力や財務に関する知識など、高度な幅広い知識が求められます。
メールや電話、現地でのプレゼンなどの業務があるため、ビジネス英語での会話力や読解力、文章作成力が必須です。
TOEICでいえば700~800点レベルが求められると考えておくと良いでしょう。
造船業界での営業活動はBtoBに分類されるため、こちらの記事をチェックしてBtoB営業への理解を深めておきましょう。BtoC営業との違いや、BtoB営業の手法・仕事内容を解説しています。
資材調達
資材調達職は、船舶建造に必要な鋼材やエンジン、各種機器などの資材を適切なタイミングかつ、適正な価格で調達する仕事です。具体的には、必要資材の洗い出し、仕様決定、見積依頼、価格交渉、発注、納期管理までの一連の業務を担当します。
一隻の船には膨大な量の資材が必要となるため、資材調達職は船舶を計画どおり建造するうえで重要な仕事です。
そのため、資材調達職は、資材の品質や鋼材相場などの市場動向を見極められる専門知識と、国内外の取引先との価格交渉や納期調整をおこなうためのコミュニケーション能力や語学力が求められます。
さらに、生産部門と連携し、必要な資材を過不足なく調達するための調整力や、予期せぬ事態に対応できる柔軟性も必要です。
このように、造船業界の資材調達職は、社内外の人々との調整力や、さまざまな資材とその市場にかかわる専門的な知識も求められる高度な職種といえます。
理工系の知識が活かせる設計職や生産管理職は、新卒から目指しやすいです。
一方で、営業職は専門知識の習得が必要であり、研究職は高度な学位が求められるため、新卒にはハードルが高く入社後の勉強や経験が欠かせません。
造船業界で製造される船の種類
造船業界では、輸送する貨物の特性に合わせてさまざまな種類の船舶が製造されています。それぞれの船は特定の役割をはたすために設計されていて、構造や設備が大きく異なるのです。
ここでは、造船業界で製造されるおもな5種類の船舶について解説します。造船業界では企業によって建造を得意とする船舶の種類が異なるため、各社の特徴を理解するためにもチェックしておくことが大切です。
タンカー:石油や化学薬品を輸送する
タンカーは、原油やガソリンなどの石油製品や、液体化学製品などの液体貨物を輸送する専用船です。船内には複数のタンクがあり、それぞれ異なる種類の液体を輸送できるよう設計されています。
タンカーはサイズによって種類が分かれていて、VLCC(Very Large Crude Carrier)と呼ばれる最大級のタンカーは、載貨重量トン数が20〜32万トンもあります。
液体貨物を輸送するタンカーは、事故が発生した際の海洋汚染防止のために、貨物が海上へ漏れ出さないように二重船殻(ダブルハル)構造が採用されているのが特徴です。
さらに、近年は、環境規制の強化に対応するため、一般的に燃料として使われる重油ではなく、LNGやメタノールなどの低環境負荷燃料を使用する船も増えつつあります。
環境規制の影響によって今後タンカー製造は衰退に向かうかどうかは国際マーケットによるところが大きいです。
しかし、国際的な環境規制の強化により、タンカー製造は新たなニーズや技術の進化に適応する形で変化していくのではないでしょうか。
そのため、タンカーだから衰退すると決めつけるのではなく、どの企業が環境技術に力を入れているのかをリサーチしたり、タンカー造船だけでなく海運なども含め広い視点で業界や企業研究したりすると良いでしょう。
船舶を使う主要な業界の一つとして、エネルギー業界が挙げられます。以下の記事ではエネルギー業界の基礎知識や専門用語について解説しているので、併せてチェックしておきましょう。
バルカー:石炭などの資源を梱包なしで輸送する
バルカーは鉄鉱石や石炭・穀物・塩・木材チップなどのさまざまな資源を大量輸送するための船舶です。資源は梱包せずにそのまま大量輸送するため、ばら積み船とも呼ばれます。船体には複数の船倉があり、ハッチカバーを開けて貨物を積み下ろす構造になっています。
船倉
船の甲板上部にある貨物を積んでおく場所。英名のCargo Hold(カーゴホールド)と呼ぶ現場もある
バルカーは用途やサイズによって種類が分かれていて、最大級のケープサイズは18万トン前後、パナマ運河を通れる最大サイズのパナマックスは8万トン前後、さらに小型のハンディマックスやスモールハンディなどがあります。
貨物の特性に合わせた専用船もあり、鉄鉱石船は比重が大きく重い鉄鉱石を効率良く運ぶため船倉が狭く設計され、木材チップ船は軽い貨物を運ぶため船倉容積を大きくするなどの工夫がされているのが特徴です。
日本の造船業界は、特にこれらの専用バルカーの建造で高い技術力を発揮しています。
コンテナ船:加工した製品を輸送する
コンテナ船は、海上コンテナに貨物を収納して輸送するための船です。衣類や電子機器、食品など多種多様な加工品を一度に大量輸送でき、定期的に決まった港を訪れます。
近年のコンテナ船は大型化が進み、最大船型は全長は約400m、幅約59mです。この船体には全長約6m、高さ約2.5mの20フィートコンテナを20,000個以上積載できます。
コンテナには貨物の特性に合わせて、一般的な貨物用のドライコンテナ、冷凍・冷蔵貨物用のリーファーコンテナなどさまざまな種類があります。
陸上の輸送機関との積み替えが簡単なため、船から直接トラックや鉄道に積み替えることができ、効率的な輸送を実現しているのです。
コンテナ船の大型化が進んでいる背景には、世界的な物流量の増加と、1回あたりの輸送コストを抑えるニーズがあります。
日本国内でも、大型船が寄港できる港湾設備の整備や陸上輸送との連携強化が求められ、物流インフラ全体の見直しが進んでいます。
LNG船:液化天然ガスを安全に輸送する
LNG
液化天然ガスのこと。Liquefied Natural Gasの略
LNG船は、天然ガスをマイナス161.5度で液化した液化天然ガスを輸送する船舶です。天然ガスは液化することで体積が約600分の1になるため、大量輸送が可能になります。
LNGは燃焼時に発生する二酸化炭素の量が少なく、環境に優しいクリーンエネルギーであるため、需要が増加しています。
LNG船の最大の特徴は、超低温の液体を安全に運ぶための特殊なタンク構造をしている点です。タンクには超低温に耐えるニッケル鋼やアルミ合金が使用され、厚い断熱材で包まれています。
輸送中に自然に気化するガスは船の推進エネルギーとして利用され、環境負荷を低減しています。
その他の船
造船業界では、ここまでで解説した主要船舶以外にも、特定の用途に特化した多様な専門船が建造されています。以下のような船舶は、それぞれ独自の構造や設備を持ち、海洋産業や物流、エネルギー開発などの分野で重要な役割をはたしています。
| 船舶の種類 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自動車船 | 完成車やトラックなどの車両を輸送する | 複数の駐車デッキを持ち、車両が自走して乗り降りするRORO方式を採用し、最大8,500台の車両を積載できる |
| クルーズ船 | 旅客に船旅を提供する | レストラン、劇場、プールなどの娯楽施設を備え、船自体が目的地となる豪華な設備がある |
| フェリー | 旅客と車両を同時に輸送する | 車両甲板と旅客区画を併せ持ち、国内の島間輸送や長距離輸送に活躍している |
| ケーブル敷設船 | 海底通信ケーブルの敷設・保守をおこなう | 精密な位置保持システムと専用のケーブル敷設機器を装備している |
| タグボート | 大型船の離着岸補助や曳航をおこなう | 小型ながら強力な推進力と高い操縦性能を持つ |
| 重量物船 | 大型機械や建造部材などの重量物を輸送する | 強力なクレーンを装備し、船倉は大型貨物に対応した設計をしている |
| FPSO | 海洋上で石油・ガスの生産・貯蔵・積出をする | 海底油田から原油を生産・処理し、タンカーへの積出までおこなう浮体式の設備を装備している |
| シャトルタンカー | 海洋上石油生産設備から原油を輸送する | 洋上での荷役に対応する特殊設備を装備している |
| サブシー支援船 | 海底設備の設置・保守作業をおこなう | 水中作業ロボットや深海対応クレーンを装備している |
| 洋上風力発電設備設置船 | 海洋上に風力発電の風車を設置する | 海底まで伸ばせる複数の脚で船体を持ち上げ、安定した作業台として機能する |
これらの特殊船は、造船技術の進化とともに常に発展していて、社会インフラやエネルギー供給、環境問題への対応など、さまざまな分野で重要な役割をはたしています。
国内トップシェア! 造船業界の大手企業
日本の造船業界は、高い技術力と品質で世界的に評価されていて、その中核を担うのが国内の大手造船企業です。これらの企業は、それぞれ独自の強みや得意分野を持ち、日本の造船業界の競争力を支えています。
ここでは、日本の造船業界の大手企業について解説します。各企業の特徴や事業内容、技術的な強みを比べて、造船業界への理解を深めましょう。
今治造船
今治造船は、愛媛県今治市に本社を置く日本最大の造船企業です。2022年の建造実績では国内シェア35%を占め、業界トップの地位を確立しています。
今治造船は本社・今治工場のほか西条工場や広島工場・丸亀事業本部など国内に複数の拠点を持ち、グループ企業としてあいえす造船、岩城造船、しまなみ造船なども傘下に収めています。
さらに、2021年には業界第2位のJMUと資本業務提携をおこない、国際競争力の強化を図っているのです。
このように、生産体制が国内トップクラスに整っていることで、多種多様な船舶の建造に柔軟に対応できるのが特徴です。
特に、バルカーの建造において、高効率なプロペラや、海水との摩擦抵抗を低減する船体外板塗料を採用したことで高い評価を受けているのが強みです。
また、環境対応船への取り組みも進めていて、LNG燃料船やアンモニア燃料船など、次世代の環境技術開発にも積極的に投資しています。
大手造船企業は安定性や設備の充実が魅力ですが、中小企業も技術力や特定分野で強みを持つ場合があります。
将来の安定を考えるなら企業規模だけでなく、事業の方向性や成長分野を見極めることが重要です。市場の変化に適応できる企業ほど生き残る可能性が高いためです。
JMU
JMU(ジャパン マリン ユナイテッド)は、2013年にユニバーサル造船と日立造船の造船部門が統合して誕生した大手造船企業です。2022年の建造実績では国内シェア16%を占め、業界第2位となっています。
2021年には中国や韓国に対抗するため、国内トップの建造量がある今治造船との資本業務提携によって関連会社となり、最先端の船舶の建造で協力する姿勢を取っています。
JMUの技術面での強みは、高い設計・開発力と多様な船種に対応する技術力です。特にタンカーやバルカーの建造で高い評価を受けているのが特徴です。有明や津・横浜・呉など国内の複数拠点で船舶を建造していて、各拠点の特性を活かした生産体制を構築しています。
またJMUは省エネ技術や次世代技術の開発にも力を入れています。自動運航船やアンモニア燃料船などの次世代環境対応船の開発・建造を進めているのです。
また、海に浮かぶ風力発電機である洋上風力浮体は、グリーンイノベーション基金事業から支援を受けて開発を進めていて、カーボンニュートラルに向けた技術開発を積極的に推進し、日本の造船業界の未来を切り開く役割を担っています。
大島造船所
大島造船所は、長崎県西海市に本社を置く大手造船企業です。2022年の建造実績では国内業界第3位、国内シェア13%を占めています。
大島造船所の主力商品は、顧客のニーズに合わせて建造される豊富な種類のバルカーです。バルカーのみで9種類あり、日本を含めて27カ国の船会社に向けて建造されています。
また、大島造船所は環境性の高い最先端技術の研究開発も進めていて、環境負荷の低いLNG燃料船を建造したり、アンモニア燃料船の設計開発に取り組んだりしているのです。
さらに、航行燃料を削減できるウインドチャレンジャーを搭載した船舶を2022年に世界で初めて竣工させたり、日本初の完全バッテリー駆動船「E/V e-Oshima」を開発したり、独自の研究開発を進めているのが特徴です。
ウインドチャレンジャー
伸縮できる帆によって風力エネルギーを船の推進力に変換する装置。
名村造船所
名村造船所は、佐賀県伊万里市に本社を置く大手造船企業で、2022年の建造実績では国内シェア10%を占めています。パナマ運河を通峡できる最大船型のパナマックスや、ケープサイズと呼ばれる大型のバルカーの建造実績が豊富です。
名村造船所の強みは、伊万里事業所を中心とした効率的な生産体制と高度な技術開発力です。大型ドックを活用した建造能力を持ち、高品質な船舶を効率良く生産しています。また、2014年には函館どっくを子会社化し、生産能力を拡大しているのです。
また環境への取組みとして、二酸化炭素の排出量を削減できるLNG燃料大型石炭専用船を2023年に世界で初めて竣工させた実績があります。さらに、2025年に開催される関西万博の会場となる夢洲と大阪市内を結ぶ旅客船として、水素燃料電池船の開発も進めています。
造船や海洋に関する学科などで高度な専門知識を学んでいるのであれば、入社後早い段階で最先端技術開発に携われるチャンスはあります。
しかし一般的には、既存船の設計や管理などの基礎分野から始まることが多いため、入社後に基礎技術を確実に習得し、中長期的に研究開発を目指すという強い意志と熱意をもって取り組むことが大切です。
新来島どっく
新来島どっくは、愛媛県今治市に本社を置く大手造船企業で、2022年の建造実績では国内シェア8%を占めています。ケミカルタンカーの建造を得意としていて、顧客の要望に合わせた多様な船種の建造に柔軟に対応できる技術力を持っているのが特徴です。
また、新来島どっくは、1973年に4,200台の自動車を積める日本初の大型自動車運搬船を建造した実績があります。そして、これまで200隻以上の大型自動車運搬船の建造を手掛けているのが特徴です。
さらに、世界最長となる150mの鉄道用レールを輸送できるレール運搬船を世界で初めて建造しています。従来は150mのレールを25mに6分割して輸出していたものを、そのまま積載できるようにする独創的なアイデアを実現したのです。
このような独自の発想で船舶を建造する設計・開発力があるのも新来島どっくの強みといえます。
造船業界で働くメリット
造船業界で働くメリット
- 人々の生活を支える社会インフラに携われる
- 需要が高いため長期的なキャリアを築きやすい
- 世界トップクラスの技術力を磨ける
造船業界は、日本の基幹産業として長い歴史を持っています。特に技術力の高さは世界的にも認められていて、そこで働くことにはさまざまなメリットがあるのです。
ここでは、造船業界で働く3つのメリットについて解説します。これらのメリットを理解して、自身のキャリアプランや価値観と照らし合わせることで、造船業界が自分に合ったキャリアかどうかを判断しましょう。
人々の生活を支える社会インフラに携われる
日本は島国であり、輸出入の99.6%が海上輸送に依存しています。つまり、私達が日常使う食料品、衣類、電子機器、エネルギー資源のほとんどは船によって運ばれているのです。そのため、造船業界で物流を支える船舶の設計・建造に携わることで、社会に貢献できます。
また建造された船舶は15〜20年以上使用されるのが一般的であるため、自身が受注や建造にかかわった船舶が長期間にわたって社会に貢献し続けることになるのです。
さらに近年では、環境に優しい船の開発も進んでいて、地球環境を守る仕事としての側面も強まっています。このように、自分の仕事が人々の生活や地球環境を支えているということは、やりがいにもつながりやすいといえます。
需要が高いため長期的なキャリアを築きやすい
造船業界は海外との競争が厳しくなっていますが、将来にわたって安定した需要が見込まれる産業です。近年は環境規制が厳しくなっていることから、2020年代後半には環境に配慮した新しい船への買い替え需要が増えると予測されています。
そのため、LNGやアンモニアなどの新しい燃料を使う船の開発・建造にかかわる人の需要は今後さらに高まり、長期的なキャリアが築きやすいことが考えられるのです。
日本の造船業界は特に高い技術力を持ち、高性能な船の分野では世界でも競争力があります。そのため、一度身に付けた知識や技術は長く役立ち、安定した仕事を続けられる可能性が高いです。
また、造船で学んだ技術は洋上風力発電などの新しい分野でも活かせるので、幅広いキャリアを考えることもできます。このように新しい技術や知識を学び続ける意欲があれば、さらに長期的に活躍しやすい業界です。
世界トップクラスの技術力を磨ける
日本の造船業界は、船の品質や燃費効率の良さで世界でもトップレベルの技術を持っています。特に環境性能に優れた船やLNG船といった高度な技術が必要な船の建造では、世界からも高く評価されています。
最先端の技術を実際の仕事を通じて学べる環境が整っているため、日本の造船業界は技術者として成長したい人におすすめです。
造船の仕事は、船の構造設計、水の抵抗を計算する流体力学、材料の選定、機械や電気の設計など、たくさんの専門分野の知識を組み合わせる必要があります。そのため、一つの船の建造プロジェクトに携わることで、幅広い技術を身に付けやすくなるのです。
また、最近は環境に優しいゼロエミッション船の開発や、IoTやAI(人工知能)を使った自動運航船の研究など、最新技術を活用したプロジェクトも増えています。そのため、造船技術だけではなく、デジタル技術や環境技術など、これからの時代に必要な知識や技術も習得できるのもメリットです。
自動車業界のような大量生産と異なり、造船業界は一隻ごとにオーダーメイドで建造されるため、製造の全工程にかかわれるのが大きな魅力です。
また、環境性能やデジタル技術の導入も進んでいて、幅広い最先端技術を身に付けられる機会があります。
プロが解説! 造船業界でキャリアを築く魅力
ここまで説明したように、造船業界でのキャリア形成は、技術力の高さや社会的な意義などの観点で多くの魅力があります。ただし、自身のキャリアの方向性を決めるための材料として「造船業界の魅力をもっと知りたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。
ここではキャリアコンサルタントの楳内さんに、造船業界でキャリアを築く魅力について詳しく聞きました。業界研究の段階にある人や、造船業界への就職を検討している人は、これらの魅力を理解したうえで、自分のキャリアプランを考えましょう。
プロのアドバイザーはこう分析!造船というスケールの大きな仕事が強いやりがいになる
造船業界は、ゼロから設計・建造し、世界の物流やエネルギー輸送を支えるスケールの大きな産業といえます。
新造船舶を初めて水に触れさせる進水式を見たことがあるのですが、巨大な船体が水しぶきをあげながら海面に降りていくその光景は壮大で、これまでに味わったことがないような感動で心がふるえたのを今でも鮮明に覚えています。造船に携わった人であればなおさら、喜びと達成感はひとしおでしょう。
また、近年では環境技術が進化し、次世代燃料船の開発が加速しています。これらの最先端技術やプロジェクトにかかわることができ、地球環境への貢献が実感できるのも造船業界の魅力の一つです。
グローバルに活躍でき自身のキャリア構築にも有利
造船業界はグローバルな仕事も多く、世界各国の造船会社との取引や海外事業所での勤務、海運会社やエンジニアと技術交流の機会も豊富にあります。
そのため技術力の強化はもちろんのこと、英語力や異文化コミュニケーション能力も磨かれていき、国際的に活躍できるフィールドを広げることにもつながっていくでしょう。
このように、ものづくりの醍醐味や環境技術の最前線、グローバルな仕事という魅力あふれる造船業界は、キャリアを築くうえで大きな挑戦と成長のチャンスを提供してくれるでしょう。
造船業界で働くデメリット
造船業界で働くデメリット
- 地方への転勤が発生する可能性が高い
- 天候により工期が遅れ残業が増える可能性がある
- 為替変動に業績が左右されて賞与に影響が出る可能性がある
造船業界で働くことにはさまざまな魅力がある一方で、いくつかのデメリットもあります。就職活動においては業界の良い面だけではなく、このようなデメリットについても理解しておくことが入社後のギャップを防ぎ、長期的に活躍するために重要です。
ここでは、造船業界で働くデメリットについて解説します。造船業界への就職を検討する前に、デメリットを理解して、自分のライフスタイルや価値観、キャリアプランと照らし合わせるための判断材料にしましょう。
地方への転勤が発生する可能性が高い
日本の主要造船所の多くは、瀬戸内海沿岸や北部九州などに集中しています。造船所の国内分布図を見ると、今治市や長崎県、福岡県、兵庫県などの沿岸部に大手の生産拠点が密集しているのが特徴です。
造船業はほかの製造業と異なり、広大な敷地と海へのアクセスが必須であるため、都市部から離れた場所に立地する必要があります。そのため、入社後は都市部にある本社での勤務よりも、地方の造船所へ配属されるのが一般的です。
特に設計・技術系の職種では、図面上だけではなく実際の建造現場での経験が重視されるため、地方の造船所での勤務期間が長くなりやすいです。また、造船所間での技術交流や、複数拠点を持つ企業での人事異動により、瀬戸内海沿岸の複数の造船所を数年ごとに異動するケースも多くあります。
そのため、都市部での勤務を希望する場合、ほかの製造業と比べて実現することが難しいことを理解しておきましょう。
造船業界に就職して全国転勤があることに不安がある人は、こちらの記事をチェックしましょう。全国転勤のデメリットやメリット、向き・不向きを確認する方法を解説しています。
天候により工期が遅れ残業が増える可能性がある
造船業は屋外での作業が多い産業のため、天候の影響を大きく受けます。特に台風や豪雨、強風などの悪天候は、安全上の理由から作業の中断を余儀なくされることがあります。
このような天候による作業の遅れを取り戻すため、晴れの日には残業が発生したり、納期が迫る時期には休日出勤が必要になったりする可能性があるのです。
また、船の建造は複数の工程が連続する大規模プロジェクトであるため、一部の工程が遅れると後続の工程すべてに影響します。
特に進水や引き渡しは、潮位や顧客のスケジュール、他船との建造ドック使用予定など多くの要因によって日程が固定されています。そのため、予定どおりに工程を進める必要があるため、突発的な残業が発生しやすいのです。
このように、造船業界では天候や工程の進行状況によって労働時間が変動しやすく、ワークライフバランスの予測がしづらい面があります。
造船業界の各社は、交代制の導入や作業の進め方の見直しやIT活用による業務効率化などで残業を減らし、休日を確保しようとしています。
ただ、大規模プロジェクトや厳しい納期の影響で、残業を完全になくすのは難しいのが現状です。
為替変動に業績が左右されて賞与に影響が出る可能性がある
造船業界は国際的な競争が激しいため、為替レートの変動が業績に大きな影響を与えます。たとえば、円高になると日本の造船所で建造する船の価格が海外と比べて高くなるため、受注が減少したり、利益率が低下したりする可能性があるのです。
そして、このような業績の変動は、社員の賞与や昇給にも直接影響する可能性があります。特に業績連動型の賞与制度を採用している企業では、好調な時期には高額の賞与が期待できる一方で、業績が悪化した際には大幅に減額されることもあります。
業績や収入の安定性を重視する人は、為替変動の影響を受ける可能性があることを理解したうえで造船業界へのキャリアを検討しましょう。
安定した職業に就きたい人には、以下の記事がおすすめです。安定した仕事の特徴と、条件面で安定した職業に就く前に知っておくべきことを解説しています。
就活のプロに聞く! 造船業界の働き方の実態
造船業界での働き方には、他業界とは異なる特有の側面があります。「残業はどれくらい多いのか」「技術職と事務職では働き方にどんな違いがあるのか」など、実際の現場の状況について疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
ここではキャリアコンサルタントの隈本さんに、造船業界の働き方の実態について詳しく聞きました。造船業界への就職を検討している人や、選考を受ける企業を絞り込もうとしている人は、業界の実態を理解しておきましょう。
アドバイザーのリアル・アドバイス!造船業界の仕事は大規模のためプロジェクト型が一般的
造船業界はチームで動くプロジェクト型の働き方が中心で、各職種が専門性を発揮しながら協力して一隻の船を作り上げていく達成感のある仕事です。技術職と営業職では、働き方や求められる力が大きく異なります。
①技術職の働き方
造船業界の技術職の仕事内容は多岐にわたり、設計や製造管理、品質保証など、職種によって求められる専門性も大きく異なります。若手のうちから一連の造船プロセスにかかわることができるため、成長の実感を持ちやすいのが魅力です。
造船は一隻ごとに設計・製造するオーダーメイドの世界で、船の設計から建造まで数年単位のプロジェクトになります。納期前になると残業が発生することもありますが、働き方改革も進み、フレックスタイムやリモート対応など柔軟な働き方も導入されつつあります。
②営業職の働き方
造船業界の営業職は国内外の船主や海運会社に対して、自社の技術や強みを提案し、受注につなげる役割を担います。営業先はグローバルで、長期的な信頼関係の構築が欠かせないため、コミュニケーション能力が重要で、英語力や国際感覚も求められます。
営業職も受注のタイミングや契約交渉の時期には業務量が増えますが、技術職よりもスケジュールを自分で組みやすいでしょう。
学部別!造船業界での活躍フィールド
造船業界は、それぞれの学部ごとに実現しやすい多様なキャリアパスがあります。「自身の学部で学んだことは、造船業界でどのように活かせるのか」を理解しておきたい人も多いのではないでしょうか。
ここでは、学部別に造船業界での活躍フィールドを解説します。自身の専攻を造船業界でどのように活かせるかを明確にイメージできるようにしましょう。
理系学部の活躍領域
理系学部の活躍領域
- 船舶工学科:設計職全般
- 機械・航空工学科:機械系業務全般
- 電気電子工学科:電気系業務
- 情報工学科:システム開発・IoT関連の技術開発業務
造船業界では、理系学部出身者が多く採用され、船舶の設計・開発から生産技術、品質管理まで幅広い技術分野で活躍しています。特に造船所では、船を設計・建造するための専門技術が求められるため、それぞれの専攻に応じた活躍の場があるのです。
ここでは、造船業界における理系学部ごとの活躍領域を解説します。自身の専門性をどのように活かせるのか理解を深めるために目を通しておきましょう。
工学部生で就職先を悩んでいる人は、以下の記事がおすすめです。工学部におすすめの就職先10選や、工学部生が就活を有利に進める方法を解説しています。
船舶工学科:設計職全般
船舶工学科の学生は、造船業界において特に専門性を活かしやすく、おもに以下のような設計部門を中心に幅広い職種で活躍できます。
各設計職で活かせる船舶工学科の専門性
- 基本設計:流体力学、船舶運動力学、推進理論、航海計算学
- 構造設計:構造力学、材料力学、強度計算学、有限要素法
- 船装設計:船体艤装学、機器設計学、人間工学
- 機装設計:機械工学、熱力学、流体機械学
- 電装設計:船舶電気工学、制御工学、電子回路学
- 生産設計:生産工学、工程管理学
基本設計では、船型計画や性能計算など船舶工学の専門知識を直接活用できるのが特徴です。船の長さや幅・深さなどの決定や、水槽試験を通じた船型の最適化、燃費性能の追求など、船舶の根幹にかかわる重要な業務を担当します。
また構造設計では、波浪や貨物による荷重に耐える船体構造の設計、船装設計では船に取り付ける装置・設備全般の設計、機装設計では機関室の配置や配管系統の設計など、さまざまな設計業務に携わることができます。
さらに生産設計や生産管理部門でも、船舶工学の専門知識をもとに造船工程の効率化や品質向上に貢献することが可能です。
また近年は、新燃料船の開発や自動運航システムの設計などの最先端技術を取り入れた業務も増えています。船舶工学科で学べる複合的な工学知識は、これらの新分野でのイノベーションにも貢献できます。
機械・航空工学科:機械系業務全般
機械・航空工学科の学生は、造船業界において船舶の動力系統や機器設備を中心に、幅広い技術分野で活躍できます。
各職種で活かせる機械・航空工学科の専門性
- 機関設計:内燃機関学、動力工学、熱力学、燃焼工学
- 推進装置設計:流体機械学、振動工学、伝動機構学
- 補機設計:機械要素設計学、油圧・空気圧工学
- 配管設計:流体力学、熱交換工学、システム工学
- 機械艤装:機械工作法、機械設計学、組立工学
- 品質管理:材料試験学、計測工学、品質工学
機関設計では、船舶のメインエンジンやその周辺機器の設計・選定をおこないます。近年は特に環境規制に対応した低排出ガスエンジンやLNG・アンモニアなどの新燃料に対応したエンジン開発が重要な分野となっています。
推進装置設計では、プロペラや推進器の設計・開発を担当し、船舶の推進効率向上に貢献することが可能です。機械工学の知識を活かして振動解析や強度計算をおこない、高効率かつ耐久性のある推進システムを構築します。
また、造船所内の生産設備の設計・保守や、建造中の船舶の機械系統の施工管理なども、機械・航空工学科出身者のニーズがある分野です。航空工学で学んだ流体力学や軽量・高強度構造の知識は、船舶の高効率化や省エネ化にも応用されています。
電気電子工学科:電気系業務
電気電子工学科の学生は、船舶の電気系統全般を担当する重要な役割を担い、以下のような職種で活躍できます。
各職種で活かせる電気電子工学科の専門性
- 電気設計:電気回路学、電力工学、配電システム学
- 制御設計:自動制御理論、センサ工学、フィードバック制御
- 通信設計:通信工学、電波工学、ネットワーク理論
- 電気艤装:電気機器学、電気工事学、電気安全工学
- 航海機器:電子回路学、マイクロプロセッサ論、レーダー工学
- 検査試験:計測工学、電気試験法、品質管理学
電気設計では、船内の電力系統や配電システムの設計を担当します。大型船舶は小さな都市のような電力需要を持つため、安全で効率的な電力供給システムの構築が重要な任務です。
制御設計では、エンジン制御、操舵システムなど、船舶のさまざまな自動制御システムの設計・開発をおこないます。特に近年は船舶の自動化が進んでいて、高度な制御技術の知識が求められているのです。
また、航海機器分野では、レーダーやGPS、自動識別装置など、安全航行に不可欠な電子機器の選定や統合システムの設計を担当します。電気電子工学の専門知識は、近年進む船舶のデジタル化や自動運航船の開発においても活かされる分野です。
情報工学科:システム開発・IoT関連の技術開発業務
情報工学科の学生は、造船業界のデジタル化が急速に進むなかで、以下のような最先端分野で活躍できます。
各職種で活かせる情報工学科の専門性
- 船舶IoT:ネットワーク工学、センサ情報学、クラウドコンピューティング
- 運航支援システム:アルゴリズム論、最適化理論、ビッグデータ解析
- 監視制御システム:リアルタイムシステム論、組込みソフトウェア工学
- 自動運航技術:人工知能、機械学習、コンピュータビジョン
- 設計支援ツール:CAD/CAMシステム論、シミュレーション工学
- 情報セキュリティ:暗号理論、ネットワークセキュリティ、リスク管理学
IoT
あらゆるモノをインターネットに接続する技術のこと
船舶IoT
船舶の運航・機器の状態や燃費などのデータを船陸間で毎時間共有する装置
船舶IoT分野では、センサーから収集したデータを活用した船舶の遠隔監視システムや予防保全システムの開発をおこないます。世界中を航行する船舶からリアルタイムでデータを収集・分析し、最適な運航を支援するシステム構築が重要な任務です。
運航支援システム開発では、気象・海象データと船舶の性能を考慮した最適航路計算や燃費最適化システムの開発を担当します。ビッグデータ解析や最適化アルゴリズムの知識が直接活かされる分野です。
さらに自動運航技術の分野では、人工知能や機械学習を応用した衝突回避システムや自律操船システムの開発に取り組みます。情報工学科で学んだプログラミングやAI技術は、造船業界のデジタル化を推進するために必要な専門知識となっています。
- 造船業界で自分の専攻分野と目指したい職種に関連が薄い場合、就職は厳しいのでしょうか?
設計・製造を除けば専攻分野が異なっても就職成功が見込める
造船業界では目指す職種と自身の専攻分野が完全に一致しなくても就職は可能です。特に設計や品質管理、営業職は、入社後の研修や実務経験を通じて必要な知識を身に付けることができます。
ただし、船舶設計や構造解析など高度な専門知識が求められる職種では専攻分野の影響が大きいため、異なる分野からの応募は難しくなる傾向があります。
その場合は関連知識の習得やインターンシップ経験を積むことで、業界への適性を示すことが重要です。
文系学部の活躍領域
造船業界は理系学部出身者が活躍する技術職のイメージが強い傾向がありますが、文系学部出身者にも多くの活躍の場があります。特に営業や経営管理部門では、文系学部で培った知識やスキルが活かせるのです。
ここでは、造船業界における文系学部の活躍領域を解説します。それぞれの学部で学んだ専門知識を造船業界の特性と結びつけて、自分の強みをどのように活かせるかをイメージしましょう。
造船業界の技術系職種は特定の専門知識が求められるため、一般的には理系の人材が中心となっていることが多いです。
ただ、工程管理や資材調達、営業などの職種から中長期的に技術系職種へのキャリアアップは可能なため、早い段階で技術系の知識やスキルを積むことでその道を切り拓いていきましょう。
経済・経営学部:船舶営・資材調達・企画業務
経済・経営学部の学生は、造船業界のビジネス面を支える重要な役割を担い、以下のような職種で活躍できます。
各職種で活かせる経済・経営学部の専門性
- 船舶営業:マーケティング論、国際経済学、交渉学、金融論
- 資材調達:調達戦略論、サプライチェーン管理、原価計算論
- 企画業務:経営戦略論、事業計画論、財務分析
- 海外業務:国際経営論、異文化コミュニケーション論
- 経理財務:管理会計学、原価管理論、投資評価論
- プロジェクト管理:プロジェクトマネジメント論、リスク管理論
船舶営業では、国内外の船主や海運会社に対して船舶の受注活動をおこないます。
一隻数十億円から数百億円という高額な商品を扱うため、経済動向の分析力や金融知識、交渉力が求められます。特に、国際商取引や為替リスクなど、経済・経営学部で学んだ専門知識が直接活かされる分野です。
資材調達では、鋼材や機器など船舶建造に必要な膨大な資材の調達計画を立案・実行します。サプライヤーとの価格交渉や納期管理、原価低減活動などを通じて、収益性向上に貢献します。経営学で学んだサプライチェーン管理や原価計算の知識を直接活かすことが可能です。
また企画業務では、新規事業の立案や中長期経営計画の策定、M&A戦略の分析など、企業の将来を左右する重要な業務を担当します。造船業界の国際競争が激化する中、経済・経営の視点からの戦略立案能力が高く評価される分野です。
法学部:人事・総務・契約関連業務
法学部の学生は、造船業界の経営基盤を支える管理部門や国際的な契約業務など、以下のような職種で活躍できます。
各職種で活かせる法学部の専門性
- 契約業務:契約法、国際私法、海事法、英米法
- 法務:会社法、労働法、独占禁止法、知的財産法
- 人事:労働法、社会保障法、組織法学
- 総務:行政法、環境法、安全衛生法規
- コンプライアンス:企業法務、リスク管理法学、倫理学
- 国際取引:国際取引法、国際海事条約、通商法規
契約業務では、船舶建造契約や保証契約など、国際的な大型契約の起案・審査・交渉を担当します。
一隻の船舶建造は複雑な契約関係をともなうため、法的知識に基づく的確な条項設計や交渉が求められるのです。特に国際取引法や英米法の知識は、外国船主との契約交渉の場で活かせます。
法務部門では、企業活動全般の法的リスク管理や各種許認可の取得、知的財産の保護など、造船事業を法的側面からサポートします。法学部で培った法令解釈能力や論理的思考力を直接活かすことが可能です。
また人事部門では、採用計画の立案や労務管理、人材育成制度の設計など、組織の人的資源を最大限に活かすための業務を担当します。
このように法学部生は、造船業において多くの技術者と技能者を支える労働法や人事制度に関する知識を駆使して、働きやすい職場環境づくりに貢献できる重要なポジションで活躍できるのです。
法学部生で就職先に悩んでいる人は、以下の記事を参考にしましょう。法学部生におすすめの就職先・職種や、大学別の就職先ランキングを解説しています。
プロに聞いた! 造船業界に向いている人の特徴
造船業界への就職を考える際、「自分はこの業界に適性があるのだろうか」「どんな人が長く活躍できるのか」と悩む人も多いのではないでしょうか。
造船業界は海に近い環境での開発をおこなうような業務特性があり、そこで長く活躍するためには、ある程度の適性や資質が求められます。
ここではキャリアコンサルタントの野村さんに、造船業界に向いている人の特徴について詳しく聞きました。造船業界への就職を検討している人や、自分の適性に不安を感じている人は、これらの特徴と自分の性格や価値観を照らし合わせて、業界選びの参考にしてみましょう。
プロのアドバイザーはこう分析!造船業界に向いている人の5つの特徴をチェックしよう
造船業界は、ものづくりへの興味や粘り強さ、チームワークなどさまざまな要素が求められる業界です。特に以下の特徴を持つ人が活躍しやすいでしょう。
①ものづくりが好きな人
巨大な船を一から設計・製造する仕事に興味を持ち、完成時の達成感を楽しめる人に向いています。
②チームで働くのが得意な人
造船は設計や建造、品質管理、営業など、多くの職種が連携するプロジェクト型の仕事です。異なる専門分野の人と協力し、課題を解決できる人が求められます。
③粘り強く取り組める人
建造には数年単位の時間がかかり、工程で問題が発生することもあります。トラブルが起きても冷静に対応し、最後までやり遂げる力が重要です。
④変化に対応できる人
近年は省エネ技術や環境規制対応が求められ、新技術の習得が必要です。柔軟に学び続けられる人は業界で活躍しやすいでしょう。
⑤グローバルな視点を持つ人
造船業界は国際競争が激しく、海外企業や顧客との取引も多いため、英語力や国際感覚があると強みになります。
造船業界は専門性が高い分野ですが、文系・理系を問わず活躍の場があります。これらの特性に合う人なら、長くやりがいを持って働けるでしょう。
活躍できる人材になるために! 造船業界で求められる汎用スキル
活躍できる人材になるために! 造船業界で求められる汎用スキル
- 多国籍チームで協働するための英語力
- 海運・メーカー企業などとのネットワーク構築力
- 環境規制やデジタル化に対応するための情報収集力
造船業界で長期的に活躍するためには、専門的な技術力や知識だけではなく、幅広い汎用スキルを身に付ける必要があります。これはグローバル化やデジタル化の進展により、造船業界を取り巻く環境は急速に変化していて、それに柔軟に対応できる力が求められるためです。
ここでは、造船業界で求められる3つの汎用スキルについて解説します。これらのスキルを学生時代から意識して磨いておくことで、入社後に即戦力として活躍しやすくなるため、目を通しておきましょう。
多国籍チームで協働するための英語力
造船業界では国際的な事業展開が進み、多国籍チームで協働する現場が多くなっています。設計部門では外国人エンジニアが増加していて、外国人の技術者と英語でコミュニケーションを取る機会が増えています。
また、顧客となる船主やオペレーターも外国人の可能性があり、船舶の仕様に関する打ち合わせや引き渡し時の交渉なども英語でおこなわれることが多いです。
造船業界で働くうえで、専門的な技術用語を理解し使いこなせるレベルの英語力があることはもちろん、異なる文化背景を持つ人々との円滑なコミュニケーションを図るための柔軟性も重要です。
船舶の設計図面や技術文書・国際機関の規則や基準なども英語で記述されているため、技術英語の読解力も必須となります。
グローバルな環境が増えている造船業界で活躍するためには、日常会話レベルを超えた実務的な英語力の習得が、キャリア構築の大きな強みとなることを覚えておきましょう。
造船業界の技術職では、技術英語の読解力と実務的な会話力が求められるため、TOEICで730点以上が一つの目安です。
図面や技術文書を読みこなす力に加え、チーム内での調整や交渉にも対応できる柔軟な英語力が求められます。
企業からどれくらいの英語力が求められるかについて理解を深めたい人には、こちらの記事がおすすめです。英語力が見られる職種と必要なレベルと、就活でアピールするための英語力をつける方法を解説しています。
海運・メーカー企業などとのネットワーク構築力
造船業界は、船主や海運会社、舶用機器メーカー、鉄鋼メーカー、船級協会など、多くの関連企業・団体との連携によって成り立っています。
船級協会
船舶の船体・機関の構造・状態を検査する組織。世界の海運国にそれぞれ船級協会がある
そのため、これらの企業・団体とのネットワークを構築・維持する能力が造船業界で長期的に活躍するうえで大切です。
たとえば、設計部門では船級協会の検査員と緊密に連携し、安全基準に合致した設計を進める必要があります。資材調達部門では舶用機器メーカーと良好な関係を築き、最適な調達条件を引き出すことが求められるのです。
また、営業部門では船主や海運会社と信頼関係を構築し、継続的な発注につなげる役割があります。
このようなネットワーク構築には、業界特有の商習慣や専門知識を理解したうえでの適切なコミュニケーション能力が必要です。また、長期的な信頼関係を築くため、誠実さや相手の立場に立って考える姿勢も重要となります。
環境規制やデジタル化に対応するための情報収集力
造船業界は、IMOによる環境規制の強化やデジタル技術の急速な進化など、大きな変革期を迎えています。
2050年のカーボンニュートラル実現に向けたゼロエミッション船の開発や、自動運航船の実用化などの課題に対応するためには、最新の技術動向や規制情報を追い続ける力が必要です。
特に環境規制については、温室効果ガス排出削減、硫黄酸化物・窒素酸化物の排出規制など、次々と新たな国際ルールが導入されています。
また、デジタル技術の分野では、IoTを活用した船舶モニタリングシステムやAIによる最適運航支援など、技術革新が急速に進んでいます。
このような変化に対応するためには、業界専門誌や学会などを通じた情報収集や、海外の先進事例や異業種の動向にも目を向けることが必要です。
学生時代から業界動向をチェックしておくことで、入社後もその変化に柔軟に対応できる人材として評価されやすくなります。
就活のプロに聞く! 造船業界へ就職する難易度
造船業界への就職を考える際、「選考の難易度は高いのか」「大手企業に入社するのはどれくらい難しいのか」など、就職難易度について疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。造船業界の選考の実態を知ることは、効果的な就活戦略を立てるうえで重要です。
ここではキャリアコンサルタントの楳内さんに、造船業界へ就職する難易度について詳しく聞きました。造船業界を志望している人や、複数の業界から就職先を検討している人は、これらの情報を理解したうえで、自身の強みを活かせる企業選びや選考対策を進めましょう。
アドバイザーのリアル・アドバイス!造船業界も大手企業ほど難易度は高くなる
造船業界へ就職する場合、大手造船企業と中小造船企業とでは難易度に差があると考えます。まず、大手造船企業は毎年一定数の新卒採用をおこないますが、応募者が多く競争率が高いです。
さらに、技術職においては機械や電気工学といった専門知識におけるバッググラウンドが求められ、学歴も重視される傾向にあります。海外取引が多くTOEICで600点以上を推奨する企業もあることから、難易度は高いといえるでしょう。
中小造船企業では勤務地が地方になることがあり、都市部の大手造船企業と比べると志望者が少なく競争率が低い傾向にあります。
海外経験や高い語学スキルを求める世界的に有名な造船所や、高い技術力で独自のカラーを打ち出している造船所は、優秀な技術者を積極的に採用したいと考えていることが多いです。
スキルや専門知識を持ち合わせている人にとっては、就職しやすいと考えることができます。
専門性の高い職種ほど専攻分野や事前リサーチが重要
造船業界は専門性の高さが求められるため、専門分野と合致しないと通過が難しくなることがあります。特に技術系インターンは選考に直結することが多く、参加していないと不利になる可能性があるのです。
またグループディスカッションや技術面接において、研究内容や技術知識を説明できることが求められ、論理的思考力や工程・コスト管理の視点を問う課題が出されることもあります。
このことから、造船業界の選考を突破するには技術力や語学力、インターン経験を活かしたり、OB・OGの訪問をつうじて積極的につながりを作ったりすることなどが大切です。
選考対策を早い段階からおこなうことでチャンスを高めていきましょう。
5ステップ! 造船業界に就職するための選考対策
5ステップ! 造船業界に就職するための選考対策
造船業界は高度な専門性と幅広い技術力が求められる業界であるため、選考においても業界特有の対策が必要です。「どのように自分の強みをアピールすれば良いか」「造船業界特有の選考のポイントは何か」など、効果的な対策方法を知りたい人も多いのではないでしょうか。
ここでは、造船業界に就職するための選考対策を5ステップで解説します。これらのステップを順番に進めることで、業界の特性を理解したうえで自分の強みを効果的にアピールしましょう。
①造船業界に就職したい理由を明確にする
まずは造船業界を志望する理由を明確にして、就活における軸を定めましょう。「船が好き」「規模が大きなものづくりに携わりたい」といった漠然とした動機では採用担当者を納得させることはできません。
造船業界の魅力や特徴を理解し、なぜほかの製造業ではなく造船業なのかを説得力のある形で伝えることが採用担当者を納得させるために重要です。
たとえば「世界の海上物流を支えるインフラづくりに貢献したい」「環境技術の革新が求められる造船業で自分の専門性を活かして技術開発に携わりたい」など、業界の特性と自分の価値観・強みを結びつけた理由を考えましょう。
また、特定の職種や企業を志望する理由も明確にしておくことが大切です。各造船所の技術的特徴や企業文化の違いを調査し、なぜその会社なのかを具体的に説明できるようにしておきましょう。
志望理由が明確であるほど、面接での受け答えに一貫性が生まれ、志望度の高さを伝えやすくなります。
- 造船業界の志望動機として「海や船が好き」という理由しか思い浮かびません。
海や船が好きという感情やきっかけを深掘りしてみよう
造船業界の志望動機として「海や船が好き」だけでは弱いため、「なぜ造船業界なのか」を掘り下げましょう。まずは「好き」という気持ちの根っこを探ってみることが大切です。
たとえば「港で大型船を見るのが好きだった」であれば、「巨大な構造物がどのように作られるかに関心がある」「人や物を世界中に運ぶ仕組みに興味がある」といった視点に広げられます。
そこから「スケールの大きなものづくりに携わりたい」「グローバルな産業にかかわりたい」といった就活軸につなげると説得力が出ます。
さらに、個人の関心を業界の課題や役割と結びつけて「環境負荷の少ない船作りに貢献したい」などと深掘りできると、さらに納得感のある志望動機となるでしょう。
②造船業界で活かせる自身のスキルを洗い出す
続いて、自己分析をおこなって、造船業界で活かせる自身のスキルや強みを洗い出しましょう。技術力はもちろん重要ですが、チームワーク力や問題解決能力、コミュニケーション能力など、造船業界で求められるさまざまな資質を自己分析の視点に含めることが大切です。
たとえば、機械工学を専攻した学生であれば、流体力学や材料力学の知識がどのように船舶設計に応用できるかを具体的に考えましょう。
また、研究室やサークル活動・アルバイトなどの経験から培った協調性やリーダーシップ、さまざまな人々と協働した経験なども造船業界で活かせるスキルです。
一方で、文系学生の場合は、経済学や法学などの専門知識がどのように営業や企画、契約業務などに活かせるかを考えることが、造船企業に貢献する方法を考えるために重要です。自身の経験や学びを振り返り、業界で求められるスキルと結びつけて整理しておきましょう。
- 造船業界を志望するうえで、特に取得しておくべき資格はスキルはありますか?
英語力に加えて志望職種と関連性の強い資格を取得しよう
造船業界を志望するなら、まずは造船業界の基本的な仕組みや環境規制、業界トレンドをしっかりと把握しましょう。
そのうえで、スキルや実績を補うために取得が望ましいといえる資格やスキルの取得を視野に入れてください。
造船業界はグローバルな仕事が多く、語学力や海外経験が入社後に役に立ちます。
語学力はすぐに身に付くものではなく、継続的に取り組む必要があるため、TOEICスコア600点以上を目指して勉強を始めてみてはいかがでしょうか。
また、文系で経理や管理部門を志望するなら簿記の知識、管理業務ではマネジメントや品質管理の知識も有利になるでしょう。
理系は技術職がメインとなるため、専門知識の習得はもちろんのこと、基本情報技術者試験やCAD、機械・電機関連の資格も造船業界への適性のアピールにつなげられます。
造船業界で活かせる自身の強みを理解するために自己分析をする人は、以下の記事を参考にしましょう。効果的な自己分析にするために必要なことや、自己分析をおこなう時期について解説しています。
③自身のスキルを事業に活かす方法を含めた志望動機を考える
造船業界の志望動機を考える際は、単に「なぜ造船業界に興味を持ったか」だけではなく、「自分のスキルをどのように事業に活かせるか」まで踏み込んで説明できることが重要です。これにより、自身が入社後にどのような貢献ができるのかを具体的にイメージしてもらえます。
たとえば、情報工学専攻であれば「AIやIoT技術を船舶の遠隔監視システムに応用して安全性向上に貢献したい」など、専門性と事業の結びつきを具体的に示しましょう。
文系学生の場合も同様に、「国際経済の知識を活かして海外マーケットの開拓に貢献したい」「法律知識を活かして環境規制への対応をサポートしたい」など、自分の強みを事業にどう活かせるかを明確にすることで、説得力のある志望動機を作りやすくなります。
スキルと事業の接点を見いだすことで、面接官にあなたの価値をしっかりと伝えられるようにしましょう。
いざ志望動機を考えようとしてうまく書き進められない人は、以下の記事を参考にしましょう。志望動機が描けない4つの原因や、すぐに志望動機を完成させる方法を解説しています。
④造船業界の課題への自身の考えを持つ
造船業界が直面している課題について自分なりの考えや解決策を持つことは、業界研究の深さを示すとともに、入社後のビジョンを明確に伝えるために重要です。造船業界のおもな課題として、以下のようなものが挙げられます。
造船業界が抱える課題の例
- 国際競争への対抗
- 環境規制の強化への対応
- 業界全体の人材不足の解決
たとえば、環境規制については「カーボンニュートラルに向けて水素やアンモニア燃料船の実用化を加速するには、エネルギー効率の向上と安全性確保の両立が課題だと考えます」のように、具体的な視点を持ちましょう。
面接では「この課題についてどう思いますか」とたずねられることも多いため、業界ニュースや専門誌、企業のIR情報などから最新情報をキャッチアップし、自分なりの意見を構築しておくことが大切です。
なお、課題に対する批判ではなく、建設的な提案をとおして課題解決に役立ちたいという気持ちを伝えることを意識しましょう。
造船業界の最新動向を把握するには、業界団体の公式サイトや、「世界の艦船」「ジャパン・シッピング・ガゼット」などの専門誌を定期的にチェックするのがおすすめです。
また、造船企業のプレスリリースや展示会、業界セミナーに参加することで、最新の技術や課題を直接知ることができます。
⑤インターンシップやOB・OG訪問で造船業界への理解を深める
造船業界は一般的な製造業とは異なる海に近い環境で働くことになるため、インターンやOB・OG訪問を通じて実際の業務内容や雰囲気を体感することが重要です。
インターンでは、可能な限り現場に近い経験ができるプログラムを選ぶことで、造船所の規模感や業務フローをより感じやすくなります。
また、OB・OG訪問では、学生時代にやっておくべき準備や、業界特有の働き方や社風など、企業の採用ページでは得られない情報を聞くことができます。質問内容は事前に準備し、限られた時間を有効に使いましょう。
さらに、造船所見学や企業説明会にも積極的に参加すると、各社の特徴や強みが見えやすくなります。特に実際の造船現場を見学できる機会は貴重で、この経験を通じて得た具体的なエピソードを面接で話せれば、業界理解の深さとともに入念な準備をしてきたという熱意も伝わりやすくなります。
このように、さまざまな企業研究をおこなうことで、選考結果を大きく左右するため、インターンやOB・OG訪問、造船所見学などに参加することを検討しましょう。
造船業界の理解を深めるためにインターンやOB・OG訪問をおこなう人は、以下の記事を参考に準備しましょう。参加までの期間ごとに必要なインターンの準備や、OB・OG訪問での質問の考え方について解説しています。
OB・OG訪問
OB・OG訪問は質問選びが鍵! おすすめ質問100選を紹介
造船業界への理解を深めてキャリアの選択肢として検討しよう
造船業界は人々の暮らしを支えてきた重要な産業です。グローバル化やデジタル化、環境規制の強化といった新たな変化に直面しているなか、造船業界への就職を検討する際は業界の現状と将来性をしっかりと理解し、自分の強みや価値観と照らし合わせることが大切です。
また、造船業界にはさまざまな職種があるため、企業ごとの特色も深く理解したうえで、自分に合った就職先を探し、造船業界へのキャリアを検討しましょう。
実際に就職活動を進める際には、この記事で紹介した5つのステップを意識しながら、業界への理解を深め、自身のスキルを活かせる分野を見つけ、具体的な志望動機を作ることが重要です。
これにより、造船業界で自身の強みを活かし、長期的に活躍できる人材として自身をアピールしやすくなります。ぜひ造船業界を将来のキャリアの選択肢として検討してみてください。
アドバイザーからあなたにエール造船業界ほどスケールの大きなものづくりの業界はめったにない
造船業界は自動車や電気電子製品に比べ、船舶というスケールの大きいものづくりにかかわれることが魅力の業界です。
巨大な船を一から作り上げる現場では、設計・生産・品質管理など多くの職種が連携し、数年単位のプロジェクトで進行していきます。技術系の職種では理系出身者が多く活躍している一方で、文系出身者が営業や調達、企画で携わるケースもあります。
プロジェクト規模が大きい傾向にあるため、チームワーク力や粘り強く物事に取り組む姿勢が求められるのもこの業界の特徴です。
インターンを通して造船業界のリアルな働き方を体験しよう
造船業界は製造拠点が地方にあることが多いため、勤務地に対して柔軟な対応ができると選択肢が広がります。一方で海外との取引が多く、グローバルに活躍できる場面も少なくありません。
就職活動では、「なぜ造船なのか」「なぜその企業なのか」という志望動機の具体性が特に重要です。環境問題や国際競争など、業界が抱える課題にも触れたうえで、自分がどう貢献したいかを語れると説得力が増します。
専門知識だけでなく、熱意や成長意欲も評価される業界です。まずは、企業研究やインターンを通じて現場のリアルを知ることから始めてみてください。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi
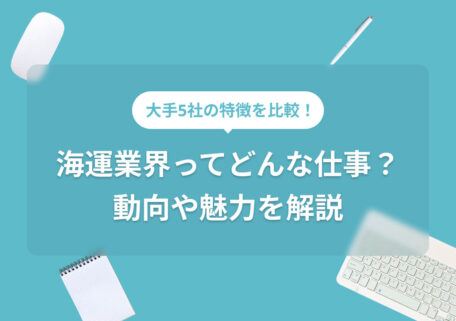





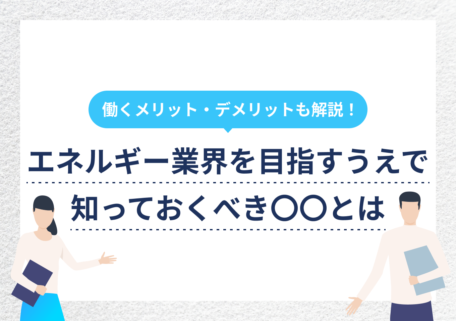




















3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/性格応用心理士1級
Minoru Kumamoto〇就職・転職サイト「職りんく」運営者。これまで500名以上のキャリア相談を受けた実績。応募書類や採用面接の対策支援をする他、自己分析の考え方セミナーを実施
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表
Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/ワーズアンドキャリア代表
Yukiko Umenai〇アナウンサーとしてのノウハウを活かし、総合人材会社で研修や社員教育を担当。人材の活躍やキャリア形成支援にも注力し、大学ではキャリア講義やカウンセリング、就職支援を担っている
プロフィール詳細