この記事のまとめ
- まずは第二新卒の就活は厳しいと言われる理由を理解することが大切
- 就活のプロが第二新卒の就活が厳しいのかそのリアルを解説
- 5つのステップを踏んで第二新卒の就活を成功させよう
第二新卒で転職活動をしたいと思っても、厳しいという話を聞いて不安に思う人もいるのではないでしょうか。しかし、第二新卒の就活が厳しいと言われているなかでも、理由を理解したうえで入念に対策をすることで選考突破が可能です。
この記事では、第二新卒の就活が厳しいと言われる理由や対策をキャリアコンサルタントの平井さん、吉野さん、谷所さんと一緒に解説します。自分の強みとなる部分を見つけ、適切にアピールして、志望企業の選考突破を目指しましょう。
【完全無料】
社会人におすすめ!
就職・転職前に使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:年収診断
志望職種×あなたの経験で今後の想定年収を確かめよう!
4位:WEBテスト対策模試
模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
5位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
第二新卒の就活は厳しい? 理由を理解すれば解決策が見つかる
現職を退職して転職活動を開始したいと考えても、「第二新卒の就活が難しい」という噂を聞いて、不安に思う人も多いはずです。
第二新卒の就職活動は厳しいと言われているのは事実ですが、その理由を理解して、入念に対策をすることで選考突破に近づけます。
そこでこの記事では、前半で第二新卒の就活が厳しいと言われる理由や選考が通らない人の特徴を解説します。採用担当者の意見を理解して、相手の不安を払拭できる選考対策を立てましょう。
そしてそのあとで、第二新卒ならではの選考対策や、転職活動を成功させるための5つのステップを解説します。記事を最後まで読めば、第二新卒でも志望企業への入社を目指すためにやるべきことが明確になります。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。
これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。
また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。
既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。
前提を把握しよう! 第二新卒とは新卒入社後1〜3年以内に前職を離職する人
第二新卒とは、学校を卒業後に新卒として企業に入社し、1〜3年以内に離職する人のことです。年齢で明確に区切られているわけではなく、新卒と中途の間の存在として扱われています。
就職活動をするうえでは中途採用の部門に応募することが多いですが、企業によっては新卒の採用ページで「第二新卒歓迎」と記載しているケースもあります。募集ページの内容を確認したうえで、条件を満たしていれば、応募して問題ありません。
- 新卒で企業に入社後、2つの企業を経験しています。この場合でも卒業後3年以内であれば第二新卒を名乗って問題ないのでしょうか?
「学校卒業後1~3年以内に離職し、転職活動をしている若手求職者」であれば第二新卒
第二新卒の明確な定義はありませんが、一般的には「学校卒業後1~3年以内に離職し、転職活動をしている若手求職者」を指します。
複数の企業を経験していても、卒業後3年以内であれば第二新卒として扱われることが多いです。
ただし、企業によっては第二新卒の定義や求める条件が異なる場合もあるため、応募先の募集要項を確認し、自身の経歴が該当するかを確認することをおすすめします。必要なら応募前に。直接問い合わせましょう。
第二新卒がいつまで名乗れるのか気になる人は、こちらの記事でも解説しているため併せてチェックしておきましょう。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。
これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。
また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。
既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。
第二新卒の就活が厳しいと言われる3つの理由
第二新卒の就活が厳しいと言われる3つの理由
- 新卒に比べて求人数が少ない
- 中途採用枠ではライバルとスキルの差が大きい
- 早期退職を懸念される
第二新卒の就活が厳しいと言われる理由は、求人数の少なさやライバルのスキル面などの要素が加わります。さらに、企業側は長く働き続ける人材を採用したいと考えるため、入社後数年で転職活動をしているという事実にも不安を感じることがあるのです。
この章では、第二新卒の就活が厳しいと言われる理由を3つ解説します。採用担当者の気持ちを理解して、自分が何をアピールするべきなのかを考えましょう。
①新卒に比べて求人数が少ない
第二新卒の転職活動は、新卒の就活と比較して求人数が少ない傾向にあります。このように、少ない求人のなかから志望企業を見つけなければいけないため、「厳しい」と言われることがあるのです。
また、企業によっては第二新卒を採用していない場合もあり、そもそも応募することすらできないケースも十分あります。
このように、数少ない選択肢から自分に合った企業を探すため、条件を絞りすぎると応募できる企業が見つからず、思うように転職できないことが考えられます。
第二新卒で大手企業を目指す場合は、採用実績のある企業を理解しておくことで就活が進めやすくなります。こちらの記事では第二新卒で大手企業を目指すコツを解説しているためぜひ参考にしてください。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。
これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。
また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。
既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。
②中途採用枠ではライバルとスキルの差が大きい
第二新卒は中途採用枠で応募する必要があります。しかし、選考の同じ土俵に立つ人のなかには長年その業界・職種で経験を積んだ人もいます。第二新卒は入社から1〜3年と短い期間で就職しているため、長年経験を積んでいる人と比較するとスキル面でほかの候補者に劣ってしまう可能性があるのです。
また、一から育成が必要な人材よりも、すでに業界や業務への知見がある人材のほうが育成の手間が少なくなるため、即戦力になる人を求めているケースがあります。
このことから、スキル面でほかの候補者に負けてしまい、選考突破できないことも考えられるのです。
「未経験者歓迎」という求人募集でも、経験者は応募します。経験者が優遇されるかは、企業が求めている人材によって違います。企業のなかには、経験者ではなく、自社で未経験者を育成したいと考えている企業もあります。
③早期退職を懸念される
第二新卒は新卒として入社後、1〜3年の短い期間で転職活動を開始しています。そのため、採用担当者から「自社に入社しても同じような短い期間で退職してしまうのではないか」と懸念される可能性があるのです。
企業は人材を一人採用して育成するだけでも、多くの時間やコストをかけています。育成した人材が早期退職してしまえば、それまでにかけたコストが水の泡となってしまいます。
そのため、選考時に長く勤める意思があることを採用担当者に伝えられなければ、ほかの候補者を選ばれてしまい、選考突破できない可能性が考えられるのです。
キャリアコンサルタントが解説! 実際第二新卒の就活は厳しい?
インターネット上では「第二新卒の就活は厳しい」という声が見受けられますが、実際はどうなのか気になる人もいると思います。
そこでこの章では、キャリアコンサルタントの平井さんに第二新卒の就活が厳しいのか、リアルな情報を聞きました。キャリアコンサルタントの意見を参考に、転職市場の状況を理解して、自身の転職活動に活かしましょう。
アドバイザーコメント
第二新卒の就活が厳しいと噂されることには3つの理由がある
転職活動を厳しいと感じるかどうかは、以下の準備に大きく左右されます。新卒時よりも「なぜこの企業を選ぶのか」「なぜこの仕事をしたいのか」が明確であるほど、選考通過率は高まります。
① 第二新卒の市場価値は高まっている
かつては「短期間で辞めた=忍耐力がない」と見られることもありましたが、現在は人材の流動性が高まり、第二新卒を積極的に採用する企業が増えています。ポテンシャルを重視する企業では、新卒採用と同様に成長の余地がある若手として評価されるケースがあります。
② 新卒就活との違いを理解する
新卒時の就職活動の経験を経た第二新卒では、仕事の向き不向き、働く環境への適応度、自分が大切にしたい価値観がより明確になっています。初職での経験からより現実的な自己理解を深め、キャリア選択の判断軸をより明確にできるチャンスなのです。
③ 初職の経験をどのように活かすか
第二新卒の転職では、「なぜ転職するのか」が重要視されます。単に「前職が合わなかった」と否定するのではなく、「初職の経験を通じてどんな学びを得たのか」「その学びをどう次の仕事に活かすのか」を明確に伝えることです。
「前職では〇〇の業務を通じて△△のスキルを習得したが、自分がより活躍できるのは□□のような環境だと気づいた」など、ポジティブな視点で伝えることが重要です。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活では、限られた選択肢の中から自分に合った仕事を見つけることが重要です。しかし、本当に自分に合った仕事とは何か、見つけるのは簡単ではありませんよね?
そこでおすすめなのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの個性や強みに最適な仕事、そして、あなたが就活でアピールできるポイントが分かります。
自分に合った仕事を見つけ、自信を持って就活を進めるためにも、 ぜひ就活を始める前に「適職診断」を試してみてください。
当てはまるなら対策を考えよう! 第二新卒での選考が通らない人の5つの特徴
第二新卒での選考が通らない人の5つの特徴
第二新卒の就活が厳しいと言われる理由には、実際に就職活動をして選考を突破できない人がいるからです。しかし、選考突破できないのは、第二新卒であること以外にも理由が考えられます。
ここからは、第二新卒での選考が通らない人の5つの特徴を解説します。すでに就活していて選考突破できない人は、当てはまる部分がないかを考えましょう。そして、当てはまる部分があれば、すぐに改善できるよう行動に移しましょう。
①1年未満の転職・退職になっている
新卒で企業に入社してから、1年未満の転職・退職となっている人は、企業側から早期退職の可能性を懸念されて、採用を見送られる可能性があります。
当然、実際に働いてみなければ本当に自分と企業が合うかどうかは判断できません。そして、人によっては企業の社風と合わず、続けることが難しいと考えて転職・退職を選んだ場合もあると思います。しかし、履歴書や職務経歴書だけで判断される書類面接ではそのことが伝わらず、落とされてしまう可能性もあるのです。
このように、志望動機を通して自分が早期退職に至った理由が採用担当者に伝わらなければ、「採用しても早期退職されるかもしれない」と考えられ、選考突破できない可能性が高まります。
早期離職の原因と対策を自分なりに分析できているかが大切です。応募書類に「早期離職となった原因は○○であると現在は反省しています。これを教訓に今後は…」など、しっかりと現在の考えを記載できると、書類突破率も上がるでしょう。
第二新卒の職務経歴書で書くことがなく悩んでいる人はこちらのQ&Aも参考にしてみてください。書き方のアドバイスをしています。
②退職理由が前職の悪口になっている
書類選考を突破して面接選考に進めた場合でも、退職理由がマイナスの印象を持たれてしまえば、採用されない可能性が高まります。
たとえば、「パワハラがあった」「残業が多かった」などの理由は、採用担当者にとっては「前職の悪口をいっている」とネガティブな印象を持つ可能性があります。
それが候補者にとっては事実であっても、退職理由がネガティブな理由では、「自社で同じようなことがあったときすぐに辞めてしまうのではないか」と考えられてしまうのです。
また、今後一緒に働く人材を選ぶなら、前向きな人柄の人を採用したいと考える採用担当者も多いはずです。そのなかで、前職の悪口を言っていると判断されれば、人柄にも不信感を持たれてしまうことが考えられます。
このように、退職理由が前職の悪口になっている人材は、選考を突破できない可能性があります。
退職理由でネガティブな内容が推奨されないと理解できても、ポジティブな理由が思い浮かばない人もいるのではないでしょうか。下記の記事では前向きな印象になる退職理由を解説しているため、ぜひ参考にしてください。
あなたが受けないほうがいい職業をチェックしよう

・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
③志望度が伝わらない志望動機や自己PRを作成している
志望動機や自己PRは、自分の志望職種や意欲を伝える大切な要素です。これは新卒でも第二新卒でも変わりません。
そして、企業に志望度の高さが伝わる内容になっていなければ、ほかに志望度が高いと感じられる候補者がいたときに、そちらを採用されてしまう可能性が高まります。
たとえば、同じ業界にある企業でも、企業理念や業務内容がまったく同じではありません。そのなかで、作成した志望動機や自己PRを使い回したり、志望企業に合わせて作り直さなかったりすると、採用担当者が見たときに「ほかの企業でも良いのではないか」と思われ、志望度が低いと判断されるのです。
このように、企業研究や業界研究によって、その企業ならではの内容に作り込まれていない志望動機や自己PRはオリジナリティが低くなり、選考で落とされてしまう可能性があります。
第二新卒の志望動機や自己PR作りに悩んだときは、それぞれのコツを理解しておくとスムーズです。こちらの記事では第二新卒の志望動機・自己PRを作成する方法を解説しているため、目を通しておきましょう。
志望動機
例文付き! 第二新卒の志望動機でアピールを最大化する秘訣を解説
また、志望動機や自己PRを作り込むためには、企業への理解を深める必要があります。下記の記事では企業研究や業界研究のやり方を解説しているため、併せて確認しておきましょう。
企業研究
作り方例4選|企業研究ノートのまとめ方をイラスト付きで解説!
④基本的なビジネスマナー・身だしなみがない
第二新卒は企業に勤めた経験があるため、基本的なビジネスマナーを身に付けていると考えられる可能性が高いです。しかし、面接で実際に会った際に、ビジネスマナーや身だしなみに問題があると判断されれば、選考突破できない可能性が高まります。
たとえば、基本的な言葉遣いができていなかったり、シワだらけのスーツで面接を受けたり、寝癖を直さなかったりなどの様子があれば、採用担当者は不信感を持ちかねません。
企業によっては顧客対応が業務に含まれ、その能力がある人材を採用したいと考えている場合は、ビジネスマナーや身だしなみがない候補者は採用リスクが高いと判断されます。忙しいなかでおこなう転職活動でも、マナーを守ったり、身だしなみを整えたりするなどの基本は守るようにしましょう。
⑤志望企業が大手ばかり
入社するならば福利厚生や給与などの条件面を考慮して、なるべく大手企業に入社したいと考える人は多いのではないでしょうか。
しかし、第二新卒は新卒に比べて求人数が少なくなるにもかかわらず、志望企業が大手企業ばかりでは、選択肢が少なくなります。また、大手企業は応募者も多いため、その分選考突破の難易度は高くなるのです。
さらに、大手企業の採用枠が中途採用と同じ場合は、高いスキルを有したライバルが数多くいます。そのなかで、スキル面で劣る第二新卒が選考に勝ち残るのは難しくなるのです。
- 第二新卒ですが、どうしても大手企業へ入社したい気持ちが強いです。選考突破する方法はないのでしょうか?
スキルアップしてから選考に臨むのも一つの手段
「第二新卒歓迎」という求人募集であれば、仕事のポテンシャルや発揮できる強み、応募企業だからこそ実現したいことを、積極的にアピールしましょう。
大手企業の第二新卒の求人募集が増えているものの、一般的に応募者が多く激戦です。第二新卒ではなく即戦力としてスペシャリストを求めるケースがあるので、第二新卒で難しい場合は、スキルアップしてから臨むと良いでしょう。
大手企業の関連会社は、労働環境や待遇面で大手企業と差異がない企業がありますので、応募を検討してみましょう。
キャリア支援のプロが解説! 厳しい側面がある第二新卒ならではの対策とは
| 第二新卒 | 新卒 | |
|---|---|---|
| 書類選考 | 長く勤める意思を表明する必要がある | 具体性や文章の読みやすさなどが評価される |
| 適性検査 | 能力検査・性格検査ともに対策が必要 | 能力検査・性格検査ともに対策が必要 |
| 面接 | 転職が必要と考えた理由を伝える必要がある | 志望度の高さや熱意が大切 |
第二新卒が就活をおこなう場合は、厳しいと言われる理由を理解したうえで、対策を考えていく必要があります。対策は書類選考・適性検査・面接それぞれおこなうことで、選考突破できる確率が高まるのです。
ここでは、第二新卒ならではの選考対策について解説します。内定を勝ち取るために必要な情報を得て、本番までに準備を進めましょう。
書類選考編
第二新卒は新卒や前職を長く勤めた中途採用に比べて早期退職が懸念されるため、書類選考を突破するためには長く勤める意思を伝える必要があります。
書類で長く勤める意思を伝えるためには、志望度の高さや仕事への熱意がわかる志望動機や自己PRを作成しましょう。そのためには、志望動機や自己PRが企業ならではの内容になるよう考えることが大切です。
ほかにも、仕事に役立つスキルや資格を取得してアピールすることで、志望度の高さが伝わる可能性があります。たとえば、経理の仕事を目指すために日商簿記2級を取得したり、不動産業界を志すために宅建の資格を取得したりすれば、早期退職のイメージを持たれることを避けられます。
適性検査編
第二新卒の選考では適性検査を実施する企業もあり、対策を立てておくことが必要です。どの適性検査を実施しているかは企業によって異なるため、事前にリサーチしつつ、以下の適性検査を網羅的に対応できるよう対策しておくと安心です。
第二新卒の選考で実施されやすい適性検査の種類
- SPI
- 玉手箱
- Web-CAB
- TG-WEB
- CUBIC
なお、各適性検査の参考書を一冊購入して網羅的に練習することで対策が可能です。一方で、性格テストもある場合は企業の求める人物像を理解しつつ、嘘をつかずに回答することが求められます。
嘘をつくと回答に矛盾が生じて、結果的に評価が低くなる可能性があることには注意しましょう。
適性検査の種類が多くて準備が大変な場合、SPIと玉手箱の対策を優先しましょう。これらは多くの企業で採用されていて、計数・言語・論理の基礎問題が共通しています。
計数や言語問題の解法に慣れ、時間内に正確に解く練習をすると、ほかの適性検査にも応用しやすくなります。まずはSPIの参考書や問題集を活用し、効率的に対策を進めましょう。
適性検査の勉強方法に悩む場合は、それぞれの傾向や対策を理解しましょう。こちらの記事では適性検査の勉強方法や対策を解説しているため、併せて目を通しましょう。
SPI
効率抜群なSPIの勉強法|出題形式と頻出問題を踏まえた対策を伝授
玉手箱
玉手箱とは? 出題内容や突破するための解き方のコツを徹底解説
Web-CAB
Web-CABでハイスコアを取る! 例題付きで突破するコツを解説
TG-WEB
TG-WEBを突破する方法 | 例題付きで対策方法やコツを徹底解説
CUBIC
例題・答え付き|CUBIC適性検査の特徴や完全攻略する方法を解説
こちらではTG-WEBの英語対策についてまとめています。あわせて参考にしてみてください。
面接編
第二新卒の面接では、企業に対する志望度の高さや熱意が伝わるように意識しましょう。そのためには、志望動機や自己PRだけでなく前職の退職理由についても返答内容を考えておくことが大切です。
採用担当者は面接選考中も「最初の企業と同じように早期退職しないだろうか」と考えている可能性があります。それでも候補者を面接に呼んだのは、直接話を聞いて判断したいと考えているからです。
だからこそ、「前職ではできない仕事がしたい」「取得した〇〇の資格を活かしたい」など転職しなければかなえられないことを志望動機や退職理由に加えることが大切です。採用担当者が退職理由に納得できれば、選考突破できる確率が高まります。
第二新卒が転職活動を進める場合は、転職の流れを理解しておくことも大切です。こちらの記事では第二新卒の転職活動の流れを解説しているため、ぜひ参考にしてください。
ここをアピールすることがおすすめ! 第二新卒の就活で強みとなる部分
第二新卒の就活で強みとなる部分
- ポテンシャル
- スキルや文化の吸収しやすさ
- 新卒・既卒に比べたビジネスマナー・スキル
第二新卒が就活を成功させるためには、自分の強みやアピールポイントを明確にしておくことが大切です。新卒や既卒にない部分を採用担当者に伝えることで、あなたならではの特徴を伝えて差別化することができ、選考突破できる確率が高まります。
この章では、第二新卒の就活で強みとなる部分を解説します。自分のアピールポイントをどのように伝えるかを考え、選考突破を目指しましょう。
ポテンシャル
第二新卒を採用したいと考える企業は、候補者が持つポテンシャルに期待している場合が多いです。第二新卒はまだ社会人の経験が短いからこそ、働いてみてから今までなかった適性が明らかになる可能性があるからです。
たとえば、人と話すのが苦手と思っていた人が営業職に就くことで、相手の意見を汲み取るよう努力して、ヒアリング力に長けた人材になる可能性が考えられます。このような経験年数が少ないからこその柔軟性は、中途採用の応募者がアピールしにくいポイントです。
このように、第二新卒が就職活動をする場合は、一早く戦力になれるよう尽力していく旨を伝えましょう。採用担当者が候補者のポテンシャルに魅力を感じれば、選考突破できる可能性が高まります。
前職での経験をしっかりと自分の糧にしている人にはポテンシャルを感じました。
経済ニュースや業界動向を気にする習慣が身についていたり、「利益率」「コンプライアンス」といった社会人ならではの言葉が自然と出たりすると、今後も新しいことを吸収できる人だと期待が高まります。
スキルや文化の吸収しやすさ
第二新卒は前職で過ごした期間が短い分、企業の社風や文化に染まり切っていないと考えられます。そのため、転職しても前職の社風にとらわれず、文化を理解するのに時間がかからないという魅力があるのです。
たとえば、前職でマニュアルがしっかり整備されていた企業に勤めていた人が、自分で作業を進めて良い企業に就職した場合、始めのうちは混乱しやすいものです。しかし、前職の社風に染まり切っていない第二新卒であれば、自分で考えて行動できるようになるまでの期間が早い可能性があります。
ほかにも、似た業務でも企業によってやり方や進め方が違う可能性は大いにあります。第二新卒であれば企業のやり方を一早く吸収して、戦力になってくれるのではと考えられ採用につながる場合があります。
新卒・既卒に比べたビジネスマナー・スキル
一度企業に就職した経験があることから、第二新卒には一般的なビジネスマナーや電話応対、メール対応などのスキルを有していると考える企業が多いです。
新卒や既卒を採用する場合、社会人経験がないことから、基本的な業務でも一から教えなければなりません。忙しい上司や先輩社員が基礎的な業務を教えるのは、企業によっては負担になるケースもあります。
その点、第二新卒であれば新卒や既卒と比べて育成コストが少なく済む場合があるのです。すでに基本的なマナーやスキルを身に付けていて、入社後すぐに教える業務が企業にまつわるものが中心になれば、それだけで即戦力になれる可能性が高まるため、その点をアピールするのがおすすめです。
対外的なマナー、電話応対のマナー、言葉遣いといったビジネスマナー・スキルは第二新卒であれば身に付けておくべきものです。
挨拶や名刺の渡し方、正しい電話応対ができなければ、対外的な信用をなくします。また社会人としての正しい言葉遣いも求めることがあります。
順序立てて行動しよう! 第二新卒の就活を成功させる5つのステップ
第二新卒の就活を成功させる5つのステップ
第二新卒が就職活動を成功させるためには、選考対策以外にも企業選びやスケジュールを決定する面で気を付ける必要があります。計画を立てないまま就職活動が進めば、うまくいかずに長引いてしまう可能性もあるのです。
ここからは、第二新卒の就活を成功させる5つのステップを解説します。順序立てて行動して、志望企業への入社を目指しましょう。
ステップ①転職を考えた理由を明確にして転職の軸を定める
第二新卒が現職を辞めたいと思うには、何か理由があるはずです。しかし、その理由を明確にせず、次の仕事でも改善されない場合、せっかく入社しても納得できず、また転職する可能性があります。
このような再度の転職を避けるためには、転職を考えるきっかけとなった理由を明確にして、譲れない転職の軸を定めましょう。転職の軸を定めることで企業選びの基準が明確になり、転職後に後悔する可能性を減らせます。
転職の軸を定めるときは、前職で「嫌だった部分」を書き出しましょう。そして、書き出した条件に優先順位をつけることで、自分が働くうえで大切にしたい事柄が見えてきます。
転職の軸が定まらない人は、下記の記事で見つけるコツを解説しているため、ぜひ参考にしてください。
ステップ②就活のスケジュールを決める
就職活動には一般的に1〜3カ月程度の時間がかかるため、どのように転職活動を進めていくかスケジュールを考えることが大切です。一方で、スケジュールを考えないまま就職活動を開始すると、現職を退職するまでに仕事が見つからない可能性があるのです。
そして、就活のスケジュールを立てるときは、自分が新しい職場に入社したいタイミングを明確にしましょう。たとえば、きりが良い時期に転職したい場合は、年度が変わる4月や人事異動のある10月がおすすめです。
もしくは、現職でボーナスをもらった6月や12月以降に就職活動を開始することもできます。自分が転職したい時期の3カ月前を目安に、就職活動のスケジュールを決めましょう。
転職のタイミングに悩んでいる人は、目的に合わせて選ぶ方法もあります。こちらの記事では転職のタイミングの選び方を解説しているため、ぜひ参考にしてください。
- 現職を今すぐに辞めて就職活動がしたい第二新卒です。新しい仕事が決まるまで辞めてはいけないのでしょうか?
辞めても問題ないが「今すぐ辞めたい」という状態は要注意
在職中に転職にこだわるべきなのは、貯金や当面の生活費に余裕がない場合です。採用されやすさや良い転職先と出会えるかどうかには、あまり関係ありません。
ただ、「今すぐ辞めたい」という状態には注意が必要です。切羽詰まった状況では、「決まればどこでもいい」と冷静な判断を欠きがちだからです。さらに、後任者への引き継ぎなど、現職で果たすべき責任が残っている場合もあります。
辞めることとより良い職場を見つけることは別の問題です。まずは、自分の経済状況を整理しましょう。
また、前職で退職するための届け出をいつ出せば良いのかわからない人もいるのではないでしょうか。こちらの記事では退職届のタイミングを解説しているため、併せてチェックしておきましょう。
ステップ③自己分析をおこない志望職種を明確にする
第二新卒が転職活動をするときは、現職と同じ職種を目指すのか、違うキャリアにチャレンジするのかを明確にする必要があります。現職と同じ職種を目指す場合は、企業に即戦力として迎え入れられる可能性があります。
一方で、違うキャリアにチャレンジする選択肢を選ぶ人もいるのではないでしょうか。違うキャリアを選ぶ場合は、自己分析をおこない、自分が何をやりたいのかを明確にして、書類や面接で伝える必要があります。
自己分析の流れ
- 現職の職務内容での不満点を考える
- 興味のあること・やってみたいことを書き出す
- 不満点と興味のあることを見比べて両立できる仕事を考える
- 出てきた職種の仕事内容や働き方を比べて志望職種を定める
自己分析で明確になったチャレンジしたい職種について、それを選んだ理由は後で見返せるようにメモしておきましょう。志望動機や自己PRを作成するときに役立ち、説得力のある内容が作成できます。
ステップ④企業研究・業界研究で転職の軸に合った企業を探す
志望職種が明確になったら、その職種が活躍できる業界を調べましょう。事務職や営業職のような複数の業界に渡って活躍できる職種の場合は、興味がある分野の企業を選ぶことがおすすめです。
たとえば、動物が好きな人であれば、ドッグフードを販売する会社やペットショップを展開する企業などが選択肢に入ります。複数の業界で悩む場合は、業界研究を通してより興味がある分野を絞り込みましょう。
業界研究ができたら、以下のような項目をリサーチする企業研究を通して志望企業を定めていきましょう。
企業研究の項目
- 基本情報
- 経営理念
- 業績
- 事業内容の特徴
- 企業の強み
- 企業の弱点や課題
- 同業他社との違い
- 求める人物像
- 社風
- 将来性
- 給与・年収
- 福利厚生
- 勤務地・転勤の有無
- 就業時間・休日
- 所感や疑問点
上記の項目に優先したい事柄から順位をつけていき、一番魅力的に感じた企業を第一志望として就活を進めることがおすすめです。
第二新卒の場合、希望する勤務地・職種・給与・働き方などを設定し、出てきた企業を研究して応募先を絞り込むことも有効です。条件面だけで選ぶのではなく、企業の特徴や将来性、求める人物像が自分とマッチしているかも確認しましょう。
求人検索はあくまで入口とし、業界研究・企業研究を深めながら、納得のいく転職先を見つけることが大切です。
ステップ⑤選考対策をおこない内定取得を目指す
志望企業の内定獲得の確率を高めるためには、書類選考や面接対策を進めることが大切です。
入念な自己分析・企業分析を重ね、志望動機や自己PRを作成したら、第三者に読んでもらい添削をお願いしましょう。添削してもらう場合は、「ほかの企業でも言える内容になっていないか」「ネガティブにとらえられないか」など、特に見て欲しい部分を明確に伝えることで、アドバイスをもらいやすくなります。
さらに、書類選考を突破したときのことを考え、面接練習もおこないましょう。面接練習は、友人や家族に面接官役をしてもらい、受け答えの様子を見てもらう方法がおすすめです。一人でおこなう場合は、自分が質問に答える様子を撮影することで、後から見返せます。
後悔のない就職活動ができるよう、できる対策はすべておこないましょう。
書類選考が通らない場合は、何か原因がある可能性があります。こちらの記事では書類選考が通らないときの対策を解説しているため、併せてチェックしておきましょう。
また、志望動機の添削方法がわからない人は以下の記事がおすすめです。さらに独自性をアピールできる志望動機が作成できるようになります。
第二新卒の就活が厳しいと悩む人におすすめのQ&Aも併せてチェック!
第二新卒が就活を進める方法が理解できても、実際に転職成功できるのか不安に思う人もいるのではないでしょうか。転職したい気持ちがあっても、やり方がわからず、悩む人もいるはずです。
そこでこの章では、PORTキャリアに寄せられたQ&Aから第二新卒の就活に悩む人へおすすめの内容を3つ紹介します。後悔しない就職活動にするために、必要な情報を身に付けましょう。
第二新卒の就活が厳しいと悩むときは自分の転職の軸を明確にしよう!
第二新卒の就活が厳しいと悩むときは、転職の軸を明確にし、自分が次の仕事でどのように働きたいのかを考えましょう。転職の軸を定めることで企業選びがしやすくなり、自分に合った企業が見つかる可能性が高まります。
また、転職活動を開始してもうまくいかないときは、志望動機や自己PRの内容がブラッシュアップできないか考えましょう。企業に合わせた内容を作成できれば、志望度の高さが採用担当者に伝わり、選考突破できる確率が高まります。
アドバイザーコメント
「第二新卒歓迎」は積極募集しているため転職のチャンス
「第二新卒歓迎」という求人募集は、第二新卒を積極的に採用したいと考えていて、実務経験より仕事の意欲やポテンシャルを評価する企業が多いです。
第二新卒を採用したい企業は、応募者が現職を短期間で辞めることは気にしませんが、なぜ辞めるのかを確認します。人間関係や労働環境が理由の場合、自社でも同様の問題が起きると考える採用担当者もいます。
できれば、新卒で就職した会社では難しく、応募企業でかなえたいことを実現したいなど、採用担当者が納得する転職理由を伝えてください。
未経験の場合は可能な限りスキルを身に付けて戦力になれることをアピールしよう
未経験の職種を希望する場合でも、コミュニケーションスキルやパソコンスキルなど汎用できるスキルや、応募職種に関連する自己研鑽をアピールして、短期間で戦力になることをアピールすると良いでしょう。
新卒採用の補填として採用したい、経験者ではないフレッシュな人材を自社で育成したいといった目的で、積極的に第二新卒や未経験者を採用したいと考えている企業もあります。
第二新卒の枠に捉われず、応募企業で叶えたいことは何か、どういった能力を発揮できるかを考えて、積極的に応募してみましょう。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi










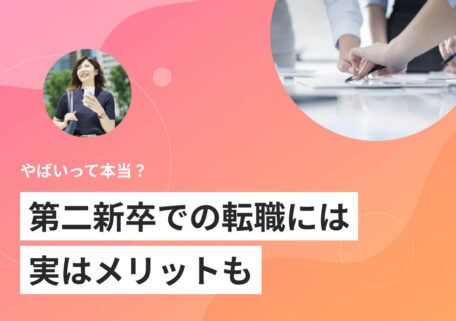








3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/産業カウンセラー
Atsuko Hirai〇ITメーカーで25年間人材育成に携わり、述べ1,000人と面談を実施。退職後は職業訓練校、就労支援施設などの勤務を経て、現在はフリーで就職・キャリア相談、研修講師などを務める
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/公認心理師
Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当
プロフィール詳細キャリア・デベロップメント・アドバイザー/キャリアドメイン代表
Kenichiro Yadokoro〇大学でキャリアデザイン講座を担当した経験を持つ。現在は転職希望者や大学生向けの個別支援、転職者向けのセミナー、採用担当者向けのセミナーのほか、書籍の執筆をおこなう
プロフィール詳細