この記事のまとめ
- 自己PRで趣味を題材にするメリット・デメリットを理解しよう
- 趣味の自己PRは4つステップを押さえれば魅力を引き出せる
- 趣味別の例文10選を参考に自己PRを書いてみよう
自己PRはさまざまなテーマで書くことができるので、自分の趣味を題材にする人もいます。しかし、そうした人のなかには、作成を進めるうえで「趣味を題材にした自己PRは企業から評価されるのかな」「趣味の自己PRはどのように書けば良いのだろう」といった悩みを抱く人もいるのではないでしょうか。
趣味を題材にした自己PRは、書くときのポイントや注意点を理解することで魅力的に企業にアピールすることができます。4ステップで解説している書き方や例文を参考にしながら自分の経験を盛り込んだ自己PRを作成しましょう。
この記事では、キャリアアドバイザーの平井さん、西さん、古田さんとともに、趣味を自己PRにすることのメリット・デメリットや書き方について解説します。
キャリアコンサルタントが趣味を自己PRにするならどのようにアピールするのかを紹介しているので、企業に刺さる内容にするために押さえておくべきポイントを整理しましょう。また、趣味から強みを見つけるポイントについても解説しているので、悩んでいる人はぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
1位:自己PR作成ツール
自己PRが思いつかない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
2位:志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
3位:WEBテスト対策模試
模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
4位:面接回答集60選
見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました
5位:逆質問例100選
面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています
【併せて活用したい!】
スキマ時間3分でできる就活診断ツール
①適職診断
たった30秒であなたが受けない方がいい仕事がわかります
②面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
趣味の自己PRはポイントを押さえれば効果的に強みを伝えられる
「自分の好きなことを通して強みを伝えられる」という点で趣味を題材にした自己PRを選ぶ人もいるかもしれませんが、ただ自分の好きなことを述べるだけでは自己PRとして不十分です。
企業は自己PRを通して学生の強みを把握し、入社後に活躍できる人材なのかを見ています。そのため、趣味を題材にする場合でも「企業が自己PRを通して知りたいこと」を押さえて作成することが、高評価の鍵となるのです。
この記事では、まず趣味を題材にすることのメリット・デメリットを解説します。デメリットもあることを理解して進めたうえで、趣味から見つけられる強みの紹介や書き方についての解説を読むことで、自分の趣味に合った強みで効果的な自己PRを書くことができます。
さらに、キャリアコンサルタントからのアドバイスや趣味別の自己PR例文を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
「趣味」をアピールするなら、自己PR作成ツールを活用しよう
自己PRは就活において必ずといっていいほど必要になります。自己PRが曖昧なまま就活がうまくいかなかったという就活生は多くいます。
そこで活用したいのが「自己PR作成ツール」です。これを使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
趣味の自己PRはどう評価される? 企業が自己PRで知りたいこと
趣味とは自分の好きなことや興味を持って取り組んでいることであるため、自己PRでも自由に内容を決められると考え、題材に選ぶ人もいるかもしれません。しかし、先でも解説したように、趣味を題材にするときは企業の求める内容で書くことが大切です。
なぜなら、企業は自己PRを含む選考のあらゆる質問を通して、学生の人柄やどんな強みを持っているのか、自社で活躍してくれる人材なのか、社風とマッチしているかなどを確認しているからです。
特徴がよくわからない学生を採用すると、自社の求める人物像とミスマッチを起こし、早期離職などのリスクにつながる恐れがあります。そのため、企業は選考中に学生がどれだけ自社とマッチしているかを見ているのです。
趣味を題材にした自己PRの場合でも、企業が自己PRで知りたい要素をうまく盛り込むことで高評価を狙えます。逆に企業の求める人物像を理解して、人柄や強みをうまく伝えることができないと「趣味の話をしたいだけ……?」と採用担当者からの評価が下がってしまう可能性があるのです。
趣味の自己PRを伝えるときは、企業が自己PRを聞く理由を理解したうえで、内容に注意しましょう。
趣味を題材にした自己PRでも、企業が求めるのは人柄や強み、社風との適合性です。趣味の話だけで終わらず、具体的なエピソードを通して自分の価値や成長が伝わるよう工夫しましょう。
自己PRで趣味を題材にするのはアリ? メリット・デメリットを確認
ここまでの内容で、自己PRで趣味を題材にする際は、「企業が知りたいことを伝えられれば趣味を題材にしてOK」と安心している人もいるかもしれません。しかし、そもそも自分の強みを述べる自己PRにおいて、趣味を題材に選ぶのには、デメリットも存在します。
そのことを理解せず、安易な気持ちで趣味を自己PRの題材に選んでしまうと、採用担当者からのマイナスの見え方に気付けず、自己PRの評価が下がってしまうかもしれません。
ここでは、自己PRの題材に趣味を選ぶうえでのメリットとデメリットを一つずつ解説します。それぞれの内容を知ったうえで、自己PRの題材に趣味を選ぶのかどうか判断しましょう。
メリット:人柄をアピールできる
趣味を伝えることで、人柄をアピールすることができます。
趣味は、基本的に強制的におこなうものではなく、自分が興味を持って熱中していることです。そのため、趣味を題材にすることで「どんなことが好きなのか」「どのように物事に取り組むのか」などを採用担当者に自分の人柄を伝えることができます。
また、趣味に対する好きという感情は人それぞれ違うので、自分の価値観や興味を示しやすく、ありのままの自分について知ってもらうにはぴったりの題材です。
デメリット:「趣味だから発揮できた」と強みの汎用性を懸念される
趣味を自己PRにすることで考えられるデメリットは、「趣味だからその強みを発揮できたのではないか」と思われる可能性があることです。
趣味は、自分から興味のあることに取り組んでいるものなので、採用担当者から見ると、「その強みは仕事でも意欲的に活かしてくれるのだろうか」と懸念されてしまうかもしれません。
そのため、自己PRで趣味を伝えるときは、培った強みだけではなく、強みを企業でどのように活かせるのかを考え、活かす意欲があることまで具体的に示しましょう。
そうすることで、入社後に企業で活躍しているイメージを採用担当者に持ってもらうことができ、選考に通る可能性が高まります。
- 趣味を自己PRの題材にするとき、マイナス評価になりやすい業界や企業はありますか?
どのような職種でも伝え方次第でプラス評価を得られる
自己PRで趣味を題材にすることは、伝え方にもよりますがプラスになることが多いです。そのため、趣味を題材にすることでマイナス評価になりやすい業界や企業が明確にあるわけではありません。
というよりは、労働時間が不規則で長時間になりがちな職種や、仕事に集中してほしいと考える企業の場合、採用後に趣味の時間が取りにくくなるため「ストレス解消がしにくくなると業務に支障が出るのでは?」と懸念される可能性はあります。
趣味を題材にすることが直接合否に影響するとは考えにくいですが、どんな職種であっても、伝え方次第でプラス評価にすることは可能です。
趣味の話は自己PR以外に、自己紹介のタイミングで話すことも可能です。こちらの記事では、自己紹介で趣味を伝える際のポイントを紹介しています。参考にしてみてください。
コピペで使える自己PR文がかんたんに作れます
自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?ツールで実際に文章を作成してみてからブラッシュアップする方が効率的に受かりやすい自己PRを作成することができます。
「自己PR作成ツール」 を使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
自分の趣味はどのタイプ? 趣味別に示せる強みを紹介

自分の趣味はどのタイプ? 趣味別に示せる強みを紹介
自己PRの題材として趣味を選ぶとき、自分の趣味はどのような強みにつなげられるのか迷う人もいるかもしれません。先でも解説した通り、自己PRとは強みをアピールするものであるため、題材に選んだ趣味から強みを見つけられなければ、自己PRとして成立しないといえます。
とはいえ、自分の趣味がどんな強みにつながっているのかわからないと悩む人もいるのではないでしょうか。
ここでは、4つの趣味別にアピールできる強みを紹介します。それぞれの趣味のタイプごとで培える代表的な強みを確認し、自分の趣味がどのような強みにつなげられるのか考えてみてください。
黙々と一人でおこなう趣味
黙々と一人でおこなう趣味には、時間をかけて取り組むという共通点があります。たとえば、映画鑑賞であれば1本の映画を観るために、2時間程度の時間が必要です。読書の場合も、本のジャンルによりますが、1冊を読み切るためには少なくとも1~2時間程度かかるため、集中力が身に付けられます。
また、こうしたタイプの趣味は集中力だけでなく、発想力や思考力を養うこともできます。映画はさまざまなシチュエーションを体験できるので、新たな気付きがあり、新しい発想につながります。ほかにも、読書においては文章の内容から物事を順序立てて考える力を養うことが可能です。
こうした趣味で培える集中力は、仕事を円滑に進めるために必須のスキルといえ、企業では、目標を達成するために試行錯誤を重ねて仕事に取り組む思考力や発想力も必要になります。
そのため、黙々と取り組む趣味で培ったこれらのスキルを仕事でも発揮できることを示せれば、どのような仕事でも懸命に取り組んでくれる人材として評価される可能性があるのです。
黙々と一人でおこなう趣味で培える強みの例
- 集中力
- 発想力
- 思考力
- 探求力
- 想像力
黙々と一人でおこなう趣味の例
- 読書
- 映画鑑賞
- 音楽鑑賞
- 料理
- 絵を描く
- ゲーム
- 営業のような人前で話す機会の多い仕事を希望する場合、趣味に読書を自己PRで伝えると物静かな人だと思われないか心配です……。
読書で得た強みを営業スキルに結びつけてアピールしよう
読書は、営業職やプレゼンの機会が多い職種でも強みとしてアピールできます。読書を通じて得た知識や洞察力は、自分の意見を説得力のある形で伝えるための基盤となるからです。
また、読書によって蓄えた情報は、顧客との会話や提案内容の幅を広げる助けにもなります。具体的なエピソードを交え、読書があなたの思考を深め、人前での説得力や対応力を向上させたことを伝えましょう。
「この本を通じて得た視点を活かし、提案に深みを持たせられた」などのエピソードを加えると、読書が営業スキルにどう結びついているか採用担当者に伝わりやすくなります。
就活で趣味を聞かれたときに、読書・映画鑑賞・音楽鑑賞と答えたい人は下記の記事を参考にしてください。アピールする際のコツなどを解説しています。
読書
「趣味は読書」は武器になる! 伝えるコツや深掘りの対策を解説
映画鑑賞
就活で「趣味は映画鑑賞」はOK? 圧倒できる3つのアピールのコツ
音楽鑑賞
例文12選|趣味の音楽鑑賞で差別化する方法! 企業側の印象も紹介
テンプレを活用すれば受かる自己PR文が作れます
自己PRのネタを決めても、それを裏付けるエピソードに悩む学生は多いです。しかし、特別なエピソードがなくても受かる自己PRを作ることはできます。
そこで紹介したいのが「自己PR作成ツール」です。自己PR作成ツールなら、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、分かりやすいテンプレであなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
外に出ておこなう趣味
外に出ておこなう趣味には、美術館巡りやカメラなどが挙げられます。
外に出ておこなう趣味の共通点は、新しいことに出会えることです。たとえば、美術館巡りであれば、さまざまな作品に触れることができるのでクリエイティブな刺激を得られます。
また、カメラで写真を撮ることを意識すると、普段何気なく過ごしている街のなかでも面白い発見ができます。どの趣味も家の中ではなく、外に出ておこなうので今まで知らなかった新しい知識への探求心にもつながります。
企業で働く際には、さまざまな情報をもとに業務の進め方を検討したり、アイデアを出し合ったりする場面がたくさんあります。この趣味で培える情報収集力は、あらゆる情報の中から有益な情報を見つけ出せる力なので、ビジネスのあらゆる場面において評価されやすいといえます。
現状に満足せず新たな発見ができる人材もまた、どんな職種であっても重宝されるため、このタイプの趣味で培える強みは自己PRでアピールするのにおすすめといえるのです。
外に出ておこなう趣味で培える強みの例
- 情報収集力
- 発見力
外に出ておこなう趣味の例
- カフェ巡り
- 美術館巡り
- カメラ
外に出る趣味を持っている人は、好奇心旺盛な人とも言えます。こちらの記事では、好奇心旺盛を自己PRでアピールするにはどうすれば良いのかを例文付きで解説しています。気になる人は参考にしてみてください。
身体を動かす趣味
身体を動かす趣味には、登山やスポーツ全般が挙げられます。
これらの趣味はただ運動をするだけでなく、その趣味のなかで自分なりの目標や目的を決めて取り組めるという共通点があります。
たとえば、登山では頂上まで登ることができると、達成感を感じ楽しいと思うかもしれませんが、その道中は決して楽ではなく、厳しいことや大変なことも起こり得ます。そのつらさから逃げることなく、目標のために頑張ることができれば、趣味であっても忍耐力が養えるといえます。
また、ランニングであれば1時間で10km走るなどの目標を掲げて実行に移すことができていれば、目標に対して諦めることなく進んでいく継続力が培えているかもしれません。
ビジネスにおいて課題に直面したり、大変な仕事に取り組んだりする機会はとても多くあるため、それらのストレスを乗り越えられる忍耐力や、冷静な思考で現状と向き合える課題解決力が求められます。
だからこそ、身体を動かす趣味で培ったこれらのスキルをしっかりアピールできれば、忍耐強く働き続けられる人材として高い評価を得られるかもしれません。
身体を動かす趣味で培える強みの例
- 忍耐力
- 課題解決力
- 協調性
- 継続力
身体を動かす趣味の例
- 登山
- スポーツ
- ランニング
登山やスポーツなどにはアクシデントがつきものです。そのため、あらかじめ危機を予測したり自己管理したりする能力が伝わります。また、多くのスポーツはチームでおこなわれるため、チームワークについても評価されるかもしれません。
継続力は自己PRでアピールしやすい強みの一つです。こちらの記事では、継続力をアピールする際の書き方や注意点を解説しています。継続力の自己PRの作成に悩んでいる人は、参考にしてみてください。
自己PRが思いつかない人は、ChatGPTを活用して自己PRを完成させよう
ChatGPTを使った自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?
簡単な質問に答えていくだけでChatGPTが自動で魅力的な自己PRを作成します。
作った自己PRは選考で活用できるものになっているので、ぜひ活用して採用される自己PRを完成させましょう。
複数人でおこなう趣味
複数人でおこなう趣味には、キャンプや旅行が挙げられます。
複数人でおこなう趣味は、意見や価値観の異なるほかの人と計画を練ったり、尊重し合って行動したりすることが必要です。
たとえば、キャンプや旅行であれば、目的地や日程の調整をしたり、必要に応じて念入りなリサーチなどやるべきことが多くあります。また、一緒に行動する人たちと円滑なコミュニケーションを取り、全員が楽しめるように気を遣うことも大切です。
こうした趣味で培える協調性は、いろいろな人とかかわりながら進めていく仕事において、重要視されるスキルの一つです。またビジネスシーンでは、滞りなく仕事を進めるために期日が設けられていることが多いので、期日までに仕事を終える計画性なども求められます。
そのため、複数人でおこなう趣味で培ったスキルを自己PRで示すことで、周囲の人と協力しながら仕事を進められる人材として認められる可能性があります。
複数人でおこなう趣味で培える強みの例
- 協調性
- 計画性
- 行動力
- コミュニケーション力
複数人でおこなう趣味の例
- キャンプ
- 旅行
- イベント参加
就活で趣味を聞かれたときに旅行と答えたい人はこちらの記事を参考にしてください。例文16選で伝え方を解説しています。
複数人でおこなう趣味から「気遣いができること」をアピールすることもできます。以下では気遣いができることを自己PRでアピールするためのコツについて、キャリアコンサルタントが解説しているので参考にしてみてください。
自己PRで悩んだらまずは作成ツールを使ってみよう!
「自己PRがうまく書けない」「どんな強みをアピールすればいいかわからない」…そんな悩みを抱えている方には「AI自己PR作成ツール」がおすすめです。
AIがあなたの経験やスキルに基づいて魅力的な自己PRを自動で生成し、短時間で書き上げるサポートをします。
短時間で、分かりやすく自分をアピールできる自己PRを完成させましょう。
就活の専門家に聞いた! 平井さんなら趣味をどう自己PRにする?
趣味を題材にした自己PRを作成しようと思ったとき、「どのようにアピールすると企業に評価されるんだろう」、「ほかの人はどんな自己PRなのかな」と気になる人も多いのではないでしょうか。
自己PRは、就活で自分をアピールできる大切な要素の一つなので、できるだけポイントを押さえたものを作成したいですよね。
ここからは、就活の専門家である平井さんが、趣味の自己PRについて解説します。平井さんのアドバイスを自分の自己PRにも反映させてみましょう。
アドバイザーコメント
どのような趣味でも企業で活躍できる視点を持つことでアピールできる
趣味を題材にした自己PRは、内容次第で「趣味だから頑張れたのでは? 」と思われる可能性があります。しかし、どんな趣味であっても自己理解を深め、それを活躍につなげる視点を持てば、企業に響くアピールが可能です。
たとえば、過去に支援した就活生は「料理」が趣味でした。一見、仕事とは直接関係ありませんが、私なら以下のようにまとめます。
「料理は計画性や段取り力が求められるため、私はそのスキルをプロジェクトの進行管理やチーム運営に活用できると考えています。また、限られた食材で最善の一皿を作る工夫や柔軟性は、仕事でも同じ発想が求められると思います」
趣味から得た気づきや成長を企業でどのように活かせるかを伝えよう
このように、趣味を通じて自分の強みを認識し、それが業務にどう活かせるかを具体的に説明することで、採用担当者に説得力を持って伝えられます。
趣味を単に楽しむものとして終わらせるのではなく、そこから得た気付きや成長を振り返ってみてください。そして、結果として自分がどのような人材なのか、どのように貢献できるのかを意識して伝えることが重要です。
自分の経験を当てはめるだけ! 趣味の自己PRの書き方を4ステップで紹介
自分の経験を当てはめるだけ! 趣味の自己PRの書き方を4ステップで紹介
- 趣味を通して培った強み
- 強みの根拠となる趣味の具体的なエピソード
- 趣味を通して得た学びや結果
- 趣味で培った強みを仕事でどのように活かすか
ここまで、趣味を自己PRでアピールすることのメリット・デメリットや代表的な強みについて解説してきました。しかし、「趣味の自己PRについて理解はできたけれど、どうやって書けば良いのだろう……」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
趣味の自己PRは、正しい書き方で作成しないと企業で活かせる強みとしてアピールすることができません。書き方をしっかり理解して企業の求める自己PRを作成しましょう。
ここからは、趣味の自己PRの書き方を4ステップで紹介します。このステップに自分の経験を当てはめていくことで、企業に魅力をアピールできる自己PRを作成できます。
趣味の自己PRは、趣味で培った強み・具体的なエピソード・学びや結果・強みの活かし方の4つのステップで作成します。自己PRで題材にする趣味を決めたら、さっそく書いてみましょう。
自己PRで悩んだらまずは作成ツールを使ってみよう!
「自己PRで伝えたいことはあるのに、言葉にできない」そんな悩みがある方には「自己PR作成ツール>」が強い味方になってくれます。
表現に悩んでいても、AIがあなたの考えを汲み取り、わかりやすく効果的なPR文にまとめてくれます。
ぜひ効率的に自己PRを仕上げ、選考の準備を整えましょう。
①趣味を通して培った強み
前述の通り、自己PRは選ぶ題材にかかわらず、自分の強みをアピールするものであるため、最初に趣味を通じて培った強みを伝えましょう。自己PRを通して企業がもっとも知りたい結論を最初にわかりやすく書くことで、採用担当者の目に留まりやすくなります。
また、最初に強みを伝えず趣味の話をしてしまうと、「この学生は趣味の話をしたいだけなのかな……? 」と面接官に思われてしまいます。好きなことを語るだけでは、自分の持っている強みや人間性を伝えるのは難しいため、自己PRに企業が求めていることを理解して、しっかりと強みを伝えられる内容を意識してください。
また、このとき選ぶ強みは、企業の求める人物像に合ったものにしましょう。企業のニーズに合う強みを選ぶことで、入社後にあなたが活躍するポジティブなイメージを持ってもらいやすくなります。
趣味を通して培った強みの例
私の強みは探求心があることです。この強みは趣味の読書で培われました。
②強みの根拠となる趣味の具体的なエピソード
次に強みの根拠となる具体的なエピソードを述べましょう。強みを伝えるだけでは信憑性が薄く、採用担当者から見ると、本当にその強みを持っているのか判断が難しいからです。
具体的なエピソードを盛り込むことで、強みに対する信憑性を高められます。採用担当者もその場面をイメージしやすくなるので、興味を持って話を聞いてもらえることにつながります。
また、エピソードのなかに趣味になったきっかけを盛り込むことも大切です。どのような理由で始めたのか、熱中していった過程などを伝えることで人柄をアピールできるので、あなたにしか話せない内容を盛り込むようにしましょう。
ここで伝える趣味の内容は、自分が楽しく語ることのできる趣味を選ぶことで、さらに魅力的な自己PRになります。
具体的なエピソードの例
最初に本を読んだのは幼稚園のときです。読書が好きな祖父からのクリスマスプレゼントでした。大好きな祖父の隣で本を読む時間がとても心地よく、大切な時間となりました。
それ以来、本の魅力に気付き、毎月10冊の本を読んでいます。さまざまなジャンルを読みますが、特にミステリー小説が好きです。ミステリー小説を読む醍醐味は、散りばめられた伏線を回収しながら謎を解明していくことだと思っています。
③趣味を通して得た学びや結果
自己PRでは、強みの根拠となるエピソードから何を学んだのかまでを伝えることが重要です。学びがあることで、「仕事に対しても前向きに学ぶ姿勢を持てる人」という好印象につながります。趣味としてただ好きなだけでなく、しっかりと目的意識を持って取り組んでいたことを伝えましょう。
趣味の中で、学びが特に思いつかない人もいるかもしれません。そのような場合は、同じ趣味の人と話をしてみることで、自分がその趣味のどんな部分に惹かれているか、どこが自分の強みと関連性があるのかなどを思いつくきっかけになるかもしれません。
学びや結果まで伝えることで、あなたらしさを盛り込んだ自己PRを作成することができるので、ほかの学生との差別化をするためにも、学びを振り返ってみてください。
得た学びや結果の例
ミステリー小説を読むようになってから、普段の生活のなかでも「なぜ?」という疑問を持つようになりました。
また、その疑問を解決するためにそのジャンルの本を読んで知識を増やすことを意識しています。読書のおかげで、物事に対して深掘りしていく探求心がついたと自負しています。
- 趣味から得た学びや結果が思いつきません。伝えるエピソードは些細なことでも大丈夫ですか?
入社後のイメージができれば些細なエピソードでも問題ない
些細なことでも問題ありませんが、自己PRの題材にした意味を持たせるためには、趣味を通じて得た「何か」を仕事にどう結びつけるかを伝えなくてはなりません。ただ「楽しい」「好き」では採用担当も困ってしまいます。
採用担当者は「この人が我が社で働くとしたら、どんな風に活躍してくれるのか」を知りたいと思っているのです。
採用担当者は、入社後応募者が活躍しているシーンをイメージできなければ、書類選考を通過させ、実際に面接で会って話したいとは思いません。
些細なことでも問題ないので、面接につなげるためにも仕事にどう活かすことができるかを考えて、それを具体的にすることが大切です。
④趣味で培った強みを仕事でどのように活かすか
最後に、ここまででアピールしてきた強みを仕事でどのように活かすかを述べます。自己PRにおいて企業は、「学生の強み」や「企業でどのように活躍してくれるか」を知りたいと思っています。
そのため、自己PRで最も大切なのは、企業でどのように活躍できるのか、過去の経験をどのように活かせるのかを伝えることです。
ここで仕事に活かせることを伝えないまま終わらせてしまうと、「趣味だから取り組めていたのでは? 」「自分の強みを仕事で発揮するイメージが持てていないのでは?」などと思われてしまい、高評価につながらない可能性があります。
自分が入社することのメリットをしっかり提示して、入社後の自分が働くイメージを採用担当者に持たせましょう。
どのように活かすかを企業に伝える際は、なるべく具体的な業務内容や数値で伝えると、企業理解の深さや熱意も伝えることができます。たとえば、「入社3年以内に営業成績1位を取りたい」や「入社後は社内エンジニアとしてシステム開発の部門で貢献したい」など具体性のある内容で伝えることを意識しましょう。
強みをどのように活かすかの例
貴社は、出版業界のなかでも特にマーケティングに力を入れていると伺いました。入社後は、培ってきた探求心を活かして、入社5年以内に過去の売り上げ1位を塗り替えることを目標に販売戦略を考え、貢献したいと思っています。
- 自己PRとは別で「趣味や特技を教えてください」と聞かれたとき、自己PRとどのように書き分ければ良いですか?
自己PRではない質問への回答は仕事と直結していなくても良い
自己PRにおける「趣味や特技」は仕事と直結する可能性が高いものを選びます。自己PRとは別の「趣味や特技」については必ずしも仕事と直結させる必要はありませんが、話す内容で印象が大きく変わります。
意外性のあるエピソードにすることで、採用担当者の記憶に残る可能性があります。私が以前担当した大学生のなかに「プラモデルが趣味でオリジナル作品を作っている」という学生がいました。
周りの大学生でプラモデルを趣味としている学生はいなかったので、「君はオンリーワンだね」と伝えた記憶があります。
その学生は自分の作品をインスタグラムに投稿するなどしていたので、プラモデルだけでなくインスタを利用できることも強みに感じました。
ガクチカで趣味を題材にする際には、自己PRとは違った対策が必要です。こちらの記事では、書き方や注意点について解説しているので、参考にしてみてください。
マイナス評価を避けよう! 自己PRで趣味を伝える際の注意点
マイナス評価を避けよう! 自己PRで趣味を伝える際の注意点
- 趣味の説明を長くしすぎない
- 印象を良くしようと嘘をつかない
- 現在も取り組んでいる趣味を選ぶ
- 趣味で培った強みのなかでも企業に合ったものを選ぶ
趣味を題材にした自己PRは、自分の好きなことで強みをアピールできるため、趣味がある学生にはピッタリです。
しかし、伝える際に気を付けるべき注意点がいくつかあります。この注意点を押さえずに自己PRを作成してしまうと、「結局何を伝えたいのだろう……?」「その強みは自社で活かせるのかな……?」とマイナス評価につながるかもしれません。
ここでは、自己PRで趣味を伝える際の注意点を紹介します。注意点をよく理解して、自分の趣味を最大限活かせる効果的な自己PRを作成しましょう。
趣味の説明を長くしすぎない
自分の好きなことの話をするとき、ついつい話が長くなってしまう人もいるかもしれません。
しかし、自己PRでは、趣味の説明部分に時間を割かないように注意が必要です。自己PRの目的は、趣味の説明ではなく、趣味から培った強みや得た内容を伝えることだと再認識しておきましょう。
また、趣味の話をするときは、専門用語などを使用せず誰が聞いてもわかる内容にすることを意識してください。採用担当者が理解できない内容だと、採用担当者の集中力が途切れてアピールにつながりにくくなるかもしれません。
自己PRの途中で回答内容への興味を失われてしまうと、深掘り質問をしてもらえなかったり、その後の話を熱心に聞いてもらえなかったりする可能性があるため、人柄や強みを最大限に伝えることが難しくなってしまうのです。
端的に要点を伝えることで、何を伝えたいのかがわかりやすくなり、自己PRの解答時間をその後の強みのアピールに有効活用できます。
印象を良くしようと嘘をつかない
採用担当者に良い印象を持ってもらいたいからといって、嘘をついたり話を盛ったりするのは避けましょう。自分の話す内容が事実でない場合、話した内容に関する深掘りの質問にもうまく答えることができず、準備不足ととらえられて評価を下げてしまう可能性があります。
選考当日までに多くの時間をかけて準備してきたことが、悪い印象に上書きされてその後の評価にも悪影響を及ぼしてしまうため、本当の自分の言葉で強みをアピールしましょう。
また、嘘をついていることに気付かれると、信頼を失うことにつながります。大切なのはエピソードの内容ではなく、趣味に対する取り組み方や考え方を伝えることです。後悔しないためにも、正直な内容で作成しましょう。
現在も取り組んでいる趣味を選ぶ
自己PRで題材にする趣味は、現在も取り組んでいる趣味を選ぶのがおすすめです。現在も取り組んでいる趣味であれば、熱量を持って話すことができたり、深掘り質問に対しても悩まず答えられたりすることができます。
過去に熱中していた趣味でも問題はないですが、一度熱意を持って取り組んでいたものの今は取り組んでいないことでは、「入社しても、仕事に飽きてすぐに意欲が低くなってしまうのではないか」と企業側に思われる可能性があります。
企業は、長く継続して活躍してくれる人材に入社してほしいと思っているので、こうした印象から評価を下げてしまうリスクはなるべく避けましょう。
自己PRから企業は、学生の強みだけではなく、人柄や価値観などを相対的に見ています。どの角度から見られてもマイナスなイメージを抱かれないように注意することが大切です。
- 過去に成績を残した経験がある趣味でも、現在取り組んでいない趣味はあまり良くないでしょうか?
自分の価値観や行動への影響力を伝えることでアピールになる
趣味そのものを続けているかどうかよりも、その経験があなたの価値観や行動にどのように影響を与えているかを伝えることが重要です。
たとえば、「大会の経験を通じて目標達成に必要なプロセスを学び、それを現在の学業やアルバイトに活用している」など、具体例を交えるとより説得力が増します。
過去の経験を通じて得たものを現在の自分と結びつけ、前向きにアピールしてください。
趣味で培った強みのなかでも企業に合ったものを選ぶ
自己PRで伝える強みは、企業に合わせて選びましょう。強みを伝えられれば内容は何でも良いわけではありません。
たとえば、「社内外の人と円滑にコミュニケーションを取れる人材」を求めている企業に「一人で黙々と仕事に向き合うことができます」という強みを伝えても、企業の求めている人物像とずれてしまうため、高評価にはつながらない可能性があります。
このように、志望する企業によって求める強みは異なります。志望企業がどのような人物を求めているのかを企業研究し、どの強みでアピールするのかを決めることが大切です。
趣味で培った強みと企業の求める強みが一致しない場合は、企業が求める強みが自分にあるのか確認するところからやり直しましょう。ある場合は、それが伝わる題材を選ぶのが賢明です。
ない場合は、題材以前に自分の強みを活かせる企業選びからやり直すことをおすすめします。
企業研究は選考を突破するために必要不可欠です。こちらの記事では、企業研究をするときに役立つノートの作り方を解説しています。どのように企業研究すれば良いのかわからない人は参考にしてみてください。
就活のプロが徹底解説! 趣味から自己PRで押し出す強みを見つけるポイントとは
企業は学生の強みを知るために自己PRを聞いているので、趣味を題材にした自己PRで企業にアピールする場合は、趣味を通して培った強みをしっかり伝えられるかを意識しましょう。
とはいえ、いざ趣味から強みを見つけようと思うと、意外と難しく感じる人もいるかもしれません。
せっかくの素敵な趣味や経験も強みにうまくつなげることができないと、自己PRとしてはイマイチな内容になってしまいます。
ここからは、就活のプロであるキャリアコンサルタントが趣味から強みを見つけるポイントについて解説します。強みの見つけ方がわからず悩んでいる人は参考にしてみてください。
アドバイザーコメント
自分では気付かない強みを得るために周りの人に聞いてみよう
趣味から自己PRを作成する場合や、自分にとっては当たり前すぎてなかなか強みを見つけられない場合は、他者からのフィードバックをもらうと良いです。
私の友人に釣りが趣味の人がいます。釣りの話になると、とても熱を込めて話してくれます。
数年前まで釣りは趣味でなかったらしいのですが、あるきっかけで釣りにのめり込むようになり、釣り竿だけでなく道具も一式良いものをそろえているようです。また、魚の種類を覚えるだけでなく、魚の調理の仕方も勉強しています。
趣味を始める前と始めた後の自分を振り返り変化した部分を整理しよう
このエピソードから、「上達したい(向上心)」、「大物を釣った時の喜び(達成感)」、「まったく釣れなかった時に対する対応力(釣り場の見直し)」、「釣りに行けない日の過ごし方(専門動画で勉強)」などを抽出することができます。
他者からの視点を取り入れることで、自分では気付かない強みが見えてきます。そして「趣味になる前の自分」と「趣味になった後の自分」とを比較し、どのような学びを得たのかを整理しましょう。
自分にしかない経験で自己PRを書こう! 趣味別の例文10選
ここまで解説した通り、趣味を題材とした自己PRでは、それぞれの趣味で培った強みから仕事でも活かせるものをアピールすることを意識して作成することが大切です。
皆さんのなかにはまず例文を見て、適切な伝え方をイメージしたうえで作成したいと思っている人もいるのではないでしょうか。
そこでここでは、趣味別の例文10選を紹介します。自分の趣味と照らし合わせながら参考にしてみてください。
①読書
読書の例文
私の強みは、想像力があることです。この力は、趣味の読書で培われました。
小学生の頃から本を読むことが好きで、毎月10冊は必ず読むことをこれまで続けてきました。読書の魅力は、自分が物語の主人公になって、さまざまな人生を経験できることだと思っています。気が弱く人に優しい主人公もいれば、自分の我が強く嫌われている主人公もいます。
多くの本と出会うことで、本のなかの主人公や著者の価値観や考え方を知ることができています。
こうして読書を続けるうちに人の表面だけで判断するのではなく、その人の考えや価値観を知ることが大切だと感じるようになりました。読書のおかげで、相手の考えや気持ちを想像する力がついたと自負しています。
貴社は、出版業界として「人に寄り添う本を来世に残す」を企業理念の一つとして掲げられています。入社後は、多くの本と触れて培ってきた想像力を活かして、作者の方の意図だけでなく、ターゲットとなる読者のニーズまで汲み取りながら、誰かの記憶に残るような本を制作したいです。
上記の例文は、読書を通じて想像力を培った点が具体的で、貴社の理念に結びつけている点が評価できます。
想像力が具体的にどのように業務に活かせるのかを、具体的な場面や行動例を挙げて説明すると、さらに説得力が増します。
②映画鑑賞
映画鑑賞の例文
私の強みは、発想力があることです。この力は趣味の映画鑑賞で培われました。
映画鑑賞は中学生の頃から続けており、ジャンルを問わず月に10本以上観ています。ただ楽しむだけでなく、ストーリー展開やキャラクターの心理描写、映像表現の意図などを深く考えながら観ています。一度観た作品でも、視点を変えて何度も鑑賞することで、新たな気付きを得ることも多くあります。
あるとき、授業のプレゼンで映画の映像構成をもとにした資料を作成しました。その際、映画で学んだ「人を引き込む構成」を意識してストーリー性のあるスライドを作成したところ、ほかの学生からは、「最後まで飽きずにプレゼンを聴けた」と言ってもらいました。
貴社の広告営業の業務では、広告内容を考える際などにクリエイティブな発想力が求められると思います。私はそうした業務の場で映画鑑賞を通して鍛えた発想力を活かし、新たなアイデアで貢献し、自分自身も周囲のさまざまなアイデアに触れて成長していきたいと考えています。
③音楽鑑賞
音楽鑑賞の例文
私の強みは、集中力があることです。この力は趣味の音楽鑑賞を通して培いました。
音楽鑑賞では、ジャンルにこだわらずあらゆる楽曲を深く聴くことを心掛けています。特に、楽曲のリズムや歌詞、メロディーの背後にある作曲家の意図を探ることが好きで、曲の背景について調べることもあります。
そんな折、大学の学際でイベントステージのBGMを選定する役割を任されました。その際、どのような映像を流すのか、どのようなイベントなのかをヒアリングし、シーンに合った楽曲を選んだところ、終了後のアンケート結果では「BGMが良い味を出していた」、「感情移入できた」などという評価をもらいました。
貴社でも音楽鑑賞を通じて培った集中力と、物事の背景まで深く分析する力を活かし、コンサルタントとして顧客の課題解決に取り組みたいと考えています。
④美術館巡り
美術館巡りの例文
私は探求心があることを強みとしています。この力は趣味の美術館巡りで培われました。
学生時代から美術館を訪れるのが好きで、国内外を問わず年間20館以上を巡っています。ただ作品を見るだけでなく、作品の背景や作者の意図についても調べることが多くあり、表面的には見えない作品の魅力を発見することに楽しみを見出しています。
私はゼミの発表で、美術館で見た絵画を取り上げました。その際、その作品について深く調べて資料を作成したところ、ほかの学生は知らなった作品の背景まで盛り込むことができ、「新しい発見ができた」という評価をいただきました。
美術館巡りで養った探求心を活かし、貴社でも新たな価値を見出し、それを形にすることで貢献したいと考えています。
上記の例文はおおむね良好ですが、「貴社でも新たな価値を見出し、それを形にすることで貢献したい」の部分が抽象的です。
「どのようにして価値を見出すのか」という方法と、「それを形にする」にはどのようにするのかを明確に書きましょう。
⑤絵を描くこと
絵を描くことの例文
私の強みは、想像力が豊かなことです。この力は趣味の絵を描くことを通じて培いました。
幼い頃から絵を描くのが好きで、特に物語性のあるイラストを描くことが好きでした。テーマを決め、そのテーマに合う絵を描くにはどんな構図が良いのか、どんなタッチが良いのかなど研究を重ね、他人が見たときにはどのように見えるのかなども意識しました。
高校時代に、地域のポスターコンテストに応募した際にも、見る人が何を感じるかを考えながらデザインした結果、優秀賞を受賞できました。この経験から、自分の想像力の豊かさで他者の心を動かす力があるのではないかと感じました。
貴社でも、私の想像力を活かしてさまざまなプロジェクトに取り組み、斬新な提案をすることで貢献したいと考えています。
⑥カメラ
カメラの例文
私はカメラが趣味なのですが、この趣味を通して培った情報収集力が自分の強みの一つだと考えています。
カメラを始めたきっかけは、風景や建物の美しさを記録したいという思いからでした。撮影する際には、撮りたいものの情報を調べ、どのように撮影するのがもっとも綺麗に映るか研究してから撮影していました。また、撮影後は写真を見返し、より綺麗に撮影するにはどうすれば良いか研究を重ねています。
以前、地域の写真コンテストに応募した際には、観光名所の歴史や背景を徹底的に調べたうえで、その背景を写真で表現できるよう撮影をおこないました。その結果、構図とストーリー性が評価され、入賞することができました。
貴社でもカメラを通じて培った情報収集力を活かし、マーケティング部の一員として困難なプロジェクトでもリサーチを欠かさず、成果につなげたいと考えています。
⑦ゲーム
ゲームの例文
私の強みは探求力です。この強みは趣味のゲームを通じて育んできました。
私はゲームが好きで、特に論理的に考えるゲームをよくおこないます。プレイ中は勝利を目指して、攻略方法や効率的なプレイスタイルを研究することが習慣となっており、ネットでの情報収集をおこなったり、自分でプレイデータを記録して研究をおこなっていたりします。
こうしたゲームでの分析や研究をおこなうなかで、物事を深く探求することの楽しさに気付きました。
そこから、ゲーム以外のことでもリサーチをする癖がつき、今では何か気になることがあると、とことん追及して分析するようにしています。この経験を通じて、自分には物事を深く掘り下げる探求力があるのだと感じました。
貴社では、この経験で培った探求心をエンジニアとして活かして、効率的な業務改善を進めていきたいと思っています。
日本のゲーム人口も年齢層幅広く増加していますが、良いイメージを持っている人ばかりではありません。
業界というより、人によって就活の場面でゲームを題材にすることを良く思わない人がいることは知っておきましょう。
⑧料理
料理の例文
私は想像力が豊かなところが強みです。
私は普段から料理を楽しんでおり、新しいレシピに挑戦することが好きです。特に、自分でアレンジを加えることで、よりおいしく、見た目も鮮やかに見えるよう工夫しています。食材の組み合わせや調理法を考える際は、レシピも参考にしながら、自分の感覚や工夫も取り入れるようにしています。
ある日、友人を招いて手料理を振る舞った際、普段食べたことのない味わいと驚いてもらい、料理の楽しさや、自分で工夫を加えることの大切さを感じました。
貴社の業務では、独自性やクリエイティブな発想が求められると考えています。食品メーカーとして国内外問わず多くの商品を届けている貴社の商品開発部の一員として、料理で培った想像力を活かし、新しい商品の開発に貢献したいです。
⑨旅行
旅行の例文
私の強みは計画力です。この力は、趣味の旅行を通して培いました。
特に海外旅行に行く際は、計画を緻密に立てることを意識しています。行き先ごとに観光地や交通手段を調べるのはもちろん、現地の文化やマナーも事前に調べ、トラブルを起こさないよう意識したり、その地域の文化に触れる体験をしていたりします。
実際に、大学時代の仲間と行った海外旅行では、日程表の作成や予約の管理を担当し、全員が安心して楽しめる旅行になりました。
貴社に入社後は、Webディレクターを目指したいと考えているのですが、この仕事は案件一つひとつを緻密に分析し、具体的な計画を練ったうえで、デザイナーなどと連携を取っていく必要があると思っております。
趣味で培った計画力を活かして、納期に間に合うように多くのチームメンバーと試行錯誤を重ねながら、質も効率も妥協せず取り組めるWebディレクターを目指したいです。
上記の例文は、旅行を通じて得た計画力を具体例とともに示し、それを業務に活かす意欲を伝えている点が良いですね。特に、旅行の計画力はスケジュール管理や調整力が求められる業界・業種で評価されやすいです。
⑩スポーツ
スポーツの例文
私の強みは継続力と忍耐力です。この力は、趣味でおこなってきたバスケットボールを通じて培いました。
私は学生時代から毎日練習を欠かさず、バスケの練習に取り組んできました。特に苦手なシュート練習には時間をかけるよう意識し、どの位置からでもシュートを決められるよう成長しました。
部活動ではキャプテンを務め、チームの練習メニュー作成も担当しておりました。そこでは個々の能力を引き出すことと、一人ひとりの課題を克服することに重点を置き練習をおこないました。その結果、チームを県大会優勝に導くことができました。
貴社でも、バスケットボールを通じて培った継続力を発揮して、長期的な視点で最後まで諦めずにプロジェクトの成功に貢献したいと考えています。
自己PRで部活を題材にするときは、高評価を取るためのコツを知ることが大切です。こちらの記事では、部活の自己PRで高評価を取るコツを解説しています。参考にしてみてください。
自己PRは、企業がどのような目的で聞いているのを理解することで、魅力的な内容でアピールすることができます。こちらの記事では、面接で印象に残る自己PRの作成方法を紹介しているので、参考にしてみてください。
趣味の自己PRで企業に活かせる強みをアピールして選考突破につなげよう!
趣味を題材にした自己PRは、入社後に活かせる強みをアピールすることで企業からの高評価につながります。ほかの学生との差別化をするためにも、自分らしさを盛り込んだ自己PRを準備しましょう。
強みのほかに、自分の人柄や考え方を伝えることも大切です。入社後に活躍しているイメージを企業に与えられるような内容の自己PRで選考を突破しましょう。
アドバイザーコメント
趣味の自己PRはスキルをどのように仕事に活かせるかから考えよう
就活を始めたばかりの人にとって、「自己PRに何を書けば良いのか」は最初にぶつかる壁といっても良いでしょう。
自己PRの題材に趣味を選ぶ場合は、趣味を通じて培ったスキルや特性が、強みとして仕事にどうつながるかを考えるところから始めましょう。
初対面の面接官に伝わりやすくするコツは、「いかにイメージしやすい言葉、表現で伝えるか」です。頭に映像が浮かばないと、文字を読んだだけで内容を理解するのは難しいものです。
そのためには、具体的なエピソードをしっかり交えることが重要です。趣味を通じて得たスキルを強調し、仕事にも活かせることをイメージしてもらいやすい表現で伝えましょう。
具体的すぎるより少し言葉足らずな方が採用担当に会って話したいと思われる
また、具体的に多くを語ろうとすると長くなってしまう傾向がありますが、要点を押さえ簡潔にまとめるスキルも求められます。少し言葉足らずなほうが、「もう少し話を聞きたいから面接に呼ぼう」と思ってもらえることもあります。
100%の内容を伝えようとせず、70〜80%ほどの内容にし、残りは面接で話すつもりで作成してみましょう。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

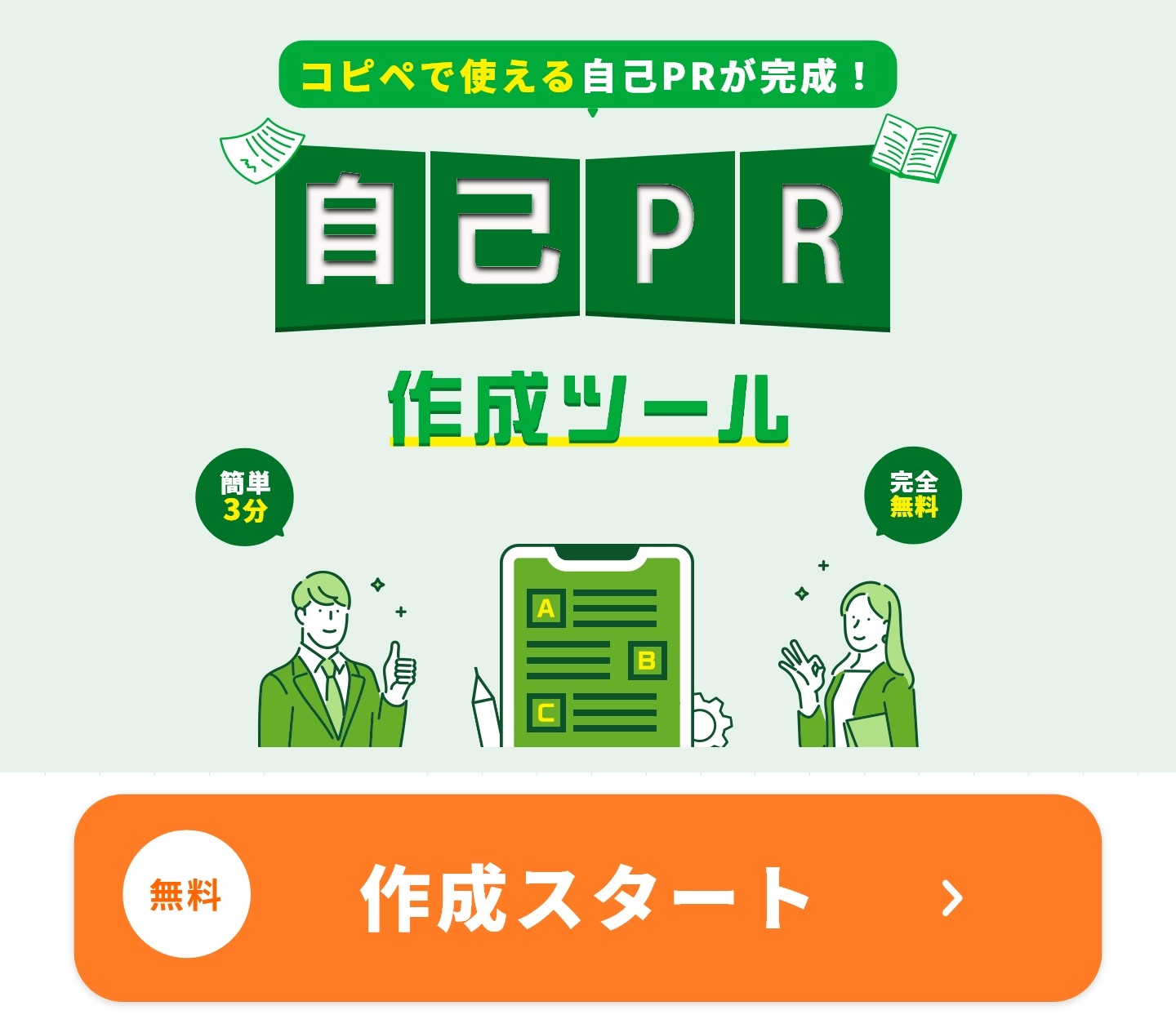

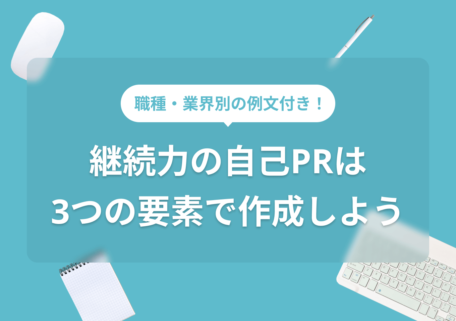




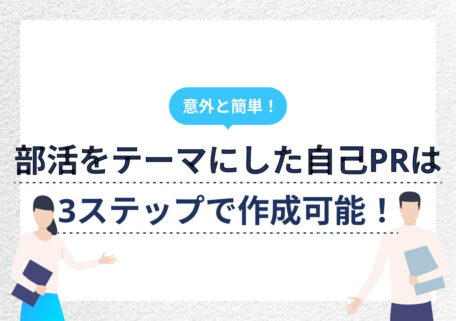














3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/産業カウンセラー
Atsuko Hirai〇ITメーカーで25年間人材育成に携わり、述べ1,000人と面談を実施。退職後は職業訓練校、就労支援施設などの勤務を経て、現在はフリーで就職・キャリア相談、研修講師などを務める
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/西雄一教育研究所代表
Yuichi Nishi〇大学では就活に関するスキルを身に付けられる実践中心の授業を展開。また、講師として企業で新人や中堅社員に向けてコミュニケーション研修、キャリアコンサルティングをおこなっている
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー
Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める
プロフィール詳細