この記事のまとめ
- ホテルへの就職を検討する前にホテルの種類や職種を理解しよう
- ホテルは経営タイプによって働くメリットが異なる
- 24時間365日営業で夜勤やシフト制が基本となるため慎重に選ぼう
ホテルへの就職を検討していて「ホテル業界は年収が低いと聞くけど本当なのだろうか」「専門学校卒が多いなかで大卒でも就職できるのか」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
ホテル業界は宿泊部門から料飲部門まで多様な職種があり、部門によって必要なスキルや働き方が異なります。そのため、事前に業界の実態を理解しておくことで、自身に合った企業や職種を選びやすくなります。
なお、ホテルの仕事は、バックヤードでおこなう業務が意外と多かったり、接客時は常に笑顔で接したりすることが求められ、表裏が分けられているため、ホテルで働くことの実態がわかりづらくなっているのも事実です。
また、一般企業とは異なる変則的な勤務体系や、繁忙期・閑散期による業務量の変動も実態を把握しづらい要因の一つです。そのため、就職活動を始める前に、業界の基礎知識から理解を深めていくことが重要といえます。
この記事では、キャリアコンサルタントの杉原さん、柴田さん、山路さんのアドバイスを交えつつ、ホテル業界の実態や職種別の仕事内容について詳しく解説します。ホテル業界へ就職を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
ホテルへの就職は働く企業と顧客層を理解したうえで検討しよう
ホテル業界への就職を検討する際は、志望する企業の特徴と顧客層をしっかりリサーチしたうえで、自身のキャリアプランに合う企業を選ぶ必要があります。ホテルによって運営方針や求める人材像が異なり、さらに顧客層によっても必要なスキルや働き方が変わってくるため、事前に企業研究を十分におこなうことが重要です。
そこでこの記事では、 ホテル業界の現状や就職するメリットまで詳しく解説します。まずはホテル業界の基礎知識を理解してから、自身の適性にあった企業選びをおこないましょう。
また、ホテルの種類によって求められる接客スキルや語学力のレベルについても解説します。顧客層に応じてどのようなスキルが必要になるのかを理解して、就活前の準備に活かしましょう。
そして記事の後半では、就職先ホテルの選び方を5つのステップで解説します。自身のキャリアプランに合うホテルを見つけるための参考にしてみてください。
あなたがホテル業界に向いているか確認してください
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
事前に知っておこう! ホテル業界の実態
事前に知っておこう! ホテル業界の実態
ホテル業界には、勤務時間や休日数・給与など、他業界とは異なる独自の労働条件があります。これらの条件は企業や職種によって異なるため、就活の際は業界の実態を正しく理解したうえで、自身のキャリアプランに合った企業選びをおこなうことが重要です。
ここでは、ホテル業界の実態について解説します。これらの情報は企業研究の際の重要な判断材料となるため、事前に理解を深めておきましょう。
勤務時間:交代制で夜勤が発生する職場もある
ホテルは24時間365日営業する施設が多いため、シフト制による交代勤務が基本となります。特に宿泊部門では、チェックインが集中する15時以降やチェックアウトの多い午前中など、時間帯によって繁忙期が異なるため、それに合わせた勤務シフトが組まれます。
また、フロントやベルなどの接客部門では夜勤が発生することがあります。夜勤の勤務時間は通常22時から翌朝8時頃までで、緊急時の対応や深夜のチェックイン受付などをおこないます。ただし、夜勤の頻度はホテルの規模や運営方針によって異なり、夜勤専門のスタッフを配置するケースもあります。
一方で、営業部門や管理部門などバックオフィス系の職種では、基本的に日勤のみで夜勤はほとんどありません。このように、部門によって勤務時間が異なるため、ホテルを選ぶ際は、配属される可能性のある部門の勤務体系を確認しておくことが大切です。
ホテル内のレストランやカフェの料飲部門は、朝食やランチ、ディナーのサービスが中心になるため夜勤は少なく、営業、管理、宴会部門も日勤がメインとなる傾向があります。
しかし、将来的には異動が考えられるので注意しましょう。
あなたとホテル業界のマッチ度を診断しよう
就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。
そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。
自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
休日:他業界より少ない
ホテル業界の休日数は、一般的な企業と比べて少ない傾向にあります。厚生労働省の令和4年就労条件総合調査によると、国内すべての企業の年間休日の平均は107日です。
ホテル業界では年間休日が107日よりも少ない求人が多く、求人サイトでは年間休日が105日となっている求人も見られます。年間休日が105日である場合、1ヵ月あたりの休日は8〜9日となるのです。
このように、ホテル業界の休日が比較的少なくなりやすいのは、土日祝日が他業界より忙しく、またゴールデンウィークやお盆、年末年始などの長期休暇シーズンも通常営業をおこなうためです。
また、シフトによっては1週間のうちに2日の休みを取れない可能性がありますが、シフトをうまく調整して週休2日をできる限り保っているホテルもあります。
なお、ホテル業界では、繁忙期に連続した休暇を取得しづらく、閑散期にまとめて休暇を取得するよう調整を求める場合もあります。
特にリゾートホテルは、シーズンによる宿泊者数の差が大きいため、休日の取得にも波があることを理解しておくことが必要です。就活では、各ホテルの休暇制度や取得実績までしっかり確認しましょう。
- ホテル業界の年間休日が少ないのはなぜですか?
24時間365日営業・繁忙期の集中・人材不足などから休みが少なくなる
ホテルはどこも24時間、365日営業しています。そのため、どうしても従業員の休日は少なくなってしまうのは業界全体に共通しています。
また、お正月やゴールデンウィーク、年末年始などの特定の期間に繁忙期が集中するため、安定的・定期的に休日を確保するのが難しいといった事情もあります。
さらに近年ではホテル業界のみならず、サービス業全体で人手不足が続いていて、人材確保に苦心している点もホテル業界の休日の少なさを加速させているようです。
ただし、人材不足を解消するためにも従業員満足度UPを目標として掲げ、働きやすい職場を提供しようとする姿勢を示すところも増えてきました。応募のさいにはこうした会社の施策についてよく調べておくようにしましょう。
仕事とプライベートを両立しながらホテルで働きたい人は、以下の記事を参考にしましょう。年間休日を比較する方法や、年間休日以外にも確認すべき条件5項目を解説しています。
まずはホテル業界に適性があるか診断しましょう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
平均残業時間:23.6時間
dodaによると、ホテル業界の1ヵ月あたりの平均残業時間は23.6時間です。全業界の平均残業時間は21.9時間なので、ホテル業界は全体の平均よりも1.7時間残業が多いということになります。
一般的なホテル業界のイメージとして、残業が多いというイメージが大きいかもしれませんが、近年ではITシステムの導入によってチェックインが簡素化されていたり、スキマバイトを採用することで人員不足の改善を図ったりしています。
これらによって各ホテルは、従業員の残業時間を減らすような取り組みをおこなっているのです。
平均年収:264万円
国税庁の令和5年分民間給与実態統計調査によると、ホテル業界が含まれる宿泊業・飲食サービス業の平均年収は264万円です。全業界の平均年収が459万円であり、宿泊業・飲食サービス業の平均年収は全業界のなかで最も低くなっています。
ただし、ホテル業界のなかでも国内大手のホテルや、外資系のラグジュアリーホテルなどでは、初年度年収が400万円以上となる求人も見受けられます。平均年収が低い業界とはいえ、働く企業や場所、ポジションによって高い年収を狙うことは可能です。
プロに聞いた! 「ホテルでの勤務は激務」は本当?
「ホテルでの勤務は激務」といわれることがありますが、「実際の現場ではどの程度の業務負荷があるのか」「休暇は十分に取得できているのか」と疑問を持つ人も多いでしょう。
また、ホテルの種類や職種によって業務内容や働き方が大きく異なるため、より具体的な実態を知りたいと考える人もいるかもしれません。
そこでここからは、キャリアコンサルタントの山路さんに、ホテル業界の労働環境や働き方の実態について詳しく聞きました。プロの視点から見たホテル業界の実態を参考にして、自身のキャリアプランに合った企業選びをしていきましょう。
アドバイザーコメント
ホテル業界の特徴柄から生活リズム・メンタルを崩す可能性がある
ホテルによって差はありますが、ここまでに述べてきたように夜勤も含めた変則的や、繁忙期と閑散期の差の激しさ、残業の多さ、休日は少なさにより生活リズムやメンタルのバランスを崩してしまうというケースはあります。
また、業務の幅についてもフロント・コンシェルジュが本来の業務であるお客様からの各種問合せ・要望への対応だけでなく、それと並行してホテルによってはロビーなどのパブリックスペースの清掃や館内で使用する備品の管理・発注、営業、館内レストラン・宴会場、ブライダル部門など、ほかの部署の業務も担うホテルもあります。
これらのことから体力面だけでなく、精神的なタフさも問われるところが激務と言われる由縁だと言えます。
業務の線引きな明確で個人の負担が少なくなるホテルも存在する
逆に言えば、そもそもの業務範囲として宿泊をはじめとした特定の分野のみに特化したホテルや業務範囲の必要性に応じて幅広い職種を設定・募集しているホテルは業務の線引きなども明確で、そうでないホテルと比べて個人への負担が小さいと思われます。
こちらのQ&Aでは、ホテルで働くメリットとデメリットについて、キャリアコンサルタントが解説しています。併せてチェックして、ホテルで働く際の実態について理解を深めましょう。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
顧客層が変わる! ホテルの種類はおもに5つ
顧客層が変わる! ホテルの種類はおもに5つ
ホテルには、立地や顧客層によってさまざまな種類があります。ホテルの種類によって必要なスキルや働き方が異なるため、就職活動を始める前に各種の特徴を理解しておくことが重要です。
ここではホテルの種類を5つに分類して解説します。就活で企業研究をする際は、これらの特徴を参考に、自身のキャリアプランに合うホテルを見極めていきましょう。
シティホテル
シティホテルは、都市部の一等地に立地し、宿泊だけではなく、レストランや宴会場、ウェディング施設なども備えた総合型のホテルです。ビジネス客から観光客、地元利用まで幅広い顧客層に対応するため、高品質なサービスと多様な施設運営が特徴です。
宿泊部門以外にも、料飲部門や宴会部門など複数の部署があり、それぞれの専門性を活かしたキャリア形成ができます。また、国際的なホテルチェーンが多いため、グローバルな環境で働くことができ、語学力を活かせる機会も豊富です。
おもなシティホテルの例は、以下のとおりです。
ビジネスホテル
ビジネスホテルは、出張などのビジネス利用をおもな対象とした宿泊特化型のホテルです。シティホテルと比べて宿泊料金が手頃な一方で、レストランや宴会場などの付帯設備は最小限に抑えられています。
ビジネスホテルは運営の効率化が重視されるため、スタッフが少人数であることが多く、一人で複数の業務をこなせる人材が求められます。また、チェーン展開している企業が多いため、全国各地でのキャリア形成が可能です。おもなビジネスホテルの例は、以下のとおりです。
少人数でフロントを切り盛りしているビジネスホテルでは、チェックアウトの時間に業務が集中しやすいなど激務になる要素が多い職場でした。
しかし近年ではDX化が進み、チェックインやチェックアウト、会計などは自動でおこなえるようになったため、業務の軽減が進んでいるといえます。
所要時間はたったの3分!
受けない方がいい職業を診断しよう
就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。
就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。
- 自分に合う職業がわからない人
- 入社後のミスマッチを避けたい人
- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人
リゾートホテル
リゾートホテルは、観光地や保養地に立地し、レジャー目的の宿泊客をメインターゲットとしたホテルです。季節や観光シーズンによって繁閑の差が大きくなっています。さらに、外国人旅行者や長期滞在客が多いため、きめ細やかなホスピタリティや語学力が求められます。
また、リゾートホテルは宿泊施設だけではなく、プールやゴルフ場などのアクティビティ施設が充実しているのが特徴です。そのため、通常の接客スキルに加えて、アクティビティの案内やイベントの企画・運営など、幅広い業務に対応できる能力が必要となります。
近年では、都市部に立地しながらリゾート的な要素を取り入れたアーバンリゾートホテルが増えています。ビジネス客と観光客の両方をターゲットとして、都会的な利便性とリゾート感を両立させた施設運営が特徴です。おもなリゾートホテルの例は、以下のとおりです。
ラグジュアリーホテル
ラグジュアリーホテルは、最高級の施設とサービスを提供する、ホテル業界のなかでも最上級に位置付けられる宿泊施設です。富裕層をメインターゲットとし、1泊数十万円から数百万円という高価格帯の客室を提供します。
宿泊料金が高額である分、顧客からの要求水準も非常に高く、細部まで行き届いた接客と、洗練されたホスピタリティが求められるのが特徴です。
ラグジュアリーホテルで働く際は、高度な接客スキルと語学力が必須で、VIP対応や予期せぬ要望への臨機応変な対応力も重視されます。また、世界的なラグジュアリーホテルチェーンが多く、海外からの宿泊者も多いため、グローバルスタンダードの接客や、異文化に対する深い理解も必要です。
キャリア面では、一般的なホテルと比べて昇進・昇給のペースが早い傾向にありますが、その分求められる能力も高くなります。
新卒採用人数は一般的なホテルと比べて少なく、そもそも新卒募集をおこなわないラグジュアリーホテルもあるため、就職を検討する際は早めに募集要項を確認する必要があります。おもなラグジュアリーホテルの例は、以下のとおりです。
ラグジュアリーホテルの例
新卒対象の求人もサービス職・総合職を中心に発生していますが、採用枠は少なく、20名以上採用した翌年に数名しか採用しないなど厳しい基準に則っている印象です。
高品質の接客を目指す企業として、応募者にはコミュニケーション能力やホスピタリティー精神、柔軟性等を求める傾向があります。
ESで悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!
『就活準備をもっと効率よく進めたい...!』と思っていませんか?「就活準備プロンプト集」は、生成AIを活用して自己PRや志望動機をスムーズに作成できるサポートツールです。
簡単な入力でプロが使うような回答例が出せるため、悩まずに就活準備を進められます。生成AIを活用して効率良く就活準備を進めたい人におすすめです。
- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト
- チャットを使用した、模擬面接プロンプト
- 自己PRで使える強み診断プロンプト
旅館
旅館は、和の伝統とおもてなしの心を大切にする日本独自の宿泊施設です。個人経営の小規模施設から、大手企業が運営する大型施設まで規模はさまざまですが、いずれも和室を中心とした客室や懐石料理などの日本料理の提供、和服を着た仲居さんによる接客が特徴となっています。
近年では、インバウンド需要の増加に対応するため、和の要素を残しながら洋室を取り入れたり、外国語対応を強化したりする施設も増えています。
旅館で働く場合、日本の伝統文化や作法への深い理解が必要で、茶道や着付けなどの専門的なスキルが求められることもあります。
大手チェーンの旅館では、ホテルのような部門制を導入しているところもありますが、比較的少人数で運営される施設が多いため、マルチタスクな対応力が必要です。おもな旅館の例は、以下のとおりです。
部門・職種別! ホテル業界の仕事内容
ホテル業界の仕事は、部門や職種によって必要なスキルや働き方が異なります。フロント業務から調理、営業まで幅広い職種があるため、自身の適性に合った部門を見極めることが大切です。
ここでは、ホテル業界の仕事内容について、部門・職種別で解説します。各部門の具体的な業務内容を理解したうえで、自身のキャリアプランに合った職種を選びましょう。
宿泊部門
ホテルの宿泊部門は、チェックイン対応から荷物の運搬、客室の清掃まで、さまざまな業務をおこないます。それぞれの職種で必要なスキルや求められる対応が異なるため、自身の適性に合った職種を理解しておくことが重要です。
ここでは、宿泊部門の5つの仕事内容を職種ごとに解説します。宿泊部門はホテルの中心となる業務を担う部門であり、多くの人がイメージする業務が集まっていますが、認識の擦り合わせの意味も含めて一度目を通してみましょう。
フロント
フロントは、チェックインやチェックアウトの対応を中心に、ホテルの顔として重要な役割を担います。フロントの具体的な業務は、以下のとおりです。
フロントの仕事内容
- 宿泊予約の確認
- 客室の割り当て
- 宿泊料金の精算
- 周辺観光地の案内
- 館内施設の予約代行
フロントでは、宿泊前から宿泊後まで一貫してサービスを提供します。宿泊前は予約内容の確認や特別リクエストの手配、チェックイン時は滞在に必要な情報提供やルームキーの受け渡し、滞在中はさまざまな問い合わせ対応や施設予約、チェックアウト時は会計処理や忘れ物確認まで、宿泊にかかわるすべてのプロセスを担当します。
また、フロントは宿泊部門の中核として、ベルやコンシェルジュなど他部署との連携も重要な役割です。たとえば、VIP客の到着情報をベル係に共有したり、特別な要望をコンシェルジュに引き継いだりと、常に館内の様々な部署と連携を取りながら業務を進めていきます。
ホテルのフロントへ就職したい人は、以下の記事をチェックしておきましょう。ホテルフロントの志望動機で本気度を見せる方法や、志望動機の例文を解説しています。
ベルマン
ベルマンは、宿泊客の手荷物の運搬や、客室までの案内をおこなう職種です。具体的な業務は、以下のとおりです。
ベルマンの仕事内容
- 宿泊客の荷物預かり
- 客室までの荷物運搬
- チェックイン後の客室誘導
- 館内施設の案内
- 配達物・アメニティのお届け
ホテルによってはベルマンが存在し、チェックイン後の宿泊客を客室まで案内するのが仕事内容です。その際、フロントよりも宿泊客と直接コミュニケーションを取る時間が長くなったり、館内施設についてより詳しく説明したりする必要があります。
なお、団体の宿泊客がいる際は、数百個以上の荷物をそれぞれの部屋に指定された時間までに届ける必要があるため、数ある職種の中でも体力が求められます。ときには、数十キロ以上のスーツケースを取り扱うことも多いので、筋力も必要です。
そのため、ベルマンは体力に自信がある人や、宿泊客との会話を楽しめる人に向いている職種といえます。
ベルは重要な仕事です。ただの荷物運び係ではありません。チェックイン後の最初のおもてなしだからです。ベル業務を通じて、基本的接客スキルの習得、ホテル全体の業務理解、お客様のニーズを理解する力を養います。
ドアマン
ドアマンは、ホテルの玄関で宿泊客を最初に出迎え、チェックアウト後はお見送りする役割を担います。具体的な業務は以下のとおりです。
ドアマンの仕事内容
- 車の誘導
- 駐車場案内
- タクシーの手配
- 雨天時の傘の準備
- 荷物の搬入
- 宅配便の受け取り
ドアマンは基本的にホテル屋外で常に姿勢良く歩き回りながら仕事をするため、体力が必要です。また、宿泊客の第一印象を左右する立場となるため、明るい笑顔と丁寧な接客マナーが求められます。
ドアマンが配置されるホテルは、大手シティホテルやラグジュアリーホテルが多くなっています。これらのホテルには、政治家や芸能人などのVIPが訪れるケースがあるため、ホテルの玄関前の安全を確保する警備員としての役割も担うのが特徴です。
ドアマンは屋外での業務が好きな人や、ホテルのドアマンとして立ち振舞いに気を配れる人に向いています。
コンシェルジュ
コンシェルジュは、宿泊客の滞在を快適にするためのあらゆる要望に応える職種です。おもな仕事内容は以下のとおりです。
コンシェルジュの仕事内容
- レストラン・イベントのチケット予約
- 観光プランの提案
- ショッピングの案内
- 館内施設の案内
- タクシーの手配
コンシェルジュはホテルの仕事のなかでも、イレギュラーな対応を求められるポジションです。たとえば、「フランス語で対応してくれるレストランを予約してほしい」や「ホテル周辺での明日の旅行プランを考えてほしい」など、フロントで完璧に対応することが難しい要望までワンストップで対応する必要があります。
特に高級ホテルのコンシェルジュは、予約が取りにくい店の手配や、急な要望への対応など、高度なサービスを提供することが求められるため、ホテルや周辺地域に関する幅広い知識と高い語学力が必要です。
コンシェルジュには、一定以上のホテルでの実務経験とスキルが必要なので、新卒での募集は基本的にありません。コンシェルジュのポジションとしての枠は、フロントやドアマンなどと比べて少ないのが特徴です。
そのため、フロントで実務経験を積んだうえで、コンシェルジュにふさわしいレベルの語学力や接客スキルをつけていくことが重要です。
- コンシェルジュになるにはどのようなキャリアを歩めば良いでしょうか?
ホテル入社後に社内公募などを利用してキャリアチェンジするのが一般的
コンシェルジュになるには特別な資格などは必要ありませんが、国籍も含めて様々なお客様のリクエストに応えることが求められます。
その為、ホスピタリティをはじめ、語学力、周辺地域の飲食店や観光地などの豊富な知識が欠かせません。
コンシェルジュになるには、まずはフロントやドアマンとして入社して経験と知識を積み、そのうえで、社内公募などの機会を活用してキャリアチェンジしていくことがキャリアルートとなります。
学生時代から出来ることとして、語学や接遇に関する勉強をしておくことも有意義ではありますが、自身がお客様側の立場で様々なホスピタリティを経験し、サービスの引き出しをストックしておくことも就職後の大きな助けになります。
ハウスキーピング
ハウスキーピングは、客室の清掃や整備を担当する部門です。おもな仕事内容は以下のとおりです。
ハウスキーピングの仕事内容
- ベッドメイキング
- バスルームの清掃
- アメニティの補充
- リネン類の交換
- 客室内の設備の不具合チェック
- 忘れ物の確認
清掃にかけられる時間は1室あたり数十分と時間が限られていて、チェックアウトからチェックインまでの間に完了させる必要があります。そのため、効率的に作業をおこなうことと、品質管理能力が求められます。体力も必要ですが、それ以上に細かな部分まで目が行き届く注意力が重要です。
なお、宿泊客と直接かかわる機会が少ないように見える職種ですが、客室があるフロアにはハウスキーピングしかいない状況が多く発生するため、宿泊客から館内の道順や施設について質問されることが多くあります。
そのため、宿泊客とコミュニケーションを取るような清掃以外の業務が発生することを覚えておきましょう。ハウスキーピングは、決められた手順で正確に仕事をこなすことが得意な人におすすめです。
調理部門
調理部門は、ホテル内のレストランやルームサービス、宴会場での料理提供を担当する部門です。ホテルの規模や特徴によって異なりますが、和食・洋食・中華など、複数のレストランを運営しているホテルが多いため、それぞれに専門のスタッフが配置されます。調理部門のおもな職種は以下のとおりです。
調理部門のおもな職種
- シェフ:調理部門全体の統括と献立の考案
- ソーシエ:各種ソースの仕込みと調理
- ブッチャー:精肉の管理と下処理
- ベーカリー:パンの製造と提供
- パティシエ・ペストリー:デザートやケーキの製造
- ガルデマンジェ:前菜や冷たい料理の調理
一般的に、新入社員は基本的な下処理や仕込みから始めて、徐々に担当範囲を広げていきます。腕を磨きながらキャリアアップを目指すことができ、最終的には料理長として部門全体を統括する道も開かれています。
ホテルの調理部門は、料理が好きな人や、同じ作業を丁寧に繰り返せる人におすすめです。
すべてがそうとは言い切れませんが、調理部門での採用には調理師免許取得が必須のホテルが少なくありません。
また、資格なしに採用されたとしても、そのような人が実務に携わるまでには資格ありの人よりもさまざまな下積みを経なければならないケースが多いです。
料飲部門
料飲部門は、レストランやバーでの接客サービスを担当する部門です。ホテル内の複数のレストランやバーの運営を担当し、朝食からディナー、深夜のバータイムまで、時間帯に応じた適切なサービスを提供します。料飲部門のおもな職種は、以下のとおりです。
料飲部門のおもな職種
- レセプショニスト:予約受付と席案内を担当
- レストランサービス:料理の提供とテーブルサービス
- バーテンダー:カクテルなどの提供と接客
- ソムリエ:ワインの選定と提案
新入社員は通常、レストランサービスからスタートし、基本的な接客マナーやサービスの技術を習得していきます。その後、適性や希望に応じて専門性を高めていくスペシャリストか、幅広い業務をおこなうゼネラリストとしてキャリアアップすることを目指すケースが多くなっています。
特にソムリエやバーテンダーは、専門的な資格取得も推奨されていて、スキルアップの機会も豊富です。また、料飲部門のマネージャーとして、部門全体の運営に携わるキャリアパスもあります。
ホテルの料飲部門は、ホテルの食べ物や飲み物に関する知識が豊富な人や、長時間立ち仕事をしながら笑顔で接客できる人に向いています。
宴会部門
ホテルの宴会部門は、結婚式や企業の会議・パーティーなど、大規模なイベントの企画・運営を担当する部門です。顧客の要望に合わせて会場のレイアウトや料理、演出を提案し、当日の進行管理まで一貫して担当します。宴会部門のおもな職種は、以下のとおりです。
宴会部門のおもな職種
- ブライダルコーディネーター:結婚式の企画から当日の進行管理を担う
- テーブルコーディネーター:会場装飾やテーブルセッティングをおこなう
- ウェイター・ウェイトレス:料理や飲み物をテーブルまで運ぶ
- クローク:顧客の手荷物やアウターを一時的に預かる
宴会部門は、一つのイベントの準備に数カ月かかることもあり、長期的な視点での計画立案と進行管理が必要です。また、料飲部門や調理部門など、他部門との連携も重要な業務となります。
宴会部門は限られたスケジュールのなかでイベントを企画したり、顧客や部門間の調整や交渉をしたりすることが得意な人におすすめです。
ブライダル部門は新郎新婦の特別な日に関わるお仕事として、人を喜ばせることが好きというのは大前提として、ほかの職種以上にマナーが問われます。
また、結婚式のない時期はほかの会議・宴会等の業務にも幅広くかかわりますので、柔軟性も問われます。
管理・営業部門
管理・営業部門は、ホテルの運営を支えるバックオフィス業務を担当する部門です。一般企業と同様の業務内容も多いですが、ホテル特有の習慣や顧客対応など、業界特有の知識も必要となります。
管理・営業部門のおもな職種は以下のとおりです。
管理・営業部門のおもな職種
- 営業:法人営業や旅行会社との取引をおこなう
- 広報:ホテルのプロモーションや広報活動をおこなう
- カスタマーサービス:顧客からの問い合わせ対応をおこなう
- 人事:採用や労務管理を担当
- 経理:財務管理や予算管理を担当
管理・営業部門は、ほかの部門と比べて規則的な勤務時間となることが多く、夜勤もありません。また、ホテルによっては本社での勤務も可能で、経営企画などを目指すこともできるのです。
ただし、宿泊や料飲部門などとは、採用の窓口が異なるケースがあります。そのため、応募するホテルの募集時期や選考方法などの採用情報をしっかり確認しておきましょう。
このようなホテルの管理・営業部門は、数字を扱うことが得意な人や、ホテル全体の運営をサポートすることに関心がある人に向いています。
こちらのQ&Aでは、ホテルの営業職についてキャリアコンサルタントが詳しく解説しています。ホテルの営業職について理解を深めたい人は、参考にしましょう。
将来性はある? ホテル業界の現状
ホテル業界の将来性について「新型コロナウイルスの影響から回復できるのだろうか」「今後も安定して働けるのだろうか」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
ここでは、ホテル業界の現状について解説します。就活でホテル業界を志望するかどうか判断する際は、業界の将来性を理解したうえで、自身のキャリアプランと照らし合わせることが重要です。
業界全体で業績が回復傾向にある
観光庁の宿泊旅行統計調査によると、2024年11月の延べ宿泊者数は5,812万人で、コロナ禍前の2019年同月と比べて17%増加しています。特に外国人の宿泊者数は、2019年同月比で62.0%増と大きく回復していて、インバウンド需要の復活が業界全体の業績回復を後押ししているのです。
また、日本人の宿泊者数も2019年同月比で7%増となっていて、国内旅行需要も堅調に推移しています。これは政府による観光支援策や、企業の出張需要の回復が要因として考えられます。
このように、国内外からの宿泊需要が回復傾向にあることから、ホテル業界全体の業績は今後も安定的に推移すると予測されているのです。
新卒採用時の求められるのは、間違いなく多言語対応能力です。これは会話ができることではなく、異文化の理解や敬意を払うことを指します。
また、IT化も進んでいるのでデジタルスキルも必要です。つまり、ホスピタリティに加えて、柔軟性、適応力が求められます。
DXにより人材不足の解消が進んでいる
DX
デジタルトランスフォーメーションの略。デジタル技術を活用してビジネス環境の変化に対応する取り組み
ホテル業界では深刻な人手不足が課題となっていましたが、DXにより、徐々に解消の兆しが見えてきています。特に配膳ロボットやスマートチェックインシステムの導入により、人手を必要とする業務の自動化が進んでいます。
たとえば、名古屋プリンスホテルでは、配膳ロボットの導入により1日あたり約3.3時間の運搬作業を自動化し、月額約16万円の人件費削減効果を実現しました。
チャットボット
顧客からの質問に自動で返答するプログラムのこと
また、チャットボットによる24時間対応の問い合わせ対応も、人手不足の解消に貢献しているのです。
このようなDXの活用により、従業員の労働負荷が軽減され、より質の高いサービスの提供に注力できる環境が整いつつあります。今後もAI(人工知能)やロボット技術の発展により、さらなる業務効率化が期待されています。
- 今後DXやAIの活用が進むことでホテルの仕事が減る可能性はあるのでしょうか…?
業務の簡素化・変化はあるが人ならではの仕事も重視されるようになる
ホテル業界において、急速にDXやAIの活用は進んではいます。
しかしながら、新しいシステムや機器の導入に苦戦している現場もあり、顧客側においても機器の使い方の説明などにスタッフのフォローを要する場面もあるようです。
加えて、各分野でDXやAIの活用が進んでいるからこそ、改めて人による接客だからこそ出せる良さ・価値に重きを置く動きも根強いものがあります。
これらのことから、DXやAIの活用によって業務が簡略化されたり、内容が大きく変化することは考えられますが、まだまだ人の力が必要な部分は多く、著しく働き口が減る可能性は低いでしょう。
とはいえ、現場で働くうえで、新しいシステムをスムーズに使いこなせるだけの吸収力・柔軟性は必要な素養といえそうです。
学歴によって異なる! ホテルに就職するメリット
学歴によって異なる! ホテルに就職するメリット
- 大学からホテルに就職するメリット
- 専門学校からホテルに就職するメリット
- 高卒からホテルに就職するメリット
ホテル業界は、大学・専門学校・高校など、さまざまな学歴の人材が活躍できる業界です。自身の学歴によって実現できるキャリアが異なるため、ホテル業界へ就職するメリットを事前に把握したうえで就職を検討することが大切です。
ここでは、学歴別のホテル就職のメリットについて解説します。就活で進路を決める際は、それぞれの学歴で得られるメリットを理解したうえで、自身のキャリアプランに合った選択をしましょう。
大学からホテルに就職するメリット
大学からホテルに就職するメリットは、幅広い職種を選択しやすい点です。ホテルの業務には、基本的に必須資格や実務経験がありません。そのため、専門学校で学んでいない大学生でも就職することは可能です。
また、接客をおこなう宿泊部門だけではなく、大学で培った論理的思考力や、ゼミ活動などで身に付けたプレゼンテーション能力などが評価されて、営業や人事などのバックオフィス部門にも就職できます。
なお、大学で語学を学んでいたり、接客が伴うアルバイトをした経験があったりすると、それらの経験を直接業務に活かせます。特に近年では外国人旅行客が増えているため、留学経験がある大学生はホテルの就職活動において有利になります。
さらに、ホテル業界は就職活動の時期が一般企業と同じで、ほかの業界と併願することもできるため、就活をおこないながらキャリアを検討しやすくなっているのもメリットの一つです。
宿泊客に対するサービスなどの実務スタッフに対し、営業やイベント企画、人事採用や経営なども重要な業務です。
実務だけでなく、大学で学んだことや経験からそれらのバックオフィスとしての役割も担える可能性がある点をアピールするのがおすすめです。
専門学校からホテルに就職するメリット
ホテル分野の専門学校から就職するメリットは、即戦力として活躍できることです。ホテル分野の専門学校では、接客マナーやホテル実務など、現場で必要なスキルを体系的に学ぶことができます。
たとえば、身だしなみ講座や発声講座、ホテル英会話・中国語講座など、ホテルで働くことに特化した講座が受けられます。実技中心のカリキュラムで実践力が身に付くため、入社後すぐに現場で活躍しやすいのです。
さらに、専門学校は学内での企業説明会や推薦制度が充実していて、就職活動がスムーズに進めやすいのも特徴です。多くの専門学校は、ホテル業界とのつながりを持っているため、インターンシップや実習を通じて、入社前から実務経験を積みやすくなっています。
高卒からホテルに就職するメリット
高卒からホテルに就職するメリットは、いち早く実務経験を積めることです。ホテル業界での人事評価は、実践を通じた学びを重視する傾向があるため、高卒でも入社後の頑張り次第で、着実にキャリアを築いていけます。
多くのホテルでは、研修制度が整えられているので、入社後の研修で基礎から段階的に業務を学ぶことでスキルを確実に身に付けやすくなっています。
またホテル業界は基本的に必須の資格や学歴、スキルが定められていないことから、高卒からキャリアを進めやすいのもメリットの一つです。
ベルマン、ハウスキーピング、レストランスタッフなどは、高卒でも比較的入りやすい職種です。ただし一度も接客業を経験したことのない人はインターンシップやアルバイトで、自分に合っているか確認した方が良いですね。
ホテル業界で求められる能力
ホテル業界で求められる能力
ホテル業界には、接客から運営まで幅広い業務があります。職種にかかわらず、ホテルで活躍するためには、共通して求められる基本的な能力があるため、これらを理解しておくことが重要です。
ここでは、ホテル業界で求められる5つの能力について解説します。就活でホテル業界を志望する際は、これらの能力と自身の適性を照らし合わせて、自己アピールの材料にしていきましょう。
あらゆる顧客に合わせて対話できるコミュニケーション力
ホテルには、ビジネス客から観光客、高齢者から子連れファミリーまで、さまざまな目的や年代の顧客が訪れます。そのため、それぞれの顧客に合わせた適切なコミュニケーションを取る能力が必要です。
たとえば、ビジネス客には簡潔で的確な案内を心がけ、観光客にはより丁寧な説明や観光情報の提供をおこないます。また、高齢者には聞き取りやすいスピードで話し、外国人観光客には非言語コミュニケーションも交えながら対応します。
このように、相手に合わせて柔軟にコミュニケーションスタイルを変えられることが、ホテルで働くうえで求められます。
ホテルの現場におけるコミュニケーションの大きな特徴の1つとして、客層の広さが挙げられます。そのため、背景の異なる幅広い人と接した経験や、その際に心がけていたことなどはホテルの就活において大きな強みとなります。
ホテルの就活でコミュニケーション能力をアピールしたいと考えている人は、以下の記事をチェックしておきましょう。企業が求めるコミュニケーション能力には12の種類があることや、自己PRで使える言い換え表現を解説しています。
さまざまな部署と連携するための協調性
ホテルでは、フロントや客室清掃・レストランなど、多くの部署が連携してさまざまなサービスを提供しています。そのため、各部署との円滑なコミュニケーションを取り、チームとして協力して業務を進める協調性が重要です。
たとえば、レストランでの食事付きプランを予約された顧客への対応では、フロントは予約情報をレストランと共有し、レストランは調理場と連携して食材の準備をおこないます。たとえば、このような部署間の連携がスムーズにいかないと、料理の提供に遅れが生じて、顧客満足度の低下につながってしまうのです。
特に混雑時には、同じ部署内での助け合いに加えて、他部署との連携がより重要になります。たとえば、チェックイン時間が重なり、フロントに長蛇の列ができた場合、ベルスタッフやコンシェルジュと連携して案内や荷物預かりの対応を分担するなど、部署を超えた協力が必要です。
ホテルの就活で協調性をアピールしたい人は、以下の記事を参考にしましょう。協調性を題材にした自己PRをありきたりにしない方法や、職種・社風別にアピールすべきポイントを解説しています。
想定外の要望にも対応できる臨機応変さ
ホテルでは、マニュアルでは対応しきれない予期せぬ要望や突発的な事態が日常的に発生します。そのため、状況に応じて柔軟に判断し、適切な対応ができる臨機応変さが必要です。
たとえば、深夜に体調を崩した顧客への対応や、予約システムのトラブル発生時の代替案の提示など、その場の状況に応じた判断が求められます。また、VIP客の突然の要望や、天候の急変による予定変更など、想定外の事態にも冷静に対応する必要があります。
マニュアル外の対応については、ホテルによって指示される対応方法が異なりますが、このような状況でも、ホテルの方針に沿いながら柔軟な対応ができる判断力が重要です。
ホテルの就活で臨機応変に対応する力を強みとして自己PRしたい人は、以下の記事を参考にしましょう。臨機応変に対応する力がある人の特徴や自己PRの例文を解説しています。
顧客一人ひとりに寄り添えるホスピタリティ
ホテルで働く場合、顧客一人ひとりのニーズを理解し、心からのおもてなしを提供するホスピタリティが求められます。これは単なる接客マナーの実践ではなく、顧客の立場に立って考え、期待以上のサービスを提供する姿勢を指します。
たとえば、カップルが記念日で宿泊する際にタオルアートのような特別な演出を提案したり、体調の悪そうな顧客には医療機関を紹介したりするなど、顧客の状況に応じた気配りが必要です。また、リピーターの顧客の好みを記憶し、次回の滞在時に反映させることで、より深い信頼関係を築きやすくなります。
このような細やかな心遣いを通じて、顧客に心地良い滞在体験を提供することが、ホテル業界で求められます。
- ホテル業界で必要なホスピタリティはどのような経験で身に付けられるのでしょうか…?
ホテルや飲食店などの業務経験を通じて思いやり・配慮を学んでみよう
ホスピタリティとは、顧客に対して心を込めたサービスの提供や、細やかな配慮のことです。顧客が満足することを第一に、顧客の言葉の端々から求められるサービスを考えます。
サービスは形のあるものではありませんが、その形のないものに対して顧客はお金を支払うので金銭的価値のある行為なのです。
学生時代にホスピタリティを実践的に学ぶなら、ホテルのインターンシップを始め、飲食店や小売業でのアルバイトをやってみるのがおすすめです。
また、福祉施設などでのボランティア活動も非常に良い機会です。自分がやってあげたいことと、相手が求めていることのギャップを感じられるでしょう。真の思いやりや配慮とは何かを経験できるはずです。
顧客の要望に応えるための語学力
近年、海外からの宿泊客が増加していて、外国人観光客との円滑なコミュニケーションを取るための英語をはじめとした語学力が必須となっています。
たとえば、チェックインの手続きや施設の案内、周辺観光地の説明など、日常的な場面で語学力が必要です。また、緊急時や特別な要望への対応など、より複雑なコミュニケーションが求められる場面も想定されます。
そのため、入社前から語学力の向上に取り組み、実践的なコミュニケーション能力を身に付けることが重要です。特に宿泊客と英語で話す場合、道案内や施設案内をおこなうケースが多いため、ホテル内の施設を案内する際に使う英語や単語を重点的に学んでおきましょう。
自身の英語力を活かして就職したい人は、こちらの記事でホテル以外の選択肢も検討してみましょう。TOEICスコア別のレベル一覧や、レベル別の英語を使った仕事40選を解説しています。
ホテル業界への就職に役立つ資格
ホテル業界への就職に役立つ資格
ホテル業界で働くために必須の資格はありませんが、取得しておくと就活を有利に進めやすくなる資格があります。資格によって身に付く知識やスキルが異なるため、自身のキャリアプランに合わせて取得を検討することが重要です。
ここでは、ホテル業界への就職に役立つ資格について解説します。就活前の準備として資格取得を考えている人は、それぞれの資格の特徴を理解したうえで、自身に必要な資格の取得を目指しましょう。
ホテルビジネス実務検定
ホテルビジネス実務検定
ホテル業界の基礎知識からマネジメントまで、幅広い知識を認定する検定試験
ホテルビジネス実務検定は、1級・2級からなるベーシックレベルとマネジメントレベルの2種類があります。ベーシックレベル2級では、宿泊・料飲・宴会を中心としたサービスオペレーションの基礎知識を問う内容となっています。一方で、1級ではこれらに加えて、マーケティングや人事など管理業務の知識も問われます。
ホテルビジネス実務検定を取得することで、ホテルの幅広い部門の業務の流れを体系的に理解できるため、配属先での仕事や部門間の連携をスムーズにおこないやすくなります。
ホテル業界の就活でホテルビジネス実務検定を活用する場合、2級以上を取得することで、ホテルの業界知識が備わっていることをアピールできます。また、入社後も実務で活用できる体系的な知識を身に付けられるのがメリットです。
マナー・プロトコール検定
マナー・プロトコール検定
ビジネスマナーからプロトコールと呼ばれる国際儀礼まで、幅広い知識を認定する検定試験
マナー・プロトコール検定は3級では基本的なマナーの知識、2級ではビジネスマナーや冠婚葬祭の作法、準1級・1級ではより高度なマナーやプロトコールの知識と実践力が問われます。
マナー・プロトコール検定を取得することで、就活時にマナーへの関心の高さをアピールできるだけではなく、ホテル入社後の接客業務でも活用できる実践的な知識が身に付きます。ホテル業界への就職を目指す場合、社会人として必須のマナーを身に付けられる2級以上の取得を目指しましょう。
冠婚葬祭や食事の作法、通過儀礼などに関する知識が問われるため、特に外国人宿泊客が多いホテルや、結婚式をおこなう宴会部門があるホテルで評価されやすくなっているのが特徴です。
そのため、外資系ホテルへの就職を検討している人や、ホテルの宴会部門への就職を志望している人におすすめです。
TOEIC
TOEIC
ビジネスで必要な英語力を測定する世界共通のテスト
ホテル業界では、インバウンド需要の増加に伴い、TOEICが採用時の重要な評価基準の一つとなっています。ホテル業界では目安として600点以上のスコアを取得すると、就活で英語力をアピールできます。
なお、ラグジュアリーホテルや外資系のリゾートホテルでは、700点以上が応募の条件とされているケースもあるため、事前に応募要項を確認しておきましょう。
TOEICは資格というよりもスコアを見られる試験のため、就活までに複数回の受験をして、目標スコアの達成を目指すことが重要です。また、スコアの有効期限は2年間とされているため、ホテル入社後に英語力を活かして業務をおこなうためにも、継続的な学習と定期的な受験を心がけるのがおすすめです。
近年のホテルでは外資系ではなくとも、一流ホテルからビジネスホテル、果てはカプセルホテルに至るまでインバウンド客でいっぱいです。
宿泊客が世界中から訪れるのですから、現場での仕事だけでなくバックオフィスでもその状況に対応できるだけの語学力が必要な業務は増えると考えます。TOEICで高得点をキープしておくに越したことはありません。
秘書検定
秘書検定
秘書や社会人として必須となる常識やビジネスマナーを証明できる資格
秘書検定では敬語の使い方や電話応対、ビジネス文書の作成方法などが問われるため、ホテルでの業務に直接活かせます。取得することで接客やビジネスマナーの基礎を身に付けていることがアピールできるのです。
ホテル業界での就活を有利に進めるためには、2級もしくは準1級を取得するのがおすすめです。特に、準1級の試験では、二次試験で面接がおこなわれます。面接は3人1組で、挨拶・報告・状況対応という3つの課題をその場でこなす形式となっているため、合格できれば実践的な話し方や動作が備わっていることをアピールできます。
ブライダルコーディネート技能検定
ブライダルコーディネート技能検定
結婚式や披露宴の企画・運営に関する知識と技能を認定する国家検定
ブライダルコーディネート技能検定は、ブライダル全体で必要となる知識や実務を学べるため、特にホテルの宴会部門に携わりたい人におすすめの資格です。ブライダルコーディネート技能検定は3級から1級までありますが、ホテル業界の就活で活かすなら、3級以上の取得を目指しましょう。
3級はこれからブライダル業界で働きたい人が対象とされていますが、ブライダルの基本的な業務となる要望のヒアリングやプランニング・プレゼンテーションをするための能力が問われる実技試験があります。
そのため、取得することで業務で、直接活かせる実践的な能力が備わっていることをアピールできるのです。
後悔する人が多数? 「ホテル就職はやめとけ」の真意をプロが解説
Web上には「ホテル就職はやめとけ」という意見がありますが、この言葉の背景には、給与水準や不規則な勤務体系など、業界特有の課題があります。また、実際に働いたときに従来のイメージと実際の業務でギャップがあることに戸惑う人もいるため、「やめとけ」という声が存在するのです。
ここではキャリアコンサルタントの杉原さんに、「ホテル就職はやめとけ」の真意や、それらの課題への向き合い方について詳しく聞きました。ホテル業界の就活を始める前に、これらの課題を理解したうえで、自身のキャリアプランに合っているか判断しておきましょう。
アドバイザーコメント
多くの人は自身の仕事に誇りを持って取り組んでいる
アフターコロナ後需要が回復して人手不足が顕著ですが、それでもホテルの給与水準は大幅アップにはなっていません。また、入社してみたものの不規則な勤務で体調を崩す場合も考えられます。
しかし、私の身の回りにはそうした理由で退職した人はいません。ホテリエに憧れてホテル職を希望した人は、インターンシップやアルバイト先もホテルを選び、職場や仕事内容をきちんと理解したうえで入社しているからです。
純粋に顧客が好きという気持ちがあり、サービスマンとして顧客のために働きたいと心底思っています。恐らく、顧客に尽くすことで自分の存在価値を感じているのだと思います。
仕事への理解を深めれば入社後のミスマッチを防げる
また、ホテルには種類とグレードがあります。シティホテル、ビジネスホテル、宿泊特化型ホテル、リゾートホテル、外資ホテル、それぞれターゲット層が全く違い、顧客のニーズも違えば、働き方も違ってきます。
こうした違いを理解しないまま入社すると長続きしないでしょう。経営的に、所有・経営・運営が別の場合があり、今一度、ホテルビジネスを研究してみてください。
ホテル業界に向いている人の特徴
ホテル業界に向いている人の特徴
- 接客することが得意な人
- 体力に自信がある人
- ルーチンワークを続けられる人
ホテルで就職するために必須の資格がないとはいえ、誰もが活躍できる業界というわけではありません。ホテルの働き方には業界ならではの特徴があるため、自身の適性や価値観と照らし合わせて、キャリアの選択肢として検討することが重要です。
ここでは、ホテル業界に向いている人の特徴について解説します。就活でホテル業界を志望するか迷っている人は、これらの特徴と自身の適性を比較して、業界選択の判断材料にしましょう。
接客することが得意な人
ホテルは、宿泊客の滞在を快適にすることが最大の目的です。そのため、どのような部門でもおもてなしの心を持って、笑顔で接客できることが必要です。特に、一人ひとりの顧客に合わせた柔軟な対応や、状況に応じた接客ができる人がホテル業界に向いています。
たとえば、海外からの観光客には文化の違いを考慮した丁寧な説明が必要で、ビジネス客には効率的で的確な案内が求められます。また、クレーム対応の際も、顧客の立場に立って冷静に対応する必要があります。
このように、さまざまな顧客とコミュニケーションを取ることが好きで、相手に合わせた接客ができる人が、ホテル業界では活躍しやすいのです。
- 一般的な飲食店のアルバイトでの接客とホテルの接客の違いはどこにありますか。
飲食店とホテルではそれぞれの過ごし方に大きな違いがある
飲食店の利用者は基本飲食のみを行いますが、ホテルでは飲食に加え、休憩や睡眠をする人もいれば仕事をしている人、また規模によってはエステやスポーツを楽しんでいる人がいます。
利用者が多様な行動をする分、対応や接遇に多様なニーズがあるのがホテルのサービスです。この点を把握しておきましょう。
接客業でアルバイトした経験をホテルの就活でアピールしたい人は、以下の記事をチェックしておきましょう。接客業経験のアピールに必要なポイントや、自己PRの例文を解説しています。
体力に自信がある人
ホテルの仕事は立ち仕事が多く、長時間の勤務になることもあります。特に宿泊部門では、チェックインが集中する夕方や、チェックアウト間際の10時頃は座る暇もないほど忙しくなる可能性があるのです。
また、レストランスタッフは重い食器を運び続けたり、客室清掃では大量のリネン類を扱ったり、体力を使う業務が数多くあります。さらに、シフト勤務や夜勤による不規則な生活リズムにも耐えられる体力が必要です。
このように、体力的な負担が大きい仕事であるため、健康に自信があり、長時間の立ち仕事でも集中力を保てる人がホテルに向いています。
ホテルで働く上で立ち仕事、力仕事、ピークタイムの忙しさは共通しており、甲乙がつけ難いものです。
加えて客室数の多さ等による移動の大変さはありますが、客室数が少ない場合でも、その分、同時に勤務している人数が少ないなど、別の大変さがあります。
ルーチンワークを続けられる人
ホテルでは、客室の清掃やベッドメイキング・食器の準備など、毎日同じ作業の繰り返しになる業務が多くあります。これらの作業は、一定の品質を保ちながら効率的におこなう必要があるため、細かい作業を正確に続けられる忍耐力が重要です。
たとえば、ハウスキーピングでは1室数十分という限られた時間で、決められた手順に沿って確実に業務を完了させなければなりません。
また、レストランでは、テーブルセッティングや食器の準備など、毎回同じ質の高いサービスを提供することが求められます。このように、決まった作業を丁寧に続けることができる人が向いているといえます。
5ステップ! 就職先ホテルの選び方
5ステップ! 就職先ホテルの選び方
ホテル業界には、シティホテルからリゾートホテルまで、さまざまな特徴を持つホテルがあります。各ホテルで顧客層や求める人材像が異なるため、自身のキャリアプランに合った就職先を見極めることが重要です。
ここでは、就職先のホテルを選ぶための5つのステップについて解説します。就活でホテルを選ぶ際は、これらのステップを順番に進めることで、より自身に合ったホテルを見つけやすくなります。
①ホテル業界に就職したい理由を明確にする
ホテル業界に就職する理由は人それぞれですが、「接客が好きだから」「英語を使えるから」といった漠然とした理由だけでは、入社後のミスマッチを招く可能性があります。そのため、より具体的な理由を言語化することが大切です。
たとえば「ラグジュアリーホテルで最高級のサービスを提供したい」「外資系リゾートホテルで多様な価値観に触れながらホテルマンとして成長したい」など、自身が何を実現したいのかを明確にします。
また、実際にホテルを利用したり、アルバイトをしたり、自身の経験から、具体的にどのような点に魅力を感じたのかを振り返ることも効果的です。このように、志望動機を掘り下げて考えることで、より適切なホテル選びがしやすくなります。
ホテルに就職したい理由を言語化するためには、以下の記事を参考にしましょう。自分に合ったやり方で自己分析をする方法や、自己理解をさらに深める分析方法を解説しています。
②ホテル業界で実現したいキャリアプランを考える
ホテル業界では、フロントやレストラン・ブライダルなど、さまざまな部門があり、それぞれ築けるキャリアが異なります。そのため、入社後どの部門でキャリアを積みたいのか、将来的にどのようなポジションを目指したいのかを考える必要があるのです。
たとえば、「フロントで接客スキルを身に付けて将来はコンシェルジュを目指したい」「料飲部門でキャリアを積んでレストランマネージャーになりたい」など、具体的な目標を設定します。
また、希望する部門に配属されやすいホテルなのか、キャリアアップの機会は十分にあるのかなども確認しましょう。このように、志望先ホテルを選ぶ前に自身の目標とホテルで実現できるキャリアパスが合致しているかを見極めることが重要です。
ホテル業界でのキャリアプランが決まっていない人は、以下の記事を参考にしましょう。誰でもできるキャリアビジョンの描き方や企業に伝えるための構成を解説しています。
以下の記事では、面接官に好印象を残せるキャリアプランの伝え方について紹介しています。参考にしてみてくださいね。
③ホテルに求める条件を洗い出す
ホテルを選ぶ際は、自身が職場に求める条件を明確にすることが大切です。たとえば、夜勤がないことや、少しでも給与が高いことをホテルに求める人もいるでしょう。ホテルに求める条件として確認すべき項目は、以下のとおりです。
ホテルに求める条件で確認すべき項目
- 顧客層
- 業務内容
- 給与
- 残業の多さ
- 夜勤の有無
- 年間休日
- 異動の頻度
上記のようなホテルに求める条件を考える際は、まず優先順位を決めることが重要です。たとえば、年間休日が120日以上で、残業が月10時間未満・夜勤なし・月額給与が21万円以上という条件を設定したとすると、実際に当てはまるホテルがかなり限られてしまいます。
そのため、この時点では最も譲れない条件を1〜2つに絞り、それ以外は柔軟に検討できる幅を持たせておくことが大切です。
まず条件をリスト化し、最も重要な条件を明確にしましょう。勤務地、勤務時間、給与、キャリアアップの機会などがあると思いますが、そのなかで将来どのようなホテリエになりたいのかよく検討してください。
業績が良いホテルの見分け方
就職先となるホテルを選ぶ場合、ホテルの業績は将来性や自身のキャリアの可能性を左右する重要な要素であるため、事前にチェックすることが大切です。
ホテルの業績を見極めるには、まずホテルの予約サイトで空室状況を確認してみましょう。平日・休日ともに予約が埋まっているホテルは、安定した集客力があると判断できます。特に3ヵ月先までの予約状況を見ることで、より正確な稼働率が把握できるのです。
また、企業のコーポレートサイトでは、売上高や客室稼働率などの業績データが公開されていることがあり、大手ホテルチェーンでは、会社案内のページで業績の推移や今後の事業計画を確認できます。
さらに、株式市場に上場しているホテルでは、四半期ごとの業績報告で具体的な数字を見ることも可能です。これらの情報を総合的に判断することで、ホテルの業績や将来性を見極めやすくなります。
ホテルの経営タイプによる違い
ホテルにはおもに以下4つの経営方式があります。
| 特徴 | 働くメリット | ホテルの例 | |
|---|---|---|---|
| 直営方式 | 自社でホテルを所有し、経営・運営をおこなう | 雇用が安定していて福利厚生も充実していることが多い | 帝国ホテル、東京ステーションホテル |
| リース方式 | ホテルの運営会社が土地や建物を借りて運営する | 現場の意見が通りやすく、幅広い業務を経験しやすい | 東横イン、ルートイン |
| 運営委託方式 | 運営のみを専門会社に委託 | 運営専門会社による高い運営基準で経験を積める | ホテルオークラ、星野リゾート |
| フランチャイズ方式 | ブランドの使用権を得て運営 | 全国共通のサービス基準で働けるため、高いレベルの接客スキルが身に付く | アパホテル、コンフォートホテル |
ホテルの経営方式によって社員の働き方や育成方針も変わってくるため、就職先を選ぶ際の重要な判断材料となります。たとえば、働き方を重視したい場合は直営方式、幅広いスキルを身に付けたい場合はリース方式など、自身のキャリアプランに合わせて選択することが大切です。
なお、ホテルの経営方式は、コーポレートサイトの企業概要・運営方針ページや、就職情報サイトの企業情報ページに記載されていることが多くなっています。これらの方法でホテルの経営方式がわからない場合、会社説明会で採用担当者に直接質問して確認しましょう。
直営方式や運営委託方式の経営をおこなっているホテルは、高品質のサービスを提供できる人材を育てる必要性から採用は比較的少数で難易度も高い傾向があります。語学力やコミュニケーション力などで高いスキルを求められます。
一方で、リース方式、フランチャイズ方式のホテルは客室数も多いため、大量採用するところが多いです。業務を標準化させ、かつDX化なども推進していることから入社後にしっかり研修をおこない業務にあたります。
④企業研究をして就職候補のホテルを決める
ホテルに求める条件を洗い出したら、企業研究をして就職先候補となるホテルを複数決めます。企業研究はホテルの公式サイトだけではなく、就職情報サイトや口コミサイトなど、さまざまな情報源から情報を集めることで、自身に合うホテルを探しやすくなります。
具体的には、以下の項目をチェックしましょう。
ホテルの募集要項で確認すべき項目
- 新卒採用実績
- 配属先の決め方
- 研修制度
- 平均残業時間
- 有給休暇の取得率
また、そのホテルならではの接客方針や顧客層、将来的な新規出店計画や改装予定なども確認することが重要です。可能であれば、実際に宿泊や食事をして、サービスの質や雰囲気を体験してみることもおすすめです。
これらの情報を整理して、自身の希望する条件に合うホテルを3〜5社程度に絞り込んでいきましょう。
これからホテルの企業研究をおこなう人は、こちらの記事を参考に進めましょう。企業研究ノートを作って、徹底的な企業比較をおこなう方法を解説しています。
⑤各ホテルのインターンシップに参加する
ホテル業界では、多くの企業がインターンを実施しています。インターンでは、接客の現場や部門間の連携を肌で感じることができるため、就職後のミスマッチを防ぐためにも参加しましょう。
インターンは、1日で接客業務を体験するものから、1週間かけて複数部署を経験するものまでさまざまです。できるだけ長期のプログラムに参加することで、より深くホテルの雰囲気や業務内容を理解しやすくなります。
また、インターンでは現場のスタッフと直接話す機会があるため、実際の働き方や社風について詳しく知ることができます。参加後は振り返りをして、そのホテルが自身に合っているか判断しましょう。
ホテルのインターンに参加する予定の人は、以下の記事をチェックしておきましょう。インターンの選考を突破する方法や、参加前の準備などについて解説しています。
インターンの志望動機
例文19選|インターンシップの志望動機づくりはこれで完璧!
インターンの面接対策
インターンシップの面接を突破する3つのカギ|質問と回答例12選
事前に把握しておこう! ホテル業界に就職する際の注意点
ホテルで働くことには魅力がある一方で、一般的な企業とは異なる働き方や業務内容もあります。これらの特徴を理解せずに入社してしまうと、早期離職につながってしまう可能性があるため、事前に業界特有の注意点を把握しておくことが重要です。
ここでは、ホテル業界に就職する際の注意点について解説します。ホテル業界を志望する際は、これらの課題を理解したうえで、自身の働き方に対する価値観と照らし合わせて判断しましょう。
勤務シフトが不規則になる可能性がある
ホテルは基本的に24時間365日営業するため、早番・遅番・夜勤などのシフト勤務が基本となります。特に宿泊部門では、チェックインが集中する15時以降や、チェックアウトの多い午前中は必ず人員を配置する必要があるのです。
また、土日祝日は観光客が多く、ゴールデンウィークや年末年始などの長期休暇シーズンも通常営業となります。そのため、平日休みや分散休暇が一般的で、友人や家族との予定が立てづらい面があります。
ただし、ホテルによっては夜勤専門スタッフを配置したり、連続休暇を取得しやすい制度を導入したりするケースもあります。就活の際は、各ホテルの勤務体系をしっかり確認しましょう。
クレーム対応が生じる職種がある
ホテルでは、予約の間違いや設備の不具合、料理の提供時間の遅れなど、さまざまな場面でクレームが発生する可能性があります。特にフロントや料飲部門では、直接顧客から意見をもらう機会が多く、ときには自身に否がないクレームに対応することもあるのです。
このような状況でも、常に冷静さを保ち、ホテルの代表として適切な対応を取ることが求められます。また、クレーム対応は1人で抱え込まず、上司や関連部署と連携して解決することが重要です。
なお、多くのホテルでは研修制度が充実していて、クレーム対応のノウハウを学ぶ機会も設けられています。経験を積むことで、適切な対応力が身に付いていくことを覚えておきましょう。
- ホテルに就職するとクレーム対応は必ず発生するものなのでしょうか…?
ホテリエの使命として顧客の訴えに真摯に応えよう
確かにクレーム対応は避けたい業務ですが、顧客の立場で考えることが重要です。顧客は何か納得できないことがあって、それを訴えているのです。
それに応えないとなるとホスピタリティマインドが足りないと言われても仕方ありません。ホテリエとしての使命を思い出しましょう。
大きな声や厳しい言葉にひるむこともありますが、いつも穏やかなコミュニケーションばかりではありません。主張が異なる場合でも、意思疎通を図れる力がコミュニケーション能力です。
クレーム対応は自分の成長とお客様からの信頼を回復する機会です。マニュアルも整備されていますから、ほかのスタッフと協力して冷静に対処すれば大丈夫です。
ホテルへの就職の実態を理解して理想とするキャリアを実現しよう
ホテルには、宿泊部門から料飲部門・ハウスキーピングまで、顧客の快適な滞在をサポートするさまざまな職種があります。そのため、自身がどの部門・職種で活躍したいのか、その仕事に必要なスキルや適性を持っているのかを見極めることが重要です。
そして、単にホテル業界に興味があるというだけではなく「どのような接客を通じて顧客に喜びを提供したいのか」を考えることで、より的確なホテル選びができるようになります。
たとえば、外国人旅行客に質の高いサービスを提供したい人は外国語を学んだり、ブライダルに関心がある人は関連資格を取得したりして、準備を進めることがおすすめです。
ホテル業界は、インバウンド需要の回復により今後も成長が期待される分野ですが、長く活躍するためには業界特有の働き方への適性が重要です。企業研究を入念におこなったり、インターンに参加したりして、自身に合ったホテルと職種を見つけていきましょう。
アドバイザーコメント
自分の携わりたい仕事を明確にして身に付けるべきスキルを考えよう
ホテルといっても経営方式や業態などによって、提供するサービスや求められるスキルはかなり異なってきます。ホテルだったらなんでもいい、と安易に考えず、自分が本当に携わりたいサービスとは、お客様に何を提供したいのか、などから志望するホテルを絞り込んでいきましょう。
また、ホテルでフロントやベル、料飲など実務的サービスのみを極めていきたいのか、もしくはイベント企画や営業、経営などのバックオフィスも経験したいのかも明確にしておきます。
ホテルによってはサービス要員からバックオフィス部門への異動ができないところもあるので、これらの点もよく調べておくようにしましょう。
語学力は必須となるため英語や中国語は最低限身に付けておこう
どの部門への配属を希望していても、これからのホテル業界に語学力は必須です。インバウンド需要で外国人客が大幅に増加しているからというのはもちろんですが、ホテル業界は買収や経営統合などで経営母体が変わるといったことも少なくありません。
昨日まで国内資本だったところが外資に吸収される、というニュースをよく耳にしますので、これらの変化にも耐えられるように、英語や中国語などのスキルも身に着けておきましょう。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi


















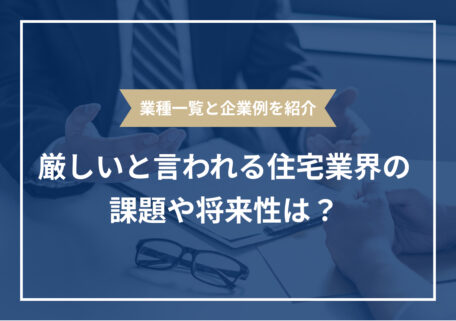









3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/2級キャリア技能士
Misako Sugihara〇石川県金沢市を拠点に15年にわたり就職支援に携わる。2年前からは転職支援も手掛けている
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士
Takako Shibata〇製造業を中心とした大手~中小企業において、従業員のキャリア形成や職場の課題改善を支援。若者自立支援センター埼玉や、公共職業訓練校での就職支援もおこなう
プロフィール詳細国家資格キャリアコンサルタント
Kazuhiro Yamaji〇会社員として長年勤務した後キャリアコンサルタントとして開業。企業の採用・高校生向けセミナー講師・転職支援・リスキリング補助など多岐にわたる分野でキャリア支援にたずさわる
プロフィール詳細