この記事のまとめ
- 大学院生の就活はスケジュールを把握して計画的に動き出そう
- 大学院生だからこそ求められる能力とアピール方法
- 研究などで忙しいなかでも効率的に就活を進めるコツ
大学院生は授業や研究で日々忙しい生活を送ることになりますが、頭の片隅に就活がある人も多いのではないでしょうか。修士課程の場合、大学院生活は2年間しかなく、修士1年の序盤から就活を意識し始める人もいるかもしれません。
しかし「就活しなければ」とは思いつつも、就活に関して右も左もわからない人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、キャリアコンサルタントの野村さん、谷所さん、村谷さんと一緒に大学院生の就活に関する基本情報や選考突破を目指せる対策方法などを解説します。
これから就活を始める大学院生は、まずこの記事から今後のスケジュールを理解して、周りに遅れを取らないように準備を進めましょう。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
大学院生だからこそ身に付けたスキルのアピールが就活のカギ
「大学院生は大学生よりも就活が有利」と聞いたことがある人もいるかもしれません。たしかに、2年間の研究によって専門的な知識・スキルを身に付けられたり、社会人として必要な能力を高められたりするため、有利になることもあります。
しかし、それらのスキル・能力を適切にアピールしなければ大学院生ならではのメリットは得られません。
そこでこの記事では、前半で大学院生の就活事情や就活スケジュールなど基本的な情報を解説します。まずは基本を押さえて、大学院生として就活する際のスタートラインに立てるようにしましょう。
そして記事後半では、大学院生だからこそ求められるスキルや就活のアピール方法、効率的に就活を進める方法などを解説します。就活の際に自分なら何をアピールできるか、それをどう伝えるかなどを考えながら読み進めていきましょう。
この記事を最後まで読むことで、大学院で身に付けた専門的な知識・スキルを適切な方法でアピールでき、就活を有利に進められるようになります。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認してみよう
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
前提を確認! 大学院生の就活事情
前提を確認! 大学院生の就活事情
「大学院生は大学生よりも初任給が高い」「学校推薦を活用できる」など、大学院生ならではの就活事情を耳にしたことがある人も多いでしょう。しかし、具体的にどのような違いや特徴があるのか、詳しく理解できていない人もいるのではないでしょうか。
大学院生は、学部卒とは異なる選考基準や評価ポイントが設けられていることが多く、これを理解することで就活を有利に進めることができます。
また、研究や専門性を活かした採用がおこなわれる一方で、文系・理系による傾向の違いや、推薦制度の活用など独自のポイントも存在するのです。
ここからは、大学院生が就活を成功させるために知っておくべき就活事情を詳しく解説します。
学校や教授からの推薦制度を活用できる
就活には大きく分けて以下の2つの応募方法があります。
就活の応募方法の種類
- 自由応募
- 推薦応募
自由応募とは、企業の採用サイトや就活サイトから自ら応募する、一般的な方法です。一方、推薦応募は学校や教授が推薦する制度を活用する方法で、学校や教授に寄せられた求人に対して応募します。
推薦応募は誰でも利用できるわけではありません。学校や教授から優秀な人材と認められた場合にのみ利用可能な制度です。そのため、推薦応募の対象となるためには一定のハードルがありますが、自由応募と比べて合格率が高いことが特徴です。
ただし推薦制度を利用する場合、内定を辞退したり早期退職することが難しくなるケースがあるため、本当に応募するかどうか慎重に判断しましょう。
学校推薦を活用した就活についてより詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。メリットや注意点などを詳しく解説しています。
初任給が大学生よりも高くなる傾向にある
厚生労働省が発表した令和5年賃金構造基本統計調査によると、学部卒と大学院卒の初任給には以下のような違いがあります。
| 学部卒の20〜24歳の賃金 | 239,700円 |
| 大学院卒の20〜24歳の賃金 | 274,000円 |
初任給は就職先企業や職種によって異なるものの、データからは大学院卒の方が初任給が高い傾向にあります。大学院生が学部生に比べて高度な専門知識やスキルを身に付けていると評価されるためです。
特に、研究職や専門職では、大学院でのスキルや研究経験を直接活かせるため、初任給が高く設定されるケースが多いといえます。
学部卒と大学院卒の給料差は、職種や業界、昇給制度、昇進基準、さらには専門職や管理職への移行状況によって異なります。
経験年数が増えるにつれてスキルや実績が重要視される傾向にあるため、これらの要素が影響して結果的に学部卒と大学院卒の給料差が縮まるケースもあります。
あなたが受けないほうがいい職業を診断しましょう
就活を進めていると、自分に合う職業がわからず悩んでしまうことも多いでしょう。
そんな時は「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格、価値観を分析して適職や適さない職業を特定してくれます。
自分の適職や適さない職業を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
理系の大学院生は企業側から歓迎されやすい
理系職種を募集する企業は、採用時に仕事に必要な専門スキルや知識を重視する傾向があります。理系の大学院生は、大学での学びに加えて、2年間の研究や授業を通じて高度な専門スキルや知識を習得していることが多いため、企業側から歓迎されやすいのです。
特に、研究開発や技術職などでは、大学院での研究経験がそのまま業務に直結することが多く、即戦力として期待される場合が多いです。また、研究を通じて培われる問題解決能力やデータ分析力、論理的思考力などは、職種を問わず高く評価されます。
さらに、理系の大学院生は、新たな技術や知見を習得する意欲が高いと見なされるため、企業にとっても長期的な成長が見込める人材として魅力的です。
このように、専門知識やスキルに裏打ちされた実績と成長性が、理系大学院生の強みとして企業に評価されるポイントとなっています。
理系の経験を活かした就職先に悩んでいる人は以下の記事を参考にしてください。理系におすすめの就職先を11選紹介しています。
理系の大学院生の就活について呆然として悩みを抱えている人もいると思います。そのような人は以下のQ&Aの回答を参考にして、具体的にどのようなことに取り組むべきかを明確にしましょう。
文系の大学院生は公務員への就職が多い傾向にある
大学院の専門分野は法学や経済、文学、外国語学、教育学などさまざまです。しかしいずれの分野でも、身に付く知識は行政の職員や教員として活かしやすいため、公務員に就職する人が多いです。
法学や経済学の分野の人は、政策の立案や法律の運用に関する知識が求められる行政職を目指す傾向があります。
また文学や外国語学の分野の人は語学や文化理解を活かした国際交流や教育関係、教育学の分野からは教員のキャリアが考えられます。
さらに、公務員のなかには専門性が求められることもあり、その場合は大学院で培った高度な知識や分析力を活かせる場面があるのです。
このように、文系大学院での学びと公務員は親和性が高いといえます。
- 文系職種の場合、専門的な知識・スキルは学部卒も院卒も大きく変わらないと思うのですが、どのような部分が評価されて初任給の差が生まれるのでしょうか。
院卒の研究で培われる専門的スキルなどが評価ポイント
文系職種における初任給の差はおもに、年齢と学校で学んだ専門知識の期待値によって生まれます。
修士課程で培われる深い思考力や問題解決能力、特定分野における専門的な知識の深さが、企業側の評価ポイントとなります。
院卒は学部卒と比較して、研究を通じて獲得したデータ分析力や論理的思考力が高く評価され、これらの付加価値が初任給に反映されるのでしょう。
文系の大学院に在籍し、就活について悩みを抱えている人は以下の記事を参考にしてください。文系の大学院生が就活で成功するためのポイントを解説しています。
理系から文系職種に応募することも可能
理系の大学院に進学したからといって、必ずしも理系職種に就かなければならないわけではありません。理系のバックグラウンドを持ちながら、以下のような文系職種に応募することも可能です。
文系職種の例
- 営業職
- マーケティング職
- 企画職
- 人事
- 広報
- 経理
- クリエイティブ職
文系職種では、長年かけて身に付ける専門スキルや知識が求められることは少なく、論理的思考力や分析力、コミュニケーション能力が重視されます。理系大学院生が研究を通じて培ったスキルは、文系職種でも大いに活かすことが可能です。
さらに、理系の知識や視点を持つことが新たな価値を生むこともあります。たとえば、マーケティング職ではデータ分析力が重宝されるほか、クリエイティブ職では理系ならではの独自性を発揮できるケースもあります。
このように、理系大学院生が文系職種に応募することで、新たなキャリアの可能性を広げることができるのです。
理系から文系職種に就職することは珍しいことではありません。具体的な方法は以下の記事で解説しています。
あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
いつから始めるべき? 大学院生の就活スケジュール
いつから始めるべき? 大学院生の就活スケジュール

大学院修士は2年間のみであり、あっという間に就活の時期がやってきます。
しかし、授業や研究に取り組みながらの就活であり忙しい生活となるため、具体的なスケジュールを把握していないと遅れを取ったり、十分な準備をせずに臨むことになったりしてしまいます。
そのため、まずは大学院生の就活スケジュールを把握しておくことが大切です。
ここからは、大学院生の就活スケジュールを詳しく解説します。いつから就活を始めるべきか、自分は今何をするべきなのかを考えながら確認しましょう。
大学院生と大学生の就活スケジュールは大きく変わりません。以下の就活スケジュール早見表を活用して、具体的なスケジュールを把握しておきましょう。
また、大学院生の就活の進め方がわからないと悩む人は、以下のQ&Aの回答を参考にしてください。
修士1年の6月:自己分析や業界・企業研究
本格的な選考は、修士1年の終わりから修士2年の始め頃にかけてスタートします。しかし、このタイミングで就活をスタートするのは遅いといえます。
なぜならこの時期は実際に応募を始める時期であり、その前に自己分析や業界・企業研究といった就活の準備が必要だからです。
自己分析や業界・企業研究を始めるのに最適な時期は、修士1年の6月頃です。この段階でしっかり準備を進めておけば、8月から始まるインターンシップに備えることができます。
自分自身を深く理解し入社したい企業についてリサーチすることで、就職の軸が定まりやすくなり、選考時にもスムーズに受け答えができるようになります。
具体的な自己分析や企業研究の方法は以下の記事で解説しています。やり方がわからずまだ進められていない人は参考にしてください。
自己分析
自己分析マニュアル完全版|今すぐできて内定につながる方法を解説
企業分析
企業分析のやり方を完璧にマスターする3ステップ|よくある注意点も
修士1年の8月:インターンシップに参加
インターンへの参加は自由ですが、8月頃には多くの企業がインターンを開催します。この時期は大学の夏休みと重なるため、それに合わせてインターンを実施する企業が増える傾向にあるのです。
インターンに参加することで、実際に仕事を体験したり、社員から会社のホームページ(HP)や採用サイトには載っていないリアルな情報を聞けたりするなど、さまざまなメリットを得ることができます。
また、参加したことでその企業の選考が有利に進むケースもあります。
もちろん、研究や授業を優先することが大切ですが、時間に余裕があったり志望する企業が明確に決まったりしている場合には、積極的にインターンに参加するのがおすすめです。この機会を活用して企業への理解を深め、就活を有利に進めましょう。
どのようにしてインターン先を選べば良いかわからないと悩む人は、以下の記事を参考にしてください。自分に合った企業を選べるようになります。
研究で忙しくてインターンとの両立が難しいと感じた場合は、研究やインターン、授業などのタスクを整理して優先順位を付け、計画的に行動するようにしましょう。
研究と関連するインターンを選べば、知識やスキルを深めることができます。一方で、短期インターンであれば、研究とインターンの両立もしやすいです。
修士1年の12月:会社説明会に参加
12月頃になると、各企業が会社説明会を実施したり、大規模な会場で合同説明会が開催されたりします。志望企業についてまだ深掘りできていない人や、応募先が決まっていない人にとって、これらの説明会は有益な機会となります。
会社説明会では、社員から直接仕事内容や会社の制度について話を聞けるだけでなく、質疑応答を通じて、会社のホームページ(HP)や採用サイトには載っていないリアルな情報を引き出すことが可能です。
また、会場での社員同士のコミュニケーションを見ることで、会社の雰囲気を把握する手がかりにもなります。
説明会への参加は数時間から一日程度の時間を要しますが、志望企業への理解を深めたり、新たに魅力的な会社を見つけたりする絶好のチャンスです。効率よく情報収集を進めるためにも、会社説明会への参加を検討してみましょう。
「会社説明会でどのような質問をしたら良いかわからない」と悩む人は以下の記事を参考にしてください。聞くべき質問と聞かない方が良い質問を解説しています。
会社説明会の流れやマナーがわからなく不安を抱えている人は、以下のQ&Aの回答を参考にしてください。就活のプロであるキャリアコンサルタントが会社説明会の流れやマナーについて解説しています。
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
修士1年の3月:本選考の応募が開始
修士1年目終了間際から2年目の始まり頃にかけて、本選考の応募が開始されます。この時期には、エントリーシート(ES)や履歴書を作成し、志望企業の採用サイトや求人サイトの専用ページから応募することが可能です。
本選考では、多くの企業が以下のような流れで選考を進めます。
選考の流れ
- 応募
- 書類選考
- 適性検査
- グループディスカッション
- 面接
特に注意したいのは、書類選考が通過の第一関門である点です。書類は企業側が最初に目を通すものであるため、記載する志望動機や自己PRが具体的かつ魅力的であることが重要です。
また、適性検査やグループディスカッションでは、論理的思考力やコミュニケーション能力が重要視されることが多いため、事前の対策が欠かせません。
さらに、企業によっては複数回の面接がおこなわれることもあるため、時間管理やスケジュール調整も重要です。
本選考では、これまでの努力を最大限活かし、丁寧に準備を進めていきましょう。そのためにも、早めに応募先企業の選考フローを確認し、計画的に準備を進めることが大切です。
ESや履歴書の基本的な書き方は以下の記事で解説しています。「書き方がわからない」と悩む人は参考にしてください。
履歴書
大学院生は履歴書で学歴・職歴をどう書く? 研究成果の伝え方も解説
ESで研究内容を書くとき
ESで研究内容を書く際はここに注意! 他の就活生の例文も紹介
修士2年の4〜10月:本選考・内定
選考を突破することで内定を獲得できます。早い場合は修士2年の4月頃、遅くとも10月頃までには多くの企業が内定を出します。この期間は就職活動の最終段階であり、内定を得るための重要な時期です。
内定後はその企業で働く準備として、企業から求められる書類の提出や研修への参加が求められる場合もあります。これらの手続きがスムーズに進むよう、早めに対応することが重要です。
さらに、内定後の辞退についても慎重に考える必要があります。推薦応募で内定を得た場合、辞退が難しい場合もあるため、事前に企業の方針やルールを確認しておきましょう。
このように、内定後も気を緩めずに計画的に進めることが大切です。
推薦内定を辞退した場合、後輩の就職機会に影響を与える可能性があります。大学と企業の関係悪化や採用計画の変更を招くため、推薦内定の辞退は極力避けましょう。
推薦応募時は、内定したら入社するつもりがあるかどうかを事前に十分に確認し、責任を持って行動してください。
採用経験者が解説! 大学院生は大学生よりも就活が有利になる?
大学院では大学での学びに加えて2年間研究に取り組むことになるため、さらなる専門スキル・知識を身に付けることができます。
大学生よりも専門的な知識・スキルの量が多い状態で入社することになるため、大学院生の方が就活が有利になるのではないかと考える人もいるのではないでしょうか。
そこで、キャリアコンサルタントの谷所さんに、大学院生は大学生よりも就活が実際に有利になるのかどうか聞いてみました。どちらにせよ選考に向けた入念な対策は必須ですが、実情を把握したうえで選考に臨みましょう。
アドバイザーコメント
大学院で学んだ専門性を武器にできれば就活が有利になる
大学院生だから就職に有利になるわけではなく、企業が大学院で学んだ専門知識やスキルを持つ学生を必要としていて即戦力になると考えていれば、就活で有利になります。
そのため就活では、なぜ大学院へ進学したのか、そして大学院で学んだことが企業でどのように活かせるかを、具体的に伝えることが大切です。
理系の大学院生は、専門知識やスキルを有していることをアピールできれば、そうした人材を求めている企業への就活が有利になります。実際に理系の大学院生を積極的に採用する企業もあるのです。
文系の大学院生は、研究や学んだことが活かせる大学や研究機関などの専門職でなければ、大学生と比較をして就職に有利になることは少ないでしょう。
大学院生は研究に関連したスキルを積極的にアピールしよう
研究や学んだことが企業の業務と直接関連しない場合は、研究で培った論理的思考力やプレゼンテーション能力などがアピール材料になります。
取り組んだ研究や専門知識、論理的思考力などを具体的にアピールできれば、大学院生の就活が大学生よりも有利になる可能性はあります。
一方で企業の業務に活かせるアピールポイントがなければ、企業が大学院生を採用するメリットは少ないと判断するかもしれません。
大学院生ではなく大学生を採用して、2年間の社会人経験を積んだほうが戦力になると考える企業もあります。
こちらの記事では大学院卒と学部卒の違いを詳しく解説しています。大学院卒のメリット・デメリットもまとめているので参考にしてみてください。
大学院卒業を就活で最大限に活かすポイントはこちらのQ&Aで解説しているので、あわせて確認してみてください。
企業目線を把握しよう! 大学院生を採用する際の評価基準
就活に臨むにあたって、企業側が何を基準に評価しているのかを理解することが重要です。
企業の評価基準を把握していなければ、的外れな回答をしてしまったり、自分のアピールポイントを誤って取捨選択してしまったりして、自分の強みなどを的確に伝えられなくなる可能性があるからです。
企業が大学院生を採用する際には、研究内容やその過程・結果に特に重きを置いて評価する傾向があります。
研究内容の専門性が企業の事業内容にどのように役立つのか、また、研究を通じてどのような問題解決能力や論理的思考力を培ったのかが評価のポイントになりやすいです。
さらに、研究過程で得た経験や、チームでの共同研究、プレゼンテーション能力なども見られる場合もあります。こうした能力は、入社後に即戦力として活躍できるかどうかを判断する重要な指標となるのです。
企業目線を理解することで、自分の経験やスキルを的確に伝え、選考の場で高い評価を得ることが可能になります。そのため、事前に企業が求める人材像や評価基準をしっかりとリサーチしておきましょう。
- 研究内容とは大きく異なる事業や専門分野に取り組む企業に応募した場合、選考が不利になることはあるのでしょうか。
専門知識や研究スキルをアピールできれば異分野でも問題ない
研究内容と異なる分野の企業に応募しても、不利になるとは限りません。
企業は専門知識だけでなく、研究で培った論理的思考力や問題解決力、データ分析力といった汎用的なスキルを評価することが多いです。
また、異分野に挑戦する意欲や柔軟性を伝えることも、選考での大きなアピールポイントになります。ただし、専門性が求められる職種では準備不足が不利に働くこともあります。
そのため、応募企業が求めるスキルや人物像を事前にリサーチし、自分の経験や強みをどう活かせるかを明確に説明できるよう準備しておくことが大切です。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
職業選択においてやりたいことはもちろんですが、その中でも適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうため適職への理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業と低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみよう!
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
就活で大学院生だからこそ求められるスキル・能力
大学院での研究経験によって得られるスキルは、学部卒の人にはない独自のものであり、企業側からの期待値も高まる要因となっています。しかし、そうした強みをまずは自身が認識できなければ、企業に対して的確にアピールするのは難しいです。
そこでここからは、大学院生が就活で求められる具体的なスキルや能力について、さらに詳しく解説していきます。どのようなスキル・能力が求められ、選考の際に何をアピールすべきなのかを考えながら読み進めていきましょう。
研究内容に関する専門的な知識と即戦力
大学院での研究を通じて得られる専門的な知識やスキルは、仕事によっては直接業務に活用できるため、大学院生を即戦力として期待し、採用を前向きに検討するケースが多くあります。
たとえば、研究開発職や技術職では、大学院で培った実験技術やデータ解析能力が、そのまま業務に役立つことがあります。また、企業が抱える課題に対して、研究を通じて得た解決策を提案できる力も評価項目の一つです。
このように、大学院生が持つ専門的な知識とスキルは、即戦力としての評価を高めるだけでなく、入社後の活躍を期待させる重要な要素となっています。
研究によって培った深い論理的思考力
専門知識だけでなく、研究過程で身に付けた論理的思考力や課題解決力、データを活用した意思決定力は、多くの企業にとって需要の高いスキルです。これらの能力は、大学院生が研究を通じて繰り返し試行錯誤するなかで自然と磨かれていきます。
論理的思考力は、複雑な問題を段階的に分解し、最適な解決策を見つけ出す力として重宝されます。企業の現場では、プロジェクトの計画やデータをもとにした戦略立案などに論理的思考力が求められるのです。
研究の過程で培ったデータ解析能力や、仮説を立てて検証するプロセスは、さまざまな実務において重要な役割をはたします。
このような深い論理的思考力は業界を問わず重要視され、大学院生が持つ強みとして企業に大きなアピールポイントとなるのです。そのため、論理的思考力を生かして企業でどのように貢献できるかを具体的に示すことが、就活成功のカギとなります。
チームとして共同で研究した経験があれば、チームのなかで担った役割などから責任感や協調性、向上心、リーダーシップ力などが、大学院生だからこそ求められるスキル・能力として挙げられます。
また。研究発表などの経験から培ったプレゼンテーション能力やコミュニケーション力が、大学院生特有の評価ポイントとなります。
大学生にはない強み! 大学院生だからこそできる就活のアピール方法
大学生にはない強み! 大学院生だからこそできる就活のアピール方法
- 研究の成果を誰でもわかるように伝える
- 研究発表で培ったプレゼン能力を自己PRに活かす
- ロジカルな思考で回答の構成を考える
大学院生には研究過程で身に付けた専門的な知識・スキルや、論理的思考力など、大学生にはない強みがあります。しかし、就活においては、これらを適切にアピールできなければ、自分自身のことを正当に評価してもらえません。
そこで、ここからは大学院生だからこそできる就活のアピール方法を解説します。学部卒との差別化を図り、大学院の2年間で培った経験やスキルを存分に伝えられるようにして、志望度の高い企業に就職できるよう準備を進めましょう。
研究の成果を誰でもわかるように伝える
大学院で取り組む研究は、非常に専門的な内容がほとんどです。研究を通じて、その分野に特化した専門知識やスキルを身に付け、世の中にあるさまざまな問題の解決に挑むことになります。
しかし、研究で得られた成果がどれだけ画期的であっても、それが一般の人や異なる分野を専門とする人にとって理解しやすいとは限りません。専門用語や業界特有の視点で説明された場合、成果が十分に伝わらないこともあります。
これは就活においても同様です。面接官が必ずしもその分野の専門知識やスキルを持っているとは限りません。そのため、研究の成果をアピールする際は、専門用語を避け、具体例や簡単な言葉を使って、誰にでもわかりやすく伝えることが重要です。
成果の伝え方次第で、面接官の研究に対する理解や評価が大きく変わる可能性があります。複雑な内容であればなおさら、シンプルかつ明確に伝える工夫をしましょう。これにより、自分の強みをより効果的にアピールできるようになります。
研究発表で培ったプレゼンテーション能力を自己PRに活かす
大学院では、研究の成果を発表する場面が頻繁にあるでしょう。その際、わかりやすいプレゼン資料を作成し、相手に伝わりやすい話し方を練習して本番に臨むなど、プレゼンテーション能力を磨く機会が多くあります。
このようにして培われたプレゼンテーション能力は、自己PRにも大いに活かすことが可能です。
自己PRを伝える際には、単に話す内容だけでなく、その話し方も含めて、相手の関心を引く工夫が求められます。研究発表で身に付けた複雑な内容をわかりやすく伝える力や限られた時間で要点を伝えるスキルは、自己PRの場でも役立つスキルです。
さらに、自己PRのなかで「プレゼンテーション能力がある」というアピールを具体例を交えておこなうことで、企業側に自分の強みをより効果的に伝えることができます。
特に、企画職や営業職といったプレゼンテーション能力が重視される職種では、このスキルが高く評価されやすいです。
研究発表の経験を自己PRの武器に変え、説得力のあるアピールを目指しましょう。これにより、ほかの応募者との差別化を図ることができます。
基本的な自己PRの構成や効果的にアピールする方法は以下の記事を参考にしてください。
面接での自己PRのコツ
面接官を惹きつける自己PRの答え方|例文12選
自己PRの構成作成テクニック
自己PRの構成作成ガイド|PREP・STAR法を使う作成法を伝授
ゼミの独自フォーマットをそのまま就活の自己PRに用いても問題ないのか疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし、ゼミのフォーマットは就活の自己PRにはあまり向いていないと理解しておきましょう。
採用担当者が理解しやすい一般的な構成を使い、研究内容と自身の成長をわかりやすく伝えることが重要です。相手の立場に立った情報提供を心掛けましょう。
ロジカルな思考で回答の構成を考える
大学院の研究に取り組む過程で、物事をロジカルに考える思考力を身に付けることができます。これは就活でも大きな強みとなり、選考での回答をより効果的に伝えるための土台となるのです。
ロジカル思考とは
物事を筋道立てて考え、矛盾や破綻がない状態で結論を出す考え方
研究では、仮説を立て、それを実験やデータで立証するというプロセスを繰り返します。この過程で、データや事実に基づいて論理的に結論を導き出す力が磨かれます。
就活の場では、面接官の質問に対して論理的な回答を構成し、説得力を持って伝えることが重要です。
たとえば、「なぜその企業を志望するのか」という質問に対して、志望理由を筋道立てて説明し、結論を明確に示すことで、面接官に納得感を持ってもらうことができます。
ロジカルな回答になっているか不安に感じる場合は、知人や先輩などに聞いてもらいましょう。第三者の客観的視点から見ても回答が論理立てられていて説得力があると思ってもらえれば、ロジカルな回答に仕上がっている可能性が高いです。
研究で培ったロジカル思考を活かして、就活の回答や自己PRの内容を入念に準備することで、選考での高評価につながりやすくなります。
甘くはない! 大学院生に見受けられる就活のよくある失敗
甘くはない! 大学院生に見受けられる就活のよくある失敗
- 研究の忙しさに就活が蔑ろになった
- 就活のスケジュールを把握してなかった
- 推薦ばかりに頼っていた
- 「大学院生だから有利」と勘違いして対策していなかった
大学院卒だからといって、必ずしも志望する企業に就職できるとは限りません。大学院生が特別に優遇されるわけではなく、この現実に気付かないまま就活を進めてしまうと、失敗につながる可能性が高まります。
そのため、大学院生だからこそ注意すべきポイントを理解し、適切な準備を進めることが重要です。ここからは、大学院生に見受けられるよくある就活の失敗例を解説します。
失敗を先回りして回避するためにも、今後の就活での適切な動きや進め方をイメージしながら読み進めましょう。
研究の忙しさに就活が蔑ろになった
大学院で取り組む研究は非常に忙しく、朝から晩まで研究室にこもる日々が続くことも珍しくありません。このような状況では、どうしても就活が後回しになってしまうことがあります。
しかし、研究の忙しさを理由に就活を蔑ろにすることは避けなければなりません。
就活は、企業側からあなたを見つけてくれるものではありません。自発的に行動しなければ、就職のチャンスは訪れないのです。研究に没頭することは重要ですが、就活を軽視すると、内定が得られないまま卒業を迎えてしまうリスクがあります。
たとえば、研究のスケジュールを見直して就活の時間を確保したり、自己分析や企業研究をスキマ時間に進めたりするなど、効率的に両立する工夫が必要です。
また、応募先企業を絞り込み、ポイントを押さえた対策を講じることで、忙しいなかでも成果を出しやすくなります。
研究と就活のバランスをうまく取ることが、大学院生として成功するための鍵となります。時間を有効に活用し、どちらにも全力で取り組む姿勢が大切です。
就活のスケジュールを把握してなかった
そもそも就活のスケジュールを把握せず、大学院での研究や活動に集中し続けた結果、就活の準備が間に合わなかったというケースは少なくありません。
多くの企業は同じようなスケジュールで選考を進めるため、この流れを把握しておかないと、選考に参加するタイミングを逃してしまう可能性があります。
就活スケジュールに遅れると、希望する企業への応募ができずに、選択肢が限られてしまうだけでなく、最悪の場合、就職先が決まらないまま卒業を迎えるリスクもあります。
特に大学院生の場合、研究活動の忙しさからスケジュールの把握が疎かになることも多いため、早い段階で計画的に取り組むことが重要です。
具体的には前述の、自己分析や企業研究を始めるタイミング、インターンや会社説明会に参加する時期、ESの提出や本選考開始の時期をあらかじめ把握しておきましょう。
さらに、スケジュールを手帳やアプリで管理して、研究と就活のバランスを取ることも大切です。
このように、入念な対策をして志望企業に就職するためには、就活スケジュールをしっかり押さえ、計画的に行動することが成功のカギとなります。
推薦ばかりに頼っていた
前述のとおり、大学院生は学校推薦や教授推薦など、推薦応募を活用した就活が可能になります。推薦応募は自由応募に比べて内定を得られる可能性が高いため、推薦を頼りに就活を進めようとする人もいるかもしれません。
しかし、推薦応募を頼りに就活に取り組むのはおすすめしません。そもそも推薦応募を利用できるのは一部の人だけであり、実際に選ばれるかどうかはわからないからです。
加えて、推薦応募であっても選考に落ちる可能性があるため、推薦ばかりを頼りにするのはリスクが高いといえるのです。
不用意な就職浪人を避けるために、推薦応募を検討している人も自由応募でエントリーする準備は並行して進めましょう。
推薦に頼りすぎると、選考で不合格になった場合にほかの選択肢がなくなるリスクがあります。
自由応募も並行しておこない、自身の希望や可能性を広げる準備が大切です。推薦を活用しつつ、多角的なアプローチを心掛けましょう。
「大学院生だから有利」と勘違いして対策していなかった
「大学院生は就活が有利」や「大学院に進学したら就職が簡単」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。
たしかに、大学院生は大学での学びに加えて2年間の研究に取り組み、専門的な知識やスキルを習得しているため、企業にとって即戦力として期待される場合があります。
特に、研究職や専門職など、高度なスキルを求められる職種では大学院生が有利になりやすいことも事実です。
しかし、「大学院生だから有利」という言葉をそのまま信じてしまい、対策を怠るのは危険です。
どれだけ専門性が高くても、それを企業に適切にアピールできなければ評価されることはありません。就活では、自分の強みをわかりやすく伝え、企業の求める人物像に合致していることを示す必要があります。
「大学院生だから」と油断せず、入念な準備と対策をおこないましょう。
就活のプロが解説! 忙しい大学院生が効率的に就活に取り組む方法
前述のとおり、大学院生は研究の忙しさから、入念に就活の準備に取り組む時間を確保するのが難しい傾向にあります。
しかし、忙しさに身を任せて就活を疎かにすると、大学院の2年間を活かせない企業に就職したり、やりたいと思えない仕事に取り組むことになったりする可能性も考えられるのです。
そこで重要なのが、効率的に就活に取り組むことです。
ここからは、キャリアコンサルタントの村谷さんに、忙しい大学院生が効率的に就活に取り組む方法を聞いてみました。研究で忙しく就活に充てる時間がないと悩む人は参考にしてください。
アドバイザーコメント
大学院生活は忙しいからこそ早めの就活スタートが肝心!
大学院生(修士)の効率的な就活方法とスケジュールの一例を紹介します。
まず、早期スタートが重要です。修士1年の夏頃から就活を始め、インターン情報の収集や業界分析を開始しましょう。就職情報サイトや就活エージェントを活用し、最新情報の入手や専門的アドバイスを受けるのがおすすめです。
自己分析と業界研究は大学院生ならではの強みを意識しておこない、専門分野以外の業界・企業も検討対象に入れてみてください。
大学院生の理想的な就活スケジュール
理想的なスケジュールは以下の通りです。
・大学院1年の4月〜6月:夏インターンの情報収集、応募
・大学院1年の7月〜9月:夏インターン参加
・大学院1年の10月〜11月:冬インターンの情報収集、応募
・大学院1年の12~2月:冬インターン参加
・大学院1年の3月:就活解禁(説明会、ES提出)
・大学院2年の4月〜:内々定が出始める
研究と就活の両立は大変ですが、上記のスケジュールを意識して計画的に進めることが重要です。早めの準備やインターンへの積極的な参加で、自己分析や業界研究を効果的に進めましょう。
また、推薦応募の可能性も検討しながら効率的な就活を心掛けてみてください。
こちらのQ&Aでは夏インターンの参加についてキャリアコンサルタントが回答しています。参加に悩んでいる人は参考にしてみてください。
視野を広げよう! 大学院生の就活以外の選択肢
視野を広げよう! 大学院生の就活以外の選択肢
- 博士課程への進学
- 研究機関に入る
- 教授の助手として研究を続ける
ここまで大学院生の就活に関する情報を解説しましたが、必ずしも就職だけが選択肢ではありません。博士課程への進学や研究の続行など、さまざまな選択肢があります。
ここからは、大学院生の就活以外の選択肢を解説します。「就職したくはないけどほかの人もやっているからやる」など、ネガティブな気持ちで就活に取り組もうとしている人は一度視野を広げて、自分に合った選択肢がないか探してみましょう。
博士課程への進学
博士課程への進学は、さらに高度な専門知識や研究能力を習得したいと考える人にとっておすすめな選択肢の一つです。博士課程では、修士課程よりもさらに深いレベルで研究に取り組むことになります。
また、新しい理論の提唱や技術の開発など、学術的な貢献が期待されるため、高度な専門性と自主性が必要となるのです。
そして、博士課程を修了すると、大学や研究機関での研究職や教員職に就くチャンスが広がります。また、企業の研究開発部門や高度な専門知識が必要とされる職種でも、博士号があることで有利になるケースがあります。
一方で、博士課程への進学には時間と費用がかかるため、進学を決断する際には明確な目標や計画、準備が必要になることは把握しておきましょう。
このように、博士課程を修了することでどのような道が開けるのかをイメージし、自分の将来像に合致するかをしっかりと見極めることが必要です。
- 修士と博士では、就活の進め方や就職の難易度にどのような違いが生まれるでしょうか。
希望する企業や職種によって就職難易度は変わる
大学院のなかでも博士課程修了者は修士課程修了者に比べ、高度な専門知識が評価されることから、研究職や技術職では就活が有利に進む傾向です。
ただし、実務経験や汎用性を重視する企業では、むしろ修士課程修了者が優先される場合もあります。
また、博士課程修了者は年齢や企業の育成方針との適合性が課題となることがあり、選考が狭まるケースもあります。
一方で、産学連携プロジェクトや特化型のキャリアパスが活用できる場合もあるため、市場ニーズを踏まえた戦略が重要です。
研究機関に入る
研究機関に入ることは、大学院で培った専門知識や研究スキルを直接活かせるキャリアパスの一つです。
研究機関では、大学や民間企業、政府系の研究所などがあり、分野ごとに多岐にわたる研究がおこなわれています。新しい知識の創出や技術の開発、社会問題の解決など、専門性を活かして社会に貢献できる場ともいえます。
研究機関での仕事は、高度な専門性が求められるため、大学院での研究経験を活用することが可能です。特に、論理的思考力、データ分析能力、課題解決能力などは、研究プロジェクトを進めるうえで欠かせません。
ただし、研究機関への就職は競争率が高いことが多いため、自分の研究分野での成果をしっかりとアピールすることが重要です。また、研究テーマの将来性や、自分がその分野でどのように貢献できるかを具体的に示すことで、選考での評価を高めることができます。
自分の専門性を活かしながら学びを深め、社会に貢献できるやりがいのある選択肢の一つとして、研究機関でのキャリアも視野に入れてみてください。
- 仕事の安定性や将来性、長期的なキャリアパスについて、研究機関と民間企業ではどのような違いがありますか?
働き方や将来性は一長一短なので慎重に検討を進めよう
大学や研究機関は、研究費を獲得する必要がありますが、時間をかけて研究できるメリットがあります。
一方で民間企業は利益を追求するので、ビジネスにつなげるためにスピードが求められます。商品化が難しければ、研究が打ち切りになるケースもあるでしょう。
仕事の安定性は一概にはいえないものの、大学や政府機関に契約社員として雇用される場合は継続して仕事ができるか不安な一面があります。
民間企業は、正社員として雇用されることが多いので仕事は安定していますが、異動などで業務が変わるかもしれません。
長期的なキャリアパスについては、大学や政府機関は研究者として教授への道があり、民間企業は、研究部門などの管理職や役員が考えられます。
教授の助手として研究を続ける
教授の助手として研究を続けることは、大学院で培った研究スキルや専門知識を活かしながら、学術的なキャリアを追求する方法の一つです。
助手としての役割には、教授の研究をサポートするだけでなく、自身の研究を深めたり、学生への指導をおこなったりすることも含まれます。教育機関内での研究に携わり続けたい人にとって魅力的な選択肢です。
教授の助手になることで、研究室運営のノウハウを学ぶ機会を得られると同時に、自身の研究テーマを発展させるためのリソースや環境を活用できます。
また、大学でのネットワークを活用することで、ほかの研究者との共同研究や学会発表のチャンスも広げることが可能です。
一方で、助手は任期制である場合が多く、安定した雇用を期待しにくいという側面もあります。そのため、将来的にどのようなキャリアを築きたいのかを明確にしたうえで、助手としての経験をキャリアアップの一環ととらえることが重要です。
大学院生ならではの差別化で就活を成功させよう
大学院の2年間は人生においてかけがえのない期間・経験となるでしょう。この2年間で専門的な知識・スキルを身に付けられたり、新しい仲間と出会えたりする可能性があるからです。
しかし、入念な準備をしたうえで就活に臨まなければ、大学院の2年間を活かせない企業に就職せざるを得ない状況となり、入社後に後悔することも考えられるのです。
将来的に自分のやりたいことを仕事にするためにも、就活では効率的かつ大学院生だからこそできるアピールをして差別化を図り、志望企業の内定を勝ち取りましょう。
アドバイザーコメント
大学院生は専門性を武器に就活を進めるのがポイント
大学院生として就活に臨む際には、研究で培った専門知識やスキルを武器に、自分らしいキャリアを目指して行動することが重要です。まずは就活スケジュールを把握し、自己分析や業界研究を計画的に進めましょう。
忙しい研究活動との両立が必要ですが、効率的に準備を進めることで、学びを活かせる就職先を見つけられる可能性が高まります。
また、大学院生は即戦力として期待されるだけでなく、柔軟性やチームでの適応力も重視されます。
研究内容や専門性をアピールする際には、簡潔かつわかりやすい説明を心掛けましょう。その成果がどのように企業に貢献できるのかを具体的に示すことが、選考を突破するカギとなります。
入社した先の長期的なキャリアを見すえて就活と向き合おう
さらに、推薦制度やインターンなど、大学院生ならではの就活方法も積極的に活用しましょう。ただし推薦に頼りすぎず、自由応募にも挑戦することで選択肢を広げることが大切です。
就活はゴールではなく、キャリア形成の一歩に過ぎません。自分の価値観や将来の目標を見すえた選択をして、納得のいくキャリアを築いてください。あなたの努力は必ず実を結びます。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi







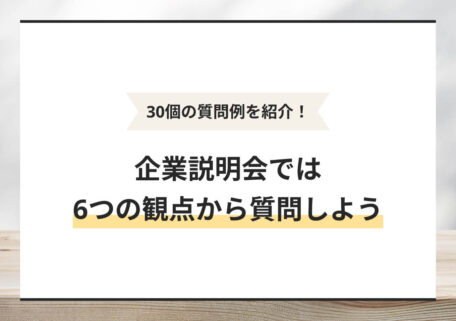

















3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表
Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/むらや社労士事務所代表
Yoko Muraya〇上場企業を含む民間企業での人事・採用経験約20年。就職支援や転職相談に従事し多くの求職者を支え、セミナー講師も務める。社労士の専門知識を活かし温かい雰囲気で各人に寄り添う
プロフィール詳細キャリア・デベロップメント・アドバイザー/キャリアドメイン代表
Kenichiro Yadokoro〇大学でキャリアデザイン講座を担当した経験を持つ。現在は転職希望者や大学生向けの個別支援、転職者向けのセミナー、採用担当者向けのセミナーのほか、書籍の執筆をおこなう
プロフィール詳細