就職したくないと悩むあなたへの解決案|悩みの原因と対処法を解説

この記事のまとめ
- 就職したくないと考える気持ちは甘えではない
- 就職したくない理由を正しく押さえることで自分が取るべき行動が見えてくる
- 就職したくないと感じたときは「行動する」もしくは「割り切る」ことが大切
- 適職診断
たった3分であなたの受けない方がいい職業がわかる!
この記事を読んでいる人におすすめ
「就職したくない」と一度は考えたことのある人も多いのではないでしょうか。「働くのって大変そうだから、就職したくないな……」「就職したくないけど、他に選べる道があるのかもわからない」と多くの学生から悩みの声が寄せられます。
就職したくないという自分の気持ちを正しく整理しないままでいると、「就職したくない」「就活したくない」という気持ちが増幅し、いつまで経っても暗い気持ちが晴れません。自分のその「就職したくない」感情や原因を正しく理解することで、自分自身の気持ちが楽になり、前向きに将来を考えられるようになります。
この記事では、キャリアアドバイザーの富岡さん、隈本さん、渡部さんのアドバイスを交えつつ解説します。就職したくないと感じている人はぜひ参考にしてみてくださいね。
【完全無料】
就活生におすすめ!
本選考前に必ず使ってほしい厳選ツールランキング
① 適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
②ChatGPT 自己PR作成ツール
ChatGPTを活用すれば、企業に合わせた自己PRが簡単につくれます
③ChatGPT ガクチカ作成ツール
特別なエピソードがなくても、人事に刺さるガクチカを自動作成できます
④志望動機作成ツール
ツールを使えば、企業から求められる志望動機が完成します
⑤面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
【本選考を控えている就活生必見】
選考通過率を上げたいなら以下のツールを活用しよう!
①内定者ES100選
大手内定者のESが見放題!100種類の事例から受かるESの作り方がわかります
②WEBテスト対策問題集
SPI、玉手箱、TG-Webなどの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
就職したくないときは自分の感情やメリット・デメリットと向き合うことが重要!
就職したくないという気持ちが強いのであれば、当然就職をしないという決断も1つの選択肢です。とはいえ、就職をしないメリットやデメリットを押さえて慎重に判断しなければ、後悔をする原因ともなります。
記事では、まず就職をしたくないと感じる理由を解説。自分の「なんとなく」はなぜそう感じるのかを明らかにしていきましょう。また、就職をしたくない学生向けに、就職以外の選択肢を紹介します。併せて就職をしないメリット・デメリットを徹底解説するため、自分の状況に合った選択をしてくださいね。
さらに、就職を前向きに捉えるコツや就職をしない選択を選ぶ際に注意するべきポイントも解説。自分のモヤモヤとした「就職したくない」という感情を、一つずつ丁寧に解きほぐし、取るべき行動を判断していきましょう。
就職活動が面倒、何もしたくない……という人は、こちらの記事を参考にするとそんな状況を脱却できますよ。
「何もしたくない……」無気力でも納得の道を見つける方法
「就職する意味って?」と考えている人は、こちらの記事もおすすめです。複数の視点から意味を解説し、自分なりの答えの見つけ方を紹介しています。
就職する意味とは|キャリアの専門家が示す後悔しない考え方
そもそも「就職したくない」という気持ちは甘えではない
就職したくないと周囲に言うと、怒られてしまったり、考えが甘いなどと言われてしまった経験のある学生もいるかもしれませんね。しかし、就職したくないという感情は決して甘えではありません。
これまでの学生生活から社会人になるという大きな環境の変化に、戸惑いや不安を抱かない人はほとんどいません。あなただけが感じている感情ではなく、多くの人が「働きたくない」「就活したくない」と考えるものです。
「就職したくないと感じる自分はダメな人間なのだろうか」と不安や自己嫌悪に陥ることなく、現実をしっかりと見つめている自分をまずは褒めてあげましょう。
あくまでも、自分が最も後悔しない道を選ぶことが大切だということを念頭に置いてくださいね。
アドバイザーコメント
隈本 稔
プロフィールを見る就職は人生の転換点であるため「就職したくない」と思う人も多い
これまで学ぶことが中心だった学生にとって、就職はこれから先、自分がどう生きていきたいかを自分なりに考える初めての機会かもしれません。それだけ大きな決断がともなう転換点であるため、「就職したくない」という気持ちを持つことは当然であり、甘えなどではありませんよ。
就職活動が近づくにつれて、自分がどういった仕事をしたいかについて漠然と考えてきたかもしれません。しかし、実際に自分が就職したい会社で事前に働くことはできず、自分で集められる情報にも限りがあります。そのため、就職先を考えていても自分に合っているかどうかは判断できず、活き活きと働いている自分のイメージが湧きにくいでしょう。
就活でこれから先のすべてのキャリアや生き方が決まるわけではない
ましてや、どんなに万全に準備をしても希望の職業に就けるとは限らないため、そういった不安からも就職したくないという気持ちになるのは当然です。ただ、今選択したことで、これから先のキャリアや生き方がすべて決まるわけではありません。
実際に就職してから学ぶことも数多くあります。まずは、自分の今後について自分なりの結論を出す機会が来たと考えて、少しずつ行動を起こしてみてはいかがでしょうか。
あなたが受けない方がいい職業を確認してください!
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
まずは自分と向き合おう! 「就職したくない」と感じる7つの理由

なんとなく就職したくないと思っているだけで理由がわからないと、焦燥感に駆られやすく、精神的に疲れてしまうことがあります。
就職したくない理由はさまざまです。自分がなぜ就職したくないと思うのか、まずはその理由と向き合っていきましょう。理由がわかることで、就職したくない感情と向き合い、対策がとれるようになりますよ。
①そもそも働きたくない
そもそも働くことを後ろ向きに感じている人もいるのではないでしょうか。
基本的に多くの学生は社会人経験はなく、あってもアルバイト経験です。学生時代のアルバイトとは異なり毎日8時間以上、定年まで働き続けることを考えると、および腰になってしまうこともあるでしょう。
また、人付き合いが苦手であったり過度な責任を負いたくない、楽をしたいという気持ちが強い学生はそもそも働きたくないと感じる人も多いようです。
身近な家族やアルバイト先の先輩たちが大変そうに働いている姿を見てきた学生は、仕事は辛い、つまらないというイメージを持っている人が多い印象です。
気の合う友人と好きなことをして過ごす今の生活と大きく変わってしまうことに不安を抱くことが「働きたくない」と感じてしまう原因とも言えます。
「働きたくない」という気持ちが強い人は、働く意味を見つけると、納得感を持って社会人への準備ができるようになるかもしれません。こちらの記事から、自分に合った働く意味を探してみてください。
働く意味ってあるの? 納得して就活を進める考え方を解説
大学3年生におすすめ!
就活準備は適職診断からはじめてください!
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
②働くことに自信がない
働くことに不安があることから就職したくない人もいます。「仕事を覚えられなかったらどうしよう」「ちゃんと働けるか自信がない」といった思いが強いことが原因の一つです。
また、周囲の話やニュースなどで仕事の辛さや過酷さを耳にして、就職することへの不安が募る人もいます。
これまでアルバイト以外で働く機会がほとんどなかった学生にとって、働くことに自信がないのは当然です。
しかし、ほとんどの人は、就職した後の経験を通して自分なりの働き方を見つけています。今は不安かもしれませんが、これまでと同じように経験から学んで不安を乗り越えることもできるはずですよ。
働くことに向いていないと感じる人は、こちらの記事で原因と対処法を解説しています。既卒・第二新卒向けの記事になりますが、新卒の皆さんも十分参考になりますよ。
働くことに向いていない原因|不安を完全に取り除く考え方・行動
③向いている仕事ややりたい仕事がわからない
今まで勉強をして、部活やサークル、遊びなどさまざまな経験をしてきましたね。しかし、それらが仕事に直結する人はごくわずかで、多くの学生は新たに今後の進路を考えることになります。自分に合った仕事がわからず就職をしたくないと感じる人もいるでしょう。
就活シーズンになり、いきなりやりたい仕事を考えてみても、学業や経験が仕事に結びつくわけでもなく、「興味がないのに働きたくないな」と感じてしまいますよね。
- 自分には向いている仕事もやりたいこともないんじゃないかと思います……。どうやって見つければ良いのでしょうか?
will・can・mustのフレームワークから見つけてみよう
向いている仕事がないなんてことはありません。自己分析をしてみると自分に向いている仕事や自分がやりたい仕事が見えてくるため、まずは自己分析から始めてみましょう。
オススメなのがwill・can・mustのフレームワークです。
willには「やりたいこと」、canには「できること」、mustには「しなければならないこと」を書き出し、3つの輪を重ねていきます。重なった部分に当てはまる仕事がその人の天職であると言われています。
今までの勉強、部活やサークル、アルバイト経験などを振り返り、自分の強み、興味関心がある分野を考えてみましょう。
mustは難しく感じるかもしれませんが、興味のある分野を深堀りしていくと現在世の中にどのような問題があるかが見えてきます。仕事を通してどのような価値を提供しなければならないかを想像していきましょう。
④希望に叶う会社が見つからない
業種や職種、給与、休暇、勤務地、福利厚生などさまざまな条件から企業を選ぶことになります。しかし、自分の希望条件にぴったり合った企業が見つからないと就職したくないと感じる原因となります。
仕事内容に興味があっても給与が低く感じる、仕事や給与が良くても全国転勤で自分の志向に合わないなど、妥協をしなければならないことを想像すると働きたくなくなってしまう人も多いものです。
自分の理想の条件をすべて満たす企業などはほとんどありません。あったとしても多くの学生が志望するため競争率は非常に高くなるはずです。
企業に高いレベルを求めれば自分も高いレベルにならなければならないことを念頭に置いてくださいね。
⑤組織や時間に拘束されたくない
上司や同僚、部下との関係を築きながら、毎日同じように同じ時間に働くことが嫌な人は、就職したくないと感じることが多いです。就職するということは、組織に所属するということです。
会社に人生を左右されたくないからこそ、組織で働きたくないと考える人もいるかもしれませんね。また、組織によって人生にレールを引かれることが嫌という気持ちも、就職したくない原因となります。
⑥就活をしたくない
就活のシステムそのものに違和感を感じ、「就活」をしたくないことが、就職したくない原因となっている人もいます。学生みんなが同じような服装や髪型をして、似たような回答をする就活スタイルに、違和感を感じてしまっているかもしれません。
また、細かいマナーがあったり、自分の良さをプレゼンしなければならないことをくだらないと思う人もいるでしょう。
就活が面倒だと感じる学生は以下の記事を参考にすると、面倒な気持ちが軽減するため、参考にしてください。
就活の面倒が一気になくなる方法14選|前向きに進める秘訣も解説
⑦就活がうまくいかない
エントリーシート(ES)や履歴書を頑張って作成したものの、書類選考が通らなかったり、準備をして面接に臨んだものの、不合格が続いてしまうことから心が折れて就職したくないと考える人もいます。
選考に落ち続けてしまうことで、「自分なんて……」「働いたってうまくいかない……」と自分を卑下してしまうこともあるかもしれません。
就活がうまくいかなくて悩んでいる人は、こちらの記事を参考にしてくださいね。
就活がうまくいかないあなたへの処方箋|今すぐできる対策を徹底解説
就活がうまくいかずに焦りを感じている学生は以下の記事を参考にしてくださいね。
就活は焦る必要まったくなし! 内定にぐっと近づく5つの考え方
就活を進めていく中で、疲れを感じることもあるかもしれません。就活の疲れから就職したくないと感じる人は、以下の記事もおすすめです。
就活に疲れた人への休息の手引き|絶対にやってはいけないことも解説
就活が始まると就活に対する漠然とした不安や就職することへの不安など不安に感じることが多くあります。就活に不安を感じている人は以下の記事を参考にしてみてください。
就活が不安なのは当たり前! 考え方を変えるコツと対処法を解説
- 就職したくないのですが、どの理由も当てはまってしまいます……。やっぱり就職することに向いていないのでしょうか?
情報の不足・過剰からそのように感じているだけ
未知のものに対する不安や怖れは人間に本能的に備わっているものです。情報を得たり経験を積んだりすることによって「未知」のものを「既知」のものに変えることができます。
今まで誰もがそうして学習し成長してきたはずですが、なぜ就職に対して特に抵抗があるのでしょうか。
原因の1つに、情報の不足や過剰があります。職業や会社のことをあまりにも知らなければ不安が募るうえ、自己分析が足りなければ働くことに常に悩むことになります。
また、過剰な情報とは、働くことがうまくいっていない先輩の話やSNSにあふれる噂などです。根拠のあいまいな情報に感化されている場合もあるかもしれません。向いていないと判断する前に、情報をまず精査してみましょう。
かんたん3分!受けない方がいい職種がわかる適職診断
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
就職したくないときの就職以外の選択肢

就職したくないと思い始めると、就活にも身が入らないことも多いかもしれません。そんなときは、就職する以外の選択肢にはどんな道があるのかを確認していきましょう。
特に現在やりたいことが決まっていない人にとっては「就職しなくてもなんとかなりそう」と思えたり、逆に「自分は就職したほうが良さそうだな」と思え、今よりも前向きになれますよ。
フリーターになる
フリーターになるメリット
・勤務日や勤務時間が柔軟
・重い責任がない
フリーターになるデメリット
・雇用が安定しない
・収入が増えづらい
・税金などを自分で払う必要がある
・社会的信用が低い傾向にある
就職しない場合でも、生きていくためにはお金が必要です。生計を立てるために、フリーターという選択肢があります。フリーターは、正社員ではなくアルバイトとして時給で働く働き方です。
勤務日や勤務時間が比較的柔軟であり、重い責任を課されることなく気軽に働けるというメリットがあるものの、雇用が安定せず、収入が増えにくいというデメリットもあります。新入社員のときは正社員とそれほど変わらない月収に見えるかもしれませんが、年を重ねれば大きな差となってしまいます。
また、フリーターは社会保険(年金・健康保険・失業保険)などがないため、自分で所得税や住民税、国民健康保険、国民年金などを支払わなければなりません。社会的信用が得られにくいこともあり、クレジットカードの作成やローンの審査が通りにくくなることもデメリットとして挙げられます。
元気に健康で働けるうちは就職せずにフリーターになるという選択肢も良いですが、うつ病などを発症してしまった場合に休職制度の適用対象外になってしまうケースがあります。
また、出産・育児休暇取得に関しても要件があるため注意してください。
1人で働く
1人で働くメリット
・自分の裁量で働ける
・人間関係の悩みが比較的少ない
1人で働くデメリット
・収入が安定しない
・稼げるようになるまで時間がかかる
・社会的信用が低い傾向にある
・自分で自分を律して働く必要がある
フリーランスになったり、起業をすれば、企業に属さず、自分の裁量で働くことができます。場所にとらわれることも少なく、やるべきことさえやれば自分の好きな時間に働けるメリットがあります。また、株式・FX・仮想通貨などの投資家となれば、1人で働くことも可能です。
しかし、いずれも収入が安定しない可能性や、稼げるようになるまで時間がかかるデメリットもあります。また働くのも働かないのも自分次第ということになるため、楽をしたい、のんびりしたいという自分の誘惑に打ち勝ち、仕事に取り組む必要があります。
また、会社員に比べて社会的信用が低くなってしまいがちで、ローンなどの審査通過はややハードルが高いという点を理解しておく必要があります。
1人で働く例
- フリーランスになる
- 起業をする
- 投資家になる
新卒から1人で働く場合には、ビジネスで起こったことのすべてを、自分で責任を負わなければいけません。
社会経験がない中で、これまで経験したことがないトラブルなどに対応するのは困難であり、信頼を失えば新しい仕事を契約することも難しくなる危険性も潜んでいます。
会社の人間関係で悩みたくない人は以下の記事を参考にしてみてください。一人でできる仕事を解説しています。
一人でできる仕事50選|失敗しない仕事選びの3ステップも解説!
留年・休学をする
留年・休学をするメリット
・就職するまでの猶予を獲得できる
・翌年以降に新卒として就活ができる
留年・休学するデメリット
・休学・留年中の活動を企業から問われることが多い
・大学での費用が発生する
卒業を保留にして、留年や休学という形で大学に在籍することで、就職するまでに猶予を獲得することができます。留年や休学であれば、翌年に「新卒」として就活ができるため、メリットは非常に大きいです。
ただし留年や休学後に改めて就活する際は、留年・休学そのものが不利になることは少ないですが、留年の理由や休学中の活動を企業に説明できるようにしなければなりません。また、大学によっては休学中も費用が発生するなどお金がかかるため、自分の所属大学はいくら必要なのか、HPを見て把握しておくなど注意を払ってくださいね。
留年と似た選択として、大学を卒業して就職浪人をする方法もあります。厚生労働省が定めた青少年雇用機会確保指針によると、学校を卒業後3年以内は新卒扱いとするとありますが、事実上企業はいわゆる「既卒」として扱うことが多いです。そのため、新卒よりはエントリーできる企業の選択肢が狭まってしまうこともあります。
既卒の定義や就活についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、既卒になることを検討している人は参考にしてください。
既卒とは? 新卒・中途との違いや就活の必勝法を徹底解説
留年や休学の場合、半期卒業などで卒業時期が異なってブランクが空いてしまうことがあります。
また、休学中の場合は、都度発生する求人情報をタイムリーに得ることが難しい場合もあるため、まめにチェックをおこなう必要がありますよ。
進学する
進学するメリット
・就職まで猶予期間が生まれる
・専門分野を極めることができる
・就職の幅が広がる可能性がある
・学部卒より高い給与を狙える
進学するデメリット
・金銭的負担が大きい
・資格によっては年齢制限がある
就職をしたくないのであれば、大学院や専門学校で勉強をするという選択もあります。進学をすることで、就職までの2〜4年の猶予期間が生まれます。専門分野を極めたり、新しい分野を学ぶことで就職の幅が広がる可能性があります。
大学院卒であれば、学部卒よりも給与が高い傾向にあるため、高収入を狙えるというメリットもありますね。
大学院・専門学校のいずれにしても、授業料など金銭的な負担が大きいことや、専門学校で資格取得を目指すのであれば、公務員・資格試験を受けるのに年齢制限があることを忘れないようにしましょう。
- 文系の大学院卒は就職に不利って噂を聞きました……。実際どうなのでしょうか?
不利になることもあるが、マッチ度を意識すれば大丈夫
希望する就職先によっては、不利になる場合もあります。極端な例ですが、文系の歴史学科でメーカーの開発職に応募をしても、マッチ度が低いため書類選考で落選するでしょう。
しかし、それはどの学部でも同じであり、文系だから不利というわけではありません。
就職活動をする際に、面接官に対してその大学院を選んだ理由や、学んだことを就職した後にどう活かせるのかを伝えることが重要です。
海外留学をする
海外留学をするメリット
・語学力が身に付く
・新しい文化や価値観に触れられる
・空白期間がポジティブな印象になる
海外留学をするデメリット
・短い留学では企業からの評価が期待できない
・金銭的負担が大きい
語学力が身に付き、新しい文化や価値観に巡り合える海外留学という選択肢もあります。見知らぬ土地で、さまざまな経験をすることができるため、自分のやりたいことや向いていることが見えてくるかもしれません。
また、就職までの空白期間について企業からたずねられた際にもポジティブな印象になりやすいといえます。
しかし、6か月未満などの短い海外留学ではそこまで自分自身が変化しないだけでなく、企業からの評価もあまり期待できないため、単純に新卒就活のタイミングを逃しただけという結果になる可能性もあります。また、海外留学は費用も掛かるため、どのようにお金を捻出するかも考えなければなりません。
アドバイザーコメント
渡部 俊和
プロフィールを見る就職以外の選択をしても人とかかわる機会は常にある
就職は、言葉を変えれば組織に属して役割を分担し、チーム単位での成果を目指すことです。人間でも動物でも、生物は生き延びるために、単独では不利なため集団で行動をします。
たとえ就職以外の選択肢を選んだとしても、おそらく誰かと協力したり連携したりする機会は常にあり、そこに根本的な違いはありません。ずっと就職しない場合は自分なりの対人関係のネットワークを築いていくことになり、いずれ就職も考えるのであれば、就職した時点で組織の既存のチームに加わることになります。
後から就職をしたいと考えたときに自分が何を企業に提供できるか考えよう
「いったん就職を保留したいがいずれは就職したい」という場合は、この「後からチームに加わる」ということがどんどん難しくなることを認識しておいてください。スポーツにたとえると、途中加入の選手が成果を上げるのはスキルや経験がある場合に限られます。
日本の新卒採用はスキルのない状態で採用して育てるため、合流が遅れればそれだけハンデが大きくなります。そのハンデに見合うだけの経験やスキルを、保留の間に持ち帰ることができるかどうか、という視点で、何をするか判断してくださいね。
就職以外にもさまざまな選択肢があることから、「就活をやめたい」と考える人もいるかと思います。そんな人はぜひ次の記事を参考にしてみてください。就活をやめたいと考えている人向けにネガティブな発想をポジティブに変えていく方法について解説していますよ。
就活をやめたい時の脱却方法は? ポジティブへの転換法を解説
就職しないメリット・デメリットから自分に合った選択を考えよう
就職しないメリット
①時間に拘束されにくい
②会社員以上に高収入が見込める可能性がある
③仕事上での人間関係に悩まなくて良い
④好きなことに集中できる
就職しないデメリット
①社会的信用が得られないこともある
②就職がしたいと思ったときに就職が厳しくなる
③安定した収入が得られにくい
④人間関係の幅が狭くなる
⑤社会人としてのマナーやスキルが身に付かない
⑥「新卒就活」ができない
就職したくないというと、頭ごなしにその考えを否定された経験を持つ学生も多いのではないでしょうか。たしかに、新卒就活をして就職をする流れが一般的です。しかし、深く考えずに就職してしまうのは少し危険かもしれません。
また、なんとなくの不安や嫌悪感から就職をせずに、後から「あのときしっかり就活すれば良かった」と後悔するのは避けたいですよね。
就職しないメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかを確認して、自分に合った選択ができるようにしましょう。
就職をする・しないのそれぞれのメリットデメリットを把握していないと、納得した選択をすることができないため後で後悔をしてしまいます。
意思を持って自分で決断し、一歩を踏み出すと、その後どんな困難なことがあっても誰かのせいにせず、「自分で決めたのだから頑張ろう」と成長していくことができますよ。
メリット①時間に拘束されにくい
就職をすると多くは週5日以上、一日8時間以上働くことになります。そのため、多くの時間を会社に割かなければなりません。
しかし、就職をしない選択をすることで、休みたいときに休む、遊びたいときに遊ぶなどといった自由な行動がしやすくなります。
たとえば、フリーターであればシフト勤務で自由が効くため、「金欠だから今月はたくさん働こう」「趣味に時間を使いたいから今週はシフトを減らそう」などと決められます。また、フリーランスであれば自分で定めた仕事さえクリアしていれば、朝働くのも夜働くのも自由です。
メリット②会社員以上に高収入が見込める可能性がある
就職をすると、企業ごとに、大まかに何歳で年収はいくらくらいもらえそうかと見えてくるものです。余程インセンティブの割合が大きくない限りは、企業に所属をすると自分が稼げる年収はある程度決まってきてしまいます。
しかし、就職しない選択をして、フリーランスや起業家、投資家などになれば、会社員では稼げないほどの収入を稼げる可能性もあります。
たとえば、フリーランスで新卒と同じ年齢でも月100万円以上稼ぐことや、起業をしてその事業を売却できれば何億円もの金額になることもあります。
会社員以上に高収入が見込める可能性があるとはいえ、フリーランスとして活動を始めても、アピールできる実績や信頼性がなければ、いきなり高単価の契約ができるのは稀です。
内閣府の調べでも、フリーランスで年収が1,000万円を超えるのは全体の4%ほどとされており、実は一握りの人たちを除けば就職している人とほとんど差がありません。
メリット③仕事上での人間関係に悩まなくて良い
就職をせず会社に属さないことで、上司や先輩からの指示を受けることもなく、また人間関係も比較的自分で選びやすいので、苦手な人と付き合わなければならない場面が少なくなります。
また、就職をしなければ業務やノルマの管理も自分自身でやるため、上司から怒られることもないなど人間関係で悩むことが減ります。
フリーランスや起業家は、組織内部の人間関係の悩みはありませんが、その分、外部との人間関係が重要になります。自由気ままにやっていても嫌われたら仕事になりません。
また、自分が代表のため、付き合いが上手くいかない相手でもかかわらざるを得ない場面もあり、代理が利かないというリスクはあります。
メリット④好きなことに集中できる
就職をしなければ、大学卒業後は特に好きなことに集中できる環境だといえます。働き方としても企業に属さないため、毎日同じ時間に出社をする必要もなく、自分の思うように働く時間を決めやすいです。
また、趣味の時間や挑戦したいことなど自分のやりたいことを自由にできるため、毎日あくせく働くよりも魅力に感じる人は多いでしょう。
さらに就職をしないということは、就活もしないということでもあります。就活をしない分、貴重な学生時代の時間を自由に使うことができます。たとえば、大学3年生の4月から就活をするとしたら2年間を好きなことに集中できますね。
就職をしなければ好きなことに集中する時間はたくさんあります。しかし、好きなことをするにもお金が必要となってくるため注意しましょう。
お金がなくて日々の生活が苦しくなり、好きなことができなくなってしまっては本末転倒です。
デメリット①社会的信用が得られないこともある
前の章でも説明してきましたが、会社員以外で働くということは社会的信用があまり得られないケースもあります。
社会的信用が低いことで起きる弊害は以下の通りです。
社会的信用が低いことで起きる弊害
- 家や車などローンが組めないことがある
- 金利が割高になることがある
- クレジットカードが作れないことがある
- 賃貸物件を借りることが難しいことがある
もちろん、必ずしも上記の弊害が起きるとは限りませんが、社会的信用が低いせいで困らないためにもお金や法律に関する知識を付けておく必要があります。
デメリット②就職がしたいと思ったときに就職が厳しくなる
就職をしないで空白期間を作り、少ししてから就職をしようとすると、空白期間が目立ってしまい、企業から働く意欲について懸念される可能性があります。
たとえば、フリーターだったら正社員としての社会人経験がないことや、フリーランスなど1人で働いていた場合は、組織に迎合できるかといった点に不安を抱かれやすいです。
実際に大学卒業後ブランクがある学生に対して企業が抱く印象は、空白期間の長さによって変わります。
やはり、ブランクが3年を超えるなど、長いほど定着の可能性が低いと判断しがちです。ブランク期間について納得のいく理由を説明できないと、希望の職業に就くのはかなり苦労するでしょう。
デメリット③安定した収入が得られにくい
会社員でないと安定して稼ぐことが難しいのも、就職をしない大きなデメリットです。フリーターであれば、コンスタントにシフトに入れるとも限らず、勤務先の状況によってはシフトを削られてしまうこともあります。
またフリーランスであれば、多くの顧客と契約を継続的に結ぶことが難しいこともあります。特に、フリーランスになりたてのときは、契約ができずに思うように稼げないといったことも少なくありません。
また、ケガや病気などで一定期間働けないときは、会社員であれば健康保険制度の1つである疾病手当金を受け取れ、生活を維持できます。しかし、就職をしていないと疾病手当金などは受け取れず安定していないとも言えます。
デメリット④人間関係の幅が狭くなる
就職をしないと企業に属さない分、人間関係の幅が狭くなりがちです。
たとえばフリーターであれば職場で人間関係は作りやすいと思うかもしれません。しかし、正社員として企業に属すると他部署や顧客とのかかわりなどもあり、人間関係の幅には差が出てきます。
また、フリーランスは顧客から依頼を受注をして1人で黙々と作業をすることになれば、寂しさを感じたり、仕事を依頼してくれる人とのかかわりが作りにくくなってしまうかもしれません。
- 人間関係の幅を持たせるとどんなメリットがあるのですか?
自身の成長はもちろん、ライフプランに関するメリットもある
企業に属するとさまざまな立場の人が働いているため、幅広い年代の多様な価値観を持った人に出会います。
自分とは違うものの見方や考え方に触れると視野を広げることができ、成長することができます。
また現在は未婚の人が増えており、その原因に「出会いがない」という理由があります。もし、将来的に結婚をしたいという考えを持つ人であれば、人間関係の幅が広ければ広いほど仕事を通して結婚相手に出会えるチャンスが高まります。
デメリット⑤社会人としてのマナーやスキルが身に付かない
社会人経験がないまま就職しない選択肢を取ってしまうと、社会人としての基本が身に付かないというデメリットがあります。
たとえば、メールの書き方や取引先との対応方法など基本的なビジネスマナー、Excelなどの基礎的なパソコンスキルなど、社会人を数年経験した人ならできるようなことを習得する機会は少ないといえます。
そして、後から就職をしようと思ったときに周囲の転職者とマナーやスキルで差がついてしまったり、フリーランスで働く際もマナーが身に付いていないことから契約を見送られてしまうなんてことになりかねません。
学生時代は友人関係のつながりがほとんどで、大学も学生側が学費を払っている立場のため、基本的なことや細かな点を叱ってくれる相手がいません。
そのため気づきにくいことですが、最低限のマナーが身についていない学生は結構多いものですよ。
デメリット⑥「新卒就活」ができない
就職をしない最大のデメリットといっても過言ではないのが、新卒就活ができないということです。新卒で就活をする機会は、基本的に人生で一度切りの貴重な機会であるということを、みなさんは深く理解しておきましょう。
とはいえ、就活にもメリットとデメリットがつきものです。就職以外にやりたいことがはっきり決まっている人以外は、就職をしない選択をする人でも、就活だけはしておいても損はありませんよ。
就活をするメリット
就活をするメリット
- さまざまな業界や仕事を見ることができる
- 未経験の仕事にチャレンジできる
- スキルを身に付ければ独立・起業の可能性が広がる
- 社内の人脈が根強いものとなる
就活をしていると、企業説明会やインターンシップなどに行くのは面倒くさいと感じる人も多いかもしれません。しかし、新卒の機会を逃してしまうと、企業から直接話を聞く機会や業務を体験できる機会を得ることは難しくなります。さまざまな業界や仕事を見れるせっかくの貴重な機会ということを念頭に置いてくださいね。
新卒は基本的にポテンシャル採用であるため、即戦力となるようなスキルは求められないことが多いです。そのため、転職求人の募集の際には未経験者を募集していないような職種や、そもそも求人をあまり出さないような業種に自由に挑戦しやすいとも言えます。スキルがないからこそ、入社後の教育を基礎から受けられるメリットは大きいですね。
企業からの研修や業務を通してスキルを身に付ければ、そこから独立・起業の可能性も広がります。また、新卒から入社をすると社内の人脈が根強くなったり、同期との絆を手に入れることもできます。
就活をすると自己理解を深めることができます。履歴書やES作成のために自分を見つめ直し、企業研究をするほか、面接官と話をする中で自分のやりたいことが見つかることも大いにあります。
就活をするデメリット
就活をするデメリット
- 就活に莫大な時間と労力をかけなければならない
- 内定が出ないと精神的に落ち込む
就活には、新卒一括採用ならではのプレッシャーがあります。ポテンシャル採用の就活では、スキルではなく自分の人柄などを評価されていると感じやすいからこそ、「自分を否定されたくない」という思いを強く抱く学生も多いです。
失敗をしたくないからこそ、就活対策に多くの時間と労力を割くこととなり、就活中はやりたいことをすることが難しいというデメリットがあります。また、不合格や不採用が続くと精神的に落ち込んでしまうことも多いです。
デメリットはあるものの、新卒就活と比較して大学を卒業してからの既卒就活は難しい傾向があることは忘れないでくださいね。
アドバイザーコメント
富岡 順子
プロフィールを見る社会的信用を築くことが難しい点は認識しておこう
就職をしない最大のデメリットは、信用を築いていくことが大変なところです。日本は一度社員になると定年まで働けるというメンバーシップ型雇用が大半を占めていることもあり、ローンなどは就職していることで借りやすくなります。私は金融機関でローン受付を担当していましたが、審査は人柄で融資の可否が決まるということはなく、あくまでも返済能力があるかどうかを基準に審査されます。
アカデミー賞受賞の稼ぎのある有名な俳優であってもローンが組めない、というニュースがあったように日本では就職しているかどうかという点を重視します。将来車や家のローンを組みたいとなったときにこういったデメリットがあることを覚えておいてください。中には審査不要で借りられる金融商品もありますが、金融トラブルにならないように注意が必要です。
対人関係での信用を築くことには強靭なメンタルが必要
お金の面だけでなく、フリーランスとして仕事をしていくうえでも信用を得ていくためには努力や工夫が必要となってきます。顧客は信頼できる事業、人に仕事を任せようと契約をしてくれます。
信用がない状態からスタートし、仕事を軌道に乗せるには時間がかかるだけでなく、強靭なメンタルが必要となります。研修の機会もないため、自分のお金を使って勉強していかなければならないということも頭に入れておきましょう。
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
就職するべきか迷ったときにやるべきこと
就職するべきか迷ったときにやるべきこと
- 人生設計を考えて就職をする必要があるのか考える
- 自分の譲れない条件を考える
- 社会人の話を聞く
- とりあえず就活だけしてみる
一時の感情ではなく、冷静にメリットやデメリットを踏まえたうえで「就職したくないけど就職するべきかも」と迷い始めた人や頭を抱える人もいるかもしれませんね。
そうであれば、今から解説する「就職するべきか迷ったときにやるべきこと」を実践してみてください。自分が就職をするべきなのかしない選択をしても良いのか、取るべき行動が見えてきます。
人生設計を考えて就職をする必要があるのか考える
今は就職したくないと考えているかもしれませんが、いつかは就職をしたいのかもしれません。自分が1年後、5年後、10年後どのような生活を送っていたいのか、ライフプランを考えてみましょう。
ライフプランを考えたうえで、就職する必要があるのかを判断することが大切です。結婚や出産、教育、住宅購入など人生における大切な出来事を、想像できる範囲でどのような未来を歩みたいのか考えてくださいね。
自分にとって理想の生活は何かを考え、理想の生活を送るのに必要な条件や資金を考えてみましょう。
- 将来のことなんてわかりません。そのときにまた考えれば良いやって思うのですが、それではまずいのでしょうか?
先延ばしにすると行動は起きないため、ある程度考えるべき
将来の理想や目標がないと人はその手段を考えようとは思いません。旅行にたとえれば、いつでも行けるからといって何も決めずにいたら永久に行動は起こらないでしょう。
まず目的地だけでも決めることによって、どうやっていくか、いつ行くか、などの手段を考えようとするのではないでしょうか。
就職は目的ではなく手段です。しかも新卒就職は今しか使えない手段なのです。よく考えずに使える手段を放棄したら、後で「新卒就職の方が有効だったのに」と後悔することもあるかもしれません。
行き当たりばったりで行動するよりは、ある程度考えておくことで、予期せぬ事態にも対処しやすくなりますよ。
自分の譲れない条件を考える
なぜ就職したくないと思うのか、自分の気持ちを言語化しましょう。そして、自分の譲れない条件を考えてみてください。
その条件に絞って企業を探せば、「働いてみても良いかも」となったり「やはり就職しないのが正解だな」と整理することができます。
自分の譲れない条件と適した企業の例
- 決まった時間に働きたくない
→フルフレックスタイム制度のある企業 - 年収が定まっていることが嫌
→インセンティブ制度のある企業 - スーツを着て会社に行くことが嫌
→服装自由やリモートワーク制度のある企業 - 朝早く働きたくない
→始業時間が遅い、もしくはフレックスタイム制度のある企業 - 満員電車に乗りたくない
→常にリモートワークが可能な企業
社会人の話を聞く
両親や、先輩、知人など働くさまざまな人から話を聞いてみましょう。楽しいことやつらいこと、やりがいなどを聞くことで、就職することのリアルなメリットやデメリットを知ることができます。
話を聞くときは、正社員や契約社員、フリーター、フリーランスなどできるかぎりさまざまな人から聞くようにすると多様な意見を取り込むことができます。
- どうやったらさまざまな働き方をしている人の話を聞くことができますか?
セミナーやワーキングスペースに行くと出会える
フリーランスや起業希望者向けに開催している各種セミナーであれば、すでにフリーランスで働いている人や、就職しながら起業を目指している人と接することができるでしょう。
また、コワーキングスペースでは、フリーランスはもちろん企業がサテライトオフィスとして使用していることがあります。
そういった場では、定期的な異業種交流会の開催や、会員同士をマッチングするサービスをおこなっていることもあります。イベント情報などを調べたうえで、一時的に会員になってみるのもおすすめです。
とりあえず就活だけしてみる
学生である今の状況では、「就活も就職もしない」「就活をして内定をもらったうえで就職しない」「就職をして少し働いてみる」「既卒で就活をする」など豊富な選択肢の中から進路を選ぶことができます。
しかし、今よりももう少し時間が経って新卒就活の時期が終わってしまうと、後悔しても新卒就活をすることはできません。よほどやりたいことが明確に決まっている人以外は、とりあえずでも良いので就活をしてみましょう。
初めての就職活動で、満足度100%の会社に就職できるとは限りません。実際に就職してみることで、自分が求める働き方が見えてくることもあります。
就職した後でも、転職はもちろん起業などもできるため、迷っているのであれば就職して社会に触れてみることも重要です。
就活をすることで、多くの社会人にも出会えます。また、就活を通してビジネスマナーを見つけることができるなど、就職先を探す以外のメリットも大きいものです。気軽な気持ちで就活に取り組むことをおすすめします。
アドバイザーコメント
隈本 稔
プロフィールを見る就職するか迷ったときは第三者の助けを借りることも視野に入れよう
自分一人だけで就職するべきか悩んで解決策を探ってもなかなか答えは出にくいと思います。そんなときは、第三者への相談やアセスメントツールの活用も検討してみましょう。
①学校のキャリアセンターで就職相談をする
高校や大学などでは、就職相談を受け付けているキャリアセンターが設けられているのが一般的です。キャリアセンターでは、企業の求人情報や合同イベントの案内だけではなく、キャリア設計についての相談も受け付けています。キャリアコンサルタントの有資格者なども在籍しているため、自分の就職についての悩みを相談してみましょう。
②ヤングハローワークを活用する
ヤングハローワークは、20代や30代を中心として若者向けの就労支援サービスをおこなっています。もちろん学生でも利用可能で、担当の相談員に具体的な求人情報の照会だけでなく、就職についての悩み相談もできます。相談員はキャリア構築に関する資格所有者が多いため、自分が話しやすい人にキャリアカウンセリングを受けてみるのも良いでしょう。
③アセスメントツールを利用してみる
就職について悩む理由には、仕事への価値観がわからないのはもちろん、そもそも仕事についてよく知らないということも少なくありません。その際には、いくつかの質問に答えることで、職業への適職について分析できるアセスメントツールを活用してみるのもいいでしょう。
ハローワークによっては、「VPI職業興味検査」や「キャリアインサイト」などのツールを無料で利用できます。診断結果をもとに、キャリアコンサルタントのカウンセリングを受けることで、仕事についての悩みを解決できる糸口を見つけられるかもしれません。
そのほかにも就活の相談ができる人やサービスは多くあります。14個の相談先や相談方法について、こちらの記事で解説しているので、併せてチェックしてくださいね。
就活の相談先14選! 良い決断ができる相談相手の選び方も解説
就職を前向きに捉える3つのコツ
就職を前向きに捉える3つのコツ
- 就活での出会いを楽しむ気持ちを持つ
- 買いたいものややりたいことを想像する
- 理想の社会人像を描く
「就職したくないけど、現実的に考えたら就職をしなくちゃ……」という人も多いかもしれません。どうせ就職をするなら前向きに捉えられた方が良いですよね。
今から解説する就職を前向きに捉える3つのコツを押さえて、少しでも就職に対してポジティブな印象を抱けるようにしましょう。
①就活での出会いを楽しむ気持ちを持つ
就職をするための就活は面倒くさいと感じる人も多いかもしれませんが、人生の中においても多くの業界や企業を知り、多くの人と出会うチャンスです。
企業説明会やOB・OG訪問で働く社員の意見を聞いたり、インターンで同年代の学生から刺激をもらったりなど、普段会うことのないような人とも出会うことができます。
無理にコミュニケーションを取る必要もありませんが、「今日はどんな人に出会えるのだろう、次はどんな人がいるのだろう」とぜひ楽しむ気持ちを持ってください。
社会に出てからは、他社の人から話を聞いたり、職場を見せてもらうことなどは簡単にはできません。
就活を楽しむための考え方として、知見を広める大きなチャンスと考えてはどうでしょうか。尊敬できる人やめったに会えない人などと出会えるかもしれません。
②買いたいものややりたいことを想像する
就職をすれば賃金として毎月コンスタントにお金が手に入ります。アルバイトでもお金を手に入れていたかもしれませんが、多くの学生にとっては会社員としての賃金の方が高いでしょう。
お金があれば、買いたいものややりたいことができます。「今までちょっと手が届かなかったものを買ってみようかな」「旅行に行ってみようかな」などと胸がうきうきと躍るような楽しいことを想像してみてください。
③理想の社会人像を描く
あなたはどんな社会人になりたいですか。就職したくないとは思いつつも、「自分が社会人になったら……」と想像をしたこともあるかと思います。理想の社会人像を描いて、就職するモチベーションを挙げてみましょう。
なにも仕事でやりたいことを考えることだけではありません。「退勤後は何をしようかな」「海外出張や駐在も楽しそうだな」などと幅広い視点で、自分の理想の姿やしてみたいことを想像してみましょう。
理想の社会人像の例
- 同僚とおしゃれなランチに行く
- 海外出張にいそしむ
- 新しい商品を企画してヒットさせる
- 後輩から慕われる
- さまざまな場所で顔が利く人脈を手に入れる
- たくさんお金を稼いで趣味を楽しむ
アドバイザーコメント
渡部 俊和
プロフィールを見る就職することでしかわからないこともある
就職は確かに人生の大きな転機ですが、あまり「取り返しのつかない重大なこと」と考えすぎても精神衛生上良くない気がします。前述したように就職はあくまでも手段であって、その先の人生をより良いものにするための選択肢の1つです。組織にもさまざまな組織があり、特徴や文化も違います。
しかし、そうしたことは外から眺めていてもわかりません。自ら飛び込んでみて経験を通じて初めて理解できることがあるのです。
長期的視点で見ると就職は自分のためになるという捉え方もできる
一般的には、何かの経験を積んでスキルを高めるために、お金を払って学ぶ方法がありますが、一方、就職は労働の対価としてお金をもらいながら、経験値を高めスキルアップを図ることができます。そして組織に守られつつ未体験の仕事にチャレンジもでき、ある程度の失敗も許されるというメリットもあります。
そう考えると、長期的に自分を成長させるうえでは、就職もあながち悪くないと思いませんか。多くの事業が会社組織によっておこなわれている中、たとえ起業や個人事業をすることになったとしても、顧客や取引先としての会社組織を知っておくことが役に立つこともありますよ。
内定後に就職したくないと感じたら?
内定後に就職したくないと感じたら?
- 初めて社会に出る不安だと割り切る
- 納得できるまで就活を進める
- 就職以外の道を選択する
就職したくないと思う人の中には、すでに内定を得ている状況の人もいるかもしれませんね。そんな人に向けて、内定後に就職したくないと感じたらどうするべきかを解説します。
就活が終盤、もしくは就活が終了してナイーブになりがちな時期でもあります。自分の気持ちを大切にしつつも、正しい状況判断をしていきましょう。
初めて社会に出る不安だと割り切る
基本的には就活で入社をする企業が、初めての社会人経験となる学生が多いです。社会人の土台となるファーストキャリアだからこそ、重要だと考えますよね。
初めて社会に出るからこそ感じる不安はあるものです。ファーストキャリアへの不安や、社会人として働く不安から就職したくないと思ってしまうことは、ある意味当たり前であり、そういうものだと割り切ることも大切ですよ。
まだまだ先だと思っていた就職が、内定をもらうことでいよいよ現実味を帯びてきます。
環境の変化に対してうまくやっていけるか不安を感じるのは当たり前です。学生から社会人になるという変化はとても大きいため、自分に自信がない人ほど大きな壁のように感じてしまいます。
納得できるまで就活を進める
就職したくない理由が、「社会人になりたくない」のではなく「内定先に就職したくない」のであれば、納得できるまで就活を進めましょう。新卒就活は基本的に人生に一度限りです。
「あのとき、もう少し企業の選考を受ければよかった」と後悔が残らないように、自分ができるところまでやり切ることをおすすめします。焦らず自分のペースで進めることが大切ですよ。
また、企業によっては欠員などが出たことにより、10月以降に秋採用を実施するところもあります。まだまだ挑戦できる機会は残されていることも多いです。
- 就活を続けても、すでに志望企業の選考は終わっていたりと、今更納得できる企業の内定をとるのは難しいと思います……。どうすれば良いですか?
「入社をしてみる」か「チャレンジを続ける」
今内定を持っている企業に入社をしたら案外自分に合っている職場だったということがあります。ただし、自分の気持ちが前向きでないとそのように感じることはできないでしょう。
どうしても諦めきれない夢や昔からなりたかった職業があるのであれば可能性がある限りチャレンジし続けてみてください。
その方が後悔が少なくなるだけでなく、行動を起こしたことによってつながる出会いが待っているはずです。
就職以外の道を選択する
内定後であっても自分のやりたいことがあるのであれば、就職をやめて、就職以外の道を選択することも1つの方法です。
就職をしてからでもできることであれば、一度就職してからスキルをつけたうえで退職する選択肢があることも忘れないでくださいね。
就活で最も大切なことは、自分が満足する形で就活を終わらせることです。人生はあなたのものです。就職以外の選択が自分にとって最適であれば、自信を持って選びましょう。
自分でタイムリミットを決めて行動できる人であれば、就職以外の道でも良いでしょう。就職以外の道が成功するとは限らないため、困ったときには就職を選ぶときが来るかもしれません。
しかし、そのタイミングが遅すぎるほど軌道修正は難しいため、ある程度タイムリミットの設定が必要です。
内定に迷う学生は以下記事で解説している判断基準を参考に、どうするべきかを考えてみてください。
内定承諾に迷う人が持つべき判断基準|NGな考え方も解説
「就職しない」という選択肢を選ぶ際に注意するべきポイント
「就職しない」という選択肢を選ぶ際に注意するべきポイント
- 一時的な感情でないか
- 自分がやるべきことややりたいことが捉えられているか
- リスクやデメリットを正しく理解できているか
メリットもデメリットも踏まえたうえで、それでも就職しないという選択肢を選ぶ人も少なからずいるかもしれませんね。そんな人は、新卒で企業に入社をしないという大きなメリットを捨てる選択をするとも言えます。
後悔をしないためにも、今から解説する「就職しない」という選択肢を選ぶ際に注意するべきポイントを押さえていきましょう。
一時的な感情でないか
「就職したくない」「〇〇がやりたい」という感情が、一時のものではないかを慎重に判断してくださいね。人の価値観は変わりゆくものです。
たとえば、高校1年生のときと大学3年生のときでは、たった数年でも考えていることや感じていることが大きく異なりますよね。
一時の感情で判断をしていないのか、立ち止まって考えることをおすすめします。
アドバイザーコメント
富岡 順子
プロフィールを見る選択を後悔しないためには自分の価値観を考えてみよう
「いっときの感情でないか」を判断するためには、自己分析を通して「就職したくない」「〇〇がやりたい」理由がどこからきているのか探してみましょう。
自己分析の中でもモチベーショングラフを用いた自己分析がおすすめです。今までの経験と、それにともなう感情をグラフ化し、振り返ることで自身の思考の癖や行動パターン、大切にしたい価値観が見えてきます。
自己分析をした結果、行動パターンとして「飽きやすい、逃げやすい」自分に気づくかもしれません。そんな自分が好きか嫌いかを見つめ直してみて、変わりたいと思うのであれば、就職という機会に「なりたい自分」に向かって一歩を踏み出してみてください。
一時的な感情に流されないためにも自己分析は必要不可欠
今感じている気持ちや興味関心は過去の経験から来ていることが大半です。「就職したくない」「〇〇がやりたい」のはなぜかを突き詰めていくと「過去のこの経験から自分はそのように感じるようになったんだな」という出来事が見えてきます。
しかし、どの経験を振り返っても特に思い当たるものがない場合は周りに流されてそう考えるようになってしまったことが考えられます。人からの情報はいっときの感情となりやすいため、自分が本当はどうありたいのか、自己分析をする中でもう少しじっくりと考えましょう。
自分がやるべきことややりたいことが捉えられているか
就職をしないということも立派な選択肢の一つです。しかし、就職をしないのであれば、これから自分が何をやりたいのか、それを実現するためにはどうするべきかを捉えておく必要があります。
たしかに、自分探しの旅のように自由な行動をすることが大切なときもあります。とはいえ、何も考えないでいると、いたずらに時間は過ぎてしまうものです。
しっかりと現実を見つめ、自分がやるべきことややりたいことが捉えられているかを考えてみましょう。
やりたいこともなく目標もないという場合、期限付きの仮の目標を立てて取り組んでみましょう。
多くの人の心理には期限のないことは無意識に先延ばしをする癖があり、これにはまさに「学生症候群」という名前がついています。
リスクやデメリットを正しく理解できているか
就職をしないという選択肢のリスクとデメリットを正しく理解できていますか。また、そのリスクやデメリットに対してどのような対策を具体的に考えていますか。
「自分ならなんとなく大丈夫だろう」と漠然とした考えや向こう見ずで無計画な考えで、就活をしない選択肢を取ってしまうといざ窮地に立たされたときに「こんなはずじゃなかった」と後悔する原因ともなりえます。
20年後などかなり先の未来を考えすぎる必要はあまりありませんが、自分が取る選択肢のリスクやデメリットを正しく理解したうえでの挑戦をしてくださいね。
アドバイザーコメント
渡部 俊和
プロフィールを見る「将来の責任を取るのは自分だけ」ということを忘れずに
先が見えない、情報が乏しい中で意思決定をするのは勇気が必要です。多くの情報があり、客観的、合理的な判断ができるのであれば良いですが、就職はそういう類のものではなく、きわめて主観的かつ個人的な「決断」を下さなくてはなりません。
たとえ親や兄弟であっても、他の誰かがあなたの将来に責任を取ってくれるわけではありません。結局、就職することもしないことも、それぞれ相応のリスクをともないます。まずその点は再認識しておいてください。
就職をしない選択をするのであれば、時間を何に使うかを考えよう
そこで「就職しない」という選択を選ぶ場合ですが、就職した人が働いている間に「自分は同じ時間を何に使うのか」については、たとえやりたいことが見つかっていなくても明確にしておきましょう。それがないと時間管理ができなくなっていきます。
就職すると時間やお金に対して制約が自動的についてきます。それをデメリットと思う人もいますが、そのおかげで生活のリズムが決まり、時間やお金の管理がしやすくなる側面もあります。体調、時間、金銭などの自己管理については、ルーズにならないよう強く意識して取り組む必要がありますよ。
就職したくないのに就活をしなければならないストレスがつらいときは、こちらの記事を参考にしてくださいね。ストレス解消法を解説しています。
就活のストレス解消法57選|悩みを根源から断ち切り楽に進める方法
就職したくないときは現状を正しく見つめ直して後悔のない選択をしよう!
ここまで解説してきたとおり、就職したくないと考える人は多くいるものです。そして、就職したくないと考える人は、そう感じる理由と、就職をしないメリット・デメリットを正しく押さえることが大切です。
就職をしない選択肢ももちろんありますが、新卒就活は非常にメリットが大きいため、慎重に判断をする必要がありますよ。
今回解説した就職するべきか迷ったときにやるべきことや、就職を前向きに捉えるコツを踏まえて、自分にとって後悔のない選択をしてくださいね。
アドバイザーコメント
隈本 稔
プロフィールを見るどの選択肢を選んでも正解が保障されているわけではない
就職したくないと悩むのは、あなただけではありません。多くの人が、これまでと大きく環境が変わってしまうことに不安を抱えています。
就職することで、これまで自由に過ごしていた時間が大幅に減り、人間関係に悩んだりすることもあるかもしれません。また、就職することを選んで頑張ったとしても、必ずしも満足のいく就職ができるとは限りません。
フリーランスや起業といった選択肢は魅力的に見えますが、会社に守られることはなく、自らの行動に責任を負わなければいけません。また、必ずしも望むように働けるわけではなく、期待通りの収入を得られるとは限りません。そこで培った経験は無駄にはなりませんが、軌道修正して就職する際にはそれなりの制限を受けてしまいます。
まさに今、自分自身について考える機会が来たと捉えよう
就職した後はもちろん、就職活動を進める中でも、自分がどういった働き方をしたいか見えてくることもあります。就職に対する不安はあるかもしれませんが、就職活動を進めながらでもいくらでも方向修正はできますよ。
これからの自分の生き方について、自分自身でしっかり考える機会が来たと思って、第三者に頼りながらでも就活といった行動をしてみることがおすすめです。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

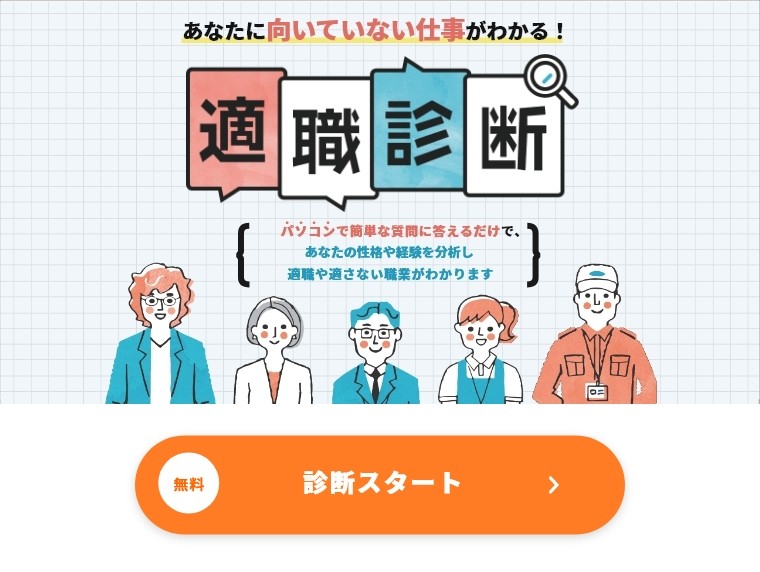





この記事にコメントしたアドバイザー
富岡 順子
コレカラボ代表 保有資格:国家資格キャリアコンサルタント(登録番号16018273)/産業カウンセラー/ワーク・ライフバランス認定コンサルタント/健康経営アドバイザー(認定番号2901967) SNS:instagram/note
続きを見る隈本 稔
職りんく運営者 保有資格:国家資格キャリアコンサルタント(登録番号19041711)/性格応用心理士1級/キャリア・デベロップメント・アドバイザー SNS:Facebook
続きを見る渡部 俊和
合同会社渡部俊和事務所代表 保有資格:国家資格キャリアコンサルタント(登録番号16029675) SNS:Facebook
続きを見る