この記事のまとめ
- 傾聴力の自己PRを作成する手順を例文付きで解説
- 傾聴力の自己PRを作るには自己分析と企業分析が必須
- 傾聴力をアピールするなら入社後にどのように活かせるかまで伝えよう
傾聴力を自己PRにしたいと思っても、なかなか完成イメージが浮かばないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。傾聴力はさまざまな仕事で求められる能力であるため、自己PRとしても十分にアピールできるスキルです。
記事では、キャリアコンサルタントの渡部さん、平井さん、田邉さん、野村さん、平野さんとともに、傾聴力の自己PRを作る方法を業界・職種別の例文付きで解説します。
また、1万人以上との面談のなかで多くの学生の自己PRを見てきた平野さん、学生から社会人まで幅広い層の就活相談を受けている野村さんからは、採用担当者が傾聴力の自己PRを評価する観点、さらに自己PRで企業とのマッチ度をアピールするコツについて、
教えてもらいました。参考に、企業が「ぜひ会いたい」と思うような魅力的な自己PRを作成しましょう。
ESや履歴書、インターン選考の自己PRを魅力的にするポイントはこちらの記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてくださいね。
【ES】
例文15選|エントリーシートの自己PRで人事を惹き込むコツを解説
【履歴書】
新卒用履歴書の自己PRを書く極意|例文28選を強み・職種別で紹介
【インターン選考】
例文18選|インターンシップ選考を勝ち抜く自己PRは5ステップで完成!
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
1位:自己PR作成ツール
自己PRが思いつかない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
2位:志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
3位:WEBテスト対策模試
模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
4位:面接回答集60選
見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました
5位:逆質問例100選
面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています
【併せて活用したい!】
スキマ時間3分でできる就活診断ツール
①適職診断
たった30秒であなたが受けない方がいい仕事がわかります
②面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
好印象を残せる自己PR「傾聴力」の作成方法
まずは、自己PRに盛り込むべき情報を把握するため、伝えたいことを整理していきましょう。ここから紹介する、自己PR「傾聴力」の作成方法を順番に進めることで傾聴力の自己PRをスムーズに組み立てられます。
就活に向けた自己PRがうまく書けない人は、以下の記事を参考にしましょう。自己PRの構成を作る方法や、初心者向けの自己PRの作成方法を30の例文とともに解説しています。
就活に向けた自己PRがうまく書けない人は、以下の記事を参考にしましょう。自己PRの構成を作る方法や、初心者向けの自己PRの作成方法を30の例文とともに解説しています。
自己PRの構成作成
自己PRの構成作成ガイド|PREP・STAR法を使う作成法を伝授
自己PRの書き方
自己PRの書き方を例文30選で紹介! 就活初心者でもわかる入門編
「傾聴力」をアピールするなら、自己PR作成ツールを活用しよう
自己PRは就活において必ずといっていいほど必要になります。自己PRが曖昧なまま就活がうまくいかなかったという就活生は多くいます。
そこで活用したいのが「自己PR作成ツール」です。これを使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
①自己分析で傾聴力を具体化する

「傾聴力」をアピールするなら、自分のどこが強みになるのか、どんなときに発揮され、どのように活かせるか、を明らかにすることが必要です。そのためには、「過去・現在・未来」で自分の傾聴力を分析する必要があります。
この作業を頭の中だけでおこなうのは難しいので、紙に自身の傾聴力の特徴を書き出して整理しながら掘り下げていくのがおすすめです。
過去の経験から傾聴力を発揮したエピソード掘り下げる方法
小学校:クラスに馴染めないでいた友人の話をじっくり聞き、友人の性格にあった具体策を出した
↓
中学校:部長として習熟度で遅れをとっているチームメイトの本音を聞き出し、個別指導の導入を提案した
↓
現在:アルバイトで新人が辞め続ける状況が続いていたため、退職者へのヒアリングをおこなって新人研修のマニュアルを作成した
↓
企業での活かし方:チームメンバーの意見を積極的に引き出し、働きやすい環境づくりに貢献したい
このように「過去・現在・未来」に沿って傾聴力を整理することで、あなたの強みが単なるスキルではなく、具体的な経験に裏付けられた個性であることをアピールできます。
さらに、自身の傾聴力を具体化するために役に立つのが「自己分析シート」です。自己分析シートを使うと、自分の強みを整理しながら掘り下げられるので、自身の客観的な魅力まで発見できます。
詳しい自己分析シートの作成方法はこちらの記事で解説しているので、併せて参考にしてみてくださいね。
②企業研究で求める人物像を見極める

自分の強みである「傾聴力」を具体化できたら、次はその強みが志望企業のニーズに合致するか調べることが必要です。この作業を欠いてしまうと企業が求める人物像から外れた自己PRができてしまう可能性もあります。
まずは企業研究をおこない、志望企業がどんな人材を欲しているのかを見極めましょう。具体的には、企業の採用ページやIR情報、社員インタビューなどをチェックして、その企業の事業内容、社風、ビジョンを深掘りします。また、志望先企業の業態、企業規模、ターゲットなどをあらゆる視点から深掘りしたり、同業他社と比較したりするのも有効です。
顧客と接点の多いサービス業や人材系の企業にとっては、傾聴力は適合性の高いスキルになります。職種では営業系全般も同様です。
意外なところでは公務員やエンジニアなども、相手の要望を的確に受け止めなければならない点で該当するといえるでしょう。
応募する職種が決まっている場合は、業務内容についても調べておくと再現性を具体的に伝えられます。「この職種のこんなところで傾聴力が活かせます」と説明するのです。職種については、厚生労働省のjobtagで調べられます。
職種の種類はこちらの記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。
自己分析だけでなく、企業研究もツールを使うことで効率的に進めることができます。詳しい方法はこちらの記事で解説しているので、併せて参考にしてみてください。
③企業の求める人物像と自分の強みが重なる点をアピールする

自己分析と企業研究が終わったら、いよいよ自己PRを作成していきます。自己分析の結果、見えてきたあなたの傾聴力という強みと、企業が求める人物像が重なる部分を見つけ、アピールしましょう。
たとえば、「お客様の声に寄り添う」という社風を掲げている企業があるとします。このような企業は「相手の気持ちを理解する力」を求めていると考えられます。一方で、あなたの傾聴力が「相手に共感し、同じ気持ちを共有する能力」であれば、志望企業のニーズとあなたの強みが結びつくのです。
このように、その企業ならではの強みをアピールすることで、企業研究をきちんとおこなっていることが伝わり、志望度の高さが伝わりやすくなります。アピールポイントを選ぶときは柔軟な視点を持ち、あなたの強みがどのように企業の課題解決に貢献できるかを具体的に考えてみましょう。
プロのアドバイザーはこう分析!説得力のある自己PRは企業の求める人物像に沿ったものである
企業はあなたの「傾聴力」そのものを求めているのではなく、その能力がもたらす「課題解決」「顧客満足度向上」といった成果を求めています。あなたの強みが、企業の求める人物像や解決したい課題と重なる部分を見つけ出すことで、より説得力のある自己PRになるのです。
私の過去の支援でも、「お客様の声に寄り添う」ことを大切にする社風の企業を志望している人がいました。そうした企業に対して、単に「傾聴力があります」と述べるだけでは不十分です。
3つの視点から経験を深掘りして企業のニーズと合致するポイントを見極めよう
そのため、「学生時代のカフェのアルバイトで、お客様の些細な声にも耳を傾け、おすすめメニューを提案し続けた結果、リピーターが2割増加しました」という具体的なエピソードを加えるようにアドバイスしました。そうすることで、「傾聴力」という抽象的な強みが、「顧客満足度向上」や「売上貢献」といった企業の求める成果に結びついていることが明確になります。
このように、傾聴力をアピールする際は、「なぜその傾聴力が身に付いたのか」「傾聴した結果何が起きたか」「誰に対して傾聴力を発揮してきたか」という3つの視点から深掘りし、あなたの強みが企業の求めるニーズとどのように重なるかを具体的に示すことが、採用担当者の心を動かす自己PRへとつながるのです。
コピペで使える自己PR文がかんたんに作れます
自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?ツールで実際に文章を作成してみてからブラッシュアップする方が効率的に受かりやすい自己PRを作成することができます。
「自己PR作成ツール」 を使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
傾聴力の自己PRを伝える3ステップ

傾聴力は「単に聞くだけのスキル」ではないため、どのように具体的に伝えられるかが選考突破のカギになります。漠然とエピソードを並べるだけでは、あなたの個性が採用担当者に伝わらず、単に「聞き上手な人」という印象で終わってしまうかもしれません。
自己PRを効果的に伝えるためには、事前に内容を整理し、論理的な構成に沿って組み立てることが重要です。そうすることで、あなたの強みが企業にとってどれほど価値があるかを明確にアピールできます。
ここでは、傾聴力の自己PRを効果的に伝えるための3つのステップを解説します。それぞれのステップがどのような役割を果たすのかを理解し、「なぜあなたの傾聴力が企業に必要なのか」を説得力を持って伝えられるように準備しましょう。
①自分の強みが傾聴力であることを簡潔に伝える

PREP法
相手にわかりやすく物事を説明する手法。Point(結論)、Reason(理由)、 Example(具体例)、Point(結論)の順番に伝える。
自己PRの冒頭では、傾聴力が強みであることを一言で明確に伝えましょう。
このとき、相手に分かりやすく物事を説明する、「PREP法」を意識するのが効果的です。PREP法を使うと、結論・理由・具体例・結論の順に言いたいことを伝えることができます。
たとえば、傾聴力の自己PRでは、「私の強みは傾聴力です。」という結論から話しましょう。これにより、採用担当者はあなたが何を伝えたいのかをすぐに理解しやすくなるのです。次に傾聴力が強みである理由と、その理由を裏付ける具体例を話し、最後に結論をもう一度伝えることが望ましいです
このように、自己PRを簡潔に伝えて採用担当者の興味を引き付け、あなたについてもっと知りたいと思ってもらうことが選考を突破するために大切です。
こちらのQ&Aでは、面接で自己PRを話す際の適切な長さについてキャリアコンサルタントが解説しています。自己PRで自身の強みとなる傾聴力を簡潔に伝えるためにも参考にしましょう。
②傾聴力を発揮したエピソードを盛り込む
次に、あなたの傾聴力が発揮された具体的なエピソードを伝えましょう。このエピソードは、傾聴力を自己PRする際の説得力を高めるための根拠となります。
単に話を聞くことが得意と述べるのではなく、どのような状況で誰に対して傾聴力を発揮し、どんな結果を得たのかを具体的に考えます。たとえば、「アルバイト先のカフェで常連顧客との会話からその日の気分を聞き出し、その要望にぴったりなドリンクをおすすめしたところ、喜んでくれた。」といったエピソードを盛り込みましょう。
このように、実体験を基にした自分にしか語ることのできないストーリーがあると、オリジナリティを持たせることができ採用担当者の印象に残りやすくなります。
ここで前述した「自己分析シート」があると、自分の過去の経験が可視化しやすくなるので、ぜひ活用してみてください。根拠となる経験を深掘りし納得感のある伝え方ができるよう、丁寧な準備をおこなっていきましょう。
③傾聴力を入社後にどう活かせるかでまとめる
最後に、傾聴力を志望企業でどのように活かすことができるかを伝えましょう。
「私には傾聴力があり、こんなときに発揮することができました」と話すだけでは、自身の強みとしての傾聴力を十分にアピールできません。
志望企業のニーズに合わせて、傾聴力をどのように活かせるかを具体的にまとめることで、採用担当者に入社後に活躍する姿をイメージしてもらいやすくなるのです。これにより、業務に活かせる力がある人材として、採用担当者へのアピールにもつながります。
たとえば、「貴社の営業職として顧客の言葉の裏にある潜在的なニーズをくみ取り、期待を超える提案をすることで、顧客満足度の向上に貢献します。」のように伝えることで、入社後どのように貢献するかまで考えていることをアピールできます。
こちらのQ&Aでは、面接でアピールポイントを効果的に伝える方法をキャリアコンサルタントが解説しています。傾聴力をさらに効果的にアピールするためにも、チェックしておきましょう。
プロのアドバイザーはこう分析!エピソードを語る際には行動+結果を盛り込むことがアピールになる
自己PRにおける「傾聴力」は、多くの学生がアピールしやすい反面、抽象的な内容にしてしまうとほかの受験者との差別化や個性の表現や納得性が難しい傾向があります。
面接官として私が注視するのは、特に②の「傾聴力を発揮したエピソードを盛り込む」ことです。ここに、傾聴によって何が変わったか(成果・影響)を具体的に盛り込むことがとても重要となります。
たとえば「相手の話を丁寧に聞いた」だけでは不十分で、「話を聞いた結果、相手の不安を軽減できた」、「チームのミスを防げた」などの行動と結果の因果関係を明確に伝えると、納得感と信頼感が生まれ相手への印象が強く残ります。
自分の傾聴力が将来どのような場面で活かせるかをリアルにイメージしてみよう
また、③の「入社後にどう活かせるか」について具体的なイメージが湧かない場合は、職種の業務を調べたうえで「顧客のニーズ把握」、「社内調整」、「後輩育成」など、傾聴力が活きる場面を想像し、自分ならどう活かすかを語ってみてください。
傾聴力とは、相手の言葉を“受け取る”力だけでなく、受け取ったうえで“意味づけし行動につなげる”力でもあると伝えることができれば、面接官に深い印象を残せます。
自己PRに時間制限や文字数の指定があるという人は、ポイントをこちらの記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてくださいね。
【面接での時間制限】
例文12選|1分の自己PRで魅力を伝え切る必勝法
【文字数制限】
例文20選|400字の自己PRで人事の心を掴む戦略
テンプレを活用すれば受かる自己PR文が作れます
自己PRのネタを決めても、それを裏付けるエピソードに悩む学生は多いです。しかし、特別なエピソードがなくても受かる自己PRを作ることはできます。
そこで紹介したいのが「自己PR作成ツール」です。自己PR作成ツールなら、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、分かりやすいテンプレであなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
(リーダーシップが強みの場合)
業界・職種別! 傾聴力をアピールする自己PR例文11選
業界・職種別! 傾聴力をアピールする自己PR例文11選
ここまで、「傾聴力」の自己PR作成の手順と、傾聴力の自己PRを伝える3ステップを解説してきました。
ここからは、傾聴力をアピールする自己PRの例文11選を紹介します。業界・職種別に具体的な内容を盛り込んでいるので、どのように自分ならではのエピソードを組み込むか、自身の傾聴力をどこに活かせるかを考えながら確認してみてください。
例文①「IT業界」の自己PR例文
例文①「IT業界」の自己PR例文
私の強みは、相手の潜在的なニーズをくみ取り、最適な解決策を提案する傾聴力です。
私は大学でWebサイト制作を学んでいます。そこで先日、親戚が経営している飲食店から「お店のメニューや雰囲気が伝わるWebサイトを作りたい」という相談を受けました。
最初は「おしゃれでかっこいいデザインにしてほしい」という漠然とした要望でしたが、私はまず「どのような層の顧客に来てほしいか」「お店のどのような点を一番アピールしたいか」など、具体的な質問を重ねていきました。
すると、親戚自身も気付いていなかった「写真よりも文字で料理へのこだわりを伝えたい」「スマホで見たときに予約がしやすいようにしたい」という本質的なニーズが見えてきたのです。
そこで、料理へのこだわりを詳細に記載できるデザインや、スマートフォンでの操作性を高めるUIを提案したところ、「想像以上の仕上がりだ」と非常に喜んでもらえました。
この経験から、相手の真のニーズを引き出すことの重要性を学びました。この傾聴力を活かし、御社では顧客の潜在的な課題を深く理解することで、顧客の期待を超えるソリューションを提供し、貴社のサービス拡大に貢献します。
上記の例文は、漠然とした要望から具体的な質問を重ねることで、潜在的なニーズを引き出し、期待以上の成果につなげたプロセスが明確です。
具体的なエピソードで傾聴力と問題解決能力が示されており、入社後の活躍がイメージできます。
例文②「金融業界」の自己PR例文
例文②「金融業界」の自己PR例文
私の強みは、相手の言葉の裏にある「本音」を汲み取り、深い信頼関係を築ける力です。
私は個別指導塾のチューターとしてアルバイトをしています。生徒はそれぞれ異なる学習目標や進路の悩みを抱えていますが、多くの生徒は表面的な質問しかしてきません。
しかし、私は「この生徒は本当に何に悩んでいるのだろう」という関心を持って、日々の雑談から積極的にコミュニケーションを取ることを心がけています。
すると、ある生徒が「親には言えないけど、将来やりたいことがあって、今の成績では無理かもしれない」という本音を打ち明けてくれたことがありました。私はその思いに共感し、一緒に具体的な学習計画を立てたことで、生徒は目標に向けて意欲的に取り組むようになり、成績も大幅に向上しました。
この経験から、相手の本音に耳を傾け、心に寄り添うことの重要性を学びました。貴社では、顧客の将来に対する漠然とした不安や悩みを丁寧に引き出し、信頼関係を築くことで顧客一人ひとりに最適な金融商品を提案し、安心した未来の実現に貢献したいです。
この自己PRの良い点は、「相手の本音を汲み取る力」という、人の気持ちに寄り添いながら課題を解決していく力を、具体的な行動と成果で示しているところです。
金融業界で重視される“信頼関係の構築力”や“傾聴力”を自然に伝えており、顧客対応に直結する強みとして説得力があります。
例文③「食品業界」の自己PR例文
例文③「食品業界」の自己PR例文
私の強みは、顧客の声を深く汲み取り、期待を超える商品やサービスを提案できることです。
私は大学時代、カフェでアルバイトをしていました。顧客から「アレルギー対応のメニューはないか」「甘さ控えめのドリンクがほしい」といったご要望をいただくことが多かったため、私は単にご要望を聞くだけではなく、「なぜそのメニューを求めているのか」といった背景まで丁寧に伺うように心がけました。
ある日、乳製品アレルギーをお持ちの顧客から「家族みんなで楽しめるケーキがほしい」と相談されたことがあります。その言葉の裏には、「みんなと一緒においしいものを食べたい」という切実な願いがあると感じました。
そこで、社内でアレルギー対応のレシピを提案し、見た目や味にもこだわった特別ケーキの企画を立てたところ、顧客に喜んでいただけたのです。
この経験から、表面的なニーズだけではなく、その裏にある思いを理解することの重要性を学びました。この傾聴力を活かし、貴社では顧客の声を商品開発やマーケティングに反映させ、より多くの食卓に笑顔を届けたいです。
上記の例文は、顧客の「切実な願い」という潜在的な思いを深く汲み取り、アレルギーに対応できるケーキという具体的な解決策を企画・実行した点が秀逸です。
単なる要望対応ではなく、商品開発への意欲と食卓に笑顔を届けたいという想いが伝わります。
例文④「広告・出版業界」の自己PR例文
例文④「広告・出版業界」の自己PR例文
私の強みは、日常会話から社会の潜在的なニーズやトレンドを読み解く傾聴力です。
私は大学で社会学を専攻していて、ゼミの課題で「若者の消費行動」について研究していました。一般的なアンケート調査に加えて、友人や知人との何気ない会話に耳を傾け、彼らが「何に面白さを感じているのか」「なぜそれを買うのか」といった背景を深く掘り下げていきました。
すると、多くの人が「有名人やインフルエンサーが使っているから」という表面的な理由だけではなく、「限定品であることの希少性」や「その商品を通じて得られる他者との共感」といった潜在的な価値を重視していることがわかったのです。
この発見を論文にまとめたところ、教授から「データだけでは見えない、人の感情に迫る分析ができている」と高い評価をいただきました。この経験から、人の声の裏に隠された本質的なニーズをくみ取る重要性を学びました。
貴社ではこの傾聴力を活かし、世の中のニーズやトレンドを的確にとらえることで、人の心を動かすような企画やコンテンツを生み出し、社会に新しい価値を届けることに貢献したいです。
この自己PRの良い点は、社会学的な視点を活かして「データでは見えない人の感情」を読み取っているところです。
広告・出版業界に求められる“共感を生む洞察力”を、実体験と成果を交えて具体的に表現しており、説得力のある内容になっています。
例文⑤「商社業界」の自己PR例文
例文⑤「商社業界」の自己PR例文
私の強みは、さまざまな人の声に耳を傾け、異なる意見を調整して最適な解決策を導き出す力です。
私は大学時代、国際交流サークルでイベントリーダーを務めていたのですが、異なる国籍や文化を持つ人が参加するため、1つの意見だけで企画を進めると、不満を持つ参加者が出てしまうことがありました。
そこで、私は企画会議の前に各国の代表者と個別に話す時間を設け、それぞれの意見や文化背景、イベントに期待することを丁寧にヒアリングするようにしたのです。
たとえば、ある国の参加者が「伝統的なダンスを披露したい」と言った場合、ただ演目として加えるだけではなく、その背景にある「自国の文化を深く知ってほしい」という要望を汲み取り、演目の前にその文化の歴史や意味を解説する時間を設けることを提案しました。
これにより、参加者全員がイベントに一体感を持って楽しむことができ、結果として例年以上に多くの参加者から「心に残るイベントだった」という感想をいただいたのです。
この経験から、異なる立場や文化を持つ人の声に深く耳を傾け、全員が納得できる解決策を探ることの重要性を学びました。貴社に入社後は、この傾聴力を活かして多様なステークホルダーと強固な信頼関係を築き、グローバルなビジネスの成功に貢献したいと考えています。
上記の例文は、国際交流サークルという多様な環境で、個別のヒアリングを通じて異なる文化背景や期待を深く理解し、全員が納得できる調整力を発揮した点が素晴らしいです。
商社で求められる多様なステークホルダーとの信頼構築力が伝わる説得力のある内容です。
例文⑥サービス職
例文⑥サービス職
私の強みは、顧客の潜在的なニーズを深く引き出し、最適な解決策を提案できる力です。
私はメガネショップでアルバイトをしていて、多くの顧客が「何を基準にメガネを選べば良いかわからない」という悩みを抱えていることに気付きました。
そこで、私は単にデザインの好みを聞くだけではなく、「どんなシーンで使いたいか」「どんな自分に見られたいか」 といった質問を重ねました。その結果、顧客自身も気付いていなかった「本当に必要なメガネ」を見つけることができたのです。
この経験から、顧客の話を傾聴したうえで、一歩踏み込んで本質的なニーズを引き出すことが、顧客満足につながることを学びました。
この傾聴力を活かし、御社では顧客一人ひとりに心から寄り添い、期待を超える体験を提供できる店舗スタッフを目指したいです。
この例は店舗スタッフ志望ですが、顧客やクライアントが何に困っているのかを考えて選択基準を整理し、少しずつ提示していたというところは、営業職で言う「ソリューション営業」の考え方に近いです。あらゆる職種で応用できる行動です。
例文⑦営業職
例文⑦営業職
私の強みは、相手が話しやすい環境を作り、心を開いて悩みを打ち明けてもらう傾聴力です。
私は大学の取り組みの一環で、悩みを抱える新入生の話を聞いて不安を解消したり、サポートをする活動に参加しています。
毎年多くの新入生が話をしに来てくれるのですが、そうして悩みを聞いていくうちに学んだことが、「相手の目を見て話を聞くこと、話を遮らないこと、あいづちは少し大袈裟にすること、まず肯定すること」の重要性です。
そうすると、話し手は「ちゃんと聞いてもらえている」「共感してくれている」という安心感を持って話してくれるので、より深い悩みを打ち明けてくれるようになるということを体験を通じて理解することができました。
また、この学びを普段の何気ない会話でも意識してみると、周りの人からは「聞き上手だね」「相談しやすい」と言ってもらえることがとても多くなり、それから自身の強みは傾聴力であると自覚するようになりました。
この活動を通して培った傾聴力を活かし、御社に入社後はクライアントの悩みを引き出して的確な解決方法を提案し、営業職として売り上げに貢献いたします。
傾聴力をどのように習得したか、具体的にどのように実践しているか、結果としてどんな変化が起きたかがわかる良い自己PRですね。営業職での活かし方も成果につなげられることがイメージできます。
例文⑧事務職
例文⑧事務職
私の強みは、常に現状をアップデートしていく力です。
私は大学の図書館でアルバイトをしており、利用者のサポートや事務作業を担っています。基本的には同じような作業が多く、単調な仕事をミスなく確実におこなうことがもとめられるのですが、それと同時に何かもっと改善できる部分はないかを観察するようにしています。
私の大学の図書館は学生の他に地域の方の利用者も多く、年配の方との世間話の延長で「この図書館は園芸書のコーナーが遠い」という声を聞きました。学生のためにある図書館なので、年配の方向けの本は入り口付近にあまり置いていなかったのです。
この言葉を受け、管理者に地域の方向けの本をもう少し入り口付近に置きたいと提案をしたところ、試験的に提案が採用されることになりました。それからは地域の方がより利用しやすい配置になり、「本が探しやすくなった」という声をいただく機会も増えました。
この経験を活かし、事務職として現場の声に耳を傾けながら、従業員がより働きやすくなるようにサポートをしてまいります。
傾聴力がアピールしづらい事務職ですが、「営業職など他の職種と協働する」という特徴をきちんと押さえられている好印象な自己PRです。仕事内容だけでなく仕事の仕方をリサーチすることの重要性がわかる良い例ですね。
例文⑨企画職
例文⑨企画職
私の強みは、寄せられる悩みの共通項を見つけ、多くの人の課題を解決する力です。
私は大学の学生課で学生をサポートする活動をおこなっています。
地方から上京した新入生の大半が口にするのが「家具への出費が痛い」という悩みでした。一方で、就職に際して引越しをする4年生は「捨てるのはもったいないけど、引越し費用がかさむから手放したい」「お金を出してゴミを捨てるのはばかばかしい」という悩みを口にしていました。
そこで、双方の悩みを解決するために学生課のサイト内に学生同士が不要なものを譲り合うことができる窓口を立ち上げました。
サイトを利用してくれる学生は徐々に増え、今では活発にやり取りがおこなわれています。「無駄な出費をしなくて済んだ」「無料で使いやすい家具が手に入って嬉しい」などの声も寄せられ、サイトを作って良かったと感じています。
御社に入社後はこの能力を活かし、より多くの人の意見を自分の中に落とし込んで解決に導くような商品企画をしてまいります。
それぞれの悩みに当事者感覚で向き合い、実社会にもあるようなサービスを学内向けに提供する過程で、サイトを立ち上げるという労力とリスク(犠牲)も払っています。行動につながっている実践的なエピソードなので説得力があります。
例文⑩エンジニア
例文⑩エンジニア
私の強みは、課題となりそうなことを見逃さず先回りして対処する力です。
私はこれまで大学の軽音楽サークルで活動していました。特に私が所属していたバンドは音楽に対する熱量が高く、経験者だけで組んだバンドで、可能な限り全員で集まって練習をするというやり方が基本になっていました。
しかし、あるときからメンバーのうちの1人の演奏に一体感がなくなってきていることに気が付きました。顔色も良くなく、何かあったのだろうと思い2人で話す機会を設けました。
話を聞くと、「金銭的に余裕がなくバイトを増やしたので、睡眠時間を削って練習に参加している」とのことでした。
このままでは体調を崩してしまう可能性もあると感じ、月に3回は全員で集まる日を設けそれ以外の日は参加が可能なメンバーだけが集まったり個人練習ができる日にした方が技術を高められるのでは、と提案をしました。
みんな快く提案を受け入れてくれ、それからはメンバーの時間が確保しやすくなり、それぞれのスキルも、チームの雰囲気にも良い影響を出す結果となりました。
この経験を活かし、プログラムの穴を見逃さないことはもちろん、周りのメンバーのフォローも率先してできるエンジニアとして、業務に貢献してまいります。
わかりやすいです。マンツーマンで話をして、本当の悩みが聞き出せた経験ですね。何かあったのかと気づく観察力も、素晴らしいです。せっかくの経験なので、メンバーフォローだけでなく、顧客やクライアントへのヒアリングにも使えることに触れても良いでしょう。
例文⑪クリエイティブ職
例文⑪クリエイティブ職
私の強みは、1つの要望を深掘りして考え、顧客の潜在的なニーズを察する能力です。
私は現在花屋でアルバイトをしており、少し前からフラワーアレンジメントについて教えてもらえるようになりました。ギフト用ブーケの作成依頼がきた時、私もその要望を教えてもらい先輩と一緒に試作としてブーケを作っています。
お客様の要望は抽象的な表現が多く、「可愛い感じに」「男の子でも喜んでもらえるように」「黄色いお花を使ってお誕生日用に」などの大まかな注文が大半です。
そこから自分なりのフラワーアレンジを考えお客様に喜んでもらうには、端的な要望をいかに深掘りして考えられるかが重要です。お花を贈る相手の好きな色もわからないときがあるので、ご本人の写真を見せていただいたり、どんな人かを聞いたり、ご来店いただいた送り主様の雰囲気から考えることもあります。
始めは深掘りの方法がわからずうまくいかなかったのですが、コツを掴むと要望を聞いた時点でぼんやりとお花のイメージができるようになりました。まだお客様の手に渡るブーケは作ったことがありませんが、先輩には「個性が出ていて素敵なブーケを作れるようになってきている」と褒めていただきました。
この経験を活かし、御社に入社後はクライアントの要望を自分の中に落とし込み、要望以上のデザインを提案できるデザイナーとして活躍いたします。
デザイナーの仕事とアルバイトの共通点をきちんと理解し、強みとしてアピールできている好印象な自己PRです。傾聴力だけでなく、仕事に前向きに取り組む姿勢も伝わるため、入社後の活躍が期待できることも好印象ですね。
自己PRが思いつかない人は、ChatGPTを活用して自己PRを完成させよう
ChatGPTを使った自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?
簡単な質問に答えていくだけでChatGPTが自動で魅力的な自己PRを作成します。
作った自己PRは選考で活用できるものになっているので、ぜひ活用して採用される自己PRを完成させましょう。
そもそも傾聴力ってどんな力?
そもそも傾聴力とは何か、深く理解できているでしょうか。ここを理解できていなければ、論点がずれて企業相手に刺さる内容にはなりません。
傾聴力とは、相手の気持ちに共感しながら話を聞き、相手の言葉の背景にある感情や意図まで深く理解できる力のことです。
たとえば、相手が抱える悩みや本音を引き出すには、話しやすい雰囲気を作るための共感やあいづち、そして相手への深い関心が必要となります。傾聴力は、相手と良い人間関係を築くための重要なスキルであり、ビジネスシーンでも高く評価される能力なのです。
まずは、以下の傾聴力がある人の特徴に目を通して、自身にどのような傾聴力が備わっているかを確認してみましょう。これによって、自身が持つ傾聴力を具体的に把握し、自己PRに活かすべきポイントが明確になります。
傾聴力がある人の特徴
- 高い共感性を持ち合わせている
- あいづちが上手い
- 相手の本音を引き出すことができる
- 相談役に回ることが多い
これらのうち、自身に当てはまるものが多い人は、無意識のうちに傾聴力を発揮している可能性があります。このように傾聴力を深掘りしたうえで自己PRでアピールすることで、あなたの強みをより効果的に伝えられます。
プロのアドバイザーはこう分析!人への興味や関心も「傾聴力のある人」の特徴の一つ
傾聴力が高い人は、相手に関心を持っている人が多い傾向にあります。そのため、会話している相手について「この人はどんな人だろう」と興味の湧く人は、傾聴力が高いと言えるでしょう。
話し手への興味がより深い理解につながる
相手に関心を持つと、相手を理解しようとしますよね。そういう人は途中で話
を遮ることがありませんし、無理やりに話の主導権を握ったりもしません。
よくあるのが、相手が話したことを受けて「そうそう、私も同じことがあって……」と、自分の話題にもっていくパターンです。これは一見相手の話を聞いて発展させているように見えますが、結局は自分のことを話し、相手の話を聞いていないケースが多いです。
また、相手を理解しようとする人は、わからないところは臆せず質問して、理解しようとします。だからこそ傾聴力の高い人は一度で理解できなかったことはそのままにせず質問し、相手の話を自分なりに理解して会話を終了する傾向にあります。
こちらのQ&Aでは、就活の自己PRで傾聴力をアピールしても良いのかについて、キャリアコンサルタントが解説しています。自己PRとして傾聴力をアピールするか悩んでいる人は、参考にしましょう。
こちらのQ&Aでは、傾聴力が短所になる可能性についてキャリアコンサルタントが解説しています。自身の傾聴力をネガティブにとらえられないようにするためにも、目を通しておきましょう。
傾聴力が自分の強みな人は以下の記事を参考にしてみてください。人の話を聞く仕事を詳しく解説しています。
傾聴力があり、相手の話を根気強く聞くことができるという人は、次の記事も併せて読んでみてください。心理カウンセラーに向いている人の特徴を紹介しています。
傾聴力の自己PRを作成する際の注意点
傾聴力の自己PRを作成する際の注意点
- 志望企業のニーズと食い違っていないか
- 聞き上手なだけのアピールになっていないか
- ありきたりな内容になっていないか
- 「自主性がない」という印象になっていないか
傾聴力の自己PRを考えるうえでは、避けておきたい注意点もあります。単に聞き上手であるとをアピールをしても、入社後に成果を上げるための具体的な強みとしては認識しづらいです。
ここでは、傾聴力の自己PRを作成する際の3つの注意点を解説します。これらの点を意識してリスクを回避し、気を抜かずに対策をしましょう。注意点にも目を通すことで、あなたの傾聴力を最大限にアピールできる自己PRになります。
自己PRの書き出しについてはこちらの記事で解説しているので、併せて参考にしてみてくださいね。
志望企業のニーズと食い違っていないか
傾聴力の自己PRを作成しても、企業が欲している人物像にマッチしていなければ魅力は激減してしまいます。
たとえば、1人で黙々と作業をこなす仕事が多い企業に対し、「私の強みは傾聴力です。相手の声に耳を傾け、適切な提案をすることができます」とアピールするのはニーズにマッチしているとは言えません。
このように、企業が求める人物像を理解せずに自己PRを作成すると、自身の強みと企業のニーズが結びつきません。そのため、企業研究を徹底的におこない、その企業がどのような傾聴力を求めているのかを見極めましょう。
- 自己PRで傾聴力をアピールしたいのですが、志望する企業が1人で黙々と作業することが多い職種の場合は、どのようにアピールすれば良いですか?
個人的な作業が多い仕事は「信頼関係を構築する能力」をアピールしよう
就職するということは、少なからず人とのかかわりが生まれますよね。仕事自体は1人であっても、上司や同僚とのコミュニケーションも発生します。このときに、良い関係性が築けていると雰囲気が良くなり、チーム全体の士気向上につながります。
そのため、「傾聴力を活かして社内での信頼関係構築に役立てる」というアピールは企業にとって魅力的な強みになります。必ずしも直接的な仕事だけでなく、仕事のプロセスや組織風土に貢献できないかどうかも考えてみましょう。
聞き上手なだけのアピールになっていないか
傾聴力の自己PRを作成する際は、ただ聞き上手なだけのアピールになっていないか確認しましょう。
たとえば「私は人の話を聞くことが得意です。適切な相槌やリアクションを取ることができます」だけで終わってしまえば、単に聞き上手なことだけをアピールしただけに留まってしまい、「それをどう活かしてくれるのか」と企業は疑問に感じたまま終わってしまいます。
傾聴力の自己PRでは、傾聴力を活かしてどんなことができるのかという点を伝えることが重要です。これにより、聞き上手という受け身な印象を払拭し、傾聴力があなたの強みとして、企業に貢献できる能力であることを説得力を持ってアピールできます。
ありきたりな内容になっていないか
傾聴力は多くの学生がアピールするテーマのため、内容がありきたりだと採用担当者の印象に残りづらくなってしまいます。ほかの学生と差別化するには、あなただけのオリジナリティを盛り込むことが大切です。
たとえば、「サークル活動で友人の話を聞いた」というエピソードは一般的ですが、そこから一歩踏み込んで、「その話を聞いた結果、チームの練習方法を改善し、大会で優勝できた」といった具体的な成果を伝えることで、独自の強みとしてアピールできます。
あなたにしか語れない経験や、その経験から得た学びを具体的に盛り込んで、あなただけの傾聴力の自己PRを作りましょう。
- 傾聴力を発揮したエピソードはいくつかあるのですが、大きな成果を上げていたり、インパクトのある派手なエピソードではありません。日常的な話題でも問題はないでしょうか?
派手なエピソードがなくても入社後に活かせることをアピールできれば良い
傾聴力での自己PRのエピソードは「相手の話に深く耳を傾けられるかどうか」が伝わる内容であるかがカギなので、日常的かつ個人的な内容でも問題ありません。
誰か1人との関係性が大きく変わったなど、実際に変化が起きていることがあればそれを伝えましょう。
これまでは印象に残るような成果を上げられる環境ではなかったかもしれませんが、実際に仕事の場面でも場に応じた傾聴力が自然に発揮できるとしたら、今度はそれは成果になって残ることになるわけです。
相手や環境が変わっても再現できる傾聴力が伝えられれば良いと考えましょう。
「自主性がない」という印象になっていないか
傾聴力は、人の話を聞き、それに共感しながら相手に寄り添うためのスキルです。しかし、「相手の話を聞くのが得意」と伝えるだけでは、自主性がない印象を採用担当者に与えてしまうリスクがあります。
あなたの主体性を判断してもらうためには、傾聴力を発揮したあとどのように行動したかを明確に伝えましょう。たとえば、「友人の悩みを聞いたうえで、一緒に解決策を考えた」「顧客の意見を聞くだけではなく、それをもとに新商品のアイデアを企画した」といったエピソードを盛り込むことが大切です。
傾聴力を単なる聞く力ではなく、問題解決や目標達成のための最初の行動としてアピールすることで、自主的に考え、行動できる人材であることを伝えましょう。
「話す」と比べると「聞く」は受け身の行動と思われがちです。傾聴力=受け身・自主性がない、との印象を持たれないためには、「なんのために傾聴力を発揮したのか」「傾聴力を発揮した結果何が変わったか」を盛り込むようにしましょう。
プロのアドバイザーならこうアドバイス!目に見えづらい長所だからこそエピソードの掘り下げが大切
客観的に傾聴力を説明するのはそもそも難しいです。「傾聴」という行為だけを見れば、きちんと聴けているかどうかは定量化もできませんし、話し手がどう感じているのかも明確には検証ができないからです。
内面的な要素に説得力を持たせるだけの材料がどうしても必要になりますが、それは変化や行動にどうつながったか、という目に見える部分をエピソードで書き出すことで形になります。個人的体験はその人固有のものなので、それを具体的に掘り下げていけば、必ず他の人との差別化になります。
誰かのためにリスクを負った経験があるかどうかを考えてみよう
また、傾聴力が身についている人は相手が感じていることを自分のことのように感じて(共感)、当事者感覚で対処しようとする傾向があります。
具体的な行動がなかなか思いつかなければ、相手のために行動した経験がないか、その際にどのような犠牲を払ったか、リスクを負ったか、というように自問自答してみてください。
自己PRで悩んだらまずは作成ツールを使ってみよう!
「自己PRがうまく書けない」「どんな強みをアピールすればいいかわからない」…そんな悩みを抱えている方には「AI自己PR作成ツール」がおすすめです。
AIがあなたの経験やスキルに基づいて魅力的な自己PRを自動で生成し、短時間で書き上げるサポートをします。
短時間で、分かりやすく自分をアピールできる自己PRを完成させましょう。
これだけは避けたい! 傾聴力の自己PRのNG例文
これだけは避けたい! 傾聴力の自己PRのNG例文
- NG例文:志望企業のニーズと食い違っている
- NG例文:聞き上手なだけのアピールになっている
- NG例文:自主性がない印象になっている
次に、NG例文の紹介です。注意点として挙げたポイントが意識されていない内容になっているので、具体的にどんな自己PRがマイナスな印象になってしまう可能性があるのかをイメージし、自分の自己PRが同じようなものになっていないかを確認してみてください。
NG例文:志望企業のニーズと食い違っている
NG例文:志望企業のニーズと食い違っている
私の強みは、もとめるものを察して柔軟に課題を解決するため、相手の視点に立ち密なコミュニケーションを取る能力です。
私は大学のボランティアサークルに所属しています。月に2回ほど地域の保育園に赴き、子どもたちと遊んだり話をして交流を深める活動をおこなっています。
そこに、いつも遊びに誘っても応じてくれず、1人でいる子がいました。なんと声をかけても輪に入ろうとしないその子のことがずっと気になっていました。
何度目かにその保育園に行った時、その子が虫の図鑑を読んでいることがありました。「虫が好きなの?」と声をかけてみたのですが、あまり反応がありませんでした。そこで、自分も同じように虫が好きなつもりになり、興味を持っていろいろと聞いてみました。
すると、次第にその子が活き活きと虫について話してくれるようになり、明るい面を見せてくれるようになりました。
距離が縮まったので、どうして他の子と遊ばないのかと聞いてみると、外で遊ぶより静かに本を読んでいるのが好きなのだと教えてくれました。
それからは無理に誘うことはせず、同じように室内で静かに遊んでいる子と引き合わせたり、本や図鑑についての話をしたりしていると、次第にその子の方から私に話しかけてくれるようになったのです。
この経験から、まず相手と同じ視点に立ち、密なコミュニケーションを取ることで課題を解決する能力が身につきました。先日御社の説明会では募集されているシステムエンジニア職では他者と頻繁にコミュニケーションを取ることは少ないとお聞きしていますが、自分の良さを活かして頑張ります。
エピソードそのものは悪くないのですが、会社が説明会で話していることとの整合性が取れていないようです。何らかのコミュニケーション能力自体は必ずもとめられているはずなので、最後の部分は方向性を合わせた表現にしましょう。
NG例文:聞き上手なだけのアピールになっている
NG例文:聞き上手なだけのアピールになっている
私の強みは、傾聴力です。
私には大学生になってから知り合い、仲良くなった友人がいます。今ではいつも一緒にいて、何でも打ち明けることのできる仲ですが、始めは「あまり気が合わないかも」と感じていました。友人は派手な見た目をしているので、近寄りにくく感じていたのです。
しかし、ゼミのグループ研究で同じ班になり、コミュニケーションを取る必要が出てきました。力を合わせて研究をするのだから仲良くなりたいと思い、ランチに誘ったことがあります。
友人は話すのが大好きで、ランチの間はずっと楽しそうに話してくれました。私はそれに合わせて相手と同じ気持ちであいづちを打ち、共感を示しました。すると「すごく話しやすくて楽しかった」と言ってくれて、それからはよく一緒にランチをしたり遊びに行く仲になりました。
この傾聴力を活かし、御社に入社後は多くの人の声に耳を傾けて会社に貢献してまいります。
傾聴力の発揮の仕方はよくわかります。しかしこれでは「聞き上手」ということのアピールにとどまってしまっているので、仲良くなった結果、本来の目的であるゼミのグループ研究の成果にどんな影響があったかまでを書きましょう。
そうすることで、傾聴力を発揮した結果、成果を出すことにつながったというアピールになります。
NG例文:自主性がない印象になっている
NG例文:「自主性がない」という印象になっている
私の強みは、相手の本音を引き出し課題に対する多くの声を収集する力です。
私はファミリーレストランでアルバイトをしており、以前からホールスタッフの動線について課題を感じていました。スペースが狭いということもあり、スムーズに行き来することができず、ときにはぶつかって料理を落としてしまうということもありました。
繁忙時にこういったことがあるとかなりのタイムロスになってしまうので、効率を上げるため誰がどこまでのテーブルを対応するかなどのポジショニングを明確にしたり、オーダーをとったあとのフローやキッチンから料理を受け取ったあとの対応をマニュアル化しようと考えました。
まずは一人ひとりと面談の時間を設け、どのようになったら動きやすいかのヒアリングを実施しました。すると建設的な意見がとても多く、どれも採用したい気持ちがありうまくまとめることができませんでした。
結果としてマニュアルを作ることはできませんでしたが、この経験から自分には相手の本音を引き出す力があると感じ、御社に入社後も積極的に対話の機会を作り、クライアントとより良い関係を築いていけるよう尽力してまいります。
この例文では、周囲の意見に流されて自分の業務を遂行できなかったという印象を受けます。また、「面談時間を設けた」「ヒアリングを実施した」としか書かれていないため、傾聴力の高さが残念ながら伝わりにくくなってしまっています。
どのようなことを意識してヒアリングをしたかを具体化すると、傾聴力があることをアピールできますよ。
就活のプロに聞いた! 傾聴力を自己PRの題材にするときのポイント
ここまで傾聴力の自己PRの例文を紹介してきましたが、「そもそも企業は傾聴力をどのように評価しているのか」「ほかの学生との差別化はどうすればいいのか」といった疑問を抱えている人もいるのではないでしょうか。
また、採用担当者の視点からどのようなポイントが見られているのかを把握し、より効果的な自己PRを作成したいと考える人もいるかもしれません。
そこでここからは、多くの学生を支援し、採用現場にも詳しいキャリアコンサルタントに、傾聴力を自己PRの題材にする際のポイントを聞きました。プロの視点から見た効果的なアピール方法を参考にして、選考に活かしていきましょう。
こちらのQ&Aでは面接で自己PRと長所を効果的に伝える方法について、キャリアコンサルタントが解説しています。長所が複数ある場合の対処法も解説しているので、参考にしてみてください。
どの職種でも好印象を残しやすいのでおすすめ
傾聴力は人間関係を良好にするうえで大きな力を発揮してくれるスキルです。最近は在宅ワークを導入する企業が増えていますが、人と接することがまったくない職種はほとんどありません。
そのため、対人コミュニケーションにおいて効果的に働く傾聴力については、どの職種でアピールしても好印象を抱いてもらえる場合が多いです。
また、聞く力がある人は「理解力がある」「聞き洩らしがなく、ミスが少ない」というイメージを抱いてもらえることもあります。
これらの素質があると、顧客やクライアントの話によく耳を傾けることができ、ビジネスシーンでは頼もしい人材になり得るので、企業から歓迎される可能性が高く、自己PRを作成するうえではとてもおすすめのテーマです。
企業は、傾聴力をアピールする学生に対して「人間関係の構築が得意であること」を期待しています。
仕事をするうえで、社内外での信頼関係はとても重要なので、傾聴力を魅力的に自己PRできれば高評価が狙えるでしょう。
人気テーマのため差別化が必須!
自己PRで「傾聴力」をテーマにする場合は、差別化が必須です。どの職種でアピールをしてもマイナスと捉えられることが少ないため、自己PRの題材に選ばれやすく、独自性に欠ける内容では採用担当者の印象に残りづらくなってしまいます。
そのため、自分の実体験をもとに過去に傾聴力を発揮したエピソードや傾聴力を身につけたエピソードを盛り込んで、オリジナリティを持たせることが重要です。
プロのアドバイザーはこう分析!あらゆる企業で「人の話に耳を傾ける」スキルは必要とされている
人はどちらかと言えば自分のことを話したがるものであり、その根底には「承認欲求」というものがあります。この欲求は視点を変えれば欠乏欲求でもあるので、誰もが自分の話に耳を傾けて聴いてもらえるということに飢えていると言えます。
相手の話にしっかりと耳を傾けることができるスキルは稀少なうえに、お金や物を使わなくとも相手を喜ばせることができるので、社内においては同僚や先輩方と、社外に対しては顧客や取引先と、リスクなしに良い関係性を築ける可能性が高いということです。
それはあらゆる仕事において有効な強みなので、業種や職種を問わず好印象を感じられる要素になっています。
「聞く」と「聴く」の違いを意識して傾聴力をアピールしよう
そうしたことを踏まえて、傾聴に使われている「聴く」という文字の意味が、単に「音や声が耳に入ってくる」という意味の「聞く」と違い、「相手の言葉を理解しようと意識的に耳を傾ける」という意味であることをよく理解して自己PRを作ってください。
この区別が感じられないような浅い内容だと「傾聴力」とは見なされないことがあります。
本当に人の話を「聴く」ことができる人材であれば知識の吸収も早いでしょうし、階層に関係なく円滑なコミュニケーションの接点として期待がかかります。
傾聴力+αでアピール! 傾聴力と相性の良い強みを例文付きで紹介
傾聴力は多くの学生が自己PRに用いる人気のテーマだからこそ、ほかの就活生と差別化するための工夫が必要です。そこで効果的なのが、傾聴力と相性の良い別の強みを組み合わせる「傾聴力+α」のアピールです。
傾聴力と別の強みを掛け合わせることで、あなたの強みがより具体的になり、採用担当者へのアピール力を高められます。
ここでは、傾聴力と組み合わせることでさらに魅力が増す4つの強みを紹介します。それぞれの強みが傾聴力とどう結びつくのか、具体的な例文とあわせて確認し、あなただけのオリジナルな自己PRを作成する参考にしましょう。
こちらのQ&Aでは、ESにおける自己PRの書き方について、キャリアコンサルタントが解説しています。ESの自己PRで傾聴力をアピールしたい人は、参考にしましょう。
課題解決能力
課題解決能力とは、現状の問題を正確に把握し、その原因を分析したうえで、最適な解決策を立てて実行する力のことです。この能力が高い人は、単に目の前の問題を片づけるだけではなく、根本的な原因にアプローチすることで、再発まで防ぐことができます。
そして、この課題解決の第一歩となるのが傾聴力です。なぜなら、問題の本質を見つけるためには、まず関係者の声に耳を傾け、表面的な不満や意見の裏に隠された真の原因をくみ取る必要があるからです。
傾聴によって得られた情報は、単なる個人的な意見ではなく、課題解決の方向性を示す重要なヒントとなります。
傾聴力+課題解決力の自己PRを作るなら、傾聴力がどのように課題解決につながるのかを明確に伝えることで、説得力が高まります。以下の例文も参考にしたうえで、自己PRを作成してみてください。
例文①傾聴力+課題解決能力
私の強みは、問題の原因を徹底的に分析し解決につなげる力です。
私は1年生の頃からアパレルショップでアルバイトをしているのですが、ときどき顧客アンケートで「スタッフの雰囲気が暗い」「店に入りづらい」などの声が届くことに問題を感じていました。
そこで、ミーティングをおこないスタッフが暗く見える原因についてどんなことが考えられるかを話し合いました。その結果、「作業に没頭して下を向いてしまう」「お客様と接しているとき以外は真顔になってしまう」の2つが挙げられました。
これを解決するために「ポジショニングを確認する声出しと笑顔の徹底」という施策を立てました。その場にいる全員に向けて「ホール入ります」「お会計入ります」などの声出しをおこない、それに対して「お願いします」「ありがとうございます」と返答をすることをルールにしました。
すると、自然とお互いが目を合わせるために顔を上げてコミュニケーションを取るようになり、笑顔を意識する習慣が付きました。その結果、店舗自体に活気が出てスタッフの雰囲気が明るくなり、アンケートで指摘されることがなくなりました。
御社に入社後も、積極的な意見の吸い上げと柔軟な落とし込みをおこない課題解決に努めてまいります。
課題を解決したエピソードとして良い構成です。補足として、自分が行動を起こして意見を聞き、集約して解決した過程がわかるような書き方ができると、より良い自己PRになります。
課題発見力
課題発見力とは、まだ誰も気付いていない潜在的な問題や改善点を見つけ出す能力のことです。課題発見力が高い人は現状に満足せず、「もっと良くするためにはどうすればいいか」という視点を持って物事をとらえることで、積極的に改善策を模索できます。
このような課題発見力を高めるうえで、傾聴力は効果的な組み合わせの一つです。なぜなら、ビジネスにおける課題は、何気ない会話のなかに隠されていることが多いからです。傾聴力を発揮して相手の声に耳を傾けることで、自分だけでは気付けなかった課題のヒントを得ることができ、それを解決に導くことができます。
傾聴力と課題発見力を掛け合わせた自己PRを作成する際は、日常の小さな声からどのように課題を見つけ、行動に移したかを具体的に伝えることで説得力が増します。以下の例文も参考にして、あなたならではのエピソードを自己PRに盛り込んでみてください。
例文②傾聴力+課題発見力
私の強みは、周囲の意見を吸い上げて問題が起こる前に課題を見つけ、対処法を考える力です。
私は1年生の頃から書店でアルバイトをしているのですが、売れ行きが良くない書籍や雑誌をよく売れている別店舗へ送る業務が月に数回ありました。
その際には他店舗に送る書籍のリストデータが全店舗に発信されるのですが、文字が細かいうえにすべての店舗の情報が同じ場所に羅列されているため見づらいという意見が常々ありました。
そこで、店舗検索欄に店舗名を入力するとその店舗に該当する情報のみがピックアップされ、他店舗の情報は表示されなくなるフォーマットを作りました。
全店へ向けて発信したところ非常に使いやすく業務負担が減ったという声が上がり、今ではそのフォーマットを使用してのリスト発信がおこなわれています。
今後も現状から先回りして課題を見つける力を活かし、働きやすい職場環境を整え無駄なコスト削減や業務の効率アップにつなげられるよう尽力してまいります。
アンケート結果を引用することで、傾聴力を活かす前と後の変化のイメージが湧きやすくまとまっている良い例文です。また、傾聴力を活かして意見を引き出したことにも触れられており、入社後にもスキルを発揮できることが伝わる自己PRですね。
行動力
行動力とは、目的を達成するために自ら積極的に動き、計画を実行に移す能力のことです。行動力が高い人は、率先して課題解決に取り組み、周囲を巻き込みながら成果を生み出すことができます。
この行動力を最大限に活かすためには、行動力と相性の良い傾聴力を活かすことが最適です。傾聴によって得た相手の本音やニーズを行動に移すことで、より大きな成果や変化を生み出すことができます。
単に話を聞くだけでは、得られた情報が活かされず、受け身の姿勢だととらえられてしまう可能性があります。しかし、聞いた情報をもとに自ら行動することで、主体性や課題解決への意欲をアピールできるのです。
傾聴力と行動力を掛け合わせた自己PRを作成する際は、傾聴がどのように行動のきっかけとなり、どのような結果につながったかを明確に伝えることが重要です。以下の例文を参考に、オリジナリティのある自己PRを作りましょう。
例文③傾聴力+行動力
私の強みは、話し手の気持ちに寄り添い共感することで、本音を引き出すことのできる傾聴力です。
私はゼミの研究テーマとして県民性に着目しており、あらゆる地域の特性とそこで生活する人々の性格的特徴の関連を研究していました。
しかし座学で情報を集めるだけでは不十分だと実感し、現地の人とコミュニケーションを取るため、大学3年生のときの4カ月間、日本各地へ赴いてさまざまな人と交流をしてきました。
もっとも苦戦したのは、初対面の人から話を聞く時、ざっくばらんに話してくれるような環境づくりをするためにはどうしたら良いかということでした。
始めは距離感を掴むのは難しかったですが、一つひとつのリアクションを大きくしたり、話し手と同じ温度感であいづちを打つことを心掛けると、自然とお互いの気持ちがほぐれてより深い話を聞くことができました。
この経験を活かし、御社に入社後は顧客の気持ちに寄り添ってニーズを引き出し、最高の提案ができる接客スタッフを目指します。
相手に合わせてリアクションを変える、というのは簡単なようでなかなかできないことです。基本的なことながら傾聴力がよく伝わる行動です。面接場面で面接官に対しても同じように行動することでより説得力を高められます。
決断力
決断力とは、さまざまな意見や情報をもとに最善の選択肢を判断し、責任を持って結論を出す力です。決断力が高い人は、不確実な状況でも立ち止まることなく、組織やチームを正しい方向に導くことができます。
傾聴力と決断力は、一見相反するように見えますが、実は相性の良い組み合わせです。これは多くの人の意見を傾聴し、多角的な情報を集めることで、より質の高い決断を下せるためです。
単に自分の考えだけで決めるのではなく、多様な視点を取り入れたうえで決断することで、周囲からの納得感も得られ、実行力が高まります。
傾聴力と決断力を掛け合わせた自己PRを作成する際は、意見が対立する状況でどのように傾聴し、その情報を踏まえてどんな決断を下したかを具体的に示すことが重要です。以下の例文を参考にして、自身の主体的な行動が伝わるエピソードを自己PRに盛り込みましょう。
例文④傾聴力+決断力
私の強みは、異なる意見を融合させてより良い環境を作る力です。
私は吹奏楽部の部長として、3年生のときから引退するまで部を牽引してきました。私の大学の吹奏楽部は非常に歴史が長く、習慣となっている取り組みが多くあります。その中の1つが、土曜日の朝10時から30分間おこなわれるパートリーダーミーティングです。
しかし毎週ミーティングをしても共有することはそれほど多くなく、時間を持て余して気が緩みがちになることを問題視する声が上がりました。そこで、長く続いてきた週1回のパートリーダーミーティングを廃止し、この時間を全員で部室に集まり基礎練習の時間にする決断をしました。
伝統を変えるということにプレッシャーを感じ、部に良い影響をもたらすことができるか不安があったのですが、結果として朝から顔を合わせることで一体感が増し、基礎練習終了後の時間に互いにコミュニケーションを取る機会ができたことで活気が出るようになりました。
御社に入社後も、周囲の意見を柔軟に取り入れ、より良い職場環境を作ることができるよう精進してまいります。
決断力を発揮したエピソードとして良いですね。補足として、パートリーダーミーティングを廃止するにあたって、みんなの意見を聞いたプロセスや進め方がわかるように書き方を工夫してみると、より良い自己PRになりますよ。
企画力
企画力とは、現状の課題やニーズを正確にとらえ、それを解決するための新しいアイデアや計画を生み出す能力のことです。企画力が高い人は、単に思いつきで行動するのではなく、論理的思考に基づいて具体的なプランを組み立て、周囲を巻き込みながら実行できます。
人々の心に響く企画は、当事者の声に深く耳を傾け、その不満や願望をくみ取るところから生まれるため、傾聴力は企画力と相性の良い強みです。
傾聴を通じて得られたリアルな声は、企画の核となり、説得力や共感を生む重要な要素になります。単に企画を考えるだけではなく、なぜその企画が必要なのかという背景を傾聴から導き出すことで、より説得力のある自己PRを作成できます。
傾聴力と企画力を掛け合わせた自己PRを作成する際は、どのような声に耳を傾け、そこからどのように企画のアイデアを発見したかを具体的に伝えることが主体性をアピールし、入社後に企業にどのように貢献できるかを具体的に示すために重要です。
例文⑤傾聴力+企画力
私の強みは、周囲の声に耳を傾け新たな企画を立てる力です。
私は1年生のときからウィンタースポーツサークルに所属しています。当時は新しくできたサークルだったためサークルメンバーは8人しかおらず、まったくの未経験という人はいませんでした。
しかし進級していくうちに部員が増え、3年生の時点で42人が所属するサークルになりました。
ただ、もともと主な活動時期が冬のみということもあり、人数が増えるとなかなか同じサークルのメンバーの顔と名前が覚えられないという声をよく聞くようになりました。
そこで、6月と10月に合宿を企画しました。多くのメンバーが参加してくれ、学年の垣根を超えた交流ができ、上級者が未経験者のゲレンデデビューをしっかりとサポートをする体制ができました。
それからは合宿以外にもオフシーズンを利用した活動が増え、みんなでトレーニングをしたり、季節に合わせた行事をおこなったり、よりサークル活動に活気が出ました。
御社に入社後も、積極的に顧客の声を吸い上げて多くの方のニーズに応えられる企画をし、売り上げに貢献いたします。
- 自分に当てはまるような傾聴力以外の強みがいくつかあるのですが、どれか1つを選ぶ場合は何を基準に選べば良いですか?
+αの強みはエピソードを基準に選ぼう
強みを伝えるエピソードを基準に選ぶのが良いでしょう。インパクトのあるエピソードである必要はありません。企業が自己PRで見たいのは、プロセスや熱意、考え方です。
どの強みを発揮したときのエピソードが、自分としてもっとも手ごたえがあったかを考えて選んでみてください。
失敗事例でも構いません。その場合は、一度は失敗したが反省から傾聴力の必要性を学び、再トライすることで目標を達成した、というストーリーとしてまとめると効果的です。
プロのアドバイザーならこうアドバイス!傾聴力とあわせて「提案力」をアピールすることもおすすめ
傾聴力が強みの学生は、友人から悩み相談をされた経験も多いのではないでしょうか。このときに、話を聞くだけでなく「◯◯をしたらどうかな」などと提案をした経験がある学生は、提案力もあわせてアピールすることもおすすめです。
些細なことでも「自ら考え提案した」という行動がアピールにつながる
提案力というと「独自性がある意見」や「クリエイティブな内容」がなければアピールできないと感じることもあるかもしれませんが、大切なのは自ら考え提案できるという行動面です。
仮に自己PRに取り上げるのが「友達に相談された際に何気なく一言伝えただけのエピソード」であったとしても、企業としては「聞く力だけでなく伝える力もあるのだな」と評価するので、提案力は傾聴力と合わせて十分アピールできる強みといえます。
企業に合わせた傾聴力の自己PRで志望度の高さをアピールしよう!
傾聴力を自己PRのテーマに選ぶ際、ほかの学生と被るのではないか、また企業から本当に評価される能力なのかと不安になる人もいるかもしれません。しかし、傾聴力は仕事で不可欠なスキルであり、伝え方次第で選考を突破するための強力な武器になります。
この記事で解説したポイントを押さえれば、あなただけのオリジナリティあふれる傾聴力の自己PRを作成できます。傾聴力の自己PRを作るうえで最も重要なのは、自己分析と企業研究を徹底的におこない、自身の傾聴力が企業のニーズにどう応えられるかを明確にすることです。
自身の傾聴力を志望企業でどのように活かせるかを具体的に示すことで、入社後の活躍をイメージさせられるだけではなく、志望度の高さも伝えられます。ぜひこの記事を参考にして傾聴力の自己PRを作り、あなたの魅力を最大限にアピールして選考突破を目指してみてください。
アドバイザーからあなたにエール傾聴力を発揮したあとの「結果」を伝えることが大切
ビジネスにおいて、傾聴力は手段であって、目的ではないことを押さえましょう。ビジネスでは、人の話を聞いて終わり、ということはありません。必ず聞く目的があります。
たとえば、
・顧客の悩みや要望、困りごとを把握して、新製品開発に反映するために聞く
・問題解決のために、今起きていること、困っていることを聞く
・チームのコミュニケーションを円滑にして、活性化するために相互に聞き合う
などです。
「傾聴力」の自己PRは目的意識を明確にして作成しよう
傾聴には目的があるということを押さえて自己PRを作る、つまり、傾聴力を発揮したプロセスややり方だけでなく、その結果達成した目的を伝えるのがおすすめです。
そうすれば、入社後も傾聴力を発揮してどんな風に貢献できるのかを採用担当者にわかりやすく伝えられるので、好印象を残すことができます。
「傾聴力」の自己PRは目的を意識したうえで作成し、その能力を入社後に活かせることをアピールして選考を通過しましょう。応援しています!
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi
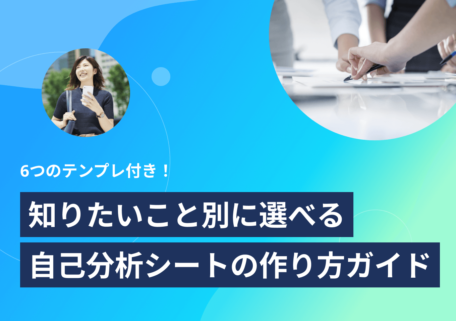


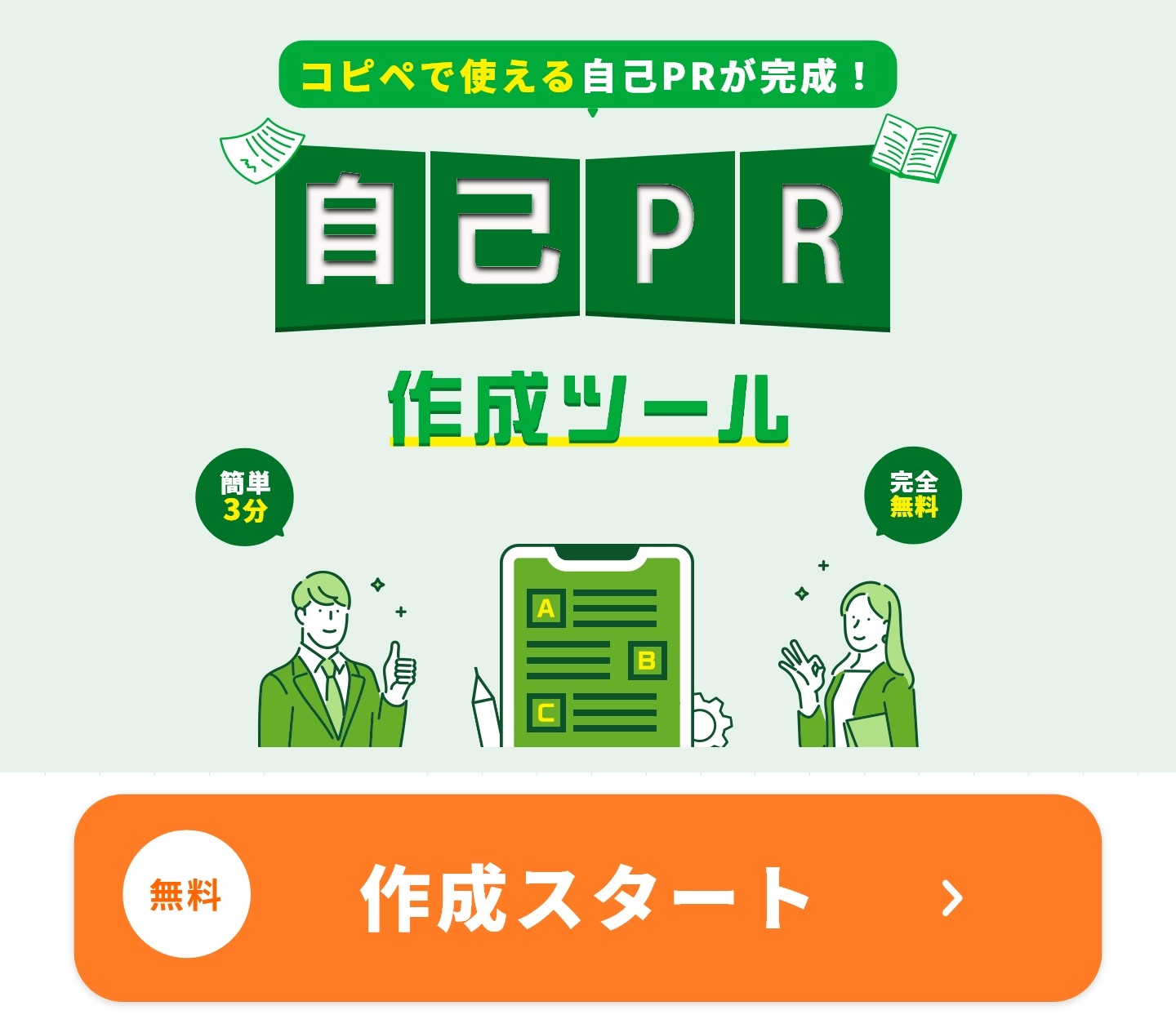





















5名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/合同会社渡部俊和事務所代表
Toshikazu Watanabe〇会社員時代は人事部。独立後は大学で就職支援を実施する他、企業アドバイザーも経験。採用・媒体・応募者の全ての立場で就職に携わり、3万人以上のコンサルティングの実績
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/産業カウンセラー
Atsuko Hirai〇ITメーカーで25年間人材育成に携わり、述べ1,000人と面談を実施。退職後は職業訓練校、就労支援施設などの勤務を経て、現在はフリーで就職・キャリア相談、研修講師などを務める
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/なべけんブログ運営者
Ken Tanabe〇新卒で大手人材会社へ入社し、人材コーディネーターや採用、育成などを担当。その後独立し、現在はカウンセリングや個人メディアによる情報発信など幅広くキャリア支援に携わる
プロフィール詳細国家資格キャリアコンサルタント/国家検定2級キャリアコンサルティング技能士
Yuichi Hirano〇主体的なキャリア形成にて代表取締役を務める。福商実務研修講座にて講師を担当するほか、人材サービス会社などで実践を重ねる。18年間で1万人以上の面談実績あり
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表
Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う
プロフィール詳細