理系向けの資格28選|「就活で有利になるの?」企業の本音も大公開

この記事のまとめ
- 資格はただ取得するだけでは就活に有利にならない
- 理系学生が資格を取得する場合は明確な目的を持つことが大切
- 理系学生におすすめの資格28選を特徴別に紹介
- 適職診断
たった3分であなたの受けない方がいい職業がわかる!
この記事を読んでいる人におすすめ
理系学生の中には、就活のために資格を取得しようと考えている人もいるのではないでしょうか。「理系学生におすすめの資格はあるのかな」「そもそも資格を取得すべきなのだろうか」と悩む人もいると思います。
理系学生には、研究などで忙しい人も多いですよね。そこで闇雲に資格を取得しようとすると、スケジュールを逼迫させてしまい肝心の就活対策がおろそかになってしまうかもしれません。資格を取得するのであれば、しっかりと目的を持って取り組むことが大切です。
記事では、キャリアアドバイザーの鈴木さん、木村さん、渡部さんと一緒に、理系学生が資格を取得すべきケースやおすすめの資格をアドバイスしていくので、資格取得を検討している理系学生はぜひ参考にしてくださいね。
【完全無料】
就活生におすすめ!
本選考前に必ず使ってほしい厳選ツールランキング
① 適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
②ChatGPT 自己PR作成ツール
ChatGPTを活用すれば、企業に合わせた自己PRが簡単につくれます
③ChatGPT ガクチカ作成ツール
特別なエピソードがなくても、人事に刺さるガクチカを自動作成できます
④志望動機作成ツール
ツールを使えば、企業から求められる志望動機が完成します
⑤面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
【本選考を控えている就活生必見】
選考通過率を上げたいなら以下のツールを活用しよう!
①内定者ES100選
大手内定者のESが見放題!100種類の事例から受かるESの作り方がわかります
②WEBテスト対策問題集
SPI、玉手箱、TG-Webなどの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
理系学生が資格を取得する場合は明確な目的を持つことが大切
「資格を取得しておけば、多少は就活を進めやすくなるだろう」と考える人もいるかもしれません。しかし、実態はそうとは限らず、場合によってはあまり役に立たないというケースもあります。研究などで忙しい理系学生は特に、資格を取得するのであれば明確に目的を持つことが大切です。
記事では、まず理系就活における資格の役割や立ち位置を解説します。資格が就活でどれほど重視されるのか理解し、そもそも資格を取得すべきか考えましょう。また、資格は目的があるのであれば取得すべきと解説しました。そこで、目的として定めるべき6つのケースを解説するので、参考にして、該当するのであれば資格を取得しましょう。
さらに、理系就活に役立つ資格を特徴別に28個紹介するので、資格を取得しようとしている人は、参考にしつつどの資格を取得すべきか考えてみてくださいね。
理系の資格のみならず、就活に有利な資格が知りたいという人はこちらの記事を参考にしてください。
就職に有利な資格33選|業界・状況別であなたに合った資格を解説
また、以下の記事では理系におすすめの就職先を解説していますので、こちらも要チェックです。
理系のおすすめ就職先11選 | 進路選びから就活対策まで完全網羅
あなたが受けない方がいい職業を確認してください!
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
知っておきたい大前提! 理系就活における資格の役割や立ち位置
理系就活における資格の役割や立ち位置
- 応募条件として課されることがある
- 応募条件にない場合資格があるからといって有利にはなりにくい
- 熱意や専門性のアピールになることはある
そもそも、理系学生の就活に資格は必要なのでしょうか。必要とされる場合、どのようなケースで必要になるのでしょうか。
ここからは、理系就活における資格の役割、立ち位置を解説していきます。資格を取得して就活に役立たせたいと感じる人は、まず理系の就活における資格の重要性を心得ましょう。
応募条件として課されることがある
まず、大前提としてその資格を持っていなければ就職できない仕事があります。たとえば、建築士、施工管理士などの専門知識を要する職種です。
気になる企業や職種があれば、まずは必要な資格があるか募集要項などで確認してみましょう。
また、資格の取得ではなく、試験のスコアを応募条件にしている企業もあります。たとえば、外資系企業などでは、TOEIC730点以上を条件などとしている企業があります。
本選考に限らず、インターンの参加資格として設定されていることもありますよ。
資格を応募条件に設定している企業は、その資格要件を満たしている社員でないと自社の事業を運営することができなくなってしまうという背景があります。裏を返せば、資格が設定されている企業は、何に特化した事業をしているかわかりやすいですね。
応募条件にない場合資格があるからといって有利にはなりにくい

就職みらい研究所の就職活動・採用活動に関する振り返り調査 データ集によると、採用において資格の有無を重視する企業は約16.1%と低い割合になっています。これは、資格で得た知識を業務で活かせるならばまだしも、そうでなければ資格があっても入社後活躍できるとは限らないからと考えられます。
人柄や熱意、ポテンシャルが重視される新卒採用では、資格があるからといって有利にならないことも多く、闇雲に資格を取得すると時間の無駄になってしまうことがあります。
理系学生が資格を持っていても有利になりにくい理由として、資格は入社後でも取得できるということも大きいです。
資格があったとしても人柄が悪かったり、やる気がない社員ばかりになってしまうと、組織運営が難しくなるため、資格よりも人柄や熱意などを重視しています。
大学3年生におすすめ!
就活準備は適職診断からはじめてください!
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
熱意や専門性のアピールになることはある
ただ、資格が必ずしも役に立たないというわけではありません。資格を取得していることで良い印象をもたらすことはあります。
特に、入社後取得しなければならないとされている資格を入社前に持っていると、「熱意がある人だな」「専門知識を持っており、即戦力になりそうだ」と好印象を持ってもらえることが多いです。
たとえば同じ能力の学生を比較した際に、資格がある人の方がより高く評価されやすいということがあります。
就職活動中の資格取得は、専門性や難易度が高いほどその業界や業種への志望度が高いことを示す手段の一つになります。
たとえ合格できなくても、分野によっては、入社前に資格取得を目指して勉強していることが高評価につながる場合もあります。
目的があるなら取得しよう! 理系学生が資格を取得すべき6つのケース

資格を取得していても、それだけでは就活で有利にはなりにくいです。そのため、資格を取得するのであれば、目的を持って挑戦することが大切です。
ただ、目的にもつけるべき優先順位があります。上のイラストを参考に、優先すべき目的なのか考え、就活の余裕度など状況に照らし合わせて資格を取るか判断しましょう。
ここからは、理系学生が資格を取得すべきケースを解説します。自分に該当するものがないか探し、資格を取得すべきかどうかの判断材料にしましょう。
①応募条件に資格がある
当然のことですが、応募条件として資格の取得が義務付けられているのであれば、資格を取得する必要があります。建築士などの専門的な職種や、英語のスコアを必要とする職種があるので、募集要項をチェックしてくださいね。
取得するまでに数か月から1、2年かかると言われている資格もあるので、資格が取得義務の場合は、あらかじめ難易度や必要な勉強期間についても調べておく必要があります。
- 具体的にどんな理系の職種や業界で応募時の資格取得が義務付けられていますか?
基礎的なレベルを求める医療や建設、土木やIT系などの業界
医療福祉、建設、土木、電気、ICT系の業界などは、専門分野を学んでいて基礎的なレベルの知識を持つ学生がほしい業界です。そのため難易度の高くないレベルの資格を義務付けている場合があります。
理系ではありませんが外資系での語学や経理職の簿記も同じような扱いになります。
理系の場合、専攻分野と資格は密接に関連しているケースが多いと思いますが、専攻と違う業界を志望する場合は取得にそれなりの時間がかかるので、計画的に取り組む必要がありますね。
応募条件に資格がある場合、履歴書の資格欄に記入が必要です。こちらの記事で書き方などをチェックしてくださいね。
履歴書の資格欄で好印象を残すには? 書き方から疑問点まで完全網羅
②高収入を狙う
専門性がある職種は市場価値が高くなり、高収入を見込めるケースもあります。たとえば保険業界で保険料率を決める「アクチュアリー」という職種がありますが、アクチュアリー資格を持っている人は、持っていない人と比較し平均年収が100~200万円異なることもあります。
高収入を狙うためには、管理職に就く、給与水準が高い業界や職種に入社するなどさまざまありますが、そのうちの1つの手段として、資格を取得し専門性を高め、市場価値を上げるという方法もあります。
資格を取得すれば、高収入を目指していくことが可能になる業界も多いので、長い目で見れば資格を取得をすると良いといえますね。
③入社後の取得が義務付けられている
社会人になってから資格を取得しようとすると、仕事終わりや休日に勉強をしなければなりません。時間的にも体力的にも厳しい状態で勉強することになるため、比較的時間がある学生のうちに資格を取得しておいた方が楽であるといえます。
また、入社後に必要な資格を持っていることで、熱意があることのアピールにもなります。
企業が推奨している資格を取得している場合は特に、入社後の配属先や担当業務を決める際の有効な参考情報になります。資格を持っていると、組織のニーズによっては新人社員にも早い段階から活躍を期待して即戦力に準ずる役割を与えられる可能性もありますよ。
もし余裕があるなら、入社後の取得が義務付けられている資格は今のうちに取得することがおすすめです。
ただ、もちろん入社後に取得すれば問題ないので、就活の状況に余裕がない人は、無理して取る必要はありません。
④企業から資格手当が出る
資格を取得していると、企業によっては資格手当が支給されることがあります。
資格手当
業務に活用できる資格をすでに持っている社員や、新たに取得した社員に向け、企業が支給する報酬
手当が支給されることで、さらなる自己研鑽に投資できたりとメリットがあるので、この場合も取得しておくことをおすすめします。
ただ、もちろん入社してからも資格手当を受けられるので、余裕がない人は資格手当を目当てに就活中に資格を取得する必要はありません。
⑤キャリアパスを叶えるために必要
キャリアパスを叶える資格を持っている場合、それを考慮して配属先を決定してもらえることもあります。そのため、希望するキャリアがしっかりと決まっているのであれば、それを叶えるために資格を持つこともおすすめです。
面接で「入社後にやりたいことは何ですか」と聞かれることがあります。その場合、たとえば「入社後5年以内に弁理士になりたい」と伝えるよりも、「資格の勉強で得た知識を活かして、5年後には弁理士になりたい」などと伝えると、より本気度が伝わりますよね。
繰り返しになりますが、社会人になってからは資格を取得する時間がなかなか取れません。そのため、学生のうちにキャリアパスを叶える資格を取得しておくと大変有効ですよ。
入社後やりたいことを聞かれた場合の答え方は、こちらの記事で詳しく解説しているので併せてチェックしてくださいね。
例文10選|入社後にやりたいことの回答で押さえるべきコツは?
⑥学生時代に力を入れたことがない
皆さんの中には、「学生時代に特別力を入れた活動なんてないな……」という人も多いのではないでしょうか。しかし、学生時代に力を入れた活動(ガクチカ)は、面接でよく聞かれる質問です。
そこで、ガクチカとして、資格を取得したことを伝えることも効果的です。資格を取得した目的や経緯、どんな資格を取得したのか、その資格を何に活かしたのかなどを伝え、ガクチカでアピールしてみましょう。
ガクチカの考え方や作成方法を詳しく知りたいという人は、こちらの記事で解説しているのでぜひチェックしてくださいね。
例文13選|誰でも「刺さるガクチカ」が完成する4ステップを解説
- 反対に、就活に向けて資格取得をしない方が良い理系学生はどんな人ですか?
大学での学業が忙しい人は無理に資格を取得しなくても良い
資格取得が絶対条件となる企業を除けば、資格は書類選考の要素の一つでしかないのもまた事実です。
資格の重要性は企業によって大きく違うので、優先順位を間違えないようにしましょう。
単位が足りていない人や研究が忙しい人は、学業に時間を取られるので、資格取得より短時間でできる選考対策や面接対策に絞ったほうが良いかもしれませんね。
また、企業との共同研究や学会発表などがある人は、その経験のほうが、就職において資格よりも重要な要素になることもあります。
かんたん3分!受けない方がいい職種がわかる適職診断
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
そもそもどんな資格があるの? おすすめの理系の資格28選
就活で資格が必ずしも有利になるとは限りませんが、解説したようなはっきりとした目標があるのであれば資格を取得してみましょう。
ここからは、理系学生におすすめの資格28選を特徴別に紹介していきます。
目的を踏まえつつ、就活やキャリアに活かせる資格を見つけてみてくださいね。
高い専門性をアピールできる資格
高い専門性をアピールできる資格
- 公害防止管理者
- 衛生管理者
- 品質管理検定
- 高圧ガス製造保安責任者
- 宅地建物取引士
- ガス主任技術者
- 電気工事士
- 第三種電気主任技術者試験
- 技術士
- 建築士
- 消防設備士
- 不動産鑑定士
- アクチュアリー
- 弁理士試験
資格の1つのメリットとして、専門知識をアピールできることが挙げられます。中でも理系の資格は、高い専門性を証明できる資格です。
そもそも応募条件として資格が設定されていたり、高収入を狙っていたり、叶えたいキャリアパスにマッチするのであれば、高い専門性をアピールできる資格に挑戦してみましょう。
ただ、専門性の高さゆえに汎用性は低く、応用が利かない場合があります。つまり転職や、異なる職種に挑戦したくなった場合は役立ちにくいということには気を付けてくださいね。
専門性が高い資格は、努力しなければ取れないものが多いです。そのため、あなたが努力できる人という証明書にもなります。専門性があるということ自体も、もちろん自己アピールに大きくつながります。
公害防止管理者
公害防止管理者とは
特定の工場において、排出ガスなどに含まれるダイオキシン類の量の測定業務を管理するための国家資格
勉強時間の目安
- 100~200時間
公害防止管理者は、取り扱う公害別に1種から4種まで分かれており、1種は6科目、2種・3種が5科目、4種は4科目あります。
合格率が高いのは 、ダイオキシン類特論、大規模水質特論、水質関係技術特論であり、いずれも6割前後になっているので、挑戦してみましょう。反対に合格率が低いのは騒音・振動特論、大気概論、大気関係技術特論で、合格率は2割弱~3割程度です。
公害防止管理者の資格を活かせる場所
- 電気供給業界
- ガス供給業界
- 熱供給業界など
ばい煙発生施設や粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設、ダイオキシン類発生施設などがある工場で働く際にその資格を活かせます。
公害防止管理者は、科目別に合格する制度もあるので、学生時代に一部の科目の合格を取り、その年を含め3年以内にほかの科目に合格できれば公害防止管理者の資格を取得することができます。まずは一科目から挑戦してみるのも良いですね。
衛生管理者
衛生管理者とは
従業員の就労中の労働災害や、健康障害を防止するためのスキルを証明する国家資格
勉強時間の目安
- 60~100時間
50人以上の労働者が存在する場合、企業は衛生管理者を設定する義務があります。衛生管理者は、その従業員の健康障害が起きないように管理する仕事をおこないます。
衛生管理者の資格を活かせる場所
- メーカー業界など
メーカー業界に就職後、有害なガスや薬品を取り扱ったり、危険性のある機械を扱う場合に管理することになります。
第一種と第二種に分かれ、第一種の合格率は4割前後、第二種は5割前後と国家試験の中ではやや難易度の低い資格です。
QC検定
QC検定とは
品質を管理するための知識をどれくらい持っているかを測る資格
勉強時間の目安
- 200時間
QC検定では、品質を管理するための方法や考え方、改善方法などの知識が問われることとなります。
QC検定の資格を活かせる場所
- メーカー業界など
メーカー業界などの品質管理部に所属し、商品の品質に問題が発生していないかなどをチェックしたりすることになります。品質管理検定の合格率は20%前後とされており、難易度は高いです。
ただ、品質管理職は、働きやすい職種として人気です。品質管理職を志望する学生は、こちらの資格を取得しておけば高倍率を勝ち抜くための1つのアピールになるかもしれません。
品質管理検定は、就活で意味があるとされるのは3級レベルからです。志望する業界が品質管理の工程に何らかの形で関係する場合は、3級の取得を目指すと良いでしょう。
高圧ガス製造保安責任者
高圧ガス製造保安責任者とは
高圧ガスと呼ばれる物質の保安業務をおこなう職種
目安の勉強時間
- 100時間
高圧ガス製造保安責任者の資格は、化学、機械、冷凍機械分野がそれぞれ甲乙丙と分かれ、全部で9種類あります。
高圧ガス製造保安責任者の資格を活かせる場所
- LPガス製造事業所
- LPガススタンド
- 石油化学コンビナートなど
この資格を取得することで、冷凍機械責任者に関する資格であれば、ビルのメンテナンスや、冷凍設備のある倉庫などで活躍することができます。
化学や機械の甲種、化学の丙種は合格率10~20%と低く、化学や機械の乙種や冷凍機械は4~50%前後とやや高い合格率となっています。化学の基礎知識があれば100時間程度で勉強できると言われていますが、そうでなければさらに時間がかかると覚悟しておきましょう。
宅地建物取引士
宅地建物取引士とは
不動産取引における専門家となる国家資格
勉強時間の目安
- 200~300時間
宅地建物取引士は、土地や建物の売買、賃貸物件の仲介などをおこなうことができます。不動産についての知識がない顧客が不当に不動産契約を結ぶことのないよう、わかりやすく説明する仕事です。
宅地建物取引士の資格を活かせる場所
- 不動産管理会社
- 住宅メーカー
- 不動産金融事業をおこなう銀行・保険会社など
合格率は20%以下となっており、難易度の高い資格です。
宅地建物取引士の資格は、特に不動産や金融業界に就職したい学生にとっては武器になる資格です。難易度が高い資格になるので、コツコツ勉強すると良いですね。
ガス主任技術者
ガス主任技術者とは
家庭で使用されるガスの、製造から供給までの作業の監督をおこなったり、保安業務をおこなうための国家資格
目安の勉強時間
- 100時間
ガス主任技術者の資格試験では、ガス関係の法令や、物理および化学理論、ガス工作物の工事や運用技術などに関する問題が出題されます。
ガス主任技術者の資格を活かせる場所
- プロパンガス設置会社
- 配管工事をおこなう会社
- ライフラインの工事会社など
こちらも甲乙丙に分かれており、いずれも合格率は20%前後と、難易度の高い資格になっています。なお、甲乙よりも丙種の方が合格率がやや高いです。
ガス業界を受ける際は、こちらの記事で志望動機の書き方を解説しているので併せてチェックしてくださいね。職種別例文7選も紹介しています。
ガス会社の志望動機は社会貢献では落ちる! 例文付きで作り方も解説
電気工事士
電気工事士とは
電気設備の工事などをおこなうための国家資格
勉強時間の目安
- 100時間
電気工事士は、第一種、二種と分かれており、第二種は一般住宅や小規模な店舗、家庭用の太陽発電設備などを取り扱うことができます。第一種はビルや最大電力500キロワット未満の工場の電気設備を取り扱います。
電気工事士の資格を活かせる場所
- 建設会社
- ビル管理会社など
電気工事士の仕事としては、建設電気工事や鉄道電気工事が挙げられます。電気工事士はニーズが高く、建設会社やビル管理会社などでは、部署によっては資格を必須としています。
筆記試験と技能試験に分かれており、50~60%の合格率と、難易度はやや低い資格といえます。
電気主任技術者
電気主任技術者とは
発電所や変電所、工場や商業ビルなどの電気設備の監督や保安業務をおこなうための資格
勉強時間の目安
- 1000時間
電気主任技術者は、電気工事士との違いがわかりにくいかもしれませんが、電気主任技術者は電気工事士を監督する立場で、電気工事士は電気主任技術者の指示に従って作業をする関係性にあります。
電気主任技術者は第一種~三種までに分かれており、第三種、二種は扱える電気工作物に制限がありますが、第一種になればすべての事業用電気工作物を取り扱うことができます。
電気主任技術者の資格を活かせる場所
- 建設会社
- ビル管理会社など
難易度は国家資格の中でも高く、合格率は10%程度です。ただ、難易度が高い分、取得しているとほかの学生と大きく差別化することができます。
技術士
技術士とは
高度な技術的知識と高い技術者倫理を備えていることを示す国家資格
目安の勉強時間
- 2000時間
技術士は、科学技術に関する技術的専門知識、高等の専門的応用能力を持っていることを示すものです。船舶・海洋部門、航空・宇宙部門、電気電子部門……といったように、資格は21の部門に分かれています。
技術士の資格を活かせる場所
- 建設会社の技術開発や研究
- コンサルタント企業
- 官公庁など
部門ごとに取り扱われている範囲は幅広く、合格率10%と難易度が高くなっています。難易度が高い分、平均年収はやや高く、572万円です。
厳密に言えば学生時代に技術士にはなれず、一次試験に合格して、修習技術者という資格を得ます。数年間の実務経験を経て二次試験の受験をし、合格して登録すれば技術士となります。その業界で長くやっていこうという人なら取り組んで損はありません。
建築士
建築士とは
建築士法に定められた、建物の設計や工事の監督をおこなえるようになる国家資格
勉強時間の目安
- 1500時間
建築士は、一級、二級、木造の3分野に分かれており、それぞれ取り扱える建物の規模や構造が異なります。大学生は受検できず、大学院生に受検資格があることには注意してください。
建築士の資格を活かせる場所
- 建築設計事務所
- 建設会社
- インテリア、照明、家具などのデザイン系の会社など
一級建築士は特に難しく、二級の合格率は30%前後ですが、一級は10%前後です。
消防設備士
消防設備士とは
施設の消防設備を点検したり整備したりする国家資格
勉強時間の目安
- 200時間
消防設備士は甲乙と分かれており、甲種を取得すると消防設備の点検や整備、設置、交換作業をおこなうことができるようになります。乙種は消防設備の点検や整備のみが可能です。
ただ、甲種を受ける場合は「甲種消防設備士」の資格を持っているなど、受験資格があることには注意してください。乙種は誰でも受験できます。
消防設備士が活躍できる場所
- ビル管理会社
- 工場など
電気工事士と仕事内容が似ているため、併せて取得する人も多くいます。
甲種は30%前後、乙種は40%の合格率となっており、国家資格の中ではやや易しいといえます。
不動産鑑定士
不動産鑑定士とは
地価を判断できるようになる国家資格
勉強時間の目安
- 2000~3700時間
不動産鑑定士は、地域環境などを考慮し、土地の価値を判断できるようになる資格です。
国や都道府県が公表する地価調査をおこなったり、公共用地の取得や裁判上の評価などをおこないます。不動産に関するコンサルティングなども実施します。
不動産鑑定士が活躍できる場所
- 不動産鑑定事務所
- 不動産業界
- 金融業界
- 鉄道などのインフラ業界など
試験は短答式試験と論文式試験に分かれており、短答式試験の合格率は30%前後、論文式試験の合格率は10%前後と難易度の高い資格です。
アクチュアリー
アクチュアリーとは
さまざまなリスクが起こる確率を統計学や確率論などを用いて数学的に算出し、保険会社の経営や、保険商品の開発をおこなうことができる資格
目安の勉強時間
- 全科目合格までは最低2年
- 基礎科目1個につき100~200時間
- 専門科目1個につき300時間
「正会員」になることでアクチュアリーと認められますが、正会員になるには第一次試験で5科目、専門科目を課される第二次試験で7科目に合格する必要があります。難易度はかなり高く、全科目合格までに最低でも2年はかかると言われています。
アクチュアリーが活躍できる場所
- 生命保険業界
- 損害保険業界
- 信託銀行
- コンサルティングファームなど
難易度が高い分、アクチュアリーになると年収も高くなり、平均1000万円以上稼げる人もいます。
- 正会員になっていなくても、アクチュアリーの中の何個かの資格を持っているだけでもアピールにはなるのでしょうか?
アピールになるかは業界によって異なるためリサーチしよう
どの程度まで取得しておくとアピールとして有効かは、同じ金融業界であってもその企業の方針によってさまざまです。
学生のうちから正会員になるのは時間的にも難しいため、計画的に専門科目の中の一つひとつを順番に攻略することを目指すのが良いでしょう。
また、勉強を進めながら就職活動をする中で、業界のOB・OGから話を聞く機会があれば、先輩たちはどのように苦手科目攻略したかをヒアリングし、自分の勉強計画の参考にするのもおすすめです。
難関試験には、必ずその人に合った対策と合わない対策があるので、先輩や周囲の一方的な助言を鵜呑みにせず、自分に合った勉強計画を立てるようにしましょう。
アクチュアリーが活躍する金融業界についてはこちらの記事で解説しているので併せてチェックし、働くイメージを持ってみましょう。
金融業界を徹底調査! 押さえておくべきトレンドや対策まで大解剖
弁理士試験
弁理士とは
知的財産権に関するスペシャリストであり、発明者の権利を守る仕事のための国家資格
勉強時間の目安
- 2000〜3000時間
弁理士は、特許権の取得や活用に必要な法的手続きや、鑑定についてのスキルを証明する資格となります。短答式試験、論文式試験、口述試験に分かれており、特に短答式試験が難しくなっています。
弁理士が活躍できる場所
- 特許事務所
- 法律事務所
- 大学
- 研究機関
- 知財経営コンサルティング会社
- その他各民間企業など
弁理士試験は、司法試験や公認開始試験に次いで難易度の高い法律資格と言われており、短答式試験の合格率は10%前後です。
難易度が高い分、弁理士の平均年収は約570万円とされており、日本の平均年収である430万円と比較すると高い水準となっています。
アドバイザーコメント
渡部 俊和
プロフィールを見る資格は自分のスキルをアピールする材料にすぎないことを心得よう
そもそも資格というのは、自分が持つスキルを客観的に証明するための手段です。取得することが目的ではなく、資格を持つ自分がそのスキルを使ってどう働けるのか、を伝えることが就活においての目的です。応募書類に書けることで多少のアドバンテージはあるかもしれませんが、ウェイトは決して高くないので、「資格さえあれば」などと勘違いしないようにしてください。
「自分にスキルがあってそれを発揮できること」をきちんと伝えることが大事です。
企業の仕事内容にしっかりとマッチした資格であればおすすめ
難易度の高い資格の場合は、資格試験に合格できていなくても学習をする過程でいろいろ学ぶことができます。志望先の仕事と自身のスキルアップに活用できる資格を選ぶことがおすすめです。
高レベルのものは資格取得の学習中であることを書類のどこかに書けば、面接の話題にも使うことができます。
また、ネームバリューだけに惑わされて、活用の機会がない国家資格や公的資格を取らないように注意しましょう。資格があっても活用しなければ知識は古くなっていき、結局は時間とお金の無駄になります。
専門性・汎用性を兼ね備える情報系の資格
専門性・汎用性を兼ね備える情報系の資格
- 基本情報技術者試験
- 応用情報技術者試験
- 情報処理安全確保支援士
- 情報セキュリティマネジメント試験
- ジェネラリスト検定
ここまで解説したのは専門的な資格であり、特定の仕事でしか活かせないものも多いです。志望する仕事が決まっていない人は、そのような資格に挑戦するのは少し勇気がいりますよね。
情報系の資格であれば、専門性もありつつ、さまざまな業界や職種で使用できる汎用性も兼ね備えています。もちろんシステムエンジニアなど、IT系の専門職につきたい人にもおすすめです。
IT系職種に興味があったり、希望する職種がしっかりと固まっていない人は、ここから解説する情報系の資格に挑戦してみてくださいね。
基本情報技術者試験
基本情報技術者試験とは
情報処理推進機構が運営する情報技術に関する基礎的な国家資格
勉強時間の目安
- 200時間
基本情報技術者試験は、ITエンジニアの登竜門とも呼ばれており、コンピューター技術に関する問題に加え、マネジメント、経営戦略に関する問題も出題されます。
基本情報技術者試験は、ITにかかわる仕事を中心に活かすことができます。具体的には、プログラマー、システムエンジニア、アプリケーションエンジニア、サーバーエンジニア、WEBデザイナーなどとして働くことができます。
IT系の国家資格の中では取得しやすい試験で、合格率は40~50%前後です。
システムエンジニアやプログラマー人材が慢性的に不足しているIT業界では、そういった人材になりうる、基本情報技術者試験の資格を取得している人については、かなりの戦力として優遇される可能性があります。
応用情報技術者試験
応用情報技術者試験とは
情報処理推進機構が運営する情報技術に関する応用的な知識を問う国家資格
目安の勉強時間
- 基本情報技術者の知識があれば200時間
- 基本情報技術者の知識がなければ500時間
応用情報技術者試験は、その名の通り基本情報技術者試験の応用版の国家資格です。基本情報技術者試験に受かってから挑戦する人が多いですが、受験資格はないので、もちろん基本情報技術者試験を取得していなくても受けることは可能です。
基本情報技術者試験は、基本的な知識や技能を持った技術者になるための資格試験ですが、応用情報技術者試験は、より高度なプログラミング知識などが問われます。また、自らの力で技術的な問題を解決するスキルや、プロジェクトマネージャ―のもとで目的達成のために品質や工程の管理をおこなうことも求められます。
学生のうちに応用情報技術者試験に合格しておくと、情報システムの開発や運用、保守、PCスキルがあることを証明できるため、IT関連の企業への就職は優位になることが多いです。
合格率は20%前後とやや難しい資格です。
情報処理安全確保支援士
情報処理安全確保支援士とは
情報技術に関する安心を確保するセキュリティ業務のスペシャリストとなる国家資格
勉強時間の目安
- 500時間
情報処理安全確保支援士は、特定の製品やソフトウェアではなく、情報技術の背景となる基礎的な知識が問われます。試験はスキルに合わせて12種類に分かれています。
また、IT技術だけでなく、経営戦略や会計、プロジェクトマネジメント、サービスマネジメントなど幅広く業務で活かせるスキルについても証明できる資格であり、情報処理安全確保支援士は、業界や職種を問わず幅広く活躍することができます。
合格率は20%前後とやや難関資格です。
情報セキュリティマネジメント試験
情報セキュリティマネジメント試験とは
情報セキュリティ関連の知識を証明するための国家資格
勉強時間の目安
- 200時間
情報セキュリティマネジメント試験では、近年問題となっているサイバー攻撃などに対するセキュリティ対策についての基本知識が問われます。
この資格を取得することで、企業のセキュリティの仕組みの理解につながったり、情報モラルを身に付けられることとなり、資格取得者は幅広い業界や企業で活躍する場があります。
情報セキュリティマネジメント試験の合格率は50%前後とやや高く、就活では強いアピールにはならないことが多いです。この資格を取得したことを伝えるのであれば、この資格を取得するまでの経緯や、この資格を活かした経験などを伝えるようにしましょう。
- IT系の資格は業界問わずとりあえず取っておこうという人も多いと思いますが、IT系の専門職としてアピールしたい場合、おすすめの資格は何でしょうか?
IPAが設定するレベル2以上の資格がおすすめ
情報処理の資格難易度の目安として、公的なものとしてはIPA(情報処理推進機構)の区分があります。
要求されるスキルITSS(ITスキル標準:レベル1~7)に対応している情報処理技術者試験をリストにしているもので、もっとも難易度の低いレベル1に「ITパスポート試験」、そのうえのレベル2に「情報セキュリティマネジメント」「基本情報技術者」などがあります。
コンピュータ理工学部などにはレベル3の「応用情報技術者」を取得する学生もいますが、専門職としてアピールする場合はまずレベル2のどちらかからをお勧めします。
短期間で取得できる資格
短期間で取得できる資格
- ITパスポート試験
- 危険物取扱者資格
- 知的財産管理技能士
- ジェネラリスト検定
「書類選考に資格を書きたいけれど、書類提出締め切り日まで時間がない……」という人も多いかもしれませんね。その場合は、短期間の勉強時間でも取得できる資格がおすすめです。
ただ、繰り返しになりますが、資格は目的を持って取得することが大切です。そのため、特に選考までの時間が限られている場合は、目的なく闇雲に資格を取得するのではなく、ESの添削や面接練習などに時間を割くことをおすすめします。
また、短期間で取得できる分、合格率も高くアピールにはなりにくい面があるということには注意してくださいね。
「入社後の取得が義務付けられている」「企業から資格手当が出る」「キャリアパスを叶えるために必要」「学生時代に力を入れたことがない」などの場合には、短期間で取得できるここで紹介する資格に挑戦してみましょう。
ITパスポート試験
ITパスポート試験とは
情報処理推進機構が運営する情報技術に関する基礎・基本的な国家資格
目安の勉強時間
- 100時間
すべての社会人に必要といっても過言ではないITについての基礎知識を習得するための資格です。企業とITの関連について学習するものであり、経営に関することからセキュリティの内容まで幅広く知識をつけられます。
ITパスポートの取得を入社後に義務付けている企業は業界問わず多く、取得しておいて損はない資格といえます。
勉強時間は約100時間、情報学部にいるなど知識があれば最短で20時間程度で取得できると言われるので、勉強時間がないが、何らかの知識を身に付けたいと考えている人は、まずITパスポートに挑戦してみると良いです。
ITパスポートを取るメリットとしては、社会人として必要なITの知識を一通り学んできているという印象付けができます。
ただ、IT専門の企業や部署が希望の場合は、ITパスポートを取っていても「当たり前だ」という印象でアピールにはなりにくいかもしれません。
危険物取扱者試験
危険物取扱者試験とは
消防法に基づく危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要な国家資格
目安の勉強時間
- 60時間
危険物取扱者試験を取得すると、化学メーカーや、ガソリンスタンド、化学工場、石油著上タンク、タンクローリーなどの施設で活躍できます。職種としては、ビルの設備管理スタッフや、発電所の保守員、試薬管理責任者などを担当します。
甲乙丙の順番で難易度が下がり、丙種は勉強時間がなくても取り組みやすい資格です。丙種は合格率50%前後で、甲乙丙合わせると40%前後です。
ただし、化学系の学部を卒業しているなど、受験資格があることには注意してください。
設備管理を志望している人は以下の記事をチェックしてください。志望動機の書き方とカギとなる要素をまとめているので参考にしてみてください。
設備管理の志望動機例文6選! カギとなる2要素で選考を突破しよう
知的財産管理技能検定
知的財産管理技能検定とは
知的財産を管理するための技能レベルを測定する国家資格
目安の勉強時間
- 50時間
知的財産管理技能検定は、学科試験と実技試験に分かれています。
知的財産管理技能士は、著作権や商標権、特許権など、アイディアを守るための権利を保護する役割を担います。
弁理士との違いがわかりにくいかもしれませんが、弁理士は、特許や意匠を得るための出願手続きを独占業務としておこなえる資格です。対して知的財産管理技能士には独占業務はなく、あくまで知的財産管理について一定の能力があることを示すものとなります。
また、弁理士は企業の外部で仕事をする専門的な知識を持つ職種という建付けですが、知的財産管理技能士は企業の内部で活躍することになります。具体的には、コンテンツの制作部門や、企業の法務部門、特許事務所などで活躍できます。
合格率は4割前後と国家資格にしてはやや高めになっています。
入社後できるだけ早い段階でこの分野の職務に就きたい場合は資格がメリットになる可能性は十分にあります。
ただし、特にその分野の専門家を目指すつもりがない場合は、逆に資格を取得したことでその分野への配属が優先されることがデメリットとなる可能性もあるので注意してください。
ジェネラリスト検定
ジェネラリスト検定とは
人工知能やディープラーニングなどの技術をビジネスに活かすために、双方について深く理解していることを証明する資格
目安の勉強時間
- 30時間
ディープラーニングとは、自動的にデータから特徴などを抽出するディープニューラルネットワーク(DNN)を用いた機械の学習ことをいいます。
ジェネラリスト検定の問題内容としては、AI技術者に必要な基礎知識が問われるものとなり、ほかにも倫理的な知識や、事業活動に必要な法律についての知識などが課されます。
ただ、合格率は60%前後とかなり高い水準であり、その分就活でアピールになることは少ないです。AI技術者などを目指す場合に基礎知識をつけるための資格と捉えると良いです。
アドバイザーコメント
渡部 俊和
プロフィールを見る短期間で取得できる資格は就活時よりも入社後に重宝されやすい
短期間で取得できる資格は就活であまり評価されることはないのですが、少し違う切り口で見ると有用なものがあります。
たとえば上記の危険物取扱者は、難易度は高くなくとも法律上の必置資格となっていて、一定の条件を満たす職場には必ず資格者を置かなければならないものです。通常、資格者がいない場合は職場の中で誰かに取ってもらわなければならないので、すでに持っている場合は重宝されるということがあります。
安全衛生にかかわる資格や立場にはそのようなものが数多くあります。スキルの証明ではなく法的な義務に基づくものなので、就活の評価には影響しにくいですが、マイナスにはならず職場で役に立ちます。
入社後に情報を多く仕入れて活躍できるアピールにもなる
また、製造業や商社における知的財産管理技能士資格は、特許調査やブランド、意匠権の管理などで役立つことがあります。担当者として実務に就く場合2級以上が目安になりますが、無形財産に関する幅広い知識も得られ、取得後に参加できる技能士会では、得られる情報が豊富なので、資格そのものよりも情報源としてコミュニティを活用するという活かし方ができます。
さまざまな企業で広くアピールできる資格
さまざまな企業で広くアピールできる資格
- TOEIC
- TOEFL
- 第二外国語の語学資格
- 簿記
- MOS
- 普通自動車免許
理系学生の中には、「受けたい企業が多く業界もばらばら」「文系就職も視野に入れている」という人もいるかもしれません。その場合は、さまざまな企業で広くアピールできる資格を取ることをおすすめします。
こちらも入社後取得義務がある場合も多いです。アピールになるレベルとともに解説するので、チェックして取得するか判断してみてくださいね。
TOEIC
TOEICとは
英語によるコミュニケーションと業務を遂行する能力を検定するための試験
目安の勉強時間
- 400~500点台から730点を目指すのであれば700時間
TOEICはビジネス上の英語力を測るための最もスタンダードな資格です。リスニング・リーディングテストまたは、スピーキング・ライティングテスト、スピーキングテストに分かれており、企業から求められるのはリスニング・リーディングテストのスコアであることが多いです。
満点は990点で、730点以上あれば「英語力がある」とアピールになることが多いです。履歴書に書くのは、最低でも600点以上からにしましょう。スコアがあれば入社後も、昇進の条件となったり、海外部門に異動しやすくなったりします。
新入社員の平均点は400~500点程度と言われていますが、そこから730点を目指すのであれば、700時間程度の勉強が必要です。
TOEICの点数を昇格の要件として組み込む企業が増えてきています。これは、仕事がグローバル化してきているので、企業としては英語力のある人材が必要だということの裏返しでもあります。
TOEFL
TOEFLとは
アメリカのNPOである教育試験サービスが主催する、英語を母国語とする人以外の英語力を測る試験
目安の勉強時間
- 50~60点台から80点を目指すのであれば700時間
TOEFLはリーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの4技能が課されるテストで、非英語圏の出身者を対象とし、基本的には留学する際に英語力を測るテストです。
たとえば外資系企業や海外企業などではTOEFLのスコアが有利になるなど、就活でも役に立つことが多いです。同程度のスコアを目指すのであれば、TOEICよりTOEFLの方がやや難易度が高いと言われており、実践的な英語力が身につきます。履歴書に書くのであれば70点から、アピールするのであれば80点以上を目指しましょう。
ただ、ビジネスの場ではTOEICを重視されることが多いので、外資系企業などを受けないのであれば、基本的にはTOEICを受けることをおすすめします。
TOEICやTOEFLのスコアなどを用いて、就活で英語力をアピールする方法はこちらの記事で解説しているので併せて参考にしてくださいね。
英語力は就活への影響大! 求められるケースとレベルを徹底解説
第二外国語の語学資格
目安の勉強時間
- 中国語検定2級の場合600時間
英語の資格を持っている学生は多いですが、第二外国語の語学の資格を持っている人はあまりいないため、差別化につながります。たとえばドイツ語検定や中国語検定などの、語学検定試験を受けてみましょう。
ただ、その言語を使用している国に進出していたり、取引している企業でなければアピールにはなりにくいので、気を付けてください。3級以上であれば履歴書に書くことができ、より強くアピールしたい場合は2級以上を目指しましょう。
個人の得意、不得意によりますが、中国語検定であれば3級を取得するのに約200時間、スペイン語検定であれば約150時間が必要と言われています。
- 実際に業務に使わないかもしれない第二外国語の資格を取得して、企業は良い印象を抱くのでしょうか?
企業の考え方によって大きく異なる
業務との関連性が低い第二外国語の資格を取得している就活生に対して企業がどのような印象を持つかは、その企業の考え方によって大きく異なると考えましょう。
第二外国語の言語が何かにもよりますが、その企業が将来商圏とする可能性のある国の言語かどうかも判断が分かれるところでしょう。ただし、第二外国語の語学能力が高い場合は、その言語の業務での有効性はなくても、新しい言語を身につけるスキルに長けていると判断され、良い印象を抱かれる可能性もあります。
たとえば、現在は取引のない国や地域の言葉でも、将来的にその企業が進出を計画する可能性がある国や地域の場合などが考えられます。
簿記
簿記とは
資産・負債・純資産の増減や、一定期間内の収益や費用を管理することができる資格
目安の勉強時間
- 2級の場合300時間
民間企業であれば、どのような企業も経営管理が必須なので、日々の経営活動を記録、計算、整理する簿記のスキルはどの企業でも役に立ちやすいです。
特に経理・財務部門では即戦力として認められやすく、特に2級以上取得していれば、経営状況の理解力が高いと評価され、将来の幹部候補として期待されることもあります。履歴書に書くのは最低3級以上と考えましょう。
簿記2級の合格率は3割程度と難関ですが、3級であれば約5割となっています。
MOS
MOSとは
マイクロソフトが認定する、Microsoft Officeのソフトに関する国際資格
目安の勉強時間
- PCに慣れている場合40時間
- PCに慣れていない場合80時間
MOSを取得していれば海外企業でもアピールが可能です。たとえばWord、Excel、PowerPointなどのソフトの技術力を証明することができます。
基本的にどの企業でも使用するツールとなるので、汎用性は高いです。事務職などでは特にアピールになることも多いです。IT企業などではGoogleスプレッドシートなど他のツールを使用していることもありますが、最低限のスキルの証明になりえます。
事務職を考えている人は、こちらの記事で事務職の特徴や志望動機の書き方を説明しているのでぜひチェックしてください。
例文20選|事務職の志望動機を職種別・業界別に徹底解説
普通自動車免許
普通自動車免許は、特に自動車での移動が必須となる企業では、入社後の取得を義務付けていることも多いです。たとえば、ドライバー、営業、MRなどの職種で必要となることがあります。
ただ、特に理系就職をするのであれば、業務で自動車を運転する機会はほとんどないため、就活でのアピールにはなりにくいです。
- 反対に、自動車免許を持っていないと不利になるということはないのでしょうか?
募集要項に書かれていなければ不利にはならないといえる
まずは募集要項を十分に確認しましょう。たとえば、自動車免許取得者歓迎のように記載されている企業の場合は、理系の仕事でも車に乗って仕事をすることが想定されます。
このように必要であれば企業側より出されている求人票や募集要項などに記載されているので、もし書かれていなければ不利にはならないといえます。
ペーパードライバーであっても記載する分には問題ありませんが、入社後自動車を運転する職種であれば、面接などでその旨を伝えておくことをおすすめします。
次の記事では、上記で解説した資格の他に取りやすい資格を解説しています。限られた時間の中で資格の取得を目指したい人などは、ぜひ参考にしてみてくださいね。
取りやすい資格25選|取得から就活でのアピールの仕方まで解説
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。
そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
忙しい理系学生の就活は特にスマートに! 資格は明確な目的があれば取得しよう
忙しい理系学生の就活は、優先順位をつけて計画的におこなうことが不可欠です。そのためには、もし資格を取得するのであれば、真に必要なものかを見極め、目的を明確にしたうえで挑戦しましょう。
理系学生が挑戦できる資格は多くあります。特に、専門知識を活かせるのは理系学生の強みともいえるので、視野を広く持ちつつ検討してみてくださいね。
アドバイザーコメント
渡部 俊和
プロフィールを見る資格の価値を見極めて挑戦することが大切
資格は公的なもの、民間のものも含め年々増えてきています。中には名前だけ立派でも民間企業が勝手に認定している価値の低いものもあるので、まず資格のレベルと価値をしっかり調べ、企業から見てどう見えるのか、自分にとって役に立つのかどうかを見極めましょう。
自分に役立つ資格かしっかりと考えて活用することも不可欠
応募に必須な資格を除けば、就活における資格の有無は書類選考時の多少のアドバンテージでしかありませんが、自分に自信が持てない時、やる気が出ない時などは、モチベーションを高めるきっかけに資格取得を使うこともできます。その場合はスキルアップや情報収集に役立つ難易度の高すぎないものを選びましょう。
より高度な専門性の高い資格を目指す場合、就職してから取得することも視野に入れ計画的に進めましょう。ただし安易に手をつけて時間を使った挙句に挫折しては元も子もありません。自分にとって意味のある資格に本気で取り組む覚悟を持って慎重に選んでください。本気で取り組んでいれば、学習の過程や取組みについては面接時のネタとしても活用できます。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

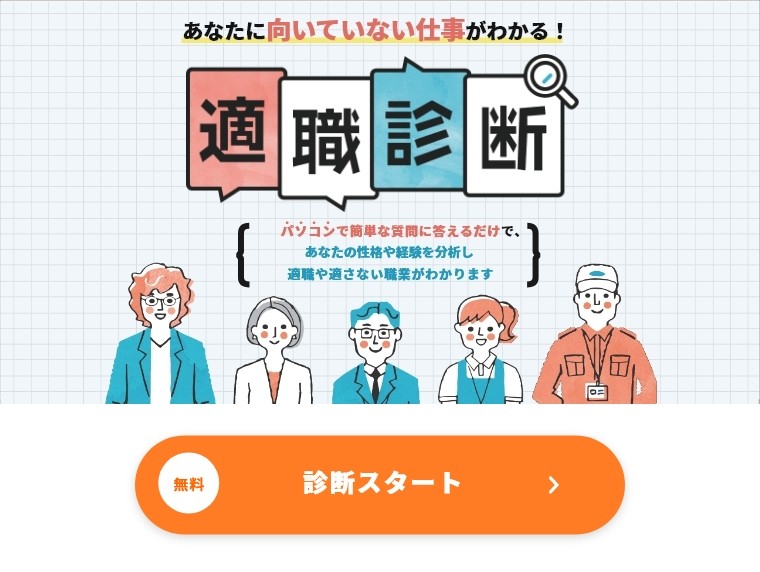





この記事にコメントしたアドバイザー
鈴木 洵市
ブルーバード合同会社代表取締役 保有資格:国家資格キャリアコンサルタント(登録番号21041822) SNS:Instagram/Facebook
続きを見る木村 千恵子
Koyori キャリアワールド代表 保有資格:国家資格キャリアコンサルタント(登録番号16050754)/キャリア・デベロップメント・アドバイザー SNS:X(旧Twitter)/Facebook
続きを見る渡部 俊和
合同会社渡部俊和事務所代表 保有資格:国家資格キャリアコンサルタント(登録番号16029675) SNS:Facebook
続きを見る