この記事のまとめ
- 就活で嘘をつくと内定取り消しや落選につながる可能性がある
- 価値観や考え方でも志望者を評価しているため嘘は必要ない
- 嘘なしの就活で本当の自分に合った理想の企業・職種に就職しよう
「就活で嘘をついても良いのかな?」という疑問は、就活初期の学生が抱える代表的な悩みです。就活の結果は今後のキャリアを大きく左右するため、少しでも自分をよく見せようと考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、就活での嘘は、発覚した際に大きなトラブルになる可能性があるため絶対に避けるべきです。
本記事では、嘘をつくデメリットやリスク、バレやすい理由について、キャリアコンサルタントの吉野さん、高尾さん、野村さんの見解を交えて解説します。嘘をつかずとも内定獲得できる方法を理解して志望企業への就職を目指しましょう。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
面接前に必ず使ってほしい厳選ツール
1位:面接回答集60選
見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました
2位:面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
3位:逆質問例100選
面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています
4位:最終面接マニュアル
通常の面接対策だけでは不十分!最終面接は個別に対策が必要です
5位:採用基準丸わかりシート
面接官が実際に使う評価シートで面接時の注意点を確認してください
【併せて活用したい!】
面接対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して面接前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
就活でついた嘘や盛った話はほとんどバレるため避けるのが基本
結論、就活でついた嘘や盛った話は、ほとんど面接官にバレます。なぜなら就活には複数のステップがあり、そのすべてで一貫して嘘をつき続けるのはほぼ困難であるためです。
一度嘘をつくと、面接官から「この志望者はほかにも嘘をついているのかな」と思われ、常に疑われた状態で選考を受ける可能性があるため、嘘は避けるのが無難です。
そして、嘘がバレた際のリスクや考えられる事態に関しては、記事の前半で解説しています。嘘が招く事態を正しく理解し、本当に嘘をつくべきかの判断の参考にしてください。
記事後半では就活での嘘が合理的でない理由や、嘘なしで内定を獲得する方法を解説します。最後まで読めば、偽りない自分の力での内定獲得に向けて、就活準備を進められます。
就職活動に必死になる学生が焦るのは仕方のないことです。
だからといって嘘をつくのは、努力の方向性が間違っていて、その行動をプラスに評価することはされません。また、嘘がばれないと思っている点に幼さを感じてしまいます。
面接対策には回答作成ツールを活用してください
面接で聞かれる質問に答えられるか不安ですよね。ただ、何を質問されるか分からず対策しようにも出来ない人は多いはず。
そこで、活用したいのが無料の「面接回答作成ツール」です。この資料があれば、穴埋めをしていくだけで面接でよく聞かれる質問の答えが一発で作成できます。
どんな質問が来ても確実に回答できるようになれば、面接はもう怖くありません。今すぐ活用し、面接を突破するのに役立てましょう!
・あなたの5年後・10年後のビジョンを教えてください。
・この職種を希望する理由を教えてください。
・あなたのモチベーションの源泉は何ですか。
・当社の業界を志望する理由を教えてください。
・入社後にどのような仕事がしたいですか。
就活における嘘とは? 真実や盛るとの違いを解説
まずは就活における嘘の定義をチェックしましょう。就活での嘘を日常生活と同じ感覚で捉えていると、意図せず面接官に嘘をついてしまう可能性も考えられます。そのため、事前に嘘の定義をチェックしておくことが大切です。
ここからは就活ではどこからが嘘になるのか、嘘と盛ることはどのように違うのかを解説します。
キャリアコンサルタントによる面接官側の意見も併せて紹介するので、併せてチェックして就活で不用意に嘘をつかずに済むようにしましょう。
就活における嘘と真実の違い
就活における嘘とは以下のとおりです。
就活における嘘
事実とは異なる内容を伝えること。
たとえば以下のようなものが、就活では嘘に該当します。
| 嘘の定義 | 例 |
|---|---|
| 事実とは異なる内容を伝えること | ・入賞したことがないのに「卒論が選考会で入賞した」と伝える ・部活動に所属していないのに「サッカー部で活動していた」と伝える |
| 実際の数値とは異なる数値を伝えること | TOEIC600点にもかかわらず「TOEICで700点をとった」と伝える |
誰が見ても事実と異なるものが、就活では嘘と定義されます。
逆に、人によって見解が分かれるものは、面接官によってその判断が異なるため、明確な嘘とは言い切れません。
たとえば「部活で一番信頼されていたから部長になった」という意見は、そのときの状況を聞かなければその真偽を確かめられません。状況を説明しても、真偽の判断は個人の見解次第です。
就活においては、事実と異なる内容を伝えることは信頼を損ねる行為となるため、正確で誠実な情報を提供することが重要です。
就活における嘘と盛るの違い
話を盛ることは、就活では意味合いが嘘と異なります。嘘は事実でないものである一方、話を盛ることは事実を過大に見せる行為です。
嘘と話を盛ることの違いは、以下のとおりです。
| 嘘 | 話を盛ること | |
|---|---|---|
| 学業について | 賞をもらっていないのに「入賞した」と伝える | 実際には研究内容が少し褒められた程度だったが、「教授に絶賛された」と伝える |
| 部活動・サークル活動について | 部活に入っていないのに「サッカー部に所属していた」と伝える | 実際には試合での活躍は少なかったが、「中心的役割を果たした」と伝える |
事実ではあるものの程度が異なる場合、それは嘘ではなく話を盛っていると判断できます。
話を盛っているとバレた場合の判断は面接官によって異なりますが、ネガティブに評価される可能性が高いので避けるのが無難です。
話を盛る背景には不安感や自己アピールの意識があるからだとは思うものの、過度な誇張には誠実性や信頼性の観点で疑問を抱かざるを得ません。
「盛っているな」と思った際にはエピソードの深掘りをし、その話の正しさを検証し、矛盾や具体性の欠如に気づくことが多いです。
就活では成果やスキルだけでなく、誠実さも評価されるため、あくまで正直で一貫性のあるアピールを心掛けてほしいです。
就活で嘘がバレるとどうなる? 考えられる5つの事態
就活で嘘がバレるとどうなる? 考えられる5つの事態
前述のとおり、就活において最後まで嘘をつき通すのはほぼ不可能です。そして、嘘の大小に関わらず、嘘がバレるとネガティブな評価を受けることが考えられます。最悪の場合、内定が取り消されたり入社後に契約が解消されたりする可能性もあるのです。
そこでここからは、就活で嘘がバレることで考えられる事態を5つ解説します。事前に嘘のリスクを以下でチェックして、本当に嘘をつくべきか今一度考えてみましょう。
①内定が取り消される場合がある
内定後に嘘が発覚した場合、嘘の程度によっては内定が取り消される場合があります。面接官が内定を決めた理由に嘘が含まれる場合、その内定は正当なものではないと判断されるためです。
企業は選考中だけでなく、正式な入社が決まった後にも志望者の経歴や申告内容に誤りがないかチェックする場合がほとんどです。そのため、就活で嘘をついた場合は内定が出たからといって安心はできません。
また、スキルや経験に関する嘘をついたり話を盛ったりした場合、本来のスキル・経験以上の仕事を任されるため、自分がつらい思いをする羽目になります。
嘘がバレて内定が取り消されても、バレずに働けてもつらい思いをする可能性がある点には留意しておきましょう。
履歴書の経歴詐欺にも要注意です。経歴詐欺が発覚した場合、どうなるか次の記事で解説してるので、併せてチェックしてみてくださいね。
②契約期間中に契約解除になる場合がある
入社後しばらく経ってから嘘が発覚した場合でも、その嘘が理由で契約解除になる可能性があります。前述の通り、嘘が内定の根拠となっていた場合その正当性自体が問題視されるためです。
また嘘をついて働いていたことは、ずっと職場の人間を騙しながら働いていたとも言い換えられます。企業から、職場の信頼関係を揺るがす可能性がある存在と認識されることも、契約解除になる可能性が生まれる要因の一つです。
契約解除にならなくても、嘘をついた事実が評価に影響を与え続けるでしょう。評価する側からの信頼を得づらくなるため、昇進・昇給がスムーズに進まない可能性も考えられます。
このように、就活での嘘は自身の信頼を大きく損なう行為であり、契約解除や評価が下がる可能性があるため、自分のためにも避けるべきです。
- 入社後しばらくして嘘が発覚した場合、企業で成果を上げたり、役職に就いたりしていても契約解除になるのでしょうか?
どのような立場であれ重大な事実にかかわる嘘は契約解除の可能性がある
成果を上げたり役職に就いていたとしても、入社後に嘘が発覚した場合、その嘘が重大な事実にかかわるものであれば契約解除になる可能性があります。
特に、嘘が入社の決め手となった情報に関するものであれば、企業の信頼を大きく損ない、契約の前提が崩れると判断されるためです。
また、嘘が明らかになることで、同僚や上司との信頼関係にも悪影響を及ぼします。
信頼は職場での円滑なコミュニケーションや成果を上げるうえで不可欠な要素であり、信頼を失うと評価やキャリア形成にも悪影響を及ぼすでしょう。
結果として、嘘は自身のキャリアを大きく損なうリスクがあるため、最初から誠実な姿勢で臨むことが重要です。
③選考で不利に働く可能性がある
大抵の場合、就活の嘘は面接官に見抜かれたり企業の調査が入ったりするため、選考段階で発覚します。嘘が発覚した場合、ネガティブな評価を付けられて選考で不利に働くことは避けられません。
嘘がネガティブに評価される理由は以下のとおりです。
嘘がネガティブな評価につながる理由
- 嘘なしで自分を表現できない人間だと判断されるため
- 入社後も嘘をついて周りを困らせるリスクがあると考えられるため
- 大事な場面で嘘をついてしまう可能性があると懸念されるため
また、面接では嘘だとわかった場合に「それは嘘ではないでしょうか」と質問されることはほとんどありません。企業からすると、まだ選考段階の人に対して嘘かどうかを問い詰めるメリットがないためです。
その場合、「多分嘘だろうな」や「この人は信用できないな」と思われるだけであるケースがほとんどです。
このように、就活の嘘がバレると弁解の余地はなく、自分の評価が無条件に下がる点は理解しておきましょう。
- もし嘘がバレて「嘘をついていますよね?」と聞かれた場合、どのように対処するのがベストでしょうか。
落ち着いて正直に状況を説明し誠実さを示すことが信頼回復の鍵
最初に、自分がついた嘘を明確にしたうえで、謝罪をしましょう。
「ご指摘の通り、◯◯については誤りで、◯◯が正しいです。」と事実を述べ、修正をしましょう。「申し訳ございません」と正直な気持ちを伝えることが重要です。
このとき、言い訳や責任転嫁は避け、自分の過ちとして受け入れる姿勢を示すことで、信頼回復の可能性が高まります。
とはいえ、もし必ずしも虚偽ではない場合には、「◯◯という表現が正しくなかったです」など、何が嘘に見えているのか、何が認識の相違で、何は正しいのかの事実関係をしっかり伝えましょう。
その後、動機と改善策の説明をおこない、今後は正直に自分を表現することを約束します。たとえば、「自己アピールを誇張して印象を良くしようとしてしまった部分がありました。
今後は誠実に対応し、自分自身の価値を正しく伝える努力を続けます」といった言葉で、面接官に誠実な姿勢を示しましょう。
最後に、今回のミスが自分の評価に与える影響についても冷静に受け入れる姿勢を示します。
「今回の件が選考に影響を与えることを理解しておりますが、今後の行動で信頼を取り戻せるよう努力したいと考えています」と伝えることで、謙虚な姿勢をアピール可能です。
嘘をついた事実は消せませんが、誠実に向き合い、自分の過ちを真摯に反省することで、面接官にポジティブな印象を与える可能性があります。
④自分に合った部署に行けない可能性が高まる
就活で能力やスキル、経験に関する嘘をついた場合、本当に自分に合った部署に配属される可能性は低くなります。
企業では個人の能力や適性をもとに配属先が決められます。しかし、就活で嘘をついた場合、本来の自分とは異なる能力・適性に基づいて配属が決められるため、自分に合っていない部署に配属される可能性が高まるのです。
自分に合わない部署に配属された場合、早期退職のリスクも高まります。仕事が合っていない分成果も出づらく、仕事自体へのモチベーションを保ちづらくなるのです。
目先の内定にとらわれて偽りの自分で就活するのではなく、将来的なキャリアを見据えて本当の自分に合う企業・職業を見つけるための就活をおこないましょう。
⑤嘘をつき通すストレスがかかり続ける
嘘には内定取り消しやネガティブな評価といったデメリットだけでなく、精神面のデメリットもあります。一度ついた嘘をつき続けることは精神的にも難しいため、通常の就活以上のストレスを感じながら選考に臨む羽目になるのです。
たとえば、「卒論が入賞した」という嘘をついた場合、それに合わせて自分の経験を改ざんする必要があります。架空の研究内容を作り上げたり、行っていない学術交流会の話について説明したりして、嘘を重ねざるを得なくなるのです。
嘘をつけばつくほど覚えておかなければならない内容が増え、嘘がバレるリスクが高まります。
面接ではついた嘘すべてに矛盾がない受け答えが必要なため、プレッシャーやストレスは倍増するのです。
そして、たとえ入社できても、契約解除にならないよう同僚や上司にも嘘をつき続ける必要があります。
就活での嘘は、長期的に自分を苦しめる可能性が高い点にも留意しておきましょう。
就活で特に注意すべき嘘! 内定取消や落選につながる絶対NGな3つの項目
就活で特に注意すべき嘘! 内定取消や落選につながる絶対NGな3つの項目
- ①学校の成績に関する嘘
- ②部活やサークルの成績に関する嘘
- ③スキルや資格に関する嘘
就活での嘘はバレた際のリスクは高く、良い評価を一変させる怖さがあると理解できたのでがないでしょうか。嘘がバレると、ほとんどの場合ネガティブな印象を持たれます。
なかにはネガティブな評価だけでなく、内定取り消しや落選につながる嘘も存在します。ここからでは特にリスクの高い絶対に避けるべき3つの嘘を解説します。
どんなに良い印象を残せていても、以下の嘘が一つでも発覚すると内定獲得の可能性が低くなるため、必ずチェックして、嘘のリスクを理解しておきましょう。
①学校の成績に関する嘘
学校の成績に関する嘘は高い確率でバレるうえ、内定取り消しや落選につながりやすいため絶対に避けましょう。成績は自分の大学での努力を表す指標で、会社が内定者を決める重要な項目の一つであるためです。
企業はエントリー時に提出する成績証明書で志望者の成績をチェックしています。特に内定者決定時には厳格なチェックがおこなわれるため、選考中についた嘘は確実にバレるのです。
「単位を落とした」「留年した」などの事実は隠したくなるものです。しかし、嘘をつくと選考に通過できる確率はほぼゼロになる点には留意しておきましょう。
なお、面接官は成績自体ではなく、その成績を取る過程や成績に対する考え方、そこから学んだことなどを評価しています。そのため、悪い成績を隠すのではなく、そこから得た学びや反省と共に伝えることで、成績の欠点をポジティブな評価に変えられます。
嘘をつかずに「単位を落とした」「留年した」などの経歴を正直に伝える学生には、誠実さや自己理解の深さを感じます。
その経験を反省し、学びを次に活かそうとする姿勢は、成長意欲や責任感として評価されると思われます。
内定後に卒業できないわかったときの行動についてはこちらの記事でまとめています。連絡方法や対処法を解説しているので参考にしてみてください。
②部活やサークルの成績に関する嘘
部活やサークルの成績を高く見せるのも、避けるべきです。大会成績の嘘は重大な偽造行為にあたるため、バレたら内定取り消しや落選は避けられないと考えましょう。
部活やサークルの成績も学業成績同様、成績証明書に記載されているため嘘は簡単にバレます。また、成績証明書に記載されていなくても、大会のホームページなどで簡単に調べられるため、嘘は厳禁です。
部活やサークル活動は特に努力の過程やそこでの苦労、苦境を乗り越えた経験が評価されます。
そのため、嘘をついて少しでも自分をよく見せようとするのではなく、「実際のなぜその成績になったのか」や「その結果から何を学んだのか」といった過程や学びを伝えましょう。
サークルで経験で嘘をつくことのリスクについてはこちらのQ&Aでも解説しているので、あわせて確認してみてください。
③スキルや資格に関する嘘
スキルや資格に関する嘘は、就活でありがちな嘘の典型例です。TOEICの点数を少し高めに伝えたり、簿記、FPなどの資格を持っていないのに保有資格として提出したりすると、発覚した際にマイナス評価となる可能性が高くなります。
スキル・資格に関する嘘も実施機関への問い合わせで簡単にバレるため嘘は厳禁です。どんなに高く評価されていても、嘘がバレた時点で内定のチャンスはほぼゼロになります。
また、まだ合否が発表されていない時点で「合格した」と伝えるのもリスクが高いため避けましょう。もし不合格であった場合、どんなに評価が高くてもその嘘のせいで落選になってしまいます。
スキルや資格について正直に述べるのはもちろん、勉強中のものがある場合はその旨を伝えるのがおすすめです。
たとえば「御社で序盤から活躍するために勉強中です」と伝えれば、その資格を保有していなくても面接官に良い印象を持ってもらえる可能性が高まります。
就活の面接での嘘はほとんどバレる! 5つの理由を解説
就活の面接での嘘はほとんどバレる! 5つの理由を解説
ここまで嘘のリスクや、内定取り消しや落選につながる絶対避けるべき嘘を解説してきました。就活では嘘をつくべきでない理由が理解できたはずです。
ただ、なかには「バレなければ良いのではないか」と考えている人もいるかもしれません。確かに嘘がバレなければネガティブな評価にはつながりません。成績証明書や問い合わせが困難なものなら嘘がバレないように思えるものです。
しかし、就活ではほぼ確実に嘘はバレます。この項では就活の嘘がバレる5つの理由を解説します。まだ嘘をつこうか悩んでいる人は、以下をチェックして嘘をつかずに就活に臨む姿勢を固めましょう。
①具体的なエピソードを話せない
具体的なエピソードやその過程をうまく話せないと、面接官に嘘をついていると疑われます。真実であれば、質問された際に具体的な過程やエピソードを話せるはずであるためです。
特に想定外の質問を投げかけられた場合に、嘘をついているとバレがちです。
たとえば「卒論が入賞した」と嘘をついた場合、研究過程や苦労した点などはスムーズに話せるかもしれません。ただ、周囲の反応や祝賀会の様子など、予想外の質問を投げかけられた際に、具体性に欠ける返答しかできなくなるのです。
これまで多くの学生を見てきた面接官は、予想外の質問に対する学生の反応から、嘘か真実かを見抜くことができます。確かめられない嘘でも、質問への反応でバレる可能性が高い点には留意しておきましょう。
「○○の資格を目指していた」というエピソードについて、「一日何時間くらい勉強しましたか?」と質問したところ、「えーと、日によって違うので…」とあいまいな回答しか返って来ず、結局試験を受けていないことがわかりました。
具体的な数値を確認する質問をすると、嘘を見抜きやすくなります。
②深掘りされた際に矛盾が生じている
具体的なエピソードを話せたとしても、その後の深掘りで嘘がバレる場合があります。一度ついた嘘を忘れたり、事実との整合性が取れなくなったりして、発言に矛盾が生じるためです。
真実であればそのとおりに話しても矛盾は生じることは少ないですが、一つでも嘘があると矛盾が生じる可能性が生まれます。矛盾が生じるとほぼ確実に嘘が見抜かれるため、確かめられなくても面接では嘘は避けるべきなのです。
また、一度嘘をつくとそれがバレないように発言し続ける必要があるのも、大きなデメリットです。嘘をついたせいでその後の面接に集中できなくなるのは、本末転倒といえます。
自分の力を最大限発揮するためにも、嘘なしで就活に臨みましょう。
面接が迫っている人は、頻出質問の回答例だけでも予習しておこう!
面接でどんな質問がされるか、そして答えられるか不安ですよね。ただ、企業によって何を質問されるか分からない人も多いはず。
そこで活用したいのが無料の「面接回答集」です。この資料があれば、森永製菓や伊藤忠商事、トヨタ自動車などの人気企業の面接で、実際に聞かれた質問とその答え方がわかるようになっています。
どんな質問にも自信をもって答えられるようになれば、面接も怖くなくなります。今すぐ活用して、面接突破の力を手に入れましょう!
③自分のエピソードを他人事のように話している
嘘をつくと、自分のエピソードでも他人事のように客観的な視点で話しがちになるため、面接官に嘘を見抜かれます。架空の話は感情やそのとき考えていたことを織り交ぜて話すのが難しく、どうしても他人事な話し方になってしまうのです。
特に知り合いの体験談を自分事かのように話したり、聞いた話を自分の考えかのように話したりする嘘は、面接官にほとんど見抜かれます。
なぜなら、深掘りされた際、そのときの感情や考えなどの具体的な情報を提供するのが難しいためです。
面接官は実績や事実だけではなく、実績を出すまでの過程や結果から学んだことなどを評価しています。深掘り不可能な他人のエピソードを流用するのではなく、自分のエピソードを深く分析し、そこから得た学びや経験で自分の魅力をアピールしましょう。
面接で、エントリーシートに記載されていた部活動の経験について質問した際、棒読みで「チームで協力して練習しました」と表面的な回答をされたことがあります。
具体的なエピソードや自身の役割を尋ねても曖昧な答えしか返ってこず、自分の経験として向き合えていない印象を受けました。
面接官は成果だけでなく、その過程や学び、そこから見えるその人らしさを知りたいと考えています。
自分の経験をしっかりと振り返り、具体的で自分らしいエピソードを語れるよう準備してほしいと感じた出来事でした。
④何かを暗記したような話し方をしている
嘘がバレないように対策している志望者は、矛盾を避けるために暗記したことだけを話しがちです。しかしこの対策が逆に面接官に怪しまれ、結果、嘘の発覚につながります。
また、嘘を暗記しただけでは想定外の質問をされた際に矛盾が生じる可能性が高いです。矛盾が生じた時点で嘘がほぼ確定するため、評価が低くなることは避けられません。
そのため、面接では嘘を暗記して受け答えするのは避けましょう。また、真実であっても、暗記した内容だけでの受け答えは好ましくありません。想定質問への返答を想定したうえで、相手に合わせて最適な形で受け答えするのが内定を勝ち取る秘訣です。
「暗記したような話し方しかできない……」と悩んでいる人は、以下の記事もチェックしてみてください。面接でうまく話せないを克服する6つの具体的なコツを解説しています。
⑤出した成果が非現実的である
話し方や受け答え、話の矛盾だけでなく、話の内容自体で嘘がバレることがあります。
特に出した成果や実績が現実的でない場合、疑わしい項目を面接で直接確認されるケースが多いです。最悪の場合、確認されないまま嘘として処理されるケースもあるのです。
嘘であるかどうかを直接確認される場合、達成までのプロセスや非現実的な目標を達成できた理由などを徹底的に深掘りされることが考えられます。そこで矛盾が生じたり、明らかな偽造が発覚したりするとネガティブな評価につながる可能性があるのです。
また、多少話を盛っただけのつもりでも、現実と異なる場合は明らかな嘘同様に評価が下がることもあります。
自身の経験や実績について語る際は嘘だけでなく話を盛るのも避け、真実をもとにアピールしましょう。
就活のプロが解説! 就活で許容される嘘
就活での嘘がほぼ確実にバレることや、嘘が招く事態を理解できたのではないでしょうか。就活での嘘はリスクが高いため、いかなる場合であっても避けるべきです。
ここからは、嘘に関して採用担当者や面接官がどのような見解を示しているのかチェックするために、採用経験のあるキャリアコンサルタントの吉野さんの意見を紹介します。
就活のプロによる就活の嘘に関する解説を見て、志望動機の作成や面接対策に活かしてみてください。
アドバイザーコメント
やっていないことを「やった」と伝えるのは絶対にNG
嘘をつくことにメリットは考えられません。これから雇用契約という重大な約束を交わす相手に対して、虚偽や偽造を交えて何の得があるでしょうか。
やっていないことを「やった」と言うのは明らかな嘘です。一方で、たとえばTOEICを受けたが点数が低かったために記載しないなど、やったことを開示しない、あるいは省略するのは程度問題です。
話を盛ることについても同様に程度問題で考えられます。
嘘をつくのではなく慎重な言葉選びによって信頼を勝ち取ろう
工夫が必要なのは、複合的な理由が絡むときです。たとえば中退、留年、浪人など、特にネガティブな事柄は原因が一つではない場合が多いです。人間関係、体調、環境不適応、目標喪失など、さまざまな要因が考えられます。
まずはこれらを整理し、理由をたくさん挙げてみましょう。そのなかから、「これなら嘘ではなく、かつ伝わりやすいだろう」という言葉を選び、就職活動に向けた説明を準備しておくことが大切です。
重要なのは適切な言葉選びです。語彙力が不足していると、不適切な表現や嘘になってしまいがちです。
適切な言葉を選ぶ力を磨くことが、信頼を得る第一歩になります。
能力や成果だけじゃない! 面接官が評価する5つのポイント
能力や成果だけじゃない! 面接官が評価する5つのポイント
就活で嘘をつきたくなる学生は、就活では能力だけが評価項目だと考えている場合が多いです。そのため少しでも自分をよく見せようとして嘘をついてしまうことがあります。
しかし、面接官は能力以外にも複数の要素をチェックしながらその学生を評価しているため、リスクを冒してまで嘘をつく必要はありません。
ここからは能力以外の5つの評価項目を解説します。この5項目をチェックすれば、嘘をつかずに就活した方が良い理由を理解できます。
①その企業への志望度の高さ
志望度が高い学生は企業への貢献度が高く、長く働き続ける傾向があるため、面接官は熱意のある学生を積極的に評価します。
産労総合研究所の「2023年度 教育研修費用の実態調査」によると、従業員1人あたりの研修費用は32,412円かかっています。新卒が仕事に慣れるまでにかかる時間や上司のサポートも加味すると、人材育成には莫大なコストがかかっているのです。
このように、企業側はコストをかけて人材を教育・育成するため、すぐに辞められることは避けたいと考えます。
そのため、選考段階で企業に長く貢献し続けてくれそうな人材を見極め、入社してもらおうとするのです。
内定に少しでも近づくためにも、志望動機ではその企業を熱望していることを伝えましょう。
社内での採用経験を通じて、「能力が高くても志望度が低いと長続きしない」という意見を担当者からよく耳にしました。
入社前の採用試験では、熱意を具体的に伝え、自社への適性を示す学生が特に高く評価される傾向にあると感じます。
志望度を聞かれた際に「御社が第一志望です」と嘘をついてもいいのか悩む人もいるかもしれません。しかし、納得のいく形で就活を終えるためにも嘘をつくことには注意が必要です。こちらのQ&Aで詳しく解説しているので、あわせて確認してみてください。
②志望者の価値観や考え方
志望者の価値観や考え方がその企業にとって魅力的かどうかも、選考で評価されるポイントです。
価値観や考え方が企業理念や社風にマッチしていなければ、能力が高くても評価は低くなります。
このように、能力が高い一方で考え方や価値観が企業にそぐわない志望者は、トラブルのリスクや人間関係への懸念からむしろ低く評価される可能性があるのです。
そのため、能力や成果に固執するのではなく、人間性や考え方などの内面性で自分の魅力をアピールしましょう。そのためには、成果や実績だけでなく、そこに至るまでのプロセスや学びなどを具体的に伝える必要があります。
また、自分がその企業に適していることを示すには、徹底した企業分析も必須です。
企業理念や社風、方針などを正しく理解したうえで、自分の価値観や経験をもとに企業に合う人材であるとアピールしましょう。
③自己理解の深さ
企業は面接の際、自分のことを正しく理解する自己分析能力の高さもチェックしています。
自分の特徴や強み・弱みを正確に把握していない志望者を採用すると、ミスマッチを引き起こす可能性があるためです。
また自己理解が深い学生のほうが、自分の能力や経験を活かせる場所を自身で見極め、力を発揮できるのも企業からの評価が高まる理由の一つです。企業は利益を追求している以上、より企業に貢献してくれそうな学生を積極的に採用したいと考えます。
自己理解を深めるには、徹底した自己分析が欠かせません。自身を正しく理解してアピールできるように、必ず自己分析で自分の価値観や性格を掘り下げておきましょう。
④論理的に説明する力
論理的に説明する能力はチーム内でのコミュニケーションだけでなく、取引先との関係構築にも欠かせません。
企業は従業員に取引先との関係構築を任せる以上、志望者にも論理的に説明する力を求めるのです。
このような論理的に説明する力は、ビジネスに不可欠のスキルである以上、面接ではほぼ確実にチェックされます。どんなに能力やスキルが高くても、それを効果的に伝えられなければ評価されません。
そして、論理的な説明をするには以下の3つが求められます。
論理的な説明に必要な能力
- 相手の聞きたいことを読み取る力
- 相手の思考の流れに沿って情報を整理する力
- 相手に伝わる言葉を選んで説明する力
面接官は受け答えのなかで論理的な説明ができるかを見極めています。対策時から論理的に説明する練習を重ね、本番で確実に力を発揮できる状態に仕上げておきましょう。
他人に自分の考えを聞いてもらう練習が大切です。文章なら添削を受け、口頭の場合は説明を聞いてもらい、フィードバックしてもらうとよいでしょう。
模擬面接も効果的です。何度もリテイクを重ねることで、論理性が高まります。
39点以下は要注意!
あなたの面接力を診断してください
「面接に自信がない」「今のままで選考通過できるか不安」そんな就活生は自分の面接力を知ることからはじめましょう!
たった30秒で面接力を把握できる「面接力診断」がおすすめです!。簡単な質問に答えるだけで、“あなたの強み”と“改善点”が明確になり、対策もしやすくなります!
・面接でなぜ落ちたかわからない人
・自信を持って、面接に臨みたい人
⑤受け答えのスムーズさ
質問に対してよどみなく答えられるかどうかも、面接官がチェックしているポイントです。受け答えがスムーズで堂々としている志望者は面接を見据えて入念に準備してきたとして、高く評価されます。
「準備している感が伝わるのは良くないのではないか」と思う人もいるかもしれません。確かにテンプレートの回答や暗記してきた回答ばかりでは、機械的な印象を与えてネガティブな評価を受ける恐れがあります。
一方で高く評価される準備とは、面接を想定して相手の求める情報を提供できる臨機応変さを指します。
事前に面接を想定して練習を重ね、相手が求めている情報に合わせて自分の考えや経験を調整して回答すれば、本気でこの面接のことを考えているとして高い評価を得られる可能性が高まるのです。
表面的な準備ではなく面接を深く想定した準備を徹底し、面接を優位に進めましょう。
- 面接官はどのようなポイントから「この学生はしっかり準備してきたのだな」と感じるのでしょうか。
自身を持って話すことができている学生は高評価を得やすい
まず、志望動機や自己PRが企業に特化した内容で、事前に企業分析をおこなっていることが伝わる場合です。
具体的には、「御社の〇〇事業に共感し、自分の〇〇経験を活かせると考えました」といった形で企業との接点を明確に述べていると、準備の丁寧さが伺えます。
また、質問に対する受け答えがスムーズで、事前に想定質問への準備をしていると感じられる場合も同様です。
特に具体的なエピソードを交えて答えられる学生は、深い自己分析や事前準備ができている印象を与えます。
準備が整っている学生ほど、自信を持って話し、面接官からも高評価を得やすいです。
スムーズなコミュニケーションや受け答えが苦手な人は、以下で対策しておきましょう。面接の苦手を解消する具体的な方法を紹介しています。
面接が苦手
面接の苦手意識を克服する21手|得意にする秘訣は「考え方」にあり
面接が苦手な人
例文15選|面接の「苦手な人は?」の回答で好印象を残すコツ
嘘なしでも内定は勝ち取れる! 就活の7ステップを具体的に解説
嘘なしでも内定は勝ち取れる! 就活の7ステップを具体的に解説
面接官が見ているポイントを押さえて自分の魅力を効果的にアピールできれば、嘘なしでも内定を勝ち取れることが可能です。
ここからは、嘘なしで内定を勝ち取るための具体的な就活ステップを解説します。嘘をつこうか悩んでいる人も、以下を読めば偽りない自分の魅力をアピールする方法がわかります。
嘘なしでの就活の具体的な進め方を知りたい人、説得力のある志望動機で面接官に評価されたい人はぜひチェックしてみてください。
①自己分析で自分の価値観や性格を掘り下げる
まずは自己分析で自分の価値観や性格を明確にし、自分がどんな人間なのかを把握しましょう。自己分析は就活を進めるうえですべての基本になるため、特に入念に取り組む必要があります。
自己分析には自分でも気づいていなかった自分の特徴を把握したり、どんな企業・業界で働きたいのかを明確にできたりといったメリットがあります。
自己分析に取り組む際は、以下のステップで取り組むと効率よく自分の特徴を明確にできます。
自己分析のおすすめステップ
- 頑張ったこと、楽しかったこと、つらかったことなどテーマを1つ決める
- テーマに関連する経験を洗い出す
- それぞれに対して「なぜ?」を繰り返し、それぞれのエピソードを具体化する
- 複数のテーマでの具体化を繰り返す
- 分析内容を共通点や相違点をもとに整理する
- 整理した内容をもとに将来像やビジョンを明確にする
このステップで自己分析すれば、過去の自分の経験から価値観を明確にして、そこから今の自分自身や理想の将来像を把握できるようになります。
自己分析ができている学生は、自分の価値観や強みを具体的なエピソードを交えて説明でき、面接での説得力が高まります。
また、企業が求める人物像と自身の特長を結びつけて伝えられるため、志望度や適性が評価されやすいです。
一方、自己分析が不十分な学生は、回答が抽象的で表面的だったり、深掘りされると矛盾が生じることがあります。
自己分析の有無はそのまま面接の印象に直結すると感じます。
自己分析についてより詳しく知りたい人は、以下の記事もチェックしてみてください。内定につながる誰でもできる自己分析法を解説しています。
②他己分析を交えて客観的な自分の特徴を把握する
自己分析を終えたら、それをもとに他人が抱く自分の印象や強み・弱みなどを整理しましょう。自己分析と客観的な視点を照らし合わせて比較することで、評価する側を意識した自己アピールにつなげやすくなります。
また、自己分析はあくまで主観的な分析であるため、自分が思い描いた自分像にとらわれている可能性がある点には留意しておきましょう。
他己分析によって客観的な視点を入れることで、事実と解釈を分けて整理できるため、本当の自分を理解しやすくなります。
| 事実 | 解釈 |
|---|---|
| 実際に起こったこと、現実に存在する事柄 | 事実に対する自分の考えや意見 |
意識的に解釈を取り払って事実をとらえ、それをもとに自身や周りの解釈を再度チェックすることでより自分の特徴が明確になります。
③就活の軸を明確にする
自己分析と他己分析ができたら、それらをもとに就活の軸を明確にします。自分の価値観にもとづいて最も大切な要素や譲れない条件をリストアップしましょう。
リストアップした要素・条件に優先順位をつけることで、就活の軸が明確になります。
そして、優先順位をつけた後は、どこまでが絶対譲れない条件なのか明確にしてください。譲れない条件と他の要素次第で妥協できる条件の線引きをしておけば、自分に合う業界・企業を選びやすくなります。
一方で、軸を明確にしなければ入社してから後悔する可能性が高まります。ミスマッチのリスクを最小限に抑えるためにも、事前に自分の軸をはっきりさせておきましょう。
④自分の軸に合う業界・企業を選定する
就活の軸を明確にできたら、次は軸にもとづいた業界・企業選定に移りましょう。軸が明確になっていれば、さほど迷わず業界と企業を絞り込めます。
エントリー先を絞り込むには、まず各業界・企業の特徴を知る必要があります。
まずは自己分析で明確になった自分の価値観をもとに興味のある業界を絞り込み、そこから業界・企業研究でそれぞれの特徴を整理しましょう。
業界・企業分析の効果的なやり方は、それぞれ以下の通りです。
| 具体的な業界分析の方法 | 具体的な企業分析の方法 |
|---|---|
| ・業界地図を見る ・書籍やニュースをチェックする ・業界団体のホームページ(HP)を見る ・合同説明会に参加する | ・就活四季報を見る ・企業HPを見る ・インターンに参加するOB・OGを訪問する・会社説明会に参加する |
上記を利用して、自分の軸に合った業界、企業を絞り込みましょう。
業界や企業の実態を把握するには、業界地図で業界全体の動向やトレンドを把握し、企業HPで企業の理念や事業内容を確認するのがおすすめです。
また、就活四季報やOB・OG訪問を活用すれば、具体的かつ実践的な情報を得ることができます。
業界・企業選定を進めている学生に役立つ情報をまとめた記事も、合わせてチェックしてみて下さい。以下を参考にすれば、よりスムーズに就活を進められます。
合同説明会の持ち物
合同説明会の持ち物15選|必要な物からお役立ちアイテムまで紹介
就職四季報
就職四季報の活用方法! 就活を有利にするポイントや読み方を伝授
インターンの探し方
インターンの効果的な探し方8選を学年別で解説! ありがちな失敗も
⑤企業分析を通じて個々の企業の違いを明確にする
自分の価値観・考え方に合いそうな企業を絞り込めたら、個々の企業分析をおこないましょう。それぞれの企業を分析してそれぞれの特徴を整理・比較することで、それぞれの企業の特徴がより明確になります。
企業分析に取り組む際は、以下のポイントを中心にそれぞれの特徴をまとめましょう。
企業分析で着目すべき項目
- 仕事内容
- 社風
- 企業理念
- 給料・福利厚生
- 労働時間・労働条件
- 将来性
- 転勤頻度
- 離職率
- 選考時期
企業ごとに上記をまとめて企業間で比較すると、各企業の特徴や強み・弱みをとらえられます。
企業分析の方法をチェックしたい方は以下の記事もチェックしてみてください。具体的な方法や注意点を明示しながら詳しく解説しています。
面接官からの評価が点数でわかる! 本番に備えて面接力を測定しよう!
自分が面接官の目にどう映っているか、きちんと把握できていますか?
「面接力診断」では、あなたが面接本番でどれほどの力を発揮できるかを100点満点で測ります。
39点以下だと実力を発揮できていない可能性が高いです。診断結果から改善策を提案するので、本番に向けて対策しましょう。
- もうすぐ初めての面接がある人
- 自信のあった面接に落ちてしまった人
- 面接への不安を和らげたい人
⑥自己分析と企業分析を擦り合わせて志望動機を作る
それぞれの企業の特徴を明確にできたら、再度自分の就活軸と照らし合わせて自分に本当に合う企業を選定しましょう。自分に合うと感じた企業や理想の将来像を実現できそうな企業をリストアップし、エントリーの準備を進めます。
このとき、エントリーする企業が多すぎても少なすぎても就活をスムーズに進めづらくなります。それぞれの選考時期をチェックして、自分の負担にならず、応募先が少なすぎて不安にならない企業数を残してエントリーしましょう。
人によって感じ方や考え方は異なるため一概には言えませんが、おすすめは20〜30社前後です。
エントリーする企業が決まったら、早速志望動機の作成に着手します。ここまで取り組んできた自己分析と企業分析を擦り合わせて、自分の価値観にもとづいた志望動機を作成しましょう。
- 自己分析と企業分析を擦り合わせた結果、その企業にアピールできる経験やスキルがないとわかった場合、その企業を受けることは諦めるべきでしょうか。
価値観やポテンシャル、成長意欲も評価するためすぐに諦める必要はない
まず、直接的なスキルがなくても、「今は直接的なスキルがないが、成長するために何をしてきたか」や「どのように貢献したいと考えているか」を具体的に伝えることが重要です。
次に、企業が求める人物像を再確認し、自分の価値観や強みがその基準に当てはまる場合は、それを志望動機として明確に伝えましょう。
たとえばチャレンジ精神やチームで働く力など、求められる人物像が幅広いケースでは、自分の経験や特性が少しでも当てはまるのであれば、それを強調した志望動機を作成できます。
さらに、選考を通じて自分に合う企業を見つけるという視点を持つことも重要です。
その企業に合わないと感じた場合でも、他の企業で自分をより活かせる場が見つかる可能性があるため、応募を続けながら、ほかの選択肢も視野に入れて行動しましょう。
最終的に「アピールできる経験やスキルがない」と感じても、柔軟に考え、視点を変えたり、工夫して伝えることで道が開けることがあります。
可能性を最大限に広げながら就活に取り組んでください!
志望動機作成の際は、以下の記事も参考にしてみてください。志望動機作成ででた不安や疑問を解消して、スムーズに志望動機を作成できますよ。
志望動機
志望動機例文35選|基本とプラスアルファで差別化するコツ
志望動機の作り方
志望動機の作り方大全|就職支援のプロが好印象を残すコツを解説
志望動機の構成
志望動機はこの構成で決まり! 盛り込む6要素と伝える順番を解説
自分史
自分史のテンプレ3選! 例文付きで当てはめるだけで自己理解が深まる
⑦ES作成・面接対策に移る
⑦ES作成・面接対策に移る
- 一次面接を通過する方法
- 二次面接を突破する方法
- 最終面接で内定を勝ち取る方法
志望動機が固まったら、そのままエントリーシート(ES)作成に移りましょう。自己分析や企業分析をもとにESを作成すれば、それぞれの企業に自分の魅力を最大限アピールできます。
また、ES作成と並行して面接対策も進めると効果的に就活を進められます。面接は採用・不採用にかかわる面接の重要な選考ステップであるため、時間をかけて対策しましょう。
企業は、就活の面接に関して段階によって異なる目的を持っているため、それぞれの対策法も異なります。
そこで、ここからは各ステップの面接の特徴や目的、具体的な対策方法を解説します。各面接の特徴を捉えて目的に合った対策を講じ、着実に専攻を進めましょう。
一次面接を通過する方法
一次面接とはESの選考を通過したあとすぐに実施される最初の面接です。基本的なビジネスマナーやコミュニケーション能力をチェックし、大勢の候補者から自社に合う可能性がある人材に絞り込みます。
一次面接を通過する具体的な方法は、以下のとおりです。
一次面接を通過する方法
- 身だしなみや言葉遣いをなどの基礎を徹底する
- 面接官からの質問にスムーズに受け答えする
- 自分のスキルや経験などのプロフィールをわかりやすく伝える
一次面接では自分の魅力を論理的に伝え、自社にマッチする可能性が高いと思ってもらうことが肝心です。基本的なマナーやコミュニケーション能力の基礎が整っていることを示し、自分の特徴や価値観、考え方をわかりやすく伝えましょう。
なお、一次面接は面接官複数に対して学生一人であったり、面接官複数に対して学生も複数であったりなど、さまざまな形式があります。
どれも時間は短い傾向があるため、簡潔に伝えることを意識してください。
失敗談や自分の短所を具体的に話せるかが、チェックポイントになります。
理想の自分と今の自分の違いを理解できていると、嘘をつかずに今後の向上意欲を伝えられます。
具体的な努力目標も伝えると、話に説得力が生まれます。
面接の不安を解消! 本番前に面接力を測って弱点を発見しよう
不安を抱えたまま面接本番に臨むと、面接官に好印象を残せず、内定が遠のいてしまう可能性があります。
そんなときこそ「面接力診断」を受けましょう。
簡単な質問に答えるだけで自分の弱点がわかり、改善方法も提案してもらえます。ぜひ活用して面接を突破してください。
- 近く面接本番を控えている人
- 自分の面接の改善点を知りたい人
- 過去の面接で力を発揮しきれなかった人
二次面接を突破する方法
二次面接の目的は、志望者が自社に必要な人材か見極めることです。一次面接より踏み込んだ質問を通じて各志望者の価値観や考え方を深掘りし、企業理念・文化・風土とのマッチ度を測ります。
二次面接を通過する具体的な方法は、以下のとおりです。
二次面接を通過する方法
- その企業に入社したい理由を明示する
- 自分と企業とのマッチ度の高さを論理的に示す
- 自分が企業に価値提供できることを明示する
二次面接は、自分がその企業に入りたいという熱意を示し、同時にその企業にとって自分が有用な存在であると示す必要があります。
一次面接と比べて時間が長めで価値観や考え方が深掘りされるため、事前に自己分析・企業分析を深めて本番に臨みましょう。
二次面接は深掘りが中心となり、嘘がバレやすいです。一貫性のない回答や具体性に欠ける話はすぐに見抜かれるため、正直で論理的な回答を心掛けましょう。
通過のポイントは、まず企業への熱意を具体的に示すことです。
自分の経験や価値観と企業の理念や文化を結びつけ、自分と企業とのマッチ度の高さや自分が貢献できる理由を明確に伝えましょう。
また、自己分析を徹底し、具体的なエピソードを準備しておくことで深掘り質問にも対応でき、説得力のある受け答えが可能になりますよ。
最終面接で内定を勝ち取る方法
最終面接の目的は、志望者と企業が本当にマッチしているかの最終判断を下すことです。より役職が高い社員や年次が上の社員が面接官となり、本当に採用しても良いかの最終チェックがおこなわれます。
最終面接を通過する具体的な方法は、以下のとおりです。
最終面接を通過する方法
- 入社意欲の高さを明示する
- 自分と企業とのマッチ度の高さを論理的に示す
- 自分の魅力や貢献できるポイントを再度アピールする
基本的に意識すべきポイントは二次面接と同じです。ただし、面接官は二次面接より役職が高い傾向があるため、より厳しい目で評価されます。
二次面接の反省を活かし、より論理的に上記3点を伝えられるように事前準備を徹底しましょう。
- 最終面接では嘘をついてもその後に辻褄を合わせる必要がないため、嘘がバレづらいのではないでしょうか?
バレる以前に嘘をつくことは相手を見くびる行為である
「嘘をついてもばれないだろう」と考えるのは、相手を見くびっていることになります。
そのようなこざかしさこそが、最終面接で落とされる原因となるので、嘘は絶対にやめておきましょう。
最終面接を担当する経営幹部は、それぞれ独自の人生哲学や人間観を持っています。
そのため、最終面接では面接対策本に載っているような典型的な質問はされず、経営幹部独自の視点から応募者に向き合ってきます。
特に最終面接でフォーカスが当たるのは、過去エピソードより、未来のことです。
人間同士の真剣勝負と心得、自分に話せる精一杯の未来の目標を伝えましょう。
面接に関する疑問解消や就活の流れの把握には以下の記事も役立ちます。ぜひチェックして、就活の不安を解消しておいてくださいね。
面接の質問
面接の質問150選! 回答例から答え方まで質問対策を完全網羅
対面面接のマナー
対面面接のマナー|入退室の流れからミスのリカバリーまで解説
面接のマナー
絶対に落とせない面接のマナー! 「即不合格」にならないための作法
就活の流れ5ステップ
就活の流れを5ステップで解説! 時期別の選考対策も紹介
嘘なしの就活で自分の価値観に合う企業の内定を勝ち取ろう!
この記事では就活で嘘をつくべきでない理由や、嘘がバレた場合のリスクなどを具体的に解説してきました。就活での嘘はバレる可能性も高く、バレた際のリスクも高いため避けるべきです。
就活は能力やスキルがすべてではなく、成果を達成したプロセスやそこに対する考え方・姿勢も大いに評価されます。そのため嘘をついて自分を大きく見せるよりも、真実を伝えてそこで得た学びや意識した点を伝えた方が自分の魅力を効果的にアピールできるのです。
嘘なしの就活で志望企業の選考を勝ち抜き、気持ちよく理想のキャリアの一歩目を踏み出しましょう。
アドバイザーコメント
嘘がバレたときのリスクは計り知れない
就活は、自分を大きく見せたい気持ちから嘘をつこうか迷うこともあるでしょう。しかし、嘘は面接官に見抜かれやすく、バレた場合のリスクは計り知れません。
内定取り消しや評価の低下だけでなく、自分の信頼を大きく損なう結果になりかねません。
面接官は、能力だけでなく誠実さや考え方、価値観を含めた人間性を重視しています。成績や経験に欠ける部分があっても、それを正直に伝え、そこから学んだことや乗り越えた経験を語る方がはるかに魅力的です。
嘘ではなく、自分の強みや努力を正直に伝えることで、面接官の心が動きます。
たとえば、「単位を落とした経験がある」という学生も、その背景にある理由や、その後の努力を具体的に説明すれば、向上心や責任感をアピールできます。
企業は失敗をどう受け止め、次にどう活かすかを見るため、正直に語ることで未来の可能性を期待できます。
本来の自分をアピールすることが本当に合った企業を見つけるためのカギ
就活は競争ではなく、自分に合った企業を見つけるプロセスです。嘘をつかず、本来の自分をアピールすることが、ありのままの自分を受け入れてくれる企業に巡り合うために、誠実な姿勢を大切にしましょう。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

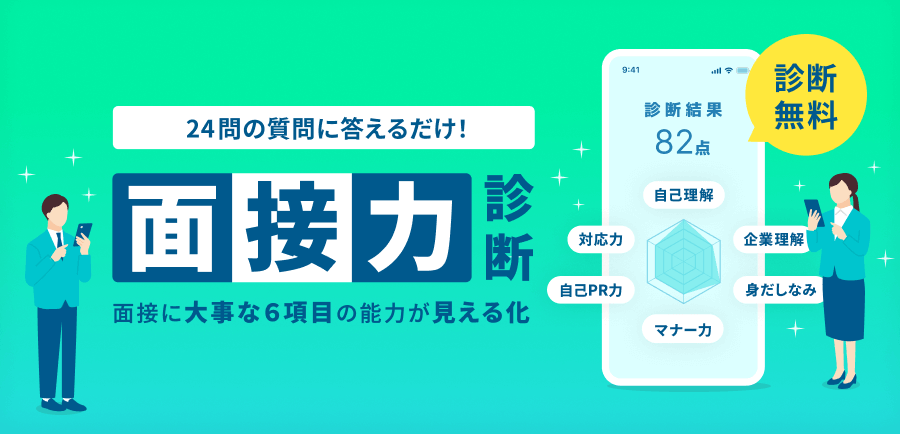









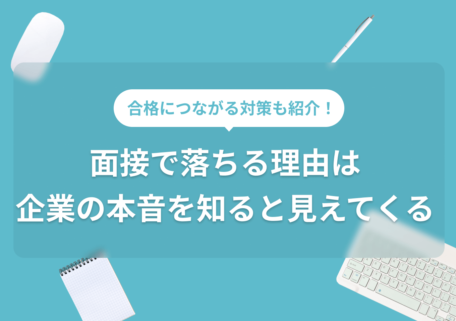








3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント
Arisa Takao〇第二新卒を中心にキャリア相談を手掛け、異業種への転職をサポートする。管理職向けの1on1やコンサルティング業界を目指す新卒学生の支援など年齢や経歴にとらわれない支援が持ち味
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/公認心理師
Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表
Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う
プロフィール詳細