この記事のまとめ
- 新卒よりも既卒就活が厳しいと言われることには4つの理由がある
- 既卒の内定率をチェックして実情を把握しよう
- 採用経験者だからこそわかる既卒のリアルな就活事情を解説
インターネット上で「既卒就活は厳しい」という言葉を目にし、不安に思っている既卒者もいるのではないでしょうか。
日本では、新卒よりも既卒就活のほうが難しいのは事実です。しかし既卒採用をおこなっている企業もあるため、ポイントを押さえて就活に取り組めば内定獲得のチャンスはあります。
この記事ではキャリアコンサルタントの吉野さん、古田さん、吉田さんのアドバイスを交えつつ、既卒就活が厳しいと言われる理由や既卒に対する評価基準を解説します。既卒就活に取り組んでいるものの内定を獲得できるか不安な人は、ぜひ参考にしてください。
【完全無料】
社会人におすすめ!
就職・転職前に使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:年収診断
志望職種×あなたの経験で今後の想定年収を確かめよう!
4位:WEBテスト対策模試
模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます
5位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
既卒就活を成功させたいなら内定獲得が厳しい理由を明確にしよう
「既卒就活は厳しい」と聞いて、就活に対する悩みが大きくなっている人もいるかもしれません。既卒の就活が厳しいと言われる理由を正確に理解することで、自分が置かれた状況を客観的に把握し、効果的な就活対策を講じることができるようになります。
この記事では、既卒就活が厳しいと言われる4つの理由を詳しく解説します。既卒就活は新卒とは異なる基準で評価されるため、戦略を誤ると選考突破は難しいです。しかし、企業がどこを見ているのかを理解し、適切な準備をすれば、内定の可能性を高めることは十分可能です。
また記事後半では、既卒に対する評価基準や内定獲得のポイントについても解説するので、厳しいと言われる選考が不安な人はぜひ最後まで読んでください。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。
これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。
また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。
既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。
新卒より不利? 既卒就活が厳しいと言われる4つの理由
新卒より不利? 既卒就活が厳しいと言われる4つの理由
- 日本の就活市場では新卒採用を優先する傾向にあるため
- 企業から就業意欲が低いと思われるため
- 実務で活かせるスキルや経験が少ないため
- 大学のキャリアセンターを利用しにくく就活の相談相手が少ないため
新卒採用を中心におこなう日本の就活では、既卒者は苦戦する可能性があります。その背景や原因を知らないまま就職活動を進めると、不利な状況に対応できず、内定獲得がさらに難しくなるかもしれません。
そこで、まずは既卒就活が厳しいと言われる理由を解説します。自分に合った戦略を立てるための第一歩として、なぜ既卒就活が難しいのかを把握しましょう。
そもそも既卒についての理解が浅い人は、こちらの記事を読んで自身が該当するか確認してください。
①日本の就活市場では新卒採用を優先する傾向にあるため
日本の就活市場は新卒一括採用の文化が根強いのが特徴的です。長期的な視点で人材育成ができたり、複数人に同時に教育できたりするなどの理由で、多くの企業では新卒採用を優先する傾向にあります。
その結果、既卒者向けの求人は少なく、そもそも既卒採用の枠を設けていない企業もあるのです。また「新卒採用で予定の人数を確保できなかった」「早期退職者の補充が必要」といった背景がある場合に既卒採用をおこなう企業が多いため、求人数も限られています。
独立行政法人労働政策研究・研究機構の若年既卒者の雇用動向によると、2014年〜2020年の大学卒の若年入職者のうち、新卒就職者は70.2%、既卒者は29.7%でした。
このような結果からも新卒採用が優先される日本の就活市場では、既卒者が厳しいと言われる理由がわかります。
既卒者OKの採用枠であれば、新卒が特別優遇されることはなく、同じ基準での実力勝負になります。
人気企業・大手企業は応募者が多いため、そもそも既卒者を対象に含めないこともあります。その結果、既卒は不利と感じられるのかもしれません。
②企業から就業意欲が低いと思われるため
部活動や留学などの前向きな理由ではなく、就職活動をしていなくて既卒になった場合、担当者から「就業意欲が低いのではないか」と懸念を抱かれる可能性があります。
大学在学中であれば周りの学生と同じタイミングで就職活動を始められますが、「それでもしなかったのは働きたくないからなのではないか」と先入観を抱かれてしまう可能性があるのです。
また、新卒採用は長期的な人材育成を目的としている側面もあるため、働くことに前向きではないなら早期離職を心配される恐れもあります。
加えて、新卒採用ではポテンシャルを重視される傾向があるなかで、「新卒で内定を得られなかったのは人物面に問題があるのではないか」という評価を受けることも少なくありません。
このような理由から、既卒者は「就業意欲が低い」「長く働いてくれないかもしれない」といった先入観を持たれやすいのです。このようなマイナスイメージを払拭するのは容易ではないため、結果的に既卒就活が厳しいとされる一因になっています。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。
これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。
また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。
既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。
③実務で活かせるスキルや経験が少ないため
ポテンシャルを重視する新卒採用と違い、既卒者はポテンシャルだけで評価されることは少なく、一定のスキルや経験が求められる傾向にあります。社会人経験のある中途採用者と同じように、実務で活かせるスキルや経験が必要とされるケースも多いのです。
しかし、既卒者のなかには大学卒業以降に専門分野で経験を積んだり、スキルを磨いたりしてこなかった人もいるのも事実です。実務で活かせるスキルや経験が少ないため、即戦力の人材を求める企業や業種での内定獲得が難しくなります。
また、スキルや経験が求められにくい未経験OKや既卒歓迎といった求人は、職種や業界が限定されやすいです。そのため希望する分野や職種を絞っていれば、就職がさらに難しくなるケースもあります。
④大学のキャリアセンターを利用しにくく就活の相談相手が少ないため
大学のキャリアセンターは、応募する業界の絞り方やエントリーシート(ES)の添削、模擬面接など、就活におけるさまざまな相談に乗ってくれます。
ただし、キャリアセンターは大学在学中の学生向けの支援が中心であるため、既卒者が利用できないことがほとんどなのです。
また、既卒者になると同じ状況で就職活動をしている仲間が少ないため、情報共有やモチベーションを保つ場面も限られます。
キャリアセンターの人や就活仲間といった相談相手がいないと、客観的な意見やフィードバックを受ける機会が減り、自分の課題や改善点をそのままにした状態で選考に臨んでしまう恐れがあります。
このように、孤独になりやすい既卒者は就活情報やアドバイスが不足しやすく、選考対策や応募企業の選定において新卒者よりも不利になる傾向があるのです。
すでに既卒の人に関しては、気持ちを切り替えて就活をしていく必要があります。過去の経歴は変えられないので、ここからどうキャリアをデザインしていくのかという未来志向が必要となります。
やれることはたくさんあるのでやるべきアクションを明確にしていきましょう。
データで確認! 2023年度の既卒就活の内定率
既卒就活に取り組んでいる人にとって、ほかの既卒者がどのような結果を出しているのか気になるのではないでしょうか。既卒者の内定率に関するデータを確認することで、就活市場の現状を客観的に理解し、次の行動につなげるヒントを得られます。
マイナビキャリアリサーチLabの2023年度既卒者の就職活動に関する調査によると、既卒者の内定保有率は34.8%で、前年が44.8%だったので10%減少しています。
2020年から2022年にかけては上昇傾向にありましたが、2023年の調査では減少する結果になりました。
また、同社の2025年卒就職内定率(内々定率)の状況によると新卒の内定保有率は90%を超えていることから、既卒就活の厳しさがわかります。
ただし、内定保有率は活動量によって大きな差が見られました。在学中より「活動量が(かなり+やや)増えた」既卒者の内定保有率は 42.7% でした。
一方で「活動量が(やや+かなり)減った」既卒者の内定保有率は 25.2% に留まっていて、積極的に行動すれば既卒就活でも内定を獲得できる可能性が高まります。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。
これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。
また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。
既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。
当てはまったら厳しいかも! 既卒就活で内定獲得が難しい人の4つの特徴
当てはまったら厳しいかも! 既卒就活で内定獲得が難しい人の4つの特徴
- 大手に絞ってエントリーしている
- 誰にも相談せずに1人で対策をしている
- 既卒であることをネガティブに捉え過ぎている
- 既卒就活が不利であることを客観的に把握できていない
既卒就活に臨む際、自分が抱える課題や弱点を認識せずに進めると、内定獲得は難しいかもしれません。そして、それ以外にも内定獲得が難しい人には共通点が存在します。
ここからは、既卒就活で内定を得るのが難しいとされる人の特徴を解説します。自分がどれかに当てはまっていないかを確認し、改善点を見つけるきっかけにしてください。
既卒で大手企業への就職を目指している人はこちらのQ&Aも参考にしてみてください。
大手に絞ってエントリーしている
既卒就活で大手企業にこだわり過ぎると選択肢が狭まり、内定獲得のハードルは高くなります。日本の大手企業では新卒採用を優先する傾向にあり、既卒者を対象とした採用枠は少ないのが現状であることも理由の一つです。
また既卒者がエントリーできたとしても、ポテンシャルが重視される新卒や、経験やスキルのある中途採用者と競争する形になり、内定を獲得するのは難しいです。
一方で中小企業やベンチャー企業は、積極的に既卒採用に取り組んでいる傾向にあります。そのため、視野を広げて中小企業やベンチャー企業にも目を向けることで、内定獲得の可能性は大きく広がるでしょう。
既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう
既卒の就活では、限られた選択肢の中から自分に合った仕事を見つけることが重要です。しかし、本当に自分に合った仕事とは何か、見つけるのは簡単ではありませんよね?
そこでおすすめなのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの個性や強みに最適な仕事、そして、あなたが就活でアピールできるポイントが分かります。
自分に合った仕事を見つけ、自信を持って就活を進めるためにも、 ぜひ就活を始める前に「適職診断」を試してみてください。
②誰にも相談せずに1人で対策をしている
就活は情報戦の一面もあるため、適切なアドバイスを受けられる相談相手の存在が大事になります。相談相手がいないと、情報収集が不十分になりやすく、自分の弱点や改善点に気づかないまま選考に挑むことになりかねません。
また、客観的なアドバイスがないことで、ESや面接の対策が進まず、なかなか選考を突破できない可能性もあります。さらに誰にも相談せずに1人で進めても選考に落ちた原因を客観的に分析できないため、同じミスを繰り返すかもしれません。
こうした問題を避けるためには、後述する既卒就活に強いエージェントに登録するなどして、信頼できる相談相手を見つけることが大切です。既卒者からの相談に対応しているキャリアセンターもあるため、ホームページ(HP)を見て活用できるか確認してみてください。
就活はストレスが多いため、第三者のサポートがなかったことでモチベーションを維持できず、ニートになってしまった人もいます。
相談相手がいるだけで就活がうまくいく可能性は確実に上がるのではないでしょうか。
③既卒であることをネガティブに捉え過ぎている
既卒であることを「自分に何か問題がある証拠」と考えてしまうと、自信を失い、面接や応募書類で自分の強みを十分にアピールできなくなります。また、そのような態度は面接官にも伝わり、マイナスの印象を持たれるかもしれません。
企業は既卒であることそのものではなく、空白期間をどのように過ごしてきたかを重視する傾向にあります。しかし、既卒期間をネガティブに捉え過ぎると、空白期間の説明を回避しようとしたり、自信を失って自分の魅力や強みを伝えられなかったりする恐れがあります。
既卒は就活を不利にする可能性がありますが、ネガティブに捉え過ぎる必要はありません。空白期間に得た学びや成長を整理し、前向きに伝えられるよう準備しましょう。
また「既卒=人生終了」と思っている人もいますが、決してそんなことはありません。暗い状況からの逆転方法はこちらの記事で解説しているので、確認して希望を見出してください。
④既卒就活が不利であることを客観的に把握できていない
ネガティブに捉え過ぎる必要はありませんが、既卒就活が新卒就活よりも不利になる可能性が高いことは事実です。その事実を把握せずに新卒就活と同じような対策をしていると、企業が既卒者に求める能力や経験を押さえた選考対策ができないため、内定獲得が難しくなります。
また、既卒就活の現実を理解していないと、自分の強みをアピールするチャンスを逃す恐れもあります。たとえば、企業が既卒者に対して重視する既卒期間の過ごし方や入社後の即戦力としての可能性をアピールしなければ、ほかの応募者との差別化が難しいのです。
既卒就活における不利な点を冷静に受け止め、それをカバーするための準備や戦略が内定を勝ち取る近道です。現状を把握して効果的な対策を講じるためにも、客観的な視点を忘れないようにしましょう。
あなたが受けないほうがいい職業をチェックしよう

・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
本当に厳しい? 既卒のリアルな就活事情を採用経験者が解説
「新卒採用が重視されるので既卒就活は厳しい」「キャリアセンターを活用できないので相談相手が少ない」との意見を聞いて不安に思っている人もいるのではないでしょうか。
ここでは多くの採用選考を経験してきた吉田さんに、既卒のリアルな就活事情を尋ね、実際どれほど厳しいのかを深堀りしていきます。既卒就活の厳しさについて具体的な実情を知りたい人は、ぜひ注意深くチェックしましょう。
アドバイザーコメント
結論、既卒就活は厳しい
まず、既卒に対して門戸を開いていない企業があります。昨今は新卒の定義が変わっていますが、それでも実態としては、新卒しか採用していない、新卒以外は経験者採用のみといって受け入れていなかったりする企業は少なくありません。
次に、既卒であることになにか問題があるとみなされてしまうことが多いです。既卒になってしまった要因にもよりますが、そもそも現代の就活において既卒で就活をすることのメリットは皆無であり、そういった未来のことを考えられかったりこれだけ情報があふれているなかでリサーチできない人材とみなされ敬遠されるケースがあります。
また、シンプルに就活をしたが就職できずに卒業してしまった場合は、コミュニケーション力の低さ、行動力の低さ、自己理解の不足を懸念され、採用したいと思わない企業は多いです。
モチベーションの低下による負のループに陥ることも考えられる
そのようななかで就活をしていくと、普通の学生よりも選考通過率は低くなり、するとモチベーションが低下しアクション数も減少します。
そうなると、より持ち駒が少なくなりやすく、持ち駒が少ないなかで選考に落ちるとモチベーションが低下するといった負のループに入ってしまい、なかなか這い上がることができなくなります。
そういった状況をサポートしてくれる人もいないので、自力で克服することが困難になってしまいます。
何を見られている? 既卒に対する4つの評価基準
何を見られている? 既卒に対する4つの評価基準
- 既卒になった理由
- 既卒期間の過ごし方
- 既卒期間中に得た学び
- 就職の実現に向けた意思
企業は既卒者に対し、新卒採用で重視される傾向にあるポテンシャルだけでなく、これまでの経験や行動から見える意欲やスキルもチェックしています。そのため、何を評価されているのかを理解しないまま選考に臨むと、自分の強みをアピールしきれず、内定獲得につながらないかもしれません。
ここでは、企業が既卒者を評価する際に注目する4つのポイントを解説します。評価基準を把握し、自分がどの部分を強化すべきか考える際に役立てましょう。
①既卒になった理由
企業は既卒になった理由を通じて応募者の考え方や行動力を評価しています。そのため、選考過程で既卒に至った経緯を質問する可能性があります。
たとえば、部活動や留学のような前向きな理由は明確な目的があるため、企業にポジティブな印象を与えられることが多いです。一方で「就活準備が不足していた」「自己分析が不十分で進路を見定められなかった」といった消極的な理由は、マイナス評価につながりやすいです。
そのため、ネガティブな理由はそのまま伝えるだけでなく、改善点や反省点をセットで説明しましょう。たとえば「準備不足から内定を得られなかった反省を活かし、希望する業界の研究や資格取得に取り組みました」など、行動した結果を伝えるのがおすすめです。
- 就活が嫌だからという理由であまり目的もなく留学に行きました。留学の目的を質問されると、自信を持って回答できない気がします……
留学を通して成長したことを伝えるのが重要
「正直、就活が嫌だったので目的意識もなく…」という当時の気持ちを話しても問題ありません。大切なのは、留学を通じて自分がどのように成長したかを伝えることです。
海外での経験は、多くの気づきを与えてくれます。視野が広がったこと、新たな人との出会いがあったことなど、人間的な成長について具体的に伝えられると良いでしょう。
②既卒期間の過ごし方
既卒になった理由と同じくらい、既卒期間の過ごし方も既卒の就活では頻出質問といえます。そのなかで、空白期間を有意義に活用していたことを示せれば、既卒という不利な状況を強みに変えられます。
たとえば、「目指す業界で必要なスキルを身に付けるために資格取得に励んだ」「アルバイトやインターンシップを通じて社会経験を積んだ」などのポジティブな経験を伝えれば、担当者に前向きな印象を持たれる可能性が高まります。
既卒期間はただネガティブな情報として捉える人もいますが、取り組み次第では自分を成長させるための時間としてアピール可能です。自己分析を通じて空白期間に得た学びや経験を整理し、自信を持って伝えられるようにしておきましょう。
自己分析については以下の記事で詳しく解説しているので、確認して空白期間を振り返ってみてください。
自己分析マニュアル
自己分析マニュアル完全版|今すぐできて内定につながる方法を解説
自分史
自分史のテンプレ3選! 例文付きで当てはめるだけで自己理解が深まる
モチベーショングラフ
テンプレ付き|モチベーショングラフを駆使して自己分析を深めるコツ
③既卒期間中に得た学び
企業は既卒期間に「何をしてきたか」だけではなく、「どんな学びを得たのか」も評価しています。既卒期間が単なる空白期間ではなく、学びながら成長できた期間であることを伝えられれば、担当者にポジティブな印象を持たれる可能性が高いです。
たとえば、「アルバイトやインターンを通じて社会人としての責任感やコミュニケーション能力を養った」「資格取得を目指して努力を続けた結果、自己管理能力が高まった」など、行動と結果が結びついているエピソードは説得力があります。
また、「資格取得で培った管理能力を活かし、入社後はチームのスケジュールを管理しながら効率的に業務を進めたいです」のように、「得た学びを入社後にどう活かすか」という視点も大切です。
行動から得た学びの活かし方を明確にすることで、採用担当者に、あなたが入社後にどのような形で貢献できるのかをイメージしてもらいやすくなるからです。
既卒期間中に得た学びを伝える際は行動と結果、入社後の活用方法を整理することで、既卒期間を有意義に過ごせたことを印象付けられます。
④就職の実現に向けた意思
就活生の内定辞退を避けたい企業は、就職の実現に向けてどれだけ行動をしてきたかに表れる志望度の高さもチェックしています。単に意欲を伝えるだけではなく、就職するための行動がともなっているかが選考突破に向けて大切です。
たとえば「志望業界・企業で必要な資格を取得した」「適性があるかを確認するために、同じ業界・業種でアルバイトとして働いた」といった具体的な行動を示せれば、就職への真剣さを伝えられます。
このように就職の実現に向けた意思の強さは、具体的な行動で示せます。志望企業に対する熱意を示すエピソードがないか、空白期間の行動を振り返ってみてください。
できることから実践しよう! 厳しい既卒就活を突破するポイント6選
厳しい既卒就活を突破するポイント
厳しいと言われる既卒就活ですが、正しい方法を実践すれば内定獲得を目指せます。ただし、「どうすれば既卒就活を成功させられるのか」「新卒就活と違う対策が必要なのか」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
ここからは、既卒就活を成功させるために取り組むべきポイントを紹介します。順番通りに取りかかる必要はないため、自分にできることから始めてみましょう。
①既卒になった理由を簡潔に説明できるようにする
既卒になった理由が曖昧であったり、ネガティブな印象につながる内容だと、「就業意欲が低いのではないか」や「働く姿勢に問題があるのでは」と判断される可能性があります。
新卒一括採用が主流である日本において、ほかの学生とは違う選択をしている人を採用することには不安を感じるためです。
面接でも高確率で質問されるため、既卒になった理由は簡潔に説明できるように準備しておきましょう。部活動や留学のような前向きな理由であれば、そのまま伝えて問題ありません。
しかし、ネガティブな理由で既卒になった場合、単に「就活に失敗しました」と伝えるだけでは、マイナス評価につながる可能性が高くなります。その場合、何が原因で失敗したのか、そしてその失敗をどのように反省し、行動を改善したのかを説明することが大切です。
「希望する業界に絞り切れずどこも対策が不十分だったので、現在はその反省を踏まえて自己分析や業界研究に注力しています」といった形で、改善への努力をアピールしましょう。
既卒就活を成功させる方法は以下の記事で解説しているので、自分の状況に合うものを選んで読んでみてください。
既卒の就活
既卒の就活を確実に成功させる5箇条! ストレスなく進める秘訣
2年目の既卒
既卒2年目でも逆転勝利! あなたにぴったりな企業に会う方法を伝授
フリーターから正社員
フリーターから正社員になる7つのコツ! おすすめの職種も紹介
- 就活をサボっていたら既卒になってしまいました。それでも正直に伝えるべきですか?
嘘はつかずに工夫を伝え方で既卒になった理由を話そう
何でも正直に話せばいいというものでもありませんが、嘘や隠し事をすることで自分が苦しくなったり、後で嘘だとわかった時に信頼を失ったりする可能性もあるため、伝え方を工夫して伝えるのがよいと思います。
就活をサボってしまった理由や、その期間に何をしていたのかなどを説明すれば、成長や反省の姿勢をアピールすることもできます。過去は変えられませんが、これからどうするかは自分で決めて変えることができます。
面接官も人間です。失敗や挫折を理解し、そこからどう立ち直ったのかを評価してくれることもあります。
人生、やり直しは何度でもできます。諦めないことが肝心なのではないでしょうか。
②既卒期間におこなっていたことを整理する
空白期間の過ごし方次第では、大きな成長を遂げている可能性があります。既卒期間になった理由と一緒に何をおこなっていたことも質問されるため、空白期間中に考えていたことや行動、そこから得た学びなどを回答できるようにしましょう。
振り返る際は空白期間の年表を作成し、その期間に取り組んだことや考えたことを、自分史やマインドマップでリストアップするのがおすすめです。
自分史とは
自分の半生を書き起こす自己分析手法。経験とその時に感じたことを文章にする。
マインとマップとは
項目から連想することを書き出していく自己分析手法。
頭で考えて終わるよりも書きながらの方が思考を深められるうえに、空白期間の出来事を抜け漏れなく整理できます。
自分史の活用方法は以下の記事で解説しているので、やり方を確認しながら実際に取り組んでみてください。
③既卒就活に強いエージェントに登録する
相談相手がいなくて孤独になりやすい既卒就活は、新卒の就活と比較してアドバイスやフィードバックを受けられる回数が少なくなりやすいです。しかし、就活では悩みを相談できたり、面接やESの対策をサポートしてくれたりする存在はが重要であるため、エージェントに登録しておくことがおすすめです。
特に既卒者向けの求人情報が豊富で、これまでに多くの既卒者をサポートしてきた経験のある以下のようなエージェントをチェックしておきましょう。
既卒就活に強いエージェント
- キャリアパーク就職エージェント:6,800社の求人を取り扱っている
- RE就活:社会人経験を問わない求人数が豊富にある
- JAIC(ジェイック):求職者向けの研修を実施している
既卒就活に強いエージェントでは、一般的な求人サイトでは見つけにくい既卒歓迎の求人や非公開求人を取り扱っているケースがあります。
また、既卒者の選考対策に精通したキャリアアドバイザーが、ES添削や模擬面接などを通じて内定獲得に向けてサポートしてくれます。大学のキャリアセンターを利用できないなどの理由で相談相手がいない既卒者は、エージェントを積極的に活用してください。
エージェントの良し悪しは担当者次第といわれます。担当者と信頼関係を築けるか、紹介される案件に納得感があるかが、成功のカギとなるでしょう。まずは一社に登録し、実際の対応を見てから、他社にも登録するか検討してみてはいかがでしょうか。
④志望分野に活かせる資格やスキルを身に付ける
社会人経験がなくても、資格取得やアルバイト、インターンなどで志望分野に活かせる知識やスキルを習得できます。たとえば、経理として働きたい人が簿記を取得して経理のアルバイトをしていれば、経理職の即戦力として働けることをアピール可能です。
また、資格や知識、スキルが身に付いたこと以上に、「志望分野に必要な知識やスキルを習得するために努力した」という姿勢が評価につながるケースもあります。なぜなら、前向きな姿勢は仕事に必要なスキルを身に付けるための計画性や行動力をアピールできるためです。
志望分野が明確に決まっているなら、就活と並行しながら入社後に役立つ資格や知識、スキルの習得に向けて取り組みましょう。
就職活動で簿記をアピールする方法はこちらの記事で詳しく解説しているのであわせて参考にしてみてください。
業界ごとの役立つ資格は以下の記事で紹介しているので、志望業界にはどんな資格が必要なのか確認してみてください。
IT
厳選15選|目指すべきIT資格の見つけ方から勉強方法まで徹底解説
金融
金融業界を徹底調査! 押さえておくべきトレンドや対策まで大解剖
ディベロッパー
ディベロッパー大手6社を徹底比較! 人気業界を突破する5つの正攻法
動物と関わる仕事
動物とかかわる仕事26選|資格のありなしと未経験からの目指し方
公務員
公務員で有利な資格って? 職種別の資格とアピールのコツも解説
秘書
秘書に向いている人の特徴5選! 仕事内容や有利になる資格も解説
心理学
仕事で心理学を活かす方法|おすすめの資格と13の職種を紹介
就職に有利な資格
就職に有利な資格33選! 業界・状況別であなたに合った資格を解説
⑤採用枠が少ないため幅広い業界・業種に興味を持つ
既卒採用は新卒採用に比べて枠が少なく、志望業界や職種を狭め過ぎると、応募できる求人が限られてしまいます。そのため、既卒就活では幅広い業界や業種に興味を持ってみましょう。
たとえば、「営業職にしか興味がない」というスタンスではなく、営業に関連するマーケティング職やカスタマーサポートなどにも目を向けることで、応募できる求人数を増やせます。
また、さまざまな業界・業種の企業と出会うには、既卒者向けの合同説明会やオンラインで参加できる説明会への参加がおすすめです。興味がなかった業界・業種でも、仕事内容や働き方を聞いて理解を深めれば、応募先の選択肢となる可能性があります。
さらに幅広い業界・業種に目を向けることで、内定獲得の可能性を高められるだけではなく、自分の適性や興味を再発見するチャンスにもなります。柔軟な姿勢を持ちながら、さまざまな企業と接点を作ってみましょう。
合同説明会やWeb説明会への参加方法や注意点は以下の記事で解説しているので、参加して選択肢を広げるのに役立ててください。
既卒者向けの求人が多い業種・業界共通しているのは、実務経験やスキルを重視するところです。
たとえば、IT・ソフトウェア業界や小売業・流通業、マーケティング・広告業界などがあります。その他、ホテルや旅行業界も多いと感じます。
⑥経験を積んだ後に転職する道もあることを理解する
求人数が限定的な既卒就活では、最初から理想の企業や職種に就けるとは限りません。業界・業種を絞ると内定獲得が難しい恐れもあるため、経験を積んだ後に転職する道もあることを理解しておきましょう。
たとえば、希望する職種や業界とは異なる分野で働き始めたとしても、そこで培ったスキルや経験を武器にして転職活動をおこなえます。営業職ならコミュニケーションスキルや交渉力を、事務職ならデータ管理や資料作成能力を習得し、既卒就活で志望度の高かった業界・業種で活かせる強みを作れるのです。
また、社会人経験を積んでから転職活動を始めれば、第二新卒としてエントリーができます。第二新卒は社会人経験が1〜3年程度の若手人材を対象にした採用枠で、既卒採用枠よりも求人数が多い傾向にあります。
このような理由から、既卒就活は短期的な成功ではなく、長期的なキャリア形成を考えながら取り組むのがおすすめです。
第二新卒については以下の記事で詳しく解説しているので、どのようなメリットがあるのか、志望業界に入りやすくなるのか考えながら読み進めてみてください。
第二新卒で大手を狙う方法
第二新卒で大手を狙う必勝法! 採用実績のある企業100選も紹介
いつまで第二新卒か
第二新卒に該当するのはいつまで? ベストな転職時期を見極める方法
第二新卒で門前払いされるかも……と感じでいる人はこちらのQ&Aも参考にしてみてください。第二新卒の就活についてキャリアコンサルタントが回答しています。
アピールして差別化を図ろう! 既卒ならではの強み
既卒という立場をネガティブに捉えがちですが、実は既卒ならではの強みをアピールすることもできます。空白期間の過ごし方や、既卒だからこそ得られた経験・成長は、ほかの応募者にはない貴重なポイントになるのです。
ここでは、既卒ならではの強みを具体的に解説します。それぞれ自分の言葉で説明できるようになっておくことで、あなたの魅力が担当者に伝わりやすくなります。独自の強みの発見にもつながるため、空白期間を振り返ってみてください。
空白期間で得た自己成長やスキル
企業は、空白期間をどのように過ごし、その期間で得た成長やスキルを入社後にどう活かすつもりなのかを重視する傾向にあります。そのため、自分を成長させるための時間として活用したことを伝えることが重要です。
たとえば、「アルバイトで接客業に携わり、強みの顧客対応力やコミュニケーション能力をさらに高めた」「資格取得を目指して計画的に学習を進め、スケジュール管理能力を養った」など、具体的な取り組みとその成果を示すことで、空白期間をポジティブに捉えて過ごしたことを伝えられます。
また、空白期間で得た自己成長やスキルを、どのように入社後の業務に活かすつもりなのかを具体的に伝えることも大切です。空白期間に自己成長のために時間を使っていたことや、得たスキルを就職後にどう活かすかを明確にすることで、志望度の高さをアピールできるからです。
加えて、「接客業で培った傾聴力を活かし、コミュニケーションを通じて顧客の潜在的な課題を引き出したい」など、入社後の貢献内容を明確にすることで、担当者はあなたが活躍する姿をイメージしやすくなります。
周囲と差別化するためにも、空白期間で得た自己成長やスキルと合わせて入社後の活かし方も一緒に伝えましょう。
- もう選考が迫っていて、資格取得やアルバイト、インターンは現実的ではありません。選考直前でも、自己成長やスキルを積み上げる方法はありますか。
選考直前でも自己成長やスキルを積み上げる方法はたくさんある
就活において基本的にやるべきことは3点、自己分析と企業研究と面接対策です。とにかくこの3点のうち、一つでもいいので徹底的に実施することをおすすめします。
・自己分析を徹底的にやり、何を言われてもブレない自分軸を見つける
・企業研究を徹底的に行い、誰よりもその企業について詳しく語れるようになる
・面接対策を徹底的におこない、どんな質問が来ても堂々と自信を持って答えられるようになる
どんなことでもかまいません。何か一つにやりきれる人は、そこから評価されたり配属のイメージがしやすくなります。
すべて中途半端になってしまうのが一番もったいない対策です。ぜひ何かをやり切り、それを自分の言葉で自信を持って伝えてみてください。
挫折を乗り越えた経験
新卒就活に失敗して既卒になった場合、どのようにして挫折を乗り越えたか伝えることでプラス評価につながりやすいです。なぜなら、挫折から立ち直った経験があれば、仕事での失敗や困難も乗り越えられる可能性があることを証明できるためです。
たとえば、「自己分析不足が原因で新卒就活に失敗したと考え、既卒就活ではキャリアセンターに通って壁打ちをしながら自己理解を深めた」のように、失敗から反省して改善のために何をしたのかを明確に伝えるのがおすすめです。
大きな挫折を経験して既卒者になっているなら、乗り越えるための考え方や行動は独自の強みになります。仕事においても、失敗や困難を経験しない人はほとんどいません。そのため、挫折から学び、そこからどのように行動を変えたのかを具体的に伝えることが重要です。
挫折経験から立ち直った方法を効果的にアピールする方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。例文も掲載しているので、じぶんの経験のアピール方法を考えながら読み進めてください。
キャリアコンサルタントが解説! 既卒就活で内定を獲得した成功事例
既卒就活が厳しいと言われる理由を解説しましたが、それでも実際に内定を獲得している人も多くいます。その成功事例を知ることで、どのように就活を進めれば良いのか、具体的なイメージを持つことが可能です。
ここではキャリアコンサルタントの吉野さんに、既卒者が内定を獲得した成功事例について質問します。既卒ならではの強みの活かし方や、厳しい状況を乗り越えるための工夫を知り、選考対策に役立ててください。
アドバイザーコメント
既卒就活で内定獲得をした人の成功のコツを3つ紹介
① 孤独感を解消し、生活リズムを整える
既卒就活で最も大変なのは孤独感です。在学中の就職活動では、周りの同級生も同じように頑張っているため、お互いに励まし合うことができます。しかし、卒業後は所属先がなくなり、自分で計画を立て、生活リズムを管理しなければなりません。
自己管理が苦手と感じている場合は、自治体の就職支援施設を活用し、就活仲間を作るのがおすすめです。セミナーや就職相談を利用することで、活動のリズムを整えやすくなります。
② 期限を決めて行動する
既卒は卒業後3年以内と定義されていますが、「3年あるから大丈夫」と考えてしまうと、ついダラダラしてしまいがちです。一般的に転職活動は3〜6か月かかると言われています。「いつまでに内定を獲得し、働き始めるか」を明確に決め、短期間で集中して行動することが重要です。
③ 何より大切なのは「応募し続けること」
最も大切なのは、応募を続けることです。当たり前のことですが、内定獲得に成功した人は、「受かるまで受け続ける」を実行しているのです。
プロが解説! 既卒が就活終盤からでも内定を獲得する方法
就活シーズンの終盤を迎えると、「もう内定を獲得するのは難しいのではないか」と焦りや不安を感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、就活終盤でもポイントを押さえて行動すれば、内定獲得のチャンスはあります。
ここでは、多くの学生の就活を支援してきた古田さんに、就活終盤を迎えた既卒者におすすめの対策方法を聞きました。就活のプロの意見を取り入れて、思うようなスタートが切れなかった遅れを取り戻しましょう。
アドバイザーコメント
工夫と努力次第で就活シーズン終盤でも内定を獲得することは十分可能
就活終盤からでも基本的な就活は新卒と同様ですが、工夫と努力次第で内定を獲得することは十分可能です。
たとえば、友人や先輩、家族、就職支援機関などの人脈を活用し、情報を共有するなど、多角的なアプローチを試みましょう。就職フェアや企業説明会など、直接企業と交流する機会を増やすことで、新たなチャンスも広がります。
また、オンラインコースなど短期間で習得できる、即戦力になるスキルを身に付け、履歴書に追加してみましょう。
現在の志望先に加えてこれまで除外していた業界にも目を向けよう
応募先も視野を広げ、これまで除外していた業界や職種にも目を向けてみましょう。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員としての採用も検討してみましょう。短期間でも経験を積むことで、正社員に転職する際のアピールになります。
相談相手がほしいときは、就職エージェントを活用してみましょう。経験豊富なプロのアドバイスやサポートを受けることで、適切な対策ができるようになります。
新卒と比べると既卒の就活は厳しい面もありますが、諦めずに行動することは、必ず以降も役立つ経験になるはずです。
空白期間があるからこその強みを活かして厳しい既卒就活を乗り越えよう
「既卒就活は厳しい」といった情報に不安を感じていた人も、既卒者ならではの強みや空白期間の活かし方を理解することで、希望を見出せたのではないでしょうか。
確かに既卒就活には厳しい面もありますが、空白期間で得た成長や経験を強みに変えられれば、ほかの求職者との差別化が可能です。空白期間に目を向けて、自分にはどんな魅力があるのか考えてみましょう。
また、既卒就活を成功させるためには、十分な準備と戦略が大切です。本記事の内容を参考にして自分を見つめ直し、志望企業の内定獲得に向けて行動してください。
アドバイザーコメント
大学在学中の人は既卒にならないようギリギリまで粘って就活しよう
まだ卒業しておらず、新卒カードを残している人は、悪いことは言わないので就職留年や新卒で就活をギリギリまで頑張ることをおすすめします。
そもそも既卒の場合は採用の門戸を閉じてしまっている企業もあり、単純にチャンスが減ってしまいます。例年、就職留年する学生は一定数いるため、採用側もそこまでネガティブなイメージをもっていません。ぜひ新卒カードを最大限活用してください。
既卒になった人はとにかく行動量を増やして内定獲得を目指そう
すでに既卒になってしまっている人は、とにかくアクションするしかありません。実際にこれまで多くの既卒就活のサポートをしてきましたが、最終的に内定を獲得する人は最後まで諦めずにチャレンジし続けた人です。
これは新卒に限らないことですが、どれだけ優秀な学生でも選考で落ちることは必ずあります。加えて、内定獲得よりも落ちることのほうが圧倒的に多いです。大切なのは落ちても落ちてもチャレンジをやめないことと、落ちたらなぜ落ちたのかを分析して次の選考に活かすことです。
企業は山ほどあります。あなたがまだ内定を持っていないのは、あなたがダメなのではなく、まだあなたを必要としている企業に出会えていないだけです。自分を信じて、就活に向き合っていきましょう。絶対大丈夫です。応援しています。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi



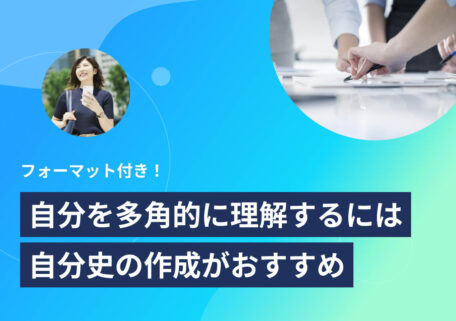















3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/公認心理師
Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー
Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める
プロフィール詳細就活塾「我究館」副館長/キャリアコンサルタント
Hayato Yoshida〇東証一部上場の人材会社で入社2年半で支店長に抜擢。これまで3,000名以上のキャリアを支援。現在はベストセラー書籍「絶対内定」シリーズを監修する我究館で副館長として従事
プロフィール詳細