この記事のまとめ
- ガクチカに盛り込むべき5つの項目を紹介
- 企業研究×自己分析ができていないガクチカはNG
- 業界別・職種別のガクチカの例文を参考にして作成しよう
就職活動では避けて通れないのがガクチカです。しかし、「ガクチカの書き方がわからない」「どんなエピソードを選べば良いのだろう」と悩む就活生は毎年多くいます。
一見難しそうに感じるガクチカ作成ですが、上手なガクチカを作成するための構成を理解できれば、魅力的なガクチカを簡単に作成することができるのです。ガクチカであなたの強みをしっかりと伝えて、志望企業の内定をつかみましょう。
この記事では、日々学生の就活を支えているキャリアコンサルタントの平井さん、田邉さん、上原さん、瀧本さん、野村さんの5名と一緒に、ガクチカの書き方について解説していきます。
特に、就活生の相談実績が延べ40,000件を超える瀧本さん、約10年間人事として採用活動を担ってきた野村さんの2名からは、ガクチカを書く際に重要なポイントや、企業に伝わりやすいガクチカの例などを解説してもらうので、上手なガクチカを書きたい人はぜひ最後まで読んでみてくださいね。
下記の記事では、ガクチカについてさらに詳しく解説しています。こちらの記事と併せて読んでみてください。
ガクチカについて
例文13選|誰でも「刺さるガクチカ」が完成する4ステップを解説
ガクチカの構成
ガクチカの構成は7ステップで高評価を狙おう! 例文12選付き
下記のQAでは「ガクチカの書き方がわからない」という悩みにキャリアコンサルタントが回答しているので、気になる人は参考にしてみてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
1位:自己PR作成ツール
自己PRが思いつかない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
2位:志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
3位:自己PR例文100選
お手本になる自己PRをまとめました。書き方に悩む人、文章の質を高めたい人へ
4位:面接回答集60選
見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました
5位:逆質問例100選
面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています
【併せて活用したい!】
スキマ時間3分でできる就活診断ツール
①適職診断
たった30秒であなたが受けない方がいい仕事がわかります
②面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
ガクチカの書き方! 5つのステップで仕上げよう

ガクチカを書く際に押さえておきたい、5つのステップがあります。ガクチカの完成形から逆算して必要な要素を整理していきましょう。
ステップの通りに書き進めることで、必要な項目をしっかりと盛り込んだわかりやすいガクチカを作成できます。
「ガクチカの書き方がまったくわかっていない」という初心者の人は、ステップ①企業研究でガクチカのゴールイメージを掴もうから順番に読み進めていきましょう。一方「ガクチカの書き方は大枠理解できていて後は最終チェックだけ」という人は、ステップ⑤最終チェック! 4つのポイントからガクチカを仕上げようから読むことでガクチカ提出前の仕上げができます。
以下の記事ではガクチカが今すぐ書ける秘策を解説しています。ガクチカで悩んでいる人はぜひ、参考にしてみてください。
ガクチカはAIを活用して作成することができます。以下の記事ではAIを活用するときの注意点などを解説しているので参考にしてみてください。
時間がない人におすすめ!
ツールを使えば、ガクチカが3分で完成します
学生時代に頑張ったこと(ガクチカ)は、自己PRや志望動機と差別化するのが重要です。とは言え、ガクチカで話せるネタがなく悩む人も多いでしょう。
そこで活用したいのが「ガクチカ作成ツール」です。このツールを使えば、簡単な質問に答えていくだけで採用担当者に魅力が伝わるガクチカが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
簡単な質問に答えるだけで、あなたの魅力が伝わるガクチカが作れます。
ガクチカ作成ツールでガクチカをつくる【無料】
ステップ①企業研究でガクチカのゴールイメージを掴もう
企業研究でガクチカのゴールイメージを掴もう
- 企業研究をおこなう
- 企業研究から企業の求めるガクチカの傾向を知る
まずは、ガクチカの完成形のイメージを掴むことが大切です。そのためには、企業が求めているガクチカを理解することが必要となるでしょう。
企業ごとに求める人物像があるため、ガクチカに盛り込むべき内容も必然的に異なるのです。自分の志望する企業の企業研究をおこない、どのような内容でガクチカを作成すべきなのか、ゴールのイメージを掴んでいきましょう。
ガクチカを書くうえで、自己理解で見つけた強みをストレートにアピールするのではなく、企業が求める人材像の目線で表現することが大切です。
たとえば、「挑戦」を大事にしている企業に「堅実」をアピールしても、採用担当者の評価は低いでしょう。「堅実」が悪いのではなく、応募先にマッチしていないのです。
コピペで使えるガクチカがかんたんに作れます
学生時代に頑張ったこと(ガクチカ)は、自己PRや志望動機と差別化するのが重要です。とは言え、ガクチカで話せるネタがなく悩む人も多いでしょう。
そこで活用したいのが「ガクチカ作成ツール」です。このツールを使えば、簡単な質問に答えていくだけで採用担当者に魅力が伝わるガクチカが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
①企業研究をおこなう
企業研究といっても企業の0から100まで知る必要はありません。要点を押さえることが重要です。
要点として、以下の5つを意識してみてくださいね。
①商材は何か
企業ごとに当然、提供しているサービスは異なります。その商材の特性を理解することが重要です。
特にその商材が有形なのか、無形なのかは意識できると良いですね。これは顧客にサービスを買ってもらう難易度や手法に直結するので、わかりやすく営業で考えてみましょう。
商材の特性を考える例
有形の商材の場合
「モノ」自体に魅力があるので買ってもらうハードルはそこまで高くない。その代わり、数多くの商品の知識を学ぶ力や、商品に魅力がある分営業で印象を損ねてはいけないので丁寧さや礼儀正しさなどの人当たりが求められる。
無形の商材の場合
売る際には商材がないので、「営業自身の力」が問われる。踏み込んで話をしたり、顧客のニーズを有形以上に知る必要がある。話の内容だけで「良い」と思ってもらうようなトーク力や積極性が重要。
このように「その商材は何か」ということを紐解いていくと、商材から仕事の内容や仕事で重要な素養をイメージしていくことができます。
②顧客は誰か
次に「顧客は誰か」を考えましょう。わかりやすくいうと法人か個人か、女性か男性か、若人か老人か、日本人か外国人かなど、誰に対して商いをしているのか、ということです。
これも例を挙げると、顧客が法人であれば営業手法はルート営業や新規営業なのではないかということが想像できます。一方で、個人であれば店舗型か訪問営業か反響営業かということが想像できるでしょう。
さらに女性と男性、若者と老人などで好みや価値観が異なるので、人気のSNSや情報を習得する媒体も異なります。
顧客毎に特性が異なるため、顧客は誰なのかを考えることで、その特性毎に活かすことが可能なスキルを紐解くことができるのです。
③単価はどれくらいか
商材の単価を掴むことができると、売るハードルの高さや手法を学ぶことができます。
有形・無形商品と一口に言っても、数十円単位の商材から1億を超える高単価の商材までその幅は非常に広いです。
数百円単位の商材であればそれを1つ売るのではなく、どれだけ数多く継続的に買ってもらえるかという視点が重要となります。一方で、高単価になればなるほど買う側は慎重になるため、より丁寧さや誠実さ、長期的な取引における信用度が重要となるのです。
その商品を扱っている業界の平均価格などは知っておけると良いでしょう。
④営業手法は何か
売り方は何か、ということも大切な要素です。営業の手法にもルート営業なのか、飛び込み営業なのか、反響営業なのか、代理店営業なのか、はたまた別の手法でサービスを提供するのか、さまざまなサービスの届け方があります。そしてそれぞれの営業手法によって問われる能力が異なるのです。
たとえば、ルート営業では顧客と長期的な取引をするための誠実さや丁寧な対応が重要になる一方で、飛び込み営業は顧客の需要がない状態から仕事をしなければならないが故にバイタリティが求められます。
同じ職種のなかでも問われる素養は異なるので、この点を正確にとらえることは重要です。
代理店営業を志望している人は以下の記事を参考にしてみてください。ほかの営業との違いや向いている人の特徴をまとめています。
⑤何が困難か
最後に、その仕事・職種において何が困難かを正確にイメージできると良いでしょう。
たとえば、無形商材であれば短時間で自分自身を信頼してもらえないかもしれない、そんなときどうするか、というのは大きな困難と言えます。
そのほか、顧客に着目しても良いかもしれません。なぜなら、顧客のメインターゲット層によって発生する困難さは異なるからです。
企業研究の結果得た知識から困難さをイメージすることで、企業が求めている「活躍できる人材像」を明確にすることができます。
アドバイザーからワンポイントアドバイス企業が求める人材像を理解したうえで自分をアピールしよう
ガクチカを作成する際には、「企業の求める人材像を理解し、それに合ったガクチカを作成する」ということがポイントとして挙げられます。
自分とはまったく違う姿を無理矢理に示していくのではなく、自分の中にあるものから企業の求める人物像に寄せて書きましょう。そのためには、企業が求める人材像がどのようなものであるのかを事前に知る必要があります。
採用ページなどから企業が求める人物像について探ることが大切
企業の採用ページには、求める人物像が書かれている場合が多いのでまずは見てみましょう。また企業の事業内容や、投資家向けのページなどにある中期経営計画や目指す姿を確認すると、企業が目指している方向性が見えてきます。企業の目指す姿を実現するために必要なのが、求める人物像です。
また、さまざまな分野で働く先輩社員の姿が示されている場合も多くあります。活躍している人材や能力を理解すると、どのような人が求められているかがわかります。
あらゆる方向から企業が求める能力や人物像を理解したうえで、自分にそのような要素があると示すことができると、自分自身をアピールできるガクチカになるでしょう。
テンプレを活用すれば受かるガクチカが作れます
学生時代に頑張ったこと(ガクチカ)は、自己PRや志望動機と差別化するのが重要です。とは言え、ガクチカで話せるネタがなく悩む人も多いでしょう。
そこで活用したいのが「ガクチカ作成ツール」です。このツールを使えば、簡単な質問に答えていくだけで採用担当者に魅力が伝わるガクチカが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
簡単な質問に答えるだけで、あなたの魅力が伝わるガクチカが作れます。
ガクチカ作成ツールでガクチカをつくる【無料】
たった3分で自己PRが完成!スマホで簡単に作れるお役立ちツールです。
②企業研究から企業の求めるガクチカの傾向を知る
企業研究で情報を得たら、その情報をもとに企業の求めるガクチカの傾向を探ることができます。
進め方については、下記の2つのポイントを押さえることが大切です。企業研究の内容をうまく活用して、自分のガクチカの方向性を決めていきましょう。
企業研究からガクチカへの応用方法
- 企業研究から求められている要素を推測する
- 求められている要素からガクチカの方針を固める
①企業研究から求められている要素を推測する
企業研究から「何が困難か」までイメージできたら、あとは「その困難をどう乗り越えるか」という発想になります。
この「困難を乗り越えるために必要な要素」=「企業が応募者に求めている要素」となるのです。
たとえば、新規営業では門前払いされることも多く、話を聞いてもらうことすらできない可能性もあります。そのような状況を困難として仮定した場合、「自分だったら必要な情報と相手にとってプラスになる内容を簡潔にまとめた資料を、一社ごとに作成してアプローチするなど、小さな努力をコツコツとしていくな」などと考えられるでしょう。
すると、企業が求める要素は「自分にできることは何かを考え行動する力」なのかもしれないと推測ができるのです。
企業は学校ではないため、誰かに教わるという姿勢ではなく、自分自身で壁を乗り越える力を持っている人材が求められます。この観点から考えると、自ずと企業の求める要素が見えてくるでしょう。
②求められている要素からガクチカの方針を固める
企業から求められている要素が何かわかったら、いよいよガクチカを考えましょう。
自分の過去の経験のなかで企業から求められている要素を一番アピールできるのは何か、ということを考えながらエピソードを探します。気を付けてほしいのは、必ずしも「一番実績を上げたこと」をアピールすれば良いというものではないということです。
企業から求められている要素をより効果的にアピールすることができる経験がほかにあるなら、その経験を主張したほうがより印象的なアピールとなります。
アドバイザーからワンポイントアドバイスガクチカ作成前の企業研究は必須! 企業の求める人物像を把握しよう
ガクチカを書く際、十分な企業研究をおこなわずに取り組む学生も少なくありませんが、実はこの段階での企業研究は、差を付けやすい重要な要素の一つになりえます。
ガクチカは一般的には「学生時代の経験」を説明する場とされていますが、企業が注目しているのはその経験自体ではなく、そこから得た強みや学びを今後どのように活かせるかという点です。そのため、企業の求める人物像や価値観を理解していなければ、貴重な経験も単なる思い出話として受け取られてしまう可能性があります。
たとえば、挑戦心を重視する企業であれば失敗からの成長を強調することが有効ですし、チームワークを大切にする企業であれば周囲を巻き込んで成果を高めた取り組みを示すことが適しています。
ガクチカは単なる経験を伝える場ではない! 企業の貢献につなげよう
こうした観点を持つには、ガクチカの作成前から企業研究をおこない、自分の経験をその企業の価値観や評価軸に沿って語れる準備を整えることが必要です。過去を語るだけではなく「御社でどう活かせるか」を示せる学生は、自然にポテンシャルを伝えられます。
企業研究はエントリー直前や面接対策に限らず、ガクチカを考える初期段階から意識すると効果的です。
- 受ける企業一つひとつを調べてガクチカを考えていては、時間がかかりすぎてしまいます。1つのガクチカをいろんな企業で使いまわすのはだめですか?
題材を使いまわしはOK! アピールポイントはそれぞれ考えよう
1つのガクチカを使いまわすことは問題ないですが、「そのガクチカで自分のどんな良いところを伝えるのか」を応募先ごとに検討しましょう。
たとえば、あなたが所属しているサークルが「最大限努力する」ことを大事にしていたら、「効率よく物事を進める」新入生と「努力して目標を達成する」新入生、どちらが自分のサークルに合っていると思いますか。
ガクチカでは自分が応募先の求めている人材であることを伝えます。面倒でも、応募先ごとにアピールポイントを見つけてください。
ガクチカ作成ツールを活用すれば、受かるガクチカが作れます
ガクチカ作成が進まず、焦っていませんか?ガクチカは、自己PRや志望動機と並ぶ重要なアピールポイントですが、作成に苦戦する人もいます。
そこで「ガクチカ作成ツール」の出番です。たった4つの質問から経験や強みを引き出し、採用担当者に刺さるガクチカを完成させます。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
ステップ②自己分析をして効果的にアピールできるガクチカを選ぼう
ステップ②自己分析をして効果的にアピールできるガクチカを選ぼう
- 自分の経験を振り返る
- 現在の自分と過去の経験とのつながりを整理する
- 自分が思い描く未来と今の自分とのつながりを整理する
- 企業から求められている要素を最も満たすガクチカを選ぶ
企業研究からガクチカを選ぶ方法を解説しましたが、更にもう1つの有効な選び方があります。
それは自己分析をして「自身軸」と「貢献軸」を明確にすることです。自分軸は、自分の将来に向けた意志を指します。たとえば、話す力を伸ばしたい、尊敬される人になりたいなどです。
そして、貢献軸とは、他人や社会に向けた意志を指します。たとえば、困っている人を助けたい、飢餓をなくしたいなどが該当するでしょう。
この2つの軸と企業研究で見えてきた企業の求めるガクチカの内容がうまく重なるエピソードを作成できれば、企業の求めるレベルを越えながら自身の就活軸をもアピールすることができるので、より企業に自社の選考に来ている納得感を生む材料となります。
ここでは、自己分析の手順を紹介していくので、一つひとつ着実に進めていきましょう。
①自分の経験を振り返る

まずは、余すことなく自分の経験を振り返りましょう。おすすめは、自分史としてまとめていくことです。上記のフォーマットをもとに振り返ってみてください。
1年毎に何があったか、その事象の背景で自分はどのようなことを考えていたか、結果的にどう行動することになったか、成果はなんだったか。これらの点が最低限自分のなかで説明できるようにしましょう。
自分史の作成方法が知りたい人は下記の記事を参考にしてみてください。
②現在の自分と過去の経験とのつながりを整理する
次に、①で挙げた経験から現在の自分を形作る意図・思考・行動になるようなものがあったかどうかを整理してみてください。
たとえば小学生の頃の印象的なエピソードに野球部でレギュラーを掴んだという経験があったとします。大事なのはレギュラーを掴んだという事象ではなくて、「レギュラーになりたいと思った動機」です。
ベンチでいる自分に焦りがあったのか、ほかの部員に負けたくないと思ったのか、ほかの人にすごいと思われたかったのか、などいろいろな理由のなかから自分がその時感じていた感情や頑張る原動力となったものを拾いあげていきましょう。
このようにして中学生、高校生の頃に自身が挙げたエピソードも同じようにどういう意図で、どんな感情で、どういう行動をして、結果どうなったのかを拾い上げていくと、すべてのエピソードに共通している意図・感情・行動を見出せます。
③自分が思い描く未来と今の自分とのつながりを整理する
次に、過去から地続きになっている今の自分が、思い描く将来とどのようなつながりがあるかという視点で夢や目標を整理します。この夢や目標が、過去・現在から地続きでつながっているように整理ができれば、それが就活軸となるのです。
たとえば、過去を振り返るなかで「自分は負けず嫌いで、だからこそ目標を持って物事に取り組んでこれた」という振り返りができていて、将来やりたいと思っていることが「同年代よりも一段階早い社会人としての成長」「成長をもとに、より大きな社会貢献をしたい」だとします。
今述べた将来やりたいことが、振り返りのなかで見いだした「負けず嫌いな一面」とつながっていると、今の自分とのつながりが明確になります。
そのまま今の事例を使うなら、「同年代よりも早く成長したいのは、元々自分が負けず嫌いで、この感情を原動力にさまざまな経験において頑張ることができたからです」という表現になるでしょう。
④企業から求められている要素を最も満たすガクチカを選ぶ
③で浮かび上がった経験のなかから、企業から求められている要素を最も満たすガクチカを選びましょう。
先ほどの例をそのまま使うのであれば「負けず嫌い」なエピソードのなかで、最も企業にアピールできそうな内容を選択し、ガクチカに使うということです。
この過程を経て選んだガクチカは、企業から評価をされ、面接官からの深掘りに強いものになるポテンシャルが高いでしょう。
アドバイザーからワンポイントアドバイスガクチカが見つからないなら就活を取り上げるのも1つの手
どうしてもガクチカに書くことが見つからなければ、いま取り組んでいる就活を取り上げて、これから作ってみてはどうでしょうか。
「PDCAサイクル」という仕事の進め方があります。「Plan(計画)ーDo(実行)ーCheck(評価)ーAct(改善)」のステップで仕事をまわす考え方です。これをそのまま就活に応用し、PDCAサイクルを身に付けていることをアピールポイントにしてみてください。
就活を通してPDCAサイクルを実践していることを伝えよう
まず就活の計画です。大きな就活スケジュールに合わせて、いつ何をするのかを決めます。
このとき、計画通りにできているかを確認するタイミングも決めましょう。計画ができたら実行します。あらかじめ決めたタイミングで振り返りをおこない、改善点を踏まえて計画を修正して、実行していきます。この繰り返しです。
これらを、たとえばこのような形でまとめてみましょう。
「私が学生時代に力を入れてきたことは、PDCAサイクルを実践して物事に取り組むことです。理由は、ただ行動するだけではなく、計画を立て、振り返ることが成果につながると考えるからです。たとえばこの就職活動でも〜(やったことを述べる)。このように身に付けたPDCAサイクルを活かして、入社後も仕事に取り組みます」
かなり意表をついたやり方ですが、今からでもガクチカは作れることを知って、ほかの題材でも良いので取り組んでみてください。
「ガクチカがない」と悩んでいる人は、こちらの記事も参考にしてください。誰でもガクチカを見つけられる方法を解説しています。
「ガクチカがない」悩みを解決! 見つけ方や今から作る方法を解説
ガクチカが本当にない人がすべきことは? おすすめのテーマも解説
ガクチカがないという悩みにキャリアコンサルタントが回答しています。気になる人はこちらもチェックしてみてください。
ガクチカで書くことがないのですがどうすれば良いですか?
ガクチカがないので詰んでます。
ガクチカがない場合、どうすれば作れますか?
ステップ③PREP法の構成でガクチカを組み立てよう

ここまでの過程を経てガクチカを選ぶことができたら、次は「書く」段階となります。
この書く段階では「PREP法」を使えると、選んだエピソードを効果的に伝えることが可能です。
PREPとは
文章を書くうえで大事な4つの構成を表す、英単語の頭文字をそれぞれ取って組み合わせたフレームワーク。
ガクチカの場合、具体的には以下の構成に当てはめましょう。
PREP法によるガクチカの構成
- Point:ガクチカの結論を伝える
- Reason:そのガクチカを頑張った理由・意図を明確にする
- Example:何をしたか具体的に伝える
- Point:結論は言い直して強調する
ガクチカの伝え方によっては、面接官が理解できずにマイナス評価となってしまいます。
たとえば、先に結論が述べられていないケースなどが該当します。伝えたいことがアピールできるように構成をきちんと意識しましょう。
面接でガクチカについて回答するときも構成は大切です。ガクチカの内容が長すぎても短すぎても、面接官に伝わりづらくなります。次の記事では、回答のちょうど良い長さについて、具体例とともに解説しています。ぜひ読んでみてくださいね。
①Point:ガクチカの結論を伝える
最初は「結論」から伝えましょう。何を話すか、何をアピールするのかを一番最初に話すことで、面接官が話を聞いて理解しやすい・メモを取りやすいというメリットが発生します。
また、どこに結論を落とすかが予めわかっていることで、初めて聞いたガクチカ・エピソードでも聞いた際に「要点はここだな」とあたりを付けながら聞くことが可能です。
面接官も話を聞きながらメモを取るのですが、一言一句漏らさずにメモを取ることはできません。落ちのわからない話は要点もわからないので「とりあえずメモを取る」という状態になりやすいため、結果として、話しているスピードにメモが追い付かない状態が発生しやすくなり、重要な要点を聞き流されてしまう可能性があるのです。
②Reason:そのガクチカを頑張った理由・意図を明確にする
結論の次は理由・意図です。そのエピソードを選んだ理由や、そのエピソード当時の行動心理・背景などをこの点で盛り込みます。
この理由があることで、企業は「再現性」を確認できるのです。つまり、自社に入社した後も同じように行動できるかどうかを見極められるということになります。
Reasonは応募者の考えが構成上強く出る部分でもあり、この考えをもとに行動をするという印象は、そのまま企業における行動イメージにつながるでしょう。
想いや意図がまったく書かれてないガクチカは、その人がどんな人物であるのかよくわかりません。
ガクチカから熱意が伝わらないので、面接官に「志望度が高くない」と思われる可能性が高いです。
エントリーシート(ES)のほかの欄の記載も含めて、「魅力的な人物ではない」と判断されてしまうと書類選考を通過することは難しいでしょう
③Example:何をしたか具体的に伝える
結論や行動心理・意図も伝えたうえで、次はエピソードの具体例につなげましょう。
具体的な状況を説明することで、企業側はあなたの取り組み方や考え方、価値観などを理解し、入社後の活躍イメージを膨らませることができます。
Exampleではその前のReasonで述べた意図・背景にもとづいた行動になっているか、を確認しながら定量的に内容を伝えることが重要です。
④Point:結論を再び伝えて強調する
そして最後に結論をもう一度伝えましょう。①で伝えた結論を再度伝えることで、より面接官の印象に残るガクチカにすることができます。
面接官が自分のメモを見返す手間を省くことにもつながり、最後にしっかりと顔を見て話すことができるため、熱量を余すことなく伝えられるのです。
エピソードを踏まえたうえで伝えたいことを簡潔に整理して、最もアピールしたい内容を効果的に伝えましょう。
アドバイザーからワンポイントアドバイス企業研究がガクチカ作成の第一歩! 企業の求めるガクチカで差を付けよう
ガクチカは「何を頑張ったか」だけでなく、「誰に・どう伝えるか」を踏まえた設計が重要です。まず、受ける企業がどのような価値観や能力を求めているのかを、企業研究を通じて把握することが出発点となります。
商材、顧客層、単価、営業手法、業界特性などから、その企業で成果を出す人材像を推測し、期待に応えるようなガクチカを構築しましょう。
PREP法を用いて相手の読みやすさを考えた構成にしよう
次に、自身の経験を振り返り、「その行動に自分らしさがどう表れていたか」「どんな成長があったか」「今後どう活かせるか」といった“過去-現在-未来”のつながりを意識して整理することが大切です。ここでは「何を選ぶか」だけでなく、「なぜそれを選ぶのか」の視点がカギとなります。
最後に、構成はPREP法を用いることで、論理的かつ印象に残る伝え方が可能です。結論→理由→具体例→再結論の流れにより、読み手の理解と共感が得やすくなります。
ガクチカは単なる経験の紹介ではなく、「自分という素材を企業のフィールドでどう活かせるか」を伝えるプレゼンです。企業研究・自己分析・構成の三位一体が成功のカギです。
ステップ④STARモデルを使って差別化できる内容にレベルアップしよう
STARモデルを使って差別化できる内容にレベルアップしよう
- Situation:PREPでいうEにおいてどういう状況だったのか
- Task:Eの中でどのような立場・意図を持っていたのか
- Action:Eの中で実際に取った細かな行動は何か
- Result:Eの中でどんな結果になったのか、何を学んだのか
ここまでで基本のガクチカの作成方法を伝えてきました。とはいえ、面接官は1日に何十件ものガクチカを見たり聞いたりするため、印象に残る内容で作成しないと、ライバルたちに埋もれてしまいます。
そこでおすすめなのが、STARモデルの活用です。STARモデルは面接官が、面接官になるための研修で用いられる重要な考え方となります。このフレームワークをうまく活用して、ほかの就活生との差別化を図りましょう。
STARとは
4つの観点を表す英単語の頭文字(Situation・Task・Action・Result)をとって並べた、話を深掘りするフレームワーク。
①Situation:PREPでいうEにおいてどういう状況だったのか
まずは、状況に関する項目です。具体的なエピソードに付け足すことで、話の納得度や成果の難易度を確かめます。
例
全国大会で優勝した → 出場500校の中で頂点に立った。
レギュラーを勝ち取った → 2カ月前まで骨折をしていた状況からレギュラーに返り咲いた。
クラス委員長としてクラスをまとめた → 委員長には自分で立候補し、初めて務めた。クラスは学級崩壊寸前だった。
このように、状況を補足すると、なぜそのアピールなのか納得しやすくなり、難易度もより鮮明に感じてもらいやすくなります。
- 状況を具体的にすると言っても、やりすぎると話が逸れたり、時間がかかりすぎてしまいそうです……。どの程度具体的にするべきでしょうか?
出来事を通じてどのように行動したかが伝わるようにしよう
企業が知りたいのは、どんなエピソードがあったかではありません。エピソード自体ではなく、その出来事を通じてあなた自身がどんな人物であるのかを知りたいのです。
状況を詳しく伝えることに捉われるのではなく、出来事を通じて、「あなたが何を感じ、どう考えて、どのような行動を取ったのか」を示すことが大切です。その中にあなたの価値観や性格、大切にしていることや思考傾向などが現れます。
②Task:Eの中でどのような立場・意図を持っていたのか
次に、立場・意図に関する項目です。エピソードに付け足すことで、就業後の活躍可能性のアピールができます。
例
全国大会で優勝した → 副部長という立場に責任を感じ、優勝するために練習のスケジュール管理が必要だと思ったので、計画を練った。
レギュラーを勝ち取った → 何か成し遂げたかった。漫然とベンチで日々過ごす自分に焦っていた。
クラス委員長としてクラスをまとめた → 自身の成長につながると思った。引っ込み思案な自分を変えたかった。
このように、立場・意図を付け足すことで、考え方や思考をより鮮明にアピールできます。
③Action:Eの中で実際に取った細かな行動は何か
そして、具体性に関する項目です。付け足すことで、成果や行動の評価を高めることができます。
例
毎日練習した → 朝は7時から9時まで、夜は16時から20時まで330日程度練習した。
苦手と向き合った → 自分を動画で納め、足りないものをノートに記載した。他者にも見てもらいフィードバックを求めた。
クラスをまとめた → ホームルームで日直が日々あった楽しいことを話すシステムを構築し、互いを知ることから始めた。
このように、具体性を上げることで、実際におこなった行動をより鮮明にアピールができます。
④Result:Eの中でどんな結果になったのか、何を学んだのか
最後に、成果に関する項目です。付け足すことで、エピソード全体がより効果的に伝わります。
例
全国大会で優勝した → 高校生以上を対象とした全国大会で、45組の参加者の中で優勝した。ここに至る過程の中で計画を遵守する実行力の大切さを学んだ。
レギュラーを勝ち取った → レギュラーを取る過程で、自分がどういう状態で満たされるのか、何が原動力かを知った。
クラスをまとめた → クラスをまとめる中で、お互いを知ることが重要だと思った。そのためのアウトプットの場があるとより良いと感じた。
このように、結果に付随して学びを記載すると、そのエピソードがあなたにとってどんな影響があったのかまで伝えることができます。
アドバイザーからワンポイントアドバイスSTARモデルの「Action」の具体性でガクチカの良し悪しが決まる
STARモデルの中で「Result」が最も大切だと思っている学生が多いのではないでしょうか。たしかに、経験者採用の場合には前職でどのような実績があるのかが採用で重視されます。
しかし、学生であればできる経験が限られているので、学生時代の成果が仕事で直接活かせないこともあります。そのため、結果ではなく「どのような行動をしたのか」が最も重視されています。
「Action」を具体化して活躍イメージを伝えよう
「Action」では、誰が聞いても同じ解釈になるように具体化をすることがポイントです。たとえば、「チームが優勝するように積極的に取り組んだ」という表現は、人によって「積極的」のイメージが異なります。
誰が聞いても同じ解釈になるためには「練習後にチームメイトへ声をかけて1時間以上フィードバックを伝えた」などと具体化をする必要があるのです。
このように具体化をすることで、面接官は就職後に仕事で活躍できるかどうかを判断しやすくなります。数字も使いこなしてわかりやすい「Action」を作成しましょう。
ステップ⑤最終チェック! 4つのポイントからガクチカを仕上げよう
4つのポイントからガクチカを見直そう
- 企業が求めている要素に対してアピールできているか
- 文章構成はPREP法を用いてわかりやすくまとめられているか
- STARモデルに則ってガクチカの質を高められているか
- 誤字・脱字がないか
ここまでの解説で、ガクチカの作成はできるようになったと思います。ただし、気付いていないミスがあるかもしれません。
ここからは、できあがったガクチカの見直しをするフェーズです。4つのポイントを紹介するので、ガクチカに失点がないよう、細心の注意を払ってガクチカを見直していきましょう。
ガクチカを書き終わってそのまま提出するのではなく、まずは誤字・脱字のチェックをしましょう。最後の見直しによって、単純ミスを防ぐことができます。
次に伝えたいことが伝わる構成や表現になっているかもチェックしましょう。
最後の見直しは、書いた翌日におこなったり、他者に見てもらったりすることがおすすめです。客観的に見てもらうことで、修正箇所が見つけやすくなります。
①企業が求めている要素に対してアピールできているか
企業が求めている要素を満たすガクチカとして成立しているかどうかを確認する必要があります。もし「方向性が少しズレている……」など違和感があれば、放置せずに原因は何かを追求しましょう。自分でも違和感があるということは、大体他者から見ると大きく違和感があることが多いです。
何を伝えたいのか、それは伝わるのかという自問自答を繰り返してみてください。
修正の際はSTARモデルを用いて内容を補足・アレンジしながら企業が求める要素を少しずつアピールしていくと良いでしょう。修正でどうにもならない場合は、抜本的にエピソードを変えることも検討してみてください。
②文章構成はPREP法を用いてわかりやすくまとめられているか
文章構成はエピソードを効果的に伝えるうえで非常に重要です。PREP法の順番で構成ができているかを再度見直すことで、構成に違和感があるかどうかに気付けます。
特にガクチカの場合は、いきなり具体的なエピソードを話し始める学生が多いです。今から何を話すのか、なぜそれを話すのかが伝わる内容になっているかを客観的に見返してみましょう。
ガクチカを200字以内で求められる企業もあります。以下の記事では200字のガクチカの書き方や構成についてまとめているので参考にしてみてください。
③STARモデルに則ってガクチカの質を高められているか
ガクチカの加点を増やせそうな箇所はないかという視点でチェックしてみてください。また、逆に曖昧で伝わりにくい場所はないとう点も非常に大切です。
企業毎に求められている要素を意識してSTARモデルに則った補足ができると、よりガクチカの質は高まります。
もう十分である、という場合にはSTARモデルに則って想定質問を考えておくのも良いでしょう。面接官の目線に立って「自分ならどう質問するか? 何を確認したいか?」を確認しながら対策を考えると、面接でも活きてきます。
④誤字・脱字がないか
文章で表現する場合、誤字・脱字は非常に勿体ないので、最終チェックで完全になくしましょう。もし誤字・脱字があった場合、修正液などで直すのではなく、書き直すことをおすすめします。
書き損じのある履歴書とない履歴書を見比べると、相対的に書き損じのない履歴書のほうが見やすさでは勝るためです。
提出した履歴書は内定まではもちろん、内定後も配属を考慮する際に使用する企業もあるので、提出以降は常に他者の履歴書と比べ続けられるという点には留意する必要があります。
ガクチカに誤字脱字が多い場合には、企業からの印象がマイナスになる可能性があるため注意が必要です。
また、金融業界などミスが許されない業界では、誤字脱字が選考結果に影響する可能性もあるため、提出前には何度も見直しましょう。
志望業界別のガクチカ例文6選
ここからは、実際のガクチカの例文を紹介します。自身のガクチカを書く前のイメージ作りや、すでにできあがっているガクチカとの比較に活用してくださいね。
まずは業界別の例文です。自分が志望する業界に当てはまるものがあれば、アピールの方向性などの参考にしましょう。
メーカー
例文①メーカー
私が学生時代頑張ったのは、レストランのホールスタッフとして働いたアルバイトです。
私はホールのリーダーとして30人のスタッフをまとめる存在でした。リーダーとして、お客様から寄せられるアンケートの結果を向上させたいという気持ちがありました。
ただ、各々のバイト歴には差があり、日によって接客の質が上下するという課題を抱えていました。そこで、私はサービスの質が均一になるようにしました。具体的にはシフトを自分で組み、ベテランと若手が必ず組むように調整を重ねました。
また、ベテランと若手でノウハウを共有できるように、出勤したら若手はノートに教えてほしい部分を記載、勤務の中でベテランはその点を指導し、退勤時にベテランはノートにコメントする形でフィードバックする仕組みを構築しました。
結果的に接客の質は向上し、アンケートの結果は10人に9人は最高評価で退店する店に成長しました。
この経験を経て、何が課題で、どうアプローチすべきかを意識してアクションする大切さを学びました。入社後も、目標に向けて、自分にやれることを探し、努力することで貴社に貢献いたします。
サービスの質を向上するために工夫した様子がしっかり書かれていますね。
さらに良くするためには、ほかのアルバイトの人にどのように説明をして、どのように納得してもらったうえで改善を進めたかを書けると、人を巻き込むことができる人物だとアピールできますよ。
IT
例文②IT
私が学生時代に頑張った経験はゼミ活動です。チームを主体的にまとめることができました。
私はゼミに所属しており、よくゼミのメンバーで共同研究結果を発表しています。元々チームスポーツをやっていた私は、高いレベルで協力ができれば大きな成果につながることを知っていましたが、ゼミのメンバーは初対面の人だらけで、チームとしての成熟度は低い状態で、そこが課題だと感じました。
そこで、皆と一緒に目標を小分けに設定することにしました。少しでも前に進んでいるということを実感し、チームで一緒にいることにやりがいを感じてもらったら良いのではないかと思ったからです。
一緒にスケジュールを作り、遅れたりしていたらまた皆を集めてスケジュールを修正しながら、少しずつ進んでいく、ということを1年間通しておこないました。
結果的に共同研究は学会で評価をされ、今の私たちの体制が後輩に引き継がれるほどに「文化」として根付きました。
この経験を経て、誰かと何かをするとき、思いやりと少しの目標が大切だと学びました。
やったことが具体的に書かれている点がとても良いですね。
ただ、冒頭と最後の結論が少しずれている印象があります。冒頭の「自分がゼミ活動を主体的にまとめた」というリーダーとしての役割を結論にするなら、最後の結論のまとめ方をもう一工夫してみましょう。
IT業界の選考を受ける人は、こちらの記事も参考にしましょう。志望動機の書き方を解説しています。
大学での研究やゼミ経験ををガクチカに盛り込む方法について下記のQAで解説しています。研究を活かしたい人は参考にしてみてください。
研究
研究を学生時代に頑張ったこととして書くコツを教えてください!
ゼミ
ゼミで培った協調性をガクチカでアピールするのはありですか?
ゼミの経験をガクチカとしてアピールするのはだめでしょうか?
小売り
例文③小売り
私が学生時代に頑張った経験は、サークルでの活動です。
私は演劇サークルに所属していました。サークルには後輩が30名ほどおり、私は上級学年として後輩に「このサークルにいて良かった!」と感じてもらえるよう活動をしていました。
コロナ禍で、対面での交流が減っていることが課題です。後輩たちにしてあげられることはないかを考える一方、押し売りになってはいけないという気持ちもありました。
そこで私は後輩に連絡を取り続けました。毎日5人程度の後輩に連絡をして、その次の日には別の5人に連絡をしてと、とにかく私は皆と仲良くなることを考えました。
仲良くならないと、本当に感じていることは聞けないと思ったからです。その本音に応えることが、「サークルにいて良かった」という気持ちにつながると思いました。
結果的にサークルの後輩は誰もやめず、先輩になった今、同じように後輩に接してくれているようです。
当時の後輩からは、今まで前例のなかった「追い出し演劇」という先輩を送り出すための演劇を企画してもらい、「先輩の連絡があったからサークルが楽しかったです」と言ってもらえました。
この経験から、他者に誠実に向き合うことの重要性を学びました。御社に入社後も、顧客に対して誠実に向き合うことで成果を残していきたいと考えます。
定性的な表現を事実に置き換えると、より良いガクチカになると思います。
たとえば「仲良くなる」は人によってイメージが異なるため、「問題があれば相談してもらう」などに変えると、誤解なく経験を伝えられますね。
不動産
例文④不動産
私が学生時代に頑張ったのは部活動です。この経験から忍耐強く行動をやりきる大切さを学びました。
私は体育会野球部に所属をしています。1年ではレギュラーだったのに、2年ではベンチに落ちてしまい、挫折を味わいました。
何が足りなかったのかと考えたとき、課題は打撃にありました。レギュラー組と比べると筋肉と体重が足りず、ボールに勢いがなかったのです。
そこで私は通常の練習メニューとは別に、食事のメニューを見直しながら追加で筋力トレーニングを自身に課しました。週4日で筋力トレーニングを1時間程度追加でおこない、バットの素振りに関しては1日300回を毎日繰り返しました。
最終的に私はレギュラーにはなれていません。しかし、ベンチの際には代打として起用されることさえなかった私ですが、毎試合代打で使ってもらえるようになりました。目標のためにやるべきことに修正を重ねながら、今もレギュラーを狙っています。
この経験から、忍耐強くやりきることは少しずつ実を結ぶと学びました。
うまくいかなかったときに原因を分析して対策を立てていることや、立てた対策を実行していることがよくわかるため、説得力があります。
具体的な数字も入っていて、とても良いですね。
エンタメ
例文⑤エンタメ
私が学生時代に頑張ったのは、長期インターンでの活動です。この経験から物事にチャレンジをする際の下準備の大切さを学びました。
私は人材系の会社で長期インターンをしていました。私以外に学生はおらず、私は当時簡単な事務仕事を担当していました。ただ、私個人としては物足りなさを感じていて、「もっと多くの人に価値を発揮できる仕事をしたい!」と強く思っていました。
私は学生なので、どうしたら社会人の先輩方に認めてもらえるかが課題でした。そこで私は、私の主観で物事を話すのをやめ、事実にもとづいた話をするように心掛けました。
具体的には会議や意見を求められる場で、自身の意見を資料で補強する癖付けをおこない、私の業務に間接的なかかわりだったとしても、市場情報や顧客の情報を集めました。「1冊の資料集にします」と宣言して、存在感をアピールすることを意識しました。
結果的に少しずつ企画関連の仕事を任されるようになってきました。物事の知識や進め方に関する情報を少しずつ回収した姿勢が評価されたとのことで、非常にやりがいを感じました。
この経験から、下準備の大切さ、そして自分の努力が伴えば周囲に認めてもらえることを学びました。貴社に入社後も、自分のやるべきことをしっかりと考え実践し、存在感のある働き方で貢献していきたいです。
自分の価値を提供したいという思いで努力できることがよく伝わります。さらに良くするためには、具体的に自分自身にどのような価値があり、誰に提供したいのか示しましょう。
自分自身の満足のために仕事をしているようにも読めてしまうので、自分がどのように会社に貢献できるようになったのか加えると良いと思います。
商社
例文⑥商社
私が学生時代に力を入れた経験は、資格取得です。資格取得を通じて、平行しながら物事をこなす難しさとやりがいを学びました。
私は学生時代に各種15以上の資格を習得しました。習得に励んだ意図として、自分の力や経験をより広げ、多くの事象や物事に対応できる大人になりたいと思ったからです。
資格取得には勉強をする時間が必要で、試験日との関係から複数の資格取得を平行する必要がありました。
目標達成のために私がおこなったことは「他者にフィードバックをもらい続けること」です。各種SNSで同じ資格取得に励んでいる方と交流をし、次の試験日までの進捗の報告を定期的におこなうようにしました。
すると、他者に比較して自分の状態が今良いのかどうかや、自分の進め方の問題点などに気づくことができ、客観的に進捗の悪いものに時間を割くようにするなど、より効率的に並行して物事を進めることができるようになりました。
これが15の資格取得につながったと思っています。貴社に入社後も、業務を並行して進めることがあると思います。その都度適切なやり方を考え、周囲にもフィードバックをもらいながら確実な業務遂行を発揮したいです。
業務を並行して進められることや、周囲の意見を聞きながら業務改善ができることが伝わってきます。
さらに、与えられた業務をこなせるということだけではなく、主体的に取り組みたいことが何であるのか示せるとより良くなるでしょう。
商社に興味がある人は、こちらの記事も必見です。5大商社の業界・企業理解を深めることができます。
商社の選考を受ける人は、併せてこちらの記事も参考にしましょう。志望動機の書き方を解説しています。
志望職種別のガクチカ例文6選
次は職種別の例文を紹介します。職種毎でも問われる特性は異なるため、自身の志望する意識に合わせてガクチカを作成する必要があるのです。
志望業界の例文を参考に、魅力的なガクチカを作成していきましょう。
法人営業
例文①法人営業
私は学生時代にスキーサークルでの活動に力を入れました。
活動を通して、自身の感情と行動を切り分けて、目標に向かって努力する大切さを学びました。
スキーサークルでは雪が降らない時期に練習ができません。春や夏にも練習をしたいと思ったとき、遠征が視野に入ります。スキーをやる以上は少しでも上達したい、そう思った私は費用を集め、遠征をしようとサークルに呼びかけました。
実際の費用集めとして、サークル員から回収する部費を上げる交渉を各サークル員とし、費用のために必要な各サークル員のバイトの管理をしました。サークル員からは不満も出たのですが、私たちのサークル活動に必要なことだと判断したので、感情を切り分けて説得を試み、賛同してもらうことを地道におこないました。
また、各サークル員のバイトの状況などを管理し、私自身もほかの部員より少し多めにお金を出せるようバイトのシフトをスケジューリングして資金集めをおこないました。
結果的に夏にオーストラリア遠征をおこない、練習をすることができました。大会でも優秀な成績をサークルで収めることができ、確実な成果を上げることができました。
以上のように目標の達成のために、自分の感情と行動を切り分けて努力する大切さを学んだことが、私が学生時代に力を入れた経験から得たものです。
法人営業には、顧客企業の課題を解決して業績を伸ばすための提案力が求められます。
サークルやバイト先などで何かを提案し、困難を乗り越えた経験があれば、積極的にアピールしましょう。
ガクチカにバイト経験を活かしたい人は、下記のQAを参考にしてみてください。
バイトリーダーをしていた経験はガクチカとして強いですか?
ガクチカになるアルバイトとしておすすめはありますか?
ガクチカがアルバイト経験しかないのですが大丈夫でしょうか?
個人営業
例文②個人営業
私は学生時代に長期インターンに力を入れました。
この長期インターンではお客様の課題に、どのようにアプローチするかを試行錯誤ができ、一歩踏み出す力が身に付いたと考えています。
私はインターンのなかで、アウトバウンドのテレフォンアポイントメントをおこなっていました。売る商材はウォーターサーバーでした。
ウォーターサーバーはその商品の特性上、老若男女問わず多くの人に営業をすることができます。一方で他社からも多くの製品が出ており、差別化が難しい商品でもありました。
そこで私は営業力で勝負をしようと考えました。ノルマとして1日に200本の電話をかけることを自身に課し、できるだけ多くの人と会話をするようにしました。
そして、その会話のなかではただウォーターサーバーの紹介をマニュアル通りにするのではなく、電話の向こうにいる人の生活に関するお悩み事がないかを探り、ニーズがどこにあるのかを考えながら話を展開することを心掛けて仕事をしました。
高齢の方であれば足腰が痛まないかなど心配をしつつ「お出かけするシーンを減らせますよ」と伝えてみたり、運動をよくされる方であれば「お店でお水を買うよりもウォーターサーバーで水を飲み、プロテインなどを作るほうが節約になりますよ」と伝えてみたりしました。
結果的にインターン生でありながら、営業成績で社会人として働く先輩方と肩を並べる業績を出すことができました。
以上の経験を経て、お客様の課題に、どのようにアプローチするかを試行錯誤ができ、一歩踏み出す力が身に付きました。
個人営業では、さまざまなタイプの人と良好にコミュニケーションがとれることが重要です。
誰とでも気軽に話をすることができ、相手に喜んでもらえたようなエピソードがあればアピールしましょう。
営業職志望の人は、こちらの記事もチェックしてみてください。営業職の志望動機の書き方についてプロが詳しく解説しています。
システムエンジニア
例文③システムエンジニア
私は学生時代にアルバイトに力を入れました。
このアルバイトでは入念な計画を立てて目標に向かう大切さを学びました。
私は学生時代に塾講師としてアルバイトをしていました。私の塾では個別指導をしており、担当する学生の志望校合格までのスケジュールを指導する側が立てます。
担当していた生徒の志望校と学力に大きな差があったのですが、学生側に志望校への強い熱意があり、本気でその学校に合格するためのスケジュールを立てることになりました。
試験日から逆算し、その学校の二次試験に必要な科目毎のスケジュールを立てました。2週に1度、個人的に作問したテストを課し、進捗を確認し、遅れていればスケジュールを更に修正して、これを繰り返しながら合格に必要な学力を身に付けるために生徒とマンツーマンで試験日まで駆け抜けました。
最終的に生徒は志望校に合格を果たしました。
以上のように、私は目標から逆算した必要なことを計画に落とし込み、実行する行動力をアルバイトを通して学ぶことができました。
システムエンジニアを受ける際には、ガクチカでリーダーシップを発揮した経験をアピールすることがおすすめです。
システムエンジニアはプロジェクトマネジメントスキルが必要なため、リーダーシップを発揮した経験がアピールできると高く評価されます。
販売
例文④販売
私は学生時代に部活動に力を入れて取り組みました。部活動では周囲の人々と良い雰囲気を作り上げる重要性を学びました。
私のサッカー部はリーグに所属し、さまざまな大学と定期的に試合をするのですが、ホームゲームで勝てるのにアウェイゲームでは負けるという課題がありました。課題の要因を更に掘り下げていくと、相手チームの雰囲気に飲まれるという点に行きつきました。
そこで私はこの課題を解決するために、休日に、ほかの大学まで来て自分たちを応援してくれるようなサポーターを作ろうと考えました。ピッチで戦う自分たちに、応援してくれる人の声が届くことが重要だと考えたのです。
実際におこなったこととして、大学のなかで1日100枚のビラを配りました。大きな声を出すだけでなく、キャンパス内を歩く人やグループに合わせて話しかけ方を変えて、少しでも多くの人に自分たちに興味を持ってくれるように、声掛けをしました。
また、公開練習をおこなったり、サッカー体験教室を大学で開くなど、自分たちとの接点を増やすための企画もおこない、かかわってくれた人に楽しんでもらいながら自分たちを応援してもらえるよう工夫しました。
結果としてチームは歴代最高順位でリーグを終えることができ、その背景には今まで以上に私たちを応援してくれるサポーターの皆さんがいました。
このように、私は周囲の人々と良い雰囲気を作り上げる重要性を学生時代に力を入れた経験から学びました。
販売職では、さまざまなタイプの人と良好にコミュニケーションが取れることが重要です。
相手の望むものを探り出し、提案することで相手に喜んでもらえたようなエピソードがあると良いでしょう。
事務
例文⑤事務
私は学生時代にゼミに精力的に取り組みました。ゼミでは他者の状況を推察しながら、先回りして動く大切さを学びました。
私たちのゼミではゼミ生による共同発表が定期的にありました。ゼミ生全員で取り組むのでうまく役割分担をしながら発表準備をおこなうのですが、一人ひとり日常生活の忙しさや状況が異なるので、定期的な発表のなかで時期により誰かが忙しく、パンクしそうになることがありました。
誰かが準備をおろそかにすると、全体に影響が出ます。そこで私は発表準備が始まる前に、事前に準備期間の忙しさを測るためのアンケートを導入しました。
アンケートのなかでは「何時間程度稼働できるか」「どういう準備が得意か」「どういう準備が苦手か」「取り組んでみたいことはあるか」を確認し、その状況に応じて役割と任せる準備量を配分するよう制度化しました。
また、実際に準備が始まった後もアンケートを活用して「この人はこれが苦手だから先回りして自分が対応しよう」という行動や「この準備はこの人が得意だから任せてみよう」、「そろそろこの人が忙しくなるから代わりにこの仕事をしよう」と気遣いながら準備に取り組みました。
結果として私たちの代は学会で評価されるほどの研究成果を出すことができました。
以上の経験から他者の状況を推察し、先回りして動く大切さを学びました。
事務職を受ける際のガクチカでは、コミュニケーションスキルのアピールがおすすめです。
事務職ではコミュニケーションスキルは要らないと思われがちですが、チームで協働することもあるため必要なスキルとなります。
事務職を志望している人は、こちらの記事も参考にしてみてください。志望動機の書き方を押さえておきましょう。
企画
例文⑥企画
私は学生時代に資格取得に力を入れました。資格取得のために必要な「実行力」をこの経験で学ぶことができたと考えます。
私は学生時代に資格を15個取得しています。資格取得にはそれぞれの試験日からの逆算したスケジュール作成が必要になります。
また、それぞれの試験で問われる能力が異なるので、勉強のやり方も変える必要があります。画一的なやり方ではうまくいかないので、自分が苦手なことや未知の経験でもまずは計画をして、実際に実行をしながら微調整をすることが重要になります。
そこで私はそれぞれの資格に取り組む前に取得のために必要なことをパワーポイントでわかりやすくまとめ、ゼミの先生や母校の恩師にプレゼンをし、必要なことや発想を頂戴し、苦手なことでも実行するようにしました。
たとえば秘書検定などでは実際に友人に協力を仰ぎ、状況を演じてもらいながら勉強をするなど、合格に必要だと思うことは実行をし、その成果をExcelにまとめながら、継続的にすべきこととそうでないことを分けて勉強しました。
結果的に資格取得ができ、それ以上にそのために必要な実行力を得ることができたと思います。実際の業務のなかでもこの実行力を活かして、さまざまな業務の分析から業務改善の実行をおこなってまいりたいと思います。
企画職を受ける際は、具体的でわかりやすく簡潔に文章を書くことが重要です。
さらに、現状をきちんと分析し、思いを込めて提案し、他人に理解してもらい、周りの人を巻き込み、何かを実行できたエピソードがあると良いですね。
ガクチカの書き方を制して選考を有利に進めよう
ガクチカは言葉のとおり、学生時代に頑張ってきたことではありますが、いざ書こうと思うとなかなか手が進まないという悩みも多いです。
そんな人は、この記事で解説してきた5ステップに従って作成することで、企業の求める内容をわかりやすく盛り込んだガクチカが書けるようになります。
ガクチカの書き方をマスターすれば、自己PRや志望動機などにも活かすことができ、就職活動を効率よく進めることができるのです。
だからこそ、本記事の書き方を参考にして、最強のガクチカを作成して、選考を突破しましょう。
アドバイザーからあなたにエールガクチカでは成果ではなくプロセスを重視することを改めて意識しよう
ここまでに紹介したガクチカの例文のように、うまく書けるかどうか不安に感じている人がいるかもしれません。しかし、ガクチカは「力を入れたこと」であって「成果をあげた経験」ではありません。そのため、成果にこだわると伝えたいことが伝えられなくなってしまう可能性もあります。
たとえば、あなたがTOEICで600点から900点までスコアを伸ばした実績があるとします。このときに、あなたがアピールすべきことは「900点を獲得したこと」ではなく「900点を獲得するまでにしたこと」です。
また、あなたが本当に伝えたいことも「スコアを伸ばすために努力をした」という後者なのではないでしょうか。
実績よりも入社後に活かせる経験をしているかどうかが重要
就活が始まるとほかの学生と自分を比べて、つい実績を重視してしまいます。しかし、説明したとおり企業が重視していることは実績よりも入社後に活かせる経験をしているかどうかです。
周りの学生と比較をするのではなく、自分がアピールしたいことと向き合い、ガクチカをアピールして自分が活躍できる企業の内定を獲得しましょう。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi






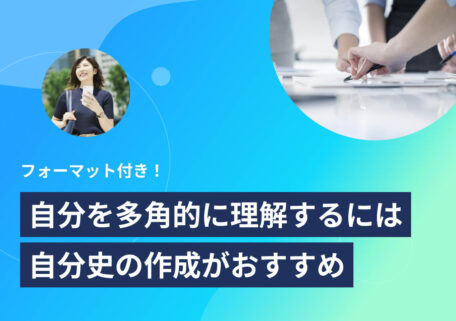




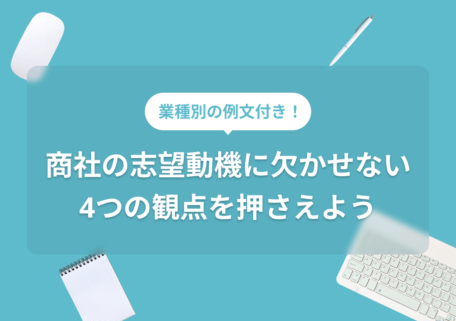
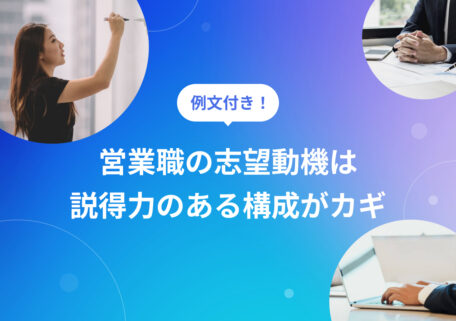














5名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/産業カウンセラー
Atsuko Hirai〇ITメーカーで25年間人材育成に携わり、述べ1,000人と面談を実施。退職後は職業訓練校、就労支援施設などの勤務を経て、現在はフリーで就職・キャリア相談、研修講師などを務める
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/なべけんブログ運営者
Ken Tanabe〇新卒で大手人材会社へ入社し、人材コーディネーターや採用、育成などを担当。その後独立し、現在はカウンセリングや個人メディアによる情報発信など幅広くキャリア支援に携わる
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士
Masamitsu Uehara〇会社員時代は人事部として3000人以上の学生と面談を実施。大学でも多くの学生のキャリア支援をおこなう。独立後は、就活生からシニア層までさまざまなキャリア相談に携わる
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表
Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアコンサルティング技能士
Hiroshi Takimoto〇年間約2000件以上の就活相談を受け、これまでの相談実績は60000件超。30年以上の実務経験をもとに、就活本を複数出版し、NHK総合の就活番組の監修もおこなう
プロフィール詳細