この記事のまとめ
- 公務員が安定している理由の把握が職業理解につながる
- 公務員のマイナスな一面も確認してから就職を判断しよう
- 安定と言われる公務員を目指して後悔する人の共通点も解説
公務員を目指す人のなかには、「安定しているから」という理由で志望する人もいると思います。しかし、公務員が安定と言われる理由や実際の働き方、デメリットなどを把握せずに志望するとイメージとのギャップに後悔してしまうかもしれません。
この記事では、キャリアコンサルタント古田さん、木原さん、前田さんと一緒に、「公務員が安定している」と言われる理由やリアルな働き方などを解説します。
「安定」という言葉に惹かれているものの公務員の実情について深く把握できていない人は、就活における判断をする際の参考にしてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
「安定」以外の公務員の特徴を知ることがミスマッチの回避につながる
公務員には「安定している」以外にもさまざまな特徴があり、人によってはデメリットと感じられる一面もあるのです。そのため、就職後のミスマッチを防ぐためには、あらかじめ「安定している」以外の公務員の特徴を理解しておくことが大切です。
この記事では、前半で公務員が「安定している」と言われる理由やリアルな働き方、デメリット・注意点などを解説します。まずは公務員として働くことの実情を知り、就職先を決める際の判断材料を集めましょう。
そして記事後半では、公務員に向いている人の特徴や、ミスマッチを防ぐための方法などを解説します。就職してから「やめておけば良かった」と後悔しないためにも、自身の適性を見極めて慎重な判断ができるようにしましょう。
あなたが公務員に向いているか確認してください
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
まずは基本から! 公務員の概要
前提として、公務員は民間企業と異なる特徴を持ち、働き方も違います。また、公務員のなかにも国家公務員と地方公務員の2種類があり、それぞれ特徴が異なるのです。
公務員を志望するにあたって、ミスマッチを防ぐためにも、これらの前提知識は必ず理解しておく必要があります。
ここからは、公務員の基本的な情報を解説します。就職後に「知らなかった」とならないよう、事前に確認しておきましょう。
公務員一本で就活をしようと考えている人はこちらのQ&Aも参考にしてみてください。キャリアコンサルタントが危険性を回答しています。
公務員と民間企業の違い
公務員と民間企業の大きな違いは、仕事の目的と雇用の安定性です。仕事の目的と雇用の安定性の違いを以下に示しています。
| 仕事の目的 | 雇用の安定性 | |
|---|---|---|
| 公務員 | 国民や地域社会のために公共サービスを提供すること | 原則としてリストラがなく、安定した収入が得られる |
| 民間企業 | 営利を追求すること | 景気や経営状況に左右されることがあるため、雇用リスクがつきもの |
さらに、キャリアパスにも違いがあります。公務員は年功序列が基本で、計画的な昇給や昇進が期待できますが、民間企業では成果主義が導入されている場合が多く、個人の業績が昇進や昇給に直結します。
これらの違いを理解することは、自分のキャリアの方向性を考える際にも重要となるため、入念に確認しておきましょう。
私は公務員と民間企業の両方で働いた経験があります。公務員は民間企業と異なり、利益を追求するわけではないので、同僚や上司との関係性が穏やかで協調性が求められることが多かったです。
ただし、業務内容や昇進のスピードが比較的制度化されているため、自分の希望だけで柔軟に動けないこともあります。
一方で民間企業は成果主義が強く、結果が昇進や評価に直結するケースが多いです。その分、自分の努力やスキルで道を切り開ける可能性はありますが、競争が激しい側面もあります。
公務員の種類
一言で公務員といっても、国家公務員と地方公務員の2種類があり、それぞれ仕事の目的や仕事内容、働き方が異なります。
自身が公務員として働くことにマッチするかどうか判断するにあたって、国家公務員と地方公務員の違いを理解し、自身の適性を見極めることが大切です。
ここからは、国家公務員と地方公務員それぞれの特徴を解説します。それぞれの種類についてまだ理解が不十分で、進路に迷いがある人は確認しておきましょう。
国家公務員
国家公務員は、国全体の運営を支える仕事です。具体的な職務内容は、国の政策立案や実行、法律の執行、国際関係の調整など多岐にわたり、国民全体に影響を及ぼす重要な役割をはたします。
勤務地はおもに中央省庁や地方支部で、各地域に派遣される場合もあります。
国家公務員の魅力の一つは、影響範囲の広い仕事に携われる点です。たとえば、外交官や財務省の職員は国際的な交渉や国の財政運営といった、国家規模での課題に取り組むことができます。
また、専門性の高い分野でキャリアを築くことができるため、長期的なキャリア形成を目指す人に向いています。
一方で、責任が大きく、長時間労働が求められる場合もあるため、体力や精神力が必要です。勤務地が全国に広がるため、転勤が避けられないケースも多いのが特徴です。
なお、国家公務員にもさまざまな種類があります。以下の記事では国家公務員の種類を解説しているので、少しでも就職の選択肢に入れている人はチェックしておきましょう。
地方公務員
地方公務員は、各都道府県や市区町村など地方自治体の運営を支える役割を担います。おもな職務内容は、地域住民に密接にかかわる行政サービスの提供です。
具体的には、税務、福祉、教育、公共インフラの維持管理、防災など多岐にわたります。地域密着型の仕事が多く、住民と直接かかわる場面が多いのが特徴です。
地方公務員の魅力は、地域の課題を解決するために直接働きかけることができる点です。たとえば、地域の活性化や住民サービスの向上に貢献できるため、地元への愛着が強い人に向いています。
また、勤務地が比較的固定されているため、転勤が少なく、地元で働きたい人にもおすすめです。
ただし、部署によっては繁忙期や特定の業務の時期に残業が発生することがあります。また、幅広い業務をこなす必要があるため、柔軟な対応力や学習意欲が求められることは理解しておきましょう。
- 地方公務員は国家公務員に比べて仕事による影響範囲が狭まりますが、その分給料が少ないなど劣る部分もあるのでしょうか。
地方公務員は相対的に給料が少ないが全体のバランスが大切
給与水準は国家公務員の方が高めです。特に、中央省庁で働く場合や特定の専門職種での給与は高くなる傾向があります。
地方公務員の給与は自治体ごとに異なりますが、国家公務員と比較すると低いことが多いです。大都市など住む場所によっても異なります。
また、国家公務員は明確で昇進の機会が多いのに比べて、地方公務員は小規模な自治体ではキャリアが限られることもあるのです。
ただし、国家公務員は転勤が多かったり、政策変更の対応などで多忙期があったりするため、ライフバランスを取るのが難しいこともあります。
何をもってして「劣る」と考えるかは人それぞれですが、自分の価値観に合った選択をすることが大切です。
あなたと公務員のマッチ度を診断しよう
就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。
そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。
自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
公務員が「安定している」と言われる7つの理由
公務員が「安定している」と言われる7つの理由

「公務員は安定している」と聞いたことがある人も多いかもしれません。この安定性を魅力に感じて公務員を志望する人もいるのではないでしょうか。
しかし、「公務員は安定している」と言われる理由や背景を理解している人は少ないかもしれません。この理由・背景を理解せずに就職すると、「思っていたイメージと違う」と後悔してしまう可能性があります。
そこでここからは、公務員が「安定している」と言われる理由を7つ解説します。公務員の安定性の背景を知って、仕事に対する理解を深めましょう。
①社会的な信用度が高い
公務員は法律にもとづき公正に職務を遂行する立場にあり、社会的な信用度が高い職業とされています。特に、国や地方自治体といった公的機関で働くことから、住民や企業からの信頼が厚く、公務員であること自体が信用の証になることが多いです。
また、安定した収入と雇用形態から、住宅ローンの審査や賃貸契約などでも優遇されるケースが多く見られます。その理由は、公務員の身分が法律で保護されていて、突然解雇されるリスクが非常に低いためです。
このように、公務員は社会的信用度の高さを活かしながら、安心して働きたい人にとって非常に魅力的な選択肢といえます。
誰もが知る大企業も確かに社会的信用度は高いですが、景気に左右される民間企業であることに変わりはありません。
そのため、長い目で見ると国や自治体に所属しているという安心感のある公務員の方が社会的信用度は高いといえます。
②リストラの可能性が極めて低い
公務員は法律で雇用が保護されているため、リストラされる可能性が極めて低い職業です。
民間企業では、業績の悪化や経営環境の変化によって雇用調整がおこなわれる場合がありますが、公務員は基本的に国や地方自治体が財源を確保しているため、安定した雇用環境が維持されています。
さらに、公務員の職務は国民生活を支える重要な役割をはたしているため、雇用調整よりもサービスの継続が優先される傾向があります。そのため、公務員は長期間にわたって働き続けやすい環境が整っているといえるのです。
ただし、自治体の財政破綻や国全体の経済状況の悪化が深刻化した場合、一部の職種や部署でリストラがおこなわれる可能性がまったくないわけではありません。実際に、過去には財政が厳しい自治体で人件費削減策が取られた事例もあります。
北海道夕張市は給与や退職金を大幅に減額し、半数以上の職員が退職し、事実上リストラといわれています。
そのほか、人口減少や地域経済が停滞する市区町村は税収が減少するため、経費削減としてリストラの可能性があります。
まずは公務員に適性があるか診断しましょう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
③転勤の回数が少ない
公務員の多く職種は、転勤の回数が民間企業に比べて少ない傾向にあります。
特に地方公務員の場合、勤務地が都道府県や市区町村内に限定されるため、地元に根付いた生活を送りながら働き続けることが可能です。家庭環境や地域コミュニティを重視したい人にとっては大きなメリットといえます。
一方で、国家公務員の場合は、特定の省庁や機関によって異なりますが地方への転勤が求められることもあります。ただし、それでも民間企業のように全国規模で頻繁に転勤があるわけではなく、比較的計画的な異動が多いです。
また、公務員は事前に異動のタイミングや勤務地が告知されるケースが多く、突然の転勤を求められることが少ない点も安心材料です。
とはいえ、全国転勤や転勤回数が多いことはデメリットばかりではありません。全国転勤が向いている人もいるので、以下の記事を参考にして、自分の向き不向きを見極めましょう。
④福利厚生が充実している
公務員は、福利厚生が充実している傾向にあります。福利厚生が充実していることは、安定した生活基盤を支える大きな要因の一つであり、多くの人が公務員を目指す理由にも挙げられます。
具体的には、健康保険や年金制度、住宅手当、育児・介護休暇制度などが整備されていて、ライフステージに応じて安心して働き続けることが可能です。
また、公務員には共済組合があり、民間企業の社会保険よりも手厚いサービスを受けられる場合があります。たとえば、医療費の補助額や退職後の年金受給額が比較的高いことなどが挙げられます。
さらに、休暇制度が充実している点も公務員の魅力の一つです。有給休暇の取得率が比較的高く、リフレッシュ休暇や特別休暇が設けられている場合もあります。これにより、仕事とプライベートのバランスを取りやすい働き方が可能です。
⑤国民の税金から給与とボーナスが支払われる
公務員の給与とボーナスは、国民から徴収される税金によって支払われています。この仕組みは、公務員が安定した収入を得られる理由の一つです。このように給与やボーナスが税収にもとづくため、経済状況の影響を受けにくく、収入が安定しているといえます。
また、民間企業のように業績によって給与が変動するリスクが少なく、一定の生活水準を維持しやすい環境が整っています。
しかし、この安定性は、公務員の仕事が常に国民の信頼と期待のうえに成り立っているという点を忘れてはいけません。
給与やボーナスの支払いが税金に依存しているため、無駄遣いや不適切な行動があれば国民の批判を受ける可能性があります。そのため、公務員には高い倫理観や責任感が求められるのです。
なお、自治体の財政状況によっては給与やボーナスの水準が見直されるケースもあります。このため、安定しているとはいえ、すべての公務員が一律に同じ待遇を受けられるわけではない点も理解しておきましょう。
⑥年功序列で昇給していく
公務員の給与体系は、年功序列の仕組みにもとづいているため、勤続年数が長くなるほど給与が着実に上がる仕組みになっています。これにより、長く働けば働くほど収入が増えるという安定したキャリアパスを描くことが可能です。
特に、若い世代では初任給が高くなくとも、昇給が見込まれることで将来的な生活の安定が期待できます。また、昇給のペースがあらかじめ決まっているため、給与が予測しやすく、住宅ローンや教育費といった長期的な資金計画も立てやすい点がメリットです。
ただし、年功序列の仕組みがすべての人にとって最適とは限りません。成果主義や能力重視の昇給を望む人にとっては物足りないと感じる場合もあります。
また、近年では年功序列の見直しを検討する動きもあり、将来的には給与体系が変更される可能性もあります。このため、制度の変化にも柔軟に対応できる準備が大切です。
民間企業では成果主義を取り入れる動きが広がっていて、公務員にも年功序列制度の廃止を求められることが増えてきています。
実際に人事評価制度の見直しや、能力や成果に応じた給与や昇進制度を導入する自治体や機関も出てきています。
ただし、公務員は公共の利益を優先して安定性や公平性が重視されるため、完全な成果主義への移行は難しいかもしれません。
年功序列を基本としつつも、成果やスキルを評価する仕組みを組み合わせた「ハイブリッド型」の人事制度が主流になる可能性があるのではないかと考えます。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
⑦多額の退職金を受け取れる
退職金は長年勤めた成果を評価したものであり、勤続年数が長いほど支給額も増加する仕組みが一般的です。特に公務員の場合、退職金の支給基準が明確で、民間企業と比較しても高水準に設定されていることが多いです。
また、公務員の退職金は、退職後の生活基盤を支える重要な収入源として位置づけられています。老後の生活費や子どもの教育費、住居ローンの返済など、将来の大きな支出に備えることができます。
ただし、将来的に公務員の退職金制度が見直される可能性もゼロではありません。財政状況や人口の変化にともない、支給額が減額されることも考えられるため、退職金だけに頼らない資産形成も必要です。
なお、安定と言われる職業は公務員以外にも存在します。以下の記事では安定な職業11選や「安定」の考え方を詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
キャリアの専門家が解説! 安定と言われる公務員のリアルな働き方
前述のとおり、公務員は収入や雇用などの安定性が高く、安心感を持ちながら仕事に取り組むことができます。
しかし、実際に一日の働き方を把握している人はいるのではないでしょうか。「安定している」と言われる裏側では、残業が多かったり、風通しが悪かったりするなどの、知られていない実情があるかもしれません。
そこで、ここからはキャリアコンサルタントの古田さんに、安定と言われる公務員のリアルな働き方について聞いてみました。古田さんのコメントを参考にして、実際に公務員として働いた際のイメージを膨らませましょう。
アドバイザーコメント
公務員の働き方は職種や部署によってさまざま
公務員と言っても職種は多岐にわたります。警察官や自衛隊員、消防士、教職員、福祉サービスの職員まで本当にさまざまです。
そのため、一日の流れを説明するのは難しいですが、一般企業に勤務する人と同様、出勤してから退勤まで担当業務をこなすだけで、公務員だからといって特別な働き方があるわけではないのです。
業務内容も職種や所属部署によって異なります。公務員というとデスクワークのイメージがあるかもしれませんが、職種や所属部署によっては一日中外出している職員もいます。
労働環境も一般企業と決定的な違いがあるわけではない
また、公務員は定時で帰るイメージがあるかもしれませんが、業務の締切が迫れば残業が発生します。警察官などは部署によって勤務時間がシフト制で拘束時間が長く、業務の合間に仮眠を取る部署もあります。
業務自体はフローが決まったものばかりで変更が簡単でない部分があるため、効率化を提案したり、自主的に業務手順を変更したりしようとしても、簡単には通らないことが多いです。
公務員はたしかに安定しているかもしれませんが、どの職種の現場も一般企業と大差ないと考えておくと良いでしょう。
所要時間はたったの3分!
受けない方がいい職業を診断しよう
就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。
就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。
- 自分に合う職業がわからない人
- 入社後のミスマッチを避けたい人
- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人
就活前に知っておきたい! 公務員のデメリット・注意点
就活前に知っておきたい! 公務員のデメリット・注意点
「安定している」と言われる公務員ですが、必ずしもメリットばかりではありません。人によってはデメリットに感じる部分もあるのです。
ここからは、公務員のデメリットや注意点を解説します。就職後に「思っていたイメージと違う」「やめておけば良かった」と後悔しないためにも、公務員のデメリット・注意点を事前に理解しておきましょう。
残業が多い職種・部署が存在する
公務員は「安定している」「働きやすい」といったイメージが強いかもしれませんが、実際には部署や職種によっては残業が多い場合があります。
特に、市役所・県庁の窓口対応や災害対策を担当する部署、または国の政策立案にかかわる国家公務員の部署では、繁忙期になると長時間労働が発生しやすい傾向にあります。
具体的には、選挙や税金関連の手続きが集中する時期、または自然災害発生時には、住民対応や復旧支援のために夜遅くまで業務をおこなうことが求められる場合があるのです。
また、公務員の仕事はチームで進めることが多いため、自分のタスクが終わってもほかのメンバーのサポートに回るケースが少なくありません。結果として、予定外の残業が発生することもあります。
そのため、公務員を目指す際は、残業の可能性がある職種や部署について事前に調べ、自分のライフスタイルや体力に合った働き方を検討することが重要です。
残業のない仕事を探している人は以下の記事がおすすめです。残業の少ない仕事24を紹介しています。
部署異動が多い
公務員は、職種や勤務地によっては頻繁に部署異動があります。特に地方自治体では、数年ごとに部署が異動するケースが一般的で、住民窓口業務、財務管理、観光振興などさまざまな業務を経験することが求められます。
また、国家公務員の場合、地方出先機関や本省間の異動が発生することもあり、勤務地が大きく変わることも考えられるのです。
このように部署異動が多い理由としては、多様な経験を積むことで公務員としてのスキルを幅広く身に付け、業務全体への理解を深められるからです。また、特定の部署に人材が集中しないようにする目的もあります。
ただし、頻繁な異動はデメリットばかりではありません。新しい業務に触れられたり、新しい人間関係を構築できたりするなどの良い一面もあります。そのため、メリット・デメリットを理解したうえで、部署異動を許容できるか判断しましょう。
業種や自治体によって異なりますが、公務員は約1〜4年ごとに異動があります。
そのたびに新しい業務を覚え、人間関係を構築していくことになるので、変化にストレスを感じやすい人は慣れるまで環境に不安を覚え、業務効率も下がるかもしれません。
ESで悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!
『就活準備をもっと効率よく進めたい...!』と思っていませんか?「就活準備プロンプト集」は、生成AIを活用して自己PRや志望動機をスムーズに作成できるサポートツールです。
簡単な入力でプロが使うような回答例が出せるため、悩まずに就活準備を進められます。生成AIを活用して効率良く就活準備を進めたい人におすすめです。
- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト
- チャットを使用した、模擬面接プロンプト
- 自己PRで使える強み診断プロンプト
民間企業への転職のハードルが高い
公務員は安定した職業である分、一度公務員として働くと民間企業への転職が難しくなる場合があります。公務員独自の職務内容や職場環境に一度慣れると、民間企業のスピード感や成果主義に適応するのが難しいと見られることがあります。
また、業務が分業化されているケースが多く、特定の専門スキルを深める機会が少ない場合、民間企業での即戦力としての評価が下がる可能性があるのです。
特に、公務員の仕事では直接的な売り上げや利益を生む役割が少なく、民間企業が重視する「収益への貢献度」をアピールしにくいことも、転職のハードルを高める要因です。
そのため、公務員から民間企業への転職を目指す場合は、在職中から専門スキルを磨く努力をしたり、資格取得や副業などで実績を積んだりすることが重要です。
実際に、民間企業への転職も視野に入れて公務員を目指す人もいると思います。以下のQ&Aコンテンツでは、公務員から民間企業への転職は不利になるのかどうか、キャリアコンサルタントが疑問に回答しているため、ぜひ参考にしてください。
決裁まで時間がかかり業務改善がされにくい
公務員の職場では、意思決定や業務改善に時間がかかる傾向があります。その理由の一つは、組織の階層が多く、上司や関係部署の承認を得るために多くの段階を経る必要があるからです。
特に予算の使用や新しい施策の実施に関しては、厳密な審査や手続きが必要となるため、迅速な対応が難しいことがあります。
また、公務員の職場は前例主義が根強い場合が多く、過去の事例や規則にもとづいた判断が優先されることがあります。そのため、現場で業務改善の必要性が感じられても、新しい提案が採用されるまでに長い時間がかかることは少なくありません。
さらに、公務員は民間企業に比べて競争環境にさらされる機会が少ないため、外部の変化に対して柔軟に対応する仕組みが整っていないことも業務改善がされにくいことの理由の一つとして考えられます。
意思決定に時間がかかることで対応が遅れると、関係者や市民に不満を与える可能性があります。
特に緊急性の高い課題や、柔軟性が求められる状況では、フラストレーションを感じやすくなります。
また、公務員では多くの人が意思決定に関与するため、書類作成や説明に手間がかかり、業務の効率が低下することもデメリットです。
将来的に必ずしも年功序列・終身雇用であるとは限らない
公務員の働き方は年功序列と終身雇用の典型的な例ですが、これが将来的に保証されているわけではありません。近年の社会情勢や財政状況の変化、そして少子高齢化にともなう労働人口の減少などが背景にあり、ゆくゆくは公務員制度が見直されることも考えられます。
さらに、AI(人工知能)やIT技術の進化により、定型業務が自動化されることで、これまでの業務形態に大きな変化が生じる可能性もあります。
このように、必ずしも将来永劫に安定しているとは限らないため、年功序列や終身雇用に安心しきるのではなく、自分のキャリアビジョンを長期的に見すえながら、公務員としての安定性をどのように活かすかを考えることが大切です。
一部の仕事がAI(人工知能)に代替される恐れがある
近年のAI技術の進化が見受けられるようになりました。特に単純作業や定型業務を中心にAIによる自動化が進んでいます。
公務員の仕事においても、データ入力や書類の整理、一定のルールにもとづいた業務処理などの下流業務を中心に、従来は人間が担当していた作業がAIに代替され自動化が進むと考えられているのです。
言い換えれば、AIの導入によって単純作業から解放されることで、より本質的で創造性の高い業務や、住民サービスの質を向上させる取り組みに注力できるようになるというメリットともとらえられます。
ただし、この変化に適応するためには、AIでは代替できないスキルや、AIを使いこなす技術を身に付けることが重要です。
このように、AIの普及による仕事の変化は公務員の安定に対して不安を感じる要因と思えるかもしれませんが、見方を変えれば新しいキャリアの可能性を広げるチャンスと理解しましょう。
従来のやり方をただ踏襲すれば良いという「守りの姿勢」が強すぎたり、自ら率先して物事を改善していくという思考が乏しかったりすると、AIの普及による変化についていくことができず、公務員として就職しても取り残されてしまう可能性があります。
公務員の仕事はAIによってなくなるのではないかと不安を感じる人もいるかもしれません。以下の記事ではAIによってなくなる仕事を紹介しているので参考にしてください。
また、公務員の高い安定性によるメリットよりも、デメリットのほうが大きいなどギャップを感じて退職・転職を検討する人も一部存在します。
以下の記事では、公務員を辞めたいと思う人に共通する特徴などを解説しているので、リアルなデメリットが気になる人は確認してみてください。
プロが語る! 公務員のキャリアは本当に安定していると言えるのか?
ここまで公務員が「安定している」と言われる理由や、デメリット・注意点などを解説しました。ここまでの内容から「結論として公務員は安定していると言えるのか」と気になる人もいると思います。
そこでここからはキャリアコンサルタントの木原さんに、公務員のキャリアは本当に安定していると言えるのかどうかを聞いてみました。安定性を重視する人は、公務員の実情を理解して、今一度自身のキャリアを考えてみてください。
アドバイザーコメント
公務員は雇用や収入の安定性の観点では安定している
公務員のキャリアは一般的に「安定している」と言われますが、何をもってして「安定」ととらえるかは悩ましいところです。
大きな特徴として挙げられるのが、雇用の安定性です。景気変動や企業の業績に左右されにくいため、解雇のリスクが低く、収入も安定しています。
そういった意味では、長期的な生活設計が立てやすいといえます。
公務員の働き方の良し悪しは自身の価値観で判断するのが大切
しかし、少子高齢化や災害対応、複雑化する行政ニーズにより、一人あたりの業務負担が増加している職場もあります。
さらに、自治体によって財政状況が異なるため、財政難に直面する自治体では職員の業務量が増加し、ワークライフバランスが課題になる例もあります。
また、専門性を極めるよりも幅広い業務に対応することが求められるため、特定分野でのスキルアップを目指す場合には不満を感じることもあるかもしれません。
公務員のキャリアは「絶対的な安定」ではなく、時代の変化や社会的な要請に応じて変わりつつあるというのが現実です。
安定志向が活きる! 公務員に向いている人の特徴
安定志向が活きる! 公務員に向いている人の特徴
ここまでの解説から、公務員は給与や雇用などの面では民間企業に比べて安定性が高いといえます。
しかし、安定な側面があるからといって、すべての人におすすめできるとは限りません。公務員の雇用形態には向き不向きがあるのも事実です。
そこで、ここからは公務員に向いている人の特徴を解説します。自身の向き不向きを見極めて、公務員を目指すかどうかの判断材料にしましょう。
収入や休日の安定を求めている
収入や休日が安定している仕事に就きたい人は、待遇や福利厚生の面で公務員が向いている可能性があります。
公務員の給与は景気の影響を受けにくく、国や自治体の予算によって支払われるため、民間企業のような急な収入減少のリスクが低いといえます。
また、年功序列による昇給制度やボーナスの支給も整っていて、将来の収入をある程度予測しながら生活設計を立てられるのが特徴です。
さらに、休日も法律にもとづいて確保されているため、年間の休日数が安定しています。そして、有給休暇の取得率が比較的高いことも、公務員の魅力として挙げられます。これらにより、仕事とプライベートを両立させやすい環境が整っているのです。
ただし、収入や休日が安定していることは、必ずしも仕事の負荷が少ないという意味ではありません。特に、繁忙期や緊急対応が必要な職場では残業が発生する可能性もあります。
そのため、安定を求めて公務員を目指す場合でも、仕事内容や職種ごとの違いをしっかり理解しておくことが重要です。
公務員に限らず、休みが多くて給料が良い仕事を探している人もいるのではないでしょうか。以下の記事では休みが多くて給料が多い仕事を紹介しているので、視野を広げるためにもチェックしておきましょう。
国や地域への貢献意欲が人一倍高い
公務員の仕事は、国民や地域社会に直接的に貢献できることが特徴です。そのため、国や地域への貢献意欲が高い人にとって、やりがいを感じられる職業といえます。
たとえば、福祉政策の立案やインフラ整備の推進、教育環境の改善、防災計画の実施など、国民・住民の生活を支える業務に携わる機会が多くあります。
このような職務では、目の前の課題に対して自ら考え、行動することが求められることが多いです。そのため、国や地域の抱える問題に真摯に向き合い、解決に貢献したいという強い意志を持つ人が活躍できる環境といえます。
また、地域住民や国民の声を直接聞き、行政サービスとして反映させる機会も多いのが公務員の特徴です。この点で、自分の仕事が誰かの役に立つと実感できる場面が多く、社会的な意義を重視する人には特に適しています。
どんなことにやりがいを感じるかは人それぞれです。人によっては、公務員以外でも十分なやりがいを感じながら仕事に取り組める場合があります。以下の記事ではやりがいのある仕事の見つけ方を解説しているので、併せて参考にしてください。
非常時でも平常心で対応できる
公務員の職務では、災害や緊急事態などの非常時に対応する場面が少なくありません。たとえば、地震や台風などの自然災害が発生した際には、被害状況の確認や救援物資の手配、避難所の運営など、迅速かつ冷静な対応が求められます。
こうした場面で必要なのが、非常時でも平常心を保ち、的確な判断を下せる能力です。
緊急事態では不安や混乱が広がりやすいため、公務員自身が冷静さを失うと国民・住民にさらなる不安を与えてしまう可能性があります。特に、防災担当や警察、消防といった危機管理に直結する職種では、よりいっそう非常時の対応能力が求められるのです。
また、非常時には住民や関係者から多くの問い合わせや要望が寄せられるため、冷静かつ丁寧に対応するコミュニケーション能力も必要です。感情的にならず、住民の不安を和らげる対応ができることは、公務員として大切な資質といえます。
アルバイト先でのクレーム対応の経験談のように、突然起こる日常生活のなかのトラブルに対し、いかに冷静かつ迅速に適切な行動を取れたかといったエピソードがあれば、就活の際も効果的なアピールポイントになります。
中立な立場で公平な判断ができる
公務員の役割は、国民や地域住民全体の利益を守ることにあります。そのため、特定の個人や団体の意見ばかりに耳を傾けるのではなく、中立な立場で業務を遂行することが求められます。
具体的には、公務員として公平な判断を下す際には法律や規則を正確に理解し、それにもとづいて意思決定をおこなうことが不可欠です。特に、異なる意見や利益が対立する場面では、中立的な立場を保ちながら最善の解決策を見出す能力が求められます。
さらに、公平性を保つには、日常業務のなかでも透明性を意識することが重要です。たとえば、手続きや審査の内容を住民に説明する際には、基準や判断理由を明確に示し、不信感を与えないよう努める必要があります。
このように日常生活のなかでも、自身の感情に左右されず物事を俯瞰的に見ながら中立な立場で物事を考えられる人は、公務員としての素質があるといえます。
住民・国民からのプレッシャーに負けない忍耐力がある
公務員は、国民や地域住民のために働く職業であるため、さまざまなプレッシャーを受ける場面が多くあります。たとえば、窓口業務では住民からのクレームや厳しい意見に対応する必要があり、災害対応や緊急事態では迅速かつ的確な判断が求められます。
これらの場面ではプレッシャーに負けず、冷静に対応できる忍耐力が欠かせません。
また、政策の実施や新しい制度の導入時には、住民や関係者の多様な意見を調整しながら進める必要があります。対立する意見に直面したり、批判を受けたりすることも珍しくありません。
このような環境のなかで感情的にならずに適切な対応を取るためには、高いストレス耐性が求められます。
このように、住民や国民からのプレッシャーに負けない忍耐力を持つことは、公務員にとって欠かせない資質であり、その役割を果たすうえで大きな強みとなります。
なお、ストレス耐性が高い人と低い人には決定的な違いがあるのです。公務員を前向きに検討しているものの忍耐力に自信がなく不安を感じる人は、併せてチェックしておきましょう。
キャリアのプロが解説! 安定性が高い公務員を選んで後悔する人の共通点
「公務員は安定しているから」と、安定性を重要視して公務員としてのキャリアを選択する人も見受けられます。しかし前述のとおり、公務員には向き不向きがあり、なかには就職後に後悔してしまう人もいるのです。
そこで、ここからはキャリアコンサルタント前田さんに、安定性が高い公務員を選んで後悔する人の共通点を聞いてみました。自身に当てはまる箇所がないかチェックして、本当に公務員を目指すべきか検討しましょう。
アドバイザーコメント
公務員の安定性の高さに気を取られず適性も併せて考慮しよう
公務員としてのキャリアを選択し、後悔する可能性のある人には以下の2つの共通点があります。
一つは、自分の適性をしっかり把握できていないという点です。公務員の業務にはさまざまな種類があり、異動も1〜4年ごとにあるのが一般的です。
そのことをしっかり認識しておかないと、自分の適性上取り組みが困難な業務に就いた際に業務そのものにもやりがいを感じられないどころか、その状況に困惑して「こんなはずでは…」と後悔してしまいます。
公務員を目指す目的や使命感を再確認しておくことが大切
もう一つは、困難な状況下に置かれると視野が狭くなってしまうという思考の癖を持っている点です。
単調で、しかもなかなか成果が上がらなかったり、そもそも成果が出なかったりする業務や、批判やクレームの多い業務に長い期間従事するといった精神的につらい状況に置かれた人は、目の前の困難さばかりに気を取られてしまいがちです。
しかしそのようななかでも、当初の使命感を忘れず、その業務の意義や全体像を俯瞰して現在の自分の状況を冷静に見つめることができる人はその状況を乗り越えられます。
そのため、自分がどのような思考の癖を持っているかという確認も大切です。
安定だけでは不十分! 公務員のミスマッチを防ぐための確認ポイント
「公務員は安定しているから」という安易な考えで就職を決めると、就職後にミスマッチが起きてしまう可能性があります。
だからこそ、自身が公務員の働き方に何を求めるかを「安定」以外の要素も含めてあらかじめしっかりと考え決断するのがおすすめです。
そこでここからは、公務員のミスマッチを防ぐために確認すべきポイントを解説します。自身が本当に後悔しないか、最終チェックの意味も込めて確認するようにしましょう。
公務員を目指す理由が「安定」以外にもあるかどうか
公務員の安定性はたしかに大きな魅力かもしれませんが、日々の業務内容に対する興味ややりがいを感じづらければ、長期的に満足感を得ることは難しいです。
公務員の仕事は、地域や国のために働き、社会全体に貢献することを目的としています。そのため、「地域課題の解決に取り組みたい」「国民の暮らしを支える政策にかかわりたい」といった明確な動機を持てるかどうかが大切です。
具体的な目標があれば、日々の業務に意義を感じやすく、モチベーションを維持しやすくなります。
このように、安定以外の理由を明確にすることで、公務員としてのキャリアに充実感を得られる可能性が高まります。
- 「安定していること」以外、公務員の魅力が見出せません……。
スケールの大きな仕事を通して社会貢献できるのも公務員の魅力
安定だけでなく、やりがいや自己成長も公務員ならではの魅力です。その理由を3つ紹介します。
1つ目は社会貢献性です。公務員は地域や国全体のために働くことが求められ、市民の生活を支える役割を担います。
たとえば、福祉や教育、インフラ整備など、生活に直結する仕事を通じて多くの人の役に立つ実感が得られます。
2つ目は多様なキャリアパスです。部署異動が定期的におこなわれるため、一つの職場にとどまらずさまざまな分野で経験を積むことができます。
3つ目は仕事のスケールです。地域活性化や政策形成など、影響力の大きい仕事に携わることができる可能性があります。
これらの特徴を踏まえると、安定以外にも公務員の仕事にはたくさんの魅力があるといえるでしょう。
仕事に求める動機や目的を明確にするためには、自己分析が欠かせません。自己分析が不十分だと思う人は、以下の記事に沿って進めてみましょう。
自己分析全般
自己分析マニュアル完全版|今すぐできて内定につながる方法を解説
自己分析ノートのやり方
自己分析ノートの効果的なやり方4ステップ|就活での活用法も解説
公務員として長期視点のビジョンを持っているかどうか
公務員を目指す際には、目先の安定だけに捉われず、「公務員として生涯何を成し遂げたいのか」という長期的な視点を持つことが重要です。
採用後にやりがいや達成感を得られるかどうかは、自分のビジョンと職務内容がどれだけ一致しているかにかかっているからです。
たとえば、「地域の暮らしを豊かにするための福祉政策を推進したい」「環境保護に貢献する行政サービスを展開したい」といった具体的なビジョンを考えておくことが大切です。
このように自分がどの分野で貢献したいのかを明確にしておくことで、公務員の働き方に対するミスマッチを抑えられるだけでなく、選考時にも説得力のある志望動機を伝えやすくなります。
公務員の職務は時代の変化にともなって求められる役割が変わることも多いため、柔軟性を持ちながらも一貫性のあるキャリアビジョンを持つことが、ミスマッチを防ぐ鍵となります。
そういった観点で今一度、自分の価値観や目標を見つめ直し、単に安定ではなくやりがいのある公務員としてのキャリアを築くための指針としましょう。
キャリアビジョンの考え方は以下の記事で詳しく解説しています。働くことの意義と併せて、今一度考えてみてください。
キャリアビジョン
キャリアビジョンとは|就活のプロが意義と描き方を徹底解説!
働くことの意義
働くとは? 社会人のリアルな声から働く意味を考えよう
安定した公務員への就職をかなえるためにQ&A回答もチェック
ここまでの内容から、公務員への適性を確かめて「自分は公務員に向いているかもしれない」と判断できた人もいるかもしれません。適性を見極めた後に必要になるのが、就職するための対策です。
ここからは、PORTキャリアに実際に寄せられた公務員の対策に関するQ&Aを紹介します。キャリアコンサルタントによる回答を参考にして、就職の実現に向けて準備しましょう。
公務員の安定以外の特徴も理解して自分に合ったキャリアを選択しよう
公務員は安定性の高い魅力的な職業の一つです。しかし、ほかにもさまざまな特徴があるため、全体像を理解したうえで自分に適性があるかどうかを判断することが、自身の理想的なキャリアパスを実現するためには大切です。
ぜひこの記事の内容を参考にして、公務員が安定していると言われる理由や実際の働き方、向き不向きなどを理解して、自分に合ったキャリアを選択できるようにしましょう。
アドバイザーコメント
安定はあくまで公務員の多くある魅力の一つに過ぎない
社会経済情勢の見通しが不透明で、AIなどのデジタル技術の発展が著しい現在、公務員の業務や役割に少しずつ変化が見られるようになっています。
その結果、公務員の魅力である「安定」も、これまでのように絶対的なものではなくなっていくという意見もあります。
そのため、「安定」だけを理由に公務員を志望するのは「こんなはずではなかった」という後悔を招きやすいかもしれません。
公共のために働くという職務の意義と業務の多様性、そして自己の適性や思考の癖などについてあらゆる角度から検討することが重要です。
公務員を目指したい理由や目的から人生設計を考えよう
その際、自分が生きるうえで何を重視したいのかという「価値観」や、どういう人生を歩んでいきたいかという「人生設計」も併せて考えてみるのがおすすめです。
少々大げさな印象を受けるかもしれませんが、長きにわたる勉強期間と困難な試験を勝ち抜いた先に獲得できるのが「公務員」という職業です。
後悔のないよう、公務員を志望するスタート地点で「自分はなぜ公務員を目指すのか」をぜひ明確にしてみてください。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi






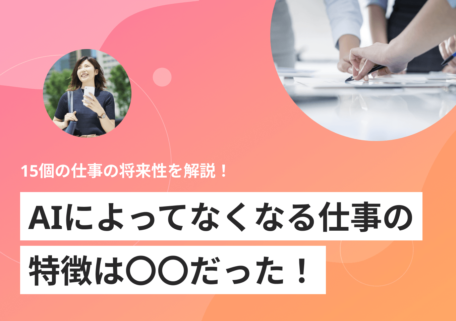







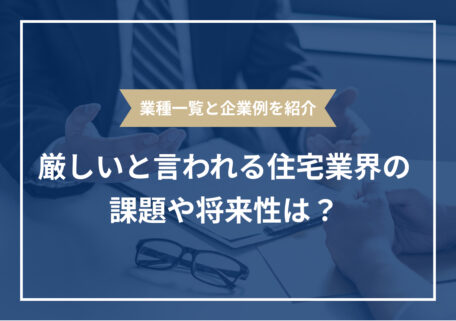
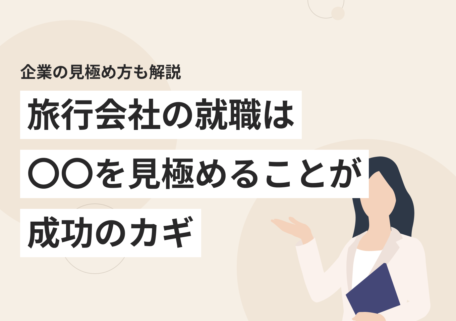









3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー
Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/1級キャリアコンサルティング技能士
Nagisa Kihara◯放送・行政・人財開発など多様な職種を経験する中でキャリア支援に興味を持つ。一人ひとりが楽しく働き、豊かに生きられる社会を目指し、現在はカウンセラーや研修講師として活動中
プロフィール詳細行政書士
Emi Maeda〇大学・短大・専門学校などでの「文章力養成講座」や「公務員試験対策講座」において、論文対策から法律系科目まで幅広い分野で講師を務め、おもに公務員を志望する多くの人のサポートに従事
プロフィール詳細