この記事のまとめ
- これから伸びる業界を把握すれば長く活躍できる環境に身を置ける
- 記事で紹介する13の伸びる業界解説をチェックすればその理由や詳細まで理解できる
- 今後伸びる業界で活躍するために欠かせないスキルや能力を身につけておこう
就職するのであればできるだけ今後も成長していく業界に入りたい、と考える学生は多いでしょう。衰退していく業界よりも、今後成長して活躍の場が広がる業界を目指したいですよね。
ただ、伸びる業界を見極めるのは就活を始めたばかりの学生には難しいでしょう。そこでこの記事ではキャリアコンサルタントの高尾さん、永田さん、野村さん、瀧本さん、渡部さんとともに、成長を見込まれる13の業界について解説します。
自動車部品、アパレル、福祉などさまざまな業界を見てきた永田さんや第二新卒を中心に異業種への転職をサポートする事業をおこなっている高尾さんなど、業界知識の豊富なキャリアコンサルタントの見解をぜひ参考にしてみてくださいね。
業界への理解を深めるコツや、成長中の業界での選考において高い評価を得るために有効な準備についても解説するので、最後まで読んでぜひ参考にして就活に就活の足がかりにしましょう。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
これから伸びる13個の業界を把握して自分の選択肢を広げよう
就活生にとってはこれから伸びる業界を見分けるのは難しいかもしれません。しかし、業界知識や就労経験が豊富な人からすれば、これから伸びる業界はある程度予想できます。また、いくつかの要因を理解すれば、就活生でも業界の明暗をざっくりと見極められるのです。
記事前半ではこれから伸びる業界の見極め方をはじめ、実際に伸びると予想される13の業界について解説します。それぞれが伸びる理由と業界の概要をチェックして、自分にあっているか見極めましょう。
記事後半では将来性をどの程度追求すべきか、将来性のある業界・企業を目指す場合にどのような点に注意すべきかなどを解説します。
最後まで読んで本当に自分が目指したいと思える業界をピックアップして、自信を持って受ける企業を選定する段階に進みましょう。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認してみよう
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
これから伸びる業界の見極め方! 業界の明暗を分ける4つの要因
これから伸びる業界の見極め方! 業界の明暗を分ける4つの要因
- IT領域の広がり
- AIの進化
- 生活様式の変化
- 少子高齢化
具体的な業界を見る前に、まずは数多ある業界の明暗を分ける要因を把握しましょう。この要因を押さえることで、業界の成長性を見極められるようになります。
なぜこの業界は成長していく可能性が高いのか、その理由を把握していないと業界への理解が深まらず、目指す業界も企業も定まりません。
これから伸びる業界への就職を目指すのであれば、成長の理由という土台の部分から知っていきましょう。
①IT領域の広がり
近年、あらゆるところでデジタル化が進行しています。身近な例としては電子マネーや電子書籍の普及が挙げられます。これらを支えるのがITと総称される領域です。自動運転車が公道を走る未来が現実味を帯びてきたように、IT領域は今後もますます広がっていきます。
反面、デジタル化が進むことで需要が縮小するものも存在します。先ほど例に挙げた電子書籍の影響を受けているのが紙の本です。出版科学研究所の2025年版出版指標年報によると、当研究所が電子出版の市場調査を開始した2014年では出版市場全体のうち6.7%ほどだったにもかかわらず、2024年には金額ベースで全体の36%を占めています。
また、デジタル化はグローバル化ともつながっています。オンライン面接にも活用されるWeb会議システムは、国外の人とのやり取りを促進し、今や海外の顧客との商談や共同事業を進めるうえでは欠かせない存在です。
その業界のビジネスがデジタルテクノロジーを取り入れて現在の市場を発展できるか、さらには新しい市場を開拓できるかどうかは、業界全体の展開を考えるうえで重要です。また、オンラインプラットフォームでのビジネス展開を期待できるかどうかも争点になります。
デジタル化により、以下のような影響が考えられます。
①企業の業務効率や生産性の向上
たとえば、AIやロボティクスの導入により、人手不足が深刻な業界でも効率的なオペレーションが可能となり、結果として労働力不足の解消が図れます。
②マーケティング戦略の精度向上
ビッグデータの解析を通じて、消費者のニーズや市場のトレンドを的確に把握できるようになります。
③働き方の変化
デジタル化によりリモートワークが可能となり、企業は柔軟な働き方を推進できるようになります。地域にとらわれない人材の採用が進み、多様な人材が活躍する環境が整うでしょう。
④オンラインでのサービス提供による新たなビジネスチャンス
たとえば、オンライン学習、遠隔医療、ストリーミングサービスなどといったオンラインサービスが普及すれば、従来の対面ビジネスモデルが大幅に変革されます。
あなたが受けないほうがいい職業を診断しましょう
就活を進めていると、自分に合う職業がわからず悩んでしまうことも多いでしょう。
そんな時は「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格、価値観を分析して適職や適さない職業を特定してくれます。
自分の適職や適さない職業を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
②AIの進化
一般的にAI(人工知能)とは、人間の知的行為を学習することでその知的能力を再現する技術を指します。平たく言えば、人間にしかおこなえなかったことを代行する可能性を持つものです。
2015年、野村総合研究所とオックスフォード大学の研究室が日本の労働人口の49%が人工知能やロボットなどで代替可能にというレポートを公表しました。2025年から2035年頃までには約半分の仕事がAIに任されうるという試算結果です。
「本当にそんなことになるの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。実際、総務省が発表した令和5年情報通信に関する現状報告の概要によれば、日本ではデジタル化に取り組んでいる企業が48.4%と半数に届かず、企業側からデジタル化の課題として最も票を集めたのが人手不足でした。そして、AI・データ解析の専門家が在籍している企業は21.2%にとどまっています。
しかし、AIはセルフレジが利用者のミスや不正を防いだり、回転寿司店で鮮度の下がった寿司をレーンから弾いたり、工場の生産ラインで不良品を瞬時に見分けたりと、すでに確実にさまざまな分野で人の業務の一部を肩代わりし、効率化を補助しています。
AIは定型的な業務の再現性が高いため、AIに仕事を奪われないか、AIを業務効率向上に活用しながら人だからこその付加価値を向上させられるかどうかが業界・企業の明暗を分けることになります。
- AIの補助で仕事がどんどん楽になるのは良いことではないんですか?
AIは各産業の人間への負担を軽減させるポテンシャルを持つ
AIの進化によって各産業分野において、日本のみならず世界的にみても大きな変化をもたらすとされています。総務省の情報通信白書:進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0の中では、業界別でのAIポテンシャルを算出していて、各分野で成長が見込まれています。
人の手でおこなっていた煩雑な業務をAIへ担わせることで、人間の負担を減らす方向へ進んでいます。
新卒採用への影響としては「AIリテラシーが備わっている人物」が重要視されることが挙げられるでしょう。AIは複雑な計算や、人間だと時間を無駄に浪費してしまうものに活用されることが多いです。
AIなどの機器を扱うことのできる、AIリテラシーの高い人が優位に立つ時代が来ているように感じます。
③生活様式の変化

生活様式はITやAIの進化とともに変化してきましたが、それを一気に促進させたのが新型コロナウイルス感染症でした。就活の軸に「リモートワークができる」ことを入れている人もいるかもしれませんね。総務省の令和5年情報通信に関する現状報告の概要ではリモートワーク導入率の推移も発表されていて、新型コロナウイルス感染症を挟んだ2019年と2020年ではリモートワーク導入率が20.2%から47.5%と急増していて、2022年には51.7%にまで至りました。
新型コロナウイルス感染症の影響が小さくなった現在でもリモートワークが続いていることから、不要不急の外出を控えていた当時に活用されたものはこれからも定着していくと想定されます。また、生活様式の変化に順応できている業界は柔軟性が高く、今後も時流の変化に適切に対応したビジネスを展開できる素地を持っているというとらえ方もできます。
リモートワークをはじめ、最新のテクノロジーを導入して業務効率の改善を積極的に図っている業界・企業は、より多くの仕事を迅速に進める環境を整えられる力を持っています。そのため、生活様式の変化をポジティブにとらえられるかどうかは業界の成長性を図る指針の一つになりえます。
生活様式への対応力は業界の成長に不可欠です。リモートワークなどに柔軟に対応できる企業は、生産性と従業員満足度が向上するため、競争力を保ちやすい傾向にあります。
業界研究では、各企業が変化に対応できるかどうかを見極める視点が重要です。
あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
④少子高齢化
少子高齢化は現代日本で最も深刻な社会問題の一つです。内閣府が公表する令和7年版高齢社会白書によると、2025年3月の確定値で、日本の総人口のうち65歳以上の人口の割合は29.4%と約3割に上っています。2070年には38.7%に到達する見込みです。
このデータからは2つのことが言えます。第1には、高年齢者の母数が増える限り高年齢者向けビジネスの需要は高まり続けます。第2には、労働者層が65歳未満であり続けるのは非現実的です。
2021年3月には高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保が社会的に求められている状況です。これからは高年齢者とも雇用の機会を分け合う時代になります。そのため、働く高年齢者にとって働きやすい業界であるかどうかは業界の労働力確保の大きなポイントです。加えて、高年齢者と若年者がシナジーを生み出せる環境であることが、業界の成長性を左右します。
また、高年齢者向けビジネスは、単純に高年齢者層が必要とするサービスを提供するのみならず、働く高年齢者の生活をより豊かにするものも該当します。雇用され一定の収入を得ている高年齢者が増えることで、高年齢者層は経済に対する影響をこれまで以上に持つことになります。
高年齢者が増え、かつその高年齢者が働く時代に順応した環境とビジネスを作り出せる業界は、今後も成長していくと考えられます。
高年齢者の割合が増すことで利益を創出しやすい業界としては、ヘルスケア・医療業界、フィットネス・ウェルネス業界、住宅・不動産業界、金融・保険業界、旅行・観光業界、教育・学習業界などが挙げられます。
これらの業界は高年齢者の健康維持、生活の質向上、資産管理、余暇の充実、生涯学習のニーズに応えることで、成長が期待できるからです。
高年齢者向けの医療・介護サービス、バリアフリー住宅、シニア向け金融商品や旅行商品などが具体例として考えられるでしょう。
これから伸びる可能性が高い13業界! 今後起こりえる展開も解説
これから伸びる可能性が高い13業界! 今後起こりえる展開も解説
ここからは具体的に将来性の高い業界を取り上げながら、各業界の成長背景や今後考えられる展開について解説します。先に紹介した業界の分岐点になりうる4つの要因のうち、どれが業界の成長性に寄与しているかも一緒に考えていきましょう。自力で各業界の展望を描くためのコツがつかめますよ。
また、業界の構造についても解説していきます。現状のビジネスモデルを把握することで将来的な方向転換の可能性についてもあなたなりの意見を持つことができるので、業界研究を深めるための参考にしてください。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
インターネット業界
インターネット業界とIT業界の違いを明確に説明できる人はなかなか少ないのではないでしょうか。IT業界とは、インターネット業界、ソフトウェア業界、ハードウェア業界、通信業界、情報処理サービス業界の総称です。インターネット業界はあくまでIT業界の一部になります。
インターネット業界のビジネスは、SNS、動画配信サービス、Webサイトの構築、後述するWeb広告や通信販売など多岐にわたります。インターネットを通じてサービスを提供するビジネスは総じてここに属するためです。
総務省が2024年3月に発表した情報通信業基本調査結果によると、2022年度の市場は4兆2,763億円で、2021度の3兆5,071億円、2020年度の3兆4,289億円から順調に拡大しています。
インターネット業界は、IT領域の広まりや、AIの進歩そのものが市場規模の拡大につながります。各業界はビジネスそのものにも、そして業界のあり方に対してもデジタルテクノロジーを取り入れている最中です。
デジタル化が進めば現在には存在しない新しいビジネスも多く生まれるでしょう。また、既存のビジネスに革新を起こすこともありえます。各業界に必要とされている存在なので、現在も成長のただ中にありますが、今後の伸びしろにも大きく期待できます。
- インターネット業界にビジネスチャンスが多いことはわかりますが、将来の展開を想像できません。
インターネット業界のビジネスチャンスは多くの分野にまたがっている
インターネット業界の将来的なビジネスチャンスの想定例は以下の通りです。
① AIとデータ分析:AI技術の進歩により、消費者行動の予測やマーケティング戦略の精度が向上します。
② IoT(モノのインターネット):スマートホームやスマートシティの管理アプリなど、新たなサービスの提供機会の増大が期待できます。
③ ブロックチェーン:取引記録の自動化や透明性向上により、金融、物流、医療などでの応用が拡大するでしょう。
④ エンターテインメントとメディア:VRやARの仮想と現実を融合した新しいコンテンツやインタラクティブなサービスの提供
⑤ 電子商取引(EC):パーソナライズされたショッピング体験やドローン配送などの新しい消費者体験が可能
領域の広いIT業界は興味があっても全貌を把握するのが難しい業界です。インターネット業界を含め、ITに入る業界を網羅的に知ることができる記事なので、IT業界に興味のある人は必見です。
通信業界を目指している人はこちらの記事も参考にしてみてください。志望動機の書き方と業界理解の方法をまとめています。
所要時間はたったの3分!
受けない方がいい職業を診断しよう
就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。
就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。
- 自分に合う職業がわからない人
- 入社後のミスマッチを避けたい人
- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人
広告業界

広告業界のなかでもとりわけ注目したいのがWeb広告業界です。サイトや動画などのコンテンツを閲覧しているときに出てくるWeb広告は身近ですね。Googleなどで検索をかけたときに検索上位にサイトを表示させるリスティング広告もWeb広告に入ります。
Web広告が広まる以前、広告は大手メディアやチラシ、屋外広告が主要な広告手法でした。より多くの人の目に触れることが目的のため、莫大な費用や多くの人手を必要とする手法です。
一方でWeb広告はユーザー一人ひとりのニーズを分析し、潜在顧客へ絞り込んでサービスの広告を表示させることが可能なので、コストを抑えつつ効率的にアピールできるメリットがあります。
電通のKnowledge&Data2024年日本の広告費を見ても、Web広告の勢いがほかの媒体を圧倒していることがわかります。年々規模を拡大する広告市場において、Web広告は47.6%の売り上げを占めています。
もともと日本は中小企業が全体の約99%を占める業界です。コストパフォーマンスの高い宣伝が可能なWeb広告は、ほか媒体よりも多くの顧客を獲得しやすいビジネスといえます。さらに、現代人のネット利用率とネット利用時間が増え続ける今、Web広告の有効性はいっそう増していくことが予想されます。
テレビやチラシなどの媒体は受け身である分、不特定多数の人にアプローチせねばならず、いわゆる「無駄打ち」が起きやすいです。
一方で、Web広告の場合はピンポイントで届けたいターゲットにリーチできるので、費用対効果も高くなります。AIの進化もあり、今後もこのようなメリットを得るための企業間の競争はさらに広がっていくことでしょう。
Webに限らず広告業界は学生からの人気が高いため、内定までには業界研究をはじめとするさまざまな準備が必須です。こちらの記事では周囲との差をつけるポイントまで解説しているので業界に興味のある人は参考にしてください。
また、Web広告などの比較的新しいビジネスを手がける企業は立ち上げも最近であることが多く、大半が中小企業に相当します。「中小企業は内定が取りやすい」といった話も上がりやすいですが、実態が気になる人はこちらのQ&Aも参考にしてくださいね。
ESで悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!
『就活準備をもっと効率よく進めたい...!』と思っていませんか?「就活準備プロンプト集」は、生成AIを活用して自己PRや志望動機をスムーズに作成できるサポートツールです。
簡単な入力でプロが使うような回答例が出せるため、悩まずに就活準備を進められます。生成AIを活用して効率良く就活準備を進めたい人におすすめです。
- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト
- チャットを使用した、模擬面接プロンプト
- 自己PRで使える強み診断プロンプト
運輸・物流業界
新型コロナウイルス感染症の外出自粛から通信販売市場が加速したことで、売買された製品を運ぶ物流業界も隆昌しています。しかしいわゆる「物流の2024年問題」、働き方改革としての労働時間適正化にともなう人手不足という課題を抱えている業界でもあります。
経済産業省は2023年6月に物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取り組みに関するガイドラインをまとめています。トラックドライバーの時間外労働の上限を年間960時間と制限したことで、2024年度には14.2%、2030年には34.1%の輸送能力が不足すると懸念されていました。
実際、経済産業省北海道経済産業局が2025年4月28日に発表した調査によると、製造業や林業、卸売業で深刻な輸送力不足が顕在化しています。
上記の試算を鑑みれば、物流の需要は今後も続くと予想できます。利便性を追求する生活様式が広まったこと、労働層が高年齢者を含むようになったこと、買い物に身体的負担を感じる高年齢者が増加することで通販の需要が高まり、EC業界が物流の担い手を奪い合う時代に突入します。
労働時間に対する政府の要請に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)化も進んでいます。労働環境の是正と人手不足が重なった現在、物流業界は学生にとっては非常に就職を目指しやすい領域といえます。
通販以外の物流業界の成長要因としては、国内外の製造業の活況やオンラインショッピング以外のBtoB取引の増加が挙げられます。また、通販の影響として、逆物流(返品物流)の増加や、迅速な配送サービスへの需要も重要なポイントです。
BtoBビジネスを物流業界について理解を深めたい人はぜひ以下の記事も参考にしてください。
BtoB企業とは
BtoB企業とは? BtoCとの違いから企業の探し方まで徹底解説
物流業界とは
例文8選|物流業界の志望動機は2つのコツで差別化しよう
EC業界

物流業界の人手不足の発端ともいえる通販業界も、外出自粛の影響や労働者層の広がりによって、今後も成長が予想されます。
経済産業省が2025年8月に発表した電子商取引に関する市場調査の結果によると、2024年のBtoC-EC市場は26兆1,225億であり、かつEC化率も加速しています。BtoB、CtoCも含めれば市場はさらに広がります。
EC業界のビジネスモデルは複数ありますが、おもには2つの形態があります。先に挙げた楽天のようにECモールへの出店・出品を募り、ECモールのブランド力による集客の見返りとしてマージンを引くものが最もポピュラーです。一方、各企業・各ブランドが専用のECサイトを構築することも多いので、BtoBのサイト構築支援ビジネスも今後の需要に期待できます。
生活様式の変化にともない、ECを取り入れる企業は今後も増え続けることが予測されます。一つのブランドがECモールへの出店・出品、独自ECサイトの立ち上げの両方をおこなうことも多いため、EC業界は今後も加速度的に成長すると予測されます。
フードデリバリー業界

フードデリバリーは物流と食品の2領域にまたがった業界といえます。新型コロナウイルス感染症に大きく成長した業界ですが、影響の薄まった現在も成長を遂げています。
エヌピーディー・ジャパンが提供する外食・中食市場情報サービスCREST®によると、2022年には若干の落ち込みを見せたものの、2023年には再上昇し8,603億円規模が見込まれていました。同レポートは客単価の上昇に言及し、家での生活をより豊かにしたいといった需要が2023年の結果をもたらしたと推測しています。
ちなみに2024年はコロナ禍からの回復もあり、フードデリバリー市場は7967億円と見込まれました。
生活において利便性と質向上が重視されるようになったことで、フードデリバリーは現代の生活にすっかり浸透しました。
Uber Eatsのように運搬のみを代行するビジネスモデルは比較的新しいものです。これ自体がデジタル技術の進歩によって成立したものですが、ここから先も技術進歩は続きます。業務効率が改善されれば、より少ない人数でより多くの配達をおこなうことができます。配達の質向上にも寄与するでしょう。
これらの理由から、フードデリバリー業界はいっそうの市場拡大が期待できます。
フードデリバリー業界の市場拡大には、いくつかの課題解決が欠かせません。
まずは配達員の確保や労働条件の改善です。その後には、AIや自動運転技術を活用した迅速かつ品質を保つ配達システムの構築も伸びしろになるでしょう。加えて、環境への配慮、地域社会との連携なども重要です。
これらの課題を解決することで顧客満足度の向上、環境評価の向上、地域密着型サービスの提供が可能となり、持続的な成長が期待できます。
食品業界

食品業界で特に注目したいのは中食です。店で調理された食事を店で食べる外食と、家で素材から調理された食事を家で食べる内食の間を取った食事形式を指していて、つまり調理済みの食事を家で食べることです。先に取り上げたフードデリバリーも該当します。
2021年版惣菜白書および2025年版惣菜白書によると、新型コロナウイルス感染症の2020年に4.8%の落ち込みを見せたものの、現在には11兆円を超えるほどの成長を見せています。もともと堅実に食市場を支えていた中食ですが、今や内食の売り上げを大幅に超えています。
要因としては、それまで家事を担っていた女性の社会進出や、高齢者層からの需要の高まりなどが挙げられています。購入頻度の高い品目が弁当やおにぎりであることから、1食を中食でまかなう人が多いことが予想できます。
食が生活に欠かせない要素であることはもちろんですが、時間や手軽さをお金で買う人が多い傾向が見えてきます。現代人のライフスタイルに適応した中食市場は今後も拡大していくことが見込まれます。
新型コロナウイルス感染症以降、家の中で「プチ贅沢」をする人が増えました。その一つとして、家で少し良いものを食べようという文化ができあがったことは事実です。
コンビニ業界でも、冷凍食品なども含め、コラボ商品や、通常商品よりやや高いプレミアム価格のものが増えました。今後も中食市場が欠かせないマーケットであることは間違いなさそうですね。
食品業界全体についてはこちらの記事で詳しく解説しています。どのようなビジネスモデルの企業が業界を構成しているのかを理解することで志望動機の説得力がぐっと増すので、食品業界に興味のある人はぜひ参考にしてください。
電子部品・半導体業界
半導体
電気を通す「導体」と電気を通さない「絶縁体」の中間の性質を持つ物質。電気を通すことも通さないこともできるため、さまざまな製品に使用される。広義には半導体によって作られるICチップを指す。
半導体は電気を使う製品には絶対不可欠なパーツです。そのため、半導体製造にかかわる企業は膨大な顧客との成約を獲得するチャンスを有しています。
半導体が不足していることはニュースでもたびたび取り上げられていて、誰しも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。必要不可欠にもかかわらず需要と供給がつり合っておらず、現在は半導体は高値で取引されている状況です。
デジタル化が進めば進むほど半導体の需要はますます高まります。加えて、半導体製造には高い技術が必要なので、新規参入が難しい業界でもあります。半導体の需要の高まりは国際的なものなので、当然見すえる市場には海外が入っています。
現在は先進国での需要が主ですが、新興国のデジタル化が進めばさらに市場は拡大していきます。
半導体業界については以下の記事で解説しています。半導体業界への就職を考えている人は参考にしてみてください。
医療・福祉業界
少子高齢化が進むにつれ、医療や介護の重要性はいっそう増していきます。実際に現場に立つ人々の人手不足は現在も指摘されていますが、今後も加速していくでしょう。人手不足の要因には労働量と報酬が見合っていないことが挙げられますが、政府も改善のために動いています。
2024年2月、厚生労働省の発表した令和5年度厚生労働省補正予算案の概要によると、介護職の月収を約6,000円上げる施策が2024年2月から5月まで実施され、以降も賃金引上げのための取り組みを続けるとしています。医療機関に対しても、厚生労働省は医療機関の働き方改革についてなどで各機関に環境改善を要請しています。
ちなみに厚生労働省が令和6年10月におこなった「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護職の平均月収は338,200円まで上昇しています。
また、この業界には現場職のみならず、現場の業務を支える機器を製造するメーカーも属します。
2023年のFacSetのIR資料FACSET 2023 ANNUAL REPORTによると、医療機器のグローバル市場における需要は半導体、情報サービスに次ぐ高さで、今後も成長を続ける見込みです。国内需要も堅調で、他国企業に比べて事業規模は劣るものの収益性・成長性は引けを取っていません。今後海外へ事業規模を拡大できれば、ますます影響力を持つ業界になっていきます。
医療・福祉にもさまざまなサービスがありますが、大枠でとらえると一定の傾向が見られます。
福祉業界については、高齢化が進んでいる国は多くあるので、日本と同様の課題を抱えている先進国への転用が可能です。
そして医療業界は、中間層が増加し、医療や福祉サービスへの需要が急速に拡大している新興国において、日本の先進的な医療機器やシステムを展開することで市場シェアを拡大することができます。
医療業界や職種についてはこちらの記事でも解説しています。職種ごとの志望動機例も掲載しているので、医療業界を志望する人はぜひ参考にしてください。
水産・農林業界
漁業・農業は高齢化や人手不足が深刻な業界というイメージを持つ人も多いでしょう。確かに、農林水産省の公表する令和6年農業構造動態調査結果や、2020年農林業センサス、令和4年漁業構造動態調査結果を見ても、就業者の減少と高齢化は深刻です。
しかし、これまで取り上げてきたIT領域の進歩によって状況は大きく変わりつつあります。もともと生命維持に必要不可欠な食の基幹を担う仕事なので、人が生活する限り需要が絶えない仕事です。ネックとなっていた労働の過酷さや収益の不安定さがAIやビッグデータの活用、IoTの駆使によって改善されつつあるため、今後は若年層の就業や企業単位での新規参入が期待できます。
2020年農林業センサスによると、農業でのデータ活用を実践している農業の担い手の割合は、2020年が36.4%、2021年が48.6%と増加傾向にあります。農林水産省は2025年度までにほぼすべての担い手がデータ活用に取り組むことを目指しています。
水産庁も2027年に次世代の水産業、デジタルテクノロジーを活用した漁業の実現を目指すと令和4年度水産の動向令和5年度水産施策概要で発表しています。
一次産業に興味がある人は、関連市場にもぜひ目を向けてみてください。
プロのアドバイザーはこう分析!農業・漁業の更なる発展には5つの点に課題がある
農業・漁業のデジタル化による成長は確かに期待されていますが、若年層の参入には多くのミッションを抱えていることも事実です。
①教育とトレーニング:若年層がデジタル技術を活用できるよう、農業高校や大学での専門教育や実地研修を強化するべきです。
②インセンティブの提供:政府や地方自治体から補助金や税制優遇、低金利の融資などのインセンティブを提供し、デジタル機器の導入支援や初期投資の軽減を図る必要があります。
③キャリアパスの明確化:農業・漁業の魅力を伝えるためには、デジタル技術を活用した成功事例を紹介し、若年層にとっての将来展望を具体的に提示していくことが必要になります。
④コミュニティの形成:若年層のネットワーキングを促進し、同世代の従事者やデジタル技術専門家との交流の場を提供し、オンラインフォーラムやワークショップを通じた情報の共有を実現しなくてはなりません。
⑤労働環境の改善:労働時間の短縮や福利厚生の充実など、労働条件の向上を図り、若年層にとって魅力的な職場を作り上げていくべきです。
業界の持続的成長のためには若年層と現場双方の歩み寄りと支援が必要
若年層への働きかけだけでなく、現在の就業者や現場そのものへの施策があってからでないと、農業・漁業のデジタル化と若年層の参入を促進できません。
そこまでおこなってようやく、業界の持続的な成長がより現実感を持つようになります。
農業についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。志望動機の例文も紹介しているので、業界に興味のある人はぜひ参考にしてください。
宇宙開発業界
宇宙開発業界とは、ロケットなどの飛翔体の打ち上げや、衛星情報の活用など、宇宙領域にかかわるビジネスの総称です。もともと国家が主導していたところ、1980年頃から徐々に規制が緩和されたことで民間企業が参入するようになりました。宇宙開発は現在国際的な盛り上がりを見せています。
宇宙空間の研究が進むと、人工衛星を活用した通信インフラの新たな活用法や、地球における環境問題の解決の糸口を発見できる可能性があります。ほかにも、無重力空間を活かした新たな物質・素材の開発や、ともすれば宇宙旅行もそう遠い夢ではありません。
しかし、2024年3月に経済産業省が発表した国内外の宇宙産業の動向を踏まえた経済産業省の取り組みと今後についてによると、特にアメリカ、中国によるロケット打ち上げ数の上昇が顕著で、日本は初動が遅かったこともあり大きく遅れを取っている状況です。
今年からは政府による宇宙戦略基金(JAXA基金)という、10年で総額1兆円の経済支援計画がスタートします。新規参入も歓迎する計画なので、もともと精密機器の製造を得意とする日本企業にとっては追い風になるでしょう。宇宙開発が進めば既存のテクノロジーのさらなる活用にとどまらず、まったく新しいビジネスの確立も可能です。影響を受ける分野はITに限らず、機械産業、医療など、ほぼすべてといっても過言ではありません。
宇宙開発業界は日本の全業界の技術を底上げする可能性を秘めています。発展すれば多くの顧客が獲得できるだけでなく、政府以外からの資金援助も期待できるため、その勢いは加速度的に増していくでしょう。
宇宙ビジネスもさまざまな階層に分かれています。ロケットの製造から始まり、衛星通信を利用した測位サービスやIotの活用など、たくさんのビジネスが存在します。
日本は小型の衛星を得意としている面もあります。今後も大手企業の技術力・研究力を活かして変わらず宇宙開発事業が進んでいくと考えられます。
エンタメ業界
日本のエンタメ業界は、ゲームや漫画、アニメだけでなく、独自の音楽やポップカルチャーを軸にしたメタバース・NFTといった多様な分野を含む産業です。
経済産業省が発表したエンタメ・クリエイティブ産業戦略~コンテンツ産業の海外売上高 20 兆円に向けた5ヵ年アクションプラン~によると、2022年のマンガやアニメ、ゲームをはじめとした日本のエンタメ自産業市場は13.1兆円の規模です。
2022年にファイナンスが発表したライブエンタメ市場の現状と今後の展望によると、コンサートや演劇を中心としたライブエンタメ市場も好調で、コロナ禍から回復した2025年には約6,600億円規模に拡大しています。
近年では、2次元と私たちが暮らす3次元の両方の性質を持つ「2.5次元」や「VTuber」といった概念やも生まれており、さらなる盛り上がりを見せる可能性を秘めています。
また、エンタメコンテンツの海外展開も進んでおり、先でも紹介した経済産業省のエンタメ・クリエイティブ産業戦略~によると、2030年代に海外売上高20兆円を目標としている点も見逃せません。
このことから考えると、日本のエンタメ業界は爆発的な成長を秘めた、比較的確度が高い伸びる業界といえます。
ドローン業界
ドローン業界とは、無人航空機の機体製造、操縦・制御システムの開発、運用サービス提供などを手がけるビジネス領域のことです。ドローンは点検や測量、物流・配送、災害対応など多岐にわたる用途で活用されていて、従来は人が担っていたリスクや危険を伴う業務を代わりにおこなっています。
ドローン活用によって業務効率化と安全性向上を同時に実現できるため、現在もさまざまな分野での導入が急がれているのです。
2024年4月18日に発表された矢野経済研究所の調査によると、2030年の産業用ドローン世界市場は1兆4,124億円にまで拡大すると見込まれています。2024年の約3,186億円の市場と比較すると、5倍近くの規模です。
現在は航行の安全性などの問題が議論されているものの、ドローン業界も技術の発展とともに大きな伸びを見せると予想されます。
AI業界
AI業界では、人工知能の研究開発やAIシステムの構築・運用などがおこなわれています。機械学習や自然言語処理、画像認識といった技術の活用によって、人間の知的作業を代わりにおこなったり、さらに高度化させたりするのが目的です。
日本国内のAI市場は急成長していて、2024年に総務省が発表した「令和6年度 情報通信白書」によると、世界の生成AI市場規模は2023年時点の670億ドルから、2032年には1兆3,040億ドルまで拡大すると見込まれています。
市場拡大の大きな契機となったのが、2022年11月に登場した対話型AI「ChatGPT」です。それ以降、生成AIがAI市場を押し広げてきました。上記のAI市場の拡大にも生成AIが寄与しており、今後もさらに発展していくことは確実といえます。
実際、AIエンジニアという職業が登場していることからも、AI産業がIT産業の一角を担うことを裏付けています。つまり、AI業界も今後飛躍的な伸びを見せる注目の業界の一つなのです。
プロのアドバイザーはこう分析!AI・エネルギー・ヘルステックの3業界は今後伸びる可能性が高い
上記で紹介している13業界の中で、今後最も伸びる可能性が高いのはAI業界です。AIは単独の産業ではなく、他産業に浸透する基盤技術であり、需要と市場規模が拡大し続けています。
AIは医療の診断支援、物流の最適化、広告配信の高度化、農業の自動化など多岐に活用され、産業構造を根本から変える力があるでしょう。
政府や企業が脱炭素と人手不足への対応としてDXを加速する中で、中心技術としてAIが位置付けられ、人材需要も急速に高まっています。こうした背景から、AI分野は中長期的に強い成長が見込まれるでしょう。
また、紹介している業界以外でも今後成長が見込まれる業界はあります。まずは、環境・エネルギー関連産業です。
再生可能エネルギーや水素、蓄電池はカーボンニュートラルの流れを追い風に、今後数十年にわたり投資と市場拡大が継続すると考えられます。電源の脱炭素化や産業プロセスの電化・水素化が進むほど、関連技術の需要は増していくでしょう。
そして、高齢化の進展により、ヘルステック産業も成長します。AIやIoTを活用した予防医療、遠隔・在宅医療、ケアの効率化は、医療提供体制の負荷軽減と質の向上に資し、継続的な需要を生みだすのです。
「伸びる業界=正解の業界」ではない! 自身の価値観を軸に業界を選択しよう
ただ、就活においては、「伸びる業界」を狙うだけでなく、「どの社会課題の解決に貢献したいか」という軸で選ぶことが、長期的な納得感と成長機会につながります。
後悔しない選択ができるようにさまざまな視点からとらえていくことが大切です。
これから伸びる仕事についても知りたい人は、以下も併せてチェックしておきましょう。伸びる業界・伸びる仕事を把握しておけば、自分が長く活躍できる職業への就職を実現できますよ。
これから需要が増える仕事
これから需要が増える仕事20選! 業界選びや適職探しのコツも解説
なくならない仕事
10年後もなくならない仕事8選! 就活のプロがその理由も徹底解説
これから伸びる業界には共通点がある! 業界を成長させる5ポイント
これから伸びる業界には共通点がある! 業界を成長させる5ポイント
先ほど、業界の明暗を分ける要因として「IT領域の広がり」「AIの進化」「生活様式の変化」「少子高齢化」の4つを挙げました。これらは科学進歩や国際情勢などの環境変化に相当しますが、その環境変化を味方につけることができた業界には共通点があるはずです。
環境に適応したビジネスの共通点を発見できれば、先に挙げた以外の成長業界を自力で見つけることが簡単になります。さらなる環境変化が起きたときにも各業界の展望を予測する力となるため、思考力を鍛えるためにも各業界の共通点について考えていきましょう。
①DXの推進に貢献している
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略称で、デジタル技術によってさまざまなプロセスの効率を改善させることを指します。一方、日本では企業の業務効率をデジタルテクノロジーによって改善することに対してDXという言葉を使う場面がしばしばあります。
背景は経済産業省にあります。令和4年7月に更新されたDXレポート2.2(概要)ではDXが国内市場全体の底上げにつながるとして、政府は各企業へデジタル化推進のための具体的な行動を求めました。
DX化は国内の全企業が抱える緊急性の高い課題です。BtoBのDX推進支援ビジネスのように、潜在顧客が多く、かつ緊急性の高い課題に対してアプローチをできるビジネスは、迅速な利益創出の可能性を持っています。
そして、人件費や原料費などのコストがかさんでいる業界にとって、業務効率の改善によるスピーディな原価回収がかなうDX推進はいっそう重要性を増しました。これらの政府の動きは、DXを強く支えるインターネット業界、ソフトウェア業界にとっては追い風になっています。
プロのアドバイザーはこう分析!BtoBのDX支援ビジネスでは莫大な金額がやり取りされる
BtoBのDX推進支援ビジネスは、企業の業務効率化をデジタル技術で支援するものです。
具体的には、最新のソフトウェアやシステムを導入して企業の業務プロセスを見直したり自動化することで、業務効率化や生産性向上、コスト削減につながります。また、デジタル化により、データの収集・分析が簡単になり、経営戦略の精度が向上し、データ活用の促進や競争力の強化にもつながるでしょう。
BtoBのDX支援は、多くの企業が抱える緊急性の高い課題に対してソリューションを提供するため、需要が非常に高いことが特徴です。企業の存続に直接影響するものであり、BtoCの一般消費者をターゲットとしたビジネスと比較して、はるかに大きなお金が動きます。
適切なDXは企業にも顧客にも大きな利益をもたらす
たとえば、製造業の在庫管理システムやサービス業の顧客管理システムの導入で、事業の効率化とコスト削減が実現した事例があります。
サービス業の顧客が顧客管理システム(CRM)やオンライン予約システムを導入したことで、顧客データの一元管理が可能となり業務が効率化されるだけではなく、マーケティング活動の精度が向上し、顧客満足度も大幅に改善した事例もあります。
一方、システム刷新に失敗して出荷停止に追い込まれた企業の事例もあり、それだけ企業の存続にかかわる重要な分野です。
②巣ごもり需要に対応している
新型コロナウイルス感染症以降にもリモートワークや中食市場の盛り上がりが続いていることから、巣ごもり需要に端を発した需要は今後も続くことが想定されます。
新型コロナウイルス感染症では家での生活をいかに充実させられるかに焦点が当てられました。先に取り上げた食事だけでなく、家のなかに一人でいても楽しめる娯楽などの需要が高まり、もともとこれらに関心のなかった人々が顧客になりました。エンターテインメントやフィットネスなどがここに相当します。
2023年5月から新型コロナウイルス感染症の分類が5類へ移行し、2025年現在では通常の社会生活が可能になっているものの、家での生活を充実させる要素は今後もビジネスとしての成長が期待できます。
新型コロナウイルス感染症により、会社に行かなくても仕事ができる在宅ワーク化が進みました。さらには週末での家族の過ごし方も変わり、外出だけでない工夫を多くの人が凝らしてきました。
その名残は現在も色濃く残っていて、「家で過ごすための質」をまだまだ多くの人が求めている状態です。基本的な需要が底上げされているため、今後も一定数維持されると思われます。
③労働層の変化に適応している
少子高齢化の際に取り上げたとおり、これからは基本的に70歳までの人が労働者としての役割を求められます。そしてそれ以前より女性の社会進出が推進されているため、家事や育児など、家庭のために長い時間を割ける人が減り続けることが予測されています。
総務省が2024年6月に発表した労働力調査によると、2023年の平均就業者数は6747万人で、うち女性は3051万人と約半数を占めます。今後も就業者全体における女性の割合は上昇すると思われます。
年齢・性別の両面から就業人の割合が増加する以上、生活を効率化するものの需要は高まるでしょう。EC業界やフードデリバリー業界がこれに相当します。また、親の就業中に子どもをあずかる保育園・幼稚園、介護を必要とする病人や高年齢者をフォローする施設の重要性は増していきます。こと高齢化が加速する現代においては介護施設や老人ホームの増設およびこれらの業界における労働環境の改善が必要です。
労働人口の変化に対応する事例として、EC業界ではオンラインショッピングの増加や、介護施設業界では高齢者の増加にともなう需要の拡大が挙げられます。
これらの業界は、需要の増加を即座に利益につなげるビジネスモデルを確立しています。
④半導体の供給に関係している
スマートフォン、家電製品、自動車など、半導体は電気によって動くあらゆる製品に必要不可欠な物質です。半導体がなければ社会インフラすら機能しない現代ですが、半導体は現在需要と供給が釣り合っていない状況です。
もともとデジタル化加速の潮流から半導体の需要はきわめて高く、各分野が奪い合いをしている状態でした。その矢先に新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生したため、半導体製造ラインが一部停止しました。それにもかかわらずパンデミックはデジタル化を後押しし、半導体の需要をさらにつり上げました。
経済産業省が2023年6月に発表した半導体・デジタル産業戦略によると、半導体製造には約1000もの工程が必要であると同時に非常に高い技術が必要であり、その過程の一部である、半導体製造装置産業と主要半導体部素材の分野で日本は世界的に高いシェアを誇っています。
一方、日本は半導体等電子部品の輸入も盛んで、財務省の地域別輸出額の推移(グラフ)や外務省の米国経済と日米経済関係によると、台湾やアメリカから多くを輸入している状態です。
課題点はあるものの、生活に必要不可欠な半導体製造に関与していることは日本の強みであり、それに貢献する業界・企業の成長性は高いです。ゴム・ガラス・セラミックス業界もここに該当します。
プロのアドバイザーはこう分析!国内の半導体供給事情はこれから大きく改善される見込み
半導体チップの設計と製造をおこなっている企業としてソニー(画像センサー)とルネサスエレクトロニクス(マイクロコントローラ、車載半導体)が挙げられます。
ソニーグループでは、台湾のTSMCが熊本の第1工場を2024年2月24日に建設したことで、今後安定的に半導体が供給できる見通しを立てています。台湾から輸入していたものが日本国内で調達することが可能となるため、期待感を示しているのです。
また、この新しい工場がもたらす熊本県内の経済波及効果は10年間で6兆8,000億円にも上るという試算もあります。
市場の動向を先読みできる企業がリードを獲得する
さらに、ルネサスエレクトロニクスとアメリカのウルフスピードは10年間にわたるSiCウェハの供給契約を締結しました。SiCウェハとは半導体の材料で、これまで半導体に使われていたシリコンウェハよりも耐久性に優れています。
今後の市場における、シリコン製パワー半導体からSiC製パワー半導体への遷移に合わせた対応です。
SiCはシリコン製パワー半導体に比べて電力変換効率が高く、システムコストの低減も見込めます。それにより省エネやEV化など、あらゆる面で普及が見込まれ、注目されているのです。
⑤政府からの支援を受けている
DX推進でも言及したとおり、政府から企業への働きかけは新しいビジネス創出や既存ビジネスの成長のきっかけとなりえます。企業は社会的責任を負っているため、政府の打ち出した方針に従ってビジネスの方向性や組織体制を変更しなくてはならない場面があります。
しかし政府は企業に要請をするばかりではありません。DX推進も基準を満たせばIT導入補助金といった補助金が使えるなど、往々にして要請と支援はセットです。政府は国の利益を最大化させるために方針を打ち出し、それを後押しするために支援をおこなうため、政府の支援を受けられる業界は国内市場を支えうると政府に見なされています。
直近で話題になったのは、宇宙戦略基金です。国際的な宇宙開発競争の激化を受け、政府は10年間で総額1兆円の支援をおこなうことを目指す宇宙基本計画を2023年6月に正式に発表しました。JAXAを中心に宇宙分野の研究開発を促進すべく、企業や大学をはじめとする研究機関などへ支援を実施する予定です。
支援組織の公募は今年の夏頃からの見込みで、内閣府の令和6年度当初予算案および令和5年度補正予算における宇宙関係予算を見ると、確かに本年度の予算は総額の10分の1に迫る8,945億円の予算が組まれています。
政府は国全体の利益にならないことへは投資しません。インターネット業界、ソフトウェア業界、宇宙開発業界などのように、政府が大きな予算を投じてプッシュする分野の将来性が高いことは間違いありません。
プロのアドバイザーならこうアドバイス!伸びる業界かどうかの見極めには社会課題とのつながりを考えよう
今現在、その業界の市場規模が伸びているかどうかは、業界全体の売上規模の推移を見ればわかります。政府統計や経済記事、検索などでもすぐに確認できるでしょう。
しかし、今後どうなるのかは需要がどう変化していくのかを考えなければなりません。
過去の事例では紳士服業界などがわかりやすいと思います。昔はホワイトカラーのビジネスマンはスーツとネクタイを着用して仕事をすることが当たり前でした。
しかし、職場のカジュアル化が進み、クールビズなど健康面の配慮も求められるようになって、スーツやネクタイの需要はどんどん減って単価も下がったことで、市場規模は大きく縮小しました。
紳士服専門店の大手は軒並み飲食事業やカラオケボックスなどフランチャイズでの多角化を進め、アパレル事業の割合は年々下がってきています。
少子高齢化などの社会問題が業界の将来性に影響を与えることも多い
また、アパレル市場の縮小は少子高齢化の影響も受けやすいです。このように、根底にある社会構造の変化に着目することも重要で、たとえば空き家の増加によるリフォーム市場の拡大なども間接的には高齢化とのつながりがあると言えます。
伸びる市場の背景には社会課題との関連があり、課題があるからこそ需要ができるという観点を持って業界の将来性を見極めていくと良いのではないでしょうか。
ビッグビジネスのチャンス! これから伸びる業界へ就職する3つのメリット
ビッグビジネスのチャンス! これから伸びる業界へ就職する3つのメリット
- 成長機会が多い
- 市場価値を高めやすい
- やりがいを持ちやすい
そもそも、将来性の高い業界への就職を目指す学生はどのような目的を持っているのでしょうか。成長していく企業であれば給与が高そう、あるいは今後当分安泰そうだから転職や離職のことを考えなくて済みそう、と思っている人もいるかもしれません。
上記も可能性としては考えられますが、メリットと呼べるほど確実性の高いものではありません。それでは成長業界にはどんなメリットがあるのでしょうか。ここでは3つの利点を紹介するので、成長業界があなたの目指す方向性と一致しているのかを確認していきましょう。
①成長機会が多い
成長業界はトレンドの変化が激しく、常に最新情報を追いかける必要があり、特に自分の業務にかかわる領域であればしっかりと腰を据えて勉強しなくてはなりません。ずっと勉強し続けている状態なので、個々人、特に若い世代の成長速度は速くなる傾向にあります。
加えて、将来性の高い業界はすなわち需要が高く、優秀な人材をいち早く現場で活躍させたいと考えています。そのため、重要顧客との接点を持つ機会や、規模の大きなプロジェクトへのアサインの機会が若手にも訪れやすいです。こういった業務の割り振りはそれまでの成果や日頃の成長意欲、または本人の志望度などから総合的に判断されますが、大きな仕事に参画するチャンスが多いのは成長業界に共通する特徴といえます。
将来性の高い業界で成長するためには、積極的な情報収集やスキルの習得が不可欠です。
トレンドを追い、積極的な姿勢で挑戦し、コミュニケーションを大切にすることが重要になります。自らの成長意欲をアピールしましょう。
②市場価値を高めやすい
市場価値
人材に対する、採用側からの需要。採用市場においてより多くの企業・組織から求められる経験やスキルを備えた人材に対して「市場価値が高い」と言う。
市場価値が問われるのは採用の場、おもには転職を検討したときです。望むキャリアを進むために転職が必要になった時、市場価値が高いほどそれをかなえやすくなります。
働く場所が変わっても企業へ貢献できる人材になるためには、どんな業界でも活用できるスキルと、それを証明するための実績が必要になります。
成長業界はトレンドの変化が非常に激しいだけでなく、幅広い業界との接点を持ちやすいことが特徴です。毎日新しい情報がとめどなく流れ込んでくる環境であり、その情報を処理するために専門領域に限らず広い分野のことを勉強しなくてはなりません。そして勉強した内容を即座に業務上で活用するために、高速でインプットアウトプットをくり返します。
いわば、常に論理的思考力や課題解決力を磨いている状態です。そして導き出した課題を解決するためには周囲の人を巻き込みながら行動する必要があり、コミュニケーションスキルも並行して鍛えられます。
これらのスキルはどの業界でも個人の努力によって獲得しうるものですが、若いうちからこれらを備えている人材は大変希少です。そして、成長中の業界は柔軟性が高く優秀な人材であれば年齢を問わず大きな事業を託す傾向が強いので、これらのスキルをより早く獲得しやすく、その証明となる実績も残しやすいです。
将来性の高い業界では、幅広いスキルセットを形成できるだけでなく、ほかの業界でも通用する普遍的なスキルと実績を積むことができ、結果として市場価値が高まります。これはキャリア選択において大きなアドバンテージです。
たとえば、新たなプロジェクトへの参画による最新の技術・ビジネスモデルを学習できる可能性があります。グローバルな視野も獲得しやすいでしょう。
そのほかにも、イノベーションへ関与するチャンスも多く、業界内外の多様な専門家やリーダーと接触できるネットワーキングなども豊富で、成長機会を得やすいです。
若手であってもリーダーシップを取れる環境なので、本人の動き方次第で多くのチャンスを得られます。
③やりがいを持ちやすい
今まさに伸びているビジネスとは、各分野からの需要がきわめて高いものです。そのため緊急性が高かったり、顧客の今後を大きく左右したり、世間に対する大きなインパクトを残す事業に参加することが多く、個人にとってもやりがいを持ちやすいです。
先述したとおり若手にも大きな仕事を任せることが多いので、入社1年目であろうと責任ある業務にかかわることが可能です。周囲からの期待を実感し、自分の仕事に誇りを持つことができると、仕事への充実感を持っていっそう主体的に仕事に取り組めるようになります。
- やりがいを持って働くことがそんなに重要なのですか? のんびりと安定的に働きたいと思っているのですが……。
不可欠ではないが悩みやモチベーションには影響をもたらす
私がかかわってきたなかで人事部で働いている人がいますが、「その人の適性を見きわめて幸せなキャリアを歩んでもらう手伝いができる」と、その人なりのやりがいを持って仕事に取り組んでいます。
会社には裏方と言われるような職種もありますが、「人をサポートすることが喜び」と感じる人にとってはやる気が湧いてくる仕事なのです。
会社にはさまざまなタイプの人間が必要になります。表に立つ人だけではなく陰で支える人たちがいてこそ成り立っているのです。
働き方や価値観はそれぞれなので、必ずしもやりがいが必要というわけではないと思います。ただ、働くなかでモチベーションが低下したり悩みが出てきたりした時、それらを払拭するためにもやりがいが感じられることは重要です。
安定性を重視して就活をしている人は以下の記事も参考にしてみてください。安定した職業についてまとめています。
理想とのギャップに用心! これから伸びる業界へ就職する際の3つの注意点
理想とのギャップに用心! これから伸びる業界へ就職する際の3つの注意点
- ハードワークになる可能性がある
- トレンドの変化が激しく勉強し続ける必要がある
- 環境変化によって業界全体の状況が急変する恐れがある
将来性の高い業界や、さらにはその業界をリードする企業で働くことには多くの魅力がありますが、美点ばかりに注目していると就職後に実態とのギャップに落胆してしまう結果になりかねません。仕事へのモチベーションの低下や早期離職を防ぐために、伸びている業界ならではの注意点を解説します。
今のうちにギャップを解消し、いきいきと働き続けるための就活準備をしていきましょう。
①ハードワークになる可能性がある
成長業界は需要が高いため、次から次へと新しい仕事がやってきます。そのため業務量が多くなりやすく、したがって残業時間が長くなる可能性があります。また、多くのプロジェクトが同時進行するため、マルチタスクに対応しなくてはなりません。
加えて、トレンドの変化や幅広い分野への対応力を養うために、業務外にも多くのことを勉強をしなくてはならないことが想定されます。特に入社して間もなくは基礎知識が備わりきっていない状態なので、自然知識の応用も難しいです。ひたすら知識を詰め込む期間を乗り越えなくてはなりませんが、学生時代とのギャップで疲れてしまう人もいるかもしれません。
勉強のポイントとして、まず目標を明確にし、定期的なスケジュールを立てて学習時間を確保しましょう。
情報収集には信頼できるインターネットサイトや専門書籍、セミナーを活用し、最新のトレンドや業界動向を把握することをおすすめします。
②トレンドの変化が激しく勉強し続ける必要がある
勉強は新人時代に限りません。業界自体の変化が激しく、情報更新が活発であるならば、たとえベテランと呼ばれるようになっても勉強をし続けなくてはなりません。
新人時代には、基礎を整え、また基礎を応用して業務に有効かつ効率的に取り組むための勉強が求められます。対して、事業の中核を担うポジションになると、先手を打って状況変化に対応するための勉強が求められます。よって、新人レベルよりもずっと深く高いレベルでトレンドを把握する必要があります。
当然基礎力が備わっている状態なので新人時代のようなゼロからの勉強ではないかもしれません。しかし、革新的な技術進歩や世界的なトレンド変化が起きた場合には、それまでに培った知識や経験ではまったく歯が立たない課題に直面することもありえます。心身のタフさが求められる業界です。
③環境変化によって業界全体の状況が急変する恐れがある
天災や国際情勢など、環境変化によって業界全体が大きな揺さぶりを受ける恐れがあることも想定しておく必要があります。成長している業界は伸びる一方だから大丈夫、ということは決してありません。
この記事で紹介した将来性の高い業界は環境変化に対応して成長しています。裏を返せば、そういった環境変化の影響を非常に受けやすい業界群でもあります。たとえば新型コロナウイルス感染症の拡大によって大量生産されたアクリル板は、現在販売数が激減し、また廃棄のために回収されたものを再利用できないかと議論されています。
たとえば新型コロナウイルス感染症の拡大によってアクリル板が大量生産され、売り上げが激増した製造業の一分野がありましたが、現在は販売数が激減しており、変化を余儀なくされています。
トレンドに乗じたビジネスを展開した際には、トレンド収束後の対応やビジネスそのものの方向転換についても考え、準備しなくてはなりません。
成長業界は外部環境の変化に敏感で、新たな法規制や天災、国際情勢の変動などによって大きな影響が起こりえます。加えて、技術の進歩や消費者の嗜好変化などにも迅速に対応しなくてはなりません。
こうした業界では、リスク管理だけでなく、柔軟な戦略、社会を先読みする先見性、継続的な学習やスキルのアップデートが重要です。
将来性はどこまで重視すべき? 就活時の業界選びのコツをプロが解説
ここまで業界の将来性にフォーカスを当ててきました。先述の通り成長する業界にはさまざまな魅力があり、特に転職が身近な若い世代にとっては最新の情報・技術に触れられる、市場価値を高めやすいといったメリットは惹かれるポイントです。
しかし、業界そのものの将来性はその後の個人の成長やキャリアプランの策定に対してどれほどの影響力を持つのでしょうか。目指す業界を絞るなかで、成長性に注目することで見逃してしまう要素などはないのでしょうか。
今回は業界の将来性を軸に、新卒就活における業界選びのコツをキャリアのプロである永田さんに聞いてみました。
プロのアドバイザーはこう分析!業界の成長性は重要だが絶対視することでもない
業界の将来性について、もちろん「必ず重視しなければいけないことだ!」と思う人もいるでしょう。
しかし、あくまで私個人の見解ですが、たとえばランクを決めてD〜Sまでレベルがあったとしましょう。Sランクが「かなり重視する」とします。そうであるならば、業界の成長性はBもしくはAあたりでしょうか。
進歩の早い時代だからこそ個人の適応力が重要になる
自己成長を目的とする人、安定を求める人、それぞれどちらかの場合もあるでしょうし、どちらも同じように求めている人もいると思います。
両者に言えることですが、一つの考え方として「環境が自分を作るのではなく、自分が環境に合わせる」という価値観を作っていくことがとても大切です。
どれだけ将来性が見込めて安定しているように見えても、日々技術革新が進んでいくなかで10年後にどのように業界や世界が変化しているかを確実に見通せている人は少ないでしょう。
だからこそ、会社に求めるのではなく業界や時代が変化しても「対応できる自分」になっていることの方が大事ではないでしょうか。場所や環境も大事ですが、目まぐるしく変化する時代への適応的な生き方を同時に身に付けることもきわめて重要だと感じます。
これから衰退の懸念がある9業界! 今後の課題や回復の見込みも解説
ここまでは成長性の高い業界について解説してきました。しかし環境変化を味方に成長した業界がある一方で、同じ環境変化によって苦境に立たされた業界もあります。
衰退を懸念されている業界の抱える課題や、その課題を解決するためにどのような対策を立てるべきかを考えることで、国内市場全体の解像度が高まります。情報収集や業界研究の段階では成長性の高い業界の魅力だけにこだわらず、多くの業界について学ぶことをおすすめします。
今回取り上げる業界には、すでに回復の兆しが見えていたり、ビジネス展開によっては急成長を期待できる業界も多く含まれています。業界研究の一例としても役立つので、ぜひ参考にしてください。
フードサービス業界
新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けた業界の一つであるフードサービス業界は、現在も困難に立ち向かっています。
帝国データバンクの「飲食店」倒産動向調査(2023年)によると、2023年に倒産した飲食店は768件と、2022年の452件を大きく上回っています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が最も大きかった2020年の780件に逼迫する結果です。
さらに2025年には上半期だけで458件と、2022年一年の倒産数を凌駕しており、過去最多の数値を記録しています。
インバウンドの影響もあり外食需要は回復しつつあるにもかかわらず倒産件数が急増したのは、食材費や電気・ガス代の高騰が一因です。ロシアによるウクライナ侵攻が原材料費を上昇させたことに加え、円安の進行が影響しました。
原材料費が上がった以上、外食需要以外にも対応できる新しいビジネス軸を立てていく必要があります。
- フードデリバリー業界が好調なら、出前に注力すれば業績は回復するのではないですか?
フードデリバリーは飲食業界の競争相手でもある
確かにフードデリバリーは一時的に売り上げを増加させる手段にはなりますが、飲食業界の包括的かつ根本的な課題の解決はしてくれません。手数料や配送コストが利益を圧迫することや、デリバリー利用者は外食を控える傾向があるからです。
飲食業界が回復するためには、以下のポイントが重要になるでしょう。
まず、コスト管理です。輸入に頼らず地元の農産物を利用し、省エネ設備を導入してエネルギー消費の最適化を図ります。
次に、新たな収益源を確保しなくてはなりません。デリバリーやテイクアウトの強化、冷凍食品や調理済みミールキットの販売なども視野に入るでしょう。
顧客体験の向上も欠かせません。サービスの質を高め、ユニークなメニューやイベントを提供し、衛生管理や快適な空間づくりに注力して、安心して来店できる環境を提供します。
デジタル化とマーケティングの強化も重要です。顧客データを活用してリピート顧客を増やすキャンペーンを実施し、SNSでブランド認知度を向上させます。
飲食業界はフードデリバリー業界と一部協力しつつも、独自性を保ちながら総合的に業績回復を図ることが求められるでしょう。
具体的な施策としては、サプライチェーンの見直し、テクノロジーの活用、新規事業の展開(テイクアウト専用店舗やゴーストキッチンの運営)などが挙げられます。
飲食業界を志望する人はこちらの記事もぜひ参考にしてください。業界について詳しく解説しながら、企業側の目線も紹介しています。
繊維・化粧品業界
衣服や化粧品の需要も、新型コロナウイルス感染症で一気に減少しました。外出自粛によって衣服や化粧品を新調する必要性が縮小したためです。
マスクで顔が隠れてしまうことから化粧をしない、するとしても簡易的に済ませる、といった人も少なくありませんでした。新型コロナウイルス感染症で通販での購入が盛んになった結果、店舗の展開を縮小するとともに人員計画を見直す企業も多かったです。
しかし、マスクなしで外出する人も増えた現在は業界全体の業績も復調しつつあり、求人数も増えています。衣服は生活必需品であり、通販を利用してかえって店舗での体験に価値を見いだす人も多いです。
今後はアジア圏の低価格帯ブランドとのシェアの取り合いや、価格勝負による利益減少への対策に重きを置くことになります。
アパレル・化粧品業界の戦略はオムニチャネルです。ECとの連携ではデジタルマーケティングやオンライン販売の強化がカギになるでしょう。
顧客ニーズをとらえ、ブランド価値を保ちつつ新たな消費者体験を提供することが業界の回復につながります。
アパレル業界・化粧品メーカーについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ業界・企業研究、選考対策に役立ててください。
アパレル業界
アパレル業界の全貌がわかる! 最新の動向から選考対策まで解説
化粧品メーカー
化粧品会社に就職する方法を業界出身者が解説!
百貨店業界
百貨店は各業界の店舗の集合体であり、特に質の高いサービスを売りとしています。店舗体験に重きを置いた業態であるため、新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響は甚大でした。
百貨店はテナントを募集して利益を生んでいるのではなく、百貨店側が各企業の商品を販売しています。その売り上げと仕入れ値の差額が百貨店の利益です。企業としては百貨店の持つブランド力に期待して販売を委託しているので、その効力が発揮できない新型コロナウイルス感染症の拡大によって業界全体が苦境に陥りました。
また、人口の減少や高齢化が進む地方では、地域密着型の百貨店が経営難に陥るケースが見られます。百貨店は商品を企業から買い取って販売しているのではなく、売り上げから常に一定の手数料を引いています。そのため、地域によってはテナント運営型のショッピングセンターに出店するほうが企業としては利益を獲得しやすいことがあります。
しかし、日本百貨店協会が発表した2024年4月全国百貨店売上高概況によると、主要都市の百貨店は売り上げを回復させています。インバウンドがラグジュアリーブランドの売り上げをプッシュしている状況です。また、中食業界の盛り上がりから、弁当や惣菜の売り上げも当面安定することが想定されます。
百貨店業界について考えるときは、地域や商材にも注目すると良いでしょう。
航空業界
航空会社はそれまで学生からの人気が非常に高く、特に大手企業は基盤の頑丈さからグループ会社も含め採用に困ることはほとんどありませんでしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の外出自粛による旅客数激減の影響は甚大でした。経営が苦しくなり、JAL、ANAの国内大手2社は21年度と22年度の採用を大幅に縮小しました。
2025年現在、ANAやJALといった大手エアラインでは採用数が大幅に増えています。実際、2025年度にはANAで330名、JALで700名程度を採用するとの発表がありました。
現在は行動規制が解除されたことに加え、円安の影響で海外からの訪日客が増えたこともあり、業績も順調に回復へ向かっています。しかし、いまだ続く原油高をはじめ、環境変化の影響を受けやすい業界だからこそ、備えとして新しい主要ビジネスを確立させていく必要があります。
プロのアドバイザーならこうアドバイス!航空業界の課題は業界がすでに持っている財産の活用で立ち向かえる
航空業界は新型コロナウイルス感染症による採用縮小や一時的な業務停止による人員不足、原油高やCO2排出量など環境面での規制といった多くの課題を抱えています。
労働環境の改善や燃料効率の向上、CO2排出量削減のための技術開発や、グリーンテクノロジーの導入を含む環境への対応といった課題への対策は必要です。しかし、豊かな人材資産とグループ会社とのシナジーの活用、デジタル化や環境対応を進めることで、今後も持続的な成長をおこなっていけるでしょう。
豊かな人材の活用とグループ連携が航空業界の成長のカギ
まず、航空業界にいる高度なスキルを持つ人材を活用し、訓練プログラムの充実や、リスキリングを通じて、新しいサービスやビジネスモデルを開発することが必要です。
さらに、グループ会社との連携を強化し、ホテルや旅行代理店などとの協力を深めることで包括的な旅行・運輸サービスを提供し、顧客満足度を向上させることも可能でしょう。
一方で、予約システムの改善や、顧客データの活用によるパーソナライズドサービスの提供などでデジタル技術を活用し、業務効率の向上だけでなく顧客体験の向上を図ることは重要課題です。
航空業界の課題や展望についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。航空業界に興味のある人はぜひ参考にしてください。
建設・住宅業界
建設・住宅業界は著しい人手不足に陥っています。現場の労働環境が問題視されることが多いことに加え、職人の高齢化が深刻です。
2023年2月に厚生労働省と国土交通省が発表した建設業における安全衛生をめぐる現状についてによると、2021年の全産業における死亡災害数は867人、うち建設業は288人と33%以上を占めていて、労働災害が多く起きている業界です。死亡災害は年々減少しているものの、危険がともなう仕事です。
こういった事故が起こる一因として、工期の遅れを解消するための強引な働き方があります。一般的に、工事は予定日までに完了しないと契約不履行として違約金などのペナルティが課されます。しかし現場は天候不良などから遅延が発生しやすく、圧迫された結果として安全を確保しないまま作業を急ぐことがあります。
また、高年齢者が形成する風土に若年層がなじめないために離職が発生する、都市への人口集中から新築の需要が下がっているなどの課題もあります。老朽化対策やメンテナンスの需要は絶えないものの、ハウスメーカーなどは新築住宅以外にも領域を広げるなどして対策をしていく必要があります。
建設業界についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、業界に興味のある人、業界にどんな仕事があるか知りたい人はぜひ読んでください。
銀行・証券業界
金融系は堅調な業界として名高く、学生からも人気の業界です。しかし、長期にわたるデフレーションや世界経済への不安から2016年1月に導入されたマイナス金利政策が銀行の資金繰りを厳しくしていました。
マイナス金利政策
経済を活性化させるための政策。民間銀行が中央銀行に預けている預金の金利をゼロ未満のマイナスにすることで、民間銀行は預金することで資金が減る状態となる。民間銀行による積極的な貸出を促進する政策。
(2024年3月に政策自体は解除済み)
民間銀行は低金利での資金貸出をせざるを得ない状況に長く置かれていたため、経済の動きが小さい地方の銀行は特に収益の少ない状況でした。そこに新型コロナウイルス感染症での経済停滞が重なったため、銀行の安定性はさらに削がれました。
加えて、仮想通貨や電子決済サービスの市場が拡大したことで、資産運用のメイン舞台が金融機関からネットへと移りつつあります。証券に関しても、手数料が安く利便性も高いネット証券がシェアを拡大しているため、株式や債権の売買手数料をおもな収益とする証券会社にとっては苦しい状況です。
しかし、新NISAやiDeCoなど、政府が若い世代へも資産運用を促していることから、個々人の資産運用に対する意識自体は高まっています。マイナス金利政策も2024年3月に解除されました。ビジネス展開によっては回復にとどまらず急成長の可能性も秘めています。
今後もAIは進化するため、銀行・証券業界もオンラインでのやり取りが主流になっていくと考えられます。
ネット銀行が発展している昨今、すでに金銭のやり取りがネットで完結することは当たり前になってきています。人件費が削れる分、金利が高いことも顧客にはメリットです。業界全体でますますIT化が進んでいくでしょう。
銀行・証券業界についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、興味のある人、就職を検討している人はぜひ参考にしてください。
放送業界
放送、つまりテレビ業界がユーザーを取り合っているのは、動画配信サービスをはじめとするさまざまな情報媒体です。配信サービスは場所を問わずコンテンツを視聴でき、時事情報もネットで閲覧が可能です。これらは家など特定の場所でないとコンテンツ視聴ができないテレビの弱点をカバーしています。
テレビ業界の利益源は企業が支払う広告費です。企業はテレビの視聴者に向けて自社サービスを宣伝するために出資しているので、ユーザーが分散すれば当然広告も分散させます。そして、費用対効果の薄い場所へは出資しなくなります。
NHK放送文化研究所が2021年に発表している国民生活時間調査2020によると、テレビ視聴率とインターネット視聴率を年代ごとに比較すると、30代未満はネット利用率がテレビ視聴率を上回っています。若年層へアピールしたい企業が出資先をネットへ移すのは自然なことです。
対照的に、30代以降はテレビがネットを上回っていて、特に60代以降のテレビ視聴率は90%以上を維持しています。少なくとも現在の高年齢者に向けたアピールはテレビに強みがあります。加えてテレビ用のコンテンツを配信するサービスも展開されているため、テレビ局の作るコンテンツが若年層に届く機会が喪失したわけではありません。
今後はネットに慣れた世代が高年齢層に入ってきます。そういった将来に向けてテレビ局はこれまでに培ってきた知見をどう活かすかがカギとなります。
テレビ業界のトレンドについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
出版業界
冒頭でも触れたように、出版業界では紙の本と電子書籍がシェアを奪い合っている状態です。出版科学研究所が公表する2025年版出版指標年報によると、業界全体では1996年をピークに出版市場は縮小を続けているものの、電子書籍に限れば売り上げは右肩上がりです。
特にコミックの売れ行きが好調です。場所と時間を問わず購入でき、持ち運びも簡単なので、定期販売される雑誌や巻数が膨らみやすい連載コミックと相性が良いためと考えられます。新型コロナウイルス感染症で家で楽しめるエンタメが盛り上がった影響が現在まで続いていることも影響しているでしょう。
対して紙の本は売り上げが減少し続けています。そもそも、電子書籍は原稿さえあれば販売できますが、紙の本は販売までに原価がかかります。もともと印刷には莫大な初期投資が必要であるにもかかわらず、現在は紙の値段が上がっていて、利益を保つことは非常に困難な状況です。
電子書籍の好調は続く見込みですが、教科書までデジタル化が進む今、紙の本は大きな課題に直面しています。紙の本は保存性に優れ、一覧性の高さや書き込みの自由度も高いといったさまざまな強みがあるので、これらを活かした施策を打ち出していく必要があります。
出版業界のトレンドについてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、選考を検討している人、業界に興味のある人はぜひ参考にしてください。
士業業界
士業
就業に専門資格の取得が必要な職業の俗的な総称。該当する職業の名称の多くの末尾に「士」が付いていることに由来する。
おもな士業
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 公認会計士
- 社会保険労務士
- 中小企業診断士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 海事代理士
士業は一般的に就業が難しく高収入であると考えられています。これらの職業は社会的需要が高く綿密なコミュニケーションを必要とするため、なぜ衰退を危ぶまれているのか疑問に思う人も多いでしょう。
例として税理士を挙げます。確定申告などのさまざまな税務を代行したり、税務に関する相談に乗ったり、企業や事業主の会計業務をサポートするといった役目を担う税理士は、お金のスペシャリストとしてほうぼうから頼られる存在です。衰退とは無縁に思う人もいるでしょう。
しかし税務とは、法律に則って正しく計算・書類作成をしたうえで、納税する業務です。これは定型的な作業が得意で計算能力の高いAIが代行しえるものです。先にも言及した日本の労働人口の49%が人工知能やロボットなどで代替可能にというレポートでも現在の税理士の業務はAIにもおこなえると指摘されています。税務処理を助ける会計ソフトもすでに普及しています。
士業は今後、AIとの差別化を図るために自身の付加価値を追求していく必要があります。
これから伸びる業界に就職するためのコツ
これから伸びる業界に就職するためのコツ
- 成長性の高い業界で求められる人材であることを伝える
- 業界の成長要因や展望を自分の言葉で話せるようにする
- 志望職種に関係なくゼネラリストとしての能力を伸ばす
これから伸びていく業界に属する企業は、企業としての成長はもちろん、社員一人ひとりの成長にも注目しています。組織は個の集まりなので、組織全体の成長には各人の向上心や成長意欲も欠かせないと考えているのです。
そのため、選考においても自身の将来性をしっかりとアピールすることが重要になります。あなたらしさが何よりも大切なアピールポイントなので、あくまでも成長性の高い業界への就職のための一参考としてください。
成長性の高い業界で求められる人材であることを伝える
これから伸びる業界ならではの「求められる人材像」を押さえると、面接官に「この学生は自社で活躍してくれそうだ」と想像させるようなアピールをしやすくなります。
成長性の高い業界では、第一に向上心や成長意欲が求められます。業界のトレンドが次々と更新されていくので、その変化に対応しながら組織に貢献しようという積極性がなくては業界をリードする存在にはなれません。
加えて、成長のただ中にある企業は組織体制や業務内容の変動も起こりやすく、そういった変化に柔軟に対応できることも重要です。変化によって刷新された内容がどういったものであろうと興味を持てる強い好奇心も面接官には好印象に映ります。
これから伸びる企業に就職したいのであれば、その環境やそこで起きる変化に適応する姿勢を見せ、自身の成長性の高さを力強くアピールしましょう。
成長業界の選考では、自身の自己理解を深め、自身の将来の夢と成長意欲を強調することが重要です。また、柔軟性やリーダーシップも必要であり、業界展望や興味を的確に表現することも好印象を残すポイントになります。
業界の成長要因や展望を自分の言葉で話せるようにする
業界が成長している背景や今後の展開を自力で予想し、自らの言葉で説明できることも、選考においては重要です。
その業界に強い興味や魅力を感じていることをアピールできるだけでなく、情報をロジカルに組み立てて持論を展開するほどの思考力を持っていることは、学生のみならず社会人としても長所になります。論理的思考力は職種やポジションを問わず鍛えるべき能力であり、学生の時点でその素地を持てると周囲との差を広げることも可能です。
- 業界の展望などは選考で聞かれることがあるのですか?
業界の展望について聞かれることは十分ありえる
企業は、自社の成長に貢献できる人材を求めています。
特に成長性の高い業界では、業界への理解度を確認するためにも、業界の現状や展望について聞いてくる可能性は高いでしょう。業界全体の動向を把握し、自らの言葉で語れることが重要だからです。
エントリーシート(ES)に盛り込む余地がない場合でも、面接の際には必ず準備しておきましょう。
業界に対する持論を持つことは、選考において大きなメリットがあります。専門性と深い興味と熱意を示せるうえ、情報を収集し、分析し、論理的にまとめることで論理的思考力をアピールできます。
常に学び続けていることを示すことで自己成長の証明となり、ほかの候補者との差別化を図ることができるのです。
業界研究を深め、自分なりの見解を持つことで、競争が激しい成長性の高い業界での就活も有利に運べます。
志望職種に関係なくゼネラリストとしての能力を伸ばす
ゼネラリスト
幅広い分野の知識や経験を有し、それらを応用してさまざまな場面に対応することができる人材。一般的にはスペシャリストの対局に位置する。
しかし、こと成長業界においては、自身の担当領域のスペシャリストであると同時に、そのほかの領域にも対処できる応用力を持ったゼネラリストでもあることが将来性に直結します。
これまで解説したとおり、成長中の業界・企業は変化が激しく、そこに身を置けば常に新しい物事に触れている状態になります。すべての分野のスペシャリストになることはおよそ不可能なので、それまでに積み上げたスキルや知見を応用して対処していくことになります。
また、これからは業界を問わず年功序列よりも成果主義の会社が増えていきます。年齢を重ねることが必ずしも社会人としての能力を高めるわけではないという考えが広がっていると同時に、成果に対する適切な評価がないと優秀な人材が流出してしまうため、年齢に関係なく組織へ貢献する人を評価し昇格させようという風潮が一般化しつつあるのです。
その結果、優秀な人は若いうちからマネジメント力を試される場面に直面しやすくなっています。そのハードルを乗り越えるとさらに成長の機会に恵まれていきます。専門職も同様です。優秀な人材が集まりやすい成長業界でより多くのチャンスをつかむには、ゼネラリストとしての能力がカギになります。
一方、個人的には、ゼネラリストは今後あまり多くは求められないかと思います。
専門領域に特化して得意分野を持っているのが時代の流れなので、よほどの幅広い対応力がない限り必要性は乏しいのかなと感じます。活躍の仕方としては「スペシャリストとして2〜3の専門領域を持つ」という感じでの幅の持ち方が良いかと思います。
これから伸びる業界で重宝される人材になるには? 今からできる準備
これから伸びる業界で活躍するためには、入社前から以下のような準備をしておきましょう。
重宝されるためにしておくべき準備
- 語学の勉強
- IT系スキル・資格の取得
- 情報を収集・精査するスキルを高める
語学スキルは、入社前にTOEIC600点以上の英語力を身に付けておくのがベターです。海外で活躍したいのであれば、TOEIC800点以上を目安に学習を継続しましょう。
また、テクノロジーの発展が進む現代では、ITスキルがどの業界でも重宝されます。プログラミングスキルやAIを活用するスキルを早いうちに身に付けておくと、昇進や転職で有利になります。
また、不確実性が蔓延する社会になっていくなかでは、本物を見抜く審美眼も欠かせない能力になっていきます。特に成長領域では常に最新の情報をキャッチアップしておかなくてはなりません。少しでも遅れを取ったら同業他社にあっという間にリードされてしまう、シビアな世界です。
玉石混交の情報のなかからどの情報が正当な根拠を持っているのか、あるいは自分にとって役に立つものなのかを自力で精査する力を身につけ、競争の激しい社会を生き抜ける強さを養っておきましょう。
悩む人が多い! 業界研究にまつわるQ&Aまとめ
ここまで、具体的な伸びる業界やそこで活躍するための極意などを解説してきました。伸びる業界と衰退していく業界それぞれの特徴、今後の展望などを解像度高く理解できたでしょう。
ただ、業界分析をしていくなかで「各業界の将来性や人気について、もっと詳しく知りたい!」と思い始める学生も多いでしょう。また、業界の選び方にまだ不安がある人もいるかもしれません。
そんな就活生に向けて、ここからは多くの人が抱きがちな疑問や悩みについてキャリアコンサルタントが一つずつ回答していきます。
本格的に業界選び・業界分析に取り掛かる前にチェックして、不安なく就活を進められる状態にしておきましょう。
業界の将来性や人気に関する質問
これから伸びる業界のうち自分に合いそうな業界が見つかった人は、より詳細な情報が欲しいと感じるでしょう。特に就活での人気度や就職難易度、その業界のネガティブな側面などは、事前に調べておくべき重要な要素です。
以下では、PORTキャリアに寄せられた業界の将来性や人気などに関する疑問をいくつか紹介します。各業界の特徴や良い点、悪い点まで知り尽くしたキャリアコンサルタントが詳しく解説しているため、事前にチェックして業界選びや分析を深める際の参考にしてみてください。
これから伸びる産業
これから伸びる産業はどこですか?
就職活動中の学生に人気の業界を教えてください。
就活でオススメしない業界はありますか?
業界の選び方に関する質問
ここまで記事を読んできた人の中にも、「伸びる業界はわかったけど、受ける業界を絞れない……」と悩んでいる就活生がいるでしょう。それぞれの業界を深掘りしていない段階では、受ける業界を決めきれないのは珍しいことではありません。
ここでは、多くの学生が悩みがちな業界選びに関する質問に、キャリアコンサルタントが丁寧に回答しています。
業界を絞りきれずに悩んでいる人や絞りすぎに対して懸念を抱いている人は、ぜひ以下をチェックして不安を拭い去りましょう。
就活で業界を絞らない
就活で業界を絞らないのはありですか?
業界を絞りすぎ
就活で業界を絞りすぎるのは良くないのでしょうか?
業界を絞らずバラバラに
就活で業界を絞らずバラバラに応募するのはまずいですか?
また、業界の絞り方や分析・深掘りの方法をより詳しく知りたい人は、以下の記事もチェックしてみてください。丁寧な手引きをチェックしながら分析をおこなえば、自分にぴったりの業界を見つけ、就活が一気に進めやすくなりますよ。
就活での業界の絞り方
業界の絞り方で就活失敗? 後悔しない絞り方7選と必須の準備を解説
これから伸びる業界の共通点を押さえた深い業界研究で内定へ近づこう
これから伸びる業界について、業界の成長要因や就職に向けた準備について解説しました。成長性の高い業界は最新の情報や技術を扱いながら大きな仕事に携われる機会が多く、学生からの人気も高いです。
だからこそ、深い業界研究と、あなたが企業へどのように貢献できるかというアピールで差別化を図ることがひときわ重要になります。
この記事で解説した各業界の成長要因や展望をもとに、志望業界への理解を深め、あなたがこれから伸びていく業界で活躍できる人材であることを選考内でアピールしていってください。そして、あなたがいきいきと楽しく働ける企業からの内定獲得を目指しましょう。
プロのアドバイザーはこう分析!これから伸びる業界は成長機会が多くキャリアの選択肢を広げられる
成長業界への挑戦は、未来へのキャリアに輝かしい可能性を秘めています。
たとえば、新興テクノロジーやデジタルマーケティングなど、最先端の分野での活躍が期待されます。夢や情熱を追求する絶好の機会であり、業界研究を通じて、興味のある分野や得意なスキルを見つけましょう。プログラミングやデータ分析などのスキルを磨くことで、自らの可能性を広げることもできます。
また、成功に向かって歩む道は、時に険しいかもしれませんが、一歩踏み出し、チャンスをつかむための努力を惜しまない姿勢が大切です。自分の可能性を信じ、今日から行動しましょう。成功は、あなたの努力と勇気が呼び込むものであり、挑戦する価値があります。
挑戦する人が多い環境へ飛び込むからこそ事前準備が大切になる
挑戦への準備として、自己PRや面接対策は重要であり、志望業界のトレンドや企業の特徴を把握し、自身の強みをアピールすることが肝心です。また、業界のプロフェッショナルとの交流やインターンシップ参加などの実践的な経験は成功への準備の一環ととらえましょう。
あなたの持ち前の前向きな姿勢と努力の継続によって、夢をかなえられる可能性が広がっていきます。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi












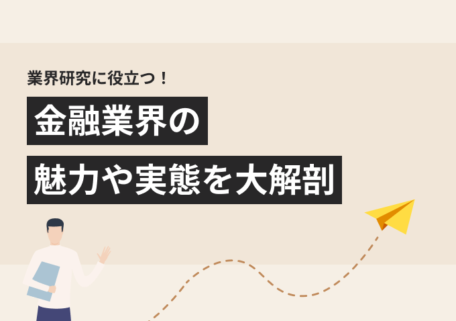















5名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント
Arisa Takao〇第二新卒を中心にキャリア相談を手掛け、異業種への転職をサポートする。管理職向けの1on1やコンサルティング業界を目指す新卒学生の支援など年齢や経歴にとらわれない支援が持ち味
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/メンタル心理カウンセラー
Syuya Nagata〇自動車部品、アパレル、福祉企業勤務を経て、キャリアコンサルタントとして開業。YouTubeやブログでのカウンセリングや、自殺防止パトロール、元受刑者の就労支援活動をおこなう
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表
Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアコンサルティング技能士
Hiroshi Takimoto〇年間約2000件以上の就活相談を受け、これまでの相談実績は60000件超。30年以上の実務経験をもとに、就活本を複数出版し、NHK総合の就活番組の監修もおこなう
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/合同会社渡部俊和事務所代表
Toshikazu Watanabe〇会社員時代は人事部。独立後は大学で就職支援を実施する他、企業アドバイザーも経験。採用・媒体・応募者の全ての立場で就職に携わり、3万人以上のコンサルティングの実績
プロフィール詳細