この記事のまとめ
- 需要が増える職種を20個紹介
- これから需要が増える仕事の共通点を就活のプロが解説
- 需要が伸びる仕事に就くためのコツを知り転職を実現しよう
転職を考えた際、「これから先も安定して働ける仕事はあるのだろうか」と疑問に感じる人もいるのではないでしょうか。
たしかに、近年のAI(人工知能)の発達やテクノロジーの急速な発展で、働き方や求められる仕事が変化しているため、需要が増え将来性がある仕事の判断基準がわからない人もいるかもしれません。
需要のある仕事に就くには、時代と共に何が変化していき、どのような職種が求められているかを理解することが重要です。
この記事では、キャリアコンサルタントの吉田さん、西さん、若林さんのアドバイスを交えながら、これから需要が増える仕事の特徴や具体的な職種と業界について解説します。
また、大学で就活に関する実践授業などもおこなっている西さんからは需要が増える仕事に共通する特徴などについても解説してもらっているため、将来性のある仕事を探している人や、自分に合った仕事で長く安定したキャリアを築きたいと考えている人はぜひ参考にしてくださいね。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
これから需要が増える仕事は人の手が必要な業務かどうかを見極めよう
これから需要が増える仕事を見極めるには、時代の変化と共にどのような業務が人の手を必要とし続けるのかを理解することが重要です。
AIや自動化技術が進化するなかで、機械ではなく人の手が必要な業務であれば、今後も需要が増える可能性が高いのです。
そこでこの記事では、まず需要が増える仕事の特徴と具体的な職種20選について解説します。これらは前提知識となる部分なので、自身のキャリアを考える基盤として理解を深めておきましょう。
次に、今後需要が増える業界についても解説します。逆に需要が低下する可能性のある仕事の特徴についても紹介するため、今後あなたが進みたいキャリアをイメージしながら、就職しても問題ないかどうかを確認してみましょう。
記事の終盤では、需要が増える仕事に就くためのコツや、仕事を選ぶ際の注意点についても解説します。これらの情報を参考にし、将来性のある職種への転職に役立てましょう。今後、安定しやすい職種に就き、自身の思い描くキャリアに近づきたい人はぜひ参考にしてください。
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
大前提! これから需要が増える仕事の4つの特徴
大前提! これから需要が増える仕事の4つの特徴
これから需要が増える仕事は、人の手が必要な業務かの見極めが重要になります。しかし、具体的にどのような特徴を持った仕事が、人の手が必要になるのかわからない人もいるのではないでしょうか。
そこで、この章ではこれから需要が増える仕事の4つの特徴を解説します。AIやIT技術のようにテクノロジーの進化によるものから、人手不足のような人材関係の理由まで特徴もさまざまです。
需要が増える仕事の前に特徴を理解しておくことで、なぜこの職種に需要があるのかを把握しやすくなります。
需要が高くなることは今後将来性があることにつながります。以下の記事では将来性のある仕事を紹介しているので読み進めて、転職の選択肢を広げましょう。
関連記事
将来性のある仕事13選! これから需要が高くなる仕事とは?
「将来的になくならない仕事に就きたい」「同じ仕事を長く続けたい」と考える人は、将来性のある業界や仕事を選びましょう。この記事では、将来性のある業界や仕事について、キャリアコンサルタントのアドバイスを交えつつ解説します。
記事を読む

あなたが受けないほうがいい業界・職種を診断しよう
就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。
そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。
自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
①AIでは代替が難しい仕事
これから需要が増える仕事の特徴には、AIでは代替が難しい仕事が挙げられます。
AIはデータに基づく分析や業務の流れが決まった作業は得意な傾向ですが、人間ならではの思考や感情の理解が必要となる業務は対応は得意ではありません。
たとえば、心理カウンセラーは相談者の表情や声のトーンから感情を読み取り、共感しながら適切なアドバイスを提供するためAIでは代替が難しい仕事です。
ほかにも、クリエイティブディレクターのように新しい発想で企画を生み出したり、保育士のように、子供たちの状況に応じて柔軟な対応が求められたりする仕事も、AIでは代替が難しいといえます。
このように、人間の感情を読み取る仕事や、臨機応変な対応が求められる仕事は、今後もAIに代替されにくく需要が安定していくと考えられます。
AIの進化によってなくなる仕事を把握しておきたい人は以下の記事も読んでみましょう。今後AIに代替されず、残り続ける仕事や今できる対策が載っているので参考にしてください。
関連記事
AIによってなくなる15の仕事|残る仕事とAI時代の動向も解説
AIによってなくなる仕事があると話題ですが、実際はほとんどの仕事でAIによってなくなる部分となくならない部分があり、切り分けを正しく認識することが重要です。この記事ではキャリアコンサルタントがAIによってなくなる仕事・残る仕事とキャリア選択のコツを解説します。
記事を読む
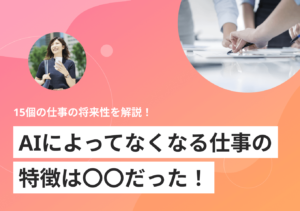
②IT関係の仕事
近年は、社会全体のデジタル化が急速に進んでいるため、あらゆる業界でITの知識やスキルを持った人材が必要とされています。そのためIT関係の仕事は、これから需要が高まる分野の仕事といえるのです。
具体的には、AIやインターネットを利用した技術にはIT技術が活用されています。これらの技術を開発し運用するITエンジニアや、データを分析してビジネスに活かすデータサイエンティストは、今後必要とされる可能性が高いのです。
また、IT関連の仕事にはAIを作ることもあるため、AIの進化とともに需要がさらに伸びる傾向もあります。
このように、私たちの生活を便利にする技術には、ITを使いこなす技術が不可欠であるため、今後もITシステムの設計や運用、管理ができる仕事は需要が高まっていくといえます。
IT関係と言われても、業界の仕組みや仕事内容を詳しく知らない人もいるのではないでしょうか。以下の記事では、IT業界の仕事内容から働く魅力を解説しているので、気になる人は読み進めてみましょう。
ITの仕事
ITの仕事って何があるの? 仕事の種類や働く魅力を詳しく解説!
IT業界
IT業界を徹底解剖! 押さえておきたい将来性やトレンドまで解説
あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
③人材が不足している仕事
そもそも人材が不足している仕事も、今後も高い需要が続くと予想されます。少子高齢化により労働人口が減っていくだけでなく、業務によって必要になる専門的スキルを持つ人材が不足しているからです。
人材が不足している仕事には、おもに下記のような特徴があります。
人材が不足している仕事の特徴
- 専門的な技術や資格が必要
- 体力的な負担が大きい
- 労働時間が長い
- 勤務時間が不規則、またはシフト制である
- 後継者が不足している
介護士を例に挙げると、近年は高齢化社会なため介護士の必要性が高まっていますが、体力的な負担や給与面での課題から人材確保が難しい状況です。
また、建設業界では熟練技術を持つ職人が高齢化し、次の後継者の育成には時間がかかるため、人材が不足しているのです。
上記のように、社会的に重要でありながらも人材不足が深刻な職種は、働き手が求められているため今後も需要が高まり続けるとされています。
どのような業界が人材不足の業界に該当するのか把握したい人は、以下の記事も読んでみましょう。この業界で働くメリットやデメリット、就職しやすい仕事の特徴が載っています。これから需要が増える仕事に就くためにも、判断材料に役立ててください。
関連記事
人手不足に悩む6つの業界を徹底解説! 就職しやすい仕事も紹介
人手不足の業界は就職しやすい反面、労働環境に注意しないと後悔につながるかもしれません。記事ではキャリアコンサルタントと、人手不足の業界の現状や就職しやすい職種を解説します。企業選びの注意点も説明するので、自分に合う仕事を見つけてください。
記事を読む

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
- 人材が不足している仕事はきついイメージがありますが実際はどうなのでしょうか
確かにきつい側面もあるがポジティブな面もたくさんある
人材が不足している仕事は確かに「きつい」と感じている現場の方は多いです。離職理由もそういった面がきっかけとなることも多く、根本改善が難しいことも現実としてあります。
一方で、上記で挙がっている介護業界や建設業界をイメージするとわかる通り、実際は社会になくてはならない仕事のため、需要がなくなることはありません。
またホワイトカラーのような仕事ほどAIやIT技術の台頭により廃れてしまう可能性があります。
人材不足の仕事にもポジティブな面はたくさんあるのでぜひ調べてみてください。
④生活するうえで必要になる仕事
私たちが日常生活を送るうえで欠かせない仕事も、将来的に需要が安定しやすいといえます。人が生きていくために必要なサービスは、社会情勢や技術の変化にかかわらず常に必要とされているのです。
たとえば、医療や介護のように人の健康を支える仕事や、保育や教育のように子どもの成長をサポートする仕事は常に必要とされている職種です。また、衣食住を支える食品製造や住宅建設、不動産管理などの仕事も生活に必要な存在といえます。
こうした生活に密接にかかわる仕事は、経済状況が悪化しても比較的影響を受けにくく、需要が安定していると考えられます。
経済状況に関係なく、交通・物流や清掃・衛生管理関連の仕事は安定した需要が期待できます。
日本では高齢化率も高く、食料品や生活必需品の配送はますます必須のものであり、また、感染症対策からもクリーンな環境が今後も求められるからです。
所要時間はたったの3分!
受けない方がいい職業を診断しよう
就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。
就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。
- 自分に合う職業がわからない人
- 入社後のミスマッチを避けたい人
- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人
キャリアコンサルタントが解説! これから需要が増える仕事に共通する特徴は?
ここまで、今後需要が伸びるとされている業界や職種を解説しましたが、同時に需要が伸びる仕事に共通する特徴も把握しておきましょう。
前述した業界や職種がなぜ伸びるのかを理解していなければ、今後自身のキャリアビジョンとは違う選択をしてしまい、就職後にミスマッチしてしまう可能性があるのです。
そこで、キャリアコンサルタントの西さんに、これから需要が増える仕事に共通する特徴を聞いてみました。今後需要が高い職種に出会うためにも、特徴を理解し転職活動に役立ててみてください。
アドバイザーからワンポイントアドバイスこれから需要が増える仕事の特徴は4つある
1つ目は人の手が必要な仕事、つまり、AIでは代えのきかない仕事になります。クリエイティブな仕事、心に寄り添う仕事、臨機応変な対応が求められる仕事などは、今度もますます需要が高くなるでしょう。
2つ目は、IT関係の仕事のなかでも、AIを作る側の仕事やデータ分析をおこない顧客に提案していく仕事です。これらは、顧客の要望に沿ったシステム開発が必要であり、顧客とのコミュニケーションが求められるからです。
3つ目は、人手不足の仕事です。日本では少子高齢化が進み、人手不足が叫ばれているからです。
人手不足の業界も今後需要が増える可能性が高い
ただ、人手不足の仕事は、そもそも待遇面や体力面、専門的な技術、労働時間などが一般の仕事と比べて「きつい」と思われがちです。しかし、今後徐々に改善されていくことが予想されます。
最後に、たとえば衣食住や教育、医療・介護にかかわる仕事など、社会情勢に関係なく、生活をするうえで必要な仕事は今後もかわらず必要なので、安定して需要があるのです。
興味が湧くかチェック! これから需要が増える仕事20選
興味が湧くかチェック! これから需要が増える仕事20選
需要が伸びる業界の説明を聞き、進むべき道を決めた人もいれば、将来進むべき道にまだ迷っている人もいるはずです。どちらの人も、これから紹介する需要が増える職種を見て、自身のキャリアビジョンに合っているかを確認してみてください。
この章では、IT系から医療や介護系、クリエイティブ系まで、幅広い分野から需要が増える20の職種を紹介しています。
それぞれの仕事の特徴や魅力、求められるスキルを知ることで、自身の適性や興味との相性を探る手がかりになるので、自身が将来的にどのような働き方をしたいのかも考えながら読み進めましょう。
やりたいことや興味のある業界が決まっていない人はこちらのQ&Aも参考にしてみてください。業界を絞らず就活を進める方法をキャリアコンサルタントが回答しています。
①ITエンジニア
ITエンジニアとは
システム開発やソフトウェア開発、ネットワーク構築などをおこなう職種
デジタル化が進む現代社会において、ITエンジニアの需要は今後さらに高まることが予想されています。この背景には、あらゆる業界でITシステムの導入が進み、開発や保守を担う人材が不可欠になっているからです。
たとえば、金融機関では、インターネットを使った銀行サービスの開発が進み、物流業界では商品の配送状況の追跡や倉庫内の在庫管理など業務を効率化するシステムが導入されました。こうしたシステムにはITエンジニアの技術が欠かせないのです。
ITエンジニアは、社会のデジタル化を支えることでやりがいを感じられる職種であるため、新しい技術に興味があり、最新技術を用いて社会に貢献していきたい人は、キャリアの選択肢に入れてみるのをおすすめします。
ITエンジニアは働き方の種類が多い仕事です。以下の記事では、ITエンジニアの仕事を20選紹介していて必要なスキルも載っているので参考にしてください。
システムエンジニア、ネットワーク、プログラマーなども引き続き需要は伸びると予測できます。しかし、単純なコーディング業務などはAIなどの台頭により需要は減っていくでしょう。
②データサイエンティスト
データサイエンティストとは
大量のデータを分析し、ビジネス課題の解決や有益な情報を提供する職種
多くの企業は、膨大なデータを保有していますが、それらをすべて活用し運用に役立てるのは簡単ではありません。そのなかで、データサイエンティストはそれらのデータを分析し、ビジネスに活かしていけるため、需要が高まっていている職種なのです。
小売業界を例に挙げると、顧客の購買履歴やWebサイトの閲覧履歴などのデータを分析すれば、消費者がどのような商品を求め、いつ売れやすくなるのかを予測できます。
ほかにも、製造業では工場の設備から得られるデータを分析することで、設備の故障を事前に予測するだけでなく、生産効率を最大化するための改善策を見つけやすくなるのです。
データサイエンティストとして活躍していくには、解析力や統計学の知識など専門的な知識が必要であり、そうした知識を持つ人材が不足しているため、今後も需要が高まる職種といえます。
③デザイナー
デザイナーとは
グラフィックやWeb、ファッションなど、さまざまな分野でデザインをおこなう職種
商品やサービスが溢れる現代において、デザイナーの需要は今後ますます高まっていくと考えられています。消費者の心をつかむためには、機能性だけでなく優れたデザイン性が不可欠になっているためです。
デザイナーは分野によって活躍の場は異なり、以下のようなデザインを手掛けます。
デザイナーが手掛ける業務の例
- ポスターやチラシのグラフィックデザイン
- Webサイトやアプリのデザイン
- 製品や商品そのもののデザイン
上記のように、商品パッケージやWebサイトなど、日常のなかで目に触れるあらゆるものにデザインの力が必要とされています。
AIによる画像生成技術が発展するなかでも、人間ならではの感性や創造力、クライアントと意思疎通を取りながら要望を汲み取る力を持ったデザイナーの価値は変わらないのです。
デザイナーに興味が出た人は以下の記事を読んでみましょう。Webデザイナーの仕事内容や将来性が載っているので、働くイメージを固めてみてください。
④アーティスト
アーティストとは
絵画や音楽、彫刻にパフォーマンスなど芸術作品を創造する職種
AIが進化しても、人の心を動かす独創的な表現は、人間ならではの感性から生まれます。そのため、アーティストは今後も社会に必要とされ需要が伸びる可能性が高い存在です。
一見、活躍の場をイメージできないかもしれませんが、企業のブランドイメージを表現する作品制作や、商業施設や公共空間を彩る空間デザインなど、アーティストの制作の場は多岐に渡ります。
またゲームや映画の音楽制作もアーティストの業務の一つです。ただし、アーティストとして活躍するには、技術力だけでなく表現力や独自の感性も必要になることは念頭に置いておかなければなりません。
人間の感性を活かし、社会に新たな価値をもたらす仕事として、アーティストも視野に入れて今後の将来を考えてみてください。
- アーティストと聞くと、最初は収入が不安定なイメージを持ってしまいます。実際はどのような働き方になるのでしょうか
会社所属やフリーランス、経営者などさまざまな働き方がある
私の周囲には、作曲家・ミュージシャン・イラストレーター・ゲームクリエイターなど、多くのアーティストがいます。
会社に所属している人もいれば、フリーランスや自分で会社を経営している人もいます。
新卒でアーティスト(クリエイター枠)での入社は門戸が狭く、採用されても採用後の試験によって希望以外の業務に配属される可能性もありえます。
ですが安定収入があるのは魅力です。 一方で、収入が不安定でも、アーティストとして生計を立てたい人は、アルバイトなどをしながらアーティストとして活動しています。
⑤インテリアコーディネーター
インテリアコーディネーターとは
住宅や店舗などの室内空間を機能的かつ美しく演出する職種
人々のライフスタイルが多様化し、住まいや店舗ではデザイン性や快適性が求められるため、インテリアコーディネーターの需要は高まっているといえます。
たとえば、住宅では施主の好みや生活に合わせた空間を提案する必要があります。商業施設では、ブランドイメージを高める空間をデザインしたり、オフィスでは働く人の意欲を高められるような環境をコーディネートしたりすることが求められているのです。
これらの仕事は、人の感性や空間把握力、提案力が不可欠であり、AIには代替されにくい作業です。
心地良い暮らしや魅力的な空間を作れるインテリアコーディネーターは、今後も必要とされ将来性がある職種といえます。
⑥営業
営業とは
どの業界にも存在し自社の商品やサービスを顧客に提案し、販売につなげる職種
デジタル化が進んでも、営業職はAIに代替されにくい仕事です。顧客の課題を見つけ、最適な解決策を提案するには、人間ならではのコミュニケーション能力や洞察力が不可欠です。
具体的には、製造業が顧客の場合は、工場の生産性を高める機械を提案したり、業務を効率化するシステムを提案したりします。商談の際は、顧客の言葉や表情、状況からニーズを読み取り、顧客の課題を解決できる商品を提案しなければなりません。
また、近年はオンライン営業も増えていますが、画面越しでも信頼関係を築くためには、高いコミュニケーション能力が必要です。
このように、営業職はAIには難しい複雑な交渉や、人と人とのつながりを生み出せるため、今後もあらゆる業界で求められる存在なのです。
営業職といっても、ルート営業や法人営業など営業先によって働き方が異なります。以下の記事を読み、営業の働き方を把握しておきましょう。
BtoB営業
BtoB営業ってどんな仕事? 魅力から大変な部分までまるごと解説
ルート営業
ルート営業に向いてる人の8つの特徴や仕事の魅力・厳しさを解説
⑦Webマーケター
Webマーケターとは
WebサイトやSNSなどを活用し、集客や販売促進をおこなう職種
企業によっては、オンラインでの集客や販売に力を入れる現代において、Webマーケターの需要は高まってきています。
Webマーケターの業務には以下のような内容があります。
Webマーケターの業務内容の例
- Webサイトの訪問者数を増やすための対策
- SNSでの情報発信
- 効果的なWeb広告の運用
上記のように、仕事は多岐にわたり、商品の魅力を伝えるWebコンテンツの作成や、顧客の興味を引くキャッチコピーを考えるのもWebマーケターの仕事なのです。
これらの仕事は、Webサイトを制作する知識だけでなく、顧客の心をつかむための企画力や、データ分析に基づいた判断力が必要になります。AIから業務内容についてヒントはもらえたとしても、すべての業務を任せることはできないのです。
そのため、オンラインでのビジネスが拡大するなかで、Webマーケターは今後も企業を支える存在として需要が伸びると予想されます。
基本的なマーケティングの知識だけでなく、SEOの知識、SNS活用スキル、データ分析能力、オンライン広告、コンテンツ作成能力などを学んでおきましょう。
また、チームで作業することが多いので、コミュニケーション力も求められます。
⑧動画クリエイター
動画クリエイターとは
YouTubeなどの動画コンテンツを企画、撮影、編集する職種
スマホの普及や通信環境の高速化により、動画コンテンツが身近になった近年では、動画クリエイターの職種も需要が伸びると予想されます。
業務は多岐にわたり、動画の企画や撮影、編集に公開まで対応することが一般的です。制作する動画には、企業のCMや商品の使い方を紹介する動画、YouTubeチャンネルの動画など、さまざまな動画があります。
そして動画制作をする際には、企画力や撮影した動画の編集スキル、視聴者の心をつかむセンスが必要になります。AIによる動画編集技術も進化していますが、人の心を動かす動画を作るには、人ならではの感性が欠かせないのです。
企業に所属するだけでなく、フリーランスとして活躍することも可能なので、将来の選択肢に動画クリエイターを入れてみるのもおすすめします。
⑨Webディレクター
Webディレクターとは
Webサイト制作の責任者として企画や設計をおこない、運用を統括する職種
Webディレクターの仕事も今後需要が高まると考えられます。Webサイトは企業の顔であり、それらを統括できる人材が求められているからです。
Webディレクターは、クライアントの要望を聞き取り、それをもとにWebサイトの構成案を作成したり、制作のスケジュール管理をおこなったりします。
企業のホームページ(HP)を新しく作り直すプロジェクトがあれば、デザイナーやエンジニアなど、さまざまな専門スタッフをまとめて指示を出す役割を担うのです。
そのため、単にWebサイトを作る技術や知識だけでなく、人の心を動かすデザインを理解する感性や、関係者と円滑に仕事を進めるためのコミュニケーション能力も重要になります。
これらの能力は、AIには代替されにくいため、Webディレクターはプロジェクトの成功を左右する重要な役割として、今後も需要が拡大し続けるといえます。
Webディレクターに興味がある人は、以下の記事も読み進めてみて、仕事内容や就職するためのコツを把握しておきましょう。
未経験からWebディレクターを目指すなら、HTML、CSS、JavaScriptなどの基本的なWeb制作スキルやデザイン知識、プロジェクト管理能力を学んでおくと役立ちます。
コミュニケーション力や調整力も強みとして評価されやすいです。
⑩医者・看護師
医者・看護師とは
病気やけがの診断、治療、健康管理、患者のケアをおこなう職種
医療の専門家である医師と看護師は、健康を守る仕事であり、いつの時代も社会に必要とされています。そして、高齢化が進む現代社会では、需要はますます高まっているのです。
医師と看護師は病院だけでなく、地域の診療所や介護施設など、さまざまな場所で活躍しています。診療所では地域住民の健康相談に乗り、介護施設では高齢者の生活を支え、訪問看護をした場合は、自宅で療養する患者のケアまで対応することが求められるのです。
これらの仕事は、患者の表情や言葉から状態を把握したり、わずかな変化に気づいて臨機応変に対応したりと、人ならではの対応が重要になります。
そのため、人々が健康に暮らすためのサポートには、医師や看護師が必要になるので、今後も需要が伸び続けるのです。
同じ看護師でも、病院で働くだけではありません。クリニックや介護施設など、就職先もさまざまです。以下の記事では、志望動機のコツだけでなく、どのような場所で働く可能性があるのかも載っているため読み進め、働き方をイメージしてみましょう。
関連記事
新卒で看護師になるための志望動機の極意|避けたいNGワードも解説
看護師を目指す新卒学生が、よく頭を抱えるのが志望動機です。「看護師になりたい」という想いをうまく言語化できない学生は多いものです。この記事では、就活のプロが効果的な志望動機の作成方法をわかりやすく解説し、看護学生が自信を持って志望動機を作成できるようにサポートします。
記事を読む

⑪介護士
介護士とは
高齢者や障がい者の日常生活をサポートし、介護サービスを提供する職種
日本の高齢化社会により、介護士は今後も需要が増え続ける職種の代表格といえます。高齢化が進むにつれて、介護サービスを必要とする人は年々増えていく傾向にあるからです。
介護士のおもな仕事は、高齢者や障がいを持つ人の生活を支えることです。食事や入浴、着替えにトイレなど、身の回りのことのサポートをおこないます。また、利用者一人ひとりの状態に合わせて対応する必要があり、会話や交流を通して心のケアも大切です。
医師や看護師同様に、利用者の表情や体調を理解し、その人に合ったサポートが求められます。
しかし、高齢者が増え続ける一方で、介護士は人材が不足しているのも現状です。働き手が求められているため、介護士は今後も需要が伸び続けるとされています。
将来的に介護士を目指す人は、面接でどのような質問をされるのかを把握しておきましょう。面接で見られているポイントや面接通過のためのコツが載っているので参考になります。
- 介護士は低収入で仕事内容がキツイと聞いたことがありますが、将来性がある職種なのでしょうか。
捉え方によって将来性があるかどうかが変わる
2040年には高齢化率が35.3%(2023年時点で29.1%)になると予測されています。
それに伴い、2040年には約272万人(2020年度で約215万人)の介護職員数が必要とされているものの、現状と比較して約57万人不足することが予測されます。
高齢化が進むなか、介護職員のニーズはますます増加しています。
また、介護士の収入はほかと比べて少ないとされているものの、介護士報酬の改定や処遇改善支援補助金などの施策により、最近では徐々に賃金の改善が進んでいます。
正社員ならば昇給・昇格も定期的におこなわれているようです。
⑫保育士
保育士とは
子どもの保育や教育、保護者への子育て支援をおこなう職種
保育士は、子どもの成長をサポートする専門職として、今後も変わらず社会に必要とされる職種です。
保育士のおもな仕事は、預かった子どもの食事や着替え、トイレなどの基本的な生活のサポートです。また、遊びを通して心や体の成長を促したり、保護者からの子育ての相談に乗り、アドバイスしたりすることも保育士の業務に含まれます。
日々の業務のなかで、子どもの表情や行動から気持ちを読み取り、その子に合った言葉かけやかかわり方が重要になるのです。
さらに、近年では共働きの家庭も増え、保育施設に預ける家庭も増えています。そのため、保育士は幼い子どもの成長を支える存在として、今後も必要とされる職種です。
子供が好きという理由だけでは保育士の面接を突破するのは難しいものです。重視されるのは園とのマッチ度や人間性であるため、具体的に何が求められているのか以下の記事で理解を深めましょう。
関連記事
例文25選|保育士の自己PRが作れる5ステップと好印象のコツ
保育士の自己PRは希望する園に合った人物であると伝えることが重要です。この記事では、保育士の自己PRの書き方をキャリアコンサルタントと一緒に解説します。園の求める人物像にそった自己PRを作成し、選考を突破しましょう。
記事を読む
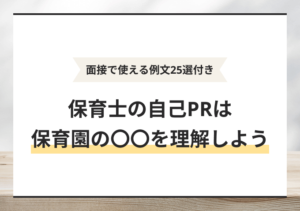
⑬理学療法士
理学療法士とは
運動療法や物理療法を用いて、身体機能の回復を支援する職種
理学療法士は、人の体と動きの専門家としてケガや病気で不自由になった体の機能を回復させる手伝いをする仕事です。
理学療法士の仕事は、患者一人ひとりの状態に合わせてリハビリ計画を立て、運動を指導することです。たとえば、骨折した人が再び歩けるように筋力をつけたり、関節の動きを良くしたりする運動を提案し指導します。
これらの仕事は、AIには代替できない人間にしかできない仕事です。患者の体を直接見て触って状態を確かめ、その人に合った運動を考え、励ましながらサポートしていきます。
人の体と動きを理解し、回復を助ける理学療法士は、高齢化社会の影響やスポーツ医療の発展により、需要が高まっている職種といえます。
理学療法士になるには、資格の取得だけでなく面接でどのように自身をアピールするかが重要になります。以下の記事では、理学療法士の志望動機の書き方を例文を交えて解説しているので読み進めてみましょう。
関連記事
例文14選! 理学療法士の志望動機は王道3パターンを押さえよう
身体機能の回復を図り、社会復帰を手助けするスペシャリストでもある理学療法士。その働き方は多様であり、志望動機の書き方について迷っている学生も多いのではないでしょうか。記事では、就職先に合わせた理学療法士のベストな志望動機の書き方を解説します。
記事を読む

⑭薬剤師
薬剤師とは
医薬品の調剤や薬の指導、医薬品情報の提供をおこなう職種
薬剤師は、薬の専門家として人々の健康と安全を守る責任のある職種です。病院や薬局で医師の処方箋に基づいて薬を調剤し、国家資格を持つ人にしかできない、専門性の高い仕事なのです。
働く場所は薬局に限らず、ドラッグストアで市販薬を選ぶ際の相談に乗ったり、健康に関するアドバイスをしたりします。ほかにも、製薬会社で新薬の開発に携わるケースもあります。
薬の飲み合わせによっては、体に悪い影響が出ることもあるため、患者が飲んでいるほかの薬や、アレルギーの有無などを確認することも重要です。
患者一人ひとりの状態に合わせて、薬の専門知識を使い、適切な判断やアドバイスをすることは人間にしかできないため薬剤師は今後も需要が伸びる職種とされています。
薬剤師に興味が出た人は以下の記事も読んでみましょう。働く場所ややりがい、志望動機作成のコツが載っているので、参考にし就活に役立ててください。
関連記事
薬剤師の志望動機はトレンドで差別化|他学生と被らない3つのコツ
薬剤師の志望動機は志望する職場の特徴で大きく変わりますが、そのうえで差別化するにはトレンドを押さえられているかが重要です。この記事では、キャリアコンサルタントとともに薬剤師の志望動機の書き方と人と被らないコツを紹介します。
記事を読む

⑮カウンセラー
カウンセラーとは
悩みや問題を抱える人の相談に乗り、心理的な支援をおこなう職種
カウンセラーは、人の心に寄り添い心の健康をサポートする仕事であるため、今後も変わらず需要が安定する職種とされています。心のケアはAIには代替できない、人間にしかできない仕事といえるのです。
おもな仕事内容は、相談に来た人の話にじっくりと耳を傾け、気持ちを理解することです。抱えている問題の原因を探り、一緒に解決策を考え、相談者が自分らしく生きていけるようにサポートします。
カウンセラーは、人の表情や言葉のニュアンスから、心の状態を読み取り、信頼関係を築きあげなければなりません。信頼関係を築き上げることで、相手とも打ち解け、相談しやすい環境を作り上げられるのです。
このように、人の心に寄り添い、心の健康をサポートするカウンセラーは、社会にとってなくてはならない存在であり、今後も需要が伸びると予想されます。
そもそもカウンセラーに自身が向いているのか判断ができない人は、以下の記事を読んでみましょう。向いている人の特徴を解説していて参考になります。
関連記事
心理カウンセラーに向いている人の6つの特徴を現役のプロが解説!
この記事では、心理カウンセラーに向いている人の特徴6選をキャリアコンサルタントや心理資格所持者とともに紹介しています。心理カウンセラーならではの魅力や仕事内容を解説しているので、これから目指したいと考えている人はぜひ参考にしてください。
記事を読む

カウンセラーの働き方は、企業に属したり副業や独立したりと多彩です。ほかのスキルと結びつけることによって応用もききます。
また勉強方法も、公認心理士などの国家資格、臨床心理士などの民間資格、独学など様々です。
⑯コンサルタント
コンサルタントとは
企業や組織の課題解決を支援し、経営戦略などを提案しアドバイスする職種
企業が抱える課題が複雑化する現代において、コンサルタントの重要性は高まっています。企業ごとに異なる状況を理解し、最適な解決策を提案するには、幅広い知識や経験、コミュニケーション能力が必要になるのです。
コンサルタントは、経営戦略やIT、人事に財務など、さまざまな分野で活躍します。企業の経営状況を分析し課題を見つけ、解決策を提案し実行することがおもな仕事になります。
企業の内情を理解し、社員と信頼関係を築き、その企業に合った解決策を共に考えることは、AIでは代替が難しく人間にしかできないことなのです。
企業の成長をサポートするコンサルタントは、今後もあらゆる業界で必要な存在になっていくといえます。
ITコンサルタントは、IT技術の成長に伴い需要が伸びてきている職種です。興味がある人は、以下の記事を読み進めましょう。仕事内容や求められるスキルが載っていて参考になります。
一般的に20~30代半ばまででしたら、未経験でもコンサルタントに転職できる可能性があります。
この仕事には顧客の課題解決のために深い洞察力が求められるほか、担当分野への専門的な知識だけではなく、コミュニケーション力や問題解決能力なども必要です。
⑰マネジメント職
マネジメント職とは
組織やチームの目標達成に向けて、人材や資源を管理・統括する職種
企業が目標を達成し成長し続けるためには、チームをまとめ引っ張っていけるマネジメント職が必要です。企業は、どのような業務でもチームで協力して取り組むことが多く、それぞれのメンバーの能力を最大限に活かし、成果を上げることが求められます。
新商品を開発するプロジェクトを例に挙げると、商品の企画やデザイン、製造から販売まで、さまざまな部署と連携して業務を進める必要があります。
マネジメント職は、それぞれの担当者の進捗状況を確認し、問題があれば解決策を考え、計画通りにプロジェクトが進むように調整を進めなければなりません。
ときにはメンバーの意見を聞き、やる気を引き出しチーム全体の力を高めることも重要な役割になるのです。
このように、チームをまとめ目標達成に導くマネジメント職は、AIには代替できず、人間ならではの対応が必要な職種です。
- 転職でマネジメント職に就くイメージが湧きません。実際は可能なのでしょうか
可能だが経験を段階的に踏むとより確実に目指せる
若い人でも転職でマネジメント職に就くケースは、実際に何度も見てきました。決して不可能ではありませんが、これまでのスキルや経験、前職での立場が大きく影響します。
特に、プロジェクトリーダーやチームリーダーとしての実績があると評価されやすいと感じます。
もし経験が不足している場合は、まずはサブリーダーやアシスタントマネージャーとして経験を積み、段階的にキャリアアップを目指すのも一つの方法です。
すぐに無理だと諦めずに、興味があるなら実績を積み重ねてチャレンジしてみましょう。
⑱建設業
建設業とは
建築物やインフラの建設、改修、解体などをおこなう職種
私たちの生活を支える建物やインフラを作る建設業は、いつの時代も必要になり、今後も安定した需要が見込まれます。
人が生活するうえで、住む場所や働く場所、移動するための道路や橋などは必要不可欠であり、これらの建設や維持をおこなう建設業は景気の影響を受けにくく、常に一定のニーズがあります。
たとえば、人口が増加している地域では、新しい住宅や学校、病院などの建設が必要です。ほかにも、道路や橋、トンネルなどのインフラは、古くなると補修や作り直しが必要になり、建設業の仕事はなくなりにくいといえます。
人々の安全で快適な暮らしを支える建設業は、社会にとってなくてはならない仕事であり、今後もその重要性は変わらないのです。
建設業界と言われても詳しい全貌を把握できていない人もいるのではないでしょうか。以下の記事では、建設業界の動向や就職のポイントが載っているので読み進め理解を深めましょう。
建設業界
建設業界の全貌がわかる! 課題・動向から仕事内容まで徹底解説
ゼネコン
ゼネコンとは? 建設業界の動向や就職のポイントまで徹底解説
⑲農業や漁業
農業や漁業とは
農作物の栽培や家畜の飼育、水産物の漁獲や養殖をおこなう職種
私たちの食を支える農業や漁業は、新しい技術を取り入れ大きく変化しています。そして、この変化が、農業や漁業を将来性があり需要の伸びる職種にしているのです。
農業では、ドローンを使って広い畑で農薬を散布したり、温度や湿度を測るセンサーを使って、作物が良く育つ環境を作ったりしています。
漁業では、魚群探知機を使って魚の群れを見つけたり、コンピューターで管理された生け簀で魚を育てたりすることが可能です。
上記のような作業の効率化にはIT技術が欠かせず、今後も新しい技術を導入することで、効率よく安定して食料を生産しやすくなります。
食料を安定して確保し、安全な食を確保するためにも、農業や漁業は生活を支える重要な職種です。
⑳通訳・翻訳家
通訳・翻訳家とは
異なる言語を話す人々のコミュニケーションを支援する職種
AI翻訳が進化する現代でも、言葉のプロである通訳と翻訳家の仕事は、今後も需要が伸びると予想されます。
通訳は、国際会議や外国人旅行者を相手に、言葉を別言語に訳すのが仕事です。翻訳家は、本や書類、Webサイトなどの文章を別言語に訳す業務を担っているのです。
言葉にはAI翻訳では完全な翻訳が難しい部分があります。また、言葉の微妙なニュアンス、文化や習慣の違いを理解し、相手に正しく分かりやすく伝えなければいけない場面もあります。
たとえば、同じ単語でも国や地域で意味が異なる場合や、ジョークなど文脈で意味が変わる表現は、AIでは正確に翻訳することは難しいのです。
このように、通訳と翻訳家は語学力に加え、異文化理解やコミュニケーション能力を活かして活躍するため、AIに代替されにくい職種だといえます。
- 需要が高いとされる職種のなかで、やりがいと感じやすい仕事はどれになるのでしょうか
やりがいを感じやすい仕事は人それぞれ
需要が高いとされる職種のなかでも、やりがいポイントは仕事によって違い、やりがいを感じる部分も人によって変わります。
そのために必要なのは、自己分析と企業分析です。
自分が何に対してやりがいを感じるのかを自己分析で明確にし、その仕事ではどのようなときにやりがいを感じる人が多いのかを企業分析で調べます。
まず自己分析から始め、自分に合った仕事を見つけましょう。そこである程度選択肢を絞ってから、業界分析や企業分析をしていくと良いでしょう。
市場の将来性も見極めよう! これからも需要が伸びる業界6選
需要が増減する仕事にどのようなものがあるかを把握した後は、具体的にどの業界が将来性が高いのかも確認しておきましょう。
業界の状況を知ることで、キャリアの方向性を決める際の判断材料を増やすことができ、自分に合った需要が増える仕事も見つけやすくなります。
この章では、これからも需要が伸びると予測される6つの業界を紹介します。各業界がなぜ成長し需要が伸びるとされるのかを理解しながら読み進め、自身の興味や適性に合っているかを判断してみてください。
医療・介護業界
医療・介護業界とは
人々の健康を守り、病気の治療や高齢者などの生活を支える業界
医療や介護業界は、今後も確実に需要が伸び続けると予測されています。日本は高齢化が進んでいて、医療や介護サービスの必要性が高まっているからです。
高齢者の人口が増えた場合、医療や介護サービスを必要とする人が増えていきます。医療機関での受診や、在宅での介護サービス、介護施設の利用が増加することは避けられません。
また、近年では健康に対する意識の高まりから、病気の予防や健康維持に関心を持つ人も少なくありません。定期的な健康診断や生活習慣病予防の運動指導、栄養相談などは医療や介護業界が担う重要な役割なのです。
そのため、病院や施設で働く医師や看護師、介護士の人手が必要となり今後も需要が伸びていく傾向です。
医療業界の道に進みたいと考えた人は、以下の記事も読んでみましょう。働き方や就職先、求められる人材が載っているため、自身のキャリアビジョンと比較し就活に役立ててみてください。
IT業界
IT業界とは
インターネットを活用し、ソフトウェアやシステム構築などで、新しい価値を生み出す業界
近年、社会全体のデジタル化が進んでいて、IT技術を活用した分野が増えているため、IT業界は今後も需要が伸びると予想されます。
たとえば、一部の企業では業務効率化や生産性向上のために、クラウドサービスやAIを活用したシステム導入が進んでいます。日常生活で利用するテレビやエアコンには、ネットを介して操作する機能が追加され、こうした技術にもITが関係しているのです。
そのため、デジタル化の流れにはIT技術が欠かせず、扱えるプログラマーやシステムエンジニアなどの技術者の需要は高まってきています。
このようにIT技術は、ビジネスと日常生活の両方において必要な存在となっているので、IT業界は新しい技術やサービスが生まれる分野として、今後も安定した成長が期待できます。
IT業界に興味が出た人は以下の記事も読み、具体的な企業も把握してみましょう。ランキング形式で紹介しているので、興味のある企業に出会うために役立ててみてください。
関連記事
IT業界の企業ランキングを徹底解剖! 内定を勝ち取るコツも紹介
キャリアコンサルタントとともに、売上、年収、働きがいなど項目別でIT業界の企業ランキングを紹介しています。そして、有名なIT企業に入社するための方法やコツなども解説しています。
記事を読む

- 未経験でもIT業界への転職は可能なのでしょうか
必要なスキルを身に付けることで未経験でも転職は可能
IT業界と言っても職種によって変わります。エンジニア、マーケティングへの転職の場合は実務経験が必要です。
そのため、コンピューターの操作ができることはもちろんのこと、ネットワークの知識も重要になります。
プログラミング言語の基礎を学ぶことでさらなる道が開けるかもしれません。
一方、営業、ITコンサルタントの場合は、コミュニケーション力・プレゼンテーション力・問題解決能力などが求められますが、これはほかの業界でも活かせて、前職の経験やスキルが活かせる部分でもあります。
どの業界でも転職に際しては新しい知識を積極的に学ぶ姿勢が求められます。進化の速いIT業界では、そのような姿勢が非常に評価されます。
半導体業界
半導体業界とは
電子機器に必要な半導体の設計・製造・販売をおこなう業界
半導体業界も、今後需要が伸び続けると予想される業界の一つです。スマートフォンをはじめとする私たちが日常的に利用する電子機器には、ほぼすべてと言って良いほど半導体が利用されているため、半導体そのものの需要が高まっているからです。
スマートフォンやパソコンといった身近な製品はもちろん、自動車の自動運転技術にも半導体は使用され、半導体の需要が伸びています。こうしたデジタル機器やAI技術の普及により、半導体の需要は世界的に急増しているのです。
半導体業界ではこの需要に対応するため、半導体製造工場の新設や生産強化の動きが進められていて、設計エンジニアや製造技術者、品質管理の専門家など、さまざまな人材が必要とされています。
このように、半導体はデジタル社会を支えるには必要不可欠な部品であるため、今後も安定した需要が見込まれる業界といえるのです。
普段耳にする半導体のワードですが、詳しく意味を知らない人もいるのではないでしょうか。以下の記事では、半導体そのものの説明だけでなく業界の現状や将来性、仕事内容まで解説しているので参考にしてください。
関連記事
半導体業界とは? 現状や将来性・仕事内容で見る6つの働き方を解説
この記事では、半導体業界について調べている人に向けて、半導体の意味や業界の実態を解説しています。キャリアコンサルタントとともに、半導体業界で働くメリットとデメリットや、より深く知る方法も説明するので、就活の選択肢に半導体業界を入れるかどうか悩んでいる人は参考にしてください。
記事を読む

教育業界
教育業界とは
学校教育や塾、オンライン教育などで人々の学びを支える業界
学校や習い事など、人が成長するうえで学びは常に必要とされるため、教育業界はこれからも需要が安定して続くと考えられる業界です。
近年では、従来の学校教育に加え、インターネットを活用した学習サービスやスマホのアプリを使った勉強法など教育の形もさまざまです。
そのため、教員や塾講師だけでなく教育用の動画や教材を作る仕事や、オンライン学習のシステムを開発する技術者などの職種も増えてきています。
また、教育現場では、生徒の個性や状況に合わせた指導や進路相談など、人ならではのサポートも重要です。
このように教育業界は、人々の学びを支える土台として、社会の変化に合わせて形を変えながらも、今後も安定した需要が期待できる分野といえます。
教育業は、一つの会社に留まらずに多様な働き方ができるのが特徴です。
たとえば、副業として英語や音楽などを教える、SNSなどで情報発信やコンサルをする、定年退職後に経験を伝える、といった働き方もあります。
インフラ業界
インフラ業界とは
電気やガス、水道に交通など社会のライフラインを支える業界
社会活動や日常生活に不可欠なライフラインを支えるインフラ業界も、今後需要が伸びる業界の一つとして挙げられます。経済状況の影響を受けにくく、インフラは私たちが生きていくうえで常に必要とされているためです。
具体的には、電気やガス、水道などのインフラは家庭や企業の活動に必須であり、これらのサービスを維持・管理する仕事は常に必要とされています。鉄道や道路などの交通インフラも人や物の移動に欠かせないものです。
また、老朽化したインフラ設備の整備や交換、地震や台風などの自然災害に強い街づくりへの取り組みも進んでいます。これらの取り組みには、より安全で持続可能なインフラを構築するため最新技術の導入や、それを担う人材の確保が不可欠です。
このようにインフラ業界は、私たちの暮らしや経済活動の基盤を支えるため、需要が伸び続ける業界だといえます。
今後とも需要が伸び続けるインフラ業界ですが、業務内容や勤務形態などを理解しておかなければミスマッチをおこす可能性があります。以下の記事では、どのような業務をおこない、事前に把握しておいた方が良い事実が載っているので参考にしてください。
関連記事
「インフラ業界はやめとけ」は本当? 懸念点や適性まで徹底解説
インフラ業界はやめとけといわれることもありますが、メリットの多い魅力的な業界です。この記事ではインフラ業界で働くメリットや適性などについてキャリアコンサルタントとともに解説します。インフラ業界へ応募を検討している人はぜひ参考にしてください。
記事を読む

空間インフラをご存じでしょうか。公共施設や湾岸施設等の設備の維持管理がおもな仕事です。
国や自治体が管轄している仕事でもあるため、仕事内容が安定してます。バリアフリー化の促進や音声ガイダンスによる案内なども、空間インフラの仕事の一つです。
エンターテインメント業界
エンターテインメント業界とは
映画や音楽、ゲームにスポーツなどで、人々に娯楽を提供する業界
エンターテインメント業界は、生活水準の向上とともに質の高い娯楽を求める傾向が強まっているため、今後も需要が伸び続けると予想されています。
この業界の強みは、人間の創造性や感性が重要な役割を果たすことです。
AIが一部の制作過程を効率化できる一方で、人々の心を動かすコンテンツの企画や演出には人間ならではの発想や感性が不可欠なため、AIに完全に代替されることなく需要が伸びると考えられます。
また、VR(仮想現実)技術を活用した娯楽体験や、動画や音楽配信のサブスクリプションなど、コンテンツを届ける形も多様化しています。そのため、デジタルコンテンツの制作や運営にかかわる専門職も増えているのです。
このようにエンターテインメント業界は、新たな技術を受け入れ活用していくことで、新たな市場を生み出し続ける、将来性の高い業界だといえます。
今後も高齢者は増え続けることから、医療・介護業界は今後も安定して伸び続けることが予想されます。
普段の相談のなかでも介護事業所からの求人相談が多く、他業種からの転職者も多く流入している業界だと感じています。
将来性を知っておこう! 今後需要が低くなる仕事の3つの特徴
将来性を知っておこう! 今後需要が低くなる仕事の3つの特徴
- テクノロジーによる代替が容易である
- インターネットの普及で不要になる
- 市場の変化により需要が減少する
将来性のある仕事を選ぶためには、需要が増える仕事だけでなく、減少していく仕事の特徴も理解しておくことも大切です。
判断の基準を知っておくことで、将来的に不安定な職種に就く可能性が減り、自身のキャリアビジョンに合った仕事を選ぶ判断にも役立ちます。
この章では、今後需要が低くなると予測される仕事の3つの特徴を解説します。テクノロジーの進化や、市場の変化を受けやすいかどうかが需要減少を見極める基準になるため理解しておきましょう。
①テクノロジーによる代替が容易である
単調で繰り返しおこなわれる作業や、明確なルールに基づいた判断をおこなう業務は、テクノロジーによる代替が可能になり、今後需要が低くなると予想されます。こうした業務はAIやロボットの方が、人間より効率的で正確に処理できるためです。
身近な生活で例を挙げると、セルフレジの普及によりレジ係は減少傾向にあります。また、データ入力をおこなう事務職であれば、自動化ツールによって入力や処理が人の手を介さずおこなえるようになりました。
ほかにも、工場での製品組み立てや検品作業も、産業用ロボットの進化によって人の手から機械作業に変化しつつあるのです。
このように、決まったパターンで進められる仕事や高度なスキルを必要としない業務は、今後テクノロジーの発展によって置き換えられ、需要が減少する可能性が高いのです。
単純作業が中心の製造業やコールセンター業界は衰退が予想されています。
特に、定型業務やデータ処理を主とする職種はリスクが高いと個人的に感じています。人間ならではのクリエイティブや価値が重視される時代へとシフトしてくるのではないでしょうか。
②インターネットの普及で不要になる
インターネットやデジタル技術の普及により、対面する必要がなくネットで完結する業務は今後減少していく可能性があります。
たとえば、書店員は電子書籍の普及により店舗数が減り、需要が減ってきています。旅行代理店の窓口担当者もオンライン予約システムの発達で、店頭に行く必要がなく減少していく傾向です。
さらに、CDやDVDショップのスタッフも、音楽や映像のストリーミングサービスにより、不要になる可能性があるのです。
このように、対面でのやり取りが必要ではなくなり、インターネット上でのサービスに移行できる業種は将来的に需要が減少していく傾向にあるといえます。
たしかに、ネットの普及で不要になった業務があるのは事実です。しかし、インターネットを使った在宅の仕事も増えているため、以下の記事も読んでみて仕事の選択肢を広げてみてください。
関連記事
インターネットを使った在宅の仕事16選|探し方や準備を徹底解説
在宅で仕事をしたいと考えている人の中には、どうしたら在宅で仕事ができるようになるか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。在宅で仕事をするためには、パソコンとインターネットの接続環境があれば誰でもおこなうことができます。 […]
記事を読む

③市場の変化により需要が減少する
社会のニーズや消費者の好みの変化によって、一部の職種は今後需要が減少していく傾向にあります。これは、人々のライフスタイルや価値観の変化、テクノロジーの進化に伴う消費行動の変化が大きく影響しているのです。
具体的には、タクシードライバーは配車アプリの普及と自動運転技術の発展により、将来的には需要が減少する可能性があります。
また、ショッピングセンターや百貨店の販売員も、オンラインショッピングの拡大により、従来ほどの人員を必要としなくなるかもしれません。
このように、時代の流れやライフスタイルの変化に伴い、現在は当たり前の職種だとしても将来的に需要が減少する可能性があるのです。
転職活動を進める際には、志望する業界や職種が市場の変化を受けやすいか、サービスや業務がAIに置き換えられる可能性がないかを十分に検討することが大切です。
- 市場の変化を受けやすい仕事かどうかを見極める方法はあるのでしょうか
AIやデジタル化の影響を受けやすいかどうかは一つの判断基準になる
市場の変化を受けやすい仕事かどうかを見極めるためには、情報収集が非常に大切です。
特に、AI・デジタル化の影響を受けやすいかどうか、市場規模が縮小していないかどうか、価格競争が起きているかどうかなどで判断することができます。
また、現場で働いている人に社会人訪問をすることによって、よりリアルな声を聞くことができ、想像できなかった現実を知ることができます。
就活のプロに聞く! 需要が低い仕事に就いてしまうとどうなる?
ここまで、今後需要が増減する仕事の特徴を解説しました。しかし、需要が低くなる仕事の特徴は理解できたとしても、「今後需要が低い仕事に就いてしまったらどうなるのか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。
そこで、キャリアコンサルタントの若林さんに、需要が低い仕事に就いた場合、将来的にどのようなことが起きてしまうのかを聞いてみました。需要が低いことで起こりうるリスクや、就いてしまった後の解決策を聞き、転職活動に役立てていきましょう。
アドバイザーのリアル・アドバイス!リストラや配置転換などのリスクがある
将来的に需要が低下する職種に就いてしまった場合、まず企業側はコスト削減や効率化を図るため、人員削減や業務の自動化を進める可能性が高いです。
特に単純作業が中心の業界や職種では、AIやロボット導入によって業務が代替され、リストラや配置転換が避けられないケースもあるでしょう。
企業側は、リストラ以外にも異動や再教育プログラムの実施、スキルアップ支援などをおこない、従業員を守る努力をすることが考えられます。
特にDXを進める企業では、デジタルスキルを持つ社員を育成することで、業務効率化と人材活用を両立させようとする動きが出てきています。
しかし、全員が希望通りの職種に就けるとは限らないため、これからは自らがキャリア形成に取り組む必要があるのです。
将来性のあるスキルを身に付けて自分ならではの活躍の場を見つけよう
私たちができることとしては、将来性のあるスキルを身に付けるために、主体的にキャリアプランを考え、それに即した学習や資格取得などをおこなうことではないでしょうか。
自分の専門分野の深堀り、他分野の知識を増やすT字型人材を目指すなど、自分に合った方法で学び、活躍し続けることを願っています。
これから需要が増える仕事に転職するための4つのコツ
これから需要が増える仕事に転職するための4つのコツ
需要が伸びる業界や職種の説明を聞いたことで、自身の進みたい道が決まり、さっそく転職活動に動き出したい人もいるのではないでしょうか。また、進むべき道をじっくり検討したい人もいるはずです。
そこで、ここからは需要が増える仕事に転職するための4つのコツを紹介します。すぐに行動を起こす人も、将来に備えて準備をしたい人も活用できる内容なので、コツを実践して需要の増える仕事への転職を成功させるために役立ててみてください。
①強みや弱みを把握して自己PRや志望動機に活かす
需要が高まっている職種は応募者も多くなり、競争が激しくなる可能性があります。そのため、採用担当者の目に止まるためにも、自身の強みや弱みを的確に把握し、その職種に求められる人材像に合わせた自己PRや志望動機を作成することが重要です。
たとえば、ITエンジニアを目指す場合、単に「数学が得意です」という強みだけでなく、「学習意欲が高いので、プログラミングの習得も積極的におこないます」といった具体的な強みも示せると、技術革新の激しいIT業界で活躍できる人材だと評価されやすくなります。
弱みについては、克服までの過程や改善しようとした動きを示すことで、問題解決力や成長意欲のアピールにつながります。
需要が高い職種では即戦力も求められますが、成長意欲と自己分析力も同様に重視されるため、自身を客観的に把握して、自己PRや志望動機に活かしましょう。
強みや弱みを把握できたとしても、活かし方がわからない人もいるのではないでしょうか。以下の記事では、強みと弱みの活かし方やアピール方法が載っているので読み進め、自身をアピールできるようにしておきましょう。
強み
強み一覧付き|自分の強みが必ず見つかる方法9選とアピール方法
弱み
就活で使える弱み100選! 短所を悪印象なくプラスに見せる秘策
弱みをアピールする際は、そのまま伝えるのではなく、改善に向けた取り組みや成長をセットで伝えることが大切です。
たとえば、「計画性が課題でしたが、タスク管理ツールを活用しスケジュール管理を徹底することで改善を図っています」といった具体例を示すと、前向きな姿勢が伝わりやすく、好印象になります。
②興味がある仕事に必要なスキルを身に付けておく
企業によっては、即戦力となる人材を求めていることもあるため、興味のある仕事があれば必要なスキルを身に付けておきましょう。
もし、ITエンジニアに興味があれば、プログラミングの勉強をしてみましょう。Webデザイナーであれば、デザインソフトの使い方を学ぶのがおすすめです。
これらのスキルは、本や動画を使って独学で身に付けることが可能です。オンライン講座を受講してみるのも良いかもしれません。
もちろん、スキルによっては、習得するまでに時間がかかるものもありますが、必要なスキルを身に付けておくことで企業にとって魅力的な人材となり、転職活動を有利に進めることができるのです。
スキルを身に付けると言われても、何をやるべきかわからず迷ってしまう人は以下の記事を読んでみましょう。スキルの探し方や今からやるべき行動が書かれていて参考になります。
関連記事
転職したいけどスキルがない! 今からやるべきことや注意点を徹底解説
転職したいけどスキルがないと、就職先が見つからない不安から行動に移せない人もいるのではないでしょうか。この記事では、転職したいけどスキルがないときのやるべきことや注意点をキャリアコンサルタントと一緒に解説します。転職成功できる方法を理解しましょう。
記事を読む
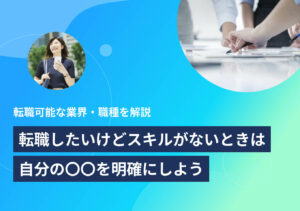
③市場の動向や最新トレンドの情報収集を忘れない
需要が増える仕事に転職するには、常に市場の動向や最新トレンドの情報を集めることが大切です。今注目されている仕事が、数年後も同じように求められているとは限らないからです。
たとえばIT業界は、技術革新のスピードが速く、数年で求められるスキルが大きく変わることがあります。
常に最新の情報を集めることで、AIやクラウドサービスなど、今後需要が伸びる可能性のある分野の変化に対応しやすくなり、自身に必要なスキルは何かを判断できるのです。
情報収集には、業界ニュースを読むことや専門家の発信をチェックすることが方法として挙げられます。
将来を見据えた準備をし、変化の激しい時代でも需要のある仕事を見つけやすくするためにも、情報収集は欠かさないようにしましょう。
市場の動向や最新トレンドを探るには、社会人訪問がオススメです。実際の現場で働いている人の生の声は、ネットではなかなか知ることのできない貴重な情報です。ぜひ積極的に社会人の声を聞くようにしましょう。
④仕事に必要な資格を取得しておく
仕事によっては、特定の資格を持っていることが、転職に有利になる場合があります。資格は、あなたがその仕事に必要な知識やスキルを持っていることを証明するものです。
具体的には、医師や看護師になるには、国家資格が必須です。また、経理の仕事では簿記の資格、不動産の仕事では宅地建物取引士の資格を持っていると、企業によっては評価が高まり転職で有利になります。
興味のある仕事に必要な資格を調べて、早めに取得することで将来の選択肢を広げましょう。
キャリアに役立てよう! 需要が増える仕事に活かせる資格
これから需要が増える仕事のなかには、特定の資格を持っていることで就職や転職が有利になったり、仕事の幅が広がったりするものがあります。需要が増える仕事に活かせる資格にはどのようなものがあるのか、以下を参考にしましょう。
| 資格 | 活かせる職種 |
|---|---|
| カラーコーディネーター検定試験 | ・デザイナー ・インテリアコーディネーター ・Webデザイナー ・商品企画 |
| 宅地建物取引士 | ・不動産営業 ・不動産管理 ・不動産コンサルタント |
| マネジメント検定 | マネジメント職 |
| 応用情報技術者試験 | ・ITエンジニア ・システムエンジニア ・プログラマー |
| 施工管理技術検定 | 建設業 |
| 税理士 | ・税理士事務所 ・会計事務所 ・経理 ・コンサルタント |
| 中小企業診断士試験 | ・コンサルタント ・マーケティング職 |
上記のように、需要が高くなる仕事に活かせる資格は数多くあり、取得することで将来の選択肢が広がります。
カラーコーディネーター検定試験は、企業で働くデザイナーだけでなく、フリーランスとして活躍する道が開かれます。税理士の資格があれば、税理士事務所だけでなく、一般企業の経理や財務部門で専門性を活かすことも可能なのです。
これらの資格は、あくまで一例です。ほかにもさまざまな資格があるため、自身が興味のある仕事、将来就きたい仕事には、どのような資格が役立つのかを調べ、計画的に学習を進めていきましょう。
資格にはさまざまな種類があり、何を取得すれば良いのか迷ってしまう人もいるのではないでしょうか。以下の記事では就活のプロがおすすめする資格が載っているので参考にしてください。
関連記事
これからの時代に役立つ資格23選! プロが注目する資格や選び方も
これからの時代に役立つ資格には、どんな特徴があるのでしょうか。この記事では、これからの時代に役立つ資格をキャリアコンサルタントとともに解説します。10年後やAI時代に生き残る資格の特徴・選び方や注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
記事を読む

- 何かほかにも需要が増える仕事に役立つ資格があるのでしょうか
介護福祉士や社会福祉士、社労士、税理士がおすすめ
私の個人的見解になりますが、介護福祉士や社会福祉士はおすすめです。
高齢化が進むなかで介護や福祉のニーズはますます拡大し、これらの資格を持つことで就職や転職に有利になると考えます。
介護以外の分野では、社労士(社会保険労務士)や税理士もおすすめです。労務管理や税務支援にかかわる専門職は、不況に強く、安定した需要が見込まれます。
専門知識を活かしてキャリアアップや独立を目指す方にとって、これらの資格は大きな武器となるでしょう。
覚えておこう! 需要が増える仕事を選ぶ際の注意点
覚えておこう! 需要が増える仕事を選ぶ際の注意点
- 選んだ仕事が必ず安定しているとは限らない
- 労働環境や適性を考慮しないとミスマッチの可能性がある
- 需要が増えていても給与や待遇が変化する可能性がある
需要が増える仕事に転職することは、将来性を考えるうえで重要ですが、単に需要があるという理由だけで判断するとミスマッチが起きる可能性があります。安定を求めて選んだ仕事が実は不安定だったり、自分に合わない労働環境だったりすることもあるのです。
この章では、需要が増える仕事を選ぶ際に注意すべき3つのポイントについて解説します。どのような仕事にも必ずリスクや考慮すべき点があることを理解し、将来のキャリア選択において偏った判断をしないために理解しておきましょう。
選んだ仕事が必ず安定しているとは限らない
需要が増えている仕事を選んだとしても、その仕事が将来にわたって必ず安定しているとは限りません。社会や経済の状況は常に変化していて、仕事の需要も変化する可能性があるのです。
たとえば、近年需要が急増している半導体業界は、世界経済や技術革新の影響を大きく受けやすい業界です。
AIやIT技術の進化により、半導体の需要は伸びることがありますが、技術革新のスピードが速いため、将来的に別の技術が主流になり、特定の半導体企業の需要が減少する可能性も考えられます。
このように、技術革新や社会の変化によって、仕事の需要は大きく変動する可能性があります。仕事を選ぶ際には、業界や職種の現状だけでなく、将来的な変化も予測しながら転職に動くようにしましょう。
そもそも安定した職業は存在するのか気になる人は、以下の記事も読んでおきましょう。安定した職業の見分け方と具体的な職種が載っているので、参考になります。
関連記事
11の職業|安定した職業の知っておくべき実情と就職する3つのコツ
「安定した職業に就きたい」「将来性のある仕事がしたい」という人に向けて、記事ではキャリアコンサルタントとともに安定した職業11選を紹介します。就職を決める前に知っておくべき情報も解説しているので、ぜひ仕事探しの参考にしてくださいね。
記事を読む

労働環境や適性を考慮しないとミスマッチの可能性がある
需要が増加している仕事でも、自身の適性や労働環境との相性を考慮しないと、ミスマッチが生じる恐れがあります。
医療業界を例に挙げると、需要が高い分野ではありますが、患者の命と向き合うプレッシャーや夜勤を含む不規則な勤務形態は念頭に置いておく必要があります。
また職種を選ぶ際は、ミスマッチを防ぐためにも自身の適性との比較が重要です。もしコミュニケーション能力が強みだとしても、一人での集中作業が求められるプログラマーの業務では能力を発揮しにくいといえます。
こうした労働環境や適性を考慮しておかなければ、入社後に自身の理想とのギャップで早期退職してしまうかもしれません。
仕事を選ぶ際には、実際に働いている人の話を聞いたり、インターンシップに参加したりして、仕事内容や職場の雰囲気をよく理解したうえで判断しましょう。
実際に働いている人の話を聞くには、インターンがおすすめです。働いてる人のリアルな声は、気になる業界の理解をより深められるからです。
以下の記事では、訪問先の企業で聞いてみると良い質問集や自己PRの例文が載っているため、参考にしましょう。
インターン
インターンは就活に不可欠? 8のメリットと選び方を詳細解説
需要が増えていても給与や待遇が変化する可能性がある
需要が増えている仕事であっても、将来的に給与や待遇が変化する可能性があることは念頭に置いておきましょう。社会の変化によって、企業や仕事の状況が変わるかもしれないのです。
たとえば、IT業界はエンジニアが高待遇で迎えられる傾向ですが、今後AIがさらに進化し、簡単なプログラミングをAIが自動でおこなうようになれば、エンジニアの仕事内容や給与が変わる可能性があります。
また、AIが人の表情や声のトーンを読み取れるようになれば、カウンセラーやコンサルタントの業務も一部が自動化され、働き方が変わるかもしれないのです。
このような変化に対応するには、自身の専門分野の知識を深めつつも、常に新しい知識やスキルを学び続ける必要があります。変化に柔軟に対応し、技術の進化に合わせて自分のスキルも更新し続けることが、長期的なキャリアの安定につながります。
医療・介護、保育士・教員などは給与や待遇が現在進行形で変化していきています。
実際に働いている現場の人たちからの声が政策に反映されています。またこれらの仕事は一般的に「きつい」仕事と認識されているものの、今後も必須の仕事になります。
需要が増える仕事に就くために気になるQ&Aも併せてチェック!
これまで、今後需要が伸びるとされる業界や職種、転職するためのコツを紹介しましたが、転職に動き出すにはまだ不安や疑問を感じている人もいるのではないでしょうか。
市場の流れを読むことや、スキルを伸ばすことが重要と理解はできても、興味のある職種の将来性がわからず迷っている人もいるかもしれません。
そこで、PORTキャリアに寄せられた悩みから、職種や業界の将来性に関する4つのQ&Aを紹介します。キャリアコンサルタントの具体的なアドバイスを参考にして、これまでの内容をより深く理解し、不安なく転職活動に挑めるようにしていきましょう。
これから需要が増える仕事は職種の将来性を見極めて就活を進めよう
これから需要が増える仕事かどうかの判断には、職種の将来性を見極める必要があります。AIに代替されることはないか、生活するうえで必要になるかなど、判断基準はさまざまですが、まずは人の手が必要な業務かどうかを考えてみてください。
人間にしか対応できない業務であれば、これからも需要が伸びる可能性が高いです。また、専門的な知識を得たり、資格を取ったりすることで需要が高い仕事に就きやすくなるので、興味のある職種があれば何が必要になるかを調べてみるのがおすすめです。
需要が高まる理由を理解し、今回紹介した転職のコツを実践して、自身の理想に合った転職先を見つけていきましょう。
アドバイザーからワンポイントアドバイス自分の強みを活かせる仕事を選ぶのが大前提
これから需要が増える仕事に就きたい・転職したいと思っている人には、自分の強みを活かせる仕事を選ぶこと、必要なスキルや資格を身に付けることが重要です。
需要がある仕事に就いても、その仕事に対するスキルや適正がなければ活躍できません。また、やりがいを感じないことも危険です。
そういった事態を防ぐためにも、自己分析が必要不可欠です。就活にしろ転職にしろ、自己分析をして強みや弱み、価値観を把握することで、最善の選択をすることができます。
世の中の変化に着いていけるよう学び続けて活躍できるようにしよう
そしてさらに、これから需要が増える仕事では学び続けることも大切です。世の中や社会は常に変わり続けているため、常に自分自身をアップデートし続けることも必要です。
現状維持は衰退であり、究極的な安定などありません。学び続けることを忘れないようにしましょう。
上記のためにも、焦らずに情報を集め、様々な人に相談することが成功への第一歩です。
社会人訪問をする、転職エージェントを活用する、キャリアコンサルタントに相談するなど、できることはたくさんあります。自分の可能性を広げるためにも、一歩ずつ前向きに行動していきましょう!
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

















3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
就活塾「我究館」副館長/キャリアコンサルタント
Hayato Yoshida〇東証一部上場の人材会社で入社2年半で支店長に抜擢。これまで3,000名以上のキャリアを支援。現在はベストセラー書籍「絶対内定」シリーズを監修する我究館で副館長として従事
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/西雄一教育研究所代表
Yuichi Nishi〇大学では就活に関するスキルを身に付けられる実践中心の授業を展開。また、講師として企業で新人や中堅社員に向けてコミュニケーション研修、キャリアコンサルティングをおこなっている
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/一般社団法人テツナグ代表理事
Hiromi Wakabayashi〇女性や学生向けのキャリア講座、行政主催の就職フェアでのキャリア相談に従事。また、ライター経歴を活かし、各種サイトでキャリアについて考えている人に向けた記事を監修
プロフィール詳細