この記事のまとめ
- 公務員試験に落ちても今後の道を冷静に選択しよう
- 公務員試験に落ちてからの就活では失敗を活かして行動することが鍵
- 民間就職を成功させる3つの手順と時期別のコツを紹介
毎年学生に人気の公務員。必死に勉強や面接対策をしたにもかかわらず、公務員試験に落ちてしまった人の中には、「公務員になることを諦めきれない」「これから民間企業に就職なんてできるのだろうか」と途方に暮れている人もいるかもしれません。「民間就職するなら何から始めたら良いのかわからない」と不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
公務員試験に落ちたからといって絶望する必要はなく、正しい振り返りと対策をすれば、納得いく企業に就職することは十分可能です。
この記事ではキャリアコンサルタントの吉田さん、古田さん、瀧本さんのアドバイスを交えつつ、公務員試験に落ちてから就活する方法や成功させるコツを解説します。
公務員試験に落ちてからどう行動して良いかわからない人や、今後の方向性を見失っている人はぜひ参考にしてみてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
1位:自己PR作成ツール
自己PRが思いつかない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
2位:自己PR例文100選
お手本になる自己PRをまとめました。書き方に悩む人、文章の質を高めたい人へ
3位:志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
4位:面接回答集60選
見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました
5位:逆質問例100選
面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています
【併せて活用したい!】
スキマ時間3分でできる就活診断ツール
①適職診断
たった30秒であなたが受けない方がいい仕事がわかります
②面接力診断
39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
公務員試験に落ちてからの就活でも大丈夫! 焦らず効率良く動こう
公務員試験に落ちてしまった場合、そのショックは大きいかもしれませんが、諦めることはありません。公務員試験への再挑戦や、民間企業への就職の道も残されています。自分にとっての最適解を模索し、焦らず効率良く行動することが重要です。
記事ではまず公務員試験に落ちたときにやってはいけない行動を説明し、試験に落ちた場合のおもな4つの道を解説するので、自分自身と向き合いながら取るべき行動を冷静に選択していきましょう。
後半では、公務員試験に落ちてから気持ちを切り替えるコツを就活のプロが解説します。さらに、公務員試験を受け続ける場合でも並行して就活するメリットや、公務員試験と民間就職の違いを解説するので、民間就職を確実に成功させる手順やコツを押さえておきましょう。
最後に公務員試験や就活で、よくある悩みにも答えているので併せてチェックし、納得のいく進路につなげてくださいね。
時間がない人におすすめ!
ツールを使えば、自己PRが3分で完成します
自己PRは就活において必ずといっていいほど必要になります。自己PRが曖昧なまま就活がうまくいかなかったという就活生は多くいます。
そこで活用したいのが「自己PR作成ツール」です。これを使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
簡単な質問に答えるだけで、強みが伝わる自己PRが作れます。
作成スタート【無料】
(リーダーシップが強みの場合)
夏以降も採用を続ける企業は多い! まずは絶望しなくて良いことを知ろう
公務員試験一本で頑張ってきた人が試験に落ちてしまった場合、すべてを失ったかのような感覚になってしまうかもしれません。いざ就活を始めるにしても「今から民間企業への就職は難しいのではないか」と考えて絶望してしまうかもしれません。
しかし秋以降も、春や夏の採用で不足した人員を補うために採用活動をしている企業も多くあり、優秀な人材を求めて特別な採用をおこなうケースもあります。公務員試験に落ちたとしても、民間に就職するチャンスは残っているため、諦める必要はないのです。
秋採用では、特に中小企業やベンチャー企業は積極的に採用をおこなう傾向があります。ただし、秋採用は春や夏に比べて企業数や採用枠は限られていて、競争が激しくなることが予想されるため、しっかり事前準備をして臨むことが大切です。
11月以降に採用を終了した企業が半数以上
実際、民間企業へ就職する場合、11月以降も選択肢は豊富にあるという調査結果も出ています。マイナビの2024年卒 企業新卒内定状況調査によると、採用活動を終了する時期を12月や年明けの3月としている企業は多く、11月以降も採用活動を継続する企業は全体の半数以上を占める55.5%という結果でした。
春夏の採用枠だけで人員が充足する企業の割合は半数程度にとどまっています。企業の採用の終了予定が後ろ倒しになっていることから、公務員試験に落ちてから民間就職を狙うことも十分可能だといえそうです。
公務員試験の後で民間就職をするなら、秋採用をおこなっている企業に絞った就活で、残された時間を有効に使い、効率良く動くことが鍵になります。
就活がいつまで続くのか不安な人は、以下の記事も併せてチェックしてみてください。
関連記事
就活はいつまで続く? 一般的な時期や長期化させない方法を解説
就活がいつまで続くのか不安な人は、まず就活の終了時期を押さえましょう。この記事では一般的な就活スケジュールを紹介します。また納得して就活を終わらせるために実施すべき対策をキャリアコンサルタントが解説しますので参考にしてください。
記事を読む

アドバイザーコメント
吉田 隼人
プロフィールを見る一度公務員試験に落ちても夢をかなえる方法はたくさんある
公務員試験に落ちてしまった場合、絶望感に駆られると思います。長い時間をかけて準備したものが無駄になってしまったことや、これから民間就活の対策をしないといけないという事実は、なかなか受け止めるのが難しいですよね。
まずは一回、しっかりとこの絶望をかみ締めましょう。絶望と向き合ったら、そこから這い上がりましょう。大丈夫です、まだ社会人生活は始まってすらいないので、ここから何とでもすることができます。
私が今まで担当してきた学生の例をいくつか紹介します。
民間就活に切り替えて何とか就職し、数年後に再度公務員試験に挑戦して公務員になった人がいました。就活のスタートが遅くても、今からしっかりと対策をすれば、いくらでも内定を獲得することが可能なのです。
また、その人は「民間を経たことでいろいろな世界を知ることができ、それが仕事の成果にもつながっているので、むしろ一度公務員試験に落ちて良かった」とまで言っていました。
また、一年休学をして、もう一度公務員試験にチャレンジをしたという人もいます。その人は、対策をするのが遅かったのが落ちた原因だったので、丸一年しっかりと対策をしました。また、滑り止めとして民間就活も同時並行し、結果として民間でも公務員でも内定を勝ち取りました。
挫折を自分の新たな可能性に気付くチャンスだととらえなおそう
このように、これまでサポートした学生たちも、一度挫折を経験することで、新たな可能性に気付いたりしました。就職活動は、自分を見つめ直し、成長する絶好の機会です。そのことを念頭に置いてここから這い上がっていきましょう。
コピペで使える自己PR文がかんたんに作れます
自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?ツールで実際に文章を作成してみてからブラッシュアップする方が効率的に受かりやすい自己PRを作成することができます。
「自己PR作成ツール」 を使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
簡単な質問に答えるだけで、強みが伝わる自己PRが作れます。
作成スタート【無料】
(リーダーシップが強みの場合)
公務員試験に落ちたときにやってはいけないこと
公務員試験に落ちたときにやってはいけないこと
- 自分を否定したり責めたりする
- 絶望して何もしない
- 手当たり次第に民間企業を受ける
公務員試験に落ちてしまった場合、途方に暮れてしまう気持ちもよくわかります。現実の自分と理想の自分とのギャップの差を埋めるのは簡単なことではありません。
しかし、いつまでも立ち止まっているのは得策ではありません。前に進むためにも、試験に落ちてしまった現実を受け止める必要があります。
その際、次のような行動をするのは避けましょう。ネガティブな感情の深みにはまってしまい、前進する妨げになってしまう可能性があります。
自分を否定したり責めたりする
過去の失敗を悔いる気持ちがあったとしても、失敗を繰り返し思い出して自分自身を否定したり、責めてしまったりするのは良くありません。「ああすれば良かった」「こうすべきだった」という過去の記憶や思考が頭の中をぐるぐると巡り、自分自身を苦しめることになります。
そのような反芻思考からは何も生まれず、結果を変えることはできません。反芻思考から脱するためには、現状を把握し、今の自分にとってベストな選択をすることが求められます。
完璧な選択ができるか不安になるかもしれませんが、現時点で完璧でなくても大丈夫です。まずは一歩踏み出すことが大切になります。失敗したことにとらわれ過ぎず、その経験を成功に変えられるよう違う視点を持ってみてください。
人には何かしら与えられた役目があると私は考えています。
望まない結果に直面したときは「これは自分に与えられた役目ではなく、ほかにするべき役目があるから縁が結ばれなかった」と考えて、次の目標への活動に切り替えるてみてはどうでしょう。
テンプレを活用すれば受かる自己PR文が作れます
自己PRのネタを決めても、それを裏付けるエピソードに悩む学生は多いです。しかし、特別なエピソードがなくても受かる自己PRを作ることはできます。
そこで紹介したいのが「自己PR作成ツール」です。自己PR作成ツールなら、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、分かりやすいテンプレであなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。
ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。
簡単な質問に答えるだけで、強みが伝わる自己PRが作れます。
自己PR作成ツールを試してみる【無料】
(リーダーシップが強みの場合)
絶望して何もしない
公務員試験に落ちてしまうと、それまで頑張ってきた努力がすべて無駄だったと絶望してしまう人もいるものです。しかし絶望感に浸って何もしないでいたら、残りわずかなチャンスも逃してしまいかねません。
まだ公務員試験に挑戦できる可能性が残っていたり、民間企業に就職を考えたりする場合も、時間が経つほど対策が不十分になり、難しくなってしまいます。冷静に周囲を見る余裕がなくなり、正しい判断もできなくなるかもしれません。
また、何もしない状態が続けば、動き出すまでに時間がかかってしまうものです。どんな事象にも良い面と悪い面があります。絶望の中でも希望は捨てずに、現実を受け入れて行動する勇気を持つことが大切です。
- 精一杯頑張ってきただけに、現実を受け止めきれません…。
自己分析をおこなってキャリアプランを見つめ直そう
公務員試験に不合格になってしまったことは大きなショックかもしれませんが、まだ多くの選択肢は残されています。
まず、自分が今後どのようなキャリアを描いていきたいかを見つめ直し、その軸に沿った就職活動を始めることが重要です。公務員には経験者採用枠もあるので、民間企業への就職が将来的に公務員試験へ再挑戦する際に有利に働くことも十分考えられます。
また、働きながら試験準備を進めることで、実務経験を積みながら社会人としての視野を広げることもできます。
いずれにせよ、まずは自己分析をおこない、自分に合った進路や企業を見つけることから始めましょう。そして気持ちを切り替え、前向きな姿勢で新たな挑戦に取り組むことが大切です。
手当たり次第に民間企業を受ける
公務員試験に落ちてから就活する場合、民間企業を志望している学生よりもスタートで出遅れてしまっている状態です。そのため、自己分析や企業研究を始めた段階で、周りは内定をもらって就活を終えていくことも珍しくありません。
しかし、そこで早く内定をもらおうと、焦りから志望度がそれほど高くない企業に応募することは避けましょう。そのような状況で入社を決めたとしても、後で後悔することになるからです。
内定をもらうのであれば、入社したいと思える企業を選ぶことが大切です。本気度は採用側にも伝わるため、いくら労力と時間をかけても成果に結びつかず、残念な結果に終わってしまう可能性もあります。準備を重ねたうえで、慎重に応募先を検討しましょう。
就職先を決めるうえでの注意点について以下の記事で解説しているので、併せてチェックしてみてください。
関連記事
就職先の決め方決定版|学生が見落としがちな視点と注意点を徹底解説
就職先の決め方は正しい「自己理解」と「企業理解」が重要です。これから就活を始める人と内定を持っている人に分けて就職先の決め方をキャリアコンサルタントが解説します。決め方の注意点も紹介しているので、後悔しない選択をするカギにしてください。
記事を読む

手当たり次第に選考を受けようとするほど焦っている人は、まず第三者に相談してみましょう。冷静さを失って闇雲に行動しても、成果につながらないことがほとんどです。
就活に詳しいキャリアコンサルタントや大学のキャリアセンターで現状について相談して、今後の戦略を立てるところから始めるのが一番の近道です。
自己PRが思いつかない人は、ChatGPTを活用して自己PRを完成させよう
ChatGPTを使った自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?
簡単な質問に答えていくだけでChatGPTが自動で魅力的な自己PRを作成します。
作った自己PRは選考で活用できるものになっているので、ぜひ活用して採用される自己PRを完成させましょう。
公務員試験に落ちた場合はどんな選択肢がある? おもな4つの道
公務員試験に落ちた場合はどんな選択肢がある? おもな4つの道
- まだ日程があれば再度公務員試験に挑戦する
- 民間企業への就職に切り替える
- 大学院への進学を検討する
- 就職浪人を見すえて公務員試験を受け続ける
ここまでで、公務員試験に落ちたとしてもそこで終わりではなく、その先に続く道があることがわかってきたかと思います。
しかし、いざ次の行動を起こしたくても、どうしたら良いのかわからない人もいますよね。公務員試験に落ちた場合は、今後どの方向に向かって進むべきか選択する必要があります。
ここでは、おもな4つの道を紹介するので、「自分は今後どうしていきたいのか」「どうするのがベストなのか」を明確にしてみてください。
①まだ日程があれば再度公務員試験に挑戦する
日程によっては、再度公務員試験に挑戦できる可能性もあります。
一般的に大学生や大卒者が受験する公務員試験は、一次試験が5~7月、二次試験が7~8月、最終合格発表が8~9月上旬に実施されることが多いです。しかし国家公務員や教養区分を採用するタイプの試験は秋受験と呼ばれていて、例年10月におこなわれます。
秋受験は「より優秀な学生の確保」「試験に落ちた学生や留学していた学生の採用」を狙っておこなわれることが多く、通常の筆記試験にはない科目が課せられているのが特徴です。
この秋受験で再度公務員試験に挑戦するのであれば、合格に向けて万全な準備をして臨みましょう。
公務員試験の秋受験は高卒程度と同じ日程で選考がおこなわれるので、SPIなどの筆記試験は少なくなり、教養試験が筆記試験の中心となります。このことから教養試験対策が重要となります。
また、論文も政策論文ではなく、作文に変わるので注意が必要です。
公務員を目指す理由をうまく伝えたい人は、以下の記事が参考になります。
関連記事
公務員を目指す理由が必ず伝わるエントリーシートの書き方|12例文
公務員のエントリーシートは、すべての項目を通じて「なぜ公務員になりたいのか」がわかるように書くことが重要です。記事ではキャリアコンサルタントと一緒に、頻出の志望動機と自己PRを取り上げ、公務員に特化したエントリーシートの書き方を解説しています。
記事を読む

公務員試験で効果的な自己PRのコツを知りたい人は、以下の記事で解説しているので実践してみてください。
関連記事
公務員の自己PRのコツは? 評価される作り方を例文付きで解説
公務員の自己PRの方法についてキャリアコンサルタントと解説します。公務員試験の自己PRを作成するうえで欠かせない基本情報も含めて解説するので、しっかりチェックして公務員の選考を突破しましょう。
記事を読む

所要時間はたったの3分!
受けない方がいい職業を診断しよう
就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。
就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。
- 自分に合う職業がわからない人
- 入社後のミスマッチを避けたい人
- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人
②民間企業への就職に切り替える
公務員から民間企業への就職に転向する選択肢もあります。民間の場合は二次募集がある企業もあるため、公務員試験に落ちてしまった後でも選考を受けることは可能です。
ただし、最初から民間企業を志望している学生からは遅れていることは事実です。のんびり構えていると、応募を締め切ってしまう企業も増えてきます。ゆっくり対策をしていると後悔につながりかねないため、早めに民間就職に切り替えて、効率的な就活対策をおこなうことが大切です。具体的な方法については後ほど詳しく解説します。
また、春までの選考に比べて夏以降は採用枠も少なくなっていくため、倍率はその分高くなります。公務員と民間企業では対策が異なる部分も多いため、この記事を参考にして適切な選考対策のポイントをしっかり押さえましょう。
就活を始める際は、具体的なやり方を解説している以下の記事も役立つので、併せてチェックしてみてください。
③大学院への進学を検討する
公務員試験に落ちてしまった場合、大学院へ進学するのも選択肢の一つです。大学院に進学すれば就職までの猶予ができ、あらためて自分の進路について考えることができます。
大学院に進学した場合でも、大学院に通いながら公務員試験を再受験できます。公務員浪人した場合は、面接で空白期間を指摘されることがありますが、大学院に進学した場合は在学期間となるため、問われる心配はありません。
また、仮に公務員試験に再挑戦して落ちてしまった場合も、大学院で何らかの専門性やスキルが身に付いているはずです。再度自分の進路を考え直すことで、新たな道が見つかるかもしれません。ただし、学費がかかること、社会に出るのが数年遅れることは考慮すべき点です。
大学院は研究や高度な能力を身に付ける場所であって、就活がうまくいかなかった人の保険ではありません。
大学院に進学した場合、研究に多大な時間を費やす必要があります。学部時代に時間があったにもかかわらず公務員試験に落ちた人が、大学院に進学して公務員試験に受かる可能性がどれほどあるのか冷静に考えてみましょう。
④就職浪人を見すえて公務員試験を受け続ける
公務員試験に落ちてしまったら、就職浪人をする選択肢もあります。その場合は、「いつまで」と具体的な期限を設けて、合格から逆算したスケジュールを立てて自己管理することが大切です。
いつか受かるだろうと安易な気持ちで受かるほど、公務員試験は決して簡単なものではありません。必ず合格するという決意と、継続して勉強する自己コントロール力が必要です。
また、3年以上就職浪人した場合は、新卒扱いではなくなり、新卒や第二新卒の求人への応募が基本的にできなくなるため注意しましょう。かといって、即戦力が求められる中途採用枠も難易度が高くなるため、就職浪人する場合は、あらかじめ期限を設けることをおすすめします。
確実に次の年での公務員合格を目指すなら、独学で勉強するよりも、受験予備校や通学講座、通信講座などのノウハウを取り入れた対策をするのが効果的です。
- 就職浪人になった後で、独学で公務員試験に再挑戦するのは難しいでしょうか?
公務員試験への再挑戦は計画管理とモチベーション維持が重要
就職浪人後に独学で公務員試験に再挑戦することは十分に可能ですが、いくつかの点に注意が必要です。
まず、専門科目のある公務員試験を受験する場合は、多くの時間と労力を要するため、強い意志と計画的な勉強が求められます。独学は自己管理が鍵となり、特に筆記試験や面接の準備には十分な時間を確保することが重要です。
また、年齢制限や試験の難易度にも注意が必要です。再挑戦する際には、前回の失敗を分析し、効率的な勉強方法を取り入れることが成功の鍵となります。必要であれば、予備校を利用することも検討してください。
大切なのは、再挑戦に向けた具体的なスケジュールを立て、モチベーションを維持しながら取り組むことです。
就職浪人をして公務員を目指そうと考えている人は、こちらの記事もあわせて参考にしてみましょう。メリット・デメリットについて詳しく紹介していますよ。
関連記事
就職浪人で人生終了? 公務員合格を目指す心得と浪人失敗の理由を解説
就職せずに浪人することは、勉強時間が確保できて受験対策も抜かりなくおこなえるため、効率的に公務員試験合格を目指せる方法です。この記事ではキャリアアドバイザーとともに、浪人しても試験に合格しやすい人の特徴や、目指す際の心得について解説します。
記事を読む

公務員試験に落ちてしまった場合の選択肢については以下の記事でも解説しています。自分に合った進路を見つける際の参考にしてみてくださいね。
関連記事
公務員試験に全落ちしたときの 4つの選択肢|民間就活成功の秘訣も
公務員試験に全落ちしたときにすべきことや4つの選択肢を解説。民間企業の就活をする際の進め方や成功の秘訣もキャリアコンサルタントとともに解説します。全落ちしないためのポイントも紹介するので、全落ちしないための方法を知りたい人も必読です。
記事を読む

自己PRで悩んだらまずは作成ツールを使ってみよう!
「自己PRで伝えたいことはあるのに、言葉にできない」そんな悩みがある方には「自己PR作成ツール>」が強い味方になってくれます。
表現に悩んでいても、AIがあなたの考えを汲み取り、わかりやすく効果的なPR文にまとめてくれます。
ぜひ効率的に自己PRを仕上げ、選考の準備を整えましょう。
公務員を諦めるべきか迷ったら? 後悔しないためにすべきこと
公務員を諦めるべきか迷ったら? 後悔しないためにすべきこと
- 自分が本当にやりたいことは何かを考える
- 公務員として働いている人の話を聞く
- 期限を決めて再挑戦する
公務員試験に落ちた場合、諦めるべきか再挑戦するべきか悩む人もいますよね。その際意識したいのが、公務員試験に合格して公務員になることがゴールではないということです。
公務員として自分に何ができるのか、どのように社会貢献できるのかといったことまでイメージする必要があります。たとえば「公務員は安定した職だから」という理由だけで、漫然と公務員を目指しているのであれば一度考え直した方が良いです。
ここでは、公務員を諦めるべきか迷ったときに後悔しないためにすべき行動を紹介するので、立ち止まって考えてみてください。
自分が本当にやりたいことは何かを考える
公務員を諦めるべきか迷ったときは、原点に立ち返ってみることも大切です。「なぜ公務員になりたいのか」「本当にやりたいことは何か」を自問自答してみてください。
「安定して働けるから」といった理由では、公務員を目指す意識としては低く、理由も曖昧です。公務員は地域社会を良くすることが仕事であり、行政や住民の暮らしを改善するために常に考えたり、働きかけをしたりする姿勢が求められます。
公務員になりたい明確な理由がなければ、試験勉強にも集中できず、次年度に試験を受けても成果が得られないかもしれません。
自分は将来どのようなことをしたいのか、どのようなことで社会貢献できるのか、この機会にじっくり考え直してみましょう。
以下の記事では、公務員になりたい理由の最適な回答と言語化のコツについて解説しているので、参考にしてみてください。
関連記事
例文あり|公務員になりたい理由の最適な回答と言語化のコツを解説
当記事では、公務員になりたい理由を明確にするための方法を紹介しています。キャリアコンサルタントが効果的にアピールできるアドバイスもしているため、公務員になりたい理由を上手にまとめられない人は参考にしましょう。
記事を読む

公務員以外にやりたいことが見つからない場合、「もし無事に公務員になっていたら何をしていたか」を想像してみましょう。
それは公務員でなければできないことですか? 人は想像できないことは実現できないと言います。まずは想像するところから始めててください。
公務員として働いている人の話を聞く
諦めずに公務員を目指す道に迷いがある場合は、公務員として働いている人に「公務員を目指した理由」や「仕事のやりがい」などを聞いてみましょう。併せて就業の実態や大変な点といったマイナス面を聞いておくことで、マイナス要素を含めて公務員になる道を目指すべきか、冷静に判断できます。
また、実際に働いている人の人物像から、どのような人が現場で求められているのかが見えてくるかもしれません。仕事環境や働き方について、現場のリアルな話を聞くことで、曖昧だったイメージも明確になっていくはずです。
公務員として働く姿を具体化することで、自分が本当にやりたいことなのか、合っている道なのかがわかり、それまでの迷いが吹っ切れて、目的意識を持って次の行動につなげられます。
OBやOGに話を聞く際は、どのような質問をするかも重要です。具体的にどのような質問をすれば良いかわからない人は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事
OB・OG訪問は質問選びが鍵! おすすめ質問100選を紹介
OB・OG訪問は質問選びが非常に重要です。事前に聞きたいことを準備しておきましょう。この記事ではOB・OG訪問でのマナーや注意点をキャリアコンサルタントが解説します。また、OB・OG訪問でおすすめの質問100選も併せて紹介します。
記事を読む

公務員の人の話を就活に活かすのであれば、公務員として培った組織的な思考や政策に関する理解、周りの人とのコミュニケーションの取り方を意識して聞くと良いです。
公務員試験では政策に関する関心と理解、計画性や調整力といったスキルが評価されやすいので、自分がどのように貢献できるかを考えましょう。
期限を決めて再挑戦する
公務員試験一本で頑張ってきた人は、公務員になることを諦めきれないかもしれません。その場合、未練を残して諦めるよりも、再度挑戦をして悔いを残さないことも大切です。
ただし、惰性で挑戦し続けることは避けましょう。公務員試験は種類ごとに受験の年齢制限が設けられていて、年齢が上がるにつれて、民間企業への就職が難しくなるためです。
再挑戦するのなら「この1年で合格する」という強い意志を持って、取り組むことが重要です。「今年落ちてもまた来年がある」という気持ちでいると、十分な準備ができず、試験を突破することは難しくなってしまいます。
本当に公務員になりたいのか、今一度、自己分析をしてみましょう。公務員試験は社会人になってからでも受けられるため、新卒のタイミングで再挑戦するメリットはあまり多くありません。
再挑戦には時間も労力もかかるため、自分の本気度を確かめるためにも自己分析をもう一度おこないましょう。
就活のプロに聞いた! 公務員に落ちてからうまく気持ちを切り替えるコツ
公務員試験に落ちてしまった後は、ショックで落ち込んでしまい、なかなか気持ちを切り替えられない人も多いですよね。しかし、自分はどの道に進むべきかを選択し、そのためにはどのような行動を取るべきか判断していく必要があります。
そこで就活支援のプロである古田さんに、公務員試験に落ちた際の気持ちの切り替え方について聞いてみました。落ち込んでしまい立ち直れずにいる人や、次の行動ができずに立ち止まっている人は、ぜひ参考にしてみてください。
アドバイザーコメント
古田 文子
プロフィールを見る公務員になりたくともそれが自分に向いているとは限らない
私のところに来た相談者の中で、5回も公務員試験にトライし続けている人がいました。その人は6回目を受けるかどうか悩んでいて、今後の方向性が定まらないと相談に来たのです。
そのとき私がしたアドバイスは、「頑張らないと結果を出せないことは不向きな可能性がある」でした。
社会はそれほど甘くなく、結果を出さないと評価されないことが多くあり、評価され続けるためには頑張り続けなければなりません。そういう仕事は継続が困難であることが多いものです。誰かのためだとしても、頑張り続けることは意外にハードでしょう。
必ずしも自分のやりたいことが自分のできることとは限らず、頑張らなくても結果を出せる仕事が適職と呼べるのではないか? と伝えたとき、相談者は憑き物が落ちたように明るい表情になって「別の道を考えます」と言って帰っていきました。
自分ができること・得意なことにも目を向けてみよう
諦めないことも大切ですが、不向きなものを頑張り続けるより、できることを掘り下げて伸ばすほうが生産的かもしれません。できることを見つけて、それを楽しむ方法を探してみましょう。
最後まで公務員試験を受け続ける人も必見! 並行して就活する3つのメリット
最後まで公務員試験を受け続ける人も必見! 並行して就活する3つのメリット
- 進路が決まらないリスクを小さくできる
- 視野を広げることでより最適な進路選択ができる
- それぞれの選考対策を双方に活かせる
公務員試験に諦めずに挑戦する場合も、就活と並行しておこなうことをおすすめします。確実に卒業後の就職先を決めたい場合は、公務員以外の選択肢を持っておくことで、万が一失敗したときの保険にもなり、就職浪人するリスクの回避につながるからです。
また、公務員試験対策が民間の就職対策にもなり、内定を一つでも獲得していれば安心して公務員試験に臨めます。
両者を並行しておこなうためには、自分の状況を正しく把握し、優先順位をつけることがポイントになります。ここでは、公務員試験と並行して就活するメリットを詳しく解説するので、あらかじめ押さえておきましょう。
①進路が決まらないリスクを小さくできる
公務員への志望度が高い人ほど、リスクを取ってでも就職留年・浪人をした方が良いと考える人もいるかもしれません。そのような人こそ、民間企業への就活を並行して進めることをおすすめします。
むやみに卒業を先送りすることで就職に苦戦した場合、経済的なリスクは想像以上に大きいものです。リスクを取って覚悟を決めることも必要ですが、避けられるリスクは小さくして公務員に挑戦しましょう。
民間企業に勤めながら公務員試験の勉強をすることも可能です。もしも公務員試験が不合格だったとしても、経済的なリスクを最小限に抑えられ、就職先が決まらないといった問題も回避できます。
もし公務員試験に落ちてしまっても民間で内定を獲得していれば、卒業後、安心して何度も挑戦できるためリスクが小さいのです。だからこそ、公務員試験対策と同時に就活も進めていきましょう。
- 公務員試験と民間就活を並行して進めるとバランスを崩して、どっちも疎かになりそうです…。
公務員試験と民間就職を並行して進められるか確認しよう
公務員試験と民間就活の並行は、時間はもちろんエネルギーやメンタルも使いますし、人生の重要な分岐点にもなるのでストレスもかかります。そこで確認してほしいのがあなたの経験です。
経験として、たとえば、部活と受験勉強の両立や、研究や学業とアルバイトの両立などが挙げられるかと思います。
こういったことをしっかりと両立して、両方で満足のいく結果を残せてきた実績があるのであれば、公務員試験と民間就活を並行しても問題ないと思います。
しかし、どちらかでしか結果を残せていなかったり、両方とも中途半端に終わってしまった経験があるのであれば、公務員試験か民間就活のどちらか一方に注力したほうが同じ失敗を避けられるのではないでしょうか。
②視野を広げることでより最適な進路選択ができる
公務員試験だけに集中していると、民間企業についてあまり知識がなく、興味も持てないかもしれません。しかし就活する場合は、自己分析や業界研究を進めていく過程で、公務員よりも自分に合った職種が見つかることもあります。
たとえば地域に貢献する点に興味を持って公務員を目指していたとしても、地方創生に注力している民間企業で働く方が、自分に合っている可能性もあるのです。
また、公務員でやりたかった仕事が民間企業で見つかったり、就活を通してこれまでの考えにはなかった新しい選択肢が見えてきたりすることもあります。
自分の強みや特技を活かした仕事に出会うチャンスを増やすことができるのも、就活を並行しておこなうメリットの一つです。
進路を考え直すにあたって大切なのは、他人からの評価や見栄などは除外して、自分にとっての幸せにつながる選択は何かを熟考することです。
ほかの誰かが喜ぶ選択ではなく、一度しかない人生を楽しむための、自分自身のための選択は何か? という視点を持ってみましょう。
③それぞれの選考対策を双方に活かせる
公務員試験対策でしてきた勉強は、民間企業の筆記テストなどに応用することが可能です。筆記試験の出題内容は、完全に同じではないものの、共通している点も多くあるのです。公務員試験対策の勉強をしておけば、民間企業のSPIなどの筆記試験・Webテストをある程度カバーできます。
また、適性検査や面接についても、公務員試験と共通する部分が多いため、たとえば民間企業の面接を受けることで公務員試験の対策にもなります。面接では失敗点を反省して次につなげたり、自分の短所や注意点を整理したりするなど、双方とも経験から学べることは多いはずです。
さらに、民間企業のエントリーシート(ES)に書く志望動機やアピールポイントなどは、読みやすく伝わる文章を書く練習になり、公務員試験でも活かせます。このように民間企業の就活も並行することで相乗効果が生まれ、どちらの通過率もアップする可能性があるのです。
就活に着手する前に! 公務員と民間就職の違いを把握しよう
公務員と民間企業では、働き方など異なる点が多くあります。就活を始める前に、両者の違いを押さえておくことも大切です。
まず公務員は、国もしくは各自治体のために活動します。国や地域に貢献し、利益を目的としない社会奉仕が最大の目的です。国家公務員であれば国民全員、地方公務員であればその市民や町民、村民など、幅広い人が顧客になります。長期的なスパンで法律や政策の実施、社会サービスの提供、公共の秩序維持など国民の暮らしを良くするためのサービスを提供するのが特徴です。
一方の民間企業は、商品やサービスの開発、販売など営利目的での活動をおこない、顧客は消費者や企業になります。利益を第一の目的とするため、大胆さやスピードを重視した働き方が求められる傾向にあります。
また給料に着目すると、公務員の場合、基本的には年功序列型であることも特徴です。終身雇用制で、重大な規則違反などをしない限り、解雇されることはほとんどありません。規定のボーナスも支給されるなど安定した収入が見込めます。
民間企業の場合は、個人の成果や会社の業績により給料やボーナスが変わるのが一般的です。成果が昇給につながる可能性がありますが、業績悪化による減給や失業、リストラのリスクがあることも一つの違いと言えます。
公務員は安定した給与と充実した福利厚生によって、長期的な生活設計が立てやすい点が魅力です。
一方、民間企業は業績に応じた昇給やボーナスが期待できます。競争が激しい分、自己成長や報酬の幅が大きい点が特徴と言えます。
民間企業についてよく知りたい人は、以下の記事で公務員との違いについて解説しているので、併せてチェックしてみてください。
関連記事
民間企業とは? 公務員との7つの違いを理解して就職先を選ぼう
民間企業と公務員の違いがわからない人に向けて、この記事では民間企業と公務員の違いや民間企業で働くメリット・デメリットをキャリアコンサルタントと解説します。自分の適性を確かめて、将来を選びましょう。
記事を読む

国家公務員に興味のある人はこちらの記事を参考にしてみてください。プロが国家公務員の種類について詳しく解説しています。
関連記事
国家公務員の種類をプロとわかりやすく解説! 役割や必要なスキルも
国家公務員の種類を一覧で紹介し、キャリアコンサルタントとともに仕事内容・応募資格・勤務地を比較しながら解説します。自分に合った種類の選び方や種類別の向いている人の特徴も解説するので、国家公務員を志望している人は必読です。
記事を読む

段階を踏んで進めよう! 民間就活を成功させる3つの手順

ここまで、公務員試験と民間就活を並行しておこなうメリットについて解説してきました。民間就活する際は、段階を踏んで進めていくことが大切です。
公務員試験勉強に時間を割いてきた分、あらためて自分の現状を正確に把握し、これから就活をどのように進めていくべきかを判断する必要があります。そのため、限られた時間で今すべきことを明確にし、効率良く準備をするのがポイントです。
ここでは、民間就活を成功させるための手順を解説するので、着実に進めていきましょう。
ステップ①自己分析や業界研究から就活の軸を決める
就活を始めるうえで、まずは軸を決めることが大切です。民間就職となると選択肢が膨大にあるため、仕事に求める条件は何かを明確にすることが、就活で企業を選択する際に自分なりの判断基準になります。
どのような働き方をしたいのか、どのような人になりたいのかといったことをヒントに自己分析を進めていくことがポイントです。自身の思考や行動パターンを理解することが、将来のキャリアビジョンを描くための基盤になります。
しかしながら、公務員試験一本でやってきた場合、具体的にどのように自己分析や業界研究を進めたら良いのかわからない人もいるのではないでしょうか。
次の章より、自己分析や業界研究をする際の具体的なアクションを紹介するので、必要な情報や内容を整理していきましょう。
自分の軸を見つけたい人は以下の記事も参考になるので、併せてチェックしてみてください。
関連記事
一目でわかる転職の軸! 自分だけの軸の見つけ方をイラストで紹介
転職の軸は企業を選ぶ際に重要な指標です。就活で定めた場合も、転職時には改めて定めるのがおすすめです。記事では、転職の軸の重要性や作り方、具体的な例をイラストで紹介しています。自分だけの転職の軸を見つけて転職を成功させましょう。
記事を読む

- ずっと公務員を目指していたので、就活の軸がうまく考えられません…。
公務員を目指したきっかけに立ち返ってみよう
自分が立てた計画が予定通りに進まないと迷子になりやすいのは誰でも同じです。就職がゴールではありませんが、迷子になったときほどスタート地点に戻って、基本である自己理解、自己分析をやり直すことが重要になってくるでしょう。
その際には、公務員になりたい理由はどこにあるのか、なりたい将来像へのきっかけになった経験などを思い出すことがポイントです。それらを踏まえて、どんな将来像があったから公務員を選択したのかが明確になれば、その将来像を実現するための別の方法も見つかるかもしれません。
言語化、見える化を徹底して、自分を客観的に把握しましょう。
価値観や強みなどをあらためて棚卸する
民間企業の就活では自分の本質や価値観を棚卸し、強みや弱点を客観的に把握することが大切です。企業は社風やポジションにマッチした人材を見極めるために人柄や潜在能力を評価するため、自己理解が不十分だと選考を突破するのが難しくなります。
自分の価値観や強みを知るためには、これまでの経験に焦点を当てて、頑張ってきたことや困難を乗り越えたことなどから何を得たのかを深掘りすることが大切です。深掘りしていく過程で、価値観や強みが見えてきます。
就活で企業側が重視しているポイントは、価値観と会社の方向性が合致しているか、社風とのマッチ度、将来的に活躍してくれそうな人材か、企業や仕事への適性などです。
自分のタイプを理解しておくことで、就活の際も強みを効果的にアピールすることができます。自分の強みを活かせて、かつ情熱を注げる仕事を見つけてみてください。
民間企業で活かせる強みが見つからない人には、他己分析がおすすめです。
自分の強みは、自分で認知できていなかったり自分にとって当たり前になってしまっていたりと、案外気付かないこともあります。
ぜひ周りの友人、親、先生、キャリアコンサルタントなどに他己分析を依頼して、民間企業で活かせる強みを見つけてもらいましょう。
自己分析のやり方については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
関連記事
自己分析ノートの効果的なやり方4ステップ|就活での活用法も解説
この記事では、ノートを使った自己分析法のやり方がわからない人に向けて、自己分析ノートの種類やメリットを紹介しています。自己分析をノートでやるときは目的に合わせた工夫が重要です。キャリアコンサルタントとともに手順も説明するので、自己分析ノートを就活に役立てたい人は参考にしてくださいね。
記事を読む

モチベーショングラフを使った自己分析の方法も参考になります。
関連記事
テンプレ付き|モチベーショングラフを駆使して自己分析を深めるコツ
自己分析に有効な手法としてモチベーショングラフがあります。モチベーショングラフは適切な書き方や活用方法を知らないと、就活にうまく活かせません。この記事ではキャリアアドバイザーがモチベーショングラフで自己分析を極める方法を解説します。
記事を読む

民間企業の業界や職種を調べる
自己分析で価値観や強みなどがわかってきたら、民間企業の業界や職種を調べていきます。限られた時間の中で就活するため、まずは自分に適した業界のリサーチをしましょう。
チェックするポイントは、業界の動向や成長性、将来のビジョンなどです。自己分析で把握した自分の長所や短所、価値観や強みなどを考慮して、自分にマッチしそうな業界をピックアップしてみてください。
さらに、ミスマッチを防ぐためには、業界や企業だけでなく、職種についてもリサーチする必要があります。職種研究を怠ると就職後に後悔するケースがあるためです。
興味のある職種が自分に合っているか、強みや経験を活かせるかどうかをチェックしましょう。たとえばチームワークを重視する働き方を望むのであれば、チームで働く業界や職種が合うかもしれません。さらに自分の専門性やスキルが活かせる職種も調べてみると視野が広がります。
自己分析で得た情報をヒントに効率良く業界を絞り、自分とマッチ度の高い企業や職種を見つけていくことが大切です。
どのような業界・職種があるか知りたい人は、以下の記事で一覧を紹介しているので、チェックしてみてください。
業界一覧
就職活動で役立つ業界一覧|仕事内容から動向まで各業界を徹底解説!
職種一覧
職種の種類一覧を徹底解説! 業種・業界・職業との違いも押さえよう
業界研究のやり方がわからない人は以下の記事が参考になるので、併せてチェックしてみましょう。
関連記事
業界研究のやり方|業界全体を捉えたうえで気になる業界を研究しよう
「就活を始めたけど、業界研究のやり方がわからない……」という人は多いでしょう。この記事では、業界研究のやり方について、キャリアコンサルタントのアドバイスを交えつつ解説します。志望業界を見つけるためにも、早めに業界研究をおこなってくださいね。
記事を読む

- 民間には業界や職種がさまざまにあって、なかなか絞れません…。
幅広い業界・職種の情報を集めながら自分の適性を見極めよう
公務員を目指していた人が民間企業への就職に切り替える際には、まず幅広い業界や職種を調べることが重要です。公務員試験に落ちた後の就活では、焦らずに多様な選択肢を検討し、自己分析を徹底して自分の適性を見極めることが求められます。
特に、民間企業に対する志望動機をしっかりと整理し、「なぜ民間企業を選んだのか」を明確に伝えることが大切です。これにより、面接での応答に説得力を持たせることができます。
また、学内で開催される合同説明会に参加したり、友人との情報交換を通じて、効率的に多くの企業情報を収集することも、業界・職種を絞るためには効果的です。
ステップ②採用活動を継続している企業を探す
公務員試験後の民間就活は、限られた時間の中で進めなくてはなりません。効率良く就活するためには、夏以降も募集している秋採用や、通年採用をしている企業を狙うのがポイントです。
学生の中には、秋採用で採用されるのは優秀な学生だけだと思う人もいるかもしれませんが、実際は秋採用であっても、十分な対策をすれば内定を獲得するチャンスはあります。
しかし、秋採用は企業数が減るだけでなく、春や夏と比べて1社ごとの内定枠が少なくなるのも事実です。自分の力で探そうとするとなかなか見つからないかもしれません。そこで、効率良く企業を絞るなら、次のような機関やサービスを活用するのがおすすめです。自分の目的や希望する業界に合わせて活用してみてください。
大学のキャリアセンターに相談する
就活における悩みや不安がある場合は、大学のキャリアセンターで相談するのがおすすめです。キャリアセンターは基本的に大学のキャンパス内にあり、無料で就活支援が受けられます。
キャリアコンサルタントなどの有資格者が相談に応じるキャリアセンターも多くあり、専門家の具体的な意見やアドバイスをもらえるのがメリットです。
また、大学のOG・OBやキャリアセンターからの紹介で、企業に応募する方法もあります。紹介という形の応募であれば、企業からも一定の信頼が得られるため、スムーズに選考が進むかもしれません。
ただし、自分で企業を探す場合よりも選択肢が狭まる可能性もあり、先輩などからの紹介があるとは限りません。過度に期待し過ぎず、主体的に活用することが大切です。
有資格者がいるキャリアセンターなら、一人ひとりが持っているスキルに合わせて適職を探す手助けをしてくれるだけでなく、傾聴の姿勢で対応してくれるので、気持ちの切り替えもうまくいくのではないでしょうか。
就職エージェントやスカウトサービスを利用する
就職エージェントに登録すると、非公開の求人や推薦枠を紹介してもらえたり、就活の方向性の相談ができたりします。書類の添削や面接対策もしてくれ、求人の紹介からエントリー手続きまで代行してくれるのがメリットです。求人を自分で探して応募する手間が省けます。
ただし、一方的に求人を紹介されるケースもあるため、自分の判断軸で企業を選ぶことが大切です。
スカウトサービスも効率的に就活を進めるうえで役立ちます。スカウトサービスは、登録された学生のプロフィールを見て企業側がスカウトを送るというサービスです。サイトにプロフィール情報を登録しておくと企業から声がかかるシステムなので、自分から企業情報を検索する手間がかかりません。
いずれも効率的に就活を進めるのに役立つので、積極的に利用してみてください。
就職エージェントの例
- キャリアチケット:自己分析から内定獲得までマンツーマンでサポート
- キャリアスタート:性格やスキル、特性を見極めながらの求人紹介が特徴
- LHH就活エージェント:入社後のキャリアまで見すえたサポートを受けられる
スカウトサービスの例
- オファーボックス(OfferBox):大手企業や中小ベンチャー企業まで優良企業からオファーが届く。5年連続学生利用率1位
- キャリアチケットスカウト:価値観にマッチする企業からスカウトが届く。スカウトにつながるフォローコンテンツも充実
- キミスカ:3種類のスカウトメールで進むべき企業を判断できる。マッチングイベントも実施
- もう人気のない企業しか残っていないと思うので、変な企業を紹介されないか心配です。
就職エージェントと関係を構築して優良企業を紹介してもらおう
信頼性や評判の高い就職エージェントを利用し、エージェントとコミュニケーションをしっかり取れば、優良企業を紹介してもらえる可能性は十分あります。
限られた時間の中で就活をするにあたり、就職エージェントを活用して効率的に就活を進めることは重要です。
また、厳しいことを言えば、その思いは企業も一緒です。「もうあまり期待できない学生しか残っていないと思うので、就職エージェントから変な学生を紹介されないか心配です」と企業に思われているかもしれません。
就活は謙虚に進めていかないと足元をすくわれかねないので、気を付けましょう。
ハローワークに出向いてみる
ハローワークは厚生労働省が提供する職業紹介、就職支援のサービス機関です。ハローワークの求人掲載は、民間のエージェントと違って企業側に掲載費用がかからないので、特に地方の企業や中小企業を見つけやすいというメリットがあります。
ハローワークでは仕事探し以外に、職業相談、履歴書の添削や面接対策、各種セミナーなど、幅広いサービスを無料で利用できます。
就活を始めたいけれど行動指針が立たない場合や、方向性が定まらない場合は、ハローワークの総合窓口を訪ねてみるのも一つの方法です。
相談員が悩みをヒアリングし、次の行動指針を立て、アドバイスをしてくれます。専門家に相談することで、悩みを解消する糸口が見つかるかもしれません。
就活について誰に相談すれば良いか悩む場合は、以下の記事でも相談先を14選紹介しているので、併せてチェックしてみてください。
関連記事
就活の相談先14選! 良い決断ができる相談相手の選び方も解説
就活の相談をするときは、相手を見極めることが大切です。この記事では、状況別におすすめの相談先や、相談方法などについてキャリアコンサルタントと解説します。また、相談する前に解決できるよう、よくある相談と回答も紹介しているので参考にしてください。
記事を読む

ステップ③公務員試験の振り返りから面接対策をする
最後のステップは、面接対策です。民間企業の面接形式は公務員試験とほとんど変わりません。公務員試験で面接対策をしていた場合は、それほど時間をかける必要はないと思います。
筆記試験に集中していて面接対策に時間を割けなかった場合は、練習時間を長めに確保するようにしてください。民間企業の一次面接、二次面接、最終面接ではそれぞれ想定される質問や評価ポイントが異なるため、相応の対策が必要です。
面接対策をする際は、公務員試験の振り返りから落ちてしまった原因を分析し、失敗を繰り返さないこともポイントになります。公務員試験での経験を活かすために、効果的な振り返りは次のようなことを意識してみてください。
面接の対策をする前にあらためて基本を押さえておきましょう。以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
関連記事
面接対策の基本を就活のプロが徹底解説! 質問実例集やマナーなど
就職活動において避けては通れない面接。この記事では面接で採用担当者を惹き付ける方法をキャリアコンサルタントとともに解説します。採用側の視点を捉えた対策をマスターして、あらゆる面接で高評価を目指しましょう。
記事を読む

まず自己分析をおこない、何が不足していたのかを具体的に振り返ることが重要です。面接での姿勢や表情、コミュニケーション力を向上させ、具体的な事例やデータを用いた志望動機をしっかり準備しましょう。
また、試験後は一度リフレッシュして心身を整え、前向きに次の目標に向けて準備を進めることも大切ですよ。
落ちた理由を客観的に分析する
公務員試験で落ちてしまった理由を客観的に分析することは、民間就活でも役立ちます。民間企業の就活にも面接は必ずあり、重視されるポイントだからです。
特に公務員試験の面接で落ちてしまった場合は、重点的に見直す必要があります。公務員試験に落ちてしまう原因としては、以下のようなことが考えられます。
公務員試験に落ちた原因として考えられること
- 緊張からうまく伝えられなかった
- 回答内容が薄かった
- 受け答えに一貫性がなかった
- 言葉遣いが正しくできていなかった
- 面接官を納得させる志望動機を提示できなかった
- 自己PRで明確な採用メリットを上手にアピールできなかった
上記のように、自分は何が原因で面接に落ちてしまったのか、振り返ってみてください。
失敗から原因を明確にして改善することで、自己成長につながります。落ちてしまった試験を思い出すのはつらいかもしれません。しかし民間企業における選考を突破するためには、公務員試験を振り返り、適切な対策を実践することが重要になるため、必ずおこなうようにしましょう。
- 公務員試験の面接に落ちた理由がわかりません…。
面接官とのやり取りを振り返って自分を客観視しよう
どんな質問をされ、それに対してどう答えたのかを思い出しながら文字に書き起こしてみましょう。その内容を振り返って、自分が採用側だったらどう感じるかを考えてみてください。
「緊張のあまり用意していた回答を言葉足らずのまま伝えていた」「質問の意味を理解できていないまま、ズレた回答をしてしまっていた」など、見える化して冷静に振り返ると、自分に不足しているところがわかりやすくなります。
真相はわからないかもしれませんが、きっとここが原因だろうというものは見つけやすい方法です。ぜひ試してみてください。
面接が苦手な人は以下の記事が参考になります。
関連記事
面接の苦手意識を克服する21手|得意にする秘訣は「考え方」にあり
面接の苦手意識は、考え方次第で克服できます。苦手意識の要因は7つあり、それぞれへの対処をすることが重要です。それぞれの要因と対処法をキャリアコンサルタントが解説しますので、意識改革の手掛かりにしてください。
記事を読む

第三者からフィードバックをもらって選考対策に活かす
第三者からのフィードバックにより、面接の良かった点や改善点などを示してもらうのも対策として有効です。
フィードバックには2種類あり、ポジティブフィードバックとネガティブフィードバックが存在します。ポジティブフィードバックは、良い点や成長箇所を前向きな言葉で承認するものです。ネガティブフィードバックは、問題点や課題を指摘し、改善のきっかけとするものになります。
ポジティブフィードバックは、積極的にアピールできる点として認識し、ネガティブフィードバックは、問題点を見つけて改善することで、選考で活かすことが可能です。この2つのフィードバックを友人や先生、エージェントのアドバイザーなどとの模擬面接で依頼し、自分自身では見落としているかもしれない改善点に気付き、面接に向けて実力を磨いていきましょう。
模擬面接を受ける際は以下の記事で流れを解説しているので、チェックしてみてください。
関連記事
模擬面接の効果を発揮させる6つのコツ|準備から進め方まで一挙解説
模擬面接は、面接の緊張感や雰囲気を体験しながら練習することが大切です。模擬面接の事前準備から実施方法までキャリアコンサルタントが解説します。模擬面接をおこなうメリットを把握し、活用することで選考突破に役立ててください。
記事を読む

公務員試験後の就活で聞かれやすい質問に備える
公務員試験に落ちてからの就活では、ほかの学生よりも遅めのスタートとなります。そのため「なぜこの時期でも就活をしているのだろう?」と気になる企業は多いです。
面接で実際に話を聞くまでは、「就活へのやる気がなかったのか」「どこの企業にも受からなかったのでは」という懸念を抱かれやすいのです。また公務員に受かるために努力していた経緯がわかったとしても、今度は「まだ未練があってすぐに辞めてしまうかも」と心配する企業もあります。
そのため公務員試験後に就活する人は、企業から聞かれやすい質問にあらかじめ備えておき、面接で堂々と答えられるようにすることが重要です。以下が特に多い質問なので、企業の懸念を払拭できるように準備しておきましょう。
公務員から民間就職に切り替えた人が聞かれやすい質問
- どうしてこの時期から就活を始めたのですか?
- 公務員を目指していたのはなぜですか?
- 民間企業への就活を並行していなかったのはなぜですか?
- うちに興味を持ったのはなぜですか?
- 公務員に未練はありませんか? また挑戦したいですか?
公務員試験のために努力していたことはアピール材料にもなります。効果的にアピールするためには、公務員試験でどんな点に力を入れていたかを言語化することが大切です。
公務員試験対策時の目標はどのような考えで設定し、課題にはどのような対策を打っていたかを伝えるようにしましょう。あなたの課題解決力が伝わるはずです。
面接の練習は一人でもおこなえます。以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
関連記事
一人でできる面接練習の方法|効果を劇的に高めるコツ6選
面接練習は一人でも工夫次第で効果を得ることができます。この記事は、面接練習を一人でおこなう際のコツや注意点を、キャリアコンサルタント監修により解説します。面接に苦手意識を持っている人や、効果的な練習方法がわからない人はぜひ参考にしてください。
記事を読む

アドバイザーコメント
瀧本博史
プロフィールを見る公務員試験後の民間就職はスケジュール管理と戦略が鍵になる
公務員試験後に就活を始める場合、一般的な就活スケジュールよりも遅れを取ることが多いため、効率的な計画が求められます。自己分析を通じて自分の強みや価値観を明確にし、それに基づいて就活の軸を決めることが最初のステップです。この軸が定まると、企業選びや選考対策もスムーズに進められるでしょう。
企業研究においては、キャリアセンターや就職エージェントを活用し、早急に情報収集をおこなうことが重要です。特に秋採用や通年採用を行っている企業に注目し、効率的に選考を進めることが求められます。また、ESや面接対策も徹底的におこない、公務員志望からの転換理由をしっかりと説明できるように準備しましょう。
民間企業で社会経験を積んだうえで公務員を目指し直すのも手
公務員試験に再挑戦することを視野に入れている場合も、民間企業で社会人経験を積むことで次回の公務員試験や民間経験者採用で有利になるかもしれないことを押さえておくと良いでしょう。この方法はリスクを最小限に抑えつつ、将来的なキャリアパスの幅を広げることができるため、多くの学生にとって有益です。
最後に、民間企業への就職活動を進める際には、迅速かつ的確な行動が求められるため、スケジュールの遅延や準備不足がないようにしましょう。
時期により必要な行動も変わる! 状況別の就活を成功させるコツ
時期により必要な行動も変わる! 状況別の就活を成功させるコツ
- 一次試験後からの就活:秋採用に備えて動き出そう
- 二次試験後からの就活:早めに対策を立てて積極的に応募しよう
- 三次試験後からの就活:すぐにエントリーを開始してエージェントなどを頼ろう
公務員試験に落ちてしまった後で民間就活を始める場合、一次試験、二次試験、三次試験のどこで落ちたかによって行動が変わります。どのタイミングで始める場合でも、スケジュール管理が重要です。
公務員試験に落ちてしまった段階で民間就活に切り替える場合、一般的な就活生よりも出だしが遅れているため、限られた時間で対策をする必要があります。
ここでは、公務員試験に落ちてしまった状況別に、就活を成功させるコツを解説するので、状況に応じた行動で内定の獲得を目指しましょう。
一次試験後からの就活:秋採用に備えて動き出そう
公務員試験の一次試験後からの就活は、7月頃から始めることになります。民間企業は3月からエントリーが開始されるため、7月には本選考を終えている企業も多い状況です。そのため本選考に無理に滑り込むよりも、秋採用か通年採用をおこなっている企業を探すことをおすすめします。
まだ選考まで時間があると思わずに、早めに準備を進めておくことが大切です。スタートで出遅れている分、目的を持った行動を意識してみてください。業界や企業研究に時間がかかるかもしれませんが、すべて把握することは難しいため、興味のある分野に絞るのがポイントになります。
これまで解説した業界・職種研究をできるだけ早く進め、秋採用に向けてエントリーができる状態にしておきましょう。
内定を獲得するコツは、他人と比べて焦らないことです。「自分は自分」と考えて一つずつ確実にクリアしていきましょう。遠回りすることが近道になるかもしれません。
遅れている状況を楽しむ余裕があるほうが良い結果を出すこともありますよ。
二次試験後からの就活:早めに対策を立てて積極的に応募しよう
公務員試験の二次試験後からの就活は、8~9月頃から始めることになります。この時期は、秋採用の募集や選考が始まる時期です。できるだけ早く就活の軸を定めて企業研究を進め、秋採用に間に合うようにエントリーしなくてはなりません。
秋採用は採用枠が少ないため、企業への理解度や志望度が重視されます。そのため二次試験で落ちてしまった場合は、企業探しと志望動機の作成に注力することが大切です。
ただし、二次試験後から限られた時間で、自分の価値観に合った企業を探すことやエントリーすること自体が難しいかもしれません。
そのため、キャリアセンターやハローワーク、就職エージェントといった就活のプロに相談するなどして、企業研究を深めてほかの就活生と差がつく志望動機を作成し、積極的にエントリーしていきましょう。
三次試験後からの就活:すぐにエントリーを開始してエージェントなどを頼ろう
公務員試験の三次試験後からの就活は、9~10月頃から始めることになります。10月は企業も秋採用を開始しているため、一刻も早くエントリーして面接を受けなくてはなりません。
時間に余裕がないため、厳しいスケジュールになることが考えられます。そのため、就職エージェントなどの就活のプロに相談し、短い期間で必要な対策を立てて、面接に臨める態勢を作ることが大切です。
就活における不安や疑問点があったら、一人で悩まずに早い段階で相談して解消しておきましょう。時間との勝負になりますが、志望動機の作成などはしっかりおこなう必要があります。企業研究を怠らずに、企業の魅力と自分が貢献できるポイントを整理してみてください。
早く内定をもらいたい場合は、以下の記事を読めば内定を得るために必要なことがわかりますので、参考にしてみてください。
関連記事
就活の内定時期はいつ? 早く内定を得るために必要なことを解説
就活における内定の時期は人や企業によって異なります。そのため、内定や内々定の時期に捉われる必要はありません。この記事では、内定と内々定の時期の平均を解説したうえで、自分が納得いく形で内定を獲得するためのカギをキャリアコンサルタントが解説します。
記事を読む

ESを作成する際は以下の記事が参考になります。
関連記事
例文12選|受かる志望動機をエントリーシートに書く4つのステップ
エントリーシートの志望動機は簡潔かつ、「読みたい」と思わせる内容にしなければなりません。キャリアコンサルタントと、惹きつける志望動機を書く4つのステップと、高評価を狙うコツをプロの目線で解説します。
記事を読む

- 時間がなくてエントリーが間に合いそうにありません…。どうすれば良いでしょうか。
焦って合わない企業に入るよりもじっくりと進路と向き合うべき
まず、就職エージェントや就活サイトのスカウト機能を利用して、エントリーしなくても選考を受けられる状態を作りましょう。時間がない中で選考を進めるには、自分の力ではなくサービスや他者を頼ったほうが賢明です。
しかし、もし興味の持てる企業が見つからなかったり、そもそもそれらに登録する時間すら確保できないのであれば、その年度の就活は諦めたほうが良いのかもしれません。
焦って就活をして、ミスマッチの企業に入ったとしても、あなたが幸せになることはほぼありません。今は就活留年をしたり休学をする学生も増えています。
就活を一年遅らせて、じっくりと自己分析や企業研究を重ね、自分が本当に進みたい道に向かって行動したほうが、納得したキャリアを歩めると思います。
公務員試験も就活も悩む人は多い! 関連するQ&Aを見てみよう
公務員試験や就活における悩みを相談したいと考える人は多いのではないでしょうか。自分以外のほかの人も同じような不安を抱えているケースは多く見受けられます。
そこでここでは、PORTキャリアに寄せられた将来の不安に関する4つのQ&Aを紹介します。キャリアコンサルタントのアドバイスを参考に、公務員試験や就活における不安を解消してくださいね。
公務員試験に落ちてからの就活は振り返りと効率的な対策で内定につなげよう
公務員試験に落ちてしまったら、ショックで落ち込んでしまうかもしれませんが、将来の道が断たれるわけではありません。気持ちを切り替えて民間就職のために就活を始める、大学院へ進学する、諦めずに公務員試験に挑戦するなど、残されている選択肢に冷静に向き合いましょう。
民間企業への就活を始める場合、限られた期間で成功させるためには、大まかな流れを把握し、適切な対策を進めることが大切です。納得のいく道に進むためにも記事を参考に前向きに行動して、望む未来をつかんでくださいね。
アドバイザーコメント
古田 文子
プロフィールを見る公務員試験に受からず落ち込んだことも糧にして「今」を楽しもう
公務員試験の望まない結果を知ってから日が浅い人にとって、今は悲しい気持ちでいっぱいかもしれません。暗い気持ちを抱えていようとも何事もなかったような顔をして前に進めとは言いません。思う存分落ち込んでください。その時間も決して無駄ではなく、そうやって思い悩みながら生きていくのが人の一生というものなのだろうと思います。
しかし、落ち込むような経験をしたおかげで得られたものもあるかもしれません。もう一度トライしてついに望む結果になることもあれば、ほかの道に進んだおかげで楽しい人生を送れることもあるでしょう。未来は誰にもわからないからこそ、「今」を大いに楽しんだほうが良いのではないでしょうか。
立ち直るための過程さえ楽しむ心持ちでいよう
私の経験からおすすめしたいのは、壁にぶつかったり困難を乗り越えたりしなければならない場面に直面したときこそ、「自分は試されている」と考えることです。そうすると立ち直る過程さえ楽しむことができるのです。
人は意外と単純な生き物です。だまされたと思ってぜひ試してみてください。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

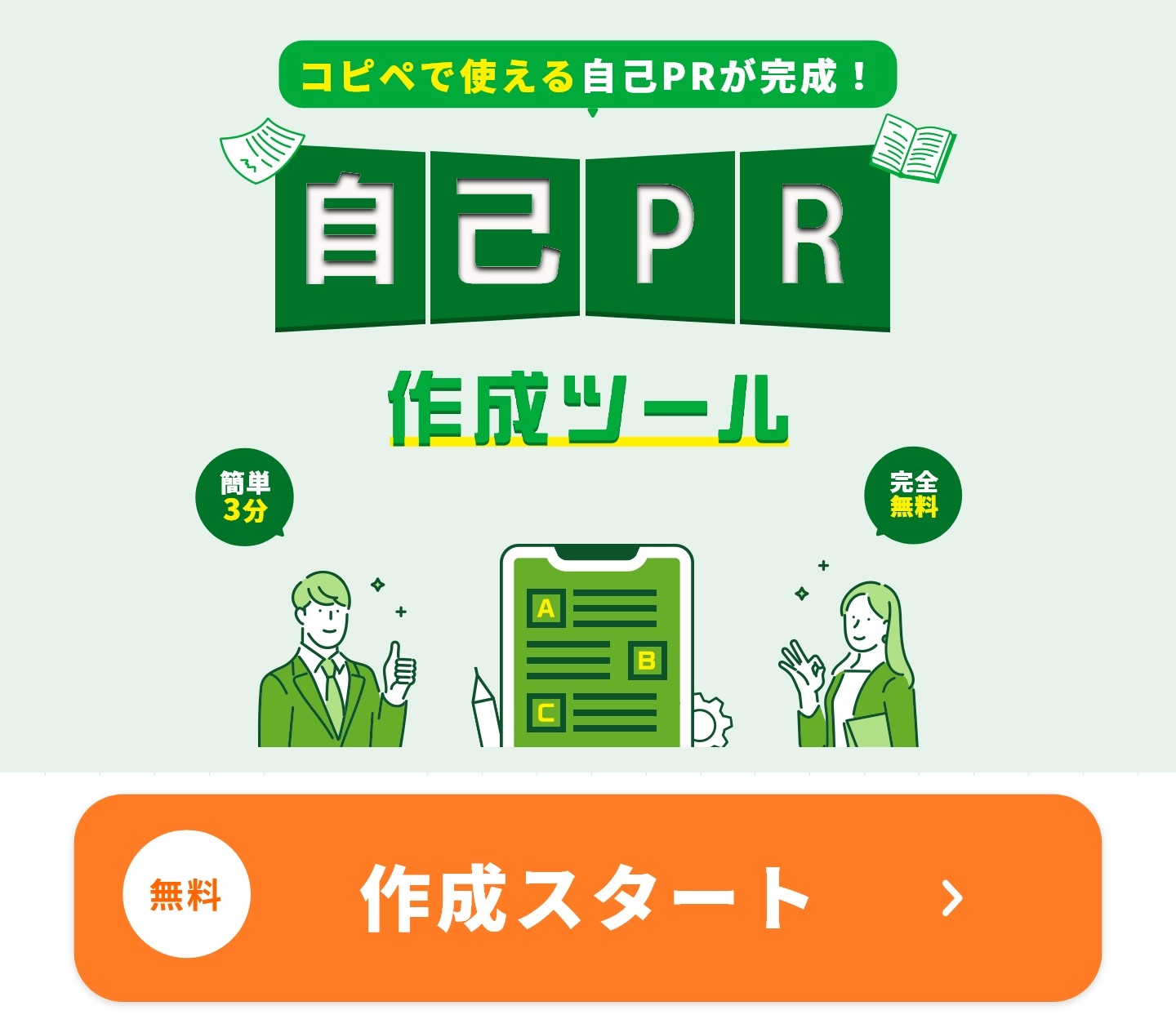













3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルティング技能士/C&Lデザイン合同会社代表
Fumiko Yoshida〇全国60大学で、民間・公務員・看護師と幅広い志望の学生を支援。インストラクショナルデザイナーとして、キャリアコンサルタントに向けた研修設計・講師力向上研修もおこなう
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー
Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアコンサルティング技能士
Hiroshi Takimoto〇年間約2000件以上の就活相談を受け、これまでの相談実績は40000件超。25年以上の実務経験をもとに、就活本を複数出版し、NHK総合の就活番組の監修もおこなう
プロフィール詳細