この記事のまとめ
- 人をサポートする仕事36選と向いている人の特徴を解説
- 人をサポートする仕事から適職を見つけるコツと注意点
- 3人の現役キャリアコンサルタントにやりがいを質問
就活を始めて自己分析に着手し、人をサポートする仕事に就きたいと考えている人も多いでしょう。
しかし、「具体的にどのような仕事があるのか知りたい」「自分が人をサポートする仕事に向いているかわからない」と、疑問点が多く不安に思っている人もいるのではないでしょうか。
一括りに人をサポートする仕事といってもさまざまな種類があるため、それぞれの仕事内容や適性を確認する必要があります。仕事内容を知らなければ業界研究や企業分析に時間をかけていないことが伝わり、熱意がないと判断されて選考落ちの原因になるためです。
この記事では、キャリアコンサルタントの高尾さん、山路さん、永田さんのアドバイスを交えつつ、人をサポートする仕事の一覧や向いている人の特徴を解説します。
また、学生をサポートする立場であるキャリアコンサルタントに実際の仕事の魅力を質問しているので、人をサポートする仕事に興味がある人はぜひ参考にしてください。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
人をサポートする仕事一覧を4タイプに分けて適職を見つけよう
人をサポートする仕事にはさまざまな種類があり、それぞれの仕事内容を把握するのは大変です。しかし、求められる資質ごとに分けると4タイプに分類できます。4タイプに分けてから詳細をチェックすることで、効率的に仕事内容への理解を深められます。
この記事では、まず人をサポートする仕事の一覧と向いている人の特徴を解説します。36種類の仕事を挙げているため、興味のある職種を見つけましょう。
次に人をサポートする仕事から適職を見つけるコツと注意点を、キャリアコンサルタントの視点から解説します。
また、人をサポートする仕事の4つの魅力も説明します。人をサポートする仕事に興味を持っているのであれば、ぜひ最後までチェックして適職探しや選考対策に活かしてください。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認してみよう
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
向いている人の特徴も解説! 人をサポートする仕事一覧36選
人をサポートする仕事一覧36選
- 人の暮らしを支える仕事
- 知識やスキルを伝える仕事
- 人の心をケアする仕事
- チャレンジする人をサポートする仕事
人をサポートする仕事は大きく4つの種類に分類できます。それぞれの種類の役割を把握していないと志望先を絞り込みにくいうえに、適職を見つけるのが難しいです。
ここからは、人をサポートする仕事を4タイプに分類し、おもな役割や特徴を解説します。また、タイプごとに代表的な職種や向いている人の特徴を説明しているので、相性の良い仕事があるのかチェックしながら読み進めてください。
人の暮らしを支える仕事17選
私達の生活はさまざまな仕事によって支えられています。生活の安全やスムーズな移動、快適な暮らしを支える仕事は、人をサポートする仕事です。
ここからは、人の暮らしを支える仕事の代表的な職種を説明します。上記に興味を持っている職種がある人は、ぜひ仕事内容や向いている人の特徴を確認してみてください。
あなたが受けないほうがいい職業を診断しましょう
就活を進めていると、自分に合う職業がわからず悩んでしまうことも多いでしょう。
そんな時は「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格、価値観を分析して適職や適さない職業を特定してくれます。
自分の適職や適さない職業を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
①医師
医師とは
医師は病気やケガで苦しんでいる患者に対して診察や治療をおこない、健康的な生活を送れるようにサポートする仕事
医学部に入学して大学で6年間学んだ後、医師国家試験に合格すれば医師として働けるようになります。
また、大学卒業後の2年間は医療機関で研修医として働く必要があるため、一人前の医師になるには最低でも8年間かかるのです。
脳外科や眼科、耳鼻咽喉科などがある医師ですが、どの分野においても思いやりを持って接する姿勢が患者に安心感を与えます。そのため、共感力があって患者の気持ちに寄り添える人は医師に向いています。
さらに、常に研究が続けられている医療は進歩が早く、患者に対して最善を尽くすためには知識やスキルのアップデートが欠かせません。そのため、探究心や自己研鑽の姿勢がある人も医師に向いているといえます。
- 医学部以外から医師を目指すにはどうしたら良いですか?
医師のハードルは高いが医療業界の仕事はさまざま
現時点で医師を目指すには本文にもあるように、大学の医学部へ入学し6年間学んで医師国家試験に合格する必要があります。
そもそも大学の医学部自体が、偏差値60は当たり前というハードルの高い世界です。目指す途中で挫折する方も一定数います。
しかし、たとえば「看護師や医療事務として、病院に訪れたり入院したりしている患者さんに寄り添ってサポートしたい」「病院で扱う医療機器や薬のメーカーとして、医療現場そのものを支えたい」というように、医師以外でも医療にかかわる仕事は多数存在します。
無資格でできるものから資格が必要なものまで実にさまざまです。自分が「どんな人をどうサポートしたいか」をイメージしてみましょう。
②看護師
看護師とは
医師の指示のもと、患者のケアや医療サポートをおこなう仕事
看護師は患者の症状や経過を観察し、医療処置の補助や生活支援を通じて回復をサポートします。
また看護師は病院や診療所だけでなく在宅医療や福祉施設でも活躍していて、ライフスタイルやキャリアプランに合わせてさまざまな場所で働けます。看護師になるためには、大学や専門学校などのカリキュラムを修了し、看護師国家試験への合格が必要です。
看護師は長時間のシフト勤務や夜勤、立ち仕事が多いため、体力的にも精神的にもタフであることが求められます。そして医師と同様に、患者の体調や心理面に配慮できる共感力や最新の医療知識や技術を学び続ける姿勢がある人が看護師に向いています。
看護師の仕事内容や志望動機の作成方法はこちらの記事でまとめているので、少しでも興味がある人はぜひ読んでみてください。
③薬剤師
薬剤師とは
薬剤師は医師が処方した薬の調剤や、患者への薬の説明・服薬指導をおこなう仕事
薬剤師は患者が薬を安全かつ効果的に使用できるようにサポートするほか、副作用や飲み合わせなどのリスクについても助言します。
また薬剤師になるには薬学部のある大学に6年間通い、国家試験に合格して薬剤師免許を取得しなければなりません。免許取得後は病院や薬局での勤務が一般的ですが、製薬会社や研究機関、行政機関でも働く機会があり、薬の専門家として幅広い分野で活躍しています。
薬剤師の調剤や確認作業は患者の健康に直結する大事な仕事です。そのため、慎重かつ正確に仕事を進められる人が向いています。そして新しい薬の開発や法制度の変更にも対応する必要があるため、薬学に関する知識をアップデートする姿勢も重要です。
薬剤師の仕事内容ややりがいについては、こちらの記事で詳しく解説しています。人をサポートする仕事のなかでも薬剤師に興味がある人は、ぜひ参考にしてください。
あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
④弁護士
弁護士とは
依頼人の法律問題を解決し、権利や利益を守るためのサポートをおこなう仕事
弁護士は民事や刑事事件の訴訟や交渉、法律相談の対応、契約書の作成や確認、法的なアドバイスなど多岐にわたる業務に携わり、困っている人の生活を助けています。
また弁護士になるためには司法試験に合格して司法修習で実務を学んだ後、司法修習生考試に合格しなければなりません。
司法試験の受験資格を得るためには、誰でも受験できる予備試験に合格するか法科大学院を卒業する必要があります。
予備試験とは
法科大学院に通わずに司法試験の受験資格を得るための試験
2023年度の予備試験の合格率は3.58%と難易度が高いため、大学の法学部で4年間学んだ後、法科大学院に進学して2年間でカリキュラムを修了する法科大学院ルートが一般的です。
弁護士は業務を通じて依頼人の権利を守り、信頼を得ることが重要なため、責任感と倫理観がある人が向いています。
弁護士が含まれる法律関係の仕事はこちらの記事で解説しています。弁護士についてより詳しく知りたい人は、ぜひチェックしてみてください。
- 弁護士を目指すために予備試験ルートを検討しています。合格確率を高めるなら、もう一度大学に入り直すべきでしょうか?
法科大学院ルートは費用が高い分学べることが多い
予備試験ルートは法科大学院ルートに比べて学費負担が軽い点が魅力的ですが、合格難易度が非常に高いため、大学に入り直すべきかを検討するのも一つの方法です。
特に法律未経験の場合、法学部に進学することで、時間と費用はかかるものの基礎知識を体系的に学ぶことで予備試験対策がしやすくなり、仲間や指導者とのネットワークも得られます。
一方で、独学に適した環境が整っていて短期集中で学べるなら、大学に通わず市販の教材や予備校、オンライン講座を活用して短期間で効率的に学び、予備試験対策に専念する方法も有効です。
個人のこれまでの学習状況や学習スタイル、目指すタイムラインや経済状況を考慮し、必要に応じて専門家に相談しながら、自分に合った方法を選択し計画を立てましょう。
⑤警察官
警察官とは
警察官は犯罪の防止や捜査、緊急対応などをおこない、公共の安全と秩序を守る仕事
警察官は日常的なパトロールや交通取締り、犯罪の捜査、地域の防犯活動や災害時の救助活動など、地域住民の安全を守るために幅広く活躍しています。
警察官になるには各都道府県の警察官採用試験を受験し、学力試験と体力試験に合格しなければなりません。そして採用後は警察学校に入校し、警察官としての基本的な知識や技能を習得するための教育と訓練を受ける必要があります。
また災害や犯罪といった緊急時にも市民を守らなければならないため、警察官には冷静かつ臨機応変に対応できる人が向いています。
そして、人々の暮らしを支えるためには法律や規則の遵守も欠かせません。そのため、強い責任感と倫理観も警察官の重要な資質です。
警察官については以下の記事で詳しく解説しています。仕事内容や選考のイメージをつかみたい人は、ぜひ確認してください。
警察官の自己PR
警察官の自己PRの書き方|説得力で差別化する秘訣を解説
警察官の志望動機
警察官の志望動機を魅力的にするには? 就活のプロがコツを伝授
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
⑥消防士
消防士とは
消防士は火災や自然災害などの緊急時に、被害の拡大防止と人命救助をおこなう仕事
消防士は火災現場での消火活動だけではなく、建物のなかから人を救助したり、事故現場で救護活動をおこなったりします。
また、防災訓練や防火教育を通じて地域住民に防災意識を高めてもらう活動もしていて、地域住民がトラブルなく生活できる環境づくりに貢献しています。
消防士になるためには、各自治体の消防士採用試験に合格しなければなりません。筆記試験と体力試験、面接を突破すると消防士として採用されます。
最初に消防学校に入校して消火技術や救助技術、救急処置などの専門知識と技能を習得した後、消防署に配属されて現場経験を積むのが一般的なルートです。
消火や救助の現場では体力と持久力が求められるため、消防士には過酷な環境でも耐えられるフィジカルの強さが必要です。また、災害時に判断が遅れると救える人も救えなくなってしまうため、状況を見ながら臨機応変に対応しなければなりません。
そのため、緊急時でも迅速かつ冷静に判断できる人は消防士に向いています。
⑦自衛官
自衛官とは
日本の安全を守るため、陸・海・空に分かれて国際紛争からの防衛や災害救助、国際平和協力活動などを実施する仕事
自衛官は毎日訓練をして身体能力や防衛能力を高めて有事に備えつつ、地震や台風などの自然災害時には、被災地での救助や支援活動もおこないます。
自衛官になるには、筆記試験や体力試験、面接で構成される採用試験に合格しなければなりません。合格後は自衛隊の教育機関で厳しい体力強化や軍事教育を受け、日本を守るために必要な技能や知識を習得します。
そして自衛隊の訓練は厳しいうえに、災害救助や国際平和協力活動では過酷な環境で働きます。そのため、自衛官に向いているのは精神的にも体力的にもタフな人です。
自衛隊を目指している人はこちらの記事もあわせて参考にしてみてください。志望動機の書き方について詳しくまとめています。
⑧公務員
公務員とは
国や地方自治体に勤務し、公共の福祉や社会の発展に貢献して住民の暮らしを支える仕事
国家公務員は中央省庁での政策立案や国内外の行政活動を担い、地方公務員は市役所や県庁などで地域住民に密接にかかわる行政サービスを提供します。
公務員になるには、一般教養や論作文、面接などで構成される各種公務員試験に合格する必要があります。希望職種や自治体によって試験内容が異なっているケースがあるため、受験をするのであればホームページ(HP)や説明会で内容を確認しましょう。
公務員は細かい事務作業や確認業務が多いため、正確かつ慎重に業務を進められる人が向いています。また住民や他部署との調整も多く、相手の立場を理解して話をするコミュニケーション能力も求められます。
公務員の選考に役立つ内容に関しては以下で解説しているので、気になる記事をチェックしてみてください。
公務員のエントリーシート(ES)
公務員を目指す理由が必ず伝わるエントリーシートの書き方|12例文
公務員の自己PR
公務員の自己PRのコツは? 評価される作り方を例文付きで解説
公務員面接での質問
公務員面接の頻出質問15選|意図を汲み取った回答で好印象を残そう
所要時間はたったの3分!
受けない方がいい職業を診断しよう
就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。
就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。
- 自分に合う職業がわからない人
- 入社後のミスマッチを避けたい人
- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人
⑨キャビンアテンダント(CA)
キャビンアテンダント(CA)とは
航空機内で安全かつ快適なフライトをサポートする仕事
CAは離着陸時の安全アナウンスやシートベルト確認、機内食のサービス、急病人が出た場合の応急処置などをおこないます。
CAになるには、ANAやJALといった航空会社の採用試験に合格しなければなりません。
特定の学部や学科で学んでいる必要はありませんが、CAの専門学校に入学したり、大学に通いながら航空業界で働くために必要なビジネスマナーやコミュニケーション能力を学べるエアラインスクールに通ったりする人もいます。
CAは日本人以外にも対応する機会が多く、英語でのコミュニケーション能力が必要です。そのため、海外留学経験がある人やTOEICやTOEFLのスコアが高い人が向いています。
CAを目指すにあたって必要な英語力は、各社採用ページでも公表されていますが、おおむねTOEIC600点以上を有することが望ましいとされています。
これはTOEFLのスコアに換算すると、ITPテストで503点程度、iBTテストで62点程度といわれています。
キャビンアテンダントの倍率については以下のQ&Aでキャリアコンサルタントが解説しているので、ぜひチェックしてください。
⑩タクシードライバー
タクシードライバーとは
タクシードライバーとは、普通自動車第二種運転免許を持って乗客を目的地まで安全かつ快適に運ぶ仕事
タクシードライバーは通勤や通院、通学、観光、買い物など乗客のさまざまなニーズに応じ、移動サービスを提供しています。
タクシードライバーに必要な普通自動車第二種運転免許を取得するには、まず普通自動車第一種運転免許を受けてから運転経歴が3年以上必要です。
仕事中は基本的に車を運転することになるため、普通自動車第二種運転免許は普通自動車第一種運転免許よりも取得が難しくなっています。
またタクシードライバーは、安全に乗客を送り届けることが大事です。そのため、交通ルールを守るのはもちろん、地理や道に詳しくて適切なルートを判断できる人が向いています。
⑪バスドライバー
バスドライバーとは
公共交通機関であるバスを運転し、定められたルートに沿って乗客を安全に送り届ける仕事
バスドライバーは路線バスや高速バス、観光バスなどで活躍し、運転だけでなく乗降時のサポートや車内アナウンスなどもおこないます。
バスドライバーとして働くには、運転するバスのサイズに応じた第二種運転免許が必要です。ただし、エントリー時に資格の有無は問われず、内定獲得後に自動車学校に通って取得するケースが一般的です。
バスは決まった時間に決まったルートを走行する定時運行が求められるため、スケジュール管理能力が欠かせません。また多くの乗客を運ぶバスドライバーには、安全運転を徹底し、責任を持って運行できる人が適しています。
- 人をサポートする仕事として、バスドライバーの魅力を教えてください。
人々の生活や思い出作りの一部を担えるのが魅力
バスドライバーは、公共交通機関の要として多くの人々の生活を支える重要な仕事であり、地域社会に大きな貢献ができます。
その魅力は、自分の運転技術と判断が安心・安全な移動、ひいては乗客の信頼につながり、乗客から直接感謝の言葉をもらえる、人々の暮らしに直結したやりがいにあります。
地域密着型の路線バスでは住民との交流が生まれたり、高速バスや観光バスでは特別な移動の思い出を支える役割を担ったりもします。また、定時運行が求められるため、時間管理能力や責任感が自然と身に付きます。
さらに、公共交通機関として安定した雇用環境があり社会的にも安定した職種である点、路線バスから観光バスまで多様な運行形態があり、自分の興味やライフスタイルに合わせてキャリアを選択できる点も魅力です。
⑫ホワイトハッカー
ホワイトハッカーとは
ホワイトハッカーとは企業や組織のシステムの脆弱性を見つけ出し、サイバー攻撃から守るための対策を講じる仕事
ホワイトハッカーはシステムの脆弱性診断やセキュリティの強化、社員に対するセキュリティ教育をおこない、不正アクセスやデータ漏洩を未然に防ぎます。
ホワイトハッカーには情報セキュリティやプログラミングの知識が求められるため、情報工学部系の学士や修士を取得するのが一般的です。
また、応用情報技術者試験や情報処理安全確保支援士などの情報やセキュリティに関する国家資格を取得しておけば、知識やスキルをアピールできて選考に有利に働く可能性があります。
またサイバー攻撃は日に日に高度化していて、企業や組織の情報を守るためには知識やスキルのアップデートが欠かせません。そのためホワイトハッカーには、ITへの興味関心が強く新しい知識を身に付けるために学び続けられる探究心のある人が向いています。
ホワイトハッカーを目指す人には、セキュリティエンジニアとしてキャリアを積んで知識やスキルを磨くのがおすすめです。
こちらの記事ではセキュリティエンジニアの魅力や新卒で入社する方法を解説しているので、キャリアプランの描き方をイメージするためにもぜひチェックしてみてください。
⑬手話通訳士
手話通訳士とは
手話を使って聴覚障がい者と耳が聞こえる人とのコミュニケーションをサポートする仕事
手話通訳士は医療、教育、就職、裁判といったさまざまなシチュエーションで活躍し、情報伝達の架け橋となります。手話通訳士になるには、国家試験の手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)への合格が必要です。
ただし、政見放送や裁判などの特定の状況を除けば、手話通訳士ではなくても手話通訳の業務に携われます。したがって、手話通訳の仕事をしながら手話通訳技能認定試験の合格を目指すことも可能です。
また手話通訳士として円滑なコミュニケーションをサポートするためには、聴覚障がい者の気持ちや立場を尊重し、信頼関係を構築する必要があります。そのため、相手に寄り添い、思いやりを持って接することができる人が手話通訳士に向いているのです。
⑭理学療法士
理学療法士とは
病気やケガ、加齢などで身体機能が低下した患者に対して、リハビリをおこなって身体機能の回復や維持をサポートする仕事
理学療法士は病院やリハビリ施設、福祉施設といったさまざまな場所で患者一人ひとりの状態に合わせた個別のリハビリプランを作成し、歩行訓練や筋力トレーニングなどを通して日常生活動作の改善を支援します。
理学療法士になるには、厚生労働省が指定する大学や専門学校などの理学療法士養成施設のカリキュラムを修了し、国家試験の理学療法士国家試験に合格しなければなりません。
カリキュラム修了予定の学生が受験ができるため、スムーズに進んだ場合、大学なら4年、専門学校なら3年で理学療法士として働けるようになります。
リハビリは長期間に及ぶことが多いため、理学療法士には根気強くサポートを続けられる忍耐力のある人が向いています。また、リハビリに対して不安や悩みを抱えている患者も多いです。
患者が少しでも早く身体機能を取り戻すためには、不安なくリハビリに取り組めるように親身になって寄り添う姿勢が重要です。そのため、相手の立場に立って考えられる人が理学療法士に向いています。
理学療法士の仕事内容やトレンドについてはこちらの記事で解説しています。理学療法士に少しでも興味を持っているのであれば、ぜひチェックしてみてください。
⑮家事代行
家事代行とは
依頼者の自宅を訪問し、掃除や洗濯、料理、整理整頓などの家事を代わりにおこなう仕事
家事代行は、夫婦共働きで忙しい家庭や自身ですべての家事をこなすのが難しい高齢者、少しでも事業の時間を確保したい経営者など、多種多様なニーズに対応するためにさまざまな場所で働きます。
家事代行として働くにあたって特別な資格は必要ありませんが、家事に関する知識やスキルは不可欠です。もし国家資格の調理師免許や民間資格の整理収納アドバイザーを保有していれば、高度な人材として良い待遇で働ける可能性があります。
また依頼者によって重要視するポイントやニーズが異なるため、依頼者のニーズを汲み取って行動できる気配り上手や、家庭ごとに合わせて柔軟に対応できる人が家事代行に向いています。
- 新卒で家事代行の求人はありますか?
家事代行のニーズは近年高まる傾向を見せている
聞きなじみがないかもしれませんが、家事代行の仕事は単身者世帯や高齢者世帯、共働き世帯などの増加を背景に近年、着実に市場を拡大させている業界の一つです。
この動きは今後もまだまだ続くとされていて、新たなインフラの一つになるのではないかとさえいわれています。
老舗企業だけに限らず、大手系列企業を中心に新規参入も比較的活発で、担い手も不足しているという現状もあり、新卒対象の募集も発生しています。
⑯介護士
介護士とは
高齢者や障がい者の日常生活をサポートし、安心して暮らせる環境を提供する仕事
介護施設やデイサービス、訪問介護など、働く場所により支援内容は異なりますが、基本的な仕事には食事や入浴、排泄などの日常生活の介助、リハビリの補助、生活相談が含まれます。
また大学や専門学校で介護を専攻していなくても、介護職員初任者研修を受講すれば基礎から学んで介護士として働くことが可能です。
そして3年以上の実務経験を積んだ後、介護で唯一の国家資格である介護福祉士に合格することで、知識やスキルを身に付けながらキャリアの幅を広げられます。
なお、利用者との関係性が築けていなければ言うことを聞いてもらえない可能性があるため、介護の仕事をスムーズに進めるためには利用者との信頼関係が重要です。したがって、利用者の気持ちに寄り添い、安心感を与えられる人が介護士に向いています。
介護職の仕事内容や適性はこちらの記事で解説しているので、ぜひ確認して相性を確かめてみてください。
⑰社会福祉士
社会福祉士とは
身体的・精神的障がいや貧困、虐待などによって生活上の問題を抱える人に対し、福祉の観点から相談・支援をおこなう仕事
相談に乗ったり、医療・教育機関と連携を取ったり、暮らしやすい環境を整備したりして、利用者の自立や生活改善をサポートします。
社会福祉士になるには、福祉士系の大学や短大などに通って社会福祉士試験の受験資格を得た後、国家試験に合格する必要があります。資格取得後は、福祉施設や医療機関、自治体、教育機関などで勤務可能です。
なお、利用者には心に大きな傷を負い、精神的に不安定な人も多いです。そのため、利用者の状況や気持ちに共感し、思いやりを持って接する能力がなければ会話をできないケースもあります。
したがって、介護福祉士として多くの利用者をサポートするためには、共感力と相手の立場に立って考える力が重要です。
福祉業界についてはこちらの記事で解説しているので、「福祉に従事する人が具体的に何をしているかイメージが難しい」という人はぜひ読んでみてください。
- 人をサポートする仕事としての、社会福祉士の魅力を教えてください。
人や社会と深くかかわり直接支えるやりがいが魅力
社会福祉士は、福祉に関する幅広く活躍ができる点が一つの魅力です。
高齢者福祉や障害者福祉だけでなく、医療や教育分野においても関連職種と連携を取りながら専門知識を活かして働くことができ、直接的に奉仕や社会貢献の活動をおこなえる点も魅力です。
加えて、社会福祉士は国家資格でもあるため一般的な職種よりも専門性が高く、地域においてなくてはならない存在であるため、長きにわたって仕事がしやすいです。
相談事を聞くことが得意な人や、困っている人を支えたいという気持ちがある人は向いている仕事といえます。
知識やスキルを伝える仕事5選
知識やスキルを伝える仕事
勉強を教えたり、スキルを伝えたりする仕事でも人をサポート可能です。ここからは知識やスキルを伝えて人をサポートする仕事を解説します。人に何かを教えるのが好きな人は、適性がある可能性が高いのでぜひチェックしてみてください。
①教師
教師とは
小学校や中学校、高等学校で児童・生徒に勉強や社会性、コミュニケーション能力などを教え、成長をサポートする仕事
授業以外にも成績評価や保護者対応、学校行事の運営、クラブ活動の指導なども教師の仕事です。
そして教師になるためには、大学や短大で教職課程を履修して教員免許を取得し、各自治体もしくは各学校が実施する教員採用試験に合格する必要があります。
教育大学や、教育学部以外でも教職課程のある学部に進学してカリキュラムを修了することで教員免許を取得可能です。
教師は授業についていけなくなったり、人間関係で悩んでいたり、体調が崩れていたりする児童・生徒の変化に敏感に気付く必要があります。もし変化を見逃すと、不登校やいじめといったさまざまなトラブルに発展する可能性があるためです。
したがって、児童・生徒の細かい変化に気付ける人は教師に向いているといえます。
- 長い残業時間やモンスターペアレントの存在など、教師の働き方の悪い面をニュースで目にする機会が多いですが、教育現場の待遇改善は進んでいますか?
近年は教師の働き方改善の取り組みが進みつつある
私は教員免許を持っていて、教員からの声を聞くことが多くありますが、教育現場の待遇改善は進行中です。
文部科学省が「働き方改革」を推進していて、授業準備や成績処理にICTを導入することで業務効率化を図っています。
また、部活動指導の外部委託など負担軽減の動きも徐々に広がっています。教員不足への対応としては、新規採用の増加や給与の引き上げや、育児・介護休暇の充実などがまさに進行中です。
さらに、モンスターペアレントへの対応についても、保護者対応の専門窓口を設ける学校が増加しています。
これらの改善策は学校によってもばらつきがあり、まだ途中段階ですが、現場での改革意識は高まっています。
教育現場の実情を理解しつつ、自身の成長と現場への貢献を目指してぜひ挑戦を検討してみてください。
②塾講師
塾講師とは
学校の授業を補完したり、受験対策をおこなったりして子どもの学力を伸ばす仕事
塾講師には個別指導や集団授業において、生徒のレベルやニーズに合わせた指導が求められます。
塾講師になるために特別な資格は必要ありませんが、子どもに勉強を教えられる学力や指導力は必須です。わかりやすく伝える力は指導経験を積むことで磨かれるため、塾講師に興味がある人はアルバイトとして働いておくと選考で高く評価されるかもしれません。
塾講師には生徒の勉強に対するモチベーションを保ちつつ受験やテストに向けて長期的にサポートできる人が向いています。
さらに自身も受験経験が豊富であれば、志望校合格に向けた勉強法や戦略もアドバイスできるため、生徒の目標達成をサポートしやすくなります。
③保育士
保育士とは
保育園や幼稚園で子ども達の成長を見守り、基本的な生活習慣や社会性を育む仕事
保育士は遊びや日々の活動を通じて子ども達の発達に合わせたサポートをおこない、家庭との信頼関係を築きながら成長を支援します。
保育士資格がなくても保育補助として保育に携わることができますが、クラスの担任を受け持つことはできません。その場合、担任の補助役として子どもとかかわったり、事務作業をおこなったりします。
そのため、保育系の大学や専門学校のカリキュラムを修了し、保育士試験を受験するのが保育士になる人の一般的なルートです。
好奇心旺盛で多くのことを吸収する園児にとって保育園は大きく成長できる場です。保育園での過ごし方が小学校の生活に影響を与えるケースもあるため、保育士は子ども達が過ごしやすい環境を作る必要があります。
したがって、明るく親しみやすい性格で、子ども達が安心して話しかけられる雰囲気の人は保育士に向いています。
こちらの記事では志望動機に必要な要素を解説しているので、保育士に興味がある人は確認して志望動機を作成するイメージをつかんでみてください。
④インストラクター
インストラクターとは
フィットネスやスポーツ、ヨガ、音楽など特定の分野で指導をおこない、受講者が目標に向かって成長できるようサポートする仕事
インストラクターはクラス形式やマンツーマンといったさまざまな形式で受講者を指導し、新技の獲得や基礎基本の習得など個人の目標達成を支援します。
インストラクターになるには、指導する分野の専門知識や技術が欠かせません。また、ダイビングインストラクターの場合は、ダイビングライセンス(Cカード)に加えてPADIやNAUIといったダイビング指導団体が認定するインストラクターライセンスの取得も必要です。
インストラクターには受講者の体力や理解度、スキルレベルに応じた指導が求められます。初心者が無理なく取り組めるように基本を丁寧に説明したり、上級者には高度な知識やスキルを伝えたりと、相手の立場に立って行動できる人はインストラクターに向いています。
⑤パーソナルトレーナー
パーソナルトレーナーとは
顧客の体力やトレーニング目的に合わせてマンツーマンで運動指導やフィットネスサポートをする仕事
パーソナルトレーナーはトレーニング方法を伝えるだけではなくフォームのチェックやモチベーションの維持、食事指導や生活習慣に関するアドバイスも大切な役割で、顧客の目標達成にコミットします。
顧客の目標達成に向けてトレーニングサポートや食事指導をおこなうパーソナルトレーナーには、運動生理学や解剖学、栄養学などの専門知識が欠かせません。
必須資格はありませんが、民間資格のNESTA PFTやJATIを取得しておくとトレーニング指導に関する専門的な知識が身に付いていることを証明できます。
また体への負担を抑えつつボディメイク、ダイエットをするには、長期的なトレーニングや食事管理が大切です。しかし、頑張っても体に大きな変化が出なければ、モチベーションの維持は難しいものです。
やる気を失いかけた顧客に対してトレーニングや食事管理を楽しく感じてもらう必要があるため、明るくポジティブでモチベーションを高められる人はパーソナルトレーナーの適性があるといえます。
- 人をサポートする仕事として、パーソナルトレーナーの魅力を教えてください。
顧客のやる気をモチベーターとして伴走できる点が魅力
人をサポートする点はもちろん魅力ですが、人のやる気を引き出す「モチベーター」としての役割の方が大きいかもしれません。
個人ではどうしてもやる気が起きなかったり、一人では乗り越えられない壁を感じたりする場面でも、パーソナルトレーナーがいることでともに乗り越えられるようになります。
そのためにパーソナルトレーナーは「伴走する」という感覚に近いです。
このように人を引っ張っていくリーダーシップが発揮でき、結果を出させることが楽しいと感じる人にとっては非常に魅力的な仕事です。また、専門的な知識を活かして仕事ができるメリットもあります。
人の心をケアする仕事7選
仕事や勉強、人間関係、スポーツなどに悩みや不安があると、心のコントロールが難しくなります。壊れたメンタルを自分で改善するのは難しく、回復に向けては専門家による精神的なサポートが必要です。そこで活躍するのが人の心をケアする仕事です。
ここからは、人の心をケアして精神的にサポートする仕事を説明します。友人から相談される機会が多かったり、相手に寄り添って共感できたりする人は向いている可能性があるため、ぜひチェックしてみてください。
①スクールカウンセラー
スクールカウンセラーとは
生徒の心の健康をサポートする職業です。生徒が抱える悩みやストレスについて相談に乗り、安心して学校生活を送れるように支援する仕事
スクールカウンセラーは教師や保護者に対しても助言やサポートをおこない、子どもの健やかな成長を促す役割を果たしています。
スクールカウンセラーには、臨床心理学や教育心理学といった専門知識が求められます。スクールカウンセラーという資格は存在していませんが、大学や大学院で心理学を専攻し、臨床心理士や公認心理師といった資格を取得してからスクールカウンセラーとして働くのが一般的です。
また、精神的に不安定な生徒は悩みを打ち明けないケースが多いです。そのため、人の表情や態度の変化といった小さなサインに気付ける観察力のある人がスクールカウンセラーに向いています。
- 心理系の学部に通っていたり資格を持っていたりしないと、スクールカウンセラーを目指すのは難しいのでしょうか?
難易度が高い分高度なスキルが求められることがほとんど
近年のスクールカウンセラーなどの募集を見ると、臨床心理士や公認心理師等の資格を有していることや、一定の現場経験を有していることが条件として設定されていることが多いです。
これは、子ども達を中心とした学校の複雑な問題に対して、個人の経験や勘だけによるサポートでは対応が難しいと考えられているからにほかなりません。
心理系の大学に通うことや、臨床心理士や公認心理師などの資格を取ることだけがすべてではありません。
しかし、何らかの形で体系的にカウンセリングスキルを学び身に付けておくことが、この仕事に就いて活躍する可能性を高めてくれます。
②産業カウンセラー
産業カウンセラーとは
仕事に従事する人のメンタルヘルスを守る仕事
産業カウンセラーは、職場におけるストレスや人間関係の問題、キャリア形成の相談など、幅広いテーマについてカウンセリングをおこない、社員が安心して働ける環境づくりをサポートします。
産業カウンセラーになるには、日本産業カウンセラー協会が認定する産業カウンセラー試験の取得が一般的です。資格取得後は民間企業のほか、公的機関や医療・福祉施設、非営利団体などでも活躍可能です。
また、相談者が悩みを包み隠さず打ち明けてくれれば、心のケアに必要なアドバイスをしやすくなります。そのため、傾聴力があって相手が話しやすい雰囲気づくりが得意で、友人から相談される機会が多い人は産業カウンセラーに向いています。
産業カウンセラー専任として採用の募集をかけている企業は、実際にはさほど多くない印象です。
大企業の一部では人事が産業カウンセラーを兼任でおこなっていたり、中小企業の場合は外部の産業カウンセラーや従業員支援プログラム(EAP)に依頼したりしていることが多いです。
産業カウンセラーの仕事をこなすには、心理学の知識が必要。産業カウンセラー以外にも心理学を仕事に活かせる仕事はこちらの記事で解説しているので、どのような職種があるのかチェックしてみてください。
③メンタルトレーナー
メンタルトレーナーとは
アスリートやビジネスパーソンの目標達成に向けて精神的にサポートし、最大限のパフォーマンスを引き出せるようにする仕事
メンタルトレーナーは集中力の維持やストレスのコントロール、自信の強化、モチベーションの向上といった心のケアを通じ、個人の能力が最大限に発揮されるように支援します。
メンタルトレーナーには、心理学やスポーツ心理学、コーチングの知識が必須です。そのため、専門の養成講座や大学で心理学を学んだり、民間資格のJADP認定スポーツメンタルトレーナーやメンタルトレーニング検定を取得したりするのが一般的です。
なお、メンタルトレーナーはカウンセリングで悩みや不安を引き出し、感情や思考を理解することで具体的なアドバイスをしやすくなります。そのため、相談者の話を上手に引き出せる傾聴力のある人は、メンタルトレーナーの適性があるといえます。
④電話相談員
電話相談員とは
電話で相談員の悩みや不安をヒアリングし、サポートやアドバイスを提供する仕事
電話相談員は健康や人間関係、仕事、学業などのさまざまな悩みに対応し、相談者が抱える不安を和らげる役割を担っています。
また電話相談員になるには特定の資格は不要ですが、大学で心理学を専攻したり、心理カウンセラーとしてアルバイトをしたりすると相談やアドバイスに役立ちます。
言葉遣いや声のトーンが柔らかくなければ、相談者はリラックスしてカウンセリングを受けられないかもしれません。そのため、リラックスできる雰囲気を作り出せる落ち着いた声のトーンの人は、電話相談員に向いているといえます。
電話相談員の仕事は、ボランティアや時給制のアルバイトが多いです。独身や実家暮らしで生活費を抑えられる場合なら生活が成り立つこともありますが、単体の収入のみで生活するのは難しい場合が多いです。
そこで、生計を成り立たせるために電話相談員の仕事を副業として、より給与の高いキャリアコンサルタントや心理カウンセラー、メンタルトレーナーなどを兼務している人も多くいます。
そのため、中長期的な収入面や働き方を検討しつつ、キャリア形成を視野に入れて選択することが重要です。
⑤占い師
占い師とは
相談者が抱える悩みや迷いに対して、タロットカードや手相、星占い、四柱推命などの占術を用いてアドバイスや指針を提供する仕事
占い師の業務は単なる未来予測に留まらず、相談者の悩みに寄り添いながら心の安定や自己理解の促進をサポートする役割も果たします。
また、占い師になるためには各種占術に関する専門的な知識と技術の習得が不可欠です。独学や養成講座、専門スクールで占術を学んだ後は、親戚や友人など身近な人を占ってスキルを磨くと良いです。
そして知識とスキルが身に付いたら、占い館の求人に応募したり、ココナラやジモティーなどのオンラインプラットフォームに掲載したりして仕事を獲得していく人もいます。
占い師は占い結果とそれにともなうアドバイスによって、相談者の人生が好転するようにサポートする必要があります。
そのため、相談者自身が未来を前向きにとらえ、より良い選択ができるように的確かつ柔軟なアドバイスを提供できる思慮深い人が占い師に向いています。
⑥コーチング
コーチングとは
ビジネスパーソンやアスリート、自己成長を目指す個人に対して、目標達成や自己実現に向けてサポートする仕事
コーチングは質問やコミュニケーションを通じて顧客の思考を引き出した後、目標に向けて具体的な行動計画を作成し、前向きに取り組めるように導きます。
コーチングは特定の資格がなくてもできますが、コーチングスクールに通って国際コーチング連盟(ICF)認定資格や日本コーチ連盟のコーチング資格を取得するのが一般的です。
コーチングでは悩み解決や目標達成に向けたアドバイスよりも、顧客に自分自身の考えや感情に気付いてもらうことが重要視されています。自身の考えた行動や計画でないとモチベーションを保ちにくく、目標達成が難しいためです。
顧客の本音や真の目標を引き出すことが重要になるため、聞き上手な人がコーチングに向いています。
- コーチングで生活をしている人は、どのように仕事を獲得しているのでしょうか?
Webを活用して知名度を高める方法が有効
よくある方法としては、YouTubeやSNS、ブログなどで情報を発信してファンを増やすというものです。
専門知識を持った人が集まってコミュニティ化している特定の分野もありますが、コーチングを得意とする人は技能もそれぞれなので、個人でおこなうことが一般的のように思われます。
まずは集客するための見込み客をどれだけ事前に集めることができるかがポイントになってきます。
ある程度の新規顧客を定期的に集めることができれば、ワークショップやセミナーなどで多人数に向けてコーチングをおこなうことも可能です。
またそのなかで人とのつながりが生まれてくれば、新たに法人向けの依頼など仕事も増えてくるような形も考えられます。
⑦臨床心理士
臨床心理士とは
心の問題やストレスに悩む人の相談に乗り、心の健康をサポートする仕事
臨床心理士は病院や学校、福祉施設、企業などで働き、カウンセリングや心理療法を実施して相談者の自己理解や問題解決を促進します。
また臨床心理士になるには、日本臨床心理士資格認定協会が実施する資格試験への合格が必須条件です。学生がこの試験の受験資格を得るためには、指定の大学院や専門職大学院で臨床心理学のカリキュラムを修了する必要があります。
臨床心理士が相談者を適切にサポートするためには、相談者の悩みや不安を引き出す必要があります。相談者に関する情報が不足している状態では、的確なアドバイスの提供が難しいためです。
したがって、相手がリラックスできる空間を作り、否定することなく話をじっくり聞ける人が臨床心理士に向いているといえます。
人の話を聞く仕事はこちらの記事で解説しているので、ぜひ読んで仕事内容への理解を深めてください。
チャレンジする人をサポートする仕事7選
売り上げアップやより良い環境の実現など、独自の目標に向けて頑張っている人が社会にはたくさんいます。そのような人達の業務を代行したり、方向性が合っているか確認したりすることで個人や会社の挑戦をサポートする仕事があります。
ここからは、チャレンジする人をサポートする仕事を説明します。挑戦が成功するまで支えることに魅力を感じる人は、ぜひチェックしてみてください。
①キャリアアドバイザー
キャリアアドバイザーとは
求職者や転職希望者の就職活動やキャリア形成をサポートする仕事
キャリアアドバイザーは企業紹介だけではなく、面接対策や履歴書の添削、企業選びのアドバイスなどをおこない、相談者が納得感を持って就職・転職できるように支援します。
キャリアアドバイザーの勤務先は、転職エージェントやハローワーク、大学のキャリアセンターなどさまざまです。そして、キャリアコンサルタントの国家資格を保有していれば、専門的な知識やスキルの証明につながり、専攻で有利に働く可能性があります。
また相談者のスムーズかつ満足度の高い転職に向けては、求職者のスキルや経験、キャリアに対する希望を見極めたうえで適切な就職先を紹介することが重要です。
そのため、多くの選択肢がある場合でも相談者の状況を考慮しながら働き方のサポートをしたいと思う人は、キャリアアドバイザーに向いています。
私は実際にキャリアコンサルタントとして仕事をしていますが、人生において仕事が占める割合はとても大きいです。
仕事や働き方を変えることは人生を変えることと言っても過言ではありません。サポートを通して、少しずつでもその人の人生が変わっていく瞬間に立ち会えることが、この仕事の大きな魅力だと感じています。
②経営コンサルタント
経営コンサルタントとは
企業の経営課題を解決し、業績向上や規模の拡大を支援する仕事
経営コンサルタントは企業の戦略策定や業務改善、新規事業の立ち上げ支援、財務管理のアドバイスといった幅広い業務に携わり、企業の目標達成をサポートします。
経営コンサルタントに必須資格はありませんが、経営学修士(MBA)や中小企業診断士などがあると顧客からの信頼につながりやすく、仕事で役立つ機会が多いです。
また経営コンサルタントは企業が抱えている顕在的な課題だけではなく、潜在的な課題を解決することで、顧客とより深い信頼関係を築けます。そのため、分析力と問題解決能力がある人は、経営コンサルタントとして企業に多くの価値を提供可能です。
- 経営経験のない新卒社員にアドバイスを求める経営者や企業はいるのでしょうか。相手にされる気がしなくて不安です……。
上司や先輩と協力して案件をこなせるため問題ない
私も新卒でコンサルティング業務を行っていましたが、経営経験がない新卒社員相手であっても、経営者や企業がアドバイスを求めることは不自然ではありません。
コンサルタントに求められるのは、経験よりも客観的な視点や分析力、徹底した事前リサーチ、論理的な問題解決能力であり、必ずしも年の功とはいえないからです。
そもそも、コンサルタントは一人で提案するわけではなく、チームで経験豊富な上司や先輩とともに案件を進めることも多いので、過度に不安を感じる必要はありません。
もちろん、身なりや立ち振る舞いなどが幼稚であることは許されませんが、業界や企業に染まっていない柔軟な発想や、若手ならではの視点などが期待されるシーンもあります。
努力を続け、質の高い提案を心掛けることで、経営者や企業にとって信頼される存在になれる可能性があります。
③芸能マネージャー
芸能マネージャーとは
俳優やアーティスト、モデル、芸人などの芸能人の活動をサポートする仕事
芸能マネージャーは仕事のスケジュール管理や出演交渉、現場でのサポート、メディアや関係者との連絡調整、プロモーション活動の実施などさまざまな仕事をおこない、芸能人が目の前の仕事に集中できる環境を作ります。
芸能マネージャーになるためには、各芸能事務所が実施する採用試験に合格しなければなりません。芸能マネージャーを志望する学生は多いため、内定を獲得するためには狭き門を突破する必要があります。
また、突発的なスケジュール変更やトラブルが頻発するのが芸能業界です。芸能マネージャーは柔軟に対応してスケジュールやタスクを調整しなければならないため、臨機応変に対応できる人には適性があるといえます。
芸能マネージャーに興味がありながら「必要な資格や学歴はあるのか」「選考では何を見られるのか」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。こちらではキャリアコンサルタントによるQ&Aを公開しているので、芸能マネージャーに興味がある人はぜひチェックしてみてください。
④青年海外協力隊
青年海外協力隊とは
日本政府の国際協力機関であるJICA(国際協力機構)が派遣するプログラムで、おもに発展途上国の現地の人々の生活改善や技術支援をおこなうボランティア
青年海外協力隊の活動分野は教育や保健医療、農林水産、スポーツ、行政、商業など多岐にわたり、専門的な知識やスキルを活かして現地の人をサポートできます。
青年海外協力隊として派遣されるためには、健康診査や語学力診査などの書類審査とWeb面接を通過しなければなりません。任期は原則2年ですが、短期派遣に応募すれば1カ月〜1年未満での帰国も可能です。
また青年海外協力隊は異なる文化や生活環境のなかで活動するため、現地の人の価値観や生活スタイルを尊重し、適応する力が重要です。
そのため学生時代にグローバルなコミュニティに入っていたり、国際シェアハウスに入居したりして異文化への理解と柔軟な適応力がある人は青年海外協力隊に向いています。
⑤税理士
税理士とは
個人事業主や企業に対して、税務に関するアドバイスや確定申告代行をおこなう仕事
税理士のおもな業務には確定申告や税務相談、相続税対策、節税計画の提案などがあり、顧客が適切に税金を収められるようにサポートします。
税理士として働くためには税理士試験に合格し、税理士登録を受ける必要があります。
全11科目で構成されている税理士試験は、必須科目の簿記論と財務諸表論の2科目、選択必須科目の法人税法と所得税法のいずれか1科目、税法3科目の合計5科目に合格しなければなりません。1年で5科目に合格する必要はないため、数年かけて取得するのが一般的です。
また、税務申告や会計処理で細かい計算や税法の解釈を適切に実施しなければならない税理士には、スピード以上に正確性が求められます。そのため、慎重で集中力の高い人が税理士に向いているといえます。
⑥秘書
秘書とは
企業役員や経営者をサポートし、業務の効率化を図る仕事
秘書のおもな仕事にはスケジュール管理や会議の準備、資料作成、来客対応、電話応対、社内外の調整業務などがあります。
秘書になるには企業に総合職として入社し、秘書課に配属されるのが一般的なルートです。ただし希望通りの配属になるとは限らないため、選考で秘書になりたい思いを伝えたり、民間資格の秘書検定を取得したりして熱意やスキルをアピールしましょう。
また現在はオンライン秘書も普及していて、クラウドワークスやランサーズといったクラウドソーシングサービス、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで仕事を受注するチャンスがあります。
秘書は役員や経営者の仕事の効率化を図る仕事なので、指示通りに動くだけではなく先回りして行動することが求められます。そのため秘書は、相手の考えを汲み取って行動する気配りができる人に向いている仕事です。
なお、「秘書はどんな仕事をするのか」「どんな人が向いているのか」と疑問に思っている人もいるでしょう。以下の記事では秘書について解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
秘書に向いている人
秘書に向いている人の特徴5選! 仕事内容や有利になる資格も解説
秘書の仕事のつらさ
秘書の仕事がつらいと言われる6つの理由|魅力や合う人の特徴も解説
就活での秘書検定のアピール方法
秘書検定は就職に活かせる! 取得メリットやアピール方法を徹底解説
秘書検定の履歴書への書き方
秘書検定は何級から履歴書に書ける? 正しい書き方とアピールのコツ
⑦営業
営業とは
業や個人の顧客に自社の商品やサービスを提案し、契約や販売を通じて売り上げを上げる仕事
営業は新規開拓営業や既存顧客との関係強化、見積書や提案書の作成、契約交渉、アフターフォローなど、多岐にわたる業務を担当し、企業の収益に直結する役割を担います。
営業として働く方法には、総合職採用で配属されたり、営業専門の会社に入社したりする選択肢があります。営業の長期インターンシップを実施している企業もあるため、興味がある人は適性を確認するためにも参加してみましょう。
またサポートを目的として提案内容を承諾してもらうためには、顧客との信頼関係が欠かせません。信頼度が低い営業の提案を聞き入れる顧客は少ないためです。
そのためチームをまとめて信頼を獲得したり、営業のインターンで会話を通じて信頼関係を築いたりした経験がある人は営業に向いています。
なお、企業の売り上げにつながる営業はさまざまな業界で活躍可能です。以下の記事では業界ごとの営業の特徴や種類による仕事内容を解説しているので、より営業への理解度を深めたい人はぜひチェックしてみてください。
不動産営業
不動産営業に向いてる人の6つの特徴|具体的な業務と未経験からなる方法
保険営業
なぜ保険営業はやめとけといわれる? 10の理由と業界のリアル
リテール営業
リテール営業とは? 仕事内容や5つの必須スキルを専門家と解説
代理店営業
代理店営業が丸わかり! 隠れた3つの魅力や適性の見極め方も紹介
反響営業
反響営業とは? 入社後のイメージを膨らませるポイントを徹底解説
インターンに参加するかどうか迷っている人に向けて、こちらの記事ではインターンの必要性を解説しているので、確認して判断材料にしてください。
就活のプロが解説! 人をサポートする仕事から適職を見つけるコツと注意点
ここまで読めば、人をサポートする仕事の業務や向いている人の特徴を理解できたのではないでしょうか。しかし、「本当に自分に向いている仕事なのかわからない」「人をサポートする仕事を選ぶ際の注意点を知りたい」と考えている人もいるでしょう。
多くの学生をサポートしてきたキャリアコンサルタントに、人をサポートする仕事から適職を見つけるコツと注意点を聞いてみます。
アドバイザーコメント
他人から見た自分を把握するのがポイント
世の中に存在する数多くの「人をサポートする仕事」のなかから、個々にとっての適職を見つけるために私が考えるコツは、「一番信頼している人に聞く」ということです。
まず最初に、あらゆる情報を頭の中に入れて知識として入れたら、その後しばらくは何も見ず誰にも聞かないように情報を遮断しましょう。
その次に、自分が信頼のおける家族や友人や知人に向かって「私って何が得意だと思う?」と聞いてみてください。不安であれば2〜3人に聞くと良いかもしれません。
他者から見える姿というのはあなた自身を忠実に表しています。そこにヒントが隠されている場合が多いので、仕事や生き方を考えるうえで大きなヒントになります。
やりたいことよりも得意なことに着目しよう
注意点としては、「自分がやりたいこと」と「向いていること」を混同しないということです。仕事でいきいきと働くことができるのは「自分が得意なこと」であって、「やってみたいこと」が必ずしも充実感につながるとは限りません。
まとめると、手順としては「①自分の得意なことは何か他人に聞く」「②やりたいことではなく得意なことを選ぶ」です。
就活のモチベーションにしよう! 人をサポートする仕事の4つの魅力
人をサポートする仕事の魅力
- 専門的な知識を活かして社会に貢献できる
- 直接人とかかわる機会が多くて感謝の言葉をもらいやすい
- 未来を創る人材を育てられる
- 多種多様な考え方を持つ人と接することで視野が広がる
人をサポートする仕事は人気の職種が多く、時間をかけて対策をしても選考に落ちる可能性があります。準備をして臨んだ選考で結果が出なければ、就活に対するモチベーションが低下することもあるでしょう。
就活に対するモチベーションを維持するためには、人をサポートする仕事の魅力を知っておくことが大切です。ここからは、人をサポートする仕事の4つの魅力を解説します。
①専門的な知識を活かして社会に貢献できる
人をサポートする仕事には、心理学や福祉、医療といった専門知識を活かす場面が多いです。自身の持っている専門知識で困っている人を助けたり、チャレンジを支援したりすれば社会に貢献している実感を得られます。
たとえば、カウンセラーや看護師は人々の健康を支え、安心して生活できる環境の整備に貢献しています。また、スポーツインストラクターやパーソナルトレーナーは、健康的な暮らしをサポートしているのです。
このように、人をサポートする仕事では専門的な知識やスキルを活用し、社会全体にプラスの影響を与えられます。
- 現在は大学生で、誰かに何かを教える機会が多くありません。それでも知識やスキルを伝えられるようになるのでしょうか。
必ずしも経験豊富でなくても伝える力は身に付けられる
知識やスキルを伝える力と、経験の有無には関係性こそありますが、絶対条件というわけでもありません。
実際に、現場経験はなかったものの、工夫を重ねて現場で活躍している人もたくさんいます。経験はあくまで実力を構成する一つの要素でしかないのです。
経験がないことに不安を感じるならば、たとえば伝え方や話し方、伝える知識やスキルの質、あなた自身のキャラクターの見せ方など、そのほかの部分で補う工夫と努力をしましょう。
これらを怠らずに継続することで、経験がなくても現場で活躍できる可能性が高まります。
人の役に立つ仕事の種類はこちらの記事で紹介しているので、チェックして業界研究や企業研究に役立ててください。
②直接人とかかわる機会が多くて感謝の言葉をもらいやすい
人をサポートする仕事は直接人とかかわる機会が多く、感謝の言葉をもらう機会が豊富です。介護職や医療スタッフ、教職員などはサポートする対象者やその家族から「ありがとう」といった感謝の言葉を受け取ることが多いです。
また、スポーツインストラクターは教え子が試合で結果を残せば、喜びを分かち合いながら感謝の言葉もかけてもらえます。厳しく接しなければならないケースもありますが、試合に勝ったり、大会で優勝したりした際の喜びはひとしおです。
このように人をサポートする仕事は職種によらず顧客から感謝されやすいため、やりがいを感じやすいといえます。
人を笑顔にする仕事の種類や向いている人の特徴はこちらの記事で解説しているので、ぜひ確認して適職を見つけてみてください。
③未来を創る人材を育てられる
人をサポートする仕事には、教師や塾講師、保育士といった教育に携わる職種もあります。教育分野や人材育成にかかわる仕事は、未来の社会を担う人材を育てる役割を担っているのです。
社会的な行動が身に付いたり、受験に合格したり、行事をやり遂げたりした際は子ども達の成長を実感し、大きなやりがいを感じられます。目標に向かって成長していく過程を見守り、ともに喜びを分かち合えることも、人をサポートする仕事の大きな魅力です。
また、キャリアアドバイザーや税理士、経営コンサルタントのように大人をサポートする仕事もあります。顧客の挑戦が成功したり、目標を達成したりした際はサポート側も大きなやりがいを感じられます。
子どもをサポートして成長を見守る仕事の一番の醍醐味は、「自分が成長できる」ということだと思います。
どんな仕事でもいえることですが、子どもを直接的にサポートするときには無邪気さや素直さなど、大人だけの関係性では気付けない面に気付かせてくれます。
④多種多様な考え方を持つ人と接することで視野が広がる
人をサポートする仕事の多くは、さまざまな人とかかわります。そのため、異なる背景や価値観を持つ人と接する機会が多く、多様な考え方に触れて視野を広げられるのです。
たとえばカウンセラーや社会福祉士は、多様な価値観やライフスタイルに触れることで、他社の考え方を理解するスキルが身に付きます。
カウンセラーや社会福祉士などの職種では個々の違いを尊重し、相手に寄り添う力が求められるため、自然と共感力や多様な視点を身に付けられるのです。
このように、多様な人々とかかわるなかで、さまざまな価値観を持っている人がいることを実感できるのも、サポートする仕事の大きな魅力です。
人をサポートしているキャリアコンサルタントに仕事のやりがいを聞いてみた
人をサポートする仕事の魅力を把握したうえで、現場で働く人はどのようなやりがいを感じているのか疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで、現在の業務で人をサポートしているキャリアコンサルタントの高尾さん、山路さん、永田さんに仕事のやりがいを聞いてみました。
の一つであるキャリアコンサルタントとして人をサポートしている3人のリアルな意見を読んで、自身のキャリアを考えるきっかけにしてみてください。
多岐にわたる経験を活かしてキャリア支援に従事している高尾さんのやりがい
アドバイザーコメント
多様な経験のなかで人をサポートする仕事の魅力を実感
私はこれまでコンサルタントや人事、マーケター、営業、広報といった多岐にわたる職種を経験し、現在は本業でコミュニティマネージャーを務める傍ら、キャリアコンサルタントとしてキャリア支援をおこなっています。
さまざまな職場での経験を通じ、「人の選択や経験は一つも無駄ではない」と感じ、それぞれの可能性を引き出す手助けがしたいという思いから、キャリアコンサルタントの道を選びました。
事業会社や支援会社など、さまざまな会社で働くなかで、人をサポートする仕事の魅力に気付いたのです。
この仕事のやりがいは、相談者が自分では気付いていなかった思いや目標を発見し、不安を乗り越えて前進する姿を見られることです。特に、自分の強みを理解し、自分らしいキャリアを選択できた瞬間に立ち会う喜びは格別です。
相談者とともに自身も成長しながら他人をサポートできる
一方で、相談者の背景や希望を的確に理解し、適切なアドバイスを提供することの難しさも実感しています。
特に、目標が明確でない場合や新しい視点に抵抗がある相談者に対しては、じっくりと話を聞き、意見を適切に引き出す傾聴力や質問力が求められます。
人をサポートする仕事を目指す人には、完璧を目指すよりも、自己研鑽を続け、多様な価値観を受け入れる姿勢が重要だと思います。特に相談者とともに成長する気持ちで取り組むことが、支援の礎になると信じています。
普段からキャリアに悩む人をサポートしている山路さんのやりがい
アドバイザーコメント
迷いや悩みを抱えた人を救い出すことがやりがい
私は普段からキャリアコンサルタントとして、カウンセリングやセミナーを通じて、漠然とした悩みを抱えた人と多くかかわっています。
たとえば、自身のキャリアに対して「何かしなきゃ」と思いつつも、「何をしたら良いかわからず踏み出せない」という人などです。
そういった人達が、眠っていた自身の内なる思いに気付き、再び歩みを進める姿を見るたびに強いやりがいを感じています。
他人の前に自分を大切にできる心が大切
そんな私が仕事のなかで大切だと思っている点は、「人をサポートするためにも、自分自身を大切に育て続ける必要がある」ということです。
「誰かをサポートしたい」という気持ちが強い人ほど、自分自身のことは後回しにしたり犠牲にしたりしがちです。しかし、自分自身のことを大切にできない人に、他人を大切にしてサポートを続けるということは難しいです。
また、支援者としてサポートを続けるためには、知識やスキルを磨き続ける自己研鑽も欠かせません。
「相手を大切に思うからこそ、自分自身も大切にし、支援者として研鑽を続ける。それがひいては相手のためになる」という思いを持ちつつ、行動し続けられる人にこそ、人をサポートする仕事への道を志してもらいたいと思います。
仕事が続かず思い悩んだ経験から人を支えたいと思った永田さんのやりがい
アドバイザーコメント
自身が仕事に思い悩んだ経験から人を支える仕事を決心
私ごとで恐縮ですが、キャリアコンサルタントになろうと思った理由は、「散々と組織での働き方で悩んで転職を繰り返してきた」からです。
私は転職を5回ほど繰り返しています。そして一番長くても、5年も続いたことはありません。だいたいは働くなかで出世するものですが、私の場合は中間管理職になると心が疲れて退職してしまうのです。
そういったときに、「同じような境遇で苦しんでいる人の力になりたい」と思ったのが始まりでした。
実際にキャリアコンサルタントとして働いてみて思うのは、相談を受けるなかで「寄り添う」という行為がどれだけ難しいことなのかということです。
人のサポートは難しい分やりがいも得られやすい
支援したい、サポートしたい、と心のなかで思いながら相談者とかかわればかかわるほど、あるいは勉強すればするほど、直接アドバイスすることなどもってのほかだということを思い知らされます。
さまざまなサポートの形がありますが、キャリアコンサルタントにおいては資格を保有し仕事に携わるなかで新たな発見を感じるのと同時に、「また一段成長できた」という嬉しさを感じられることもまた事実です。
人をサポートするというのは奉仕の精神で素晴らしいことですが、一方で非常に繊細で難しい仕事であるということも頭に入れておいていただければと思います。
就活で「人をサポートする仕事がしたい」はOK? 専門家の本音を聞いてみた
就活では組織のリーダーとして活躍したエピソードを話したり、グループディスカッションで話をまとめたりする中心的な人が目立つ傾向にあります。
そのため、「裏方としての役割が大きいサポート業がしたいと面接で回答すると消極的な印象を与えるのではないか」と不安に思っている人もいるのではないでしょうか。
そこで、採用担当者として多くの企業の選考に携わってきたキャリアコンサルタントに、「人をサポートする仕事がしたい」と述べる学生に抱く印象を聞いてみましょう。
アドバイザーコメント
人をサポートしたいという主張自体は好印象を与えやすい
「人をサポートする仕事がしたい」という言葉は、選考において決して悪い印象を与えるわけではなく、むしろ人への思いやりや貢献意欲が伝わるポジティブなメッセージです。
ただし、それだけでは抽象的で具体性に欠けるため、「なぜそう思ったのか」「どういった形でどんな人をサポートしたいのか」を明確にすることが重要です。
たとえば、部活動で仲間を支えた経験など、自身の経験をもとに具体的に誰かをサポートしてきた実体験を挙げ、それを通じて何を学び、将来どう活かしたいのかを述べることが必要になります。
人のサポートに対するやりがいや目標を具体化しよう
また、自分の価値で企業にどう貢献できるかを伝える視点も欠かせません。たとえば、「サポートを通じて顧客満足度を高めたい」など、具体的にどのような形で企業や社会に貢献したいのかを示すと、採用担当者もイメージしやすくなります。
さらに、就活において注意したいのは、サポートする仕事への志望理由が消極的な動機に見えないようにすることです。
「誰かを支えることで成果を生み出すことにやりがいを感じる」などポジティブな表現を心掛けたり、企業が求めるスキルや求める人物像に自分の強みを結びつけて伝えたりするなどの工夫が必要です。
人をサポートする仕事への就職に役立つQ&Aを紹介
人をサポートする仕事から適職を絞り込んだものの、「本当に自分でもなれるのか」「選考を突破できるか不安」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
ここでは、PORTキャリアに寄せられた人をサポートする仕事への就職に役立つQ&Aを紹介します。現場で就活を見てきたキャリアコンサルタントによるアドバイスが掲載されているので、人をサポートする仕事への就職で困っている人はぜひチェックしてください。
人をサポートする仕事一覧をもとに自分に合った働き方を見つけよう
人をサポートする仕事には多くの種類があり、生活支援やメンタルケア、チャレンジの応援など多岐にわたります。タイプごとにサポート方法やかかわる相手などが異なるため、漠然と人をサポートする仕事に就くと、相性の悪い職種を選んでしまい早期離職につながるかもしれません。
人をサポートする仕事で適職を見つける際に効果的なのが、4タイプに分けて適性のある分野を見つけることです。この記事でもジャンルごとに分類しているので、相性の良い仕事を絞り込み、自分に合った働き方を見つけましょう。
アドバイザーコメント
ほとんどの仕事は人や社会のサポートにつながっている
ここまで「人をサポートする仕事」というテーマでさまざまな仕事について解説してきました。
極論ではありますが、今回取り上げた仕事に限らず、どんな仕事も本質的には誰かを何らかの形でサポートし、支えているといえます。だからこそ需要が発生していて、仕事として成り立っているのです。
「誰かの役に立てるのか?」「サポートできているのか?」といった問いに自信を持って答えるために大切なのは、仕事の内容以上に、実際に働く私達自身がそのことを意識できているかどうかです。
人をサポートすることで得たいゴールを明確にしよう
人をサポートすることを仕事にしたいと考え、この記事を最後まで読んだ人には、なおさら「どんな人達をサポートしたいのか?」「どんなサポートをしたいのか?」「そのサポートを通して相手にどうなってほしいのか?」などにとことん向き合い、追い求めてほしいと思います。
これはどんな仕事に就くかを決める際だけでなく、仕事に就いた後も成長して働き続けるためにも問い続けていかなければならないテーマなのです。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

















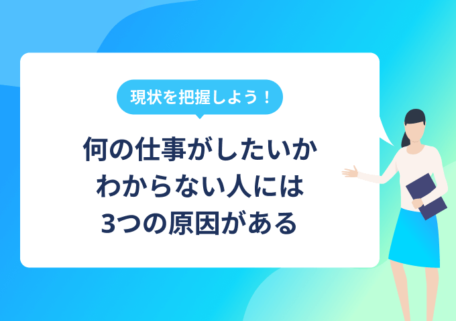









3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント
Arisa Takao〇第二新卒を中心にキャリア相談を手掛け、異業種への転職をサポートする。管理職向けの1on1やコンサルティング業界を目指す新卒学生の支援など年齢や経歴にとらわれない支援が持ち味
プロフィール詳細国家資格キャリアコンサルタント
Kazuhiro Yamaji〇会社員として長年勤務した後キャリアコンサルタントとして開業。企業の採用・高校生向けセミナー講師・転職支援・リスキリング補助など多岐にわたる分野でキャリア支援にたずさわる
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/メンタル心理カウンセラー
Syuya Nagata〇自動車部品、アパレル、福祉企業勤務を経て、キャリアコンサルタントとして開業。YouTubeやブログでのカウンセリングや、自殺防止パトロール、元受刑者の就労支援活動をおこなう
プロフィール詳細