この記事のまとめ
- 文系職から就職先を選ぶ際は向いている職業を見極めることが重要
- 文系の職業は特徴の異なるさまざまな業界で求められている
- 自分に合った文系の職業は3ステップで見極めよう
就活を意識し始めると、そもそも文系にはどんな職業があるのか気になる人も多いですよね。「文系の職業にはどんな選択肢があるんだろう」「自分に合った文系の職業がわからない……」という声が多くの学生から寄せられます。
文系の職業についてよく知らないまま就活を進めてしまうと、就活がうまくいかなくなるだけでなく、ミスマッチの原因となり入社後に後悔する可能性が高まってしまいます。自分の将来の可能性を広げるためにも、満足のいく就活にするためにも、文系の職業を幅広く押さえていきましょう。
この記事では、キャリアアドバイザーの柴田さん、渡部さん、木村さんのアドバイスを交えつつ解説します。文系はどんな職業に就けるのかが気になる人は参考にしてくださいね。
なかんか内定が取れず悩んでいる文系の人もいるのではないでしょうか。次の記事では、文系学生の平均エントリー数や内定獲得数を紹介しています。気になる人は、併せて読んでみてくださいね。
【完全無料】
大学3年生(27卒)におすすめ!
就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう
3位:16タイプ性格診断
あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します
4位:面接力診断
39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう
5位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう
【併せて活用したい!】
選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール
①自己PR作成ツール
AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう
②志望動機作成ツール
他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう
文系の職業は多種多様! 特徴や適性を見極めて合うものを見つけよう
文系の職業というと「営業」「事務」などの代表的なものしか思い浮かばない人も多いかもしれません。しかし文系の職業は多種多様で、業務内容だけでなくそれぞれ求められるスキルや能力も異なります。
就職してから「もっと自分に合う職業があったかもしれない…….」と後悔しないためにも、就活に取り掛かる前に文系の職業を漏れなくチェックしておきましょう。
記事前半では文系の職業を網羅的に解説します。それぞれ向いている人の特徴やキャリアコンサルタントの見解も交えて解説するので、自分が適性があるか考えながらチェックしてみてください。
記事後半では文系職業の採用がある業界一覧や、自分の適性を見分ける具体的な方法を解説しています。最後まで読めば文系の職業に関する知識が備わるだけでなく、自分の目指す職業・適性のある職業をより明確にイメージできるはずです。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認してみよう
自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。
そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。
今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。
文系の職業はポテンシャル採用のため選べる仕事の幅が広い
基本的に新卒採用はポテンシャル採用です。即戦力となるような知識やスキルは求められないことが多く、基礎的なコミュニケーション能力や資質などが合否を分ける大きな要となります。
特に文系の新卒採用はポテンシャル採用が顕著であり、学部などこれまでの学びがあまり選考に影響せず、ポテンシャルだけで内定を得ることも可能だといえます。「自分は文系で特別なスキルがないから……」と考えてしまう人も多いかもしれませんが、企業の募集要項を見て、資格などが記載されていなければ誰もが応募できます。
これほどまでに多くの職業を選べる時期は、新卒就活ならではの特権です。さまざまな文系が就ける職業を押さえて、臆せずチャレンジしてみましょう。
「文系だから……」と固定観念を持たず、さまざまな職業を見るべきです。たとえば、技術系の職場に文系学生を採用するケースは少なくありません。
よく知られているものだとSEやプログラマーなどがありますが、航空会社の自社養成パイロットも文系学生の採用実績が多いことで知られています。
またメーカーの生産や品質管理の領域では高い語学力が必要なため、文系学生も採用・配属します。文系だからと決めつけずにさまざまな職業をチェックしておきましょう。
こちらの記事では文系の就職先を幅広く紹介しています。業界別の人気企業ランキングと選び方付きなので、ぜひ併せて参考にしてみてください。
自分に合った仕事を見つけたい人は、こちら記事を参考にしてくださいね。後悔しない方法とやってはいけないNG方法もまとめています。
文系におすすめの職業13選! 向いているかの見分け方も解説
まずは文系におすすめの職業を一つずつチェックして、どのような職業に就職できるのかを把握しましょう。それぞれの特徴を知らずに自分に合う職業を見つけるのは困難です。
前述の通り、文系の就職先は多種多様で、その業務領域も幅広いです。そのためそれぞれの職業に必要な資質や適性も大きく異なります。
以下では、それぞれの職業の説明と併せて向いている人の特徴も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
①営業
営業とは?
顧客が求めている情報を収集・提供し、商品やサービスを顧客に販売する職業。あらゆる業界に存在する職業で、業務内容も幅広い
営業は企業の売上・業務成績に直接的に関与する重要な職業です。顧客とかかわる機会が多く、企業の「顔」としてさまざまな企業にサービスを販売したり、契約を結んだりします。
営業は実績が数字として現れやすいため、文系の職業のなかでも特に実績を重視されやすい傾向があります。先方の担当者と直接会話する機会が多い分、コミュニケーション能力が高いことはもちろん、相手のニーズを読み解くヒアリング能力や、行動力なども求められます。
おもな営業職の種類は以下の通りです。
おもな営業職の種類
- 新規開拓営業:まだ取引のない相手と関係性を構築することで新しい顧客を獲得する
- ルート営業:すでに取引実績がある既存顧客に対して製品・サービスを売り込む
- 訪問営業:実際に顧客のもとに訪問したうえでおこなう
- 飛び込み営業:新規開拓営業の手法の1つで、アポを取らずに法人や個人宅に訪問する
- テレアポ営業:テレフォンアポインター営業の略。取引先になりそうな法人や個人に電話をかけ、担当者や決裁者からアポイントメントを取る
- 反響営業:折り込みチラシやダイレクトメール、ホームページなどを見て問い合わせをしてくる顧客に製品・サービスを売り込む
- 文系の職業というと営業のイメージがあります。実際、文系の多くは営業になるのでしょうか?
企業によって異なるが、その傾向が強い
企業によって異なりますが文系の場合、技術職以外の「総合職」と「一般職」でそれぞれどのような職種に配属されるかは異なります。
企業によっていろいろなパターンがありますが、一般的に営業職には総合職で採用した文系の人材が多く配属される傾向があるようです。その場合、一般職で採用された人材はその営業担当者の補助的な業務を担当する部署に配属される傾向にあります。
また営業以外で文系が配属されるような部署として総務・人事部や企画部、商品開発部、マーケティング部などがありますが、配属される人数自体は営業よりも少ない傾向にあります。
向いている人の特徴
営業に向いている人の特徴は以下の通りです。
営業向きの人の特徴
- コミュニケーション能力が高い
- 粘り強さがある
- 好奇心旺盛で学習意欲が高い
- 目標達成意欲が強い
営業では、顧客と信頼関係を築き、相手のニーズを満たす最適な解決策を提示することが求められます。だからこそ、相手と粘り強くコミュニケーションを取る力が必要不可欠となるのです。
つまり、単に「人と話すのが好き」という理由だけで営業職を選ぶと、実際の業務とのギャップに苦しむことがあります。
自分の適性を判断する際は話すこと自体が好きかどうかだけでなく、「相手のニーズを察知する力があるか?」「言葉で相手を動かすことができるか?」なども併せてチェックしましょう。
営業に興味を持った人は以下の記事も参考にしてみてください。営業のキャリアプランや向いている人の特徴を詳しく解説しています。
営業のキャリアプラン
営業職の6つのキャリアプランとは? なりたい将来像を想像してみよう
営業事務に向いてる人
営業事務に向いてる人の特徴5選! 意外な魅力や日々の仕事も解説
②事務
事務
書類の作成・処理、データ整理・入力、電話対応や来客対応などをおこなう職業。社内のサポート役として、社内の細かな仕事まで対応する
事務がおこなう業務内容は多岐に渡りますが、その業務内容は総じてほかの社員のサポートです。社内では縁の下の力持ちのような役割を担います。
事務は直接企業の利益に貢献ができる職業ではありませんが、ほかの社員がスムーズに仕事できるような支援を通じて企業の売り上げ・業務成績に貢献しています。
おもな事務の種類
- 一般事務
- 営業事務
- 経理事務
- 総務事務
- 人事事務
- 法務事務
- 貿易事務
一般事務といった社内の事務作業をなんでもこなす役割から、営業事務や法務事務といった部署に特化した事務作業を担う役割までさまざまです。
事務職は「言葉を的確に使えること」が重要なスキルになります。対外的なやりとりだけでなく、内部でも意思の疎通や情報共有のあらゆる場面で事務がかかわります。
論理思考力や表現力、調整力なども文系が強みにできる要素ですね。
向いている人
事務が向いている人の特徴は、以下の通りです。
事務向きの人の特徴
- 細かな作業が得意
- 物事を整理するのが好き
- 協調性がある
- サポート意識・フォロワーシップが強い
これらの特性を持つ人が事務職に向いている理由は、事務作業では「正確性」と「効率」が強く求められるためです。
事務は、決算や見積書、プレゼン資料の作成など、企業の事業にとって重要な業務の補佐をおこなう作業も多く、そうした業務では少しのミスが大きな損害になりかねません。
そのため、細部まで丁寧に業務を遂行したり、正確かつスピーディに作業をこなしたりできる人が重宝されるのです。さらに事務作業では、複数の部署・関係者と協力して業務を進めます。だからこそ協調性やサポート意識も強く求められます。
ただし、「激しい競争が苦手だから」といった消極的な理由で事務職を選ぶのは控えましょう。事務でも業務への積極的な姿勢や常に改善しようとする能動的な意思が重視されるため、選ぶ際は自分の適性を中心に判断してください。
営業に興味を持った人は以下の記事も参考にしてみてください。営業のキャリアプランや向いている人の特徴を詳しく解説しています。
事務に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。併せてチェックすれば事務職や向いている人の特徴をより深く理解できます。
事務職
事務職の仕事内容が丸わかり! 必要なスキルや就職のコツも
営業事務に向いてる人
営業事務に向いてる人の特徴5選! 意外な魅力や日々の仕事も解説
③人事
人事とは?
採用や人材配置、人材計画をおこない、社員の採用から能力を発揮できる仕組みづくりを一貫して担う職業
人事は採用のみならず、社員の研修・教育を担当する企業の縁の下の力持ちのようなポジションです。社内評価制度の作成や勤怠管理などの労務関係の仕事を含むこともあります。
人事のおもな仕事内容
- 新卒採用・中途採用
- 従業員の配置・移動
- 従業員の評価
- 人材育成・キャリア開発
- 人事制度策定・運用
- 労務管理
- 社会保険・福利厚生
人事はさまざまな機密情報を扱うため、口が堅く秘密を守れることは必須です。また社員と向き合う職業のため、相手の立場に立って判断ができる人が人事に向いているといえるでしょう。
向いている人の特徴
人事が向いている人には、以下のような特徴があります。
人事向きの人の特徴
- 相手の資質や能力を見極める力がある(人を見る目がある)
- 現状を変えようとする強い行動力や意思がある
- 分析する力に優れている
- 変化に柔軟に対応できる
人事職は新しい社員の採用をおこなうだけでなく、今いる社員の成長や活躍を支援する役割があります。だからこそ人を見る目や、人・組織を分析する力が必要です。
また、既存の人事体系や教育システムを常に最適な形にアップデートできる行動力や、企業の変化についていける柔軟性も欠かせません。
自分が人事に向いていると感じた人は、以下も併せてチェックしてみてください。人事の選考でのポイントや注意点とともに志望動機の書き方を解説しています。
④経理・財務
経理・財務
- 経理:お金や取引の流れを記録・管理する職業。特に企業がこれまでに使用したお金を取り扱う。
- 財務:企業の資金管理や予算の活用に関する業務をおこなう職業。おもにこれから企業が使用するお金を管理する。
経理・財務は企業のお金を管理する役職であるため、大きな責任やプレッシャーがかかる職業です。
なお、経理・財務はどちらも企業内のお金を扱う職業ですが、それぞれメインで取り扱う資金が異なります。経理は日々のお金の流れや取引を記帳して決算書などの資料を作成するのに対し、財務は資金管理や予算計画作成などを通じて資金不足にならないように企業運営を支えます。
一般的に、財務のほうが経理よりも難易度が高いです。そのためまずは経理として入社し、キャリアアップして財務職になるルートが一般的です。
向いている人の特徴
以下は、経理・財務が向いている人の特徴です。
経理や財務向きの人の特徴
- 数字やデータに対して抵抗がない
- 注意力・集中力がある
- 守秘義務を守れる誠実さがある
経理・財務も事務などの職業と同様に、ミスなくスピーディに業務を遂行する能力が求められます。お金を扱う部署であるため、少しのミスや誤差が大きなトラブルにつながりかねないためです。
また企業の内部情報に深くかかわる職業であるため、守秘義務を守れることも必要な素養の一つと言えます。
なお、経理・財務は確定申告や企業の決算期に業務量が増える点には留意しておきましょう。
新卒で経理職に就きたい人は、以下の記事も併せてチェックしてみてください。新卒がとるべき2つの戦略について、詳しく解説しています。
⑤広報・IR
広報・IR
- 広報:企業の方針や新商品・サービスについて外部に発信する職業
- IR:企業の財務状況などを株主や投資家に発信する職業
広報・IRはどちらも情報を外部に発信する役割を担います。発信内容が企業のイメージや信用に大きな影響を与えるため、その役割は重大です。ミスが許されないだけでなく、法令や規則を遵守した発信が求められるため、難易度が高い職業とも言えます。
広報のおもな種類
- 社外向けの活動報告作成
- 企業プロモーション
- Webサイトの更新・管理
- 社内広報
など
IRのおもな仕事内容
- 株主総会の運営
- 有価証券報告書の作成
- 決算短信の作成
- IRサイトの情報発信
など
社内の各部署とのコミュニケーションや、企業外部の関係者と関わりも多く、矢面に立って企業の成長に貢献する職業です。
- 人事や経理・財務、購買、広報・IRなどバックオフィス系の職業に就くためにどうしたら良いのでしょうか?
ジョブ型雇用の求人に応募しよう
上記の部署や職種を強く希望していても、総合職などのメンバーシップ型採用であれば希望の部署に配属されないこともあります。
そのような人は部署や仕事内容を限定して応募できるジョブ型雇用の求人に応募しましょう。
または、人事にかかわる仕事をしたいのであれば人材コンサルティング会社、経理・財務ならそれらのアウトソーシング事業会社、広報・IRならPR会社などやりたい業務そのものの分野を専門とする企業を探してみてはどうでしょうか。
あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう
就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。
そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。
早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。
向いている人の特徴
広告・IRが向いている人には、以下のような特徴があります。
広告・IR向きの人の特徴
- 相手の立場で物事を考えられる
- コミュニケーション能力が高い
- ものづくりやクリエイティブな作業が好き
- 論理的な思考ができる
広報・IRは、情報を人に伝えるのがおもな役割です。だからこそ、相手視点に立って物事を考えたり、伝わりやすい表現で相手の心を動かしたりできる人が向いています。
また、コミュニケーション能力が高い人も、広告・IRに向いている可能性が高いです。なぜならコミュニケーション能力が高い人は自然に相手のニーズを察知したり、相手に伝わりやすい表現を選択するのに長けているためです。
自分が広報・IRに向いているかを見分ける際は、相手の気持ちになって情報を伝えた経験をもとに判断しましょう。
⑥企画・マーケティング
企画・マーケティング
企業の商品・サービス開発や改良を担う職業。開発や改良に必要な情報を集め、分析した結果をもとに実際に商品やサービスを開発・提供する
企画・マーケティングはどちらも商品やサービス開発にかかわる職業ですが、厳密には両者でその業務内容は異なります。
企画は消費者ニーズを満たす商品の開発・改良自体がメインである一方、マーケティングは企画に至るまでの情報収集や分析、発売・ローンチ後の商品訴求まで関わります。簡単に言うと、企画が商品やサービスを生み出し、それをマーケティングが広めるイメージです。
特に近年ではマーケティング自体をサービスとして提供している企業も多いです。
マーケティングを提供する企業の例
- WPP
- P&G
- 電通
- 博報堂
- サイバーエージェント
など
社内のマーケティング部と外部のマーケティング会社でタッグを組み、より洗練されたマーケティングをおこなう会社も増えてきています。
向いている人の特徴
企画やマーケティングが向いている人の特徴は、以下の通りです。
企画・マーケティング向きの人の特徴
- 創造性と柔軟な発想力に優れている
- 多角的な視点をもとに考えられる
- 相手目線で物事を考えられる
- トレンドや情報への感度が高い
そもそも企画やマーケティングの目的は、消費者やクライアントに購入される商品やサービスを生み出し、利益を拡大することです。だからこそ、相手の目線に立って的確にニーズをとらえ、求められる商品・サービスを作り出せる能力が必要になります。
また、どんな企業であっても、その時代にあった商品・サービスを提供することが常に求められています。企画やマーケティングはこのニーズを満たすためにも、高い情報・トレンドへの感度や多角的な視点が求められる点も知っておきましょう。
常に時代の流れを読み、一分野のトレンドを追い続けられる人や、相手目線や周囲の目線を考えながら行動できる人は、企画・マーケティングとして活躍できる可能性があります。
企画・マーケティング職に興味がある人は、以下の記事もチェックしてみてください。併せてチェックすればそれぞれの職業をより深く理解できます。
マーケティング職
新卒でマーケティング職に就くには? 仕事内容から対策まで徹底解説
企画職
企画職の仕事や適性を徹底解剖! 新卒が企画職を狙うのはハード?
⑦コンサルタント
コンサルタント
クライアント企業の経営課題を特定し、戦略の立案や業務プロセスの改善などのアドバイスを提供する経営の専門家。「相談する」という意味を持つ「consult」が語源になっている
コンサルタントは経営者や個人事業主をクライアントとして、課題解決のためのアドバイスやサービスを提供する職業です。最近ではIT技術を通じた課題解決が欠かせない手法の一つになってきているため、IT職のような印象を持たれる場合もあります。
コンサルタントはおもにコンサルティング会社やシンクタンクなどに属し、企業や個人にコンサルティングをおこないます。
| 呼び名 | 属する企業 |
|---|---|
| BIG3(世界的な戦略コンサルティング会社) | マッキンゼー・アンド・カンパニー ボストン・コンサルティング・グループ ベイン・アンド・カンパニー |
| BIG4(日本のトップコンサルティング会社) | デロイト トーマツ コンサルティング PwCコンサルティング EYストラテジー・アンド・コンサルティングKPMGコンサルティング |
| 日本大手5大シンクタンク | 日本総合研究所 野村総合研究所 三菱総合研究所 三菱UFJリサーチ&コンサルティング みずほリサーチ&テクノロジーズ |
向いている人の特徴
コンサルタントが向いている人の特徴は、以下の通りです。
コンサルタント向きの人の特徴
- 論理的思考力が高い
- 行動力があり、情報収集に長けている
- 柔軟な発想力がある
- コミュニケーション能力が高い
- ストレス耐性がある人
コンサルタントは複雑かつ難易度の高い仕事であるため、これらの特性が総合的に求められます。
クライアントが抱える課題を分析して最適な解決策を提案するためには、情報を論理的に整理する能力と、それを相手に分かりやすく伝えるコミュニケーション力が必要だといえるのです。
さらに、クライアントよりもさらに深くクライアントのことを理解したうえで、新たな発想や論理的な思考から生まれる解決策を提示する必要があるため、上記のような資質が求められます。
なお、コンサルタントはスマート・華やかといったイメージがあるかもしれませんが、実際の業務は膨大な資料作成や調査分析など地道な作業も多いことを理解しておきましょう。
また、クライアントとの関係構築や成果への責任など精神的プレッシャーも大きいため、メンタル面での強さも求められます。
⑧販売
販売職とは実際に店舗に立ち、接客やレジ打ち、商品の品出しなどをおこなう職業です。顧客に最も近い距離で接する職業であり、商品やサービスの魅力を直に伝える重要な役割を担っています。
販売職の種類の例
- アパレル販売スタッフ
- 食品販売スタッフ
- 家具販売スタッフ
- ブライダルコーディネーター
- 飲食店ホールスタッフ
販売職は顧客と直接接点を持つため、営業と並ぶ企業の顔となるポジションです。アルバイトなどでも従事できるため簡単そうと思う人も多いですが、自身の対応や接客が企業の評価に直結するため、実は重大な責任が伴う仕事とも言えます。
- 人と話すことが好きなため、販売や営業に興味があります。どちらかの職業を選ぶにあたってどんな観点から選べばいいのでしょうか?
扱う商材が好きかどうかで考えてみよう
販売も営業も、自社の商品やサービスを売る仕事です。「売上という成果が数字でわかる」という直接的な手ごたえを感じられる仕事という点では似ていますが、市場に対するアプローチが異なります。
販売は顧客のアクションを待って対応しますが、営業はこちらから顧客に対してアクションを起こします。どちらも客層や価格帯、売り方などの前提がありますが、職種よりも扱う商材が好きかどうかの方が重要かもしれません。
営業の方がより個人の力量が成果に反映されやすく、成果に差がつきやすい職種です。販売は顧客の側にすでに商品、サービスの認知がある状態から始まります。そのため営業より難易度は低い傾向ですが、商品知識が深まると面白味が増す仕事です。自分はどちらに面白みを感じるか考えてみましょう。
あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!
就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。
まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事がわからない人
・時間をかけずに自己分析をしたい人
向いている人の特徴
以下のような特徴を持つ人は、販売員に向いている可能性があります。
販売員向きの人の特徴
- コミュニケーション能力が高い
- 傾聴力がある
- 継続的に学び続けられる
これらの特性が販売員に求められる理由は、顧客との信頼関係の構築が販売の成功に直結するためです。販売員の最大の目的は商品やサービスを通じて相手のニーズを満たすことであるため、相手の話に耳を傾け、丁寧にコミュニケーションを取ることが欠かせません。
また、相手のニーズを的確に満たすには商品やサービスの深い知識も必要です。日々変化する商品知識や市場トレンドに対応し、相手のニーズに刺さる提案を磨き続ける努力が販売員には求められます。
販売員に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。接客業全般の情報をチェックしておけば、自分にとって適職かをより正確に判断できます。
接客業に向いてない
接客業に向いていない人の特徴4選|ベストな道の選び方もプロと解説
⑨司書・学芸員
図書館司書・学芸員
- 図書館司書:図書館で資料の選定や貸出、読書案内に至るまでの全般的な業務をおこなう職業
- 学芸員:博物館で資料を収集、保管、展示するとともに調査研究をおこなう職業
図書館の運営をする図書館司書と、博物館や美術館で資料を扱う学芸員は、どちらも国家資格です。
図書館司書は本の専門家としてレファレンスサービスをおこない、学芸員は魅力的な展示を作れるなど専門性が必要であり、採用数が少ないだけでなく非正規採用の募集になることもあるため、正社員で就職する難易度は高いです。
レファレンスサービス
図書館利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、必要とされる資料を検索・提供・回答する業務
向いている人の特徴
司書や学芸員が向いている人には、以下のような特徴があります。
司書・学芸員向きの人の特徴
- 知的好奇心が旺盛
- 人に教えることが好き
- 文化や歴史に対して深い関心がある
司書や学芸員は常に文化的な領域で仕事をすることになるため、就職するには文化や歴史に対して深い興味を持っていることは必須です。
また司書は本や資料に関して、学芸員は展示物に関して、常に何を聞かれても答えられる状態にしておく必要があります。そのため、常に自分の専門領域における知識探究を続けられる人でなければ務まりません。
なお、司書・学芸員は人気の職業である一方、求人数が限られているため、就職競争が厳しい傾向がある点には留意しておきましょう。近年は非正規雇用も増えているので、雇用形態についても事前に確認して、自分の希望に沿うかチェックしておいてください。
⑩秘書
秘書
経営者や役員など、組織のキーパーソンをサポートする職業。多様な業務を通じて組織の円滑な運営を陰で支え、依頼者が本来の業務に集中できる環境を整える
秘書は経営者や役員のサポートがおもな業務内容ですが、その仕事内容は多岐に渡ります。
秘書の主な仕事内容
- 上司のスケジュール管理と調整
- 来客・電話対応や会議のセッティング
- 出張手配や経費精算
- 各種文書・資料の作成と管理
- 情報収集や調査活動
など
このように、秘書は経営者の定常業務ではない仕事のほとんどを請け負うのです。
秘書には特別な資格は必須ではありませんが、秘書検定やビジネス文書検定などの資格を持っていると就活を有利に進められる強みとなります。特に秘書検定は業務に直結する具体的な資格であるため、目指す人は積極的に取得を検討しましょう。
向いている人の特徴
秘書が向いている人の特徴は、以下の通りです。
秘書向きの人の特徴
- さまざまな立場の人とうまくコミュニケーションを取れる
- 臨機応変な対応ができる
- 優先順位をつけて効率よく仕事をこなせる
- 観察力が高い
秘書は社内外のさまざまな人とやり取りするため、円滑なコミュニケーション能力は必須です。また、依頼主が抱える種類の異なるタスクを任されるため、優先順位を付けて効率よくそれらを捌く能力も欠かせません。
上記の能力に加えて、採用選考時にはビジネスマナーや正しい言葉遣いなどが厳しくチェックされます。依頼主には経営者や会社役員などが多い分、失礼のない対応ができることが最低条件であるためです。
このように、基本のマナーやビジネススキルがありつつ、かつ常に先読みして担当する役員や経営者の業務を補佐できる人は、秘書として長期的に活躍していけるといえます。
秘書に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。それぞれチェックすれば、自分が秘書に向いているかをより正確に判断できます。
秘書に向いてる人
秘書に向いている人の特徴5選! 仕事内容や有利になる資格も解説
秘書検定就職で
秘書検定は就職に活かせる! 取得メリットやアピール方法を徹底解説
秘書の仕事がつらい
秘書の仕事がつらいと言われる6つの理由|魅力や合う人の特徴も解説
⑪通訳者・翻訳家
通訳者・翻訳家
- 通訳者:異なる言語話者がコミュニケーションを取れるように言語的仲介を担う職業。会話に入り、一方が話した言語を即座に翻訳してもう一方の言語で伝える
- 翻訳家:ある言語で作られた本・映像などを、異なる言語に変換する職業。言語が持つニュアンスまで汲み取って翻訳することが期待される
通訳者と翻訳家は、ある言語を異なる言語に翻訳して伝えるという点では共通しています。しかし、2つの業務領域はまったく異なっており、活躍する場面も大きく異なります。
| 通訳者 | 翻訳家 | |
|---|---|---|
| 目的 | 即座の言語変換によるコミュニケーションのサポート | 文化的背景などまで含めた意図の正確な変換・伝達 |
| 業務形式 | 会議・インタビューなどのコミュニケーションが発生する場で仕事をする | 作品を深く読み込み、時間をかけてニュアンスや意図まで正確に翻訳する |
どちらもグローバル化が進む現代社会において重要な役割を担っています。所属先もそれぞれ異なり、通訳者は翻訳会社、翻訳家は出版社に勤める場合が多いです。最近ではフリーランスとして活動する人も増えています。
向いている人の特徴
以下のような特徴がある人は、通訳者・翻訳家に向いている可能性があります。
通訳者・翻訳家向きの人の特徴
- 2カ国語以上を流暢に使いこなせる
- 微妙な言葉のニュアンスをとらえられる(smile VS grinなど)
- 異文化理解や国際交流が好き
- 継続的に勉強を続けながら仕事に取り組める
通訳・翻訳の仕事は単に言葉の意味を置き換えるのではなく、訳す言語の文化や、書き手、話し手の意図を踏まえた伝達をおこなうことが求められます。
特に通訳の場合、瞬時に異なる言語に変換する高度な処理能力に加えて、会話の流れを途切れさせないようスピーディーに伝えなければいけないため、高いレベルでの言語理解と集中力が必須です。
一方、翻訳家には時間をかけてでもぴったりのニュアンスの訳を考えることや、正確かつ深い言語学の知識が求められます。
なお、言語は時代によって変化し続けるため、通訳者・翻訳家になるのであれば常に勉強して自分のスキルを磨き続ける必要があることも覚えておきましょう。
⑫記者・ライター
記者・ライターは、情報を収集・分析し、それを言葉で表現して社会に伝える専門職です。事実や意見、感情などを文章で表現し、読み手に正確に伝えることを職務としています。
実は記者・ライターにも、執筆する媒体によってさまざまなジャンルがあります。
記者・ライターのジャンル
- 新聞記者:実際に取材に赴き、迅速かつ正確な報道の準備をおこなう
- ジャーナリスト:あらゆるメディアに掲載する記事や情報自体を提供する
- 雑誌ライター:紙媒体、もしくはその電子版に掲載するコンテンツを執筆する
- Webライター:おもにネット上のメディアやブログなどに掲載する記事を執筆する
それぞれ掲載する媒体は違っても、情報を調査してそれを発信に適した形に整えるという業務内容は共通しています。
なお、記者・ライターは企業に勤めずフリーランスとして活動している人も多いです。フリーランスとして働けば場所や時間にとらわれずに仕事できるため、自由な仕事に就きたい人にもおすすめの選択肢の一つです。
自由な仕事に興味がある人は、以下の記事もチェックしてみてください。自由かつやりがいのある仕事と適職の探し方を詳しく解説しています。
向いている人の特徴
記者・ライターが向いている人の特徴は、以下の通りです。
記者・ライター向きの人の特徴
- 「書く」ことが好き
- 情報収集能力や行動力が高い
- 自己管理能力が高い
- 人に事実や考えを伝えるのが得意
記者・ライターは「情報収集」と「情報伝達」が仕事の核となるため、正しい情報を迅速に集め、それをわかりやすい形で人に伝えられるスキルがなければ、活躍することが難しいかもしれません。
また、記者やライターになると、好きなこと以外の興味のない話題について執筆しなければいけない場合も多いです。
特に最初のうちは得意・好きな仕事ではなく、任されたジャンルの仕事についてリサーチし、執筆することが求められる場合があるため、どんなテーマでも好奇心を持って取り組める人はこの仕事に向いているといえます。
ライターに興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。併せてチェックすればライターについてより深く理解できます。
⑬編集者・ディレクター
編集者・ディレクターは、雑誌や書籍、Webメディア、映像作品などのコンテンツ制作において中心的な役割を担う職業です。企画立案から完成までの工程を統括し、チームを指揮して制作にあたります。
前述の記者やライターを統括するのがメインの業務で、納品物のチェックや校正を担当するのも編集者・ディレクターの役割です。
編集者・ディレクターの仕事内容
- 企画立案
- 執筆者・クリエイターの採用
- チームの統括・進行管理
- 納品物の内容編集・校正
- 品質管理と最終チェック
出版業界では書籍編集者や雑誌編集者、Web編集者などに分かれます。一方、映像業界ではテレビディレクターや映画ディレクター、広告ディレクターなどが職業の細かな分類です。
編集者やディレクターになるには、出版社やWeb媒体の編集部に入り、アシスタント編集者からキャリアアップする方法や、記者やライター経験を積んでキャリアアップする方法が一般的です。
記者や編集者は文章力が問われる仕事です。あるテーマやトピックに関して自分の視点やそれとは異なる視点で、考えをわかりやすく簡潔な文章で書ける能力が期待されています。
そのため文系には高い言語化能力と文章力が求められています。
向いている人の特徴
編集者・ディレクターが向いている人の特徴は、以下の通りです。
編集者・ディレクター向きの人の特徴
- モノづくりが好き
- 相手の立場になって物事を考えられる
- 責任感が強い
- リーダーシップがある
編集者・ディレクターはチームを統括する役割であるため高いスキルが求められるのはもちろん、人の上に立つ素質も求められます。人を動かして業務を遂行するには、リーダーシップや制作物に対する強い責任感、常に誰よりも深く思考できる力などが欠かせません。
なお、編集者やディレクターは制作物の責任を負う必要があるため、納期や進行状況によっては長時間労働を強いられる可能性があります。
自身の審美眼が常に求められるため、常にプレッシャーに晒されることも理解しておきましょう。
専門性が高い文系職業一覧! 資格や受験が必要な10の専門職
専門性が高い文系職業一覧! 資格や受験が必要な10の専門職
文系の就活生のなかには、専門的な分野での仕事に興味があるという人もいるのではないでしょうか。
実はここまで紹介した職業以外にも、文系の学生が、専門性を活かして働けるおすすめの職業があります。
ここからは専門性が高い文系の職業とそれぞれの特徴を解説します。各職業に必要な資格や受験が必要な場合についても紹介するので、キャリア選びの参考にしてみてください。
①公務員
公務員
国や地方自治体の機関に属して国民や市民のために働く職業。憲法では「全体の奉仕者」と規定されている
公務員は、行政サービスの提供や公共政策などを実行することで人々の暮らしを支えることが目的であるため、社会的な信頼の高さや職の安定性などが魅力といえる職業です。
公務員には国家公務員と地方公務員の2種類があり、それぞれ多様な職種があります。
国家公務員の職種
- 官公庁職員
- 国税専門官
- 裁判所職員
など
地方公務員の職種
- 県庁職員
- 市役所・区役所職員
- 消防官
- 警察官
など
公務員になるためには公務員試験に合格する必要があります。なお、国家公務員になるためには公務員試験に合格するのとは別に、該当する官庁や機関での試験や面接を経る必要があるため、国家公務員のほうが難易度が高いのです。
公務員に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。公務員の仕事だけでなく、就活時に悩む人が多い点についても解説しています。
公務員と民間を併願
公務員と民間企業の併願で共倒れ? 状況別で両立のコツを解説
国家公務員の種類わかりやすい
国家公務員の種類をプロとわかりやすく解説! 役割や必要なスキルも
公務員の安定
「公務員は安定」の実態は? 確認すべき現実と注意点を解説
②弁理士・裁判官
弁護士・裁判官
- 弁理士:新規の発明品の知的財産権を申請することや特許権の侵害などの知的財産権を巡る紛争を解決する職業
- 裁判官:法律に従って中立公正な立場から裁判をおこなう職業
法律関係の専門職は、法律にかかわることができる公正中立な立場となり、厳しくもやりがいがある職業です。
法律専門職というと、裁判所や公的機関で働くイメージが強いかもしれません。しかし、たとえば、弁護士などでは民間企業で顧問弁護士として働くこともありますよ。
また一口に法律専門職といっても、法律に関する仕事には多くの職業があるため、法律にかかわる職業に就きたいと思った人は自分の適性に合った職業を探してみましょう。たとえば、Web上で「法律 資格」などと検索をしてどんな資格があり、どんな業務内容なのかを確認してみてくださいね。
そのほかのおもな法律専門職
- 検察官
- 弁護士
- 行政書士
- 裁判所書記官・事務官
③公認会計士
公認会計士
企業の財務情報の信頼性を担保する会計と監査の専門家。法定監査や税務業務、会計業務など、お金に関するさまざまな業務を遂行する
社会の健全な経済活動を支える職業で、文系の学生からの人気も高いです。公認会計士はおもに以下のような業務に従事します。
公認会計士の仕事内容
- 監査:財務諸表や計算書類などのチェックや企業の経営・財務状態の確認
- 会計:企業のお金の管理や資金繰りなどの事業計画の策定など
- 税務:企業の経済活動に係る税務書類の作成や税務申告のフォロー
一人前になるには公認会計士試験に合格した後、監査法人などに就職して最低2年の実務経験を経る必要があります。試験の合格率は約10%と難関で、専門の対策スクールに通う人も多いです。
④ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー(FP)
お金に関する専門家として、個人や企業の資産運用や家計管理、保険や税金などの相談に乗る職業。最適な資金計画を提案し、依頼者の人生設計を財務面からサポートする
ファイナンシャルプランナー(以下FP)は、「お金のかかりつけ医」と言われることもある職業で、個人から企業までさまざまな相手から依頼を受けます。資産運用のアドバイスやライフプラン設計から、保健の見直しや家計簿作成のサポートなどの個人の生活の手助けまで、幅広いサービスを提供する職業です。
近年はお金に関する不安が高まっていることもあり、FPの需要も高まっています。実際、FP資格を取得する人数も増加傾向にあり、近年では年間10万人を超えています。
FP資格には1級から3級まであり、2級以上が高く評価されるのが一般的です。FPになるためにFP資格は必須ではありませんが、取得しておけばキャリアアップの面で有利になります。
⑤教育者・教授
教育者・教授は、学校や大学などの教育機関で知識や技能を教える専門職です。生徒や学生の能力や可能性を引き出し、社会で活躍できる人材を育成する重要な役割を担っています。
実は教育者・教授は授業を執りおこなう以外にも、以下のような業務を兼任します。
教育者・教授の仕事内容
- 授業計画の立案
- 生徒・学生の指導・評価
- 部活動の顧問担当
- 生徒の生活指導・進路指導
- 研究活動(特に大学教授)
小学校〜高校の教育者の場合、学生への授業や学生の生活指導、進路相談への対応などがおもな業務です。一方、大学の教授は授業だけでなく研究もメインの業務領域となります。
業務の分量や生徒との距離感は異なりますが、どちらも自分の専門領域を使って業務に取り組む点は共通しています。
教育者になるのに必要な資格は高等学校教諭普通免許状、中学校教諭普通免許状など、属する機関によって必要な教員免許が異なります。
教職課程のある大学や短大で単位を取得し、資格を取得したら、教員採用試験を受験する流れです。合格したら教員として採用されます。
教員に就職するメリットとしては教育者としてのプライドや人を育てるやりがいなど無形のステータスがある仕事に携われるという点です。
しかし実情は教えるだけでなく学校運営に関する業務が多岐にわたるため、マルチタスクが求められる大変な仕事でもあります。
教育関係の職業に就きたい人は、実際の志望動機を解説した以下の記事もチェックしてみてください。参考にすれば、より好印象を与える志望動機を作成できます。
教育業界の志望動機
教育業界の志望動機はこう書く! アピールポイントやトレンドも解説
教員の志望動機
教員の志望動機で自分らしさを出すコツとは? 小中高の例文も紹介
養護教諭の志望動機
理由別6例文|養護教諭の志望動機が誰でも書ける6ステップ!
⑥保育士
保育士は、保育所や幼稚園・保育園などの児童福祉施設で0歳から就学前の子どもの保育をおこなう専門職です。子どもの心身の発達を促し、保護者の子育てを支援する役割があります。
保育士は発育初期段階の子どもに教育を施す職業であり、子供の成長に直接かかわる重要な役割を担います。子供を預かっている間は、日常生活の援助から発達段階に応じた遊びやレクリエーションの実施、健康・安全管理まで、すべて保育士の仕事です。
現在は全国的な保育士不足や施設の不足が問題となっています。2024年1月の保育士の有効求人倍率は3.54倍で、一人の保育士に対して3.54の求人があることを意味します。つまり、保育士が全員仕事についたとしても必要な保育士の数が足りない状況なのです。
保育士になるには、まず厚生労働大臣が指定する養成施設で学び、所定の過程を修了する必要があります。その後、保育士試験に合格することで国家資格の一つである保育士免許を取得できます。
資格は一度取得すると基本的に失われることはありません。なお、保育士の資格があれば保育所や児童福祉施設だけでなく、以下のような施設でも働けます。
保育士免許があれば働ける就職先
- 児童相談所
- 企業内保育所
- 児童発達支援センター
⑦社会福祉士
社会福祉士
生活上の困難を抱える人々を支援する福祉のスペシャリスト。日常生活に支障のある方の相談に応じ、福祉サービスの提供者とつなぐ相談援助役割を担う
社会福祉士は福祉サービスを必要とする人に適切な福祉サービスやその提供者を紹介する、福祉サービスの仲介役です。おもな仕事内容は以下の通りです。
社会福祉士の仕事内容
- 高齢者、障害者、児童などの生活相談
- 相談者への適切な福祉サービスの提供
- 弱い立場にある人々の権利を守る活動の推進
- 住民や関係機関と協力し地域福祉を推進
社会福祉士の固有の特徴は、他の専門職とは異なり「人の生活全体」を支援対象とする点です。医療や教育といった特定分野に限定せず、生活全般にわたる総合的な支援をおこないます。だからこそ、福祉に関する幅広い知識と多職種との連携の能力が求められます。
社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験に合格する必要があります。受験資格を得る方法はさまざまで、福祉系の学部を卒業していなくても社会福祉士資格の取得は可能です。
社会福祉士国家試験の受験資格を得る方法
- 福祉系の大学や短大で指定科目を履修、卒業する
- 短期養成施設や一般養成施設で一定期間以上学ぶ
- 特定の福祉職で一定期間の実務経験を積む
将来は独立して福祉コンサルタントとして活動する選択肢や、大学教員として福祉人材の育成に携わる選択肢もあります。
⑧社会保険労務士
社会保険労務士
労働・社会保険関連の法律のスペシャリスト。「社労士」とも呼ばれ、雇い主と労働者の健全な関係構築や適正な社会保険制度の運用をサポートする
社会保険労務士(以下、社労士)は企業と従業員の双方を支援する労働と社会保険の専門家です。労働・社会保険に関する法律に精通しており、労使関係の調整役を担います。
社労士の仕事内容
- 企業の労働条件や就業規則の整備
- 企業の人事制度の設計へのアドバイス
- 企業・個人の社会保険手続きの代行
- 労働関係紛争の解決手続
社会保険労務士は、企業と労働者のどちらもがクライアントであるという点が特徴的です。時には両者から相談を受け、両者のトラブルを解決する役割を担います。
また企業から制度設計を依頼された場合は、経営と従業員の両方の視点から企業にアドバイスします。そのため単に法律知識を知っているだけでなく、企業経営や人事管理の実務に精通していることや、労働者の視点を持ち合わせていることが求められます。
社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験への合格に加え、実務経験2年以上もしくは事務指定講習の修了が必須です。試験自体も合格率6~7%程度と言われており、難易度の高いため、社労士になるのは狭き門と言えます。
⑨宅地建物取引士
宅地建物取引士
宅建士とも呼ばれる不動産取引の専門家。購入者と売却者の間に立ち、安全な取引をサポートする重要な役割を担う
宅地建物取引士(以下、宅建士)は、不動産の公正な取引をサポートする専門家です。宅建士にしかおこなえない独占業務も存在するなど、その特別性が特徴的な職業です。
宅建士の仕事内容
- 不動産取引の重要事項説明
- 契約書類の作成と確認
- 顧客対応や物件の紹介
法律では、宅建業を営む際は事業所の従業員5人につき1人以上の割合で宅建士を配置することが義務付けられています。そのため、事前に宅建士の資格を取得しておけば有利に就活を進められます。
宅建士には不動産取引に関する民法、宅建業法などの法律知識が必須です。また、契約書作成や重要事項説明書の作成では、小さなミスも許されないため、相応の集中力も求められます。
なお、毎年20万人前後の受験者数を誇る試験に合格することで宅建士として仕事が可能になります。国家資格としては最大規模の受験者数を誇りますが、ほかの国家資格と比べて易しいと言われがちです。
しかしその合格率は約15〜17%と低めのため、決して易しい試験とは言えない点を理解しておきましょう。
⑩心理カウンセラー
心理カウンセラー
対話を通じて相談者の悩みを解決に導く
心の悩みを抱える人々の相談に乗り、問題解決や精神的な健康の回復を支援する専門家
心理カウンセラーは相談員とも呼ばれている通り、精神的な問題を抱えた人の相談に乗る職業です。ただ人の話を聞くだけでなく、資格取得の過程で培ったスキルや心理学のテクニックを用いて問題解決するのが特徴です。
心理カウンセラーの仕事内容
- カウンセリングの実施
- 治療プランの立案
- 医師や社会福祉士と連携した支援業務
- 定期的な相談を通じた予防医療
心理カウンセラーは高い共感力と客観的分析力の両方が求められます。相談依頼者の悩みに寄り添いながらも、客観的な視点を忘れず、冷静に解決に向けて話を進める必要があるのです。
精神的に弱っている相手がほとんどであるため、相手に受け入れられるかつ問題解決につながる絶妙なバランスの解決策を提示する必要があるのも、難しいポイントです。
資格がなくても心理カウンセラーとしては働けますが、一般的には公認心理師という国家資格、もしくは臨床心理士などの民間資格を取得した人がカウンセリングをおこないます。
資格がある方がキャリアアップもしやすいため、心理カウンセラーに興味がある人は資格取得を見据えてキャリアプランを立てましょう。
心理カウンセラーに興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。向いている人の特徴をより詳しく解説しています。
就活前に知っておくべき! 文系職業の採用がある10の業界
ここまで文系の職業について解説してきました。ここまでチェックしてきて、自分に合う職業のイメージが固まりつつある人もいるでしょう。
ただなかには文系におすすめの職業だけではなく、文系が進める業界について、気になっている人もいるはずです。ここからは、文系の職業が実際に活躍している10の業界を解説します。
同じ職業でも、それぞれの業界でその業務内容や労働環境は大きく異なります。比べながらそれぞれをチェックし、自分のイメージに近い働き方ができる業界を探してみましょう。
①金融・保険
金融・保健業界
- 金融業界:お金や株式などを通じて、社会全体の経済活動を支えている業界。個人や企業の資産を管理している
- 保健業界:不慮の事故に備えるための保険サービスを提供する業界。社会の 「金融セーフティネット」 として機能している
金融・保険業界で文系学生が活躍できるおもな職業
- 営業
- 事務
- コンサルタント
金融・保険業界はお金と密接に関わりのある業界で、営業・事務などの職業での採用も多く、文系が活躍できる仕事が多い業界の一つです。文系向きの職種のなかでも営業職は、給与や昇進などが営業成績によって左右される場合が多く、頑張り次第では文理に関係なく高収入が目指せます。
金融・保険業界に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。併せてチェックすれば業界のリアルをより深く理解できます。
金融業界
金融業界を徹底調査! 押さえておくべきトレンドや対策まで大解剖
保険営業はやめとけ
なぜ保険営業はやめとけと言われる? 10の理由と業界のリアル
②商社
商社
国内外のさまざまな商品の取引を仲介し、製品の売り手と買い手をつなぐ。物流や市場開拓だけでなく投資や事業経営にも携わり、その事業領域を拡大し続けている
商社は今ではあらゆるジャンルの事業を手掛けていますが、中核となる事業は「物を買って、必要な人に売る」ことです。特に海外から製品を輸入し、日本の市場に卸す役割をになってきました。
商社は総合商社と専門商社に分かれています。
| ジャンル | 業務内容 | 企業例 |
|---|---|---|
| 総合商社 | あらゆる製品を取り扱う | 三菱商事・伊藤忠商事など |
| 専門商社 | 一ジャンルに特化して商品を取り扱う | メタルワン・三菱商事エネルギーなど |
商社で採用がある文系の職業は、以下のような営業や事務などが中心です。商社業界は、取り扱う商品やサービスなどによってさまざまな分野があり、それぞれで多数の企業が存在しているため、文系が目指せる職種の求人数も多いと考えられます。
商社業界で特に文系学生が活躍できるおもな職業
- 営業
- 事務
- 企画・マーケティング
また、海外事業を展開している商社であれば、そこで働く営業職やそのほかの職種でも語学力が求められるため、文系科目のなかでも語学に自信のある人にとっては活躍の場が多いといえるのです。
商社に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。それぞれチェックすれば商社業界についてより深く理解できます。
総合商社
総合商社の仕事が丸わかり! 7大商社の違いと就活術もプロが解説
商社の一般職
商社の一般職の実情が丸わかり! 働く魅力や厳しさまで徹底解説
5大商社
5大商社を徹底比較! 事業や社風の違いから内定への道筋まで解説
7大商社
7大商社への就職を成功させる3つの対策|各社の特徴や魅力も解説
食品商社
食品商社の仕事内容と向いてる人|リアルな働き方も詳しく解説
専門商社
専門商社の仕事や魅力をプロが解説! 総合商社との違いや代表企業も
③コンサルティング
コンサルティング業界
企業経営のさまざまな課題を解決する役割を担う業界。専門的なアドバイスやサポートの提供を通じて、課題解決の手助けをおこなう
先でも解説したコンサルタントは、業務において理系の知識が必ずしも重要になるわけではなく、文系学生が活躍できる仕事の一つであるため、コンサルティング業界も同様に文系におすすめの業界です。
コンサルティング業界は昨今大きく成長を続けていて、業界自体の需要が高まっているため、文系学生がコンサルタントとして活躍できる機会も増えているといえます。
コンサルティング業界の代表的な企業としては、以下のような企業があります。
| 呼び名 | 属する企業 |
|---|---|
| BIG3(世界的な戦略コンサルティング会社) | マッキンゼー・アンド・カンパニー ボストン・コンサルティング・グループ ベイン・アンド・カンパニー |
| BIG4(日本のトップコンサルティング会社) | デロイト トーマツ コンサルティング PwCコンサルティング EYストラテジー・アンド・コンサルティングKPMGコンサルティング |
コンサルティング業界では、どのような課題に対して解決策を提案するのかによって、以下のようなコンサルタントの種類があります。
コンサルティングの職種例
- 戦略コンサルタント
- マーケティングコンサルタント
- 人事コンサルタント
など
このようにコンサルタントは、人事やマーケティングなど、コンサルティング以外の職業経験が活かせる場合があるため、一度ほかの職業に就いてから転職してコンサルタントになるという選択も可能です。
④不動産
不動産業界
土地や建物の売買、賃貸、管理、開発などをおこなう業界。住宅や商業施設、オフィスビルなどさまざまな不動産を扱うだけでなく、街づくりも併せておこなう
建築や街づくりを通じて人々の生活や企業活動の基盤を支えるのが不動産業界です。建築・建設の実務的な部分では、物理学や建築学といった理系の分野の知識が必要になりますが、顧客に対して、不動産の売買などを勧める営業職での採用も多いため、文系学生が活躍できる業界といえます。
また不動産業界は、土地や建物など取り扱う商材が高価であるため、1件の成約による売り上げへの影響も大きく、実績を出せれば高収入が目指せる業界でもあるのです。
不動産業界で文系学生が活躍できるおもな職業
- 営業
- 営業企画
- 広報・IR
不動産業界に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。併せてチェックすれば自分の適性や就活の進め方がわかります。
不動産営業に向いてる人
不動産営業に向いてる人の6つの特徴|具体的な業務と未経験からなる方法
不動産業界の志望動機
例文5選|不動産業界の志望動機を書く3つのコツと注意点を解説
⑤メーカー
メーカー(製造業)
さまざまな製品を企画・開発・製造・販売する業界です。自動車、電機、食品、化粧品、アパレルなど製品のジャンルは多岐に渡る
製造業を担う企業の集合体をメーカーと呼ぶため、メーカー業界にはジャンルの異なるさまざまな企業が存在しています。
メーカーは自社内で開発から販売までおこなっている場合も多いため、企画・マーケティングや営業、事務などさまざまな文系職で採用があります。店舗があるメーカーの場合は販売員の自社採用があったり、研究職などの理系職の採用もあったりと、採用の幅も企業によってまちまちです。
メーカー業界で文系学生が活躍できるおもな職業
- 営業
- 企画・マーケティング
- 販売員
それぞれ採用方法が分かれているため、自分の描く理想のキャリアや適性によって職業を決めやすい点もメーカー業界の魅力といえます。
メーカーに興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。併せてチェックすれば
各メーカーの特徴や就職に向けた動き方をより詳しく理解できます。
メーカーへの就職
メーカーへの就職はここから! プロがリアルな風習や働き方を解説
スポーツメーカーへの就職
スポーツメーカーへの就職を実現する方法|志望動機例文も紹介
飲料メーカー
飲料メーカーの仕事や魅力を徹底解説! 内定を得るための工夫も紹介
文房具メーカーへの就職
文房具メーカーへの就職を勝ち取る方法|職種別に志望動機例文も紹介
⑥広告・出版
広告・出版業界
- 広告業界:企業や商品の宣伝活動を代行・サポートする業界。雑誌やメディアを効果的に使いながら、企業の魅力を伝える手助けをおこなう
- 出版業会:書籍や雑誌などの出版をメインにおこなう業界。近年ではデジタルコンテンツの作成・販売にも注力しており、徐々にその形を変化させている
広告・出版業界は情報を魅力的な形で人々に届ける役割を担います。昔は新聞や雑誌、テレビが主戦場だったものの、近年ではWebメディアやSNSでのコンテンツ営業が増加中です。
広告・出版業界はその業務領域が多岐に渡るため、幅広い職種で採用があり、文系学生の活躍の場も多い業界といえます。
なかでも企画・マーケティングに関連する職業の採用は、他業界に比べて多い傾向があります。ほかにも、記者・ライターや編集者・ディレクター採用も多めです。
広告・出版業界で文系学生が活躍できるおもな職業
- 営業
- 広報・IR
- 記者・ライター
広告・出版業界は時代の変化に伴って、その業務領域を絶妙に変化させ続けています。企業自体も、変化し続けているため、広告・出版業界に入るなら職業自体への適性に加え、変化への適性も必要です。
広告・出版業界に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。それぞれチェックすれば、仕事内容をより詳しく理解できます。
広告代理店の仕事内容
広告代理店の5つの仕事内容|やりがいから厳しい面まで実態を解説!
出版社への就職
出版社への就職を叶える5つの必須準備|トレンドや選考対策も解説
⑦人材・教育
人材・教育業界
人の成長や可能性を引き出すことを目的とした業界。人材系はおもに求職者と企業を繋げる役割を、教育系は人の成長を支援する役割を担う
人材・教育業界では人材紹介や人材派遣、教育サービスの提供などをおこなっており、働き方の多様化とともにその事業領域を拡大しています。
時代の変化とともに「EdTech(教育×テクノロジー)」という言葉も誕生し、この領域のスタートアップも成長中です。そのため従来多かった営業や事務、コンサルタント職だけでなく企画・マーケティングといったの文系職のニーズも拡大しています。
人材・教育業界で文系学生が活躍できるおもな職業
- 営業
- 事務
- 人事
人材・教育業界は、人手を探している側と仕事を探している側、教える側と教わる側、といった、人を相手にする事業であるため、相手に合わせた臨機応変な提案や対応ができれば、理系分野のような専門知識がなくとも大いに活躍できる可能性があるのです。
人材・教育業界に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。併せてチェックすれば、自分の適性をより深く理解できます。
⑧インフラ
インフラ業界
電力・ガス・水道・通信・交通といった、人々の暮らしになくてはならないモノ・サービスを提供する業界。社会の基盤を支える重要な役割を担う
インフラ業界の企業は、私たちが当たり前に使用している電気やガス、水道、通信などを整備しています。
一見すると理系向けのイメージに感じる人もいるかもしれませんが、実は多くの文系人材が活躍できる業界でもあります。
たとえば、最近では電力事業への参入が自由化されたことで、各社とも個人や法人からの契約獲得が急務となっていて、営業職の重要性や需要が高まっているのです。また、契約数の多いインフラ会社では、事務を中心とした文系職の採用も一定数存在します。
理系の専門知識やスキルを持つ技術職なども、各インフラ業界においては重要な職種の一つではありますが、時代のニーズに合わせたインフラサービスを提供していくためには、文理の違いに関係なく、社会に貢献したいという意欲のある人材が求められているのです。
インフラ業界で文系学生が活躍できるおもな職業
- 営業
- 事務
- 経理・財務
インフラ業界を目指したいと思ったら、以下の記事をチェックしてみましょう。まず業界のリアルをチェックして、目指したいと思ったら志望動機例を参考にしてみてください。
インフラ業界はやめとけ
「インフラ業界はやめとけ」は本当? 懸念点や適性まで徹底解説
インフラの志望動機
業種別例文付き|インフラ業界の人事に刺さる志望動機のポイント
⑨IT
IT業界
情報技術(Information Technology; IT)を活用してさまざまなサービスやシステムを提供する業界。コンピュータやソフトウェア開発、システム構築、Webサービスを通じて事業を展開する
IT業界には多岐にわたる事業領域があり、テクノロジーの進化とともに休息に成長を続けています。近年はAI(人工知能)やIoT(Internet of Things)、ビッグデータの活用やクラウドサービスなどの新技術が台頭してきており、その変化は他業界に比べて目覚ましいスピードです。
IT業界は理系のイメージがあるかもしれませんが、営業や企画・マーケティングといった文系職の採用も活発におこなわれています。また、一部のエンジニアは文系かつ未経験でも就職可能であるため、IT業界は意外にも、文系就職の間口が広い業界の一つといえるのです。
特に文系学生が活躍できるおもな職業
- 営業
- 企画・マーケティング
- 広報・IR
IT業界に興味がある人は以下の記事も参考にしてみてください。以下を読めば詳しい仕事内容や細かな職業の違いまで詳しく理解できます。
Itの仕事
ITの仕事って何があるの? 仕事の種類や働く魅力を詳しく解説!
It業界
IT業界を徹底解剖! 押さえておきたい将来性やトレンドまで解説
It未経験
未経験からIT業界に就職する秘訣とは? 必要なスキルまで徹底解説
It業界のランキング
IT業界の企業ランキングを徹底解剖! 内定を勝ち取るコツも紹介
⑩官公庁・公社・団体
官公庁・公社・団体
- 官公庁:国や地方自治体の行政機関の総称。内閣府や国会なども含まれ、おもに国家公務員が働く領域を指す
- 公社・団体:地方公共団体や公立の施設の総称。特に後者とは特殊法人、独立行政法人などを指し、団体とは公立の学校や病院を指す
国民・地域民の生活の安定や社会インフラの整備、公共サービスの提供などを担うのが官公庁・公社・団体です。事業を通じて社会全体の利益の担保を目指しています。民間企業とは異なり、利益追求よりも公共の福祉の向上を第一の目的としているのも大きな特徴です。
官公庁・公社・団体に属する機関の例
- 中央省庁(財務省、厚生労働省、経済産業省など)
- 地方自治体(都道府県庁や市区町村役場)
- 独立行政法人(JICA、JETROなど)
- 特殊法人(株式会社日本政策金融公庫、日本赤十字社など)
官公庁・公社・団体で採用のある文系の職業は事務や経理などが中心で、一般企業のような営業や企画・マーケティングでの採用は少なめです。業務内容も多岐に渡るため、一般的な職業の枠組みにはとらわれない、職業を横断した業務のある仕事で募集がかかる場合もあります。
特に文系学生が活躍できるおもな職業
- 事務
- 経理・財務
文系職業の採用がある企業の収入ランキング
文系が理想のキャリアを実現するには、ここまで紹介した文系の職業やそれぞれへの適性、文系職採用がある業界などを適切に理解しておく必要があります。ここまでの解説で、文系の職業に対するイメージが膨らんだことでしょう。
しかし、皆さんのなかには「文系の職業のなかで、トップクラスなのはどれ?」「高収入の企業の文系職で働きたい」などと思っている人もいるかもしれません。
| ランキング | 企業名・職業 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | M&A キャピタルパートナーズ(営業) | 2,688万円 |
| 2位 | キーエンス(営業) | 2,182万円 |
| 3位 | ヒューリック(営業) | 1,803万円 |
| 4位 | 伊藤忠商事(営業) | 1,579万円 |
| 5位 | 三井物産(営業) | 1,558万円 |
東洋経済オンラインによる2023年3月28日の「平均年収が高い会社」ランキング全国トップ500では、年収が高い企業は、すべて営業職という結果となりました。業界は人材業界からメーカー業界、商社業界などさまざまです。
営業の収入が高くなりやすい理由は、営業は自身の成果次第で年収を高めやすいためです。成績によって年収や昇進スピードが決まるほか、歩合やインセンティブなど、直接年収を伸ばしやすい制度が整っているのも理由の一つといえます。
営業は、企業の成績に直結する重要な職業です。企業の利益は営業が生み出す契約によって生み出される部分が大きいため、高い営業実績を叩き出す営業パーソンには高い年収が与えられます。
つまり、文系で専門性がない場合でも、営業スキルを磨くことで専門職にも負けない高年収を実現できるのです。
収入については以下の記事でも詳しく解説しています。高収入を目指したい人は、ぜひ以下を参考にすれば就活をスムーズにすすめられます。
新卒の年収
2023年最新版! 新卒の年収や高収入を目指せる業界をチェック
女性の給料高い仕事
女性の給料が高い仕事おすすめ15選|最新版平均年収ランキングも
休みが多くて給料が良い仕事
12選! 休みが多くて給料が良い仕事一覧と選考突破のコツを解説
3ステップで見分けよう! 自分に合った文系の職業の探し方

文系の職業はさまざまあるからこそ、どんな職業に就こうか迷ってしまいますよね。イメージだけで選んでしまったりすると就活そのものがうまく進まないだけでなく、入社後にギャップが生まれ、早期離職の原因ともなり得ます。
今から自分に合った文系の職業を探す方法を3ステップで解説するため、どんな文系の職業が良いのかわからない人は参考にしてくださいね。
自分に合わない職業かどうかは、本来はすぐにはわからないものです。
しかしひとたび「自分に合わない」と感じてしまうと、仕事を覚える・先輩から学ぶ・能力やスキルを磨くなどへの情熱がなくなる場合があり、早期離職につながってしまう危険性があります。
①自己分析で自分の経験・価値観・適性などを把握する
自己分析の種類
- 自分史
- モチベーショングラフ
- マインドマップ
一般的に理系は「大学で化学工学を専攻してきたからこの職業」と過去に学んできたスキルで職業を決めることがあります。しかし、多くの場合文系は「文学部だからこの職業」「社会学部だからこの職業」などと過去に学んできたスキルで職業が決まるわけではありません。
そのため、学んできたことから文系が就ける職業を考えることももちろん良いのですが、自分がやりがいを感じた経験や頑張れた経験をもとに自己分析から職業を考えることがおすすめです。
過去の経験を整理するために、今から解説する自己分析をやってみましょう。
自分史

自分史は、過去から現在にかけての自分の出来事を時系列に整理してまとめたものです。自分史では過去から現在にかけて頑張ったことや大変だったこと、気づいたことを洗い出していきます。
自分史を作成することで、自分の大切にしている価値観や課題にぶつかったときの行動パターンが見えてきますよ。達成できたことやできなかったことなどにも着目してみましょう。
自分史の作り方
①ノートとペン、もしくはwordなどまとめられるものを用意する
②以下の内容を参考に小学校から現在までの出来事を年代別に洗い出していく
一番頑張ったこと
一番辛かったこと
一番うれしかったこと
当時、熱中していたこと
大きな失敗や挫折
困難を乗り越えたこと
自分から率先しておこなったこと
③過去の経験を喜怒哀楽などで考え方が似ているエピソードをまとめる
④まとめた内容が自分の価値観を表す
自己分析では小学校から現在までの出来事を年代別に洗い出すときに、必ずその理由を考えてみましょう。
「なぜ一番頑張れたのか」「なぜ一番うれしかったのか」「なぜ困難を乗り越えられたのか」「なぜ自分から率先してできたのか」などこれらの「なぜ」を追及していくと、自分の強みが必ず見出せるはずです。
自分史については、以下の記事でも詳しく解説しています。活用方法も紹介しているので、是非参考にしてみて下さい。
モチベーショングラフ

モチベーショングラフは、過去から現在にかけての自分のモチベーションの上下をグラフ化することで、自分はどうしたらモチベーションが上がったり下がったりするのかを確かめることが可能です。
過去から現在にかけて頑張ったことや大変だったこと、気づいたことを洗い出していきます。
過去の経験から現在の自分の位置を知り、モチベーションの源泉を押さえることで未来の自分を類推することができます。やりがいや喜びを感じる場面を整理していきましょう。
モチベーショングラフの作り方
①縦軸をモチベーション、横軸を時間の経過とする
②小学校から現在までの具体的な出来事とモチベーションの推移を上下で書く
③出来事に対してとった行動や思考など、そのときの状況を整理する
④モチベーションを上下させる要素を抽出する
マインドマップ

マインドマップは、中央に議題となるテーマを置き、テーマから連想される経験や情報を線でつなげながら、周辺に展開していく思考方法です。
自分が頭の中で考えていることを1枚の絵のように俯瞰してみることが可能となります。
自分が認識できていない考えや価値観が可視化されたり、言語化できていなかった自分の強みや個性、臨むキャリアプランが明確になってきますよ。
マインドマップの作り方
①無地の紙を用意する
②中央にメインテーマを書く
③メインテーマの周辺にアイデアをキーワードで書く
③キーワードから、さらに関連するキーワードを書く
- さまざまな自己分析方法がありますが、自分に合った職業を探すという観点ではどの自己分析がおすすめですか?
自分史がおすすめ
自分に合った職業を見つけるための自己分析は自分史がおすすめです。自分の歴史を振り返りつつ「自分ができること」は何なのかをよく確認できるためです。
「できる」と「やりたい」は必ずしも一致しません。もしそこに気づかずに「やりたい」だけを追い求めて仕事を選ぶと「できる」業務が得られないというミスマッチが起こります。
「できる」ことが仕事の中で見いだせないとモチベーションや自己肯定感があがらず、早期退職の原因にもなります。しかし「できる」ことを活かす場が仕事で与えられると、たとえこれまでそれに対して興味がなくてもやりがいを感じるものです。それこそが自分に合った職業になりえるでしょう。
自己分析については以下の記事でより詳しく解説しています。併せてチェックすれば、よりスムーズに自己分析をすすめられます。
自己分析
自己分析マニュアル完全版|今すぐできて内定につながる方法を解説
大切にしている価値観
「大切にしている価値観」の6つの型と回答方法を解説|12例文付き
②理想の働き方や自分のスキルとマッチする文系の職種を考える
自己分析をして自分の価値観や頑張れる環境を押さえたら、キャリアプランとライフプランを考えて、理想の将来像を思い描いていきましょう。
まずは自己分析をもとに自分の興味関心や価値観を言語化して、自分の現状を理解します。次に、自分の3年後・5年後・10年後の将来を考えてどのようなキャリアを歩みたいか、どのようなプライベートを送りたいかを考え、将来と現在をつなぐ道筋を作成することで理想の将来像と現在を結んでいきます。
そして、自分が思い描く未来と結びつく文系の職業を考えていきましょう。たとえば、専門性を高めて市場価値が高い状態で働いていたいのであれば、資格取得をして公認会計士や税理士などを目指すと良さそうですね。また、残業は少なめでプライベートを優先したいのであれば事務職が考えられます。
気になる職種の中で自分が「やりたいこと」「できること」「やらねばならないこと(使命感を持って取り組めること)」のどれか1つ以上があるかどうか探してみましょう。
将来的にその3つが揃うイメージが持てる仕事が望ましいと言われています。
③選んだ職種から自分の価値観にマッチする具体的な職業を見つける
自分の将来と結びつく文系の職種を考えたとしても、それだけではまだ自分に合っている文系の職業とは言えません。
なぜなら、一つの職種内であっても実際の職業としての業務内容は異なることが多いからです。
たとえば「マーケティング職」という職種であっても、WebマーケティングなのかSNSマーケティングなのか具体的な業務内容は多岐にわたりますよね。また、「事務職」でも貿易事務や営業事務、経理事務などさまざまです。
職種と職業の違いとは?
「職種」は「仕事の業務内容」を指す
→例:営業職、販売職
「職業」は「おもに就いている仕事」を指す
→例:メーカー営業、アパレル販売スタッフ
「自分が考えていた業務内容と違う……」と悪いギャップを生んでしまわないためにも、自分の理想の将来像とマッチした職種の中から、具体的にどんな職業が合っているのかを考えていきましょう。職種から職業を絞り込む作業が必要となります。
たとえば、職種として「営業職」になりたいと考えたとします。営業にはテレアポ営業や訪問営業、ルート営業などさまざまありますが、自分が数字やノルマの重圧をあまり背負いたくないのであれば、新規開拓よりも「ルート営業」があなたに向いてる職業だといえますよね。
また、職種として「事務職」になりたいと考えたとき、英語を使いたいのであれば経理事務などよりは英語を使う機会の多い「貿易事務」があなたに向いている職業といえるでしょう。
アドバイザーコメント
まずは職業に関するさまざまな情報を集めることが大切
文系・理系にかかわらず、「どんな職業が自分に合っているのか」を最初からわかっている人はほとんどいません。まずは自分が興味を持った業種や職種について、できるだけ情報を集めて理解を深めることをおすすめします。できれば、OG・OBなどの現職でその仕事をしている人の話を聞くのも良いでしょう。
同じ職種名でも業界や業種が違えば、役割や職務の範囲がまったく異なる場合も十分にありえます。そのため、1つの例を見聞きしただけでその職業についてすべてわかったつもりにならずに、興味を持った職業があればさまざまな組織の情報を積極的に集めましょう。
とりあえず「自分に合っているかもしれない職業」という認識を持とう
自分に合っているかどうかは、実際にその職種を現場で経験してみないとわからないものです。しかし気が進まないなと感じる職種については、割とすぐにわかるものです。
つまり、自分が強く抵抗を覚える職種以外は、積極的に情報収集をして仮で「自分に合っているかもしれない」という認識を持っておきましょう。そうすることで、自分に合っている職業に出会えるチャンスが増えてきますよ。
企業を研究する際は、以下の記事を参考に進めてみてください。チェックしながら企業研究を進めれば、自分にマッチする企業をスムーズに見つけられます。
企業分析のやり方
企業分析のやり方を完璧にマスターする3ステップ|よくある注意点も
ミスマッチを防ごう! 文系学生が自分に合う職業に就くためのコツ3選
ミスマッチを防ごう! 文系学生が自分に合う職業に就くためのコツ3選
- ①自己分析と職業分析のすり合わせを徹底する
- ②OB・OG訪問や会社説明会を通じてより深い情報を集める
- ③インターンに参加して実際の仕事を体験してみる
具体的な文系の職業とその特徴を理解し、自己分析を通じて自分に合う職業を探せば、多くの学生は自分に合いそうな職業・企業を見つけられます。ただ、なかには上記のステップを踏んでも自分に合う職業が見つからない人もいるでしょう。
企業選びに納得しないまま、なんとなく自分に合いそうな職業を選んで就職すると、ミスマッチを起こして後悔するリスクが高まります。
入社後に後悔するリスクを下げるために、ここからはミスマッチを防ぐための具体的な就活のコツを3つ紹介します。
ここまでの解説で自分に合う職業が見つからなかった人も落胆せず、以下のコツを意識して再度職業探しに取り組んでみてください。
①自己分析と職業分析のすり合わせを徹底する
興味のある文系職が決まったとしても、自己分析と業務分析のすり合わせが不十分では、企業とのミスマッチを起こす可能性があります。このすり合わせ作業こそが、自分の価値観や適性、働き方の特徴に沿った職業を見極める肝となるのです。
両者のすり合わせが十分にできて初めて、自分が納得できる職業が見つかります。具体的には、以下のようなポイントを意識して分析内容をすり合わせましょう。
自己分析と職業分析のすり合わせのコツ
- 自己分析で「譲れない条件」と「希望条件」を明確に切り分ける
- 職業分析を通じて、譲れない条件を満たす職業をピックアップする
- 希望条件をもとに職業を優先順位ごとに並べ、選考対策に取り掛かる
また、自己分析と職業分析のどちらか一方だけ完璧でも、もう一方への解像度が低ければ自分に合う職業には出会えません。
文系職か理系職かといった視点だけで決めてしまうのではなく、仕事における自分の価値観や職業自体への解像度を高め、多角的な視点で自分に合う仕事なのか判断しましょう。
②OB・OG訪問や会社説明会を通じてより深い情報を集める
職業・企業分析をおこなう際は、積極的にOB・OG訪問や会社説明会の機会を利用しましょう。働く人のリアルな声を聞くことでより深い情報が集まり、職業・企業の実態を掴めます。
理系職はその専門性の高さゆえに、おもな業務内容についてはどの企業も似ている部分が多いですが、文系の職業は同じ職種でも企業によって業務内容や担当範囲が異なる場合もあるため、事前に仕事の詳細をチェックしておくことがおすすめです。
文系学生で自分に合う職業が見つからないという人は、職業分析・企業分析の解像度が低いことが原因である可能性が考えられます。職業や企業の魅力、業界の情報などが不足していると、自分が働いているシーンを想像しづらくなるため、結果として自分に合う職業が見つかりにくくなるのです。
職業や企業への理解を深めるために、OB・OG訪問や会社説明会では以下のような点を質問してみましょう
文系の職業をチェックする際のおすすめ質問
- 文系出身者が実際に取り組む業務
- 楽しさや価値を感じるポイント
- 同職業の仲間との雰囲気や関係性
- 仕事の難しい部分や負荷を感じる業務
- 入社当初のキャリアパスと、現状思い描く将来
など
特に文系の職業は、深い情報を得ることが理想のキャリア形成できるかを左右します。インターネットでは得られない生の情報を収集すれば、職業・企業への理解度が高まり、自分に合う職業が見つかりやすくなるはずです。
③インターンに参加して実際の仕事を体験してみる
職業を深く知るには、実際に体験してみることが非常に有効です。可能な限りインターンに参加して、実際に自分が仕事を体験してどのように感じるかをチェックしてみましょう。
どれだけ細かく分析し、自己分析と職業分析をすり合わせていても、実際に体験してみて「想像と違う……」となるケースは往々にしてあります。特に文系の職業は理系のように選考と業務内容が直結しない場合も多く、事前にチェックしていなければミスマッチを起こす可能性が高まるのです。
また一方で、自分に合わないと思っていた文系職でも、実際に体験してみることで意外と熱中できることに気付く場合もあります。まずは選り好みせず各職業・各業界のインターンに参加し、自分がどう感じるかをチェックしてみるのも良いかもしれません。
想像と現実のギャップを事前にできるだけ小さくしておくことが、入社後に後悔しないための鍵といえます。
インターンに関して悩みがある人は、以下から悩みにマッチするものをチェックしてみてください。参考にすれば、不安をうまく軽減しながら就活をすすめられます。
インターン
インターンは就活に不可欠? 8のメリットと選び方を詳細解説
インターンでの質問
インターンでおすすめの質問70選|深い情報を引き出す5つのコツ
インターンの履歴書
インターンの履歴書の書き方|履歴書の選び方や作成時の注意点も解説
インターン選考
インターン選考は何を見てる? 受かる対策の秘訣を企業目線で解説
インターンの期間
インターンは期間別にメリットが違う! 就活に活きる企業選びを解説
インターンシップの時期
新制度のインターンシップの開催時期は? 1・2年生ができる対策も
多様な文系の職業から自分に合う仕事を見つけて選考に備えよう!
この記事では文系の職業一覧やそれぞれに向いている人の特徴から、自分に合う職業の見極め方まで網羅的に解説してきました。前半の内容から文系の職業が多種多様であり、それらはさまざまな業界で必要とされていることを理解できたでしょう。
また、後半で説明した自分に合う職業の見分け方やミスマッチを避けるコツは、就活の成功に直結する内容です。事前にチェックしておけば、就活の方向性設定に大いに役立ちます。
文系の職業は多岐に渡るからこそ、自分の適性や価値観とマッチする職業を見極めることが重要です。
記事の内容を参考に自分に合う職業を見つけ、理想のキャリアをスタートさせてくださいね。
アドバイザーコメント
「文系」という言葉に縛られることなく進路を選ぼう
文系・理系という区別の妥当性はともかくとして、一般的には幼少時から義務教育の間にモノづくりや数学、化学に興味を持つ人がおもに理系になり、それ以外の人が文系になっていきます。
そのため大学進学時にも、理系は得意分野から選択的に進路を決めている場合が多く、文系は消去法で非選択的に進路を決めている場合が多くなります。また、語学を除く文系の専門分野である法律や会計などが、若いうちから興味を持つような分野ではないことも影響しているでしょう。
今まさに「選ぶ」という機会があなたの元に訪れている
非選択的に進路を決めてきた文系の人にとっては、何をやるか絞り込むことは勇気が要るかもしれません。しかし、理系に比べ文系は多種多様な指向性を持つ人であふれています。文系という言葉に縛られることなく、いろいろな可能性を考えて納得できる決断をしてください。
多種多様な可能性がある反面、文系は決断が遅く優柔不断という弱点もあります。何も決めなければ「何者にでもなれる」という可能性が残り、それは居心地が良いと感じるでしょう。しかし、いつかは決めなければなりません。機会を逃さないよう注意して職業選択をしてくださいね。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー
記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi









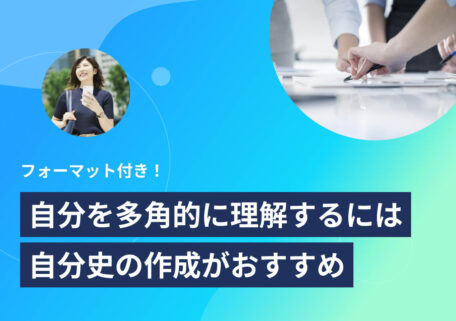













3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士
Takako Shibata〇製造業を中心とした大手~中小企業において、従業員のキャリア形成や職場の課題改善を支援。若者自立支援センター埼玉や、公共職業訓練校での就職支援もおこなう
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/合同会社渡部俊和事務所代表
Toshikazu Watanabe〇会社員時代は人事部。独立後は大学で就職支援を実施する他、企業アドバイザーも経験。採用・媒体・応募者の全ての立場で就職に携わり、3万人以上のコンサルティングの実績
プロフィール詳細キャリアコンサルタント/Koyoriキャリアワールド代表取締役
Chieko Kimura〇2度のアメリカ留学、20年以上の外資系IT企業勤務を経て、現在は留学生向け就職支援をおこなう。また、企業のキャリア支援や新入社員のクラウドコーチングなどにも幅広くたずさわる
プロフィール詳細